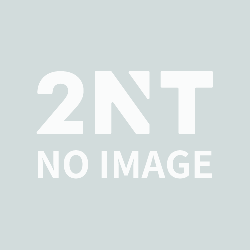2024-04-25
付録・邦画傑作選・「夜ごとの夢」(監督・成瀬巳喜男・1933年)
この映画の面白さ(見どころ)は、何と言っても「配役の妙」にある。小津安二郎作品でお馴染みの坂本武、飯田蝶子コンビが阿漕な仇役、齋藤達雄が救いようのない無様な男を演じ、吉川満子、新井淳が思い切りお人好し、善人夫婦の景色を醸し出す、そのコントラストがたまらなく魅力的であった。
主人公はおみつ(栗島すみ子)という名のシングルマザーである。一人息子の文坊(小島照子)が出世することだけを生きがいに、酒場の女給に甘んじている。冒頭は、おみつが(空しい出稼ぎの)旅を終えて、古巣の佃島に帰ってくる場面、馴染みの船員(大山健二、小倉繁)と渡船の桟橋で出会った。おみつがタバコを一本所望すると、船員は気前よく差し出しながら「お前が居ないと、酒場は火が消えたようだぜ」などと言い「どうだい、船で遊んでいかないか」と誘うが「話があるんなら、今晩、酒場で聞くよ」と言い残して渡船に乗り込む。乗客の白い目が一斉に彼女に注がれた。
数分で船は佃島に着く。おみつが向かったのは懐かしいわが家(といっても二階一間の貸間にすぎなかったが)、「夜ごとの夢」に見た愛しい文坊が待っていた。文坊の面倒を見て居てくれたのが隣部屋の夫婦(新井淳、吉川満子)、絵に描いたような善人で、文坊を孫のように可愛がっている。夫は電気会社の中年外交員、子どもには恵まれなかったようだ。文坊はおみつの顔を見るなり「おかあちゃん!」と叫んで抱きついた。しっかり抱きしめながら妻に礼を言う。「永いこと面倒を見て頂いてありがとうございました」。文坊はおみつに「お土産は?あたいおとなにしていたんだよ」。でも、おみつには何も持ち合わせがない。「今晩、もってくるからね」とごまかした。「そう言えば、留守中に男の人が訪ねて来ましたよ」と妻が言う。おみつには心当たりがあるようだったが、顔を曇らせるだけであった。その晩からおみつは店に出た。酒場はいつものように酔客で繁盛の様子、一息ついたところでおみつは女将(飯田蝶子)に借金を申し込む。文坊へのお土産と、面倒を見てくれた夫婦に御礼をしなければならない。しかし女将の返事はつれなかった。「帰ってくる早々、どんな金が要るんだい。もうすこし稼いでからにしてもらいたいね」。そこに「その金、俺に立て替えさせてもらおううか」という声が聞こえ、船長(坂本武)が入ってきた。おみつに金を渡して「俺は前からお前に目をつけていたんだぜ」とにやけまくる。その様子を「あたしゃ知らないよ、どうぞ御勝手に」という素振りで眺めている女将の表情が、(小津作品の坂本武と飯田蝶子の関係を知っているだけに)何とも可笑しかった。おみつは船長の金を頂いて、文坊へのお土産を買い深夜に帰宅する。文坊はまだ寝ないで隣室の夫婦と遊びながら待っていた。夫は「なあんだ、お土産をお待ちかねで寝なかったのか」と文坊の頭をなでたのだが・・・。待っていたのは文坊だけではなかった。妻が言う。「この前の男の人、今日も来て、あんたの部屋で待っているの」。おみつは固辞する夫婦に礼金を渡し、自室に行くと、男がうたた寝をしている。三年前、妻子を捨てて雲隠れした前夫・水原(齋藤達雄)だったのだ。叩き起こし「出て行っておくれ、あんたとあたしは、もう赤の他人なんだ」「それが昔の男に浴びせる言葉か」「ふん、聞いて呆れるよ。あたしたちを放り出しておきながら、よくのめのめと会いにこれたもんだ」「あの時のことは俺も自分に愛想が尽きている。どうか一時でも坊やの父親にさせてもらいたいんだ」。おみつは水原に帽子を被せて追い出す様子、そこに顔を出したのが文坊と隣室の夫婦、「文坊のお父さんでしたか、それとわかっていたら・・・」などととりなすが、水原は「いえ、いいんです。もう坊やの顔を見られたので思い残すことはありません」と、部屋を出て行こうとする。夫婦は、まあまあと必死に止めるが、水原の気持ちは変わらなかった。階段を降りてとぼとぼと去って行く。夫婦が「あんた、本当にそれでいいのかい?文坊にはお父さんが必要だよ」と言うと、おみつの表情が一変した。「そうだ、強情ばっかり張ってはいられない」、慌てて水原を呼び止める・・・。かくて、親子三人の新しい生活が始まったかに見えたのだが・・・。水原には思うような仕事が見つからない。隣の外交員が口を探してくれたが、世の中は不況のどん底で、人では余っている。水原にも才覚は感じられず、毎日、文坊や近所の子どもたちと遊び呆けている。「やっぱり、俺はだめなんだ」とおみつに愚痴をこぼし出す。おみつは、何とか励まし続けて店に出ていたのだが、強欲な船長がしつこくつきまとう。ある夜、水原が居酒屋に赴いてその場面を目撃、
おみつを助け出したつもりになっていたのだが、「おかしくって、あんな奴になめられてたまるかってんだ」「あの位の出入りが怖くて女給商売ができるものか」と、おみつは動じない。「何だって、お店なんかに来たのさ」「もうあんな商売やめてくれないか」「あんたが養ってくれるとでもいうの」などと夜道を歩きながら語り合ううちに、とうとう水原の心が決まった。「俺は、働く!」。・・・・、翌日、勇んで「職工募集」の会社を渡り歩いたがすべて断られた。おみつが「どうだった?」と問えば「やはり、俺なんかこの家にいない方がいいんだ」と弱音を吐く。おみつが「安心おし、あんたの顔に泥を塗るようなことはしないから」などと言っている時、どやどやと近所の子どもたちが駆け込んで来た。「文坊が自動車に轢かれた!」慌てて、家に運び込み医者(仲英之助)を呼ぶ。一命はとりとめたが右腕は複雑骨折している。病院で手術を受けなければならない。おみつは、化粧を始めた。「こんな時に出かけるのか」と水原が問えば「女将さんに相談してくる」と言う。あの船長の言いなりになって、金を作ろうとするのか、そう考えると水原の気持ちは居ても立ってもいられず、「俺が友だちに借りてくる」と部屋を飛び出した。行く先はお決まりの銀行、それとも郵便局、押し入って金銭を強奪、警官に追われ腕に被弾したが、何とか戻って来た。札束を渡されたおみつは驚いて「その傷はどうしたの?」と問い質したが、答はわかっていた。「そんなことをしてくれと誰が頼んだ」とその場に泣き崩れる。
でも済んだことはしかたがない。おみつは札束を水原に握らせて「あんた、自首して。神妙に勤めれば、また三人で暮らせるんだから」。外には警官の気配がする。水原はうなずき「坊やを頼んだよ」と言い残して、闇に紛れた。
翌朝、けたたましく隣室の外交員たちが駆け込んで来た。「あんたの亭主が、身投げしたんだ!」。おみつは渡船の桟橋に走ったが、すべては後の祭り、覆水は盆に返らなかったのである。刑事(西村青児)から遺書を手渡される。そこには「俺なんかどうせ死んでしまった方がいいんだ。呉々も坊やを頼む」と記されていた。戻る道、バッタリと船長に出会う。相変わらずにやけて「お前の亭主だっていうじゃねえか」という言葉に、キッとして睨みつけ、思い切りピンタ一発、腹を突き飛ばして自室に戻る。何も知らずに寝ている文坊・・・。「弱虫、いくじなし。死ぬなんて、この世の中から逃げるなんて。それが男のすることかい」と叫んで遺書を食いちぎる。やがて、なすすべもなく力が脱けて、文坊の枕元に泣き崩れるうちに、この映画は「終」となった。
前述したように、この映画の見どころは、坂本武、飯田蝶子の阿漕ぶり、齋藤達雄の無様さだが、文坊が事故に遭ってからの展開は、3年前(1930年)に作られた小津安二郎監督作品「その夜の妻」に酷似している。そこでは妻(八雲千恵子)が夫(岡田時彦)に「早く逃げて」と手引きをするが、夫は立ち戻り刑事(山本冬郷)に捕縛(自首)される。男同士の意気地が感じられるが、この水原という男は、死後も「弱虫、いくじなし」と罵られる体たらく、まさに成瀬巳喜男監督が描き出そうとする《男性像》の極め付きであった。一方、栗島すみ子の、どこか崩れた《女性像》、朋輩の女給(沢蘭子)との交流も水商売風だが、わが子の前ではどこまでも優しい慈母の風情が魅力的である。やはり成瀬監督ならではの演出が随所に散りばめられていて、小津作品とのコントラストが鮮やかに浮き彫りされる名品であったと、私は思う。(2017.7.31)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

主人公はおみつ(栗島すみ子)という名のシングルマザーである。一人息子の文坊(小島照子)が出世することだけを生きがいに、酒場の女給に甘んじている。冒頭は、おみつが(空しい出稼ぎの)旅を終えて、古巣の佃島に帰ってくる場面、馴染みの船員(大山健二、小倉繁)と渡船の桟橋で出会った。おみつがタバコを一本所望すると、船員は気前よく差し出しながら「お前が居ないと、酒場は火が消えたようだぜ」などと言い「どうだい、船で遊んでいかないか」と誘うが「話があるんなら、今晩、酒場で聞くよ」と言い残して渡船に乗り込む。乗客の白い目が一斉に彼女に注がれた。
数分で船は佃島に着く。おみつが向かったのは懐かしいわが家(といっても二階一間の貸間にすぎなかったが)、「夜ごとの夢」に見た愛しい文坊が待っていた。文坊の面倒を見て居てくれたのが隣部屋の夫婦(新井淳、吉川満子)、絵に描いたような善人で、文坊を孫のように可愛がっている。夫は電気会社の中年外交員、子どもには恵まれなかったようだ。文坊はおみつの顔を見るなり「おかあちゃん!」と叫んで抱きついた。しっかり抱きしめながら妻に礼を言う。「永いこと面倒を見て頂いてありがとうございました」。文坊はおみつに「お土産は?あたいおとなにしていたんだよ」。でも、おみつには何も持ち合わせがない。「今晩、もってくるからね」とごまかした。「そう言えば、留守中に男の人が訪ねて来ましたよ」と妻が言う。おみつには心当たりがあるようだったが、顔を曇らせるだけであった。その晩からおみつは店に出た。酒場はいつものように酔客で繁盛の様子、一息ついたところでおみつは女将(飯田蝶子)に借金を申し込む。文坊へのお土産と、面倒を見てくれた夫婦に御礼をしなければならない。しかし女将の返事はつれなかった。「帰ってくる早々、どんな金が要るんだい。もうすこし稼いでからにしてもらいたいね」。そこに「その金、俺に立て替えさせてもらおううか」という声が聞こえ、船長(坂本武)が入ってきた。おみつに金を渡して「俺は前からお前に目をつけていたんだぜ」とにやけまくる。その様子を「あたしゃ知らないよ、どうぞ御勝手に」という素振りで眺めている女将の表情が、(小津作品の坂本武と飯田蝶子の関係を知っているだけに)何とも可笑しかった。おみつは船長の金を頂いて、文坊へのお土産を買い深夜に帰宅する。文坊はまだ寝ないで隣室の夫婦と遊びながら待っていた。夫は「なあんだ、お土産をお待ちかねで寝なかったのか」と文坊の頭をなでたのだが・・・。待っていたのは文坊だけではなかった。妻が言う。「この前の男の人、今日も来て、あんたの部屋で待っているの」。おみつは固辞する夫婦に礼金を渡し、自室に行くと、男がうたた寝をしている。三年前、妻子を捨てて雲隠れした前夫・水原(齋藤達雄)だったのだ。叩き起こし「出て行っておくれ、あんたとあたしは、もう赤の他人なんだ」「それが昔の男に浴びせる言葉か」「ふん、聞いて呆れるよ。あたしたちを放り出しておきながら、よくのめのめと会いにこれたもんだ」「あの時のことは俺も自分に愛想が尽きている。どうか一時でも坊やの父親にさせてもらいたいんだ」。おみつは水原に帽子を被せて追い出す様子、そこに顔を出したのが文坊と隣室の夫婦、「文坊のお父さんでしたか、それとわかっていたら・・・」などととりなすが、水原は「いえ、いいんです。もう坊やの顔を見られたので思い残すことはありません」と、部屋を出て行こうとする。夫婦は、まあまあと必死に止めるが、水原の気持ちは変わらなかった。階段を降りてとぼとぼと去って行く。夫婦が「あんた、本当にそれでいいのかい?文坊にはお父さんが必要だよ」と言うと、おみつの表情が一変した。「そうだ、強情ばっかり張ってはいられない」、慌てて水原を呼び止める・・・。かくて、親子三人の新しい生活が始まったかに見えたのだが・・・。水原には思うような仕事が見つからない。隣の外交員が口を探してくれたが、世の中は不況のどん底で、人では余っている。水原にも才覚は感じられず、毎日、文坊や近所の子どもたちと遊び呆けている。「やっぱり、俺はだめなんだ」とおみつに愚痴をこぼし出す。おみつは、何とか励まし続けて店に出ていたのだが、強欲な船長がしつこくつきまとう。ある夜、水原が居酒屋に赴いてその場面を目撃、
おみつを助け出したつもりになっていたのだが、「おかしくって、あんな奴になめられてたまるかってんだ」「あの位の出入りが怖くて女給商売ができるものか」と、おみつは動じない。「何だって、お店なんかに来たのさ」「もうあんな商売やめてくれないか」「あんたが養ってくれるとでもいうの」などと夜道を歩きながら語り合ううちに、とうとう水原の心が決まった。「俺は、働く!」。・・・・、翌日、勇んで「職工募集」の会社を渡り歩いたがすべて断られた。おみつが「どうだった?」と問えば「やはり、俺なんかこの家にいない方がいいんだ」と弱音を吐く。おみつが「安心おし、あんたの顔に泥を塗るようなことはしないから」などと言っている時、どやどやと近所の子どもたちが駆け込んで来た。「文坊が自動車に轢かれた!」慌てて、家に運び込み医者(仲英之助)を呼ぶ。一命はとりとめたが右腕は複雑骨折している。病院で手術を受けなければならない。おみつは、化粧を始めた。「こんな時に出かけるのか」と水原が問えば「女将さんに相談してくる」と言う。あの船長の言いなりになって、金を作ろうとするのか、そう考えると水原の気持ちは居ても立ってもいられず、「俺が友だちに借りてくる」と部屋を飛び出した。行く先はお決まりの銀行、それとも郵便局、押し入って金銭を強奪、警官に追われ腕に被弾したが、何とか戻って来た。札束を渡されたおみつは驚いて「その傷はどうしたの?」と問い質したが、答はわかっていた。「そんなことをしてくれと誰が頼んだ」とその場に泣き崩れる。
でも済んだことはしかたがない。おみつは札束を水原に握らせて「あんた、自首して。神妙に勤めれば、また三人で暮らせるんだから」。外には警官の気配がする。水原はうなずき「坊やを頼んだよ」と言い残して、闇に紛れた。
翌朝、けたたましく隣室の外交員たちが駆け込んで来た。「あんたの亭主が、身投げしたんだ!」。おみつは渡船の桟橋に走ったが、すべては後の祭り、覆水は盆に返らなかったのである。刑事(西村青児)から遺書を手渡される。そこには「俺なんかどうせ死んでしまった方がいいんだ。呉々も坊やを頼む」と記されていた。戻る道、バッタリと船長に出会う。相変わらずにやけて「お前の亭主だっていうじゃねえか」という言葉に、キッとして睨みつけ、思い切りピンタ一発、腹を突き飛ばして自室に戻る。何も知らずに寝ている文坊・・・。「弱虫、いくじなし。死ぬなんて、この世の中から逃げるなんて。それが男のすることかい」と叫んで遺書を食いちぎる。やがて、なすすべもなく力が脱けて、文坊の枕元に泣き崩れるうちに、この映画は「終」となった。
前述したように、この映画の見どころは、坂本武、飯田蝶子の阿漕ぶり、齋藤達雄の無様さだが、文坊が事故に遭ってからの展開は、3年前(1930年)に作られた小津安二郎監督作品「その夜の妻」に酷似している。そこでは妻(八雲千恵子)が夫(岡田時彦)に「早く逃げて」と手引きをするが、夫は立ち戻り刑事(山本冬郷)に捕縛(自首)される。男同士の意気地が感じられるが、この水原という男は、死後も「弱虫、いくじなし」と罵られる体たらく、まさに成瀬巳喜男監督が描き出そうとする《男性像》の極め付きであった。一方、栗島すみ子の、どこか崩れた《女性像》、朋輩の女給(沢蘭子)との交流も水商売風だが、わが子の前ではどこまでも優しい慈母の風情が魅力的である。やはり成瀬監督ならではの演出が随所に散りばめられていて、小津作品とのコントラストが鮮やかに浮き彫りされる名品であったと、私は思う。(2017.7.31)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-24
付録・邦画傑作選・「浪華悲歌」(監督・溝口健二・1936年)
ユーチューブで映画「浪華悲歌」(監督・溝口健二・1936年)を観た。19歳の女優・山田五十鈴主演の傑作である。冒頭は、薬種問屋の主人・麻居(志賀廼家弁慶)が、けたたましい嗽いの音を立てて洗面・歯みがきをしている。タオルで顔を拭きながら縁側に出る。女中に「このタオル、しめってるがな」。朝の太陽を仰ぎながら「商売繁盛、家内息災」、やがて朝食。茶を啜ると「ああ、苦い」、「卵がない」「海苔がない」、女中の手を見て「汚い」、小言が止まることがない。「あれは、どうした。すみ子は?」「へえ、頭が痛いと寝ておいでです」「昨日は何時頃帰った?」「2時頃です」。女房のすみ子(梅村蓉子)はまだ蒲団の中、隣には子犬も寝ていた。麻居はこの家の養子、すみ子に頭が上がらず、その鬱憤を女中連中にぶつけているのである。そこに、医師・横尾(田村邦男)が訪れた。すみ子の診察に来たのである。結果は異常なし、麻居は横尾に愚痴をこぼす。「おもしろうないわ」。すみ子が起きてきてすぐにでも出かける様子、「なんや、お前また出かけるんか」。すみ子は平然と「婦人会に行かななりませんし・・・」と言い、一向に意に介さない。麻居は横尾に「なあ君、夫婦もこうなったらおしまいやな」と言う。横尾は「しょうもないこと言いなさんな」と取りなした。麻居が若い頃を思い出し「あなた、なあに」と呼び合いたいと言えば、どこぞに若い娘を囲ったらいい、と言う。「お前はやきもちをやくんやろ」「あほらしい、あんたは養子、そんな甲斐性があるかいな。そやそや昨日、婦人会の仕事を手伝わせたさかい、この芝居の切符、西村にあげたろ」と、すみ子はさっさと出て行く。西村(原健作)とは、この問屋の店員である。すみ子が西村に近づくと、その様子を電話交換室から目ざとく見つけ、すぐに西村に社内電話するのが、この映画の主人公・村井アヤ子(山田五十鈴)であった。彼女はこの店の電話交換手、西村と一緒になりたいと思っているが、家庭では、父・準造(竹川誠一)が300円(現在の約200万円余り)の借金を負って逃げ回っている。退勤後、アヤ子は西村を誘い、そのことを相談するが「何ともならへん」と頼りない返事、力を落として帰宅すると妹の幸子(大倉千代子)が一人、借金取りに囲まれて困っていた。借金取りの会社員(橘光造)は、「横領罪で告訴する」と脅したが、アヤ子は平謝りして、その場は収まった。まもなく準造が釣り堀から戻る。アヤ子は夕食を食べながら父を責め立てる。「株なんかに手出すからこんなことになるんや。甲斐性なしの親持つとろくなことあらへんわ。こんな親ならいない方がマシや」。父は激昂し「アホ!誰のおかげで大きくなったんだ。そんなにイヤなら出て行けばいいんや」。その言葉を聞くと、アヤ子は「ほんじゃ出て行くわ」と、幸子が必死に止めるのを振り切って、飛び出していく。
かくて、アヤ子は店も辞め、行方知れずとなったが、「灯台下暗し」彼女は、ちゃっかりと店主・麻居の「囲い者」に納まってしまうのだ。以後は、自由奔放な「男遍歴」を展開、助平で自堕落、いくじなしの男たちが、次々と「食い物」にされる景色は痛快であった。まずは、麻居。アヤ子に豪華なアパートを与え、300円も調達する。文楽座で密会中、医者の横尾夫妻と観劇に来ていた女房・すみ子とバッタリ鉢合わせ、その窮地は、たまたま居合わせた友人の株屋・藤野(進藤英太郎)の機転で救われたが・・・。別の日、アパートで発熱、横尾を呼んだが、横尾は本宅に駆けつけ、真相がばれてしまった。アパートに踏み込んだすみ子がアヤ子に向かって「あんたも、こわい人やなあ。主人を誘惑するなんて。二度と会ったら承知しませんで!」「フン、頼まれても会いまへんわ」。アヤ子の目的は、父を救うための300円、もう麻居は「用無し」となったのである。アヤ子は西村と所帯を持つことを夢見て、会いに行く。その途中の駅で妹の幸子に会った。幸子の話では、兄の弘(浅香新八郎)が家に戻っている。まもなく大学を卒業、就職も決まっているが、学費が払えない、どうしても200円(現在の150万円弱)要るとのこと、「姉ちゃん、何とかならんか」。「そんなこと知るか」「姉ちゃん、家を飛び出したりして、兄ちゃんボロクソに言ってたで」「わてには、わての考えがあるんや。偉そなこと言うなチンピラのくせに」。幸子も「ほな、放っとくわ」と立ち去った。アヤ子はしばし考えて留まっていたが、思い直して西村との待ち合わせ場所へ・・・、しかし西村の姿は現れなかった。
次に「食い物」にされたのは株屋の藤野、アヤ子に200円の小切手を渡して料亭に繰り込む。西村が「あんたとは縁があったんや」と迫ると「悪縁や」と言っていなす。なおも、しつこく絡んでくるのでアヤ子はさっさと帰り支度を整え、「あんたは、ここにゆっくりいなはれ。姉さん、この旦はんに馴染みの芸者を呼んで・・・」「何だ、取るもの取っといて、わしゃ許さへんぞ!」と怒り出す藤野を残して出て行った。その足で、西村に電話、アパートに来て欲しいと誘った。喜んで飛んで来た西村に、アヤ子は(自分は囲い者になっているという)真相を打ち明ける。「ええっ?」と西村が驚いているところに、藤野が怒鳴り込んできた。「金を返せ」と言うのだろう。アヤ子は少しも動じず「あんたもエライしつこい人やな、あきらめてお帰り、たかが2,300ばかりで、相場が外れたと(思えばいいこと、大騒ぎしなさんな)」「そうはいかんで」というと、後ろ向きの西村を用心棒に見立てて「ややこしくならんうちに、さあ、お帰り、お帰り」と追い出してしまった。西村はビビりまくり「アヤちゃん、ボク帰らしてもらうわ」「エッ?・・・」。西村がドアを開けると、外に刑事が立っていた。二人は、鬼刑事とおぼしき峰岸(志村喬)の取り調べを受ける。「罪を憎んで人を憎まず、が法のたてまえ、正直に本当のことを言って、謝りなさい」「あの人と一緒になりたくてしたんです」「あの男に指図されたんだろ?」。峰岸はそれを確かめに西村を調べるが、とてもそんな様子は見られない。「あの女に踊らされていたんです。あんなおそろしい女だとは知りませんでした。騙されたんです」。隣室でアヤ子はその言葉を聞いた。表情は、一瞬凍りつく。峰岸が戻ってきてしみじみと言う。「おまえは大した女だなあ」「そうでっしゃろか」先に釈放される西村の背中に「進さん!」と声をかけたが、反応はなかった。
翌朝か、翌々朝か・・・、父・準造がアヤ子の身柄を引き受けに来た。「今回は初犯だから・・・」という峰岸の言葉に準造は平謝り、アヤ子は父と家に戻ったが・・・。幸子と弘が夕食のすき焼きを食べている。アヤ子も席についたが、皆、無言である。とりわけ、父はうつむいて、何かを必死にこらえている。「どうしたんねん、みんな口も聞かんと」。弘が口を開いた。「お前みたいな不良は、兄弟でもなんでもあらへん」。昨日の一件が、新聞で取り沙汰されて、幸子は学校にも行けなくなった、弘は「家を出て行け」と言う。父までもが「警察のお世話になって、留置場に泊められて、この親不孝者」と呟いた。
その言葉を聞いて、アヤ子は「よう言わんわ」と懐かしい家を後にした。
橋の上に佇み、水に映るネオンに目をやアヤ子、たまたま通りかかった医者の横尾が声をかけた。「どないしたんや、何してるんや、こんな所で」「野良犬や、どないしていいかわからへんねん」「病気と違うか」「まあ、病気やな。不良少女っちゅう立派な病気やわ。なあ、お医者はん」「何やねん」「こないなったオナゴは、どないして治しはんねん?」「さあ、それにはボクにもわからんわ」。
アヤ子は歩き出す。その姿、上半身、そしてキッとした顔が大写しになり「終」となった。
この映画の眼目は、一人の生娘・アヤ子が、強がりばかりで「いくじなし」の父親と、体面ばかりの兄のために、助平で「いくじなし」の店主と助平で「けちくさい」株屋を手玉にとって、捨て身で助けようとしたのだが、その気持ちがほとんど通じない。「いくじなし」の恋人にも裏切られ「どないしていいかわからへん」、あげくは、世間から「不良少女」というレッテルをはられ、医者にも見放された。《にもかかわらず》前に進んでいくんだ、という一途な女の「心もよう」を描出したかったのではないだろうか。言い換えれば、男の「いくじなし」「身勝手」に対する挑戦であり、覇気である。それは次作「祇園の姉妹」に着実に引き継がれていく。ほぼ同じ俳優が、所を京都に変えて演じるドラマ(人間模様)もたいそう見応えがあった。
ところで、アヤ子が警察に拘引された容疑は何だったのだろうか。アヤ子の「詐欺」?、西村の「脅迫」(美人局)?、それとも未成年の「不純異性交遊」の補導?、いずれにしても、訴えたのは株屋の藤野という、いっっぱしの男である。その自堕落で間抜けな助平根性が、一人の生娘を「不良少女」という「立派な病気」に仕立て上げるのだから、救いようがない。その不条理を告発することこそが、女性映画の巨匠・溝口健二監督の「ねらい」だったかもしれない。それにしても、若き日の山田五十鈴は、すでに風格十分で他を寄せつけない「存在感」を示していた。戦後では「非行少女」(監督・浦山桐郞・1963年)の和泉雅子、「事件」(監督・野村芳太郎・1978年)の松坂慶子、大竹しのぶ、「疑惑」(監督・野村芳太郎・1982年)の桃井かおりといった女優が思い浮かぶが、その貫禄においてはまだまだ及ばないことを確認した次第である。そう言えば、「疑惑」には山田五十鈴もクラブのママ役で出演、法廷の場面で(その空気に臆することなく)ホステス役(被告人)の桃井かおりを叱りつけ、弁護士役の岩下志麻に「啖呵を切って」黙らせる迫力は、さすがに年輪を重ねた、大女優ならではの「女模様」であったと、私は思う。(2017.6.19)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

かくて、アヤ子は店も辞め、行方知れずとなったが、「灯台下暗し」彼女は、ちゃっかりと店主・麻居の「囲い者」に納まってしまうのだ。以後は、自由奔放な「男遍歴」を展開、助平で自堕落、いくじなしの男たちが、次々と「食い物」にされる景色は痛快であった。まずは、麻居。アヤ子に豪華なアパートを与え、300円も調達する。文楽座で密会中、医者の横尾夫妻と観劇に来ていた女房・すみ子とバッタリ鉢合わせ、その窮地は、たまたま居合わせた友人の株屋・藤野(進藤英太郎)の機転で救われたが・・・。別の日、アパートで発熱、横尾を呼んだが、横尾は本宅に駆けつけ、真相がばれてしまった。アパートに踏み込んだすみ子がアヤ子に向かって「あんたも、こわい人やなあ。主人を誘惑するなんて。二度と会ったら承知しませんで!」「フン、頼まれても会いまへんわ」。アヤ子の目的は、父を救うための300円、もう麻居は「用無し」となったのである。アヤ子は西村と所帯を持つことを夢見て、会いに行く。その途中の駅で妹の幸子に会った。幸子の話では、兄の弘(浅香新八郎)が家に戻っている。まもなく大学を卒業、就職も決まっているが、学費が払えない、どうしても200円(現在の150万円弱)要るとのこと、「姉ちゃん、何とかならんか」。「そんなこと知るか」「姉ちゃん、家を飛び出したりして、兄ちゃんボロクソに言ってたで」「わてには、わての考えがあるんや。偉そなこと言うなチンピラのくせに」。幸子も「ほな、放っとくわ」と立ち去った。アヤ子はしばし考えて留まっていたが、思い直して西村との待ち合わせ場所へ・・・、しかし西村の姿は現れなかった。
次に「食い物」にされたのは株屋の藤野、アヤ子に200円の小切手を渡して料亭に繰り込む。西村が「あんたとは縁があったんや」と迫ると「悪縁や」と言っていなす。なおも、しつこく絡んでくるのでアヤ子はさっさと帰り支度を整え、「あんたは、ここにゆっくりいなはれ。姉さん、この旦はんに馴染みの芸者を呼んで・・・」「何だ、取るもの取っといて、わしゃ許さへんぞ!」と怒り出す藤野を残して出て行った。その足で、西村に電話、アパートに来て欲しいと誘った。喜んで飛んで来た西村に、アヤ子は(自分は囲い者になっているという)真相を打ち明ける。「ええっ?」と西村が驚いているところに、藤野が怒鳴り込んできた。「金を返せ」と言うのだろう。アヤ子は少しも動じず「あんたもエライしつこい人やな、あきらめてお帰り、たかが2,300ばかりで、相場が外れたと(思えばいいこと、大騒ぎしなさんな)」「そうはいかんで」というと、後ろ向きの西村を用心棒に見立てて「ややこしくならんうちに、さあ、お帰り、お帰り」と追い出してしまった。西村はビビりまくり「アヤちゃん、ボク帰らしてもらうわ」「エッ?・・・」。西村がドアを開けると、外に刑事が立っていた。二人は、鬼刑事とおぼしき峰岸(志村喬)の取り調べを受ける。「罪を憎んで人を憎まず、が法のたてまえ、正直に本当のことを言って、謝りなさい」「あの人と一緒になりたくてしたんです」「あの男に指図されたんだろ?」。峰岸はそれを確かめに西村を調べるが、とてもそんな様子は見られない。「あの女に踊らされていたんです。あんなおそろしい女だとは知りませんでした。騙されたんです」。隣室でアヤ子はその言葉を聞いた。表情は、一瞬凍りつく。峰岸が戻ってきてしみじみと言う。「おまえは大した女だなあ」「そうでっしゃろか」先に釈放される西村の背中に「進さん!」と声をかけたが、反応はなかった。
翌朝か、翌々朝か・・・、父・準造がアヤ子の身柄を引き受けに来た。「今回は初犯だから・・・」という峰岸の言葉に準造は平謝り、アヤ子は父と家に戻ったが・・・。幸子と弘が夕食のすき焼きを食べている。アヤ子も席についたが、皆、無言である。とりわけ、父はうつむいて、何かを必死にこらえている。「どうしたんねん、みんな口も聞かんと」。弘が口を開いた。「お前みたいな不良は、兄弟でもなんでもあらへん」。昨日の一件が、新聞で取り沙汰されて、幸子は学校にも行けなくなった、弘は「家を出て行け」と言う。父までもが「警察のお世話になって、留置場に泊められて、この親不孝者」と呟いた。
その言葉を聞いて、アヤ子は「よう言わんわ」と懐かしい家を後にした。
橋の上に佇み、水に映るネオンに目をやアヤ子、たまたま通りかかった医者の横尾が声をかけた。「どないしたんや、何してるんや、こんな所で」「野良犬や、どないしていいかわからへんねん」「病気と違うか」「まあ、病気やな。不良少女っちゅう立派な病気やわ。なあ、お医者はん」「何やねん」「こないなったオナゴは、どないして治しはんねん?」「さあ、それにはボクにもわからんわ」。
アヤ子は歩き出す。その姿、上半身、そしてキッとした顔が大写しになり「終」となった。
この映画の眼目は、一人の生娘・アヤ子が、強がりばかりで「いくじなし」の父親と、体面ばかりの兄のために、助平で「いくじなし」の店主と助平で「けちくさい」株屋を手玉にとって、捨て身で助けようとしたのだが、その気持ちがほとんど通じない。「いくじなし」の恋人にも裏切られ「どないしていいかわからへん」、あげくは、世間から「不良少女」というレッテルをはられ、医者にも見放された。《にもかかわらず》前に進んでいくんだ、という一途な女の「心もよう」を描出したかったのではないだろうか。言い換えれば、男の「いくじなし」「身勝手」に対する挑戦であり、覇気である。それは次作「祇園の姉妹」に着実に引き継がれていく。ほぼ同じ俳優が、所を京都に変えて演じるドラマ(人間模様)もたいそう見応えがあった。
ところで、アヤ子が警察に拘引された容疑は何だったのだろうか。アヤ子の「詐欺」?、西村の「脅迫」(美人局)?、それとも未成年の「不純異性交遊」の補導?、いずれにしても、訴えたのは株屋の藤野という、いっっぱしの男である。その自堕落で間抜けな助平根性が、一人の生娘を「不良少女」という「立派な病気」に仕立て上げるのだから、救いようがない。その不条理を告発することこそが、女性映画の巨匠・溝口健二監督の「ねらい」だったかもしれない。それにしても、若き日の山田五十鈴は、すでに風格十分で他を寄せつけない「存在感」を示していた。戦後では「非行少女」(監督・浦山桐郞・1963年)の和泉雅子、「事件」(監督・野村芳太郎・1978年)の松坂慶子、大竹しのぶ、「疑惑」(監督・野村芳太郎・1982年)の桃井かおりといった女優が思い浮かぶが、その貫禄においてはまだまだ及ばないことを確認した次第である。そう言えば、「疑惑」には山田五十鈴もクラブのママ役で出演、法廷の場面で(その空気に臆することなく)ホステス役(被告人)の桃井かおりを叱りつけ、弁護士役の岩下志麻に「啖呵を切って」黙らせる迫力は、さすがに年輪を重ねた、大女優ならではの「女模様」であったと、私は思う。(2017.6.19)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-23
付録・邦画傑作選・「祇園の姉妹」(監督・溝口健二・1936年)
ユーチューブで映画「祇園の姉妹」(監督・溝口健二・1936年)を観た。祇園の芸妓として生きる姉妹の物語である。姉は梅吉(梅村蓉子)、妹はオモチャ(山田五十鈴)と呼ばれている。その借家に、木綿問屋主人・古沢(志賀廼家辯慶)が転がり込んできた。店が倒産、骨董・家具などが競売されている最中、夫人(久野和子)と大喧嘩して家を飛び出して来たのだ。古沢は梅吉がこれまでお世話になった旦那、「よう来ておくれやした」と梅吉は歓迎するが、オモチャは面白くない。新しい女のあり方を女学校で学んだ彼女は、男に尽くして食い物にされている姉の姿が不満なのである。八坂神社をお詣りしながら、「あんな古沢さんを居候にするのは反対や」、「これまでお世話になったのだから恩返しをするのは当たり前や」「姉さんは世間の評判を気にして、いい女になろうとしているが、世間が私たちに何をしてくれたというの」といった問答を重ねる姿が、たいそう可笑しかった。たまたま朋輩と出会い、「オモチャさん、あの木村さんがあんたに“ホの字”なのよ」という話を聞く。「なんや、あほらしい」とその場はやり過ごしたのだが・・・。
オモチャが置屋に顔を出すと、女将(滝沢静子)の話。「今度の“御触れ舞”に梅吉さんを出したい。芸は申し分ないけど“ベベ”がねえ」、それなりの衣装が揃えられるか、という打診である。どうしても梅吉に出てもらい、有力な旦那に巡り合わせたいオモチャは「“べべ”の方は私が何とかします」と請け合った。折りしも、やってきたのが呉服屋丸菱の番頭・木村(深見泰三)、オモチャにねだられて、最高級(50円以上・現在の35万円以上)の反物をプレザント、そこまでの「やりとり」(男心をくすぐるオモチャの手練手管)は実にお見事で、私の笑いは止まらなかった。
やがて、“御触れ舞”の日、骨董商・聚楽堂(大倉文男)が泥酔し、梅吉の家を訪れる。古沢とは顔馴染みで「古沢さん、私が売った軸が売られている様子を見て、実に情けなかった」と絡む。古沢は「やあ、実に面目ない、ところで少し小遣いを融通してくれないか」と頼み込む始末、聚楽堂の財布には大枚の札束があることを見届けたオモチャは、「お家までお送りします」と連れ出した。ハイヤーに乗り込み、行き先は茶屋町の待合へ。聚楽堂が酔いから覚めて「ここはどこや、あんたは誰や」と驚く。オモチャは平然と「まあ、一杯お飲み」と酒を注ぐ。「私は梅吉の妹や」と言いながら、姉さんがあんたさんにお世話してもらいたいと思っている、ついては居候の古沢さんを追い出したいので手切れ金を、とせがむ。聚楽堂もすぐにその気になって100円(現在のおよそ70万円)を手渡した。
オモチャはその金を持って帰宅。梅吉の留守を見計らって古沢に話をつける。「お姉さんは、本当は迷惑なんや、それを言い出せないでいるから、わてが言うわ。これを持ってどこぞへ往んでくれへんか」と50円(現在のおよそ35万円)を手渡した。もとより、遊び人の古沢、長逗留する気などさらさらない。「わかった、ほんじゃ出て行くわ、おおきに」と言い残して、この家を後にした。行き先はいずこへ・・・。
帰宅した梅吉、「古沢はんは?」と訝ったが、オモチャは平然と「どこぞへ往ってしもうたわ」「なんや、お別れぐらい言うてほしかった、つれない人やなあ」「それみい、男はんなんて、みんなそんなもんや」。オモチャの計略はまんまと成功したのである。
一方、呉服屋丸菱では、番頭・木村の反物着服が発覚、主人・工藤三五郎(進藤英太郎)は木村を叱りつけている。「あれを誰にあげたんや」「オモチャさんです」「よし、ワシが話をつけてくる」と、梅吉宅に向かった。ここでも、オモチャは工藤を平然と迎え入れ、愛嬌たっぷりに、酒をもてなす。当初は意気高々、こわばっていた工藤の表情が、オモチャの一言一言によって崩れていく景色は抱腹絶倒、ここでも私の笑いは止まらなかった。
かくて、オモチャは工藤の愛人となる。木村に「あんな女に騙されて情けない。今後は絶対にかかわるな」と言うだけでお咎め無し、夫人(いわま櫻子)は「あんた、うまいことゆうて丸めこまれたんと違いますか」と思ったのだが・・・。
梅吉の家に聚楽堂がやってきた。オモチャは「姉さん、うまいことやりいや」と言い残して工藤との密会に出かける。しばらくすると、木村がやって来ていわく「今、途中で古沢さんに会いました」「どこで」「八坂下です。銘茶店で居候しているようですよ」梅吉は聚楽堂が止めるのも聞かず、一目散に古沢の元へ、聚楽堂も追いかけて二人とも居なくなった。木村は留守番の態でそこに居残っている。梅吉が銘茶店に赴くと「よう、ここがわかったな」「黙っていなくなるなんて、あんまりでは」「いや、オモチャさんからお前が迷惑しているからと聞かされて、出たんだ」「やっぱりオモチャが謀ったんだ」「ここは、実に住み心地がよい。お前も来たらどうだ」、梅吉にもようやく事態がのみこめたようだ。
一方、オモチャは工藤と洋風レストランで密会、しかし工藤は財布がないことに気づいた。おそらく、あの時、梅吉の家に置き忘れたのだろう。それともオモチャが掠め取ったか。ともかくも、二人は梅吉宅を探すことにした。戻った二人は、そこに木村が居るのを見て仰天する。「お前、こんなところで何をしてるんや、アホ!」と工藤が叱りつけたが、今度は木村も黙っていない。「大将、何ですねん。わしを叱っといて、このザマは」。「お前、主人に向かって何ていうこと言うんや、すぐに暇出したる!はよ、ここから出て行け」と罵られたが、オモチャに向かって「大将は、オモチャさんの、まさか・・・」「へえ、わての旦那さんです」「ようそんなことが言えるな、このドタヌキめ!」「わてら芸妓や、時には嘘もつきまっせ、たった反物一枚でええ男ぶりやがって」「何!」と掴みかかろうとする木村を工藤がはねのける。木村はもうこれまでと覚悟を決めた。「よう、おぼえておけよ」と捨て台詞を残して立ち去った。
木村は、この事実を工藤の夫人に電話で連絡、帰宅した工藤と夫人の間に丁々発止のバトルが始まる。「ええ年して、まだ極道が止みまへんのか!」その頃、木村もまた極道の世界へ赴いていた。
古沢の元から小走りで戻った梅吉も覚悟を決めた。手早く荷物をまとめ始める。「姉さん、聚楽堂さん喜んだやろ」と話しかけたが「わてはこの家、出て行くさかい。みんな古沢さんから聞いたえ」「古沢さんに会うたんか。姉さんお待ち!」という言葉を振り切って出て行った。一人残ったオモチャ、座り込んで「何て、あほなんやろ」と呟く。
しばらくすると「こんばんは」という声、見知らぬ男が「工藤さんから、お迎えの車が参りました」と言う。オモチャは欣然として衣装直し、化粧を施して車に乗り込んだのだが・・・、運転手(橘光造)がドスの利いた声で話しかけた。「オモチャはん、景気はどうだす。どこぞで遊ぼうか」、オモチャ、キッとして「あんまり心やすう呼ばんといて」「わてはあんさんのこと、よう知っとるで。どこぞの番頭口説いて、ぎょうさん巻き上げたんと違うか」「アホなこと言わんとき」と言い返すが「ええ顔して、ええ旦那さんもなく、相変わらずがつがつしてると思うと、かわいそうなもんじゃな」「はよう、工藤さんの所へ連れてってえな」「工藤さん?あんなしみったれな旦那やめとき。わてが、金ぎょうさん持ってる極道者世話してやるけえ、何だったらわてでもええぜ」「やめとくれやす」「ほんなら、そこのええ男はどうや」。よく見ると、助手席には木村が乗っていた。
万事休す、どうみてもオモチャに勝ち目はない。彼女も覚悟を決めて車から飛び降りた。それとも落とされたか、重傷を負って病院に運ばれた。その知らせが、梅吉のもとに入る。あわてて梅吉は病院へ。古沢も「後から駆けつける」と言う。
病院には包帯姿のオモチャ、「まあ、まあ、こんなことになるなんて、男はんの心を弄ぶからこんなことになるんや」と諫めたが「こんなことで、男に負けるもんか、わては負けはへん」と叫んでいる。ともかくも安静にと頼んで、梅吉が古沢の元に戻ると、その姿は消えていた。突然、奥さんから電報が届いて、奥さんの故郷に向かったと言う。そこで新しく人絹工場を始めるらしい。なんぞ書き置きでもと訪ねると「わしのような頼りない男ではなく、もっといい旦那を見つけてくれ」という伝言だった由。
傷心の梅吉はやむなく病院に戻る。オモチャの傍らで泣いていると「どうしたんや、そんな不景気なもの出して」「古沢さん、急に故郷に帰ってしまったんや、わてには何にも言わんと」「そんなこっちゃ、みとうみ。なんぼ実を尽くしても、自分の勝手な時には、わてらを捨てて行ってしまうんや」「わては、それでええねん。するだけのことをしてきたんだから、古沢さんも喜んでくれるやろ。世間にだって立派に顔を立ててきたんやから」「そやけど、それで姉さんはどうなった?世間に立派な顔をたてたやろうけど、世間はいったい何をしてくれた。古沢さんは喜んだやろ、けど、姉さんはどうなった。ええ暮らしができるようになったか、黙って言うなりになって、ええ人間になっても、どうもしてくれはらへんねん。商売上手にやったら腐ったやっちゃと言われるし、わてらはどうすればいいのや。わてらにどうせいと言うのや。何で芸妓なんて商売、世の中にあるんや。何で泣かなあかんのや。こんな間違ったもの・・・、なかったらええのや。」とオモチャもまた号泣するうちに、この映画は「終」となった。
さすがは、女性映画の巨匠・溝口健二監督の「傑作」である。見どころは何と言っても、山田五十鈴のはじけるような魅力であろう。二十歳そこそこの若さで、中高年の男心をくすぐり、弄ぶ手練手管の数々を十分に楽しめる。その根底には、「男なんかに負けてたまるか」という確固たる意志と意地が横たわっている。オモチャの「何で芸妓なんて商売があるんや」という怒り、憤りは、監督・溝口健二自身の当時の思い(フェミニズム)を代弁して余りある。
ほとんどの登場人物が和服を着ている中で、さっそうと洋服を着こなし帽子をかぶる姿が、「新しい女」の息吹を象徴している。比べて、姉・梅吉の梅村蓉子は心身ともに和風、義理・人情を重んじ、まず相手の立場・気持ちを忖度する。正反対の「生き様」だが、姉妹の絆はしっかりと結ばれている。オモチャにとって梅吉は、誰よりも大切な人、その姉を守るために「危ない橋」も渡らなければならなかったのだ。
この姉妹に比べて、男たちの「生き様」は、どれをとっても喜劇的である。オモチャに手切れ金の半額とも知らずに渡されて、あっさりと遊びに行く古沢、色香に迷い、30万円以上の反物を騙しとられた木村、それを取り返しに行って「ミイラ取りがミイラになった」工藤、オモチャの口車に弄ばれる聚楽堂などなど、間抜けで助平な男の「本質」を、志賀廼家辯慶、深見泰三、進藤英太郎、大倉文男といった男優陣が見事に描出していた。異色なのは運転手役の橘光造、関西ヤクザの勲章とでも言うべき、ドスの利いた「立て板に水」の啖呵は、オモチャを思わず車から飛び降りさせるほどの迫力があった。
この映画を、女性映画の名手・成瀬巳喜男監督の「噂の娘」と比較する向きもあるようだが、それは野暮というものである。生い立ちでは、溝口が先輩、ともに東京出身、経歴も似ているが、女性観には大きな差が感じられる。溝口の姉は芸者上がりの子爵夫人、自分も「痴話喧嘩のもつれから、同棲中の一条百合子(別れた後、貧しさのため娼婦となる)に背中を剃刀で切られるという事件」(ウィキペディア百科事典から引用)を起こしていることなど、「女の性」「女の怖さ」を知り尽くしているように感じる。一方、成瀬は当時の花形女優・千葉早智子と結婚、一子をもうけたが3年後に離婚、子どもは千葉が育てたという。成瀬のモットーは「女性賛歌」、もっぱら「女のたくましさ・したたかさ」を畏敬する姿勢が窺われる。言い換えれば、溝口の女は濡れており、映画は悲歌をベースにしているが、成瀬の女は乾いており、映画は謳歌をベースにしている。さればこそ、「比べようがない」のである。
ただ一点、二人に共通しているのはフェミニズムという「人権思想」であることはたしかであろう。
(2017.5.27)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

オモチャが置屋に顔を出すと、女将(滝沢静子)の話。「今度の“御触れ舞”に梅吉さんを出したい。芸は申し分ないけど“ベベ”がねえ」、それなりの衣装が揃えられるか、という打診である。どうしても梅吉に出てもらい、有力な旦那に巡り合わせたいオモチャは「“べべ”の方は私が何とかします」と請け合った。折りしも、やってきたのが呉服屋丸菱の番頭・木村(深見泰三)、オモチャにねだられて、最高級(50円以上・現在の35万円以上)の反物をプレザント、そこまでの「やりとり」(男心をくすぐるオモチャの手練手管)は実にお見事で、私の笑いは止まらなかった。
やがて、“御触れ舞”の日、骨董商・聚楽堂(大倉文男)が泥酔し、梅吉の家を訪れる。古沢とは顔馴染みで「古沢さん、私が売った軸が売られている様子を見て、実に情けなかった」と絡む。古沢は「やあ、実に面目ない、ところで少し小遣いを融通してくれないか」と頼み込む始末、聚楽堂の財布には大枚の札束があることを見届けたオモチャは、「お家までお送りします」と連れ出した。ハイヤーに乗り込み、行き先は茶屋町の待合へ。聚楽堂が酔いから覚めて「ここはどこや、あんたは誰や」と驚く。オモチャは平然と「まあ、一杯お飲み」と酒を注ぐ。「私は梅吉の妹や」と言いながら、姉さんがあんたさんにお世話してもらいたいと思っている、ついては居候の古沢さんを追い出したいので手切れ金を、とせがむ。聚楽堂もすぐにその気になって100円(現在のおよそ70万円)を手渡した。
オモチャはその金を持って帰宅。梅吉の留守を見計らって古沢に話をつける。「お姉さんは、本当は迷惑なんや、それを言い出せないでいるから、わてが言うわ。これを持ってどこぞへ往んでくれへんか」と50円(現在のおよそ35万円)を手渡した。もとより、遊び人の古沢、長逗留する気などさらさらない。「わかった、ほんじゃ出て行くわ、おおきに」と言い残して、この家を後にした。行き先はいずこへ・・・。
帰宅した梅吉、「古沢はんは?」と訝ったが、オモチャは平然と「どこぞへ往ってしもうたわ」「なんや、お別れぐらい言うてほしかった、つれない人やなあ」「それみい、男はんなんて、みんなそんなもんや」。オモチャの計略はまんまと成功したのである。
一方、呉服屋丸菱では、番頭・木村の反物着服が発覚、主人・工藤三五郎(進藤英太郎)は木村を叱りつけている。「あれを誰にあげたんや」「オモチャさんです」「よし、ワシが話をつけてくる」と、梅吉宅に向かった。ここでも、オモチャは工藤を平然と迎え入れ、愛嬌たっぷりに、酒をもてなす。当初は意気高々、こわばっていた工藤の表情が、オモチャの一言一言によって崩れていく景色は抱腹絶倒、ここでも私の笑いは止まらなかった。
かくて、オモチャは工藤の愛人となる。木村に「あんな女に騙されて情けない。今後は絶対にかかわるな」と言うだけでお咎め無し、夫人(いわま櫻子)は「あんた、うまいことゆうて丸めこまれたんと違いますか」と思ったのだが・・・。
梅吉の家に聚楽堂がやってきた。オモチャは「姉さん、うまいことやりいや」と言い残して工藤との密会に出かける。しばらくすると、木村がやって来ていわく「今、途中で古沢さんに会いました」「どこで」「八坂下です。銘茶店で居候しているようですよ」梅吉は聚楽堂が止めるのも聞かず、一目散に古沢の元へ、聚楽堂も追いかけて二人とも居なくなった。木村は留守番の態でそこに居残っている。梅吉が銘茶店に赴くと「よう、ここがわかったな」「黙っていなくなるなんて、あんまりでは」「いや、オモチャさんからお前が迷惑しているからと聞かされて、出たんだ」「やっぱりオモチャが謀ったんだ」「ここは、実に住み心地がよい。お前も来たらどうだ」、梅吉にもようやく事態がのみこめたようだ。
一方、オモチャは工藤と洋風レストランで密会、しかし工藤は財布がないことに気づいた。おそらく、あの時、梅吉の家に置き忘れたのだろう。それともオモチャが掠め取ったか。ともかくも、二人は梅吉宅を探すことにした。戻った二人は、そこに木村が居るのを見て仰天する。「お前、こんなところで何をしてるんや、アホ!」と工藤が叱りつけたが、今度は木村も黙っていない。「大将、何ですねん。わしを叱っといて、このザマは」。「お前、主人に向かって何ていうこと言うんや、すぐに暇出したる!はよ、ここから出て行け」と罵られたが、オモチャに向かって「大将は、オモチャさんの、まさか・・・」「へえ、わての旦那さんです」「ようそんなことが言えるな、このドタヌキめ!」「わてら芸妓や、時には嘘もつきまっせ、たった反物一枚でええ男ぶりやがって」「何!」と掴みかかろうとする木村を工藤がはねのける。木村はもうこれまでと覚悟を決めた。「よう、おぼえておけよ」と捨て台詞を残して立ち去った。
木村は、この事実を工藤の夫人に電話で連絡、帰宅した工藤と夫人の間に丁々発止のバトルが始まる。「ええ年して、まだ極道が止みまへんのか!」その頃、木村もまた極道の世界へ赴いていた。
古沢の元から小走りで戻った梅吉も覚悟を決めた。手早く荷物をまとめ始める。「姉さん、聚楽堂さん喜んだやろ」と話しかけたが「わてはこの家、出て行くさかい。みんな古沢さんから聞いたえ」「古沢さんに会うたんか。姉さんお待ち!」という言葉を振り切って出て行った。一人残ったオモチャ、座り込んで「何て、あほなんやろ」と呟く。
しばらくすると「こんばんは」という声、見知らぬ男が「工藤さんから、お迎えの車が参りました」と言う。オモチャは欣然として衣装直し、化粧を施して車に乗り込んだのだが・・・、運転手(橘光造)がドスの利いた声で話しかけた。「オモチャはん、景気はどうだす。どこぞで遊ぼうか」、オモチャ、キッとして「あんまり心やすう呼ばんといて」「わてはあんさんのこと、よう知っとるで。どこぞの番頭口説いて、ぎょうさん巻き上げたんと違うか」「アホなこと言わんとき」と言い返すが「ええ顔して、ええ旦那さんもなく、相変わらずがつがつしてると思うと、かわいそうなもんじゃな」「はよう、工藤さんの所へ連れてってえな」「工藤さん?あんなしみったれな旦那やめとき。わてが、金ぎょうさん持ってる極道者世話してやるけえ、何だったらわてでもええぜ」「やめとくれやす」「ほんなら、そこのええ男はどうや」。よく見ると、助手席には木村が乗っていた。
万事休す、どうみてもオモチャに勝ち目はない。彼女も覚悟を決めて車から飛び降りた。それとも落とされたか、重傷を負って病院に運ばれた。その知らせが、梅吉のもとに入る。あわてて梅吉は病院へ。古沢も「後から駆けつける」と言う。
病院には包帯姿のオモチャ、「まあ、まあ、こんなことになるなんて、男はんの心を弄ぶからこんなことになるんや」と諫めたが「こんなことで、男に負けるもんか、わては負けはへん」と叫んでいる。ともかくも安静にと頼んで、梅吉が古沢の元に戻ると、その姿は消えていた。突然、奥さんから電報が届いて、奥さんの故郷に向かったと言う。そこで新しく人絹工場を始めるらしい。なんぞ書き置きでもと訪ねると「わしのような頼りない男ではなく、もっといい旦那を見つけてくれ」という伝言だった由。
傷心の梅吉はやむなく病院に戻る。オモチャの傍らで泣いていると「どうしたんや、そんな不景気なもの出して」「古沢さん、急に故郷に帰ってしまったんや、わてには何にも言わんと」「そんなこっちゃ、みとうみ。なんぼ実を尽くしても、自分の勝手な時には、わてらを捨てて行ってしまうんや」「わては、それでええねん。するだけのことをしてきたんだから、古沢さんも喜んでくれるやろ。世間にだって立派に顔を立ててきたんやから」「そやけど、それで姉さんはどうなった?世間に立派な顔をたてたやろうけど、世間はいったい何をしてくれた。古沢さんは喜んだやろ、けど、姉さんはどうなった。ええ暮らしができるようになったか、黙って言うなりになって、ええ人間になっても、どうもしてくれはらへんねん。商売上手にやったら腐ったやっちゃと言われるし、わてらはどうすればいいのや。わてらにどうせいと言うのや。何で芸妓なんて商売、世の中にあるんや。何で泣かなあかんのや。こんな間違ったもの・・・、なかったらええのや。」とオモチャもまた号泣するうちに、この映画は「終」となった。
さすがは、女性映画の巨匠・溝口健二監督の「傑作」である。見どころは何と言っても、山田五十鈴のはじけるような魅力であろう。二十歳そこそこの若さで、中高年の男心をくすぐり、弄ぶ手練手管の数々を十分に楽しめる。その根底には、「男なんかに負けてたまるか」という確固たる意志と意地が横たわっている。オモチャの「何で芸妓なんて商売があるんや」という怒り、憤りは、監督・溝口健二自身の当時の思い(フェミニズム)を代弁して余りある。
ほとんどの登場人物が和服を着ている中で、さっそうと洋服を着こなし帽子をかぶる姿が、「新しい女」の息吹を象徴している。比べて、姉・梅吉の梅村蓉子は心身ともに和風、義理・人情を重んじ、まず相手の立場・気持ちを忖度する。正反対の「生き様」だが、姉妹の絆はしっかりと結ばれている。オモチャにとって梅吉は、誰よりも大切な人、その姉を守るために「危ない橋」も渡らなければならなかったのだ。
この姉妹に比べて、男たちの「生き様」は、どれをとっても喜劇的である。オモチャに手切れ金の半額とも知らずに渡されて、あっさりと遊びに行く古沢、色香に迷い、30万円以上の反物を騙しとられた木村、それを取り返しに行って「ミイラ取りがミイラになった」工藤、オモチャの口車に弄ばれる聚楽堂などなど、間抜けで助平な男の「本質」を、志賀廼家辯慶、深見泰三、進藤英太郎、大倉文男といった男優陣が見事に描出していた。異色なのは運転手役の橘光造、関西ヤクザの勲章とでも言うべき、ドスの利いた「立て板に水」の啖呵は、オモチャを思わず車から飛び降りさせるほどの迫力があった。
この映画を、女性映画の名手・成瀬巳喜男監督の「噂の娘」と比較する向きもあるようだが、それは野暮というものである。生い立ちでは、溝口が先輩、ともに東京出身、経歴も似ているが、女性観には大きな差が感じられる。溝口の姉は芸者上がりの子爵夫人、自分も「痴話喧嘩のもつれから、同棲中の一条百合子(別れた後、貧しさのため娼婦となる)に背中を剃刀で切られるという事件」(ウィキペディア百科事典から引用)を起こしていることなど、「女の性」「女の怖さ」を知り尽くしているように感じる。一方、成瀬は当時の花形女優・千葉早智子と結婚、一子をもうけたが3年後に離婚、子どもは千葉が育てたという。成瀬のモットーは「女性賛歌」、もっぱら「女のたくましさ・したたかさ」を畏敬する姿勢が窺われる。言い換えれば、溝口の女は濡れており、映画は悲歌をベースにしているが、成瀬の女は乾いており、映画は謳歌をベースにしている。さればこそ、「比べようがない」のである。
ただ一点、二人に共通しているのはフェミニズムという「人権思想」であることはたしかであろう。
(2017.5.27)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-22
付録・邦画傑作選・「虞美人草」(監督・中川信夫・1941年)
ユーチューブで映画「虞美人草」(監督・中川信夫・1941年)を観た。冒頭の字幕に「征かぬ身はいくぞ援護へまっしぐら」とあるように、日本が「決意なき開戦」(真珠湾攻撃)を行った年の作品である。原作は夏目漱石の小説に拠る。時代は明治、大学を卒業して2年経つのに、未だに身の固まらない青年たち(27~8歳)の物語である。一人は甲野欽吾(高田稔)、母とは死別、父も客死、甲野家の長男として相続すべき立場だがその意思をはっきりと示さない。家も財産も継母の豊乃(伊藤智子)と妹の藤尾(霧立のぼる)に譲り、自分は放浪したいなどと言う。病弱で痩身、哲学を専攻している。藤尾は24歳、洋風好みで、英語を習いピアノを奏でる。もう一人は、宗近一(江川宇礼雄)、欽吾の親友だが性格は正反対、豪放磊落で「計画よりは実行」を重んじる。外交官を目指しているが資格試験に及第しそうもない。父は、欽吾の父とも昵懇で、一と藤尾の許婚の約束を交わしていたようだ。一にも糸子(花柳小菊)という妹が居る。裁縫が得意で、兄の着物(袖なし)を仕立てたりしている。一は妹を「糸公」と呼んで可愛がっている。そんな様子を見て、欽吾も糸子に好意を寄せている。一と藤尾、欽吾と糸子というカップルが成立すれば・・・それでこの物語は終わるが、そうは問屋が卸さない。藤尾は勝気で「西洋流」、外交官の妻としては申し分ないと一は思っているのに、藤尾は一を嫌っている。試験に落第する男など「まっぴら」ということらしい。そこで、さらにもう一人の青年・小野清三(北沢彪)が登場する。彼は、藤尾の(英語の)家庭教師として甲野家に出入りしている。文学専攻の秀才で、大学を首席で卒業(恩賜の銀時計授受)、現在は博士号取得のため、論文作成に取り組んでいる。藤尾は(母・豊乃も)断然、小野を気に入り、ゆくゆくは(欽吾を追い払い)甲野家の婿として迎えたいという魂胆である。しかし、そうは問屋が卸さない。小野は幼い時両親と死別、京都で養父同然に育ててくれた井上孤堂(勝見庸太郎)という恩師が居るからである。娘・小夜子(花井蘭子)と分け隔てなく育て、ゆくゆくは「小野と小夜子を一緒にさせたい」と井上は考えている。今では妻に先立たれ、娘との二人暮らしを託っている身、頼りになるのは小野だけか・・・、そんな思いで、上京してきたのだが・小野は「心変わり」して、藤尾に惹かれている。
要するに、宗近一と甲野藤尾、藤尾と小野清三、小野と井上小夜子、甲野欽吾と宗近糸子という「男女関係」がこの物語の骨子である。そして、主人公は、甲野の父がロンドンで買い求めた50万円の懐中時計、今は藤尾の手許にあるが、それを受け取るのは誰か、という筋書きで物語は展開する。
場面は、①欽吾と一が京都旅行を終え東京に向かう東海道線の車中、そこで偶然にも、上京する井上父娘との遭遇、②甲野家の豊乃、藤尾、欽吾の白々しい対話、③藤尾と小野の親密な出会い、④井上転居宅での小野と小夜子の他人行儀な挨拶、⑤東京勧業博覧会で鉢合わせする欽吾、一、藤尾、糸子の4人グループと小野、井上父娘の3人グループ、⑥小野と井上孤堂の対面、⑦小野との「縁談破談」を申し入れる小野の友人・浅井(嵯峨善兵)と孤堂の討論、⑧浅井から頼まれて小野の下宿を訪れる宗近の侠気、⑨小野の決断と新橋駅での藤尾との訣別、⑩大詰め、藤尾から小野、小野から藤尾、藤尾から宗近へと渡った懐中時計が、暖炉に投げ込まれる瞬間、⑪藤尾の服毒自殺、その訃報(電報)を手にする宗近、といった内容であった。
見どころは満載だが、中でも法律専攻の浅井と弧堂の「討論」は格別、原作にある以下のセリフが忠実に再現されている。「小野は近頃非常なハイカラになりました。あんな所へ行くのは御嬢さんの損です」「君は小野の悪口を云いに来たのかね」「ハハハハ先生本当ですよ」「余計な御世話だ。軽薄な」・・・「何だって、そんな余計な事を云うんだ」「実は頼まれたんです」「頼まれた? 誰に」「小野に頼まれたんです」「小野に頼まれた?」「ああ云う男だものだから、自分で先生の所へ来て断わり切れないんです。それで僕に頼んだです」「ふうん。もっと精しく話すがいい」「二三日中じゅうに是非こちらへ御返事をしなければならないからと云いますから、僕が代理にやって来たんです」「だから、どう云う理由で断わるんだか、それを精しく話したら好いじゃないか」「理由はですな。博士にならなければならないから、どうも結婚なんぞしておられないと云うんです」「じゃ博士の称号の方が、小夜より大事だと云うんだね」「そう云う訳でもないでしょうが、博士になって置かんと将来非常な不利益ですからな」「よし分った。理由はそれぎりかい」「それに確然たる契約のない事だからと云うんです」「契約とは法律上有効の契約という意味だな。証文のやりとりの事だね」「証文でもないですが――その代り長い間御世話になったから、その御礼としては物質的の補助をしたいと云うんです」「月々金でもくれると云うのかい」「そうです」・・・「君は妻君があるかい」「ないです。貰いたいが、自分の口が大事ですからな」「妻君がなければ参考のために聞いて置くがいい。――人の娘は玩具じゃないぜ。博士の称号と小夜と引き替にされてたまるものか。考えて見るがいい。いかな貧乏人の娘でも活物だよ。わしから云えば大事な娘だ。人一人殺しても博士になる気かと小野に聞いてくれ。それから、そう云ってくれ。井上孤堂は法律上の契約よりも徳義上の契約を重んずる人間だって。――月々金を貢いでやる? 貢いでくれと誰が頼んだ。小野の世話をしたのは、泣きついて来て可愛想だから、好意ずくでした事だ。何だ物質的の補助をするなんて、失礼千万な。――小夜や、用があるからちょっと出て御出、おいいないのか」・・・ 「先生そう怒っちゃ困ります。悪ければまた小野に逢って話して見ますから」「君は結婚を極めて容易い事のように考えているが、そんなものじゃない」・・・「君は女の心を知らないから、そんな使に来たんだろう」・・・「人情を知らないから平気でそんな事を云うんだろう。小野の方が破談になれば小夜は明日あしたからどこへでも行けるだろうと思って、云うんだろう。五年以来、夫だと思い込んでいた人から、特別の理由もないのに、急に断わられて、平気ですぐ他家へ嫁に行くような女があるものか。あるかも知れないが小夜はそんな軽薄な女じゃない。そんな軽薄に育て上げたつもりじゃない。――君はそう軽卒に破談の取次をして、小夜の生涯を誤まらして、それで好い心持なのか」「じゃ、まあ御待ちなさい、先生。もう一遍小野に話して見ますから。僕はただ頼まれたから来たんで、そんな精しい事情は知らんのですから」「いや、話してくれないでも好い。厭だと云うものに無理に貰ってもらいたくはない。しかし本人が来て自家に訳を話すが好い」「しかし御嬢さんが、そう云う御考だと……」「小夜の考えぐらい小野には分っているはずださ」「ですがな、それだと小野も困るでしょうから、もう一遍……」「小野にそう云ってくれ。井上孤堂はいくら娘が可愛くっても、厭だと云う人に頭を下げて貰ってもらうような卑劣な男ではないって。――小夜や、おい、いないか」「そう返事をして差支さしつかえないだろうね」「先生もう一遍小野に話しましょう」「話さないでも好い。自家に来て断われと云ってくれ」「とにかく……そう小野に云いましょう」(「夏目漱石 虞美人草 青空文庫」より抜粋引用)
小野同様、浅井も弧堂を師と仰いでいる。その子弟の対話(討論)が、真に迫っていてたいそう面白いのである。
極め付きは、⑧の場面の宗近と小野の対話、これもまた原作どおりに再現されている。
「小野さん、真面目まじめだよ。いいかね。人間は年に一度ぐらい真面目にならなくっちゃならない場合がある。上皮ばかりで生きていちゃ、相手にする張合はりあいがない。また相手にされてもつまるまい。僕は君を相手にするつもりで来たんだよ。好いかね、分ったかい」・・・「分ったら君を対等の人間と見て云うがね。君はなんだか始終不安じゃないか。少しも泰然としていないようだが」「そうかも――知れないです」「そう君が平たく云うと、はなはだ御気の毒だが、全く事実だろう」「ええ」「他人が不安であろうと、泰然としていなかろうと、上皮ばかりで生きている軽薄な社会では構った事じゃない。他人どころか自分自身が不安でいながら得意がっている連中もたくさんある。僕もその一人かも知れない。知れないどころじゃない、たしかにその一人だろう」「あなたは羨うらやましいです。実はあなたのようになれたら結構だと思って、始終考えてるくらいです。そんなところへ行くと僕はつまらない人間に違ないです」「小野さん、そこに気がついているのかね」「いるです」・・・「僕の性質は弱いです」「どうして」「生れつきだから仕方がないです」「君は学問も僕より出来る。頭も僕より好い。僕は君を尊敬している。尊敬しているから救いに来た」「救いに……」「こう云う危あやうい時に、生れつきをたたき直して置かないと、生涯不安でしまうよ。いくら勉強しても、いくら学者になっても取り返しはつかない。ここだよ、小野さん、真面目になるのは。世の中に真面目は、どんなものか一生知らずに済んでしまう人間がいくらもある。皮だけで生きている人間は、土だけで出来ている人形とそう違わない。真面目がなければだが、あるのに人形になるのはもったいない。真面目になった後あとは心持がいいものだよ。君にそう云う経験があるかい」・・・「なければ、一つなって見たまえ、今だ。こんな事は生涯に二度とは来ない。この機をはずすと、もう駄目だ。生涯真面目まじめの味を知らずに死んでしまう。死ぬまでむく犬のようにうろうろして不安ばかりだ。人間は真面目になる機会が重なれば重なるほど出来上ってくる。人間らしい気持がしてくる。――法螺じゃない。自分で経験して見ないうちは分らない。僕はこの通り学問もない、勉強もしない、落第もする、ごろごろしている。それでも君より平気だ。うちの妹なんぞは神経が鈍いからだと思っている。なるほど神経も鈍いだろう。――しかしそう無神経なら今日でも、こうやって車で馳かけつけやしない。そうじゃないか、小野さん」「僕が君より平気なのは、学問のためでも、勉強のためでも、何でもない。時々真面目になるからさ。なるからと云うより、なれるからと云った方が適当だろう。真面目になれるほど、自信力の出る事はない。真面目になれるほど、腰が据すわる事はない。真面目になれるほど、精神の存在を自覚する事はない。天地の前に自分が儼存げんそんしていると云う観念は、真面目になって始めて得られる自覚だ。真面目とはね、君、真剣勝負の意味だよ。やっつける意味だよ。やっつけなくっちゃいられない意味だよ。人間全体が活動する意味だよ。口が巧者に働いたり、手が小器用に働いたりするのは、いくら働いたって真面目じゃない。頭の中を遺憾なく世の中へたたきつけて始めて真面目になった気持になる。安心する。実を云うと僕の妹も昨日きのう真面目になった。甲野も昨日真面目になった。僕は昨日も、今日も真面目だ。君もこの際一度真面目になれ。人一人ひとり真面目になると当人が助かるばかりじゃない。世の中が助かる。――どうだね、小野さん、僕の云う事は分らないかね」「いえ、分ったです」「真面目だよ」「真面目に分ったです」「そんなら好い」「ありがたいです」(「夏目漱石 虞美人草 青空文庫」より抜粋引用)
この対話のキーワードは「真面目」(真剣勝負)ということである。宗近の「計画よりも実行」という信念に裏づけられて、いかにも説得力がある。かくて、小野真三は藤尾との訣別を決意、恩師・弧堂との約束に応えることができたのである。
そしてまた、藤尾は「虚栄の毒を仰いで斃れた」。原作によれば、欽吾は小夜子と結ばれ、義母・豊乃とも「和解」する。藤尾が「宗近か、小野か」、小野が「藤尾か、小夜子か」と迷ったことは《喜劇》であり、「生か、死か」、という問題こそが《悲劇》なのだという夏目漱石の「眼目」は、極めて哲学的である。
「虞美人草」という小説は、1935年、監督・溝口健二によっても映画化されているが、現在そのフィルムは完全な形で残されていない(大詰めの部分が消失している)。しかし、脚色・演出の方法は対照的であるように思われた。展開は、井上弧堂と小夜子の「悲劇」の風情が色濃く、きわめて女性的であった。また、監督・中川信夫の本作品でも、大詰めの場面は原作と異なっている。藤尾が大森に出かけようとして新橋駅で小野を待つ、小野はそこに現れて藤尾に別れを告げる。しかし、原作では、小野は小夜子を伴って甲野家を訪れる。藤尾は小野に会えずやむなく帰宅、そこで欽吾、豊乃、宗近兄妹、小野、小夜子らと一堂に会し、懐中時計の「死」に遭遇するのである。(「宗近君は一歩を煖炉に近く大股に開いた。やっと云う掛声と共に赭黒あかぐろい拳が空くうに躍おどる。時計は大理石の角かどで砕けた。」・原作)そして、藤尾はその場に卒倒する。こうした場面の描出を中川信夫が避けたのはなぜだろうか。夏目漱石の「哲学的」な結末に比べて、その情景を「映画的」に描出することは困難、もしくは野暮と考えたか。いずれにせよ、夏目漱石の文学よりは「女性的」であることは確かなようである。
とはいえ、原作にあくまで忠実、「真面目」に映画化を試みた「傑作」であることは間違いない。厭世感をを漂わせた哲学者・甲野の高田稔、磊落で行動的な外交官の卵・宗近の江川宇礼雄、秀才だが気弱な脆さを感じさせる文学者・小野の北沢彪、体面を重んじ世間体を気にする明治上流階級の典型的な女性・豊乃の伊藤智子、新しい時代で自己を貫こうとする藤尾の霧立のぼる、琴を奏で、どこまでもしとやかな小夜子の花井蘭子、兄思いでおきゃん、しかし古風な豊乃に真っ向から対立して憚らない糸子の花柳小菊、お人好しで俗物、損な役回りを平気で引き受ける浅井の嵯峨善兵、時代の流れに置かれていこうとする井上弧堂の勝見庸太郎、同じく宗近一の父の玉井旭洋、宗近とともにロンドンに向かう同僚の龍崎一郎、といった実力者の面々が綺羅星のごとく居並んでいる。まことに豪華絢爛な配役で、余裕派・夏目漱石の作品を飾るには文字通り「適材適所」、見事な出来映えに心底から拍手を贈りたい。
(2017.5.3)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

要するに、宗近一と甲野藤尾、藤尾と小野清三、小野と井上小夜子、甲野欽吾と宗近糸子という「男女関係」がこの物語の骨子である。そして、主人公は、甲野の父がロンドンで買い求めた50万円の懐中時計、今は藤尾の手許にあるが、それを受け取るのは誰か、という筋書きで物語は展開する。
場面は、①欽吾と一が京都旅行を終え東京に向かう東海道線の車中、そこで偶然にも、上京する井上父娘との遭遇、②甲野家の豊乃、藤尾、欽吾の白々しい対話、③藤尾と小野の親密な出会い、④井上転居宅での小野と小夜子の他人行儀な挨拶、⑤東京勧業博覧会で鉢合わせする欽吾、一、藤尾、糸子の4人グループと小野、井上父娘の3人グループ、⑥小野と井上孤堂の対面、⑦小野との「縁談破談」を申し入れる小野の友人・浅井(嵯峨善兵)と孤堂の討論、⑧浅井から頼まれて小野の下宿を訪れる宗近の侠気、⑨小野の決断と新橋駅での藤尾との訣別、⑩大詰め、藤尾から小野、小野から藤尾、藤尾から宗近へと渡った懐中時計が、暖炉に投げ込まれる瞬間、⑪藤尾の服毒自殺、その訃報(電報)を手にする宗近、といった内容であった。
見どころは満載だが、中でも法律専攻の浅井と弧堂の「討論」は格別、原作にある以下のセリフが忠実に再現されている。「小野は近頃非常なハイカラになりました。あんな所へ行くのは御嬢さんの損です」「君は小野の悪口を云いに来たのかね」「ハハハハ先生本当ですよ」「余計な御世話だ。軽薄な」・・・「何だって、そんな余計な事を云うんだ」「実は頼まれたんです」「頼まれた? 誰に」「小野に頼まれたんです」「小野に頼まれた?」「ああ云う男だものだから、自分で先生の所へ来て断わり切れないんです。それで僕に頼んだです」「ふうん。もっと精しく話すがいい」「二三日中じゅうに是非こちらへ御返事をしなければならないからと云いますから、僕が代理にやって来たんです」「だから、どう云う理由で断わるんだか、それを精しく話したら好いじゃないか」「理由はですな。博士にならなければならないから、どうも結婚なんぞしておられないと云うんです」「じゃ博士の称号の方が、小夜より大事だと云うんだね」「そう云う訳でもないでしょうが、博士になって置かんと将来非常な不利益ですからな」「よし分った。理由はそれぎりかい」「それに確然たる契約のない事だからと云うんです」「契約とは法律上有効の契約という意味だな。証文のやりとりの事だね」「証文でもないですが――その代り長い間御世話になったから、その御礼としては物質的の補助をしたいと云うんです」「月々金でもくれると云うのかい」「そうです」・・・「君は妻君があるかい」「ないです。貰いたいが、自分の口が大事ですからな」「妻君がなければ参考のために聞いて置くがいい。――人の娘は玩具じゃないぜ。博士の称号と小夜と引き替にされてたまるものか。考えて見るがいい。いかな貧乏人の娘でも活物だよ。わしから云えば大事な娘だ。人一人殺しても博士になる気かと小野に聞いてくれ。それから、そう云ってくれ。井上孤堂は法律上の契約よりも徳義上の契約を重んずる人間だって。――月々金を貢いでやる? 貢いでくれと誰が頼んだ。小野の世話をしたのは、泣きついて来て可愛想だから、好意ずくでした事だ。何だ物質的の補助をするなんて、失礼千万な。――小夜や、用があるからちょっと出て御出、おいいないのか」・・・ 「先生そう怒っちゃ困ります。悪ければまた小野に逢って話して見ますから」「君は結婚を極めて容易い事のように考えているが、そんなものじゃない」・・・「君は女の心を知らないから、そんな使に来たんだろう」・・・「人情を知らないから平気でそんな事を云うんだろう。小野の方が破談になれば小夜は明日あしたからどこへでも行けるだろうと思って、云うんだろう。五年以来、夫だと思い込んでいた人から、特別の理由もないのに、急に断わられて、平気ですぐ他家へ嫁に行くような女があるものか。あるかも知れないが小夜はそんな軽薄な女じゃない。そんな軽薄に育て上げたつもりじゃない。――君はそう軽卒に破談の取次をして、小夜の生涯を誤まらして、それで好い心持なのか」「じゃ、まあ御待ちなさい、先生。もう一遍小野に話して見ますから。僕はただ頼まれたから来たんで、そんな精しい事情は知らんのですから」「いや、話してくれないでも好い。厭だと云うものに無理に貰ってもらいたくはない。しかし本人が来て自家に訳を話すが好い」「しかし御嬢さんが、そう云う御考だと……」「小夜の考えぐらい小野には分っているはずださ」「ですがな、それだと小野も困るでしょうから、もう一遍……」「小野にそう云ってくれ。井上孤堂はいくら娘が可愛くっても、厭だと云う人に頭を下げて貰ってもらうような卑劣な男ではないって。――小夜や、おい、いないか」「そう返事をして差支さしつかえないだろうね」「先生もう一遍小野に話しましょう」「話さないでも好い。自家に来て断われと云ってくれ」「とにかく……そう小野に云いましょう」(「夏目漱石 虞美人草 青空文庫」より抜粋引用)
小野同様、浅井も弧堂を師と仰いでいる。その子弟の対話(討論)が、真に迫っていてたいそう面白いのである。
極め付きは、⑧の場面の宗近と小野の対話、これもまた原作どおりに再現されている。
「小野さん、真面目まじめだよ。いいかね。人間は年に一度ぐらい真面目にならなくっちゃならない場合がある。上皮ばかりで生きていちゃ、相手にする張合はりあいがない。また相手にされてもつまるまい。僕は君を相手にするつもりで来たんだよ。好いかね、分ったかい」・・・「分ったら君を対等の人間と見て云うがね。君はなんだか始終不安じゃないか。少しも泰然としていないようだが」「そうかも――知れないです」「そう君が平たく云うと、はなはだ御気の毒だが、全く事実だろう」「ええ」「他人が不安であろうと、泰然としていなかろうと、上皮ばかりで生きている軽薄な社会では構った事じゃない。他人どころか自分自身が不安でいながら得意がっている連中もたくさんある。僕もその一人かも知れない。知れないどころじゃない、たしかにその一人だろう」「あなたは羨うらやましいです。実はあなたのようになれたら結構だと思って、始終考えてるくらいです。そんなところへ行くと僕はつまらない人間に違ないです」「小野さん、そこに気がついているのかね」「いるです」・・・「僕の性質は弱いです」「どうして」「生れつきだから仕方がないです」「君は学問も僕より出来る。頭も僕より好い。僕は君を尊敬している。尊敬しているから救いに来た」「救いに……」「こう云う危あやうい時に、生れつきをたたき直して置かないと、生涯不安でしまうよ。いくら勉強しても、いくら学者になっても取り返しはつかない。ここだよ、小野さん、真面目になるのは。世の中に真面目は、どんなものか一生知らずに済んでしまう人間がいくらもある。皮だけで生きている人間は、土だけで出来ている人形とそう違わない。真面目がなければだが、あるのに人形になるのはもったいない。真面目になった後あとは心持がいいものだよ。君にそう云う経験があるかい」・・・「なければ、一つなって見たまえ、今だ。こんな事は生涯に二度とは来ない。この機をはずすと、もう駄目だ。生涯真面目まじめの味を知らずに死んでしまう。死ぬまでむく犬のようにうろうろして不安ばかりだ。人間は真面目になる機会が重なれば重なるほど出来上ってくる。人間らしい気持がしてくる。――法螺じゃない。自分で経験して見ないうちは分らない。僕はこの通り学問もない、勉強もしない、落第もする、ごろごろしている。それでも君より平気だ。うちの妹なんぞは神経が鈍いからだと思っている。なるほど神経も鈍いだろう。――しかしそう無神経なら今日でも、こうやって車で馳かけつけやしない。そうじゃないか、小野さん」「僕が君より平気なのは、学問のためでも、勉強のためでも、何でもない。時々真面目になるからさ。なるからと云うより、なれるからと云った方が適当だろう。真面目になれるほど、自信力の出る事はない。真面目になれるほど、腰が据すわる事はない。真面目になれるほど、精神の存在を自覚する事はない。天地の前に自分が儼存げんそんしていると云う観念は、真面目になって始めて得られる自覚だ。真面目とはね、君、真剣勝負の意味だよ。やっつける意味だよ。やっつけなくっちゃいられない意味だよ。人間全体が活動する意味だよ。口が巧者に働いたり、手が小器用に働いたりするのは、いくら働いたって真面目じゃない。頭の中を遺憾なく世の中へたたきつけて始めて真面目になった気持になる。安心する。実を云うと僕の妹も昨日きのう真面目になった。甲野も昨日真面目になった。僕は昨日も、今日も真面目だ。君もこの際一度真面目になれ。人一人ひとり真面目になると当人が助かるばかりじゃない。世の中が助かる。――どうだね、小野さん、僕の云う事は分らないかね」「いえ、分ったです」「真面目だよ」「真面目に分ったです」「そんなら好い」「ありがたいです」(「夏目漱石 虞美人草 青空文庫」より抜粋引用)
この対話のキーワードは「真面目」(真剣勝負)ということである。宗近の「計画よりも実行」という信念に裏づけられて、いかにも説得力がある。かくて、小野真三は藤尾との訣別を決意、恩師・弧堂との約束に応えることができたのである。
そしてまた、藤尾は「虚栄の毒を仰いで斃れた」。原作によれば、欽吾は小夜子と結ばれ、義母・豊乃とも「和解」する。藤尾が「宗近か、小野か」、小野が「藤尾か、小夜子か」と迷ったことは《喜劇》であり、「生か、死か」、という問題こそが《悲劇》なのだという夏目漱石の「眼目」は、極めて哲学的である。
「虞美人草」という小説は、1935年、監督・溝口健二によっても映画化されているが、現在そのフィルムは完全な形で残されていない(大詰めの部分が消失している)。しかし、脚色・演出の方法は対照的であるように思われた。展開は、井上弧堂と小夜子の「悲劇」の風情が色濃く、きわめて女性的であった。また、監督・中川信夫の本作品でも、大詰めの場面は原作と異なっている。藤尾が大森に出かけようとして新橋駅で小野を待つ、小野はそこに現れて藤尾に別れを告げる。しかし、原作では、小野は小夜子を伴って甲野家を訪れる。藤尾は小野に会えずやむなく帰宅、そこで欽吾、豊乃、宗近兄妹、小野、小夜子らと一堂に会し、懐中時計の「死」に遭遇するのである。(「宗近君は一歩を煖炉に近く大股に開いた。やっと云う掛声と共に赭黒あかぐろい拳が空くうに躍おどる。時計は大理石の角かどで砕けた。」・原作)そして、藤尾はその場に卒倒する。こうした場面の描出を中川信夫が避けたのはなぜだろうか。夏目漱石の「哲学的」な結末に比べて、その情景を「映画的」に描出することは困難、もしくは野暮と考えたか。いずれにせよ、夏目漱石の文学よりは「女性的」であることは確かなようである。
とはいえ、原作にあくまで忠実、「真面目」に映画化を試みた「傑作」であることは間違いない。厭世感をを漂わせた哲学者・甲野の高田稔、磊落で行動的な外交官の卵・宗近の江川宇礼雄、秀才だが気弱な脆さを感じさせる文学者・小野の北沢彪、体面を重んじ世間体を気にする明治上流階級の典型的な女性・豊乃の伊藤智子、新しい時代で自己を貫こうとする藤尾の霧立のぼる、琴を奏で、どこまでもしとやかな小夜子の花井蘭子、兄思いでおきゃん、しかし古風な豊乃に真っ向から対立して憚らない糸子の花柳小菊、お人好しで俗物、損な役回りを平気で引き受ける浅井の嵯峨善兵、時代の流れに置かれていこうとする井上弧堂の勝見庸太郎、同じく宗近一の父の玉井旭洋、宗近とともにロンドンに向かう同僚の龍崎一郎、といった実力者の面々が綺羅星のごとく居並んでいる。まことに豪華絢爛な配役で、余裕派・夏目漱石の作品を飾るには文字通り「適材適所」、見事な出来映えに心底から拍手を贈りたい。
(2017.5.3)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-21
付録・邦画傑作選・「阿部一族」(監督・熊谷久虎・1938年)
ユーチューブで映画「阿部一族」(監督・熊谷久虎・1938年)を観た。タイトルの前に「国民精神総動員 帝国政府」という字幕が一瞬映し出される。原作は森鷗外、九州肥後藩で起きた、一族滅亡の物語である。監督・熊谷久虎も九州出身、女優・原節子の叔父として知られているが、この映画を制作後(1941年)、国粋主義思想団体を結成し教祖的存在になる。一方、出演は1931年に、歌舞伎大部屋(下級)俳優が創設、(民主的な)「前進座」総動員、というわけで、その取り合わせが、たいそう興味深かった。もっとも、当時の社会が「大政翼賛体制」へと突き進んでいく時勢であったとすれば不思議ではない。冒頭のキャッチ・フレーズがそのことを雄弁に物語っている。
筋書きは単純、先君・肥後守細川忠利の逝去に当たり、18名の殉死が許されたが、阿部一族の当主・阿部弥一右衛門(市川笑太郎)は許されなかった。そのことを嘲笑う城内の空気感じて、彼は追い腹を切る。藩主の細川光尚(生方明)は「余への面当てか」と激怒したが、殉死扱いとしてお咎めはなかった。にもかかわらず、弥一右衛門の長男・権兵衛は先君の一周忌法要で、父の位牌がないことを知るや、焼香の後いきなり自分の髻を切り落とした。かねてより阿部一族の武勲に面白くない大目付の林外記(山崎進蔵、後の河野秋武)は「何たる不埒」と光尚に進言、権兵衛は縛り首に処せられる。合わせて、「阿部一族に不穏な動きあり」という噂を流す。かくて、次男・弥五兵衛(中村翫右衛門)、三男・一太夫(市川進之助)、四男・五太夫(山崎進二郎)、五男・七之丞(市川扇升)ら兄弟とその家族、一族郎党が、籠城して討ち死にする。阿部家の隣は、柄本又七郞(河原崎長一郎)の屋敷、両家は親しく交流していたが、討ち入りの際には、「情は情、義は義」と言い、一番槍で弥五兵衛と対峙したのであった、という物語である。
この映画の眼目(見どころ)は、ひとえに「死に様」の美学であろうか。冒頭の二人の殉死、そして弥一右衛門、追い腹の場面は真に迫っていた。
殉死の一人目は内藤長十郞(市川喜菊之助)、酒好きで失敗を重ねたが、先君に咎められることなく可愛がられ、務めを全うした由、新婚の妻(平塚ふみ子)、母(伊藤智子)、弟(伊藤薫)を後に残して、欣然と東光院に赴く。長十郞享年17歳。二人目は、仲間の五助(中村進五郎)、先君の愛犬の世話を仰せつけられたか、その犬とともに高淋寺に赴く。木の根元に腰を下ろして五助が言う。「オレが死んでしもうたらお前は明日から野良犬じゃ。もし、野良犬でも死にとうなかったら、この握り飯を食え。もし、死にたければ食うな」と言って差し出す。犬は、握り飯を一瞥すると五助の顔を見た。「そうか、お前も一緒に死んでくれるか、ヨカヨカ」と言って犬に頬ずり、涙に暮れた。握り飯に落ち葉が降りかかる。その直後「ワン」という声とともに「松野様。よろしくお頼み申します」、という五助の声が聞こえた。五助享年38歳。
弥一右衛門追い腹の場面、ある雨の降りしきる晩、弥一右衛門は息子5人、一族郎党をを集めて機嫌がよい。庭先に来た仲間・太助(市川延司、後の加東大介)に「ええか、この刀をやる。刀は武士の魂じゃ、これを見たらワシじゃと思え」と愛刀を授ける。息子たちに向かって「ワシは命よりも名を惜しむ。名門のためなら追い腹切って、犬死にでもよい。ワシのことを瓢箪に油塗って切るという者もあるが、ワシは瓢箪に油ば塗って《腹を》切る」と言い放つ。瓢箪に入った酒をまず長男の権兵衛に注ぎ、「ワシにも注いでくれ」。次々と、酒を酌み交わしながら「死なぬはずのワシが死んだら、みんながおぬしたちのことを侮るかもしれん。その時はわしの子に生まれたことを不運だと思ってくれ、しょうがつことなか、ええか、兄弟仲良くせえよ。みんな心を合わせて武士らしく振る舞えよ、アハハハハ」」と笑い飛ばし、終わりに十八番の舞「清経」を披露する。とろどころ「みるめをかりの夜乃空。西に傾く月を見ればいざや我も連れんと。南無阿弥陀佛弥陀如来、迎へさせ給へと、ただ一聲を最期にて、船よりかっぱと落汐(おちじお)の、底の水屑(みくづ)と沈み行く、憂き身の果ぞ悲しき」などと詠うのが聞こえた。
さらに、この場面は「阿部一族」討ち死にの、大詰めでも再現される。弥五兵衛が父の残した瓢箪で弟たちと酒を酌み交わし、「清経」を舞う。
武士道とは死ぬことと見つけたり、主君のために死ぬことが武士の本分であり、主君が死ねば殉死する、その精神こそが「国民精神総動員」(キャンペーン)の本質であることは間違いない。かくて、日本国民はまっしぐらに軍国主義、戦争への道を歩んだのである。 あの「前進座」までもがそれに加担していたという「事実」を知る上で、貴重な歴史的産物であると、私は思った。そして今、再び「戦争の足音が聞こえる」世の中になっているが、断じて同じ過ちを繰り返すまい。映画の最後には「犬死一番」という文字も見えたが、現代では、犬死(戦死)こそが最も愚かな「死に様」であることを肝に銘じたい。
他に、この映画には多くの女性、子どもが登場する。例えば、前述した殉死者・内藤長十郞の新妻、そして母、さらには阿部家の仲間・太助の恋人で、柄本家の女中(堤真佐子)、柄本又七郞の妻(山岸しづ江)、阿部権兵衛の妻(一ノ瀬ゆう子)、一太夫の妻(原緋紗子)、五太夫の妻(岩田富貴子)といった面々だが、彼女らの存在感は希薄、ただ男たちの「義」に従属するだけ、子どもたちもまた「遊び呆ける」姿を見せるだけで、軍国下にある婦女子の苦悩、愛憎、悲哀の描出は不発に終わったと思う。それもまた、当時の社会を反映した、悲しい証しかもしれない。
(2017.6.6)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

筋書きは単純、先君・肥後守細川忠利の逝去に当たり、18名の殉死が許されたが、阿部一族の当主・阿部弥一右衛門(市川笑太郎)は許されなかった。そのことを嘲笑う城内の空気感じて、彼は追い腹を切る。藩主の細川光尚(生方明)は「余への面当てか」と激怒したが、殉死扱いとしてお咎めはなかった。にもかかわらず、弥一右衛門の長男・権兵衛は先君の一周忌法要で、父の位牌がないことを知るや、焼香の後いきなり自分の髻を切り落とした。かねてより阿部一族の武勲に面白くない大目付の林外記(山崎進蔵、後の河野秋武)は「何たる不埒」と光尚に進言、権兵衛は縛り首に処せられる。合わせて、「阿部一族に不穏な動きあり」という噂を流す。かくて、次男・弥五兵衛(中村翫右衛門)、三男・一太夫(市川進之助)、四男・五太夫(山崎進二郎)、五男・七之丞(市川扇升)ら兄弟とその家族、一族郎党が、籠城して討ち死にする。阿部家の隣は、柄本又七郞(河原崎長一郎)の屋敷、両家は親しく交流していたが、討ち入りの際には、「情は情、義は義」と言い、一番槍で弥五兵衛と対峙したのであった、という物語である。
この映画の眼目(見どころ)は、ひとえに「死に様」の美学であろうか。冒頭の二人の殉死、そして弥一右衛門、追い腹の場面は真に迫っていた。
殉死の一人目は内藤長十郞(市川喜菊之助)、酒好きで失敗を重ねたが、先君に咎められることなく可愛がられ、務めを全うした由、新婚の妻(平塚ふみ子)、母(伊藤智子)、弟(伊藤薫)を後に残して、欣然と東光院に赴く。長十郞享年17歳。二人目は、仲間の五助(中村進五郎)、先君の愛犬の世話を仰せつけられたか、その犬とともに高淋寺に赴く。木の根元に腰を下ろして五助が言う。「オレが死んでしもうたらお前は明日から野良犬じゃ。もし、野良犬でも死にとうなかったら、この握り飯を食え。もし、死にたければ食うな」と言って差し出す。犬は、握り飯を一瞥すると五助の顔を見た。「そうか、お前も一緒に死んでくれるか、ヨカヨカ」と言って犬に頬ずり、涙に暮れた。握り飯に落ち葉が降りかかる。その直後「ワン」という声とともに「松野様。よろしくお頼み申します」、という五助の声が聞こえた。五助享年38歳。
弥一右衛門追い腹の場面、ある雨の降りしきる晩、弥一右衛門は息子5人、一族郎党をを集めて機嫌がよい。庭先に来た仲間・太助(市川延司、後の加東大介)に「ええか、この刀をやる。刀は武士の魂じゃ、これを見たらワシじゃと思え」と愛刀を授ける。息子たちに向かって「ワシは命よりも名を惜しむ。名門のためなら追い腹切って、犬死にでもよい。ワシのことを瓢箪に油塗って切るという者もあるが、ワシは瓢箪に油ば塗って《腹を》切る」と言い放つ。瓢箪に入った酒をまず長男の権兵衛に注ぎ、「ワシにも注いでくれ」。次々と、酒を酌み交わしながら「死なぬはずのワシが死んだら、みんながおぬしたちのことを侮るかもしれん。その時はわしの子に生まれたことを不運だと思ってくれ、しょうがつことなか、ええか、兄弟仲良くせえよ。みんな心を合わせて武士らしく振る舞えよ、アハハハハ」」と笑い飛ばし、終わりに十八番の舞「清経」を披露する。とろどころ「みるめをかりの夜乃空。西に傾く月を見ればいざや我も連れんと。南無阿弥陀佛弥陀如来、迎へさせ給へと、ただ一聲を最期にて、船よりかっぱと落汐(おちじお)の、底の水屑(みくづ)と沈み行く、憂き身の果ぞ悲しき」などと詠うのが聞こえた。
さらに、この場面は「阿部一族」討ち死にの、大詰めでも再現される。弥五兵衛が父の残した瓢箪で弟たちと酒を酌み交わし、「清経」を舞う。
武士道とは死ぬことと見つけたり、主君のために死ぬことが武士の本分であり、主君が死ねば殉死する、その精神こそが「国民精神総動員」(キャンペーン)の本質であることは間違いない。かくて、日本国民はまっしぐらに軍国主義、戦争への道を歩んだのである。 あの「前進座」までもがそれに加担していたという「事実」を知る上で、貴重な歴史的産物であると、私は思った。そして今、再び「戦争の足音が聞こえる」世の中になっているが、断じて同じ過ちを繰り返すまい。映画の最後には「犬死一番」という文字も見えたが、現代では、犬死(戦死)こそが最も愚かな「死に様」であることを肝に銘じたい。
他に、この映画には多くの女性、子どもが登場する。例えば、前述した殉死者・内藤長十郞の新妻、そして母、さらには阿部家の仲間・太助の恋人で、柄本家の女中(堤真佐子)、柄本又七郞の妻(山岸しづ江)、阿部権兵衛の妻(一ノ瀬ゆう子)、一太夫の妻(原緋紗子)、五太夫の妻(岩田富貴子)といった面々だが、彼女らの存在感は希薄、ただ男たちの「義」に従属するだけ、子どもたちもまた「遊び呆ける」姿を見せるだけで、軍国下にある婦女子の苦悩、愛憎、悲哀の描出は不発に終わったと思う。それもまた、当時の社会を反映した、悲しい証しかもしれない。
(2017.6.6)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-19
付録・邦画傑作選・「浅草の灯」(監督・島津保次郎・1935年)
ユーチューブで映画「浅草の灯」(監督・島津保次郎・1935年)を観た。東京・浅草を舞台に繰り広げられるオペラ一座の座長、座員、観客、地元の人々の物語である。
冒頭は、オペレッタ「ボッカチオ」の舞台、座員一同が「ベアトリ姉ちゃん」を合唱し ている。その中には、山上七郎(上原謙)が居る。藤井寛平(斎藤達雄)が居る。飛鳥井純(徳大寺伸)が居る。香取真一(笠智衆)が居る。そして、新人・小杉麗子(高峰三枝子)の姿もあった。その麗子の前に、二階席から花束が投げ込まれた。投げたのは、麗子の熱狂的ファン、ポカ長と呼ばれる新人画家の神田長次郎(夏川大二郎)である。その花束を麗子が手にしてくれたので、彼はうれしくてたまらない。公演途中で外に出ると、すぐ傍にある射的屋に赴く。店番をするのはお竜(坪内美子)、下宿仲間のドクトルこと医学生・仁村(近衛敏明)が遊んでいた。ポカ長の射的は百発百中の勢いで、景品を仁村にプレゼント、意気揚々と引き揚げていく。やがて、公演が終わった楽屋で、麗子がもらった花束を「あんた、そんなものいつまで大事にするつもり?」と先輩の吉野紅子(藤原か弥子)が冷やかす。踊り子たちが大騒ぎをしているところに、山上が顔を出した。麗子を呼び出して「ペラゴロ(ポカ長)なんか、相手にするんじゃないよ」と忠告する。
そして麗子はまた呼び出された。今度は酒場のマダム・呉子(岡村文子)、「麗子ちゃん、ちょっと来てくれない?」。呉子は麗子の親代わり、彼女を二階に住まわせている。麗子は呉子に付いていく。その様子を二階から見咎める、一座の座長・佐々木紅光(西村青児)・・・。
麗子が酒場に行くと、土地の顔役・半田耕平(武田春郎)が亭主(ヤクザ)の大平軍治(河村黎吉)と待っていた。半田が「おいしいものを食べに行こう」と言う。麗子は、大平の一睨みでイヤとは言えない。呉子に急かされて洋服に着替え、半田と出て行こうとすると、佐々木が現れた。麗子に向かって「こんなところで何をしているんだ、早く楽屋に帰りなさい」と言うなり連れ去った。佐々木は大学出のインテリ、周囲からは「先生」と呼ばれている。さすがに半田も大平も逆らえない。鳶に油揚をさらわれた恰好で、「チクショウ!。ふざけたまねしやがって。公園に居られないようにしてやる」「一番、やってやろうか」と息巻いた。公園の夜店では大平の配下、地回りの仙吉(磯野秋雄)が、通行人を相手に怪しげな賭博を開帳、遊びに来ていた丁稚小僧に話しかけていたが、「アッ、いけねえ。刑事だ」と遁走する隙に小僧の懐から蟇口を掏り取る。その現場を目撃したのはポカ長、仙吉を捕まえて「おい待てよ。返してやれよ。何も知らない小僧さんが困ってるじゃないか」「何だと、おいペラゴロ!お前、オレを誰だと思っているんだ」「あんたの顔は知らないけど、やったことは知っている、さあ返してやれよ、オレは正義漢なんだ」「ふざけやがって、この野郎、こっちへ来い」と仲間の所へ引きずろうとする。そこに偶然、山上が通りかかった。何だ、どうしたと仙吉を見る。「これは兄貴!、こいつが因縁をつけやがるんで」「まあ、今日の所は引いてくれ」と山上は、カウボーイ・ハットを脱いで頭を下げたのでその場は収まった。ポカ長は、思わぬ所でオペラのスター山上に助けられ感激する。そして二人は「十二階」へ、遠い彼方を見やりながら語り合う。「どこを見てるんですか」「あっちに故郷があるんだ」「どこですか」「信州だ」「私も信州です。上諏訪という所です」「そうか、オレは岡谷だ」。かくて、二人の間には厚い友情が芽生えたか・・・。
やがて、半田、大平一味の復讐が始まる。配下の仙吉たちに佐々木の舞台を「ヤジリ倒せ」と指示する。舞台は「カルメン」、カルメン役は、佐々木の妻・松島摩利枝(杉村春子)であった。大勢の役者が袖に消え、舞台は摩利枝ひとりになった。そこに現れるホセ役の佐々木、その姿を見て仙吉たちが大声を上げてヤジりまくる。あまりのひどさに、佐々木は客席に向かって仁王立ち、「私は芸人じゃない、これでも芸術家なんだ!」と叫んだ。「ホンマカイナ」という声を聞いて山上も袖から飛び出す。客席では乱闘が始まるという有様で、当日の公演は中止となってしまった。激高した佐々木は、「もう舞台には立たない」という。奥役(河原侃二)が止めるのも聞かず、「摩利枝、さあ帰るんだ!」と妻を促すが、意外にも摩利枝は「イヤです!私はここに残ります」と、動こうとしない。一味の計略はまんまと成功したのである。それもそのはず、摩利枝は半田と裏でつながり、麗子との間をとりもとうとしていたのだから・・・。摩利枝は佐々木と別れて新しい劇団を作りたい、その資金を半田に求めていた。半田はその見返りに麗子を求めている。
摩利枝は麗子に半田の所に行くよう説得する。イヤとは言わせない雰囲気に麗子はやむなく承諾、摩利枝は一瞬頬笑んだが、「この前みたいにすっぽかしたら承知しないよ。紅子、送って行ってやりな」と言い置いて立ち去った。泣き崩れる麗子を見て、紅子は「こんな可愛い子を行かせたくない。いいわ、あたし独りで行ってくる」と言う。「大丈夫よ、何とか誤魔化してくるわよ。それより麗子ちゃん、何でも山上さんを頼りにするといいわ、いい人よ、正義漢よ、男よ」。紅子もまた山上に恋い焦がれているのであった。紅子を見送り、なおも泣きじゃくっている麗子を山上が見つけた。事情を聞いた山上は、麗子を仲間の部屋に連れて行く。 このままでは麗子の身が危ないと座員と思案しているところに、ポカ長が訪ねて来た。ちょうどいい、ポカ長の下宿に匿ってもらおうというと、ポカ長は「下宿代が滞っているので・・・」と渋る。香取が「100円ほどあればいいか、オレが何とかする」。彼は、大阪の新劇運動に参加する、その前に100円前借りして、「ドロンする」と涼しい顔で言うのだ。渡りに船、一同はすぐさま同意、麗子は根岸にあるポカ長の下宿で身を隠すことになった。一刻も早く、ということで麗子はポカ長の下宿へ・・・。その様子を射的屋のお竜が目撃していた。
またまた、すっぽかされた半田は激怒して摩利枝に電話する。摩利枝はあわてて半田の所に行ったのだが、麗子の行方は判らない。
翌日、山下は香取が調達した100円を渡しに神田の下宿に行く。神田と麗子に外出はしないようにと言い含め、浅草に戻ると、仙吉たちが待ち構えていた。お竜から、麗子がポカ長と一緒に立ち去ったことを聞き出していたのだ。「ポカ長の下宿はどこだ」「知るもんか」と揉めている所に、藤井が飛んで来た。「飛鳥井の容体が急変した、オレは医者を呼んでくる」と告げる。飛鳥井は山上たちの親友、かねてから胸を患っていた。座員の皆に看取られて、飛鳥井は逝った。「人間は、遅かれ早かれ皆死ぬんだ」という香取の言葉に、山下は嗚咽しながら肯く・・・。
舞台稽古が始まっている。それを客席から見つめる摩利枝、佐々木の代わりに演出を手がけている様子、その場に山上がやって来ると、振り向いて言う。「ねえ、いいかげんに麗子を返しなよ。どこにやったの?」「知りませんね」「先生がいなくなってからバカに楯突くじゃないの」。そこに香取が割って入った。「麗子なら、私が100円前借りして関西に逃がしましたよ。いずれは楽天地か宝塚でしょう」。摩利枝は驚くやら、怒るやら、悔しいやら、あたふたとその場を立ち去った。香取はすでに大阪行きの切符を手にしている。「今夜はお別れだ、いつもの所に飲みに行こう」。
飛鳥井は死に、香取も去った、山上は淋しさをこらえながらポカ長の下宿を訪れる。飛鳥井の死を知らせに来たのだが・・・。しかし、そこでは麗子が、神田や下宿仲間とトランプに興じていた。山上は呆れて、神田に「今の連中に麗子の素性を教えたのか」に訊ねると「ああ、教えた」「何だってそんなことをしたんだ」「見ればわかるじゃないか、ビクビクするなよ。オレは麗子さんのためなら命を投げ出したっていい」。その言葉を聞いて山上は激怒した。「てめえ、一人の命で何が解決するんだ、みんながどんなに苦労しているかわからねえのか」と神田を殴り倒し、足蹴にする。泣き出す麗子に「こんなところにいられない。さあ、行くんだ」と連れ出そうとしたが、麗子は拒否する。「あたしはここにいます」。山上は一瞬キッと睨んだが、「そうか、それならそれでいい」という表情になり出て行った。
一人とぼとぼと楽屋に戻る道、途中から雨が降り出した。楽屋に戻る道でお竜と出会った。麗子の件で仙吉たちに嫌がらせを受け、浅草に居辛くなった、田舎に帰るという。「山上さん、一緒に行ってくれない。あなたと一緒になった夢を見たの」「オレは今、男と女のことは考えたくない」「怒ったの」「いや、でもごめん、オレ先に行くよ」。山上の心中には麗子の姿が浮かんでいたのかも知れない。
翌日も雨、楽屋の部屋では紅子が飛鳥井の遺影に線香を上げている。弁当を掻っ込む山上に、お茶を注ぎながら「香取さん、どうしているかしら。淋しくなったわねえ」「あいつのことだから、うまくやっているよ」、そこに藤井がやって来て「佐々木先生が奥さんと別れ話をしている。行ってみてくれないか」と言う。摩利枝の楽屋に行くと、佐々木が「山上君、お別れを言いに来た。もうこの年で役者でもあるまい。日本の演劇史を書こうと思う」「それはいい、大賛成です」「ところが、こいつは反対なんだ」。摩利枝は「別れるなら手切れ金を出しなさい」の一点張り、「奥さん、役者を辞めて、先生の仕事を手伝ってあげてください」と懇願するが「何を生意気な!」と摩利枝は応じない。終いには「あたしは、くどいことは嫌いなんだ!」と毒づく始末、もうこれまでと、山上はポケットからナイフを取り出した。「まあ!何をするんです」とたじろぐ摩利枝に「奥さん、先生に謝りなさい。さもなければ、ここで指を詰めるまでだ。オレも浅草の山七だ。今まで通らなかった話はない。どうせ身寄りもないオレだ、指がなくなったってどうということはない。さあ、謝れ!謝らなければ指を詰めるぞ」と必死に迫る。佐々木を慕う山上のまごころに打たれたか・・・、摩利枝は泣きながら「ごめんなさい、私が間違っていました」と佐々木に頭を下げた。山上も安堵して「手荒なことをしてすみませんでした」と謝る。
そこにお竜が飛び込んで来た。「たいへん、ポカ長が大平の家に麗子ちゃんの荷物を取りに行き、閉じ込められてるの」「オレはポカ長のことは知らない」「それでも男なの、いくじなし、卑怯よ」「何? 卑怯だと」、山上は頭に来て、大平の店に駆けつける。大平が仙吉たちに「半殺しにしろ」と指示している。山上は、若い者を殴り飛ばして、大平に迫る。「ポカ長を返せ」「誰だそれは」「二階のお客様だ」。かくて、ポカ長は無事、救出された。「すまねえな、兄貴!」「あんな危ないところに行く奴があるか」「でも、麗子ちゃんの着物や大切なものを取りに来たんだ」「・・・」「ところで兄貴、オレ、麗子ちゃんと結婚したいんだが」「・・・麗子は何と言ってるんだ」「山上さんが承諾すれば・・・と」「・・・そうか、じゃあいいだろう。結婚しろよ」「そうか!いいのか、ありがとう、兄貴」「そのかわり、勉強していい絵をかけよ」。
山上が楽屋に帰る途中、お竜が待っていた。「どうだった」「ああ、無事終わったよ」「そう、よかったわね」「オレ、話があるんだ」「何?」「これから大阪へ行こうと思う。香取にいろいろ教えてもらうんだ。もう浅草に用はない」「じゃあ、あたしも連れてって、女中でも何でもするから」「・・・・」
かくて二人の姿は、東海道線の車中に・・・、車窓には、雪を頂いた富士山の景色がくっきりと映っていた。そして画面には「終」の文字もまた・・・。
この映画の眼目は「痛快娯楽人情劇」の描出にあるのだろう。そのための役者は揃っていた。善玉の上原謙、夏川大二郎、笠智衆、齋藤達雄、西村青児に、徳大寺伸が「悲劇」を演じる。悪玉の武田春郞、河村黎吉、磯野秋雄、日守新一が、思い切り浅草ヤクザの「柄の悪さ」を描出する。女優では、悲劇のヒロイン高峰三枝子、先輩の藤原か弥子、着物が似合う坪内美子、悪玉の岡村文子、特別出演の杉村春子などなど、おのおのが存分に持ち味を発揮して、ねらい通り、たいそう見応えのある作品に仕上がっていたと、私は思う。
見どころは、何と言っても上原謙の「男っぷり」である。麗子、紅子、お竜の三人から惚れられ、ポカ長からも「兄貴」と慕われる。ケンカにはめっぽう強く、自分の思いを通さなかったことはない。土地のヤクザからも一目置かれている。ただ一点、本命の麗子からは「袖にされた」か、カウボーイ姿でとぼとぼ歩く姿が「絵になっていた」。極め付きは、杉村春子との対決、身勝手で気が強くおきゃんな摩利枝を、思わず「改心」させる「侠気」が光っていた。次は、その杉村春子の舞台姿である。当時は28歳、多少「うば桜」とはいえ、一座のプリ・マドンナとして堂々と「カルメン」を踊り歌う。夫役の西村青児とも丁々発止と渡り合う「啖呵」は、たまらなく魅力的であった。他にも、ポカ長・夏川大二郎の、強者(仙吉、大平)には敢然と立ち向かう「正義漢」振り、弱者(麗子)には「女ことば」まで使ってプロポーズする「道化」振りが際立っていた。さらには、飄然とした笠智衆の風情、極道もどきで滑稽な河村黎吉、武田春郞、磯野秋雄、日守新一らの姿が色を添えていた。
最後は、ようやく願いが叶った坪内美子を、霊峰・富士山が祝福する・・・、見事なエンディングであった。
(2017.6.13)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

冒頭は、オペレッタ「ボッカチオ」の舞台、座員一同が「ベアトリ姉ちゃん」を合唱し ている。その中には、山上七郎(上原謙)が居る。藤井寛平(斎藤達雄)が居る。飛鳥井純(徳大寺伸)が居る。香取真一(笠智衆)が居る。そして、新人・小杉麗子(高峰三枝子)の姿もあった。その麗子の前に、二階席から花束が投げ込まれた。投げたのは、麗子の熱狂的ファン、ポカ長と呼ばれる新人画家の神田長次郎(夏川大二郎)である。その花束を麗子が手にしてくれたので、彼はうれしくてたまらない。公演途中で外に出ると、すぐ傍にある射的屋に赴く。店番をするのはお竜(坪内美子)、下宿仲間のドクトルこと医学生・仁村(近衛敏明)が遊んでいた。ポカ長の射的は百発百中の勢いで、景品を仁村にプレゼント、意気揚々と引き揚げていく。やがて、公演が終わった楽屋で、麗子がもらった花束を「あんた、そんなものいつまで大事にするつもり?」と先輩の吉野紅子(藤原か弥子)が冷やかす。踊り子たちが大騒ぎをしているところに、山上が顔を出した。麗子を呼び出して「ペラゴロ(ポカ長)なんか、相手にするんじゃないよ」と忠告する。
そして麗子はまた呼び出された。今度は酒場のマダム・呉子(岡村文子)、「麗子ちゃん、ちょっと来てくれない?」。呉子は麗子の親代わり、彼女を二階に住まわせている。麗子は呉子に付いていく。その様子を二階から見咎める、一座の座長・佐々木紅光(西村青児)・・・。
麗子が酒場に行くと、土地の顔役・半田耕平(武田春郎)が亭主(ヤクザ)の大平軍治(河村黎吉)と待っていた。半田が「おいしいものを食べに行こう」と言う。麗子は、大平の一睨みでイヤとは言えない。呉子に急かされて洋服に着替え、半田と出て行こうとすると、佐々木が現れた。麗子に向かって「こんなところで何をしているんだ、早く楽屋に帰りなさい」と言うなり連れ去った。佐々木は大学出のインテリ、周囲からは「先生」と呼ばれている。さすがに半田も大平も逆らえない。鳶に油揚をさらわれた恰好で、「チクショウ!。ふざけたまねしやがって。公園に居られないようにしてやる」「一番、やってやろうか」と息巻いた。公園の夜店では大平の配下、地回りの仙吉(磯野秋雄)が、通行人を相手に怪しげな賭博を開帳、遊びに来ていた丁稚小僧に話しかけていたが、「アッ、いけねえ。刑事だ」と遁走する隙に小僧の懐から蟇口を掏り取る。その現場を目撃したのはポカ長、仙吉を捕まえて「おい待てよ。返してやれよ。何も知らない小僧さんが困ってるじゃないか」「何だと、おいペラゴロ!お前、オレを誰だと思っているんだ」「あんたの顔は知らないけど、やったことは知っている、さあ返してやれよ、オレは正義漢なんだ」「ふざけやがって、この野郎、こっちへ来い」と仲間の所へ引きずろうとする。そこに偶然、山上が通りかかった。何だ、どうしたと仙吉を見る。「これは兄貴!、こいつが因縁をつけやがるんで」「まあ、今日の所は引いてくれ」と山上は、カウボーイ・ハットを脱いで頭を下げたのでその場は収まった。ポカ長は、思わぬ所でオペラのスター山上に助けられ感激する。そして二人は「十二階」へ、遠い彼方を見やりながら語り合う。「どこを見てるんですか」「あっちに故郷があるんだ」「どこですか」「信州だ」「私も信州です。上諏訪という所です」「そうか、オレは岡谷だ」。かくて、二人の間には厚い友情が芽生えたか・・・。
やがて、半田、大平一味の復讐が始まる。配下の仙吉たちに佐々木の舞台を「ヤジリ倒せ」と指示する。舞台は「カルメン」、カルメン役は、佐々木の妻・松島摩利枝(杉村春子)であった。大勢の役者が袖に消え、舞台は摩利枝ひとりになった。そこに現れるホセ役の佐々木、その姿を見て仙吉たちが大声を上げてヤジりまくる。あまりのひどさに、佐々木は客席に向かって仁王立ち、「私は芸人じゃない、これでも芸術家なんだ!」と叫んだ。「ホンマカイナ」という声を聞いて山上も袖から飛び出す。客席では乱闘が始まるという有様で、当日の公演は中止となってしまった。激高した佐々木は、「もう舞台には立たない」という。奥役(河原侃二)が止めるのも聞かず、「摩利枝、さあ帰るんだ!」と妻を促すが、意外にも摩利枝は「イヤです!私はここに残ります」と、動こうとしない。一味の計略はまんまと成功したのである。それもそのはず、摩利枝は半田と裏でつながり、麗子との間をとりもとうとしていたのだから・・・。摩利枝は佐々木と別れて新しい劇団を作りたい、その資金を半田に求めていた。半田はその見返りに麗子を求めている。
摩利枝は麗子に半田の所に行くよう説得する。イヤとは言わせない雰囲気に麗子はやむなく承諾、摩利枝は一瞬頬笑んだが、「この前みたいにすっぽかしたら承知しないよ。紅子、送って行ってやりな」と言い置いて立ち去った。泣き崩れる麗子を見て、紅子は「こんな可愛い子を行かせたくない。いいわ、あたし独りで行ってくる」と言う。「大丈夫よ、何とか誤魔化してくるわよ。それより麗子ちゃん、何でも山上さんを頼りにするといいわ、いい人よ、正義漢よ、男よ」。紅子もまた山上に恋い焦がれているのであった。紅子を見送り、なおも泣きじゃくっている麗子を山上が見つけた。事情を聞いた山上は、麗子を仲間の部屋に連れて行く。 このままでは麗子の身が危ないと座員と思案しているところに、ポカ長が訪ねて来た。ちょうどいい、ポカ長の下宿に匿ってもらおうというと、ポカ長は「下宿代が滞っているので・・・」と渋る。香取が「100円ほどあればいいか、オレが何とかする」。彼は、大阪の新劇運動に参加する、その前に100円前借りして、「ドロンする」と涼しい顔で言うのだ。渡りに船、一同はすぐさま同意、麗子は根岸にあるポカ長の下宿で身を隠すことになった。一刻も早く、ということで麗子はポカ長の下宿へ・・・。その様子を射的屋のお竜が目撃していた。
またまた、すっぽかされた半田は激怒して摩利枝に電話する。摩利枝はあわてて半田の所に行ったのだが、麗子の行方は判らない。
翌日、山下は香取が調達した100円を渡しに神田の下宿に行く。神田と麗子に外出はしないようにと言い含め、浅草に戻ると、仙吉たちが待ち構えていた。お竜から、麗子がポカ長と一緒に立ち去ったことを聞き出していたのだ。「ポカ長の下宿はどこだ」「知るもんか」と揉めている所に、藤井が飛んで来た。「飛鳥井の容体が急変した、オレは医者を呼んでくる」と告げる。飛鳥井は山上たちの親友、かねてから胸を患っていた。座員の皆に看取られて、飛鳥井は逝った。「人間は、遅かれ早かれ皆死ぬんだ」という香取の言葉に、山下は嗚咽しながら肯く・・・。
舞台稽古が始まっている。それを客席から見つめる摩利枝、佐々木の代わりに演出を手がけている様子、その場に山上がやって来ると、振り向いて言う。「ねえ、いいかげんに麗子を返しなよ。どこにやったの?」「知りませんね」「先生がいなくなってからバカに楯突くじゃないの」。そこに香取が割って入った。「麗子なら、私が100円前借りして関西に逃がしましたよ。いずれは楽天地か宝塚でしょう」。摩利枝は驚くやら、怒るやら、悔しいやら、あたふたとその場を立ち去った。香取はすでに大阪行きの切符を手にしている。「今夜はお別れだ、いつもの所に飲みに行こう」。
飛鳥井は死に、香取も去った、山上は淋しさをこらえながらポカ長の下宿を訪れる。飛鳥井の死を知らせに来たのだが・・・。しかし、そこでは麗子が、神田や下宿仲間とトランプに興じていた。山上は呆れて、神田に「今の連中に麗子の素性を教えたのか」に訊ねると「ああ、教えた」「何だってそんなことをしたんだ」「見ればわかるじゃないか、ビクビクするなよ。オレは麗子さんのためなら命を投げ出したっていい」。その言葉を聞いて山上は激怒した。「てめえ、一人の命で何が解決するんだ、みんながどんなに苦労しているかわからねえのか」と神田を殴り倒し、足蹴にする。泣き出す麗子に「こんなところにいられない。さあ、行くんだ」と連れ出そうとしたが、麗子は拒否する。「あたしはここにいます」。山上は一瞬キッと睨んだが、「そうか、それならそれでいい」という表情になり出て行った。
一人とぼとぼと楽屋に戻る道、途中から雨が降り出した。楽屋に戻る道でお竜と出会った。麗子の件で仙吉たちに嫌がらせを受け、浅草に居辛くなった、田舎に帰るという。「山上さん、一緒に行ってくれない。あなたと一緒になった夢を見たの」「オレは今、男と女のことは考えたくない」「怒ったの」「いや、でもごめん、オレ先に行くよ」。山上の心中には麗子の姿が浮かんでいたのかも知れない。
翌日も雨、楽屋の部屋では紅子が飛鳥井の遺影に線香を上げている。弁当を掻っ込む山上に、お茶を注ぎながら「香取さん、どうしているかしら。淋しくなったわねえ」「あいつのことだから、うまくやっているよ」、そこに藤井がやって来て「佐々木先生が奥さんと別れ話をしている。行ってみてくれないか」と言う。摩利枝の楽屋に行くと、佐々木が「山上君、お別れを言いに来た。もうこの年で役者でもあるまい。日本の演劇史を書こうと思う」「それはいい、大賛成です」「ところが、こいつは反対なんだ」。摩利枝は「別れるなら手切れ金を出しなさい」の一点張り、「奥さん、役者を辞めて、先生の仕事を手伝ってあげてください」と懇願するが「何を生意気な!」と摩利枝は応じない。終いには「あたしは、くどいことは嫌いなんだ!」と毒づく始末、もうこれまでと、山上はポケットからナイフを取り出した。「まあ!何をするんです」とたじろぐ摩利枝に「奥さん、先生に謝りなさい。さもなければ、ここで指を詰めるまでだ。オレも浅草の山七だ。今まで通らなかった話はない。どうせ身寄りもないオレだ、指がなくなったってどうということはない。さあ、謝れ!謝らなければ指を詰めるぞ」と必死に迫る。佐々木を慕う山上のまごころに打たれたか・・・、摩利枝は泣きながら「ごめんなさい、私が間違っていました」と佐々木に頭を下げた。山上も安堵して「手荒なことをしてすみませんでした」と謝る。
そこにお竜が飛び込んで来た。「たいへん、ポカ長が大平の家に麗子ちゃんの荷物を取りに行き、閉じ込められてるの」「オレはポカ長のことは知らない」「それでも男なの、いくじなし、卑怯よ」「何? 卑怯だと」、山上は頭に来て、大平の店に駆けつける。大平が仙吉たちに「半殺しにしろ」と指示している。山上は、若い者を殴り飛ばして、大平に迫る。「ポカ長を返せ」「誰だそれは」「二階のお客様だ」。かくて、ポカ長は無事、救出された。「すまねえな、兄貴!」「あんな危ないところに行く奴があるか」「でも、麗子ちゃんの着物や大切なものを取りに来たんだ」「・・・」「ところで兄貴、オレ、麗子ちゃんと結婚したいんだが」「・・・麗子は何と言ってるんだ」「山上さんが承諾すれば・・・と」「・・・そうか、じゃあいいだろう。結婚しろよ」「そうか!いいのか、ありがとう、兄貴」「そのかわり、勉強していい絵をかけよ」。
山上が楽屋に帰る途中、お竜が待っていた。「どうだった」「ああ、無事終わったよ」「そう、よかったわね」「オレ、話があるんだ」「何?」「これから大阪へ行こうと思う。香取にいろいろ教えてもらうんだ。もう浅草に用はない」「じゃあ、あたしも連れてって、女中でも何でもするから」「・・・・」
かくて二人の姿は、東海道線の車中に・・・、車窓には、雪を頂いた富士山の景色がくっきりと映っていた。そして画面には「終」の文字もまた・・・。
この映画の眼目は「痛快娯楽人情劇」の描出にあるのだろう。そのための役者は揃っていた。善玉の上原謙、夏川大二郎、笠智衆、齋藤達雄、西村青児に、徳大寺伸が「悲劇」を演じる。悪玉の武田春郞、河村黎吉、磯野秋雄、日守新一が、思い切り浅草ヤクザの「柄の悪さ」を描出する。女優では、悲劇のヒロイン高峰三枝子、先輩の藤原か弥子、着物が似合う坪内美子、悪玉の岡村文子、特別出演の杉村春子などなど、おのおのが存分に持ち味を発揮して、ねらい通り、たいそう見応えのある作品に仕上がっていたと、私は思う。
見どころは、何と言っても上原謙の「男っぷり」である。麗子、紅子、お竜の三人から惚れられ、ポカ長からも「兄貴」と慕われる。ケンカにはめっぽう強く、自分の思いを通さなかったことはない。土地のヤクザからも一目置かれている。ただ一点、本命の麗子からは「袖にされた」か、カウボーイ姿でとぼとぼ歩く姿が「絵になっていた」。極め付きは、杉村春子との対決、身勝手で気が強くおきゃんな摩利枝を、思わず「改心」させる「侠気」が光っていた。次は、その杉村春子の舞台姿である。当時は28歳、多少「うば桜」とはいえ、一座のプリ・マドンナとして堂々と「カルメン」を踊り歌う。夫役の西村青児とも丁々発止と渡り合う「啖呵」は、たまらなく魅力的であった。他にも、ポカ長・夏川大二郎の、強者(仙吉、大平)には敢然と立ち向かう「正義漢」振り、弱者(麗子)には「女ことば」まで使ってプロポーズする「道化」振りが際立っていた。さらには、飄然とした笠智衆の風情、極道もどきで滑稽な河村黎吉、武田春郞、磯野秋雄、日守新一らの姿が色を添えていた。
最後は、ようやく願いが叶った坪内美子を、霊峰・富士山が祝福する・・・、見事なエンディングであった。
(2017.6.13)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-18
付録・邦画傑作選・「桃中軒雲右衛門」(監督・成瀬巳喜男・1936年)
ユーチューブで映画「桃中軒雲右衛門」(監督・成瀬巳喜男・1936年)を観た。
原作は真山青果、明治から大正にかけ、浪曲界の大看板で「浪聖」と謳われた桃中軒雲右衛門の「身辺情話」である。成瀬作品にしては珍しく「男性中心」の映画で、女優は雲右衛門の曲師であり妻女のお妻を演じた細川ちか子、愛妾・千鳥を演じた千葉早智子しか存在感がない。(他は、ほとんど芸者衆である。)
筋書きは単純、九州から東京に凱旋する桃中軒雲右衛門(月形龍之介)が、先代からの曲師・松月(藤原釜足)と、途中の静岡で雲隠れ、番頭(御橋公)や弟子(小杉義男)たちが大騒ぎする中、国府津に置いてきた息子、泉太郎(伊藤薫)の後見人・倉田(三島雅夫)の説得で、ようやく東京入り。本郷座での公演は大成功を収めるが、たまたま出会った芸者・千鳥の初々しさに惹かれ、病を抱えたお妻との関係が疎遠になっていく。新聞では雲右衛門の醜聞が大きく取り上げられるが、どこ吹く風、これも「芸の肥やし」と全く意に介さない。やがて、お妻は病状が悪化、泉太郎や千鳥までもが見舞うように勧めるが「お妻はただの女ではない。芸を競い合う相手だから、俺を慕うような(俺に助けを求めるような)姿は見たくない」と言い、頑なに拒絶する。その気持ちがお妻にも通じたか、弟子に看取られながら、静かに息を引き取った。その亡骸の前で、雲右衛門は威儀を正し、極め付きを披露する。あたかも、曲師お妻の「合いの手」を頼りにするかのように・・・。
この映画の見どころは、若き日、月形龍之介の雄姿であろうか。雲右衛門は「俺はしがない流し芸人の倅、名誉や地位などどうでもよい。傷だらけになって、ただ芸一筋に生きるのだ」と主張する。その容貌とは裏腹に、脱世間・常識破りで不健全な、カッコ悪い生き様を求めているのだ。そのことを周囲は理解できない。理解できたのは妻女のお妻ただ一人。共に立つ舞台でお妻の調子が外れた。そのことを指摘するだけで(昔のように)怒ったり殴ったりしない雲右衛門を、お妻は激しく罵倒する。その名場面こそが、見どころの極め付きであったと、私は思う。「お妻、今日は二度まで調子を外したが、オレの芸にいけねえ所があったのか」「弾いていて泣けません」「ちょっと三味線持っといで」と、穏やかに言うが、お妻はハッキリと断る「あたしはイヤだ。他の人にやらせたらいいでしょう」。雲右衛門はキッとして「お妻!」と言ったが、「何です」と軽くあしらわれて次の言葉が出なかった。「・・・・」「お前さん、この頃のあたしの三味線をどう聞いてます。自分ながら、あたしの三味線はもう峠を越したと思ってます。身体の病には勝てやしない」。雲右衛門は「オレはそれほどとは思っていなかったが・・・」と取りなすが、健気にもお妻は攻勢に出た。「その女房に小言一つ言えずに結構がって詠っているお前さんは、それでも天下の雲右衛門か、桃中軒の総元締めか。昔のことを思うと涙がこぼれらあ」。雲右衛門も「夫婦の中でも芸は仇だ、勝手なことを言うなよ」と反撃に出たが「お前さんは昔、あたしの三味線の出来が悪い日には撲ったり蹴ったりした人だよ。もとより女として可愛がられたこともない。自分の芸のためにあたしの三味線を食ったんだ。自分の芸のためなら人も師匠も忘れられる強い心を持っていたんだよ。(九州時代からの)夫婦でも芸は仇、お互いに負けまいという真剣さはどうなったんだい」「それはオレも思うよ」と認めて弱音を吐く。「人気が下がって芸が落ちるのなら、お前さんもそれだけの人だよ」「そうじゃあねえ。衰え始めたオレの芸に、かえって反対の人気が立ってくるんだ。オレはそれを思うといつも背中が寒くなる」「お前さん、いくつなんだい、それを言って済む歳かい」、お妻は、「あたしの身体はもう長くない、今のお前さんの意気地ない姿を見て、逝くところへ逝けるかい」と一睨み、最後に「お前さんは女でも女房でも自分の芸のためなら、みんな食ってきた人なんだよ、それが何だい、いまごろ女房の三味線に蹴躓いて汗なんか流して。これだけ言やあたくさんだろ・・・」と言って、背中を向けすすり泣く。雲右衛門は「お妻!」と言って立ち上がったが、後は無言、静かに頭を垂れる他はなかった。
二人の対話は、これを最後に交わされることはなかったのである。
この場面こそが、この映画の真髄であり、男の弱さと女の強さ・逞しさが見事に浮き彫りされる、成瀬監督ならではの演出ではないだろうか。それまで、夫唱婦随の景色で、しおらしく見られていた曲師・お妻が、一転、立て板に水のような啖呵がほとばしる。細川ちか子の「鉄火肌」の片鱗も垣間見られて、この場面だけで、私は大いに満足できたのである。蛇足だが、千鳥役、千葉早智子の演技も冴えていた。芸妓から雲右衛門の新造に納まり、初々しかった娘の景色に貫禄が加わる。世間の風評を意に介さず、弟子や番頭とも五分で渡り合い、お妻を見舞う素振りも見せながら、足りない責任はは雲右衛門におっかぶせるという姿勢は、成瀬監督が自家薬籠中の「女模様」に他ならない。女性映画の名手・成瀬巳喜男のモットーは、ここでも貫かれているのである。比べて、男性陣が繰り広げる様々な対立や葛藤は、所詮「小競り合い」に過ぎず、悲劇を装えば装うほど、喜劇的にならざるを得なかった。名優・藤原釜足が、電話口でお妻の訃報(臨終の様子)を聞き、「オレはこの年になって、それを聞こうとは思わなかった、早く電話を切ってくれ」と、涙ぐむ姿が、何よりもそのことを雄弁に物語っている。
国威高揚の空気が強い当時において、その片棒を担がされる雲右衛門に、思い切り無様で無力な姿をダブらせようと試みる成瀬監督の「腕は鈍っていない」のである。拍手。
(2017.6.18)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

原作は真山青果、明治から大正にかけ、浪曲界の大看板で「浪聖」と謳われた桃中軒雲右衛門の「身辺情話」である。成瀬作品にしては珍しく「男性中心」の映画で、女優は雲右衛門の曲師であり妻女のお妻を演じた細川ちか子、愛妾・千鳥を演じた千葉早智子しか存在感がない。(他は、ほとんど芸者衆である。)
筋書きは単純、九州から東京に凱旋する桃中軒雲右衛門(月形龍之介)が、先代からの曲師・松月(藤原釜足)と、途中の静岡で雲隠れ、番頭(御橋公)や弟子(小杉義男)たちが大騒ぎする中、国府津に置いてきた息子、泉太郎(伊藤薫)の後見人・倉田(三島雅夫)の説得で、ようやく東京入り。本郷座での公演は大成功を収めるが、たまたま出会った芸者・千鳥の初々しさに惹かれ、病を抱えたお妻との関係が疎遠になっていく。新聞では雲右衛門の醜聞が大きく取り上げられるが、どこ吹く風、これも「芸の肥やし」と全く意に介さない。やがて、お妻は病状が悪化、泉太郎や千鳥までもが見舞うように勧めるが「お妻はただの女ではない。芸を競い合う相手だから、俺を慕うような(俺に助けを求めるような)姿は見たくない」と言い、頑なに拒絶する。その気持ちがお妻にも通じたか、弟子に看取られながら、静かに息を引き取った。その亡骸の前で、雲右衛門は威儀を正し、極め付きを披露する。あたかも、曲師お妻の「合いの手」を頼りにするかのように・・・。
この映画の見どころは、若き日、月形龍之介の雄姿であろうか。雲右衛門は「俺はしがない流し芸人の倅、名誉や地位などどうでもよい。傷だらけになって、ただ芸一筋に生きるのだ」と主張する。その容貌とは裏腹に、脱世間・常識破りで不健全な、カッコ悪い生き様を求めているのだ。そのことを周囲は理解できない。理解できたのは妻女のお妻ただ一人。共に立つ舞台でお妻の調子が外れた。そのことを指摘するだけで(昔のように)怒ったり殴ったりしない雲右衛門を、お妻は激しく罵倒する。その名場面こそが、見どころの極め付きであったと、私は思う。「お妻、今日は二度まで調子を外したが、オレの芸にいけねえ所があったのか」「弾いていて泣けません」「ちょっと三味線持っといで」と、穏やかに言うが、お妻はハッキリと断る「あたしはイヤだ。他の人にやらせたらいいでしょう」。雲右衛門はキッとして「お妻!」と言ったが、「何です」と軽くあしらわれて次の言葉が出なかった。「・・・・」「お前さん、この頃のあたしの三味線をどう聞いてます。自分ながら、あたしの三味線はもう峠を越したと思ってます。身体の病には勝てやしない」。雲右衛門は「オレはそれほどとは思っていなかったが・・・」と取りなすが、健気にもお妻は攻勢に出た。「その女房に小言一つ言えずに結構がって詠っているお前さんは、それでも天下の雲右衛門か、桃中軒の総元締めか。昔のことを思うと涙がこぼれらあ」。雲右衛門も「夫婦の中でも芸は仇だ、勝手なことを言うなよ」と反撃に出たが「お前さんは昔、あたしの三味線の出来が悪い日には撲ったり蹴ったりした人だよ。もとより女として可愛がられたこともない。自分の芸のためにあたしの三味線を食ったんだ。自分の芸のためなら人も師匠も忘れられる強い心を持っていたんだよ。(九州時代からの)夫婦でも芸は仇、お互いに負けまいという真剣さはどうなったんだい」「それはオレも思うよ」と認めて弱音を吐く。「人気が下がって芸が落ちるのなら、お前さんもそれだけの人だよ」「そうじゃあねえ。衰え始めたオレの芸に、かえって反対の人気が立ってくるんだ。オレはそれを思うといつも背中が寒くなる」「お前さん、いくつなんだい、それを言って済む歳かい」、お妻は、「あたしの身体はもう長くない、今のお前さんの意気地ない姿を見て、逝くところへ逝けるかい」と一睨み、最後に「お前さんは女でも女房でも自分の芸のためなら、みんな食ってきた人なんだよ、それが何だい、いまごろ女房の三味線に蹴躓いて汗なんか流して。これだけ言やあたくさんだろ・・・」と言って、背中を向けすすり泣く。雲右衛門は「お妻!」と言って立ち上がったが、後は無言、静かに頭を垂れる他はなかった。
二人の対話は、これを最後に交わされることはなかったのである。
この場面こそが、この映画の真髄であり、男の弱さと女の強さ・逞しさが見事に浮き彫りされる、成瀬監督ならではの演出ではないだろうか。それまで、夫唱婦随の景色で、しおらしく見られていた曲師・お妻が、一転、立て板に水のような啖呵がほとばしる。細川ちか子の「鉄火肌」の片鱗も垣間見られて、この場面だけで、私は大いに満足できたのである。蛇足だが、千鳥役、千葉早智子の演技も冴えていた。芸妓から雲右衛門の新造に納まり、初々しかった娘の景色に貫禄が加わる。世間の風評を意に介さず、弟子や番頭とも五分で渡り合い、お妻を見舞う素振りも見せながら、足りない責任はは雲右衛門におっかぶせるという姿勢は、成瀬監督が自家薬籠中の「女模様」に他ならない。女性映画の名手・成瀬巳喜男のモットーは、ここでも貫かれているのである。比べて、男性陣が繰り広げる様々な対立や葛藤は、所詮「小競り合い」に過ぎず、悲劇を装えば装うほど、喜劇的にならざるを得なかった。名優・藤原釜足が、電話口でお妻の訃報(臨終の様子)を聞き、「オレはこの年になって、それを聞こうとは思わなかった、早く電話を切ってくれ」と、涙ぐむ姿が、何よりもそのことを雄弁に物語っている。
国威高揚の空気が強い当時において、その片棒を担がされる雲右衛門に、思い切り無様で無力な姿をダブらせようと試みる成瀬監督の「腕は鈍っていない」のである。拍手。
(2017.6.18)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-15
付録・邦画傑作選・「出来ごころ」(監督・小津安二郎・1933年)
ユーチューブで映画「出来ごころ」(監督・小津安二郎・1933年)を観た。昭和初期、人情喜劇の傑作である。主なる登場人物は男4人、女2人。男は、東京のビール工場で働く日雇い労働者・喜八(坂本武)、その息子・冨夫(突貫小僧)、喜八の同僚・次郎(大日向伝)、近所の床屋(谷麗光)、女は、千住の製糸工場をクビになり、途方に暮れている小娘の春江(伏見信子)、春江を雇い面倒をみる一善飯屋のおたか(飯田蝶子)である。
今日も仕事を終え、喜八親子、次郎たちは小屋がけの浪曲を楽しんでいる。演目は「紺屋高尾」、演者は浪花亭松若。桟敷に蟇口が落ちている。客の一人がそっと取り上げて見ると中身は空っぽ、バカバカしいと放り投げる。他の客もその蟇口を取っては放り投げる。それが喜八の前に飛んで来た。喜八も同様に放り投げようとしたが、「待てよ、俺の蟇口よりこっちの方が豪勢だ」と思ったか、その蟇口は懐に、代わりに自分の蟇口を空にして放り投げた。その蟇口をまた手にする他の客・・・、そのうちに、一人の客が立ち上がる。蚤が飛び込んで来たか、浴衣の裾をはたいて大騒ぎ、蚤は次から次へと客の懐に飛び込んでいく。客席は全員が立ち上がり、浪曲どころではなくなったが、最後は口演中の浪花亭松若のもとに飛び込んだという次第。蟇口と蚤の連鎖が織りなす客席風景は、抱腹絶倒の名場面であった。それでも舞台は万雷の拍手で終演となり、喜八たちが小屋を出ると、行李を手にした春江がポツンと立っている。喜八は、ことのほか気になり、冨夫を負ぶいながら春江に近づこうとする、そのたびに冨夫が喜八の頭をポンと叩く姿が、可笑しい。次郎は春江には全く関心が無く、おたかの店に喜八を誘う。ほどほどに酒を飲み、帰ろうとすると、路地にまた春江が立っている。「このへんに泊まるところはないでしょうか」「お前さん、宿無しかい」。春江には家族もないとのこと、喜八はおたかに一晩の宿を頼み込んだ。おたかは、面倒なことに巻き込まれないかと危惧したが、不承不承に承知した。
翌朝、7時30分を過ぎたのに、喜八はまだ寝ている。冨夫が「ちゃん、工場に遅れるよ」と起こしたが、いっこうに起き出さない。業を煮やした冨夫は台所のスリコギ棒を持ってきて、思い切り喜八の脛に振り下ろした。思わず跳び上がる喜八、その姿に私の笑いは止まらなかった。同様の手口で冨夫は隣家の次郎も起こしに行く。家に戻ると、冨夫はかいがいしく喜八の着替えを手伝う。工場で使う軍手を手渡しながら「チャン、手袋の指は、なぜ五本なのか知ってるかい」「なぜだ」「四本だったら手袋の指が一本余っちゃうじゃないか」「なるほど、よくできてやがらあ」。喜八たちは井戸端のバケツで顔を洗い、口をすすぎ、一同の朝飯はおたかの家で・・・。そこに春江の姿が現れた。にこやかに「昨晩はいろいろと有難うございました」。おたかも「いろいろと話を聞いてみたが、当分の間、ウチで働いて貰うことにしたよ」と頬笑んだ。
かくて、春江の身の振り方は一件落着となったが、喜八の方がおさまらない。いい年をして、寝ても覚めても春江のことが忘れられない。仕事はさぼる、酒は飲む。しかし、春江はどうやら次郎の方に惹かれているらしい。おたかが寿司折りと酒瓶を持って、喜八の部屋を訪れた。「春江と次郎さんの間をとりもってくれないか。お前さんなら、何とかできそうだ」。喜八も、一度は落胆したが、よく考えれば「なるほど、それもそうだ。オレは年を取り過ぎた、一肌脱いでやろう」と納得、次郎に話をつけようとする。だが次郎は断固拒否、やるせない「恋の痛手」を抱えて、喜八の酒量は増える一方、冨夫は級友からも「お前の親父はバカだってよ、字も読めないのに、工場も休んで飲み歩いている」と罵倒される始末、冨夫は泣いて家に戻るが、誰もいない。縁側にあった盆栽の銀杏をちぎっては食い、ちぎっては食ううちに寝入ってしまった。夜遅く帰ってきた喜八、丸裸になった盆栽を見て「誰がやったんだ」「俺がやったんだよ、正直に言ったんだ、ジョージ・ワシントンだって・・・」「俺の知らない話で誤魔化すな」「チャンのバカ!新聞も読めないくせに」「新聞はまとめて屑屋に売るもんだ」「工場にも行かずに毎日酒ばかり飲んで」と言うなり、冨夫は辺りの新聞紙を喜八に投げつける。そこから父子の壮絶なバトルが始まった。冨夫を十数回、平手打ちする喜八、殴られるたびに喜八をにらみ返す冨夫、躊躇した喜八に今度は冨夫が泣きながら数十回の平手打ち、とどのつまり喜八は殴られっぱなし、全く無抵抗のままこのバトルは終わった。冨夫の言い分の方がはるかに筋が通っていたからである。セリフは喜劇、所作は悲劇というトラジ・コミックの名場面であった。
喜八は心底から冨夫に「すまねえ、親らしいことは一つもやってやれねえで」と思ったに違いない。次の日の朝、50銭という大金を冨夫に与えた。「これで好きなものでも買え」。久しぶりに工場に出勤した喜八に緊急の連絡が入った。「お前の子どもが病気になった、すぐに帰れ」、「俺のガキが病気になるはずはない」と訝ったが、帰ってみると、たしかに寝かされて唸っている。「どうしたんだ」と訊ねると「50銭で駄菓子を全部食べた」とのこと、冨夫は急性腸カタルであえなく入院の身となった。しかし、「宵越しの銭は持たない」喜八には、家財道具を売り払っても、入院費が払えない。見かねた春江が「私が何とかします」。今度は次郎が黙っていなかった。「オレが何とかする!お前が大金を稼ぐとすれば、その方法は知れている。若い身空で自分をダメにしてはいけない」、そのとき、初めて次郎に恋心が生まれたか、次郎は床屋から借金、自分は北海道へ出稼ぎに行く覚悟を決めた。「と、いった人々の温かい人情で」冨夫の病状は快復、退院の運びとなった。夜、喜八と冨夫が減らず口を叩きながらくつろいでいると、床屋が飛び込んで来た。「次郎公のやつ、北海道に行くんだってよ」「どうして?」「オレが金を用立てたからだよ」、そうか、次郎の奴、俺たちのために北海道行きを決めたのか、あわてて次郎の部屋に行くと、きれいに片付いて、もぬけの殻。外を探すと、路地で語り合う次郎と春江の姿があった。「一生の別れってんでもなし、そうめそめそ泣くなよ」「せっかく分かって頂いたのにすぐにお別れなんて・・・、私には一生、幸せなんてこない気がするの」「心細いことをいうない。ちょっとの間の辛抱だ。必ずお前の所に帰ってくる」と次郎が出発しようとすると、喜八が「待て」と止めに入る。「北海道はオレが行く」「富坊をどうするんだ」「子どもなんて、親が無くても育つもんだ、お前を頼りにしている人がいるじゃないか」、二人の押し問答が続いたが、最後は喜八の鉄拳一発、次郎はその場に昏倒した。かくて、喜八は準備を整え、おたかの店に行く。そこには冨夫、床屋も居た。「オレが行くことにした。ガキはよろしく頼むぜ」と言えば、床屋は「オレにとっては大切な金だが、人の子一人助けたと思えば、諦めもつく。お前の気持ちだけうれしいんだ」。おたかも「借金ぐらい、どこだって返せるじゃないか」と、思いとどまらせようとするのだが「長生きはしてえもんだよ。オレはこんないい気持ちのこと、生まれて初めてだ」。冨夫が「チャン、今度いつ帰ってくるんだい」と問うのに「馬鹿野郎!くだらねえことを聞いて手間取らせるない」「オレは酔狂で行くんだ。放っといてくれ」という言葉を残して行ってしまった。喜八の心中には、(おたかから頼まれた)次郎と春江の「取り持ち」を、今、実現できるのだ、という固い思いがあったからに違いない。
大詰めは、北海道に向かう船の中、集められた人夫連中で酒盛りが始まっている。喜八は息子の自慢話を披露する。「お前たち、手袋の指はなぜ五本あるか知ってるかい」。人夫の一人(笠智衆)が首をかしげると、すかさず寝台にいた他の人夫が応じた。「四本だったら手袋に指が一本あまっちゃうからだよ」。そのとたんに、喜八は冨夫のことを思い出す。船はまだ出たばかり、懐にしまった冨夫の習字を取り出して「千代吉 福太郎」という墨書を見るにつけ、「いけねえ、いけねえ」と気が変わった。「おい、この船、停まらねえか」一同は大笑い、しかし喜八は大まじめ、対岸を指さして「あそこは、東京と陸続きか」「あたりめえよ」「そんなら、オレは一足お先に帰らせてもらうよ」と言うなり、一同が止めるのも聞かずに、ザンブと海に飛び込んだ。海中にポツンと喜八が一人、プカプカ漂いながら、先日、冨夫に教えられた問答を呟く。「海の水はなぜしょっ辛い」「鮭がいるからさ」。思わず笑いがこぼれ、悠々と抜き手で岸に泳ぎ着くと同時に、この映画は「終」となった。
サイレント映画だが、人々の話し声、周囲の物音がハッキリと聞こえてくるような名作であった。見どころは満載、坂本武と突貫小僧の絶妙の絡みをベースに、大日向伝の「いい男振り」、飯田蝶子、谷麗光の「温もり」(人情)、伏見信子の「可憐」な風情、背景には浪曲「紺屋高尾」(篠田實)の色模様も添えられて、寸分の隙も無い作品に仕上がっていたと思う。(タイトルの)「出来ごころ」とは「計画的でなく、その場で急に起こった(よくない)考え」のことだが、人は皆、その場の感情に左右されて生きて行く。登場人物の誰が、どんなところで、どんな感情に左右され、どのように振る舞ったかを見極める、「人生読本」としても有効な教材ではないだろうか、と私は思った。(2017.5.22)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

今日も仕事を終え、喜八親子、次郎たちは小屋がけの浪曲を楽しんでいる。演目は「紺屋高尾」、演者は浪花亭松若。桟敷に蟇口が落ちている。客の一人がそっと取り上げて見ると中身は空っぽ、バカバカしいと放り投げる。他の客もその蟇口を取っては放り投げる。それが喜八の前に飛んで来た。喜八も同様に放り投げようとしたが、「待てよ、俺の蟇口よりこっちの方が豪勢だ」と思ったか、その蟇口は懐に、代わりに自分の蟇口を空にして放り投げた。その蟇口をまた手にする他の客・・・、そのうちに、一人の客が立ち上がる。蚤が飛び込んで来たか、浴衣の裾をはたいて大騒ぎ、蚤は次から次へと客の懐に飛び込んでいく。客席は全員が立ち上がり、浪曲どころではなくなったが、最後は口演中の浪花亭松若のもとに飛び込んだという次第。蟇口と蚤の連鎖が織りなす客席風景は、抱腹絶倒の名場面であった。それでも舞台は万雷の拍手で終演となり、喜八たちが小屋を出ると、行李を手にした春江がポツンと立っている。喜八は、ことのほか気になり、冨夫を負ぶいながら春江に近づこうとする、そのたびに冨夫が喜八の頭をポンと叩く姿が、可笑しい。次郎は春江には全く関心が無く、おたかの店に喜八を誘う。ほどほどに酒を飲み、帰ろうとすると、路地にまた春江が立っている。「このへんに泊まるところはないでしょうか」「お前さん、宿無しかい」。春江には家族もないとのこと、喜八はおたかに一晩の宿を頼み込んだ。おたかは、面倒なことに巻き込まれないかと危惧したが、不承不承に承知した。
翌朝、7時30分を過ぎたのに、喜八はまだ寝ている。冨夫が「ちゃん、工場に遅れるよ」と起こしたが、いっこうに起き出さない。業を煮やした冨夫は台所のスリコギ棒を持ってきて、思い切り喜八の脛に振り下ろした。思わず跳び上がる喜八、その姿に私の笑いは止まらなかった。同様の手口で冨夫は隣家の次郎も起こしに行く。家に戻ると、冨夫はかいがいしく喜八の着替えを手伝う。工場で使う軍手を手渡しながら「チャン、手袋の指は、なぜ五本なのか知ってるかい」「なぜだ」「四本だったら手袋の指が一本余っちゃうじゃないか」「なるほど、よくできてやがらあ」。喜八たちは井戸端のバケツで顔を洗い、口をすすぎ、一同の朝飯はおたかの家で・・・。そこに春江の姿が現れた。にこやかに「昨晩はいろいろと有難うございました」。おたかも「いろいろと話を聞いてみたが、当分の間、ウチで働いて貰うことにしたよ」と頬笑んだ。
かくて、春江の身の振り方は一件落着となったが、喜八の方がおさまらない。いい年をして、寝ても覚めても春江のことが忘れられない。仕事はさぼる、酒は飲む。しかし、春江はどうやら次郎の方に惹かれているらしい。おたかが寿司折りと酒瓶を持って、喜八の部屋を訪れた。「春江と次郎さんの間をとりもってくれないか。お前さんなら、何とかできそうだ」。喜八も、一度は落胆したが、よく考えれば「なるほど、それもそうだ。オレは年を取り過ぎた、一肌脱いでやろう」と納得、次郎に話をつけようとする。だが次郎は断固拒否、やるせない「恋の痛手」を抱えて、喜八の酒量は増える一方、冨夫は級友からも「お前の親父はバカだってよ、字も読めないのに、工場も休んで飲み歩いている」と罵倒される始末、冨夫は泣いて家に戻るが、誰もいない。縁側にあった盆栽の銀杏をちぎっては食い、ちぎっては食ううちに寝入ってしまった。夜遅く帰ってきた喜八、丸裸になった盆栽を見て「誰がやったんだ」「俺がやったんだよ、正直に言ったんだ、ジョージ・ワシントンだって・・・」「俺の知らない話で誤魔化すな」「チャンのバカ!新聞も読めないくせに」「新聞はまとめて屑屋に売るもんだ」「工場にも行かずに毎日酒ばかり飲んで」と言うなり、冨夫は辺りの新聞紙を喜八に投げつける。そこから父子の壮絶なバトルが始まった。冨夫を十数回、平手打ちする喜八、殴られるたびに喜八をにらみ返す冨夫、躊躇した喜八に今度は冨夫が泣きながら数十回の平手打ち、とどのつまり喜八は殴られっぱなし、全く無抵抗のままこのバトルは終わった。冨夫の言い分の方がはるかに筋が通っていたからである。セリフは喜劇、所作は悲劇というトラジ・コミックの名場面であった。
喜八は心底から冨夫に「すまねえ、親らしいことは一つもやってやれねえで」と思ったに違いない。次の日の朝、50銭という大金を冨夫に与えた。「これで好きなものでも買え」。久しぶりに工場に出勤した喜八に緊急の連絡が入った。「お前の子どもが病気になった、すぐに帰れ」、「俺のガキが病気になるはずはない」と訝ったが、帰ってみると、たしかに寝かされて唸っている。「どうしたんだ」と訊ねると「50銭で駄菓子を全部食べた」とのこと、冨夫は急性腸カタルであえなく入院の身となった。しかし、「宵越しの銭は持たない」喜八には、家財道具を売り払っても、入院費が払えない。見かねた春江が「私が何とかします」。今度は次郎が黙っていなかった。「オレが何とかする!お前が大金を稼ぐとすれば、その方法は知れている。若い身空で自分をダメにしてはいけない」、そのとき、初めて次郎に恋心が生まれたか、次郎は床屋から借金、自分は北海道へ出稼ぎに行く覚悟を決めた。「と、いった人々の温かい人情で」冨夫の病状は快復、退院の運びとなった。夜、喜八と冨夫が減らず口を叩きながらくつろいでいると、床屋が飛び込んで来た。「次郎公のやつ、北海道に行くんだってよ」「どうして?」「オレが金を用立てたからだよ」、そうか、次郎の奴、俺たちのために北海道行きを決めたのか、あわてて次郎の部屋に行くと、きれいに片付いて、もぬけの殻。外を探すと、路地で語り合う次郎と春江の姿があった。「一生の別れってんでもなし、そうめそめそ泣くなよ」「せっかく分かって頂いたのにすぐにお別れなんて・・・、私には一生、幸せなんてこない気がするの」「心細いことをいうない。ちょっとの間の辛抱だ。必ずお前の所に帰ってくる」と次郎が出発しようとすると、喜八が「待て」と止めに入る。「北海道はオレが行く」「富坊をどうするんだ」「子どもなんて、親が無くても育つもんだ、お前を頼りにしている人がいるじゃないか」、二人の押し問答が続いたが、最後は喜八の鉄拳一発、次郎はその場に昏倒した。かくて、喜八は準備を整え、おたかの店に行く。そこには冨夫、床屋も居た。「オレが行くことにした。ガキはよろしく頼むぜ」と言えば、床屋は「オレにとっては大切な金だが、人の子一人助けたと思えば、諦めもつく。お前の気持ちだけうれしいんだ」。おたかも「借金ぐらい、どこだって返せるじゃないか」と、思いとどまらせようとするのだが「長生きはしてえもんだよ。オレはこんないい気持ちのこと、生まれて初めてだ」。冨夫が「チャン、今度いつ帰ってくるんだい」と問うのに「馬鹿野郎!くだらねえことを聞いて手間取らせるない」「オレは酔狂で行くんだ。放っといてくれ」という言葉を残して行ってしまった。喜八の心中には、(おたかから頼まれた)次郎と春江の「取り持ち」を、今、実現できるのだ、という固い思いがあったからに違いない。
大詰めは、北海道に向かう船の中、集められた人夫連中で酒盛りが始まっている。喜八は息子の自慢話を披露する。「お前たち、手袋の指はなぜ五本あるか知ってるかい」。人夫の一人(笠智衆)が首をかしげると、すかさず寝台にいた他の人夫が応じた。「四本だったら手袋に指が一本あまっちゃうからだよ」。そのとたんに、喜八は冨夫のことを思い出す。船はまだ出たばかり、懐にしまった冨夫の習字を取り出して「千代吉 福太郎」という墨書を見るにつけ、「いけねえ、いけねえ」と気が変わった。「おい、この船、停まらねえか」一同は大笑い、しかし喜八は大まじめ、対岸を指さして「あそこは、東京と陸続きか」「あたりめえよ」「そんなら、オレは一足お先に帰らせてもらうよ」と言うなり、一同が止めるのも聞かずに、ザンブと海に飛び込んだ。海中にポツンと喜八が一人、プカプカ漂いながら、先日、冨夫に教えられた問答を呟く。「海の水はなぜしょっ辛い」「鮭がいるからさ」。思わず笑いがこぼれ、悠々と抜き手で岸に泳ぎ着くと同時に、この映画は「終」となった。
サイレント映画だが、人々の話し声、周囲の物音がハッキリと聞こえてくるような名作であった。見どころは満載、坂本武と突貫小僧の絶妙の絡みをベースに、大日向伝の「いい男振り」、飯田蝶子、谷麗光の「温もり」(人情)、伏見信子の「可憐」な風情、背景には浪曲「紺屋高尾」(篠田實)の色模様も添えられて、寸分の隙も無い作品に仕上がっていたと思う。(タイトルの)「出来ごころ」とは「計画的でなく、その場で急に起こった(よくない)考え」のことだが、人は皆、その場の感情に左右されて生きて行く。登場人物の誰が、どんなところで、どんな感情に左右され、どのように振る舞ったかを見極める、「人生読本」としても有効な教材ではないだろうか、と私は思った。(2017.5.22)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-14
付録・邦画傑作選・「三百六十五夜」(監督・市川崑・1948年)
ユーチューブで映画「三百六十五夜」(監督・市川崑・1948年)を観た。原作は小島政二郎の恋愛通俗小説(メロドラマ)である。登場人物は、川北小六(上原謙)、大江照子(山根寿子)、その母(吉川満子)、その父(河村黎吉)、小牧蘭子(高峰秀子)、津川厚(堀雄二)、姉小路三郎(田中春男)、大江家の女中・お咲(一宮あつ子)、おでん屋のおかみ(清川玉枝)、宮田龍之助(大日向伝)、キャバレーの歌手(二葉あき子)といった面々である。この映画が封切られたとき、私は4歳だったので、もしユーチューブがなければ絶対に観ることはできなかった作品だが、主題歌「三百六十五夜」(詞・西条八十、曲・古賀政男、唄・霧島昇、松原操)の方はよく知っていたので、映画の内容はどのようなものか、興味津々であった。筋書きは単純だが冗長、①小六と蘭子は親同士(小牧家は大阪で発展を重ねる事業家、川北家は没落気味の建築業)が決めた許嫁、しかし小六は蘭子の言動が気に入らず、東京へ転出するが蘭子は小六を追いかける。②小六は下宿を変えて大江家の貸間に移る。そこに居たのが戦争未亡人の照子、転居後まもなく大江家に泥棒が闖入、小六が退治する。照子と小六は相愛の仲となる。③小六の父が上京、150万円の借金で会社は倒産寸前、蘭子と早く結婚し、小牧家の援助が得られるようにしてほしいと言う。しかし小六は断固拒否。その様子を窺っていた照子は、小六の恋敵・津川から150万円借り入れる。津川は小牧家の使用人として東京の事業を拡大している。蘭子に恋しているが相手にされず、照子を狙っているようだ。④ある日、照子の母とは絶縁状態の父が金の無心に訪れる。断られたが、引き出しに入れてあった150万円の小切手を見つけ、盗み去る。⑤父はその小切手を持って、津川が経営するキャバレーに繰り込んだが、津川配下でマネキン業の姉小路に奪い取られる。⑥照子は小六のために150万円を稼ごうとして姉小路の事務所を訪れた。洋装モデルの写真を撮れば1回2千円払うと持ちかけられ、エロ写真を撮られてしまう。⑦その写真を目にした小六は、絶望してノイローゼに、それを看護する蘭子、なぜかそこに訊ねてくる照子、といった場面がいつ終わるともなく延々と続くのだが・・・。要するに、小六と照子は相思相愛、最後に結ばれる。津川は蘭子にも、照子にも振られる。そして殺される。蘭子はただひとすじに小六を慕い続けるが思いは届かず、最後は警察に捕まる。という筋書きからみれば、この悲劇の主人公は男は津川、女は蘭子ということになる。事実、蘭子を演じた高峰秀子の艶姿は素晴らしく存在感があった。勝ち気でおきゃん、典型的な日本女性・山根寿子とのコントラストも鮮やかに、その洋装スタイルを見るだけで戦後の息吹きが伝わってくる。恋しい男を追い続け、「思い叶わぬ恋」の余韻をいつまでも、どこまでも漂わせていた。そしてまた、小六の仇役・堀雄二の阿漕振りも見事であった。貧しかった子ども時代を振り返り「金がすべて」だと確信している。彼が初めからワルだったとは思えない。最後に小六の父に刺され倒れ込み、喘ぎながら吐いた「何でもないんだから、みんな騒がないでくれ。一人の人間が血にまみれて生まれてくるように、血にまみれて死ぬだけだ。照子さんは純潔だ、それだけが俺の救いだ」というセリフがそれを暗示している。
比べて、小六役・上原謙と照子役・山根寿子の相思相愛模様は、やや単調で生硬、主題歌「三百六十五夜」の歌声(霧島昇と松原操)には及ばなかったように感じる。(監督の市川崑と高峰秀子が昵懇の間柄だったとすれば、やむを得ないか・・・。)
見どころは他にも、照子の父・河村黎吉の落ちぶれたヤクザ振り、女中を演じた一宮あつ子のコミカルな表情、おでん屋・清川玉枝の人情味、画家を演じた戦前の二枚目スター・大日向伝の貫禄などなど満載であった。極め付きは、キャバレーで歌う二葉あき子の舞台姿、「恋の曼珠沙華」、そして「別れのルンバ」の名曲が、往時の魅力そのまま残されている。その歌声を十分に堪能できたことは望外の幸せであった。(2017.4.24)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

比べて、小六役・上原謙と照子役・山根寿子の相思相愛模様は、やや単調で生硬、主題歌「三百六十五夜」の歌声(霧島昇と松原操)には及ばなかったように感じる。(監督の市川崑と高峰秀子が昵懇の間柄だったとすれば、やむを得ないか・・・。)
見どころは他にも、照子の父・河村黎吉の落ちぶれたヤクザ振り、女中を演じた一宮あつ子のコミカルな表情、おでん屋・清川玉枝の人情味、画家を演じた戦前の二枚目スター・大日向伝の貫禄などなど満載であった。極め付きは、キャバレーで歌う二葉あき子の舞台姿、「恋の曼珠沙華」、そして「別れのルンバ」の名曲が、往時の魅力そのまま残されている。その歌声を十分に堪能できたことは望外の幸せであった。(2017.4.24)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-13
付録・邦画傑作選・「女優と詩人」(監督・成瀬巳喜男・1935年)
ユーチューブで映画「女優と詩人」(監督・成瀬巳喜男・1935年)を観た。戦前(昭和初期)日本の夫婦コメディの佳作である。主なる登場人物は演劇界のスター女優・二ツ木千絵子(千葉早智子)とその夫で童謡詩人の二ツ木月風(宇留木浩)を中心に、隣家の保険勧誘員・花島金太郎(三遊亭金馬)、その妻・お浜(戸田春子)、小説家志望の能勢梅堂(藤原釜足)といった面々、タイトルに主題歌ならぬ「主題落語・三遊亭金馬」とあるのが、何とも異色で興味深かった。
千絵子は夫を「ゲップー」と呼び捨てにし、掃除、洗濯、炊事、買い物を一切、月風にやらせている。それというのも、千絵子は人気女優として稼ぎまくり、月風の収入はほとんどゼロに近い。2階建ての借家の家賃、生活費のすべてを千絵子が賄っているとすれば、一家の主人とは名ばかりで、頭が上がらない。隣家のお浜やクリーニング屋から「大変ですねえ」と言われても「軍隊に入ったと思えばどうってことありません」と頓着しない月風の様子がどこか飄々として清々しかった。今日も2回では千絵子が芝居仲間(三島雅夫、宮野照子たち)と稽古に余念がない。一息つくと千絵子は「ゲップー」と呼び、「チェリー、バット、ホープ、それにみかんとお芋を買ってきて頂戴!」と命令する。タバコ屋に赴いた月風は友だちの下宿人・能勢梅堂に遭遇する。彼は部屋代を半年も溜め、おかみさん(新田洋子)に合わす顔がない。やむなく2階から屋根伝いに脱出を図る始末であった「借金で首が回らないというが、自分の場合は、借金で階段が降りられない」と笑い飛ばす、藤原釜足の風情が絵になっていた。貧乏を苦にもせず「会社は辞めて、大衆小説のコンクールに応募する。賞金は5000円だぞ」と言いながら、月風が買ったタバコを一本ちゃっかり頂戴する。しかし、その様子をおかみさんに見つかり、どこかに遁走してしまった。月風が家に戻ろうとすると、おはまが「お向かいの家に若夫婦が引っ越してきましたよ、今晩はお蕎麦が食べられますね」などという。様子を見ると家財道具はゼロ、掃除もできない。月風は我が家から箒、バケツ、雑巾を貸し出したが、買い物から帰らずに油を売っている月風を千絵子は「ゲップー」と呼び戻し、「何、おせっかいなことしてるのよ、これから出かけますよ」と仲間と外出してしまった。夜、ひとりで干物を焼いていると、隣家のおはまが誘いに来た。「家の主人が一人で飲んでもつまらない。となりの御主人を呼んでこいと言うんです。その干物を持っておいでなさい。あら、いい物があるじゃないですか」と言い、戸棚の缶詰まで持ち出す。三人で酒盛りが始まると、おはまが金太郎に曰く「お向かいの若夫婦、保険に入れなさいよ」。途中で座を外し金太郎は向かいの家に・・・、まもなく商談は成立、金太郎は欣然と戻って来た。「めでたい、お祝いで今夜は、とことん飲みましょう」。月風は童謡のレコードを取ってきて、金太郎が踊り出す。
《もしもしお山のタヌキさん あなたの得意な腹鼓 ポンポロ鳴らしてくださいな》という歌声に合わせて、三遊亭金馬が踊る景色は絶品であった。ビールを1ダース空けた頃、月風は(金太郎も)泥酔状態、家に帰ってからも千絵子のプロマイドに日頃の鬱憤を当たり散らす、帰宅した千絵子は呆れて、月風へ蒲団を放り出しそのまま寝てしまった。
翌朝、千絵子はまだ寝ている。いつものように月風は朝食の準備にとりかかる。隣のおはまがダイコンの煮付けを持ってやって来た。まもなく始まる千絵子の公演チケットを貰いたかったが、「それは大家さんにあげてしまいました」と月風が言うと、当てが外れ、ダイコンの容器を早々に取り戻して帰ってしまった。やがて「ゲップー」という千絵子の声、「私たちケンカをしたことがないのでどうしても感じが出ない、本読みを手伝って」と言う。月風は鍋をコンロにかけたまま相手役の本読みに・・・。その内容は夫が妻に無断で友だちを居候にしてしまう場面、「どうせ空いている2階だから貸してやってもいいではないか」「いやなことだわ。貸すというのはお金を取って住まわすことを言うんだわ」「だってかわいそうじゃないか。あの男だって金が無くて困っているからこそ頼みに来ているんじゃないか」「あんたの友だちときたら一人だってろくな人はいやしない。みんな風車のピーピーといった人たちばかりじゃないの」「困っている時は相身互いだ。居候の一人ぐらいおいてやると言ったって、それがどうしたんだ」「大きなことを言うもんじゃないわ。毎月ここの家賃は誰が払っていると思うの」といった口喧嘩が次第にエスカレート、やかんの蓋、枕など辺りの物を投げ合い、終いには打擲の音まで聞こえた時、ひょっこり梅堂が来訪した。ただならぬ状況に梅堂は驚き止めに入る。「まあ、二人とも冷静に、落ち着きなさい。奥さんケガはありませんか」。しかし、芝居の稽古だと分かり大笑いしたのだが、台所から焦げ臭い匂いが漂ってきた。コンロにかけていた飯は黒焦げ、千絵子は「梅堂さんと丼でも取って食べなさい」と言い2階へ、芝居の稽古を続けるらしい。梅堂が訪ねてきたのは、引っ越しの相談、とうとう下宿を追い出されるという。「君の家の2階を貸してくれないか。原稿料が入ったら払う。別に千絵子さんに相談しなくたっていいだろう?君はこの家の主人なんだから」。月風は「えっ!」と戸惑ったが《主人》という言葉を聞くと、そうだ!と思ったか、承諾してしまった。梅堂はすぐさま「それでは荷物を取ってくる」と出て行く。そこに降りてきたのは千絵子、梅堂の要件を聞いて、怒り出した。さっき稽古をした芝居のセリフそのままに、今度は本当の夫婦喧嘩が始まる。千絵子に「ここの家賃は誰が払っていると思うの、みんなあたしよ!男なら男らしく稼いで居候の100人でも200人でも養ってみなさいよ。あんたの原稿なんて屑屋に売った方がよっぽどお金になるわよ」などと毒づかれて、月風は「何だと!」と激高、千絵子を張り飛ばした。「痛い!」・・・、その場面に梅堂が荷物を抱えて戻って来た。「やってるね」などと笑いながらその様子を見物する。物音に気づいた隣家のおはまがやって来ると「奥さん、なかなか面白い芝居ですよ。ここで見物しましょう」。しかし、その芝居は芝居にあらず、梅堂が居候を決め込んだことが原因だったことが判明する。その時、向かいの家の気配が慌ただしい。金太郎が駆け込んできた。「おはま、大変だ。昨日の夫婦、心中したらしい」「まあ!生命保険はどうするの、心中しそうかどうか見ればわかりそうなもの、本当に呆れたよ」と怒り出し、家に戻っていったかと思うと、たちまち夫婦喧嘩が始まった。玄関先には箒が飛んでくる。蒲団が飛んでくる。
月風は梅堂に言う。「友だちとして言いにくいことだが、君の居候の申し出は、主人としてハッキリ断るよ。家賃はみんな千絵子が払っているんだ」「家賃を払うのが誰だろうが、主人の君から断られれば致し方ない。申し出は潔く撤回するよ。奥さん、あなたの芝居の居候は結局どうなるんですか」「懸賞金が3000円、転がり込んでくるんです」「そうですか、ボクの方は5000円だけど、どうなるかはわからない」。一方、金太郎とおはまの喧嘩も山場を迎えている。掴み合いながら「あんた、あの二人が死んだらどうするの」「死んだら冷たくなって息しないだけだ」「まぬけだね」「オレがしたんじゃないよ、だいたいお前は生意気だよ、オレは夫だぞ」「夫が聞いて呆れるよ、オットセイみたいな顔しやがって」、それを見ていた梅堂が「女なんてあれだからいやなんだ、ボクは独身を通すぞ」月風と千絵子は、いつのまにか仲直りしている。「痛くなかったかい」「あなた、本当にゴメンなさいね」荷物を抱えて出て行こうとする梅堂を千絵子が呼び止めた。「あたしたちの喧嘩の原因になってくれてありがとう。おかげで明日の芝居のいい工夫がついたんです。それからあなたは、初めて二ツ木月風をこの家の主人として認めてくれた方です。どうか汚い家ですけどウチにいらしてください」。
かくて、この映画はメルヘンチックな大団円を迎えることになる。心中した若い二人も命はとりとめた模様、金太郎夫妻にも平穏が訪れて「終」となった。
主人公が童謡詩人とあって、映像の背景には童謡のメロディーが多用されている。「雀の学校」「靴が鳴る」「夕焼け小焼け」「浜辺の歌」「埴生の宿」などが、それぞれの場面の雰囲気を、鮮やかに醸し出していた。まさに「大人の童話」、しかし、金太郎とおはまの喧嘩を見て、梅堂が「とかく女は養いがたし、七人の子を生しても女に気を許すな、女心は秋の空」と嘆じる景色は、男にとっては切実、「女の逞しさ」が一際目立つ、成瀬巳喜男ならではの傑作であったと、私は思う。
(2017.5.8)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

千絵子は夫を「ゲップー」と呼び捨てにし、掃除、洗濯、炊事、買い物を一切、月風にやらせている。それというのも、千絵子は人気女優として稼ぎまくり、月風の収入はほとんどゼロに近い。2階建ての借家の家賃、生活費のすべてを千絵子が賄っているとすれば、一家の主人とは名ばかりで、頭が上がらない。隣家のお浜やクリーニング屋から「大変ですねえ」と言われても「軍隊に入ったと思えばどうってことありません」と頓着しない月風の様子がどこか飄々として清々しかった。今日も2回では千絵子が芝居仲間(三島雅夫、宮野照子たち)と稽古に余念がない。一息つくと千絵子は「ゲップー」と呼び、「チェリー、バット、ホープ、それにみかんとお芋を買ってきて頂戴!」と命令する。タバコ屋に赴いた月風は友だちの下宿人・能勢梅堂に遭遇する。彼は部屋代を半年も溜め、おかみさん(新田洋子)に合わす顔がない。やむなく2階から屋根伝いに脱出を図る始末であった「借金で首が回らないというが、自分の場合は、借金で階段が降りられない」と笑い飛ばす、藤原釜足の風情が絵になっていた。貧乏を苦にもせず「会社は辞めて、大衆小説のコンクールに応募する。賞金は5000円だぞ」と言いながら、月風が買ったタバコを一本ちゃっかり頂戴する。しかし、その様子をおかみさんに見つかり、どこかに遁走してしまった。月風が家に戻ろうとすると、おはまが「お向かいの家に若夫婦が引っ越してきましたよ、今晩はお蕎麦が食べられますね」などという。様子を見ると家財道具はゼロ、掃除もできない。月風は我が家から箒、バケツ、雑巾を貸し出したが、買い物から帰らずに油を売っている月風を千絵子は「ゲップー」と呼び戻し、「何、おせっかいなことしてるのよ、これから出かけますよ」と仲間と外出してしまった。夜、ひとりで干物を焼いていると、隣家のおはまが誘いに来た。「家の主人が一人で飲んでもつまらない。となりの御主人を呼んでこいと言うんです。その干物を持っておいでなさい。あら、いい物があるじゃないですか」と言い、戸棚の缶詰まで持ち出す。三人で酒盛りが始まると、おはまが金太郎に曰く「お向かいの若夫婦、保険に入れなさいよ」。途中で座を外し金太郎は向かいの家に・・・、まもなく商談は成立、金太郎は欣然と戻って来た。「めでたい、お祝いで今夜は、とことん飲みましょう」。月風は童謡のレコードを取ってきて、金太郎が踊り出す。
《もしもしお山のタヌキさん あなたの得意な腹鼓 ポンポロ鳴らしてくださいな》という歌声に合わせて、三遊亭金馬が踊る景色は絶品であった。ビールを1ダース空けた頃、月風は(金太郎も)泥酔状態、家に帰ってからも千絵子のプロマイドに日頃の鬱憤を当たり散らす、帰宅した千絵子は呆れて、月風へ蒲団を放り出しそのまま寝てしまった。
翌朝、千絵子はまだ寝ている。いつものように月風は朝食の準備にとりかかる。隣のおはまがダイコンの煮付けを持ってやって来た。まもなく始まる千絵子の公演チケットを貰いたかったが、「それは大家さんにあげてしまいました」と月風が言うと、当てが外れ、ダイコンの容器を早々に取り戻して帰ってしまった。やがて「ゲップー」という千絵子の声、「私たちケンカをしたことがないのでどうしても感じが出ない、本読みを手伝って」と言う。月風は鍋をコンロにかけたまま相手役の本読みに・・・。その内容は夫が妻に無断で友だちを居候にしてしまう場面、「どうせ空いている2階だから貸してやってもいいではないか」「いやなことだわ。貸すというのはお金を取って住まわすことを言うんだわ」「だってかわいそうじゃないか。あの男だって金が無くて困っているからこそ頼みに来ているんじゃないか」「あんたの友だちときたら一人だってろくな人はいやしない。みんな風車のピーピーといった人たちばかりじゃないの」「困っている時は相身互いだ。居候の一人ぐらいおいてやると言ったって、それがどうしたんだ」「大きなことを言うもんじゃないわ。毎月ここの家賃は誰が払っていると思うの」といった口喧嘩が次第にエスカレート、やかんの蓋、枕など辺りの物を投げ合い、終いには打擲の音まで聞こえた時、ひょっこり梅堂が来訪した。ただならぬ状況に梅堂は驚き止めに入る。「まあ、二人とも冷静に、落ち着きなさい。奥さんケガはありませんか」。しかし、芝居の稽古だと分かり大笑いしたのだが、台所から焦げ臭い匂いが漂ってきた。コンロにかけていた飯は黒焦げ、千絵子は「梅堂さんと丼でも取って食べなさい」と言い2階へ、芝居の稽古を続けるらしい。梅堂が訪ねてきたのは、引っ越しの相談、とうとう下宿を追い出されるという。「君の家の2階を貸してくれないか。原稿料が入ったら払う。別に千絵子さんに相談しなくたっていいだろう?君はこの家の主人なんだから」。月風は「えっ!」と戸惑ったが《主人》という言葉を聞くと、そうだ!と思ったか、承諾してしまった。梅堂はすぐさま「それでは荷物を取ってくる」と出て行く。そこに降りてきたのは千絵子、梅堂の要件を聞いて、怒り出した。さっき稽古をした芝居のセリフそのままに、今度は本当の夫婦喧嘩が始まる。千絵子に「ここの家賃は誰が払っていると思うの、みんなあたしよ!男なら男らしく稼いで居候の100人でも200人でも養ってみなさいよ。あんたの原稿なんて屑屋に売った方がよっぽどお金になるわよ」などと毒づかれて、月風は「何だと!」と激高、千絵子を張り飛ばした。「痛い!」・・・、その場面に梅堂が荷物を抱えて戻って来た。「やってるね」などと笑いながらその様子を見物する。物音に気づいた隣家のおはまがやって来ると「奥さん、なかなか面白い芝居ですよ。ここで見物しましょう」。しかし、その芝居は芝居にあらず、梅堂が居候を決め込んだことが原因だったことが判明する。その時、向かいの家の気配が慌ただしい。金太郎が駆け込んできた。「おはま、大変だ。昨日の夫婦、心中したらしい」「まあ!生命保険はどうするの、心中しそうかどうか見ればわかりそうなもの、本当に呆れたよ」と怒り出し、家に戻っていったかと思うと、たちまち夫婦喧嘩が始まった。玄関先には箒が飛んでくる。蒲団が飛んでくる。
月風は梅堂に言う。「友だちとして言いにくいことだが、君の居候の申し出は、主人としてハッキリ断るよ。家賃はみんな千絵子が払っているんだ」「家賃を払うのが誰だろうが、主人の君から断られれば致し方ない。申し出は潔く撤回するよ。奥さん、あなたの芝居の居候は結局どうなるんですか」「懸賞金が3000円、転がり込んでくるんです」「そうですか、ボクの方は5000円だけど、どうなるかはわからない」。一方、金太郎とおはまの喧嘩も山場を迎えている。掴み合いながら「あんた、あの二人が死んだらどうするの」「死んだら冷たくなって息しないだけだ」「まぬけだね」「オレがしたんじゃないよ、だいたいお前は生意気だよ、オレは夫だぞ」「夫が聞いて呆れるよ、オットセイみたいな顔しやがって」、それを見ていた梅堂が「女なんてあれだからいやなんだ、ボクは独身を通すぞ」月風と千絵子は、いつのまにか仲直りしている。「痛くなかったかい」「あなた、本当にゴメンなさいね」荷物を抱えて出て行こうとする梅堂を千絵子が呼び止めた。「あたしたちの喧嘩の原因になってくれてありがとう。おかげで明日の芝居のいい工夫がついたんです。それからあなたは、初めて二ツ木月風をこの家の主人として認めてくれた方です。どうか汚い家ですけどウチにいらしてください」。
かくて、この映画はメルヘンチックな大団円を迎えることになる。心中した若い二人も命はとりとめた模様、金太郎夫妻にも平穏が訪れて「終」となった。
主人公が童謡詩人とあって、映像の背景には童謡のメロディーが多用されている。「雀の学校」「靴が鳴る」「夕焼け小焼け」「浜辺の歌」「埴生の宿」などが、それぞれの場面の雰囲気を、鮮やかに醸し出していた。まさに「大人の童話」、しかし、金太郎とおはまの喧嘩を見て、梅堂が「とかく女は養いがたし、七人の子を生しても女に気を許すな、女心は秋の空」と嘆じる景色は、男にとっては切実、「女の逞しさ」が一際目立つ、成瀬巳喜男ならではの傑作であったと、私は思う。
(2017.5.8)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-12
付録・邦画傑作選・「兄いもうと」(監督・木村荘十二・1936年)
ユーチューブで映画「兄いもうと」(監督・木村荘十二・1936年)を観た。多摩川の川師・赤座一家の物語である。川師とは、洪水を防ぐために川の流れを堰き止めたり、川底に石を敷いて流水の勢いを弱めたり、用水路を整えたり、といった河川管理を生業とする。父の赤座(小杉義男)は数十人の人足を束ねる現場監督だ。気性は荒く、「褌が乾いている」人足や、楽をしようと蛇籠に軽い石を選んでいる人足を見ると、容赦なく打擲する。一方、母のりき(英百合子)は、温和で優しく、人足たちからは「いい、おかみさんだ」「まったくだ、嬶仏よ」と慕われている。この夫婦に三人の子どもがいた。
兄・伊之(丸山定夫)、長妹・もん(竹久千恵子)、末妹・さん(堀越節子)である。伊之は腕のいい石材職人だが、仕事も気ままで、遊び好き、ある晩など馴染みの女を連れて来て父に見つかりそうな所を、妹のもんに助けられたことがある。もんは東京にある寺の奉公に出ていたが、その時、学生の小畑(大川平八郎)と恋仲になり身籠もった。その後、小畑は故郷に逃げ帰り、もんは捨てられて、やむなく実家に戻って居る。さんは、純情可憐な乙女の風情、学者先生の家に女中奉公の身である。
身重になったもんが実家で休んでいると伊之が帰ってきた。縁側には、(さんも来ているようで)さんが持参した(母宛の)土産の駒下駄が置いてある。彼はそれを取り上げ一瞬顔をほころばせ、もんの寝姿を見て、そこに日が当たらないように簾を下ろす。気がついたもんが「何だ、兄さんか」と言えば「さんが来たのか」「ええ」「お前の男から手紙が来たか」「いいじゃないのそんなこと、来たって来なくたって」「てめえ、そんな体にされて、うっちゃられやがって」「人のこと心配しなくたっていいわよ」といったやりとりが次第にエスカレート、二人は激しく罵り合う。戻って来た母・りくが「怒っていいときと、悪いときがあるんだ。怒ってもらいたければ父さんにしてもらえばいいんだ。父さんはじっと黙っていなさるんだもの。今はもんを静かに休ませる時なんだよ」となだめる。もんは「父さんは、お前のことはお前が“かたをつけろ”、顔も見たくないと言う、兄さんから何を言われても頭痛がするばかりで、どうしていいかわからない」と呟く。その時、家の前を馴染みの郵便局員が「よう、もんちゃん。今度は長い逗留だね。こんなに暑くっちゃ、町にも出られないや」と言って通り過ぎた。黙って見ている伊之、もんは「なあに、女一匹、何をしたって食べていけるんだ!」と決意したが・・・。 それから1年が過ぎた。もんが身籠もった子どもは死産、今では五反田の花街で働いている。そんな折、赤座の家に小畑が訪ねてきた。応対に出たもんの父に向かって「いろいろと御迷惑をおかけしたことをお詫びして、さっぱりしたい」と言う。父は激昂する気持ちを抑え、「小畑さん、今回はお前さんの勝ちだったが、今後、こんな罪作りなことはおやめなせい」と言い、仕事場に戻っていく。小畑は母に名刺と金を手渡し帰路に就くが、帰り道、伊之が追いかけてきた。「オレはもんの兄だが、ちょっと話がある」と林の中に誘う。「オレともんは兄妹以上に仲がよかったんだ。1年前、もんに辛く当たったのは、オレが盾になって、世間の目から守るためだ。お前のおかげでもんは自暴自棄、どうしようもない女になってしまった」と小畑に鉄槌を下し、足蹴にした。それでも無抵抗で倒れ込んだ小畑に「あんたも妹がいればオレと同じことをしただろう」と助け起こし「お前、大丈夫か」と気遣う様子が、何とも男らしく、私の涙は止まらなかった。
それから1週間後、もんが久しぶりに実家に帰ってくる。見るからに厚化粧、バスの中ではタバコを吹かし、なるほど一端の商売女に変貌していた。橋の上で、さんを見つけるとすぐさま車を降り、姉妹が連れ立って懐かしい我が家へと向かう。途中で交わす、もんの話はもっぱら男、「お前が奉公している御主人様は変な目で見ないかい?」「ハハハハ、御主人様は学者で、禿げているのよ」。二人を優しく出迎える母、もんに「七日ばかり前に小畑さんが訪ねてきたよ」。もんは一瞬驚くが「御苦労様なこと、あの人、もう来なくてもよかったのに。お父さんと会ったの?乱暴しなかった?」「ああ、相手をいたわるようだったよ。昔なら殴っていただろうけれど、ずいぶん温和しくなったね」という言葉を聞いてホッとしたか、「でもちょっといい男だったでしょう?」。「呆れるよ、この子は」
「兄さんには会わなかったでしょうね」「伊之には、会わなかったと思うよ」。
だがしかし、伊之が昼食のために帰宅した。もんの姿を見るなり「自堕落女め、またおめおめと帰って来やがったのか!・・・どこかで泥臭い人足相手に騒いでいた方がいいぜ。ここはこう見えても堅気のウチなんだから」と毒づいた。母やさんが「帰ってくるなりそんなことを言うもんじゃない」と取りなすが「この前、来た野郎もそうだ、来れた義理でもないのに、こっちを舐めているから、のこのことやって来れるんだ」。その言葉を聞いたもんの表情が変わった。「小畑さんに会ったの?」「ああ、会った」「何をしたのあの人に、乱暴したんじゃないわよね」「思うだけのことをしてやった。蹴飛ばしたが、叶わないと思ったか手出しをしねえ、オレは胸がすうっとしたくらいだ」「もう一度言ってごらん、あの人に何をしたというの」「半殺しにしてやったんだ」「えっ、半殺し?」その言葉を聞いて、もんの心は張り裂けたか、傍にあったタバコの箱を投げつけると、伊之に掴みかかった。「誰がそんなことをお前に頼んだ。手出しをしないあの人を何で殴ったり蹴ったりしたんだ。この卑怯者! 極道者!」と叫びながら引っ掻く、「痛え、このあま!」と突き飛ばされても果敢に掴みかかったが、庭先に叩き出され「さあ殴れ、さあ殺せ」と居直った。「やい!はばかりながらこのもんは、ション便臭い女を相手にしているお前なんぞとは違う女なんだ」「やい、石屋の小僧!それでもお前は男か。よくも、もんの男を打ちやがったな。もんの兄貴がそんな男であることを臆面もなくさら出し、もんに恥をかかせやがったな、畜生、極道者!」という啖呵に、伊之は応えられない。母に「いいからこの場を外しておくれ」と言われ「畜生!とっとと失せろ」と捨て台詞を吐いてその場から立ち去った。用意されている昼食を掻っ込むが、気持ちは収まらず庭に出る。棒立ちで泣いている。男泣きに泣いている。その姿には「もん、お前はどうしてそんな女になってしまったんだ」という心情が浮き彫りされているようだ。もんも泣いている。さんも泣いている。母はしみじみと「もん、お前は、大変な女におなりだねえ」と嘆息する。「そうでもないのよ、お母さん。心配しなくたっていいわ」「でも、あれだけ言える女なんて初めてだよ。後生だから、堅気の暮らしをして、女らしい女になっておくれ」「あたし、お母さんが考えているほどひどい女になりはしないわ」
母は箪笥から小畑の名刺を取りだし、おもんに手渡す。もんは一瞥して名刺を破り捨てた。「こんなもん、私にはもう用はないわ」。「私がこの家に戻るのは、時々、お母さんの顔を見たくなるから、あんなイヤな兄さんでも顔を見たくなるのよ」。その声が聞こえたかどうか、伊之はまだ泣きながら職場へと戻って行った。 そんな修羅場を見ることなく、父の赤座は船の中、数十人の人足を率いて「夏までに仕事を延べて続けるんだ。その気持ちのある奴は手をあげろ!」「おおおう」と全員の手が上がるのを見届けて、現場に赴く。威勢よく船を降りる人足たちの水しぶきを映しながらこの映画は「終」となった。
この映画の見どころは、何と言っても名優・丸山定夫が演じた伊之という男の魅力であろう。妹・もんとは「兄妹」以上の仲、その妹が書生っぽの若造・小畑に汚され、自堕落になっていく。何とか立ち直ってほしいと思うが、どうすることもできない。そのやるせない気持ちが、二つの修羅場に漂っている。言動は粗暴だが、心根は優しい。そんな兄を知り尽くしているおもんだからこそ、思う存分、伊之に毒づくことができるのだ。もんを演じた竹久千恵子の実力も見逃せない。全体を通して、小畑への恋慕が一途に貫かれている。とりわけ、修羅場では、兄を慕い、その兄が自分のために弱い者いじめをしている情けなさが、「兄貴がそんな男であることを臆面もなくさら出し、もんに恥をかかせやがったな」という言葉の中に感じられる。《私の兄貴は本来、そんな男ではなかったはずなのに》という思いは、伊之が《オレの妹は、そんな女であるはずがない》と思う気持ちと重なる。伊之は小畑を「半殺し」にしたわけではない。「お前、大丈夫か」と気遣い、帰りの停留所まで教えてやる、優しい心根の男なのである。しかし、もんはそのことを知らない。そうした行き違いの悲劇を竹久は見事に描出しているのである。
この原作は、戦後、監督・成瀬巳喜男によっても映画化されている。そこでは、伊之・森雅之、もん・京マチ子、父・山本礼三郎、母・浦辺粂子、さん・久我美子、小畑・船越英二という配役で物語が展開する。時代背景も戦後に手直し、さんの恋人役(堀雄二)を付け加えるなど、それは、それとして充実した佳品に違いないとはいえ、人物の風格、人間模様の描出という点では、今一歩、この作品に及ばなかったと私は思う。とりわけ、丸山定夫と森雅之の「男泣き」の景色、竹下千恵子と京マチ子の「啖呵」の勢いに差が出たことは否めなかった。戦前を代表する文芸作品の中でも、屈指の名作であることを確認した次第である。
(2017.5.10)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

兄・伊之(丸山定夫)、長妹・もん(竹久千恵子)、末妹・さん(堀越節子)である。伊之は腕のいい石材職人だが、仕事も気ままで、遊び好き、ある晩など馴染みの女を連れて来て父に見つかりそうな所を、妹のもんに助けられたことがある。もんは東京にある寺の奉公に出ていたが、その時、学生の小畑(大川平八郎)と恋仲になり身籠もった。その後、小畑は故郷に逃げ帰り、もんは捨てられて、やむなく実家に戻って居る。さんは、純情可憐な乙女の風情、学者先生の家に女中奉公の身である。
身重になったもんが実家で休んでいると伊之が帰ってきた。縁側には、(さんも来ているようで)さんが持参した(母宛の)土産の駒下駄が置いてある。彼はそれを取り上げ一瞬顔をほころばせ、もんの寝姿を見て、そこに日が当たらないように簾を下ろす。気がついたもんが「何だ、兄さんか」と言えば「さんが来たのか」「ええ」「お前の男から手紙が来たか」「いいじゃないのそんなこと、来たって来なくたって」「てめえ、そんな体にされて、うっちゃられやがって」「人のこと心配しなくたっていいわよ」といったやりとりが次第にエスカレート、二人は激しく罵り合う。戻って来た母・りくが「怒っていいときと、悪いときがあるんだ。怒ってもらいたければ父さんにしてもらえばいいんだ。父さんはじっと黙っていなさるんだもの。今はもんを静かに休ませる時なんだよ」となだめる。もんは「父さんは、お前のことはお前が“かたをつけろ”、顔も見たくないと言う、兄さんから何を言われても頭痛がするばかりで、どうしていいかわからない」と呟く。その時、家の前を馴染みの郵便局員が「よう、もんちゃん。今度は長い逗留だね。こんなに暑くっちゃ、町にも出られないや」と言って通り過ぎた。黙って見ている伊之、もんは「なあに、女一匹、何をしたって食べていけるんだ!」と決意したが・・・。 それから1年が過ぎた。もんが身籠もった子どもは死産、今では五反田の花街で働いている。そんな折、赤座の家に小畑が訪ねてきた。応対に出たもんの父に向かって「いろいろと御迷惑をおかけしたことをお詫びして、さっぱりしたい」と言う。父は激昂する気持ちを抑え、「小畑さん、今回はお前さんの勝ちだったが、今後、こんな罪作りなことはおやめなせい」と言い、仕事場に戻っていく。小畑は母に名刺と金を手渡し帰路に就くが、帰り道、伊之が追いかけてきた。「オレはもんの兄だが、ちょっと話がある」と林の中に誘う。「オレともんは兄妹以上に仲がよかったんだ。1年前、もんに辛く当たったのは、オレが盾になって、世間の目から守るためだ。お前のおかげでもんは自暴自棄、どうしようもない女になってしまった」と小畑に鉄槌を下し、足蹴にした。それでも無抵抗で倒れ込んだ小畑に「あんたも妹がいればオレと同じことをしただろう」と助け起こし「お前、大丈夫か」と気遣う様子が、何とも男らしく、私の涙は止まらなかった。
それから1週間後、もんが久しぶりに実家に帰ってくる。見るからに厚化粧、バスの中ではタバコを吹かし、なるほど一端の商売女に変貌していた。橋の上で、さんを見つけるとすぐさま車を降り、姉妹が連れ立って懐かしい我が家へと向かう。途中で交わす、もんの話はもっぱら男、「お前が奉公している御主人様は変な目で見ないかい?」「ハハハハ、御主人様は学者で、禿げているのよ」。二人を優しく出迎える母、もんに「七日ばかり前に小畑さんが訪ねてきたよ」。もんは一瞬驚くが「御苦労様なこと、あの人、もう来なくてもよかったのに。お父さんと会ったの?乱暴しなかった?」「ああ、相手をいたわるようだったよ。昔なら殴っていただろうけれど、ずいぶん温和しくなったね」という言葉を聞いてホッとしたか、「でもちょっといい男だったでしょう?」。「呆れるよ、この子は」
「兄さんには会わなかったでしょうね」「伊之には、会わなかったと思うよ」。
だがしかし、伊之が昼食のために帰宅した。もんの姿を見るなり「自堕落女め、またおめおめと帰って来やがったのか!・・・どこかで泥臭い人足相手に騒いでいた方がいいぜ。ここはこう見えても堅気のウチなんだから」と毒づいた。母やさんが「帰ってくるなりそんなことを言うもんじゃない」と取りなすが「この前、来た野郎もそうだ、来れた義理でもないのに、こっちを舐めているから、のこのことやって来れるんだ」。その言葉を聞いたもんの表情が変わった。「小畑さんに会ったの?」「ああ、会った」「何をしたのあの人に、乱暴したんじゃないわよね」「思うだけのことをしてやった。蹴飛ばしたが、叶わないと思ったか手出しをしねえ、オレは胸がすうっとしたくらいだ」「もう一度言ってごらん、あの人に何をしたというの」「半殺しにしてやったんだ」「えっ、半殺し?」その言葉を聞いて、もんの心は張り裂けたか、傍にあったタバコの箱を投げつけると、伊之に掴みかかった。「誰がそんなことをお前に頼んだ。手出しをしないあの人を何で殴ったり蹴ったりしたんだ。この卑怯者! 極道者!」と叫びながら引っ掻く、「痛え、このあま!」と突き飛ばされても果敢に掴みかかったが、庭先に叩き出され「さあ殴れ、さあ殺せ」と居直った。「やい!はばかりながらこのもんは、ション便臭い女を相手にしているお前なんぞとは違う女なんだ」「やい、石屋の小僧!それでもお前は男か。よくも、もんの男を打ちやがったな。もんの兄貴がそんな男であることを臆面もなくさら出し、もんに恥をかかせやがったな、畜生、極道者!」という啖呵に、伊之は応えられない。母に「いいからこの場を外しておくれ」と言われ「畜生!とっとと失せろ」と捨て台詞を吐いてその場から立ち去った。用意されている昼食を掻っ込むが、気持ちは収まらず庭に出る。棒立ちで泣いている。男泣きに泣いている。その姿には「もん、お前はどうしてそんな女になってしまったんだ」という心情が浮き彫りされているようだ。もんも泣いている。さんも泣いている。母はしみじみと「もん、お前は、大変な女におなりだねえ」と嘆息する。「そうでもないのよ、お母さん。心配しなくたっていいわ」「でも、あれだけ言える女なんて初めてだよ。後生だから、堅気の暮らしをして、女らしい女になっておくれ」「あたし、お母さんが考えているほどひどい女になりはしないわ」
母は箪笥から小畑の名刺を取りだし、おもんに手渡す。もんは一瞥して名刺を破り捨てた。「こんなもん、私にはもう用はないわ」。「私がこの家に戻るのは、時々、お母さんの顔を見たくなるから、あんなイヤな兄さんでも顔を見たくなるのよ」。その声が聞こえたかどうか、伊之はまだ泣きながら職場へと戻って行った。 そんな修羅場を見ることなく、父の赤座は船の中、数十人の人足を率いて「夏までに仕事を延べて続けるんだ。その気持ちのある奴は手をあげろ!」「おおおう」と全員の手が上がるのを見届けて、現場に赴く。威勢よく船を降りる人足たちの水しぶきを映しながらこの映画は「終」となった。
この映画の見どころは、何と言っても名優・丸山定夫が演じた伊之という男の魅力であろう。妹・もんとは「兄妹」以上の仲、その妹が書生っぽの若造・小畑に汚され、自堕落になっていく。何とか立ち直ってほしいと思うが、どうすることもできない。そのやるせない気持ちが、二つの修羅場に漂っている。言動は粗暴だが、心根は優しい。そんな兄を知り尽くしているおもんだからこそ、思う存分、伊之に毒づくことができるのだ。もんを演じた竹久千恵子の実力も見逃せない。全体を通して、小畑への恋慕が一途に貫かれている。とりわけ、修羅場では、兄を慕い、その兄が自分のために弱い者いじめをしている情けなさが、「兄貴がそんな男であることを臆面もなくさら出し、もんに恥をかかせやがったな」という言葉の中に感じられる。《私の兄貴は本来、そんな男ではなかったはずなのに》という思いは、伊之が《オレの妹は、そんな女であるはずがない》と思う気持ちと重なる。伊之は小畑を「半殺し」にしたわけではない。「お前、大丈夫か」と気遣い、帰りの停留所まで教えてやる、優しい心根の男なのである。しかし、もんはそのことを知らない。そうした行き違いの悲劇を竹久は見事に描出しているのである。
この原作は、戦後、監督・成瀬巳喜男によっても映画化されている。そこでは、伊之・森雅之、もん・京マチ子、父・山本礼三郎、母・浦辺粂子、さん・久我美子、小畑・船越英二という配役で物語が展開する。時代背景も戦後に手直し、さんの恋人役(堀雄二)を付け加えるなど、それは、それとして充実した佳品に違いないとはいえ、人物の風格、人間模様の描出という点では、今一歩、この作品に及ばなかったと私は思う。とりわけ、丸山定夫と森雅之の「男泣き」の景色、竹下千恵子と京マチ子の「啖呵」の勢いに差が出たことは否めなかった。戦前を代表する文芸作品の中でも、屈指の名作であることを確認した次第である。
(2017.5.10)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-11
付録・邦画傑作選・「大学の若旦那」(監督・清水宏・1933年」
ウィキペディア百科事典では、この作品について以下のように説明している。「・・・『大学の若旦那』(1933年)に始まる「大学の若旦那シリーズ」で明るく朗らかな笑いを提供し、清水は、このシリーズの成功によって松竹現代劇の娯楽映画を代表する監督となった。主演には、清水と体型が似た慶応ラグビー出身の藤井貢があたったが、このシリーズは、清水のオリジナルなアイデアであり、スポーツの花形選手でもある下町の老舗の若旦那が、恋とスポーツに活躍する朗らかでスマートなコメディである。シリーズ全般を通して、坂本武、吉川満子、武田春郎、三井秀男ら松竹の脇役俳優たちが、朗らかで暖かい笑いをみせて、非常に面白い映画として当時の観客を喜ばせたと言われている」。
配役は、主演、大学の若旦那・藤井に藤井貢、その父(老舗醤油店・丸藤店主)五兵衛に武田春郞、その長妹・みな子に坪内美子、末妹・みや子に水久保澄子。藤井の伯父・村木に坂本武、みな子の夫・若原に齋藤達雄、丸藤の番頭・忠一に徳大寺伸、半玉・星千代に光川京子、柔道部主将に大山健二、ラグビー部選手に日守新一、山口勇、特に藤井を慕う後輩・北村に三井秀男、その姉・たき子に逢初夢子、待合の女将に吉川満子といった面々である。
筋書きはあってないようなもの、登場人物の人間模様だけが浮き彫りにされる「朗らかでスマートなコメディー」であった。藤井は大学ラグビーの花形選手だが、勉強はそこそこに遊蕩三昧、二階から帳場の銭入れに、吊したカブトムシを投げ入れ、札を掴ませる、それを懐に入れて夜な夜な花街へと繰り出す。芸者連中には扇子にサインをせがまれるプレイボーイ振りである。父はラグビーを「スイカ取り」と称して苦々しく思っているが、藤井は「どこ吹く風」、今夜も柔道部の連中が「選手会」(実は芸者遊び)の誘いにやってきた。丁稚に肩をもませている隙をねらってまんまと家出、馴染みの料亭に繰り込めば、伯父の村木と鉢合わせ、「おじさんも、なかなか若いですなあ。おいみんな、今日はおじさんの奢りだぜ」。
要するに、店主・五兵衛の思惑は、①長妹のみな子は近々、若原を婿に結婚の予定、②末妹のみや子はゆくゆく番頭の忠一と添わせるつもり、だが、③忠一は半玉・星千代と「できている」、藤井とみや子はそれにうすうす気づいている、④星千代は若旦那・藤井に惚れている、⑤藤井と忠一はそれにうすうす気づいている、⑤ラグビー選手の山口は藤井の存在が面白くない、大柄で強そうだがケンカには弱い、⑥ラグビー選手の北村は藤井に憧れている、⑦北村の姉・たき子はレビューのダンサーで弟の学資を稼いでいる、⑧藤井は星千代にせがまれてラグビーの練習風景を見せようと大学構内に連れて来た。みや子のセーラー服を着せ「ボクの妹だ」と紹介したが、実際のみや子が現れ、真相が判明。藤井はラグビー部から除名される羽目に・・・。⑨心機一転、藤井はみな子の婿になった遊び人・若原とレビュー通い、北村の姉・たき子の「おっかけ」を始める。⑩まもなく、ラグビー大学選手権、藤井が欠けたチームは戦力ダウン、北村は藤井を呼び戻したい。⑪藤井とたき子は「いい仲」になりつつあったが、北村は「チームのために藤井と別れてくれ」と談判。泣く泣くたき子は受け入れる、⑫晴れて藤井はチームに復帰、試合はもつれにもつれたが逆転優勝!、⑬しかし、たき子から離別の手紙を貰った藤井は試合後のシャワーを浴びながら独り泣き濡れていた、という内容である。
見どころ、勘所は奈辺に・・・。プレイボーイ・藤井の「侠気」であろうか。番頭・忠一と末妹・みや子を添わせるために半玉・星千代から身を引いた。レビューダンサー・たき子への「おっかけ」も、そのための方便だったが、次第に「本心」へと発展、恋の痛手に泣いている。しかし、星千代も傷ついた。たき子も傷ついた。みや子と忠一は・・・?
何とも、曖昧模糊とした結末だったが、「朗らかで暖かい笑いをみせて、非常に面白い映画として当時の観客を喜ばせたと言われている」とすれば、当時の観客はその《曖昧模糊》を喜んだということになる。そのギャップが、私にはたいそう面白かった。
さらにまた、挿入された往時の「浅草レビュー」の舞台、「大学ラグビー選手権」の試合なども十分に楽しめる傑作であったと私は思う。(2017.2.27)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

配役は、主演、大学の若旦那・藤井に藤井貢、その父(老舗醤油店・丸藤店主)五兵衛に武田春郞、その長妹・みな子に坪内美子、末妹・みや子に水久保澄子。藤井の伯父・村木に坂本武、みな子の夫・若原に齋藤達雄、丸藤の番頭・忠一に徳大寺伸、半玉・星千代に光川京子、柔道部主将に大山健二、ラグビー部選手に日守新一、山口勇、特に藤井を慕う後輩・北村に三井秀男、その姉・たき子に逢初夢子、待合の女将に吉川満子といった面々である。
筋書きはあってないようなもの、登場人物の人間模様だけが浮き彫りにされる「朗らかでスマートなコメディー」であった。藤井は大学ラグビーの花形選手だが、勉強はそこそこに遊蕩三昧、二階から帳場の銭入れに、吊したカブトムシを投げ入れ、札を掴ませる、それを懐に入れて夜な夜な花街へと繰り出す。芸者連中には扇子にサインをせがまれるプレイボーイ振りである。父はラグビーを「スイカ取り」と称して苦々しく思っているが、藤井は「どこ吹く風」、今夜も柔道部の連中が「選手会」(実は芸者遊び)の誘いにやってきた。丁稚に肩をもませている隙をねらってまんまと家出、馴染みの料亭に繰り込めば、伯父の村木と鉢合わせ、「おじさんも、なかなか若いですなあ。おいみんな、今日はおじさんの奢りだぜ」。
要するに、店主・五兵衛の思惑は、①長妹のみな子は近々、若原を婿に結婚の予定、②末妹のみや子はゆくゆく番頭の忠一と添わせるつもり、だが、③忠一は半玉・星千代と「できている」、藤井とみや子はそれにうすうす気づいている、④星千代は若旦那・藤井に惚れている、⑤藤井と忠一はそれにうすうす気づいている、⑤ラグビー選手の山口は藤井の存在が面白くない、大柄で強そうだがケンカには弱い、⑥ラグビー選手の北村は藤井に憧れている、⑦北村の姉・たき子はレビューのダンサーで弟の学資を稼いでいる、⑧藤井は星千代にせがまれてラグビーの練習風景を見せようと大学構内に連れて来た。みや子のセーラー服を着せ「ボクの妹だ」と紹介したが、実際のみや子が現れ、真相が判明。藤井はラグビー部から除名される羽目に・・・。⑨心機一転、藤井はみな子の婿になった遊び人・若原とレビュー通い、北村の姉・たき子の「おっかけ」を始める。⑩まもなく、ラグビー大学選手権、藤井が欠けたチームは戦力ダウン、北村は藤井を呼び戻したい。⑪藤井とたき子は「いい仲」になりつつあったが、北村は「チームのために藤井と別れてくれ」と談判。泣く泣くたき子は受け入れる、⑫晴れて藤井はチームに復帰、試合はもつれにもつれたが逆転優勝!、⑬しかし、たき子から離別の手紙を貰った藤井は試合後のシャワーを浴びながら独り泣き濡れていた、という内容である。
見どころ、勘所は奈辺に・・・。プレイボーイ・藤井の「侠気」であろうか。番頭・忠一と末妹・みや子を添わせるために半玉・星千代から身を引いた。レビューダンサー・たき子への「おっかけ」も、そのための方便だったが、次第に「本心」へと発展、恋の痛手に泣いている。しかし、星千代も傷ついた。たき子も傷ついた。みや子と忠一は・・・?
何とも、曖昧模糊とした結末だったが、「朗らかで暖かい笑いをみせて、非常に面白い映画として当時の観客を喜ばせたと言われている」とすれば、当時の観客はその《曖昧模糊》を喜んだということになる。そのギャップが、私にはたいそう面白かった。
さらにまた、挿入された往時の「浅草レビュー」の舞台、「大学ラグビー選手権」の試合なども十分に楽しめる傑作であったと私は思う。(2017.2.27)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-10
付録・邦画傑作選・「東京の宿」(監督・小津安二郎・1935年)
ユーチューブで映画「東京の宿」(監督・小津安二郎・1935年)を観た。原作はウィンザァト・モネとあるが、英語のウィズアウト・マネーをもじった名前で、「金無しに」「金が無ければ」「金の他に」ほどの意味であろう。要するに、架空の人物であり、脚色の池田忠雄、荒田正夫、監督・小津安二郎の合作ということである。
舞台は昭和10年頃の東京郊外、ガス・タンクや電柱などが林立する荒涼とした工業地帯を辿る道を、三人がとぼとぼと歩いている。一人は薄汚れたハンチング、丸首シャツ一枚にズボンといういでたちの男・喜八(坂本武)、あとの二人はその長男・善公(突貫小僧)と次男・正公(末松孝行)である。善公は大きな風呂敷包みを背負い、正公は飲み水の入った、水筒代わりの酒瓶を腰にぶら下げている。そのうらぶれた父子の姿は、文字通り「ウィズアウト・マネー」(文無し)の風情そのものであった。
喜八は職探しのため工場をあちこちと巡り歩き、善公と正公はその「お供」をさせられているのである。しかし、仕事は見つからない。疲れ果てて座り込んでいると、一匹の犬が通り過ぎた。「ちゃん、40銭!」と叫んで善公が走り出した。野犬を捕まえて届けると、40銭がもらえるのだ。喜八も正公を負ぶって追いかけたが、逃げられてしまった。文字通り「住所不定無職」の家族であり、夜は木賃宿「萬盛館」に泊まっている。宿は失業者でいっぱい、たまたま同宿者の子どもの新しい軍帽が、善公の前に転がってきた。善公が手に取ると、「ダメだい」とひったくり「あかんべえ」をする。
翌日も職探し、「砂町の方にでも行ってみるか」と三人で出かけていく。でも、仕事は見つからない。また、また黒い犬が通り過ぎた。今度は正公が走り出し、まんまと捕獲する。しかし、犬の体が大きく引きずられっぱなし、善公が代わって「ここで待ってろ」と言い、しばらくすると帰ってきた。後ろ手に何か持っている。真新しい軍帽である。正公いわく「犬は、めしじゃないか。ちゃんに怒られるぞ」。案の定、喜八は「馬鹿なものを買いやがって」と叱ったが、どうすることもできなかった。その日も、「萬盛館」に泊まるが、いよいよ持ち金が底をついてくる。善公が「明日は犬を捕まえよう」などと言っていると、和服姿の女・おたか(岡田嘉子)がその娘・君子(小嶋和子)を連れて入ってくる。向こうに座った君子と善公の目が合い、善公が「あっかんべえ」と舌をだすと、君子も舌を出す。正公も善公と一緒に舌を出す。それは子どもたち同士の「あいさつ」に他ならない。
いよいよ三日目、喜八はまた門番に断られた。途方に暮れて、三人は工場の見える空き地に座り込む。憔悴した喜八の前に善公が座って、励ますように「ちゃん、酒でも飲もう」と手まねで酌をする。喜八も受け取って飲む素振り「ああ、うめえ」、「ちゃん、するめだよ」と善公が草の一本をむしりとって渡すと「そうか、でもやっぱり酒の方がいいや」、「おい、おめえも飯を食え」と正公に呼びかける。「善公、よそってやれ」、正公も応じて食べる素振り、「うめえか」、正公が首を振ると「お茶をかけてやれ」、三者三様の男同士の「ままごと」(の景色)には、えも言われぬ詩情が漂っている。そこを通りかかったのが、おたかと君子。おたかが「猿江はどっちの方でしょうか」と喜八に訊ねてきた。たちまち君子と善公、正公が遊び始める。「子どもはすぐに仲良くなるね」などと語り合う姿が、「絵になっていた」のだが・・・。
いよいよ土壇場、宿に泊まるか、めしを食うか、三人は迷う。季節は夏、めしを食って野宿をすることに決めたが、雲行きがあやしい。飯屋を出るとすぐに本降りになってきた。三人が床屋の軒下で立ちすくんでいると、通りかかったのが、(喜八とは昔馴染みの)おつね(飯田蝶子)。彼女はさっきの飯屋を切り盛りしていたのだ。かくて、三人はおつねの厄介になることに・・・。おつねの口利きで喜八は工場勤め、善公も学校に通うようになったのだが・・・。喜八の悪い癖は「おせっかい」な「浮気心」か。おたか母子のことが気にかかる。おたかをおつねに紹介、一緒に面倒をみてくれ、という気配が感じられて、おつねは面白くない。
大詰めは、君子が疫痢にかかりその治療代を工面するため、おたかは酌婦に、その境遇を救わなければならない。喜八はおつねに借金を申し込んだが、すげなく断られ、やむなく20円を窃盗、警官から追われている。「このお金をおばちゃんのところに届けてくれ」と善公、正公に言い付け、おつねの家に逃げ込んだ。おつねに「いったい何をしたんだい」と問われても答えられない。「せっかく芽が出たと思っていたのに、お前さん、また悪いクセがでたんだね。はじめから本当のことを話してくれれば、何とかしたものを」とおつねは悔やんだが、すべては後の祭り。お互いに貧乏はしたくない、でも「かあやん(おつね)のおかげで職にありつけてからこの10日ほどが、俺の一番楽しい時だったよ」と言い残し、喜八は警察に向かう。その姿を、おつねは落涙しながら見送る他はなかったのである。
この映画の前半は、あくまで「コメディ」だが、後半に暗雲が立ちこめる。「四百四病の病より貧ほど辛いものはない」という決まり文句そのままに、終局を迎える。この映画の眼目は、「金無しに」(文無し)の生き様か、「金が無ければ」の悲劇か、「金の他に」生きがいがあるという提唱か、それは観客の判断(感性)にまかせよう、といった原作者・ウィンザァト・モネの「居直り」が窺われて、たいそう面白かった。いずれにせよ、飲んべえで女たらしの「身の上話」(身辺情話)などではさらさらなく、昭和恐慌、満州事変、五・一五事件、国際連盟脱退という流れの社会背景の中で、貧しい人々がどのような生活を余儀なくされたか、一方その裏には、しこたま儲けて甘い汁を吸っている連中もいることを「暗に」浮き彫りする傑作であったことに違いはない。セリフはサイレントだが、終始流れている音楽監督・堀内敬三のBGMも美しく、印象的であった。(2017.5.19)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

舞台は昭和10年頃の東京郊外、ガス・タンクや電柱などが林立する荒涼とした工業地帯を辿る道を、三人がとぼとぼと歩いている。一人は薄汚れたハンチング、丸首シャツ一枚にズボンといういでたちの男・喜八(坂本武)、あとの二人はその長男・善公(突貫小僧)と次男・正公(末松孝行)である。善公は大きな風呂敷包みを背負い、正公は飲み水の入った、水筒代わりの酒瓶を腰にぶら下げている。そのうらぶれた父子の姿は、文字通り「ウィズアウト・マネー」(文無し)の風情そのものであった。
喜八は職探しのため工場をあちこちと巡り歩き、善公と正公はその「お供」をさせられているのである。しかし、仕事は見つからない。疲れ果てて座り込んでいると、一匹の犬が通り過ぎた。「ちゃん、40銭!」と叫んで善公が走り出した。野犬を捕まえて届けると、40銭がもらえるのだ。喜八も正公を負ぶって追いかけたが、逃げられてしまった。文字通り「住所不定無職」の家族であり、夜は木賃宿「萬盛館」に泊まっている。宿は失業者でいっぱい、たまたま同宿者の子どもの新しい軍帽が、善公の前に転がってきた。善公が手に取ると、「ダメだい」とひったくり「あかんべえ」をする。
翌日も職探し、「砂町の方にでも行ってみるか」と三人で出かけていく。でも、仕事は見つからない。また、また黒い犬が通り過ぎた。今度は正公が走り出し、まんまと捕獲する。しかし、犬の体が大きく引きずられっぱなし、善公が代わって「ここで待ってろ」と言い、しばらくすると帰ってきた。後ろ手に何か持っている。真新しい軍帽である。正公いわく「犬は、めしじゃないか。ちゃんに怒られるぞ」。案の定、喜八は「馬鹿なものを買いやがって」と叱ったが、どうすることもできなかった。その日も、「萬盛館」に泊まるが、いよいよ持ち金が底をついてくる。善公が「明日は犬を捕まえよう」などと言っていると、和服姿の女・おたか(岡田嘉子)がその娘・君子(小嶋和子)を連れて入ってくる。向こうに座った君子と善公の目が合い、善公が「あっかんべえ」と舌をだすと、君子も舌を出す。正公も善公と一緒に舌を出す。それは子どもたち同士の「あいさつ」に他ならない。
いよいよ三日目、喜八はまた門番に断られた。途方に暮れて、三人は工場の見える空き地に座り込む。憔悴した喜八の前に善公が座って、励ますように「ちゃん、酒でも飲もう」と手まねで酌をする。喜八も受け取って飲む素振り「ああ、うめえ」、「ちゃん、するめだよ」と善公が草の一本をむしりとって渡すと「そうか、でもやっぱり酒の方がいいや」、「おい、おめえも飯を食え」と正公に呼びかける。「善公、よそってやれ」、正公も応じて食べる素振り、「うめえか」、正公が首を振ると「お茶をかけてやれ」、三者三様の男同士の「ままごと」(の景色)には、えも言われぬ詩情が漂っている。そこを通りかかったのが、おたかと君子。おたかが「猿江はどっちの方でしょうか」と喜八に訊ねてきた。たちまち君子と善公、正公が遊び始める。「子どもはすぐに仲良くなるね」などと語り合う姿が、「絵になっていた」のだが・・・。
いよいよ土壇場、宿に泊まるか、めしを食うか、三人は迷う。季節は夏、めしを食って野宿をすることに決めたが、雲行きがあやしい。飯屋を出るとすぐに本降りになってきた。三人が床屋の軒下で立ちすくんでいると、通りかかったのが、(喜八とは昔馴染みの)おつね(飯田蝶子)。彼女はさっきの飯屋を切り盛りしていたのだ。かくて、三人はおつねの厄介になることに・・・。おつねの口利きで喜八は工場勤め、善公も学校に通うようになったのだが・・・。喜八の悪い癖は「おせっかい」な「浮気心」か。おたか母子のことが気にかかる。おたかをおつねに紹介、一緒に面倒をみてくれ、という気配が感じられて、おつねは面白くない。
大詰めは、君子が疫痢にかかりその治療代を工面するため、おたかは酌婦に、その境遇を救わなければならない。喜八はおつねに借金を申し込んだが、すげなく断られ、やむなく20円を窃盗、警官から追われている。「このお金をおばちゃんのところに届けてくれ」と善公、正公に言い付け、おつねの家に逃げ込んだ。おつねに「いったい何をしたんだい」と問われても答えられない。「せっかく芽が出たと思っていたのに、お前さん、また悪いクセがでたんだね。はじめから本当のことを話してくれれば、何とかしたものを」とおつねは悔やんだが、すべては後の祭り。お互いに貧乏はしたくない、でも「かあやん(おつね)のおかげで職にありつけてからこの10日ほどが、俺の一番楽しい時だったよ」と言い残し、喜八は警察に向かう。その姿を、おつねは落涙しながら見送る他はなかったのである。
この映画の前半は、あくまで「コメディ」だが、後半に暗雲が立ちこめる。「四百四病の病より貧ほど辛いものはない」という決まり文句そのままに、終局を迎える。この映画の眼目は、「金無しに」(文無し)の生き様か、「金が無ければ」の悲劇か、「金の他に」生きがいがあるという提唱か、それは観客の判断(感性)にまかせよう、といった原作者・ウィンザァト・モネの「居直り」が窺われて、たいそう面白かった。いずれにせよ、飲んべえで女たらしの「身の上話」(身辺情話)などではさらさらなく、昭和恐慌、満州事変、五・一五事件、国際連盟脱退という流れの社会背景の中で、貧しい人々がどのような生活を余儀なくされたか、一方その裏には、しこたま儲けて甘い汁を吸っている連中もいることを「暗に」浮き彫りする傑作であったことに違いはない。セリフはサイレントだが、終始流れている音楽監督・堀内敬三のBGMも美しく、印象的であった。(2017.5.19)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-08
付録・邦画傑作選・「母を恋はずや」(監督・小津安二郎・1934年)
ユーチューブで映画「母を恋はずや」(監督・小津安二郎・1934年)を観た。「(この映画の)フィルムは現存するが、最初と最後の巻が失われている不完全バージョンである」(ウィキペディア百科事典)。
裕福な家庭・梶原家が、父の急逝により没落していく、そこで展開する家族の人間模様がきめ細やかに描き出されている。父(岩田祐吉)は、今度の日曜日、家族と七里ヶ浜へピクニックに行く約束をしていたが、長男の貞夫(加藤精一)と次男の幸作(野村秋生)が小学校の授業中に呼び出され、「お父さんに大変なことがおありだから、早く家に帰りたまえ」と告げられる。父は突然、心臓マヒで他界してしまったのである。
葬儀も終え、母・千恵子(吉川満子)と貞夫、幸作が父の遺影の下で朝食を摂っていると、父の友人・岡崎(奈良真養)が弔問に訪れた。彼は大学時代、ボート部の仲間だった。岡崎が言う。「ちょっと、お話ししたいことが・・・」、その内容は、「これからも貞夫君を永久に真の子どもとして育ててもらいたい」ということであった。貞夫は病没した先妻の子どもだったのだ。千恵子は「そのことなら、貞夫も幸作も区別なく、同じ気持ちで育ててまいります。亡くなられた奥様や主人にも誓うことができます」と応えた。「あなたも、これから大変ですなあ」「子どもたちを立派に育てることが楽しみです」。
それから8年後、岡崎の元に絵はがきが届いた。中学4年になった幸作の修学旅行先からである。岡崎は久しぶりに、洋館の屋敷から移った梶原家を訪れる。そこでは千恵子が浮かない様子、「貞夫が大学の本科に行く手続きで、戸籍謄本を見てしまった。あの子のあんな悲しい顔は今まで見たことがありません」と言う。岡崎は二階で憔悴している貞夫(大日向伝)の元に行き「お母さんに心配をかけないように」と話しかけるが、貞夫は拒絶する。「お母さんは君を本当の子だと思えばこそ、黙っていたんだ」「小父さんだってボクを騙していた一人だ、いつかは、判ることです。なぜもっと早く知らせてくれなかったんです!ボクは馬鹿にされていたように感じます。こんなことなら我が儘を言うんじゃなかった!いい気になって無遠慮な振る舞いをするんじゃなかった」。その言葉を聞いた岡崎は一喝する。「それが、多年の骨折りに対して返す言葉か!」たまらず寝転がる貞夫に返す言葉がない。岡崎は「起き上がって聞いたらどうだ。これまでお母さんが君と幸作君を区別したことがあったか。お母さんは君たち二人の成長だけを楽しみにしておられるのだ。その優しい心遣いを君はまるでわからないのか」。貞夫の肩が激しく揺れている。岡崎は貞夫に近づきその肩を優しく叩いた。気持ちが通じたか・・・、貞夫は起き上がり、涙を拭いながら「すみません! 小父さん」と呟いた。そして千恵子の前に正座して深々と頭を下げる。「すみません、母さん。ボクは母さんの本当の子です」。千恵子と見つめ合い涙がこぼれ出すのを見て、貞夫は母の膝に泣き崩れた。千恵子は「これからは何もかもお前に打ち明けようね」と言い、貞夫の頭を優しく撫で回す・・・。
やがて、梶原家はさらに郊外の借家に転居した。貞夫と幸作(三井秀雄)はトラックから荷物を降ろし整理する。懐かしい父の遺品のパイプを見つけ出し、兄弟で煙をふかす。ハットを目にすると、母に被せて父を思い出している。そこに岡崎の夫人(青木しのぶ)が訪ねて来た。岡崎は一年前に他界、遺品のオールを届けに来たのだ。兄弟は、サインを読み取りながら、父や岡崎の青春時代に思いを馳せる。兄弟もまた大学のボート部員になっていた。
幸作は仲間と伊豆巡りの計画を立てていた。兄も誘ったが用事があると言う。服部(笠智衆)という部員に好きな女ができ、横浜のチャブ屋に入り浸っている、貞夫は服部を連れ戻しに行こうとしているのだ。単身でチャブ屋に乗り込むと、服部にピンタをかませ、外に連れ出した。服部の女・らん子(松井潤子)が「勘定ぐらい置いて行ってもらいたいねえ。お前さんおけらのくせに、たいそう強がるじゃないか。」と毒づけば、またもやピンタ一発、「ああ、金なら何時でも持ってきてやらあ」と言い残し去って行く。その後ろ姿を見て、朋輩の光子(逢初夢子)が「あいつ、ちょっと勇ましいじゃないか」と目を細めた・・・。
貞夫は帰宅すると、縫い物をしている千恵子に「困っている友だちが居るんで、少しお金が欲しいんですけど」と無心した。千恵子はすぐに頷いて、箪笥から財布を取り出し紙幣を渡す。貞夫はそれをありがたく頂いて、自室に向かったのだが、そこには幸作がしょんぼりと座っていた。家の暮らしは楽ではない、「だから伊豆巡りに行ってはいけない」と言われた由、貞夫は直ちに千恵子のところに戻り、「このお金を幸作に与えて、行かせてやってください」と言ったが「幸作は遊びのお金、あなたのお金は友だちのへ義理、同じではありません」と取り合わない。やむなく、貞夫は幸作に金を渡し、旅行の準備を手伝う。様子を見に来た千恵子に「母さん、やっぱり出かけてきます」と幸作は喜んだが、「お前、兄さんに無理を言ってはいけないよ」と不同意、貞夫は「ボクがあげたんです。
幸作は前から楽しみにしていたんです。ボクだけが貰うのは不公平です」・・・、幸作は「だいたい母さんは兄さんばかりよくする。叱られるのはボクばかりだ」と帽子を放り投げてふてくされる。貞夫も「ボクもそう思います」と同意、千恵子はしばらく立ち尽くしていたが「そんなに行きたければ、出かけてもかまわないんだよ」と翻意した。
かくて、幸作は伊豆巡りに出立、そろそろ帰る日の頃であろうか、千恵子は夫の遺品、洋服を虫干ししている様子。懐中時計を耳に当て、遺影を眺めている。そこに貞夫も帰宅して父のハットを被ってみたりする。千恵子は父のチョッキをたたみながら「幸作が山に行くんだったら、これを持たせてやればよかった」「そんな古い物、幸作は来ませんよ」「まだ繕えば着られる洋服があります。幸作ならこれで十分・・・」と言うと、貞夫の顔色が変わった。「どうして幸作なら十分なんですか?」「・・・・」「母さんは、やっぱりボクと幸作を区別してるんだ」「そんなつもりはないけれど・・・」。貞夫はキッとして、自室に立ち去り、着物に着替えて外出の構え、千恵子がやって来て「どうすれば、お前の気に入るのか話しておくれ」「そういう気遣いがイヤなんです、気に入らなければボクを殴ればいいでしょう」「何もそんなに言わなくても・・・」。取り合わず、貞夫は横浜のチャブ屋に向かった。光子の部屋に落ち着く。掃除婦(飯田蝶子)が雑巾がけをしている。貞夫に母の姿が浮かんだか、ウィスキーをたてつづけに飲んで、じっと(ささくれの)手を見た。光子が「お前さん、親不孝者だね」「・・・・」「ささくれがあるのは、親不孝の証し」と言う。光子の指にも包帯があった。貞夫はたまらずそこを飛び出して家に向かう。その様子を呆然と見送る掃除婦、光子も「わからないね、その気持ち」と呟いた。
貞夫が家に戻ると、幸作が帰宅していた。険しい顔つきで「帰ってきたんだたら、母さんに謝ったらどうだい。兄さん、母さんに何を言ったんだい。母さんを泣かせるなんて馬鹿だ、大馬鹿だ!」と言う。「年をとって涙もろくなったんだろう」と応えると、幸作はたまらず殴りかかった。貞夫は殴られるまま「外に出ろ!」と言う。夜道を歩く二人・・・、向かい合うと貞夫が言う「あんなおふくろのどこがいいんだ」「それは本心か」「嘘ではない、あんなおふくろのことでムキになる気持ちがわからない」、幸作はまたも貞夫に殴りかかる。一発、二発、三発、四発、五発・・・、しかし貞夫は殴り返さない。幸作は手を止め泣き出した。「なんで殴り返さないんだ!」「おまえのような奴を殴ったって仕方がない」「・・・・」「(おふくろを)せいぜい大事にしてやれよ」と言い残すと、どこかに行ってしまった。幸作は力なく家に戻る。千恵子に「あんな奴どうなったってかまわない。散々ボクや母さんの悪口を言って、どこかへ行っちまいやがった」と言う。「お前、兄さんをそんな人だとお思いかい」「母さんはまた兄さんの肩を持つのか」「私には、貞夫の気持ちがよくわかります」「・・・・」「あの子は立派なことをしようとしたんだよ」「・・・・」「兄さんはね、私の本当の子ではなかったんだよ」「・・・!」「それをお前に知らせたくなくて、お前の大学の手続きはみんな兄さんがやってくれたんだ」「・・・・」「兄さんは、お前のためにこの家から身を引こうとして・・・」と言うなり、千恵子は泣き出した。「心にもない悪口を言って、私たちを諦めさせようとしたんだよ」。幸作は千恵子の前にひざまづき「ボクは馬鹿でした。どんなことがあっても兄さんに戻って来てもらう、そして思う存分殴ってもらうんだ」と泣き崩れる。母もまた・・・・。
貞夫は横浜のチャブ屋に居た。「また今日も暮れちゃうんだなあ」と貞夫が溜息を吐くと、光子が「帰りたけりゃお帰りよ」と言う。そんなところに、母の千恵子と幸作、彼の友人が迎えに来た。まずは千恵子が一人でチャブ屋に赴き、ロビーで貞夫と面会する。「ボクに何の用ですか。ボクは母さんに用はありません」「そんな心にもないことを言って・・・。母さんは小さい頃からお前のことはよく知っています」「知っているんなら放っておいてください。ボクは一人が性に合っているんだ」「お願いだから戻っておくれ。お前がいないと夜もおちおち眠れない。幸作やお友達だって、待っているんだよ」。しかし、貞夫は応じない。「ボクは、家に戻って母さんや幸作の面倒を見るなんてまっぴらだ!」。いつのまにか、チャブ屋の女たちが二人を取り巻いている。「ボクはもう母さんから何も聞きたくないんです。これ以上何を言っても無駄ですよ」と言い放ち、部屋に立ち去ってしまった。万事休す、千恵子はすごすごと戻っていく。その後に従う幸作と友人・・・、その姿を二階の窓から見送る貞夫・・・、光子が入ってきて「お前さん、大芝居だったね。よっぽど大向こうから声かけようと思ったんだけど」と感想を述べる。貞夫は全身の力が脱けてベットに横たわる。光子は朋輩に「おなかが空かない」と言われ出て行く。入れ替わりにに掃除婦が入ってきて部屋を片付け始める。その様子を見ていた貞夫は起き上がり、掃除婦にタバコを勧める。掃除婦は一本頂戴、煙を吐きながら言う。「悪いことは言いませんよ。木の股から生まれたんじゃあるまいし、あんまり親は泣かせるもんじゃありませんよ」「・・・」「あたしにも丁度、あんたぐらいの息子があるんですけれど」・・・・、貞夫が「オレよりましだって言うのかい?」と問いかけると、掃除婦は淋しそうに笑って「よけりゃ、こんなことしてませんよ」と出て行った。貞夫はまたベッドに横たわる。サンドイッチを調達した光子が部屋に戻る。貞夫にも勧めるが、天井を眺めたまま無言。光子はサンドイッチをぱくついて貞夫の方を見やった時、この不完全バージョンの映像は途切れた。以後の字幕では、貞夫は掃除婦の言葉に心を動かされ、家に戻り、母に謝罪する、それから三年後、一家は再び郊外に転居、母子三人の平穏な暮らしは続いていると記されている。
この映画の見どころは、裕福な暮らしをしていた梶原家が大黒柱の父を失うことにより没落していく中で、母と息子二人(異母兄弟)が繰り広げる「人間模様」の《綾》である。母は、二人の息子を同じように育てているつもりだが、無意識に、亡夫への義理のため先妻の子・貞夫の方を重んじる。幸作に比べると、どこか他人行儀でよそよそしい。貞夫は当初、母に甘え我が儘な振る舞いをしていたが、千恵子が実の母ではないと知ってからは、いわば「母なし子」状態、甘える相手を失ってしまったのだ。「ボクは一人が性に合っているんだ」という貞夫の言葉が何よりも雄弁にそのことを物語っている。その立場に置かれなければわからない、絶対的な《孤独感》なのである。しかし、掃除婦の「木の股から生まれたんじゃなし、あんまり親を泣かせるもんじゃないよ」という一言は、そんな孤独感を払拭するには十分であった。掃除婦にも自分と同じくらい息子が居る。貞夫は「オレよりはマシだろ?」と問いかけるが、答は意外にも「よけりゃ、こんなことしてませんよ」。そうか、その息子も親を泣かせているんだ、オレもこんな所(チャブ屋)で、こんなこと(無為に日々を過ごすこと)をしているときではない、と思ったに違いない。そんな心の《綾模様》を、二枚目スター・大日向伝は鮮やかに描き出していたと、私は思う。
母・千恵子を演じた吉川満子の風情もたまらなく魅力的、誰よりも夫を愛し、子どもたちを慈しむ。時には背かれて雑言を浴びせかけられ涙ぐむこともあるが、毅然として耐え、誠を貫こうとする「母性」の気高さがひしひしと伝わってくるのである。
弟・幸作を演じた三井秀雄の「弟振り」も見事であった。とりわけ、兄が母の本当の子ではないと知らされた時の表情、そこには「なぜもっと早く知らせてくれなかったんだ」という思い(母への恨み)は微塵も感じられず、「ボクが間違っていました」と母に謝る純情が浮き彫りされている。その兄を、わけも知らずに殴ってしまった後悔、その償いのために「ボクを殴ってもらうんだ」と思う素直さが輝いていた。
極め付きは、掃除婦を演じた飯田蝶子の存在感、出番はほんのちょい役だが、たった一言、二言のセリフで主役・貞夫を翻意させる実力は光っている。彼女は、不器量のため女優への道はなかなか開けなかったが、私のような者がいなければ主役は引き立たないと、自分を売り込んだという。さすがは、終始「老け役」を貫いた名優の至言である。
その他にも、奈良真養の庶民的な風格、笠智衆の意外な若さ、逢初夢子の色香などなど見どころ満載の傑作であった。
(2017.7.1)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

裕福な家庭・梶原家が、父の急逝により没落していく、そこで展開する家族の人間模様がきめ細やかに描き出されている。父(岩田祐吉)は、今度の日曜日、家族と七里ヶ浜へピクニックに行く約束をしていたが、長男の貞夫(加藤精一)と次男の幸作(野村秋生)が小学校の授業中に呼び出され、「お父さんに大変なことがおありだから、早く家に帰りたまえ」と告げられる。父は突然、心臓マヒで他界してしまったのである。
葬儀も終え、母・千恵子(吉川満子)と貞夫、幸作が父の遺影の下で朝食を摂っていると、父の友人・岡崎(奈良真養)が弔問に訪れた。彼は大学時代、ボート部の仲間だった。岡崎が言う。「ちょっと、お話ししたいことが・・・」、その内容は、「これからも貞夫君を永久に真の子どもとして育ててもらいたい」ということであった。貞夫は病没した先妻の子どもだったのだ。千恵子は「そのことなら、貞夫も幸作も区別なく、同じ気持ちで育ててまいります。亡くなられた奥様や主人にも誓うことができます」と応えた。「あなたも、これから大変ですなあ」「子どもたちを立派に育てることが楽しみです」。
それから8年後、岡崎の元に絵はがきが届いた。中学4年になった幸作の修学旅行先からである。岡崎は久しぶりに、洋館の屋敷から移った梶原家を訪れる。そこでは千恵子が浮かない様子、「貞夫が大学の本科に行く手続きで、戸籍謄本を見てしまった。あの子のあんな悲しい顔は今まで見たことがありません」と言う。岡崎は二階で憔悴している貞夫(大日向伝)の元に行き「お母さんに心配をかけないように」と話しかけるが、貞夫は拒絶する。「お母さんは君を本当の子だと思えばこそ、黙っていたんだ」「小父さんだってボクを騙していた一人だ、いつかは、判ることです。なぜもっと早く知らせてくれなかったんです!ボクは馬鹿にされていたように感じます。こんなことなら我が儘を言うんじゃなかった!いい気になって無遠慮な振る舞いをするんじゃなかった」。その言葉を聞いた岡崎は一喝する。「それが、多年の骨折りに対して返す言葉か!」たまらず寝転がる貞夫に返す言葉がない。岡崎は「起き上がって聞いたらどうだ。これまでお母さんが君と幸作君を区別したことがあったか。お母さんは君たち二人の成長だけを楽しみにしておられるのだ。その優しい心遣いを君はまるでわからないのか」。貞夫の肩が激しく揺れている。岡崎は貞夫に近づきその肩を優しく叩いた。気持ちが通じたか・・・、貞夫は起き上がり、涙を拭いながら「すみません! 小父さん」と呟いた。そして千恵子の前に正座して深々と頭を下げる。「すみません、母さん。ボクは母さんの本当の子です」。千恵子と見つめ合い涙がこぼれ出すのを見て、貞夫は母の膝に泣き崩れた。千恵子は「これからは何もかもお前に打ち明けようね」と言い、貞夫の頭を優しく撫で回す・・・。
やがて、梶原家はさらに郊外の借家に転居した。貞夫と幸作(三井秀雄)はトラックから荷物を降ろし整理する。懐かしい父の遺品のパイプを見つけ出し、兄弟で煙をふかす。ハットを目にすると、母に被せて父を思い出している。そこに岡崎の夫人(青木しのぶ)が訪ねて来た。岡崎は一年前に他界、遺品のオールを届けに来たのだ。兄弟は、サインを読み取りながら、父や岡崎の青春時代に思いを馳せる。兄弟もまた大学のボート部員になっていた。
幸作は仲間と伊豆巡りの計画を立てていた。兄も誘ったが用事があると言う。服部(笠智衆)という部員に好きな女ができ、横浜のチャブ屋に入り浸っている、貞夫は服部を連れ戻しに行こうとしているのだ。単身でチャブ屋に乗り込むと、服部にピンタをかませ、外に連れ出した。服部の女・らん子(松井潤子)が「勘定ぐらい置いて行ってもらいたいねえ。お前さんおけらのくせに、たいそう強がるじゃないか。」と毒づけば、またもやピンタ一発、「ああ、金なら何時でも持ってきてやらあ」と言い残し去って行く。その後ろ姿を見て、朋輩の光子(逢初夢子)が「あいつ、ちょっと勇ましいじゃないか」と目を細めた・・・。
貞夫は帰宅すると、縫い物をしている千恵子に「困っている友だちが居るんで、少しお金が欲しいんですけど」と無心した。千恵子はすぐに頷いて、箪笥から財布を取り出し紙幣を渡す。貞夫はそれをありがたく頂いて、自室に向かったのだが、そこには幸作がしょんぼりと座っていた。家の暮らしは楽ではない、「だから伊豆巡りに行ってはいけない」と言われた由、貞夫は直ちに千恵子のところに戻り、「このお金を幸作に与えて、行かせてやってください」と言ったが「幸作は遊びのお金、あなたのお金は友だちのへ義理、同じではありません」と取り合わない。やむなく、貞夫は幸作に金を渡し、旅行の準備を手伝う。様子を見に来た千恵子に「母さん、やっぱり出かけてきます」と幸作は喜んだが、「お前、兄さんに無理を言ってはいけないよ」と不同意、貞夫は「ボクがあげたんです。
幸作は前から楽しみにしていたんです。ボクだけが貰うのは不公平です」・・・、幸作は「だいたい母さんは兄さんばかりよくする。叱られるのはボクばかりだ」と帽子を放り投げてふてくされる。貞夫も「ボクもそう思います」と同意、千恵子はしばらく立ち尽くしていたが「そんなに行きたければ、出かけてもかまわないんだよ」と翻意した。
かくて、幸作は伊豆巡りに出立、そろそろ帰る日の頃であろうか、千恵子は夫の遺品、洋服を虫干ししている様子。懐中時計を耳に当て、遺影を眺めている。そこに貞夫も帰宅して父のハットを被ってみたりする。千恵子は父のチョッキをたたみながら「幸作が山に行くんだったら、これを持たせてやればよかった」「そんな古い物、幸作は来ませんよ」「まだ繕えば着られる洋服があります。幸作ならこれで十分・・・」と言うと、貞夫の顔色が変わった。「どうして幸作なら十分なんですか?」「・・・・」「母さんは、やっぱりボクと幸作を区別してるんだ」「そんなつもりはないけれど・・・」。貞夫はキッとして、自室に立ち去り、着物に着替えて外出の構え、千恵子がやって来て「どうすれば、お前の気に入るのか話しておくれ」「そういう気遣いがイヤなんです、気に入らなければボクを殴ればいいでしょう」「何もそんなに言わなくても・・・」。取り合わず、貞夫は横浜のチャブ屋に向かった。光子の部屋に落ち着く。掃除婦(飯田蝶子)が雑巾がけをしている。貞夫に母の姿が浮かんだか、ウィスキーをたてつづけに飲んで、じっと(ささくれの)手を見た。光子が「お前さん、親不孝者だね」「・・・・」「ささくれがあるのは、親不孝の証し」と言う。光子の指にも包帯があった。貞夫はたまらずそこを飛び出して家に向かう。その様子を呆然と見送る掃除婦、光子も「わからないね、その気持ち」と呟いた。
貞夫が家に戻ると、幸作が帰宅していた。険しい顔つきで「帰ってきたんだたら、母さんに謝ったらどうだい。兄さん、母さんに何を言ったんだい。母さんを泣かせるなんて馬鹿だ、大馬鹿だ!」と言う。「年をとって涙もろくなったんだろう」と応えると、幸作はたまらず殴りかかった。貞夫は殴られるまま「外に出ろ!」と言う。夜道を歩く二人・・・、向かい合うと貞夫が言う「あんなおふくろのどこがいいんだ」「それは本心か」「嘘ではない、あんなおふくろのことでムキになる気持ちがわからない」、幸作はまたも貞夫に殴りかかる。一発、二発、三発、四発、五発・・・、しかし貞夫は殴り返さない。幸作は手を止め泣き出した。「なんで殴り返さないんだ!」「おまえのような奴を殴ったって仕方がない」「・・・・」「(おふくろを)せいぜい大事にしてやれよ」と言い残すと、どこかに行ってしまった。幸作は力なく家に戻る。千恵子に「あんな奴どうなったってかまわない。散々ボクや母さんの悪口を言って、どこかへ行っちまいやがった」と言う。「お前、兄さんをそんな人だとお思いかい」「母さんはまた兄さんの肩を持つのか」「私には、貞夫の気持ちがよくわかります」「・・・・」「あの子は立派なことをしようとしたんだよ」「・・・・」「兄さんはね、私の本当の子ではなかったんだよ」「・・・!」「それをお前に知らせたくなくて、お前の大学の手続きはみんな兄さんがやってくれたんだ」「・・・・」「兄さんは、お前のためにこの家から身を引こうとして・・・」と言うなり、千恵子は泣き出した。「心にもない悪口を言って、私たちを諦めさせようとしたんだよ」。幸作は千恵子の前にひざまづき「ボクは馬鹿でした。どんなことがあっても兄さんに戻って来てもらう、そして思う存分殴ってもらうんだ」と泣き崩れる。母もまた・・・・。
貞夫は横浜のチャブ屋に居た。「また今日も暮れちゃうんだなあ」と貞夫が溜息を吐くと、光子が「帰りたけりゃお帰りよ」と言う。そんなところに、母の千恵子と幸作、彼の友人が迎えに来た。まずは千恵子が一人でチャブ屋に赴き、ロビーで貞夫と面会する。「ボクに何の用ですか。ボクは母さんに用はありません」「そんな心にもないことを言って・・・。母さんは小さい頃からお前のことはよく知っています」「知っているんなら放っておいてください。ボクは一人が性に合っているんだ」「お願いだから戻っておくれ。お前がいないと夜もおちおち眠れない。幸作やお友達だって、待っているんだよ」。しかし、貞夫は応じない。「ボクは、家に戻って母さんや幸作の面倒を見るなんてまっぴらだ!」。いつのまにか、チャブ屋の女たちが二人を取り巻いている。「ボクはもう母さんから何も聞きたくないんです。これ以上何を言っても無駄ですよ」と言い放ち、部屋に立ち去ってしまった。万事休す、千恵子はすごすごと戻っていく。その後に従う幸作と友人・・・、その姿を二階の窓から見送る貞夫・・・、光子が入ってきて「お前さん、大芝居だったね。よっぽど大向こうから声かけようと思ったんだけど」と感想を述べる。貞夫は全身の力が脱けてベットに横たわる。光子は朋輩に「おなかが空かない」と言われ出て行く。入れ替わりにに掃除婦が入ってきて部屋を片付け始める。その様子を見ていた貞夫は起き上がり、掃除婦にタバコを勧める。掃除婦は一本頂戴、煙を吐きながら言う。「悪いことは言いませんよ。木の股から生まれたんじゃあるまいし、あんまり親は泣かせるもんじゃありませんよ」「・・・」「あたしにも丁度、あんたぐらいの息子があるんですけれど」・・・・、貞夫が「オレよりましだって言うのかい?」と問いかけると、掃除婦は淋しそうに笑って「よけりゃ、こんなことしてませんよ」と出て行った。貞夫はまたベッドに横たわる。サンドイッチを調達した光子が部屋に戻る。貞夫にも勧めるが、天井を眺めたまま無言。光子はサンドイッチをぱくついて貞夫の方を見やった時、この不完全バージョンの映像は途切れた。以後の字幕では、貞夫は掃除婦の言葉に心を動かされ、家に戻り、母に謝罪する、それから三年後、一家は再び郊外に転居、母子三人の平穏な暮らしは続いていると記されている。
この映画の見どころは、裕福な暮らしをしていた梶原家が大黒柱の父を失うことにより没落していく中で、母と息子二人(異母兄弟)が繰り広げる「人間模様」の《綾》である。母は、二人の息子を同じように育てているつもりだが、無意識に、亡夫への義理のため先妻の子・貞夫の方を重んじる。幸作に比べると、どこか他人行儀でよそよそしい。貞夫は当初、母に甘え我が儘な振る舞いをしていたが、千恵子が実の母ではないと知ってからは、いわば「母なし子」状態、甘える相手を失ってしまったのだ。「ボクは一人が性に合っているんだ」という貞夫の言葉が何よりも雄弁にそのことを物語っている。その立場に置かれなければわからない、絶対的な《孤独感》なのである。しかし、掃除婦の「木の股から生まれたんじゃなし、あんまり親を泣かせるもんじゃないよ」という一言は、そんな孤独感を払拭するには十分であった。掃除婦にも自分と同じくらい息子が居る。貞夫は「オレよりはマシだろ?」と問いかけるが、答は意外にも「よけりゃ、こんなことしてませんよ」。そうか、その息子も親を泣かせているんだ、オレもこんな所(チャブ屋)で、こんなこと(無為に日々を過ごすこと)をしているときではない、と思ったに違いない。そんな心の《綾模様》を、二枚目スター・大日向伝は鮮やかに描き出していたと、私は思う。
母・千恵子を演じた吉川満子の風情もたまらなく魅力的、誰よりも夫を愛し、子どもたちを慈しむ。時には背かれて雑言を浴びせかけられ涙ぐむこともあるが、毅然として耐え、誠を貫こうとする「母性」の気高さがひしひしと伝わってくるのである。
弟・幸作を演じた三井秀雄の「弟振り」も見事であった。とりわけ、兄が母の本当の子ではないと知らされた時の表情、そこには「なぜもっと早く知らせてくれなかったんだ」という思い(母への恨み)は微塵も感じられず、「ボクが間違っていました」と母に謝る純情が浮き彫りされている。その兄を、わけも知らずに殴ってしまった後悔、その償いのために「ボクを殴ってもらうんだ」と思う素直さが輝いていた。
極め付きは、掃除婦を演じた飯田蝶子の存在感、出番はほんのちょい役だが、たった一言、二言のセリフで主役・貞夫を翻意させる実力は光っている。彼女は、不器量のため女優への道はなかなか開けなかったが、私のような者がいなければ主役は引き立たないと、自分を売り込んだという。さすがは、終始「老け役」を貫いた名優の至言である。
その他にも、奈良真養の庶民的な風格、笠智衆の意外な若さ、逢初夢子の色香などなど見どころ満載の傑作であった。
(2017.7.1)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-07
付録・邦画傑作選・「生さぬ仲」(監督・成瀬巳喜男・1932年)
ユーチューブで映画「生さぬ仲」(監督・成瀬巳喜男・1932年)を観た。原作は大正時代に連載された柳川春葉の新聞小説で、ウィキペディア百科事典ではそのあらすじが以下のように紹介されている。
東洋漁業会社社長、渥美俊策の一子、滋子をめぐって生母、珠江と、生さぬ仲の継母、真砂子との葛藤をえがく。
【成瀬版映画あらすじ】
ハリウッドで女優をしている珠江は、前夫である俊策のもとに残してきた娘・滋子を取り戻すため、日本に一時帰国する。6歳になる滋子は後妻の真砂子を本当の母と思って育っている。俊策は事業の失敗から刑務所に収監され、家屋敷を失った真砂子と滋子は俊策の母・岸代とともに侘び家で暮らし始める。貧乏暮らしを嫌う岸代は、珠江に協力して、真砂子に内緒で滋子を連れだしてしまう。悲しむ真砂子は、俊策の友人・日下部に協力を求めて滋子の行方を捜す。珠江は一生懸命滋子の機嫌をとるが、滋子は継母・真砂子を慕い、家へ帰りたいと泣き暮らす。行方を突き止めた真砂子は珠江の家を訪ねるが、滋子とは引き離されてしまう。日下部は珠江に、本当の母とは何かを説く。泣き叫ぶ滋子を見て、ついに珠江は滋子を真砂子の元に戻し、アメリカで作った財産を真砂子に譲り、アメリカに帰っていく。
成瀬監督は女性映画の名手と言われている。なるほど、この映画に登場する4人の女性、渥美絹子・改め清岡珠江(岡田嘉子)、渥美真砂子(筑波雪子)、岸代(葛城文子)、滋子(小島寿子)の「葛藤」は真に迫っていた。夫・渥美俊策(奈良真養)と生まれたばかりの滋子を捨て渡米、ハリウッド女優になった珠江は、人気と財力にまかせて滋子を取り戻そうとする。岸代は根っからの貧乏嫌い、会社を倒産させてしまった俊策を責め立てる。真砂子は渥美家の後妻だが、継子の滋子を慈母の風情で育んでいる。滋子は真砂子を「本当のお母さん」と慕い、実母の珠江を拒絶する。4人が4人とも「自己」を主張し、対立・葛藤が激化する有様が、見事に描出されていた。
一方、男性は5人登場する。漁業会社社長の渥美俊策、その友人で貧乏浪人の日下部正也(岡譲二)、珠江の弟でヤクザの巻野慶次(結城一朗)、その弟分、ペリカンの源(阿部正三郎)、滋子の遊び友達(突貫小僧)である。
女性陣に比べて、男性陣は迫力がない。いずれもが、結局は女性に追従する。当時の風潮は表向きは「男尊女卑」だが、内実は「女権社会」そのもので、男性相互の対立・葛藤はほとんど際立たない、といった演出がたいそう面白かった。つねに事を起こすのは女性であり、男性はそのまわりをウロウロするか後始末に奔走するのである。わずかに、日下部が「生むだけでは母の資格はない。育てて始めて母になれるのだ」と珠江に迫るが、彼女を翻意させたのは、実子・滋子の真砂子への慕情に他ならなかった。珠江の財力によって渥美一家が救われるというハッピーエンドも「女性優位」の証しである。
最も興味深かった場面、会社が倒産寸前、藁をも掴む思いの俊策に融資を申し出たのは珠江、二人は対面するが、俊策の表情はたちまち強ばり、「夫と子どもを捨てた女に助けて貰う気はさらさらない」と言って断固拒絶、自ら収監される道を選ぶ。一方、俊策の母・岸代もペリカンの源に誘われて珠江と対面、俊策とは打って変わってニッコリ・・・、「立派になられておめでとう」と祝福する。そこから事は始まるのだが、珠江に対する(俊策と岸代の)態度の違い(コントラスト)、女性同士の絆が織りなす人間模様、その周囲で翻弄される男性相互のアタフタ沙汰の描出がこの映画の眼目であろう。加えて、わずか6歳の滋子も行動的である。珠江とのかかわりを断固拒否、岸代に真砂子の元に戻りたい懇願する。叶わないと思えば、周囲の目を盗み、敢然と(分身の「青い目の人形」を携えて)脱走する。結果は失敗に終わり人形も失われたが、滋子の思いは変わらない。
そうした女性の強さ、たくましさ、したたかさが随所に散りばめられている。まさに、女性映画の名手・成瀬巳喜男監督ならではの作物であった。大詰め、米国に帰る珠江、随行を許されて大喜びの巻野と源は大型客船のデッキの上、それを見送る渥美一家と日下部たち、俊策も珠江の姿を見つけて懸命に手を振った。しかし、珠江はそれに応えることなく独り、船室に姿を消す。その心象風景(「生みの親より育ての親」)も鮮やかに、この映画の幕は下りたのである。
(2017.2.19)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

東洋漁業会社社長、渥美俊策の一子、滋子をめぐって生母、珠江と、生さぬ仲の継母、真砂子との葛藤をえがく。
【成瀬版映画あらすじ】
ハリウッドで女優をしている珠江は、前夫である俊策のもとに残してきた娘・滋子を取り戻すため、日本に一時帰国する。6歳になる滋子は後妻の真砂子を本当の母と思って育っている。俊策は事業の失敗から刑務所に収監され、家屋敷を失った真砂子と滋子は俊策の母・岸代とともに侘び家で暮らし始める。貧乏暮らしを嫌う岸代は、珠江に協力して、真砂子に内緒で滋子を連れだしてしまう。悲しむ真砂子は、俊策の友人・日下部に協力を求めて滋子の行方を捜す。珠江は一生懸命滋子の機嫌をとるが、滋子は継母・真砂子を慕い、家へ帰りたいと泣き暮らす。行方を突き止めた真砂子は珠江の家を訪ねるが、滋子とは引き離されてしまう。日下部は珠江に、本当の母とは何かを説く。泣き叫ぶ滋子を見て、ついに珠江は滋子を真砂子の元に戻し、アメリカで作った財産を真砂子に譲り、アメリカに帰っていく。
成瀬監督は女性映画の名手と言われている。なるほど、この映画に登場する4人の女性、渥美絹子・改め清岡珠江(岡田嘉子)、渥美真砂子(筑波雪子)、岸代(葛城文子)、滋子(小島寿子)の「葛藤」は真に迫っていた。夫・渥美俊策(奈良真養)と生まれたばかりの滋子を捨て渡米、ハリウッド女優になった珠江は、人気と財力にまかせて滋子を取り戻そうとする。岸代は根っからの貧乏嫌い、会社を倒産させてしまった俊策を責め立てる。真砂子は渥美家の後妻だが、継子の滋子を慈母の風情で育んでいる。滋子は真砂子を「本当のお母さん」と慕い、実母の珠江を拒絶する。4人が4人とも「自己」を主張し、対立・葛藤が激化する有様が、見事に描出されていた。
一方、男性は5人登場する。漁業会社社長の渥美俊策、その友人で貧乏浪人の日下部正也(岡譲二)、珠江の弟でヤクザの巻野慶次(結城一朗)、その弟分、ペリカンの源(阿部正三郎)、滋子の遊び友達(突貫小僧)である。
女性陣に比べて、男性陣は迫力がない。いずれもが、結局は女性に追従する。当時の風潮は表向きは「男尊女卑」だが、内実は「女権社会」そのもので、男性相互の対立・葛藤はほとんど際立たない、といった演出がたいそう面白かった。つねに事を起こすのは女性であり、男性はそのまわりをウロウロするか後始末に奔走するのである。わずかに、日下部が「生むだけでは母の資格はない。育てて始めて母になれるのだ」と珠江に迫るが、彼女を翻意させたのは、実子・滋子の真砂子への慕情に他ならなかった。珠江の財力によって渥美一家が救われるというハッピーエンドも「女性優位」の証しである。
最も興味深かった場面、会社が倒産寸前、藁をも掴む思いの俊策に融資を申し出たのは珠江、二人は対面するが、俊策の表情はたちまち強ばり、「夫と子どもを捨てた女に助けて貰う気はさらさらない」と言って断固拒絶、自ら収監される道を選ぶ。一方、俊策の母・岸代もペリカンの源に誘われて珠江と対面、俊策とは打って変わってニッコリ・・・、「立派になられておめでとう」と祝福する。そこから事は始まるのだが、珠江に対する(俊策と岸代の)態度の違い(コントラスト)、女性同士の絆が織りなす人間模様、その周囲で翻弄される男性相互のアタフタ沙汰の描出がこの映画の眼目であろう。加えて、わずか6歳の滋子も行動的である。珠江とのかかわりを断固拒否、岸代に真砂子の元に戻りたい懇願する。叶わないと思えば、周囲の目を盗み、敢然と(分身の「青い目の人形」を携えて)脱走する。結果は失敗に終わり人形も失われたが、滋子の思いは変わらない。
そうした女性の強さ、たくましさ、したたかさが随所に散りばめられている。まさに、女性映画の名手・成瀬巳喜男監督ならではの作物であった。大詰め、米国に帰る珠江、随行を許されて大喜びの巻野と源は大型客船のデッキの上、それを見送る渥美一家と日下部たち、俊策も珠江の姿を見つけて懸命に手を振った。しかし、珠江はそれに応えることなく独り、船室に姿を消す。その心象風景(「生みの親より育ての親」)も鮮やかに、この映画の幕は下りたのである。
(2017.2.19)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-05
付録・映画「虹立つ丘」の《市松人形》
ユーチューブで映画「虹立つ丘」(監督・大谷俊夫・1938年)を観た。舞台は竣工まもない箱根強羅ホテル、そこで働く兄妹の物語である。兄・弥太八(岸井明)はホテルのポーター、妹・ユリ(高峰秀子)は売店の売り子を勤めており、たいそう仲が良い。そこに療養にやってきた長谷川婦人(村瀬幸子)が、実は関東大震災で生き別れになったユリの母であった、という筋書きで、兄妹にとっては切ない幕切れとなったが、時折、兄が口ずさむ唱歌(「旅愁」「峠の我が家」)、妹・高峰秀子の初々しい絵姿(14歳?)も見られて、戦前(昭和13年)の風俗を感じるには恰好の作物であった。なかでも、箱根強羅ホテルの佇まいは、現代のホテルと大差ない。鉄筋コンクリート4階建て、大きな玄関を入ると広いロビー、売店に並んだ土産物、対面にはエレベーターという配置は、今でもお馴染みの風景だ。登山鉄道、周囲の山々、芦ノ湖の風情には「隔世の感」があるだけに、ホテルのモダンさが際立つのである。なるほど、全国に展開する温泉ホテルの原型はここにあったのか。また、その利用客は当時のセレブ層であることは確か、庶民は簡素な湯治宿に甘んじる他はなかっただろう。だとすれば、現代に生きる私たちは往時のセレブ層に等しい歓楽を味わっていることになる。幸せと言うべきか・・・。たしかに、私たちの生活は豊かになり、便利になったが、そのことによって失われたものもある。
震災で孤児となったユリを兄として育ててきた弥田八、親との絆を求めて今でも大切に市松人形を飾るユリ、父母との邂逅そして兄との別れ、妹が残していった市松人形をしっかりと抱きしめる弥田八、そうした人物・場面に浮き彫りされる「無言の温もり」は、私たちの財産であった。薄汚れた、質素な市松人形こそが「人間の絆」であり、何よりも大切にされなければならない、と私は思う。(2017.1.6)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

震災で孤児となったユリを兄として育ててきた弥田八、親との絆を求めて今でも大切に市松人形を飾るユリ、父母との邂逅そして兄との別れ、妹が残していった市松人形をしっかりと抱きしめる弥田八、そうした人物・場面に浮き彫りされる「無言の温もり」は、私たちの財産であった。薄汚れた、質素な市松人形こそが「人間の絆」であり、何よりも大切にされなければならない、と私は思う。(2017.1.6)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-04
付録・邦画傑作選・「君と行く路」(監督・成瀬巳喜男・1936年)
ユーチューブで映画「君と行く路」(監督・成瀬巳喜男・1936年)を観た。タイトルに「三宅由岐子作『春愁紀』より」とある。舞台は神奈川・鎌倉海岸の別荘地、ある別荘に母・加代(清川玉枝)とその息子、長男の天沼朝次(大川平八郎)、次男の天沼夕次(佐伯秀男)が住んでいた。母は芸者上がりのシングル・マザー、亡くなった旦那から別荘と財産を貰い受け、女手一つで二人の子どもを育て上げた。兄の朝次はすでに会社勤め、弟の夕次はまだ大学生である。この家の隣は、尾上家の別荘、そこには娘の霞(山縣直代)が居た。朝次と霞は、相思相愛の仲である。夕次はテニス部員で、夕食後も海岸をランニング、その時、叔父の空木(藤原釜足)から声をかけられた。「夕次、今晩、朝次と一緒に遊びに来んか」「ええ。行きます」と答えて帰宅する。空木は、周囲から「殿様」と呼ばれている。雛(高尾光子)という妾を連れて近くの別荘に来ているらしい。尾上家とも縁続きのようである。夕次がランニングから帰宅しても、朝次はまだ帰らない。母が「夕飯はどうするんだろう」と案じるが、夕次は「もう食べただろう」と言う。「会社って、いつも7時までやっているのかしら」。朝次は会社の上司、同僚と宴会の席に居た。しかし、なぜかはしゃげない。上司に「おい天沼、どうした?」と声をかけられる。それを聞いた女将が、「天沼長二郎さんの?」「ええ、ボクの親爺です」「じゃあ、やっぱり。加代次(母の源氏名)さんの息子さんだったのね。ずいぶん大きくなったわねえ」。芸子が「あたし、加代次姐さんの昔の写真見たわよ」「あなたのおっ母さん、大変な人気だったのよ。清元が達者で・・・」。女将と母が同輩だったと知らされると、朝次の気持ちはますます重くなる。
それと言うのも、恋仲の霞に縁談話があるからだ。尾上家は最近凋落気味、その危機を救うため、霞を北海道の資産家に嫁がせようとしている。相手は大金持ちだが老人である。でも霞は朝次の他は眼中にない。それを言っても、気位の高い尾上家では「あんな妾の子とは一緒にさせられない」と、まるで相手にしないのだ。だから、朝次は霞との結婚を諦めていた。自分の方から絶交を申し出るが、霞は応じない。朝次に会いたいと別荘にやって来たが、監視の目が厳しくて外に出られない。そんな時、友だちの呉津紀子(堤真佐子)が東京から追いかけて来た。その電車の中で、たまたま夕次が、ひときわ目立つ津紀子の洋装姿を目にするが、たちまち一目惚れ、「結婚するならあの人だ」と朝次に告白する。津紀子は、(朝次から霞宛ての)手紙を届けに来たのだが、監禁状態の霞を見て手引きをする。久しぶりに出会った霞と朝次は、夜の海岸を散歩する。「ねえ、霞ちゃん、こんなこといつまで続くと思う?」「朝ちゃんが続かせなければ続けられりゃしないわ」「霞ちゃんだって、続けられる?」「あたしは死ぬまで続けるわ」「そんなことできるもんか、お嫁にいってしまえば」「行かないったら、やな人ねえ」・・・。「ボクには自信がなくなってしまったんだ」「どうして」「ボクは妾の子なんだ」「また、そんなこと。あたしのお母さんだって酌婦だったわ」「でも、正式な奥様になってるじゃないか」「そんなことどうだっていいじゃないの」「違うよ、形式というのはとっても大切なものなんだよ」「でも、あなたのお母さん、とてもいい人よ。うちのお母さんとは比べものにならないくらい」・・・。「霞ちゃん、ボク、アメリカに行けるかもしれない」「いつ?」「君が結婚する前に」「行かないったら、わからない人ねえ」「そんなこと言ったって、家には代えられないだろう」「子どもより家を大切にする親なんてこっちも考えないわ」・・・「それより本当にアメリカに行くの?(結婚できなければ情死する約束)忘れちゃったの?」「忘れやしない、ただボクは死ぬのなら独りで死ぬんだ。誰にも知られないところで」「あたしは?」「君は死ぬ必要はない。ボクは世の中がイヤになったんだ」「・・・じゃあいいわ、あたしも独りで死ぬから」「君には呉さんといういいお友達があるじゃないか」「だから、だからできるだけ生きていたいんじゃないの。それを朝ちゃんはひとりで勝手に・・・」と、霞は泣き崩れる。朝次は「じゃあ、できるだけ二人で努力しよう!、もしそれでダメだったら・・・」、霞は静かに頷いた。
この二人の対話は、まさに「君と行く(末)路」を暗示しているようだ。
尾上家の別荘に、霞の相手が訪れる結納の日、空木が尾上家の執事を連れてやって来た。執事は朝次から霞に宛てた手紙の束を差し出して言う。「これをお返しするように言いつかって参りました。霞様の手紙がありましたらお返しください」。朝次はその手紙を受け取り、引き出しの中から霞の手紙を取りだした。「これで私が言い掛かりをつけると思っているのですか。この手紙はお返しできません」と言うなり、破り捨て暖炉の火に投げ込んだ。執事は驚いたが、ともかくも安堵、「つきましては、朝次様、洋行の足しにでも」と言い、壱千円の小切手を手渡す。朝次は直ぐさまそれも破り捨て、「妾の子だと思って、私のことまで芸者扱いするのか!」と、空木、執事を追い返し、独り浜辺に向かう。
その日、津紀子も「虫の知らせ」で霞を救いに訪れた。玄関払いをさせられようとしたが、霞が飛び出して来て自室に招き入れる。あわててメモを記し、朝次のもとに届けてほしいと依頼する。朝次は独り浜辺で悔しさに耐えている。そこに夕次がやって来た。「こんな所で何してるんだい、この前の人が霞ちゃんの手紙を持ってきてくれたよ」と言う。夕次は、電車の中で見初めた意中の人が、霞の親友・呉津紀子だったことが判り、喜んだ。 三人で家に戻り、朝次は手紙を呼む。そして、「津紀子さん、弟の夕次をどう思いますか。お付き合いしていただければ・・・。」津紀子も嬉しそうに同意した。「霞さんには、すぐに返事をします。ボクの行動を見てその様子を知らせてあげてください。その前に、ちょっと出かけてきます」と、夕次と津紀子を残して出て行く。入れ替わりに母がやって来た。)朝次が「夕次のお嫁さんが来ているよ」と言ったので御挨拶に伺いました。(玄関先で自動車が発進するエンジンの音が聞こえた)「まあ、すてきなお洋服だこと!」と津紀子の姿に目を細める。一目で気に入った様子だったのだが・・・。
突然、電話が鳴り響き、朝次の自動車事故を知らせる。独り、崖道を激走して転落したのである。
数日後、霞の姿が見えなくなった。家の者の目を盗んで津紀子の家を訪れる。お別れに来たと言う。「もう、二、三日後ね(嫁ぐ日は)」と津紀子が言う。「この間の手紙渡してくださった?」「ありがと」「霞ちゃん、朝次さんのこと何にも聞かない?」「・・・・」「きっと、誰も言やしないわねえ・・・」。津紀子は霞に朝次の死を告げる。霞は呆然としたが、「誰も言わないんだもの」と座り込む。「明日が埋骨式よ」「津紀子さん、あたしも連れてってくれない?」と懇願したが、津紀子は首を横に振る。「もう、仕方がないじゃないの」。霞は「朝ちゃん!」と叫んで泣き崩れたが、「行く路」を決意したのだろう。
天野の別荘では、朝次の骨箱を夕次が運んでいる。「母が仏壇の前に置いておくもの」と言うのも聞かず、隣の霞に部屋の窓が見える場所に安置する。式に出るのは、母、夕次、空木、雛、津紀子の5人と数えていると、雛が訪れた。御前様の来るのが遅れる、昨日から霞が行方不明で、今探しているところだと言う。夕次が「津紀子さんの所じゃないか」と言っているところに、津紀子も供花を持ってやって来た。どこか元気がない。供花を力なく骨箱の上に乗せる。夕次が「霞ちゃんがねえ・・・」と言いかけると、昨日の経緯を告げた。「あたし、霞ちゃんはもう亡くなっていると思う」「そんなことはないよ、どこかで働き口でも探しているんだろう」「そうだといいんだけど」。夕次は津紀子との縁談話を確かめようとするが、津紀子は意外にも「否」、自分たちもまた死ななければならなくなる、と言う。夕次はその意味を必死で訊ねるが、「もっと、あたしたち強くなってから、またお会いしましょう」と答えるだけであった。・・・、津紀子の予感は当たった。空木が沈痛な表情で到着する。「霞ちゃんは?」「居たよ」「どこに?」「家の裏の池の中に、浮かんでいたんだ」。まあ、と聞いた一同は涙を拭う。しばらくして、雛が言う。「でも、霞さんは朝次さんの所に行って、お幸せにお暮らしになるんでしょう。朝次さんはきっと喜んでいると思いますわ」。その言葉を聞いて、津紀子は夕次のもとへ行き「夕次さん、さようなら、ごきげんよう」と言い立ち去った。夕次は椅子に座り込んで嗚咽する。その様子を訝しがる母、「いったいどうしたんだねえ、あの人は。変な子だねえ津紀子さんていう人は。霞ちゃんはね、親の言うことを聞かないからこんなことになってしまった。親の言うことを聞いていればいい奥さんになれたのに。お前だって、ごらんな、出世ができるのにこんなにグズグズしてさ・・・」。そう言われた夕次は、たまらず立ち上がり「バカ! お母さんのバカ!」と叫ぶ。その勢いに、母は目を丸くして呆気にとられる。別荘の外では、何かをこらえ、足早に浜辺を立ち去る津紀子の姿を映すうちに、この映画は「終」となった。
女性映画の名手と謳われた成瀬巳喜男の作品としては、あまり評価は高くないようだが、私にとってはまさに傑作、他に比べて優るとも劣らない出来映えであった。筋書きは「天国に結ぶ恋」もどきの悲恋物語にも見えるが、実は登場する4人の「女模様」がくっきりと浮き彫りされて、そのコントラストがたいそう興味深いのである。
その一人は、加代という女性、朝次、夕次の母である。名士・天沼長二郎の愛妾として、豪華な鎌倉の別荘を譲り受け、さらに膨大な手切れ金(息子たちの養育費)も頂戴、お春という女中まで置いている。にもかかわらず、その金を「わずかばかりの端金」と言って憚らない。世の中はすべて金、義理も人情も「どこ吹く風」、霞の死を、今、泣き悔やんでいたかと思えば、「霞ちゃんはね、親の言うことを聞かないからこんなことになってしまった。親の言うことを聞いていればいい奥さんになれたのに」などと、哀悼の意を忘れ去る。たまらず、夕次が「お母さんのバカ」と叫んでも、その気持ちがわからない。空木を「御前様」と奉る一方、陰では「いい年をしてみっともない」と見下げる。夕次の縁談話でも、相手の娘を「器量はよくないけど女学校出だとさ」と評価する。レター・ペーパーをラブレター、デスクをデクスと言い間違えても気づかない。その極め付きは、「自分が芸者であったこと」に全く頓着しないことである。夕次が「ボクが好きになった人なら、その家が魚屋であっても材木屋であってもかまわない」と言えば「カフェの女給なんか困るよ」と言い、朝次から「芸者より女給の方がマシだ」と言われ「まあ、この子ったら」と涙ぐむ。しかし、いつまでもクヨクヨしないのが彼女の真骨頂だ。そもそも、朝次の死、霞の後追い自殺は、加代が芸者上がりであったことに因る、そして夕次が津紀子に振られたのも同じ理由に因る。つまり自分が蒔いた種だったということに気がつかない。いわば「無知の逞しさ」とでも言おうか、かつては、「どこにでも居そう」な女性の生き様を、女優・清川玉枝は見事に演じきったと、私は思う・
その二人目は、霞の風情、見るからに楚々として初々しい。語り口もたどたどしいが、その内容は正鵠を射ている。朝次との密会中、「ねえ、霞ちゃん、こんなこといつまで続くと思う?」と問われて「朝ちゃんが続かせなければ続けられりゃしないわ」と毅然と答え「霞ちゃんだって、続けられる?」「あたしは死ぬまで続けるわ」「そんなことできるもんか、お嫁にいってしまえば」「行かないったら、やな人ねえ」という対話の中には、明確な意志・覚悟がある。さらに、「それより本当にアメリカに行くの?(結婚が叶わなければ情死という約束)忘れちゃったの?」「忘れやしない、ただボクは死ぬのなら独りで死ぬんだ。誰にも知られないところで」「あたしは?」「君は死ぬ必要はない。ボクは世の中がイヤになったんだ」「・・・じゃあいいわ、あたしも独りで死ぬから」というやりとりの中にも、確固とした決意が窺われる。たしかに朝次は「独りで」死んだ。しかし、それは世間の「形式」(格式・義理)に対する敗北であり、弱者の死である。比べて。霞の自死は、男に対する誠を貫くと同時に、世間の「形式」に対する挑戦なのだ。さればこそ、父・尾上の「落胆」は激しく、心底からの後悔と反省をもたらすことができたのである。いわば、強者の死であり、さらに「美しさ」も添えられている。「み袖のままで浮かんでいた。美しい姿だった」という空木の言葉が、何よりも雄弁にそのことを物語っている。そんな芯の強い、一本筋の入った女性の姿を、女優・山縣直代は健気に描出しているのである。
その三人目は呉津紀子、モガのスタイルで明るく行動的、彼女に頼めばどんな夢でも叶いそうな存在感がある。事実、彼女の手引きによって霞と朝次の「逢瀬」は実現、二人の絆をよりいっそう強めることができたのだが、悲劇的な結末を前にして動揺する。とりわけ、夕次との交際が「同じことの繰り返し」になるだろうと予感、「私たちもっと強くなりましょう」「必ず、なってみせるわ」と断言、(霞と同様)毅然と訣別する姿は、理知的で冷静である。加代は「変な子だねえ」と訝るが、自分自身がが世間の「形式」からは、変な存在だと思われていることに気づかない。そのコントラストがたいそう可笑しい。
その四人目は、空木の愛妾・雛である。年の離れた爺さんを旦那にもち、「遺産を狙っているに違いない」と加代からはさげすまれているが、一向にお構いなく、「お酒が飲みたい、隣で調達してきて」と空木を使い走りさせる。「家でゆっくり飲むわ」とちゃっかり、ボトル一本をゲットする様子は可笑しく、遊び人で「いい男」の空木が可愛がるのも肯ける。霞の死を知って「霞さんは朝次さんの所に行って、お幸せにお暮らしになるんでしょう。朝次さんはきっと喜んでいると思いますわ」と泣き崩れる姿も月並みだが、それが津紀子の「毅然とした訣別」を導いたことは、確かである。「私は違う!。私は《死んで楽しい天国であなたの妻になりますわ》などということは信じない!」と思ったに違いない。
以上が、女性映画の名手・成瀬巳喜男監督が描き出した「女模様」の実像ではないだろうか。
(2017.6.24)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

それと言うのも、恋仲の霞に縁談話があるからだ。尾上家は最近凋落気味、その危機を救うため、霞を北海道の資産家に嫁がせようとしている。相手は大金持ちだが老人である。でも霞は朝次の他は眼中にない。それを言っても、気位の高い尾上家では「あんな妾の子とは一緒にさせられない」と、まるで相手にしないのだ。だから、朝次は霞との結婚を諦めていた。自分の方から絶交を申し出るが、霞は応じない。朝次に会いたいと別荘にやって来たが、監視の目が厳しくて外に出られない。そんな時、友だちの呉津紀子(堤真佐子)が東京から追いかけて来た。その電車の中で、たまたま夕次が、ひときわ目立つ津紀子の洋装姿を目にするが、たちまち一目惚れ、「結婚するならあの人だ」と朝次に告白する。津紀子は、(朝次から霞宛ての)手紙を届けに来たのだが、監禁状態の霞を見て手引きをする。久しぶりに出会った霞と朝次は、夜の海岸を散歩する。「ねえ、霞ちゃん、こんなこといつまで続くと思う?」「朝ちゃんが続かせなければ続けられりゃしないわ」「霞ちゃんだって、続けられる?」「あたしは死ぬまで続けるわ」「そんなことできるもんか、お嫁にいってしまえば」「行かないったら、やな人ねえ」・・・。「ボクには自信がなくなってしまったんだ」「どうして」「ボクは妾の子なんだ」「また、そんなこと。あたしのお母さんだって酌婦だったわ」「でも、正式な奥様になってるじゃないか」「そんなことどうだっていいじゃないの」「違うよ、形式というのはとっても大切なものなんだよ」「でも、あなたのお母さん、とてもいい人よ。うちのお母さんとは比べものにならないくらい」・・・。「霞ちゃん、ボク、アメリカに行けるかもしれない」「いつ?」「君が結婚する前に」「行かないったら、わからない人ねえ」「そんなこと言ったって、家には代えられないだろう」「子どもより家を大切にする親なんてこっちも考えないわ」・・・「それより本当にアメリカに行くの?(結婚できなければ情死する約束)忘れちゃったの?」「忘れやしない、ただボクは死ぬのなら独りで死ぬんだ。誰にも知られないところで」「あたしは?」「君は死ぬ必要はない。ボクは世の中がイヤになったんだ」「・・・じゃあいいわ、あたしも独りで死ぬから」「君には呉さんといういいお友達があるじゃないか」「だから、だからできるだけ生きていたいんじゃないの。それを朝ちゃんはひとりで勝手に・・・」と、霞は泣き崩れる。朝次は「じゃあ、できるだけ二人で努力しよう!、もしそれでダメだったら・・・」、霞は静かに頷いた。
この二人の対話は、まさに「君と行く(末)路」を暗示しているようだ。
尾上家の別荘に、霞の相手が訪れる結納の日、空木が尾上家の執事を連れてやって来た。執事は朝次から霞に宛てた手紙の束を差し出して言う。「これをお返しするように言いつかって参りました。霞様の手紙がありましたらお返しください」。朝次はその手紙を受け取り、引き出しの中から霞の手紙を取りだした。「これで私が言い掛かりをつけると思っているのですか。この手紙はお返しできません」と言うなり、破り捨て暖炉の火に投げ込んだ。執事は驚いたが、ともかくも安堵、「つきましては、朝次様、洋行の足しにでも」と言い、壱千円の小切手を手渡す。朝次は直ぐさまそれも破り捨て、「妾の子だと思って、私のことまで芸者扱いするのか!」と、空木、執事を追い返し、独り浜辺に向かう。
その日、津紀子も「虫の知らせ」で霞を救いに訪れた。玄関払いをさせられようとしたが、霞が飛び出して来て自室に招き入れる。あわててメモを記し、朝次のもとに届けてほしいと依頼する。朝次は独り浜辺で悔しさに耐えている。そこに夕次がやって来た。「こんな所で何してるんだい、この前の人が霞ちゃんの手紙を持ってきてくれたよ」と言う。夕次は、電車の中で見初めた意中の人が、霞の親友・呉津紀子だったことが判り、喜んだ。 三人で家に戻り、朝次は手紙を呼む。そして、「津紀子さん、弟の夕次をどう思いますか。お付き合いしていただければ・・・。」津紀子も嬉しそうに同意した。「霞さんには、すぐに返事をします。ボクの行動を見てその様子を知らせてあげてください。その前に、ちょっと出かけてきます」と、夕次と津紀子を残して出て行く。入れ替わりに母がやって来た。)朝次が「夕次のお嫁さんが来ているよ」と言ったので御挨拶に伺いました。(玄関先で自動車が発進するエンジンの音が聞こえた)「まあ、すてきなお洋服だこと!」と津紀子の姿に目を細める。一目で気に入った様子だったのだが・・・。
突然、電話が鳴り響き、朝次の自動車事故を知らせる。独り、崖道を激走して転落したのである。
数日後、霞の姿が見えなくなった。家の者の目を盗んで津紀子の家を訪れる。お別れに来たと言う。「もう、二、三日後ね(嫁ぐ日は)」と津紀子が言う。「この間の手紙渡してくださった?」「ありがと」「霞ちゃん、朝次さんのこと何にも聞かない?」「・・・・」「きっと、誰も言やしないわねえ・・・」。津紀子は霞に朝次の死を告げる。霞は呆然としたが、「誰も言わないんだもの」と座り込む。「明日が埋骨式よ」「津紀子さん、あたしも連れてってくれない?」と懇願したが、津紀子は首を横に振る。「もう、仕方がないじゃないの」。霞は「朝ちゃん!」と叫んで泣き崩れたが、「行く路」を決意したのだろう。
天野の別荘では、朝次の骨箱を夕次が運んでいる。「母が仏壇の前に置いておくもの」と言うのも聞かず、隣の霞に部屋の窓が見える場所に安置する。式に出るのは、母、夕次、空木、雛、津紀子の5人と数えていると、雛が訪れた。御前様の来るのが遅れる、昨日から霞が行方不明で、今探しているところだと言う。夕次が「津紀子さんの所じゃないか」と言っているところに、津紀子も供花を持ってやって来た。どこか元気がない。供花を力なく骨箱の上に乗せる。夕次が「霞ちゃんがねえ・・・」と言いかけると、昨日の経緯を告げた。「あたし、霞ちゃんはもう亡くなっていると思う」「そんなことはないよ、どこかで働き口でも探しているんだろう」「そうだといいんだけど」。夕次は津紀子との縁談話を確かめようとするが、津紀子は意外にも「否」、自分たちもまた死ななければならなくなる、と言う。夕次はその意味を必死で訊ねるが、「もっと、あたしたち強くなってから、またお会いしましょう」と答えるだけであった。・・・、津紀子の予感は当たった。空木が沈痛な表情で到着する。「霞ちゃんは?」「居たよ」「どこに?」「家の裏の池の中に、浮かんでいたんだ」。まあ、と聞いた一同は涙を拭う。しばらくして、雛が言う。「でも、霞さんは朝次さんの所に行って、お幸せにお暮らしになるんでしょう。朝次さんはきっと喜んでいると思いますわ」。その言葉を聞いて、津紀子は夕次のもとへ行き「夕次さん、さようなら、ごきげんよう」と言い立ち去った。夕次は椅子に座り込んで嗚咽する。その様子を訝しがる母、「いったいどうしたんだねえ、あの人は。変な子だねえ津紀子さんていう人は。霞ちゃんはね、親の言うことを聞かないからこんなことになってしまった。親の言うことを聞いていればいい奥さんになれたのに。お前だって、ごらんな、出世ができるのにこんなにグズグズしてさ・・・」。そう言われた夕次は、たまらず立ち上がり「バカ! お母さんのバカ!」と叫ぶ。その勢いに、母は目を丸くして呆気にとられる。別荘の外では、何かをこらえ、足早に浜辺を立ち去る津紀子の姿を映すうちに、この映画は「終」となった。
女性映画の名手と謳われた成瀬巳喜男の作品としては、あまり評価は高くないようだが、私にとってはまさに傑作、他に比べて優るとも劣らない出来映えであった。筋書きは「天国に結ぶ恋」もどきの悲恋物語にも見えるが、実は登場する4人の「女模様」がくっきりと浮き彫りされて、そのコントラストがたいそう興味深いのである。
その一人は、加代という女性、朝次、夕次の母である。名士・天沼長二郎の愛妾として、豪華な鎌倉の別荘を譲り受け、さらに膨大な手切れ金(息子たちの養育費)も頂戴、お春という女中まで置いている。にもかかわらず、その金を「わずかばかりの端金」と言って憚らない。世の中はすべて金、義理も人情も「どこ吹く風」、霞の死を、今、泣き悔やんでいたかと思えば、「霞ちゃんはね、親の言うことを聞かないからこんなことになってしまった。親の言うことを聞いていればいい奥さんになれたのに」などと、哀悼の意を忘れ去る。たまらず、夕次が「お母さんのバカ」と叫んでも、その気持ちがわからない。空木を「御前様」と奉る一方、陰では「いい年をしてみっともない」と見下げる。夕次の縁談話でも、相手の娘を「器量はよくないけど女学校出だとさ」と評価する。レター・ペーパーをラブレター、デスクをデクスと言い間違えても気づかない。その極め付きは、「自分が芸者であったこと」に全く頓着しないことである。夕次が「ボクが好きになった人なら、その家が魚屋であっても材木屋であってもかまわない」と言えば「カフェの女給なんか困るよ」と言い、朝次から「芸者より女給の方がマシだ」と言われ「まあ、この子ったら」と涙ぐむ。しかし、いつまでもクヨクヨしないのが彼女の真骨頂だ。そもそも、朝次の死、霞の後追い自殺は、加代が芸者上がりであったことに因る、そして夕次が津紀子に振られたのも同じ理由に因る。つまり自分が蒔いた種だったということに気がつかない。いわば「無知の逞しさ」とでも言おうか、かつては、「どこにでも居そう」な女性の生き様を、女優・清川玉枝は見事に演じきったと、私は思う・
その二人目は、霞の風情、見るからに楚々として初々しい。語り口もたどたどしいが、その内容は正鵠を射ている。朝次との密会中、「ねえ、霞ちゃん、こんなこといつまで続くと思う?」と問われて「朝ちゃんが続かせなければ続けられりゃしないわ」と毅然と答え「霞ちゃんだって、続けられる?」「あたしは死ぬまで続けるわ」「そんなことできるもんか、お嫁にいってしまえば」「行かないったら、やな人ねえ」という対話の中には、明確な意志・覚悟がある。さらに、「それより本当にアメリカに行くの?(結婚が叶わなければ情死という約束)忘れちゃったの?」「忘れやしない、ただボクは死ぬのなら独りで死ぬんだ。誰にも知られないところで」「あたしは?」「君は死ぬ必要はない。ボクは世の中がイヤになったんだ」「・・・じゃあいいわ、あたしも独りで死ぬから」というやりとりの中にも、確固とした決意が窺われる。たしかに朝次は「独りで」死んだ。しかし、それは世間の「形式」(格式・義理)に対する敗北であり、弱者の死である。比べて。霞の自死は、男に対する誠を貫くと同時に、世間の「形式」に対する挑戦なのだ。さればこそ、父・尾上の「落胆」は激しく、心底からの後悔と反省をもたらすことができたのである。いわば、強者の死であり、さらに「美しさ」も添えられている。「み袖のままで浮かんでいた。美しい姿だった」という空木の言葉が、何よりも雄弁にそのことを物語っている。そんな芯の強い、一本筋の入った女性の姿を、女優・山縣直代は健気に描出しているのである。
その三人目は呉津紀子、モガのスタイルで明るく行動的、彼女に頼めばどんな夢でも叶いそうな存在感がある。事実、彼女の手引きによって霞と朝次の「逢瀬」は実現、二人の絆をよりいっそう強めることができたのだが、悲劇的な結末を前にして動揺する。とりわけ、夕次との交際が「同じことの繰り返し」になるだろうと予感、「私たちもっと強くなりましょう」「必ず、なってみせるわ」と断言、(霞と同様)毅然と訣別する姿は、理知的で冷静である。加代は「変な子だねえ」と訝るが、自分自身がが世間の「形式」からは、変な存在だと思われていることに気づかない。そのコントラストがたいそう可笑しい。
その四人目は、空木の愛妾・雛である。年の離れた爺さんを旦那にもち、「遺産を狙っているに違いない」と加代からはさげすまれているが、一向にお構いなく、「お酒が飲みたい、隣で調達してきて」と空木を使い走りさせる。「家でゆっくり飲むわ」とちゃっかり、ボトル一本をゲットする様子は可笑しく、遊び人で「いい男」の空木が可愛がるのも肯ける。霞の死を知って「霞さんは朝次さんの所に行って、お幸せにお暮らしになるんでしょう。朝次さんはきっと喜んでいると思いますわ」と泣き崩れる姿も月並みだが、それが津紀子の「毅然とした訣別」を導いたことは、確かである。「私は違う!。私は《死んで楽しい天国であなたの妻になりますわ》などということは信じない!」と思ったに違いない。
以上が、女性映画の名手・成瀬巳喜男監督が描き出した「女模様」の実像ではないだろうか。
(2017.6.24)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-03
付録・邦画傑作選・「その夜の妻」(監督・小津安二郎・1930年)
ユーチューブで映画「その夜の妻」(監督・小津安二郎・1930年)を観た。登場人物は、深夜ビジネス街で拳銃強盗を働き警官から追われている橋爪(岡田時彦)、その妻まゆみ(八雲恵美子)、その子みち子(市村美津子)、橋爪を捕縛しに訪れた刑事(山本冬郷)、病臥するみち子を往診する医者(齋藤達雄)、その他大勢(橋爪を追いかける警官隊、強盗被害者)とシンプル、ほぼ5人の「絡み」だけで物語は展開する。時間も、ある日の午後9時から翌日の9時まで(原作は短編小説『九時から九時まで』・オスカー・シスゴール)という設定で、当時の人間模様がコンパクトに凝縮された佳品であった。
橋爪は愛娘・みち子の治療代を捻出しようと借金に出かけたが誰も相手にしてくれない。やむなく強盗を余儀なくされたが、拳銃を所持しているところを見ると堅気とは思えない。いでたちもスーツにネクタイ、ハットとアメリカ風である。住まいは雑居ビルの一室、テーブル、椅子、ベッド、コーヒーポット、洗面器、アイスピック等々、家具・調度品の全てが洋風、壁にはローマ字のポスター、看板も見える。もしかして橋爪の職業はペンキ職人?、彼自身が呟いたように「俺たち貧乏人」であることは確かなようである。室内に干された洗濯物、床に並んだペンキ缶が哀れを誘う。 ベッドではみち子が目をさまして「お父ちゃんはどこ、お父ちゃんを呼んできて」と泣き叫ぶ。医者の話では今晩がヤマとのこと、途方に暮れるまゆみの姿がひときわ艶やかであった。追われ身の橋爪が帰宅、奪ってきた金をわしづかみにしてまゆみに手渡す。「あなた、もしかして・・・」と夫の顔を見据えれば、静かに拳銃を差し出し、「みち子の病気が治ったら、自首するつもりだ」。そこに訪れたのが円タクの運転手を装っていた刑事、「その筋の者だが、御主人は在宅か」。夫、現金、拳銃をあわてて物陰に隠し、「いいえ、主人はまだ帰っておりません」「では待たせてもらおう」「それは困ります。娘が大病なんです。お帰りください」「氷を割るくらいならやってあげるよ」などと言いながら机上に置き忘れた橋爪の帽子を取り上げてまゆみの頭に被せる。「実を言うとさっきあなたの夫をそこまで車に乗せてきたんだ」と言いつつ拳銃を取り出し「出てこい!」と叫んだ。まゆみも意を決したか、隠した拳銃を取り出して刑事の背中に押し突ける。「あなた!早く逃げて」。橋爪、姿を現したが泣き叫ぶみち子の枕元に駆け寄り「俺にはこの子を手放してゆく勇気はねえよ」「それなら私のことはかまわずに介抱してあげてください」なおも拳銃を突きつけて「今夜はこの子が生きるか死ぬかの一大事なんです。夫はこの子が峠を越したら自首すると言っています。それまではいつまでもこうしています」。刑事は静かに両手を挙げ、椅子に腰かけた。時刻は午前1時50分。橋爪の看病が続く。刻一刻と時間が過ぎ、時刻は3時・・・、睡魔がまゆみを襲う。夜が明け始め牛乳配達がやって来た頃、ふと気がつくと事態は逆転していた。拳銃を握っていたのは刑事、橋爪はみち子のそばで眠り込んでいる。慌てるまゆみに「静かに、子どもが目を覚ましてしまうよ。医者が来るまで待つから君も一休みしたまえ。袂の紙幣は僕が預かったよ」などと言う。万事休す、まゆみの力は脱けてしまった。やがて医者がやって来た。診察後、欣然として「もう大丈夫です!危険状態は脱しましたよ」。しかし、橋爪には妻子との別れが待っている。「別れのコーヒーでも入れてもらおうか」、まゆみがふとみると、待ちくたびれたか、刑事が居眠りをしている。咄嗟に「あなた、逃げて!」と夫を玄関口から送り出した。後ろを振り向くと、刑事が立っている。「僕が徹夜の疲れで眠ってしまったと思ったか、その通り、だからわざと逃したんじゃない」。刑事は「その夜」をこの親子たちと過ごすうちに、「拳銃も現金も取り戻した。もういいか」と許す気持ちになったのか・・・。少なくとも「俺はこの男を捕縛したくない」(できれば親子を救いたい)と思ったに違いない。静かに立ち去ろうとして玄関のドアを開けると、橋爪が立っていた。「逃げるなんて馬鹿な考えはやめた。刑期を務めれば思いっきりみち子を抱けるんだ」。わざと逃がしてくれた刑事に対するせめてもの恩義だろうか。呆然とするまゆみ、しかし気を取り直してみち子を抱き上げ、牽かれていく夫を見送る「その夜の妻」の姿はひときわ鮮やかであった。母として、妻として千々に乱れる女心を、女優・南雲恵美子はその表情・目線を通して見事に描出していた。さらに、二枚目・岡田時彦の「やくざ」な色気、ハリウッド映画出演経験者・山本冬郷の「いぶし銀」のような渋さ、モダンな背景・大道具・小道具も添えられて、たいそう魅力的な作品に仕上がっていた、と私は思う。お見事!と思わず心中で叫んでしまった。(2017.1.19)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

橋爪は愛娘・みち子の治療代を捻出しようと借金に出かけたが誰も相手にしてくれない。やむなく強盗を余儀なくされたが、拳銃を所持しているところを見ると堅気とは思えない。いでたちもスーツにネクタイ、ハットとアメリカ風である。住まいは雑居ビルの一室、テーブル、椅子、ベッド、コーヒーポット、洗面器、アイスピック等々、家具・調度品の全てが洋風、壁にはローマ字のポスター、看板も見える。もしかして橋爪の職業はペンキ職人?、彼自身が呟いたように「俺たち貧乏人」であることは確かなようである。室内に干された洗濯物、床に並んだペンキ缶が哀れを誘う。 ベッドではみち子が目をさまして「お父ちゃんはどこ、お父ちゃんを呼んできて」と泣き叫ぶ。医者の話では今晩がヤマとのこと、途方に暮れるまゆみの姿がひときわ艶やかであった。追われ身の橋爪が帰宅、奪ってきた金をわしづかみにしてまゆみに手渡す。「あなた、もしかして・・・」と夫の顔を見据えれば、静かに拳銃を差し出し、「みち子の病気が治ったら、自首するつもりだ」。そこに訪れたのが円タクの運転手を装っていた刑事、「その筋の者だが、御主人は在宅か」。夫、現金、拳銃をあわてて物陰に隠し、「いいえ、主人はまだ帰っておりません」「では待たせてもらおう」「それは困ります。娘が大病なんです。お帰りください」「氷を割るくらいならやってあげるよ」などと言いながら机上に置き忘れた橋爪の帽子を取り上げてまゆみの頭に被せる。「実を言うとさっきあなたの夫をそこまで車に乗せてきたんだ」と言いつつ拳銃を取り出し「出てこい!」と叫んだ。まゆみも意を決したか、隠した拳銃を取り出して刑事の背中に押し突ける。「あなた!早く逃げて」。橋爪、姿を現したが泣き叫ぶみち子の枕元に駆け寄り「俺にはこの子を手放してゆく勇気はねえよ」「それなら私のことはかまわずに介抱してあげてください」なおも拳銃を突きつけて「今夜はこの子が生きるか死ぬかの一大事なんです。夫はこの子が峠を越したら自首すると言っています。それまではいつまでもこうしています」。刑事は静かに両手を挙げ、椅子に腰かけた。時刻は午前1時50分。橋爪の看病が続く。刻一刻と時間が過ぎ、時刻は3時・・・、睡魔がまゆみを襲う。夜が明け始め牛乳配達がやって来た頃、ふと気がつくと事態は逆転していた。拳銃を握っていたのは刑事、橋爪はみち子のそばで眠り込んでいる。慌てるまゆみに「静かに、子どもが目を覚ましてしまうよ。医者が来るまで待つから君も一休みしたまえ。袂の紙幣は僕が預かったよ」などと言う。万事休す、まゆみの力は脱けてしまった。やがて医者がやって来た。診察後、欣然として「もう大丈夫です!危険状態は脱しましたよ」。しかし、橋爪には妻子との別れが待っている。「別れのコーヒーでも入れてもらおうか」、まゆみがふとみると、待ちくたびれたか、刑事が居眠りをしている。咄嗟に「あなた、逃げて!」と夫を玄関口から送り出した。後ろを振り向くと、刑事が立っている。「僕が徹夜の疲れで眠ってしまったと思ったか、その通り、だからわざと逃したんじゃない」。刑事は「その夜」をこの親子たちと過ごすうちに、「拳銃も現金も取り戻した。もういいか」と許す気持ちになったのか・・・。少なくとも「俺はこの男を捕縛したくない」(できれば親子を救いたい)と思ったに違いない。静かに立ち去ろうとして玄関のドアを開けると、橋爪が立っていた。「逃げるなんて馬鹿な考えはやめた。刑期を務めれば思いっきりみち子を抱けるんだ」。わざと逃がしてくれた刑事に対するせめてもの恩義だろうか。呆然とするまゆみ、しかし気を取り直してみち子を抱き上げ、牽かれていく夫を見送る「その夜の妻」の姿はひときわ鮮やかであった。母として、妻として千々に乱れる女心を、女優・南雲恵美子はその表情・目線を通して見事に描出していた。さらに、二枚目・岡田時彦の「やくざ」な色気、ハリウッド映画出演経験者・山本冬郷の「いぶし銀」のような渋さ、モダンな背景・大道具・小道具も添えられて、たいそう魅力的な作品に仕上がっていた、と私は思う。お見事!と思わず心中で叫んでしまった。(2017.1.19)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-04-01
付録・邦画傑作選・「港の日本娘」(監督・清水宏・1933年)
ユーチューブで映画「港の日本娘」(監督・清水宏・1933年)を観た。戦前の男女の色模様を描いた傑作である。港の日本娘とは黒川砂子(及川道子)のことである。彼女には無二の親友、ドラ・ケンネル(井上雪子)がいた。この二人に絡むのが男三人、プレイボーイのヘンリー(江川宇礼雄)、貧乏な街頭画家・三浦(齋藤達雄)、酒場の紳士・原田(南條康雄)である。
砂子とドラは、横浜・山の手の女学校に通う仲良しで、下校時いつも最後まで残るのはこの二人、その帰り道を狙って、ヘンリーがオートバイに乗って近づいて来る。どうやら、砂子の方がヘンリーに惹かれている様子、ドラはいつも置いてきぼりにされることが多かった。ヘンリーはオートバイに砂子を乗せ、海に、山に、街に逢瀬を楽しんでいた(幸福を楽しんでいた)のだが、「移ろいやすいのは恋」、ヘンリーの前にに新しい恋人、シェリダン耀子(沢蘭子)が現れると、今度は砂子が置き去りにされる。その頃からヘンリーの素行は悪化、与太者仲間との付き合いも始まった。ドラはヘンリーが隠し持っていたピストルを取り上げて、ヘンリーの翻意を促す。しかし、ヘンリーには、熟女・耀子の色香の方が魅力だったのだろう、豪華船内で催されるダンスに誘われて赴く。その帰り、酔いつぶれた耀子を介抱しようと、ヘンリーが街(女学校?)の教会に入ると、「神様の前で結婚しちゃうんだよ」などと耀子がうそぶく。ドラに言われて、波止場までヘンリーを迎えに行った砂子は二人を教会まで追跡してきたか、静かにドアを開け、無言で耀子と睨み合う。耀子が嘲けて笑いかけた時、砂子の手にしたピストル一発が炸裂、耀子はその場に倒れ込んだ。あわてて抱き起こすヘンリー。砂子のピストルはドラがヘンリーから取り上げた代物に他ならない。清純な女学生たちの間に、悲劇の幕が切って落とされたのである。砂子は「神様!」と救いを求め、叫んだが、神様は許してくれなかった。
気がつけば、砂子は「横浜から長崎へ、長崎から神戸へと渡り歩く哀しい女」になってしまっていたのである。神戸の波止場を朋輩・マスミ(逢初夢子)と、日傘をさしながら散歩している。マスミが「そろそろ横浜に住み替えだ」と言えば、砂子も「あたしも横浜に帰ろうかな」。マスミが後ろを振り返って「あの居候はどうするのさ」。二人の後ろから、砂子のヒモらしき貧乏画家・三浦が、とぼとぼ付いてきていたのだ。「犬ころみたいに付いてくるんだもの、どうしょうもないじゃないか」。「彼は一体、何者?」「あれでも画家よ。長崎からの道ずれさ、くっついて離れないんだもの」「あんたの亭主? 情夫?」「さあ、何だかねえ」と砂子は応えた。
かくて三人は横浜へ。横浜では真面目になったヘンリーとドラが新所帯を構えていた。まもなく子どもも生まれる。帰宅したヘンリーは、食事をしながら「砂ちゃんが戻って来たらしい。昔の面影はないそうだ」とドラに告げる。一瞬、顔を曇らせるドラ・・・。
ある雨の夜、客の来ない「ハマのキャバレー」では女たちが三々五々帰って行く。残されたのは砂子と紳士、そこにヘンリーが訪れた。びっくりする砂子、思わず厚化粧の姿を見られまいと壁に隠れたが、やがて見つめ合う二人。紳士は「邪魔者は消えるよ」と立ち去った。二人とも無言で俯いていたが「お酒、飲む?」「・・・」、ヘンリーは下を向いたまま首を振る。「ドラは今、どうしているかしら、消息知らない」「・・・・」「あたしの聞き方が悪かったわね。二人は今、幸せ?」「・・・・」「あなたたちのこと、心から祝福するわ」と言って砂子は涙ぐむ。ヘンリーは終始無言、「あたし、もう帰るわ。それとも、あたしのお客になる?」「・・・・」「冗談よ」。ヘンリーは無言のまま砂子のアパート(従業員寮)へ。「ドラによろしくね」と言って砂子がドアを開けると、のっそり三浦が顔を出し、パタンとドアを閉めた。やはり、無言のままヘンリーの姿は画面から消える。部屋の中では三浦が、隣に女の人が引っ越してきた。何か言い仕事はないか探している旨を砂子に告げる。「あんた、他人のことより自分のことを考えたら」とそっけない返事が返ってくるだけだった。
翌朝、砂子のアパートをドラが訪れる。砂子は一瞬たじろいだが「ここは、あなたの来るところではないわ」「私が来られないでいられると思って?」「ヘンリーは真面目に働いているし、家庭は円満だし、それを喜んでもらいたいとでもいうの」と、閉め出した後で、泣き崩れた。自分の姿は、あばずれですれっからし、相手は清楚な若奥様、あの仲良しが今はこんな関係になってしまうなんて、という悔恨が伝わってくる、名場面であった。
そして日曜日、今度は砂子がヘンリーの家を訪れる。ドラもヘンリーも歓迎、ヘンリーは昔を思い出したか、レコードをかけ砂子とダンスを踊る。馳走の準備をしていると、床に毛糸の玉がコロコロ転がっているのが見えた。その毛糸は生まれてくる子どものためにドラが靴下を編もうとしていた物、手を取り合って楽しそうに踊っている二人の足元に毛糸が絡みついていたのだ。そのことも気づかずに・・・、ドラは唖然として二人を見つめる。その視線を受けながら、砂子は腕時計に目をやり「もうそろそろお暇します」。砂子を見送りながら「送っていらしゃったら」とヘンリーを促す。ヘンリーと砂子は、あちこちと散歩しながら、昔、逢瀬を重ねた思い出の場所に辿り着いた。ヘンリーは言う。「砂子さん、お願いがあるんだ。真面目な生活に帰ってもらいたい。あなたの不幸な生活を見ていられない、苦しくて・・・」「帰りたい。でも出来ないことらしいわ。あなたの胸で泣かせて・・・」と砂子はヘンリーに縋りつく。そしてキャバレーに戻り、マスミが止めるのも聞かずに酒をあおりダンスに興じる。相手はいつもの紳士・・・。
砂子のアパートでは、三浦がせっせと洗濯の最中、そこに隣の女が通りかかる。今日も仕事にあぶれたようだ。「私にも手伝わせて」、三浦は砂子の下着も依頼しようと部屋に戻ると、ヘンリーが待っていた。三浦はかまわず洗濯物をまとめて出てていこうとすると、ヘンリーが「砂子さんは?」と問いかけた。「留、留守ですよ」と応じれば「君は一体、砂子さんの何なんだい」「何に見える?」「兄妹にも見えないし、まんざら他人でもなさそうだ。と言って亭主にはなおさら見えない」。三浦も再び出て行こうと振り返り「ところで、あなたは一体、あの人の何なんです?」「何に見える?」「兄妹にも見えないし、まんざら他人でもなさそうだが、亭主には絶対見えないよ」。この恋の鞘当ては、どちらに分があるのやら・・・。夜、三浦が洗濯物にアイロンをかけていると、砂子がフラフラと千鳥足で帰ってくる。「あんた、あたしの下着まで洗濯したの?」「隣のご婦人がやってくれたんだ」「じゃあ、この御礼を持っていきな」と金を渡す。入れ替わりにマスミがやって来た。「あたし、お店から足ヌケするよ。少し遠いところへ行くつもりさ。辛い浮世に短い命」。突然の話で砂子はびっくりしたが、その言葉を聞いて「私も連れてって」と言う。マスミは「落武者一騎、ひとりで逃げるのがせいぜいだよ」と言ってて出て行こうとする。しかし、ドアの外には刑事と警官の姿があった。一瞬たじろいだが、「悪いことはできないよ、あばよ」と言い残し、自ら曳かれて行った。
次の日か、三浦がヘンリーの家を訪れ、近頃ヘンリーがたびたび砂子のアパートを訪れているとドラに告げる。ショックを隠せないドラが「砂子さんはどんなお考えですの」と訊ねると、三浦は勝ち誇ったように「さあ、それが問題ですな」。ドラがたしかめようとして、アパートを訪れると案の定、ヘンリーが来ていた。三浦も砂子も不在、ドラはやむなく帰ろうとする。ヘンリーはドラを呼び止め「砂ちゃんに、何か用かい」「あなたは」「・・・・」、ドラは再び帰ろうとする。ヘンリーは「誤解しないでくれ」と言えば「誤解するようなことがあるんですの」と立ち去ろうとする。あわてて追いかけるヘンリー、家に戻ってからも気まずい沈黙が続いた。
一方、砂子のアパートでは大喧嘩が始まった。三浦をにらみつけ砂子の怒号がとぶ。「お前はとんだ悪戯をしたもんだね」、「あたしは、せっかく一つだけあった真面目な世間とのつながりをなくしてしまった」と嘆くと、珍しく三浦が抗弁した。「僕は、ヘンリーが憎かったんです!砂子さんには僕の気持ちがわからないんですか」。その言葉を聞いて、堪忍袋の緒が切れた。砂子は「出てお行き!」と叫ぶなり、三浦の持ち物、画材、キャンバスなどなど、一切をドアの外に投げ捨てる。三浦もまた放り出されてしまった。
「ハマのキャバレー」に、もうマスミの姿はない。砂子はいつもの紳士と酒を飲んでいる。そこにヘンリーがやって来た。砂子は笑って「ドラのお許しが出たの?」「ここに来るのに、許可がいるのか」「そうね、あなたはお客さんだったわね」「少し、話したいことがある」「あたし、お客様とは深刻な話はしないの」と言って、いつもの紳士とダンスに興じる。うなだれるヘンリー、つれなく袖にされる姿が一際あわれであった。
深夜、砂子がアパートに帰ると、ドラが待っていた。「ヘンリーは?」と訊ねる。砂子は「あたし、あなたのハズのことなんて知りませんわ」と他人行儀に応じれば「あなたが
一番知っていると思ったのに」「ドラ、私のことそんな女だと思っているの」、力なく帰って行くドラを放っておけず、砂子はヘンリーの家まで同行する。そこで「砂ちゃん、私もうすぐママになるのよ」という言葉を聞かされた。「それなのに、ヘンリーったら毎晩お酒を飲んで帰ってくるのよ」とドラは涙ぐむ。砂子はハッとして「あたしがいけなかったんだわ、甘えていたのよ」と自分の姿にはじめて気づいたか・・・。たちまち家を出て、ハマの歓楽街をしらみつぶしに探し回る。ヘンリーは4軒目の店に居た。「こんな所に居たのね、ドラは淋しく赤ちゃんの靴下(たあた)を編んでいるのよ」。ヘンリーは憔悴して「ぼくは、一体どうすればいいのか(わからない)」と言う。砂子はキッとして「早く家に帰ってパパになる勉強をなさればいいんだわ」とヘンリーを連れ戻した。「さあ、ここで生まれてくる赤ちゃんの名前でも考えていたらいいのよ」。ドラに「雨降って地固まる、ヘンリーを可愛がっておやりなさい」と言い残してその場を去って行く。「ヘンリー、ドラ、あたしはこれからどこに行けばいいの?」と呟きながら・・・。
アパートに戻ると、隣室から三浦が出てきた。「可哀想な女だ」。隣の女は医者に見放される病、もう永くはないと言う。砂子は、ベッドに横たわるその女を、一目みるなり驚愕した。自分が傷つけた、あのシェリダン耀子だったのである。見つめ合う二人、「砂子さん、あなただったの。シェリダン耀子もこうなってはおしまいね」と耀子が力なく笑う。窓の外は降りしきる雨。「こんな夜に世間から見捨てられて一人淋しく死んでいくなんて惨めね」。「でもこれが正しい裁きかも・・・、ヘンリーやドラはどうしているかしら」。砂子は「二人は結婚しましたわ、今、幸福に暮らしております」と告げる。「あなた、二人をそっとしておいてあげなければいけないわよ」「あたし、そのことに気がつかなかったんです。でも、二人は今、幸福です」「砂子さん、私がいい見本よ。早く真面目な生活に帰りなさい」「でも、世間は許してくれるでしょうか」「待つのよ、許してくれるまで待つのよ、じっと堪えて」「わかったわ、耀子さん。あたし待ちます。許してくれるまで待ちますわ」と、耀子の膝元で泣き崩れた。「逢えて本当によかったわ」、それが耀子の遺言であった。窓の外の雨はいっそう激しく降り注ぐ。哀しい女たちの涙を象徴しているかのように・・・。
かくて「横浜よ、さようなら」の日がやって来た。すっかり旅支度の整った砂子に、三浦が言う。「僕はどうなるんだね」、砂子はニッコリして「旅は道連れ、あたしに話し相手が一人ぐらいあってもいいんだわ」。パッと表情が輝いた三浦もまた慌てて旅支度を始める。やがて二人は船の甲板、海を見つめている。三浦が手にしている(砂子の)肖像画を見て砂子が言う。「そんなもの、捨てておしまい!」。三浦は一瞥したが、惜しげもなく二枚の絵を海に投げ捨てた。波間を漂う二枚の絵、それは過去との訣別、新しい生活、とりわけ真面目な生活への餞であったかもしれない。船は港を離れた。五色のテープが乱れる中、ヘンリーとドラが波止場に駆けつける。一足先に見送りに来ていた、酒場の紳士が「よろしく言っていましたよ」と二人に告げて立ち去った。二人は遠ざかる船を見つめる。カモメが飛び交い、波間に漂う砂子の肖像画が見え隠れするうちに、この映画は「終」となった。
映画はサイレントだが、オートバイの音、ピストルの音、波の音、雨の音、風の音、人物の話し声、叫び声、泣き声・・・などが鮮やかに聞こえてくる力作である。
映画の眼目は、男女の色模様で「よくある話」、とりわけ二枚目(イケメン)ヘンリーの優柔不断さに振り回される女たち、砂子、ドラ、耀子の姿が哀愁を誘う。三枚目の三浦が「ボクはヘンリーが憎い」と言う心情には十分、共感できる。三浦には女を選り好みする気などさらさらない。徹底したフェミニストなのだ。ヘンリーは変貌した砂子を見て「その姿を見るのが苦しい」と言い、新妻のドラを捨て置いて酒場をさまよう。そんな姿は見苦しく、男らしさのひとかけらも感じられない。その根性が憎いのさろう。三浦の風采は凡庸、未だにうだつが上がらないとはいえ、ただひたすら砂子に追従することを目指す心意気の方が、よほど男らしいではないか。しかし、その魅力は砂子には通じない。そこら辺りの「心模様」がこの映画の眼目かもしれない。さらにまた、ほんの端役ながら、いつも砂子に寄り添い、決してそれ以上踏み込もうとしない酒場の(無名)紳士の「男振り」も、実に清々しく爽やかで、際立っていたと思うのだが・・・、男女の色模様は、げに「不可思議」というべきか。
一方、女学生時代の砂子、ドラを演じた及川道子、井上雪子の清純な美しさは輝いていた。それが、ひょんなことから、たちまち「あばずれ・すれっからし」「所帯やつれ」に変貌する姿も見事である。その領分では、マスミの風情が一枚上か、「辛い浮世に短い命」「あばよ!」という「決めゼリフ」がたいそう堂に入っていたと、私は思う。
監督・清水宏の作品では、『有りがたうさん』『大学の若旦那』『按摩と女』『簪(かんざし)』等が有名で、この作品はそれほど知られていない(もしくは不評の)ようだが、夭逝した及川道子を主人公に据え、江川宇礼雄、井上雪子といったハーフの俳優にヘンリー、ドラという外人もどきの役柄を脇役に配した演出はユニークでであり、貴重な異色作品あると、私は思った。 (2017.6.9)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

砂子とドラは、横浜・山の手の女学校に通う仲良しで、下校時いつも最後まで残るのはこの二人、その帰り道を狙って、ヘンリーがオートバイに乗って近づいて来る。どうやら、砂子の方がヘンリーに惹かれている様子、ドラはいつも置いてきぼりにされることが多かった。ヘンリーはオートバイに砂子を乗せ、海に、山に、街に逢瀬を楽しんでいた(幸福を楽しんでいた)のだが、「移ろいやすいのは恋」、ヘンリーの前にに新しい恋人、シェリダン耀子(沢蘭子)が現れると、今度は砂子が置き去りにされる。その頃からヘンリーの素行は悪化、与太者仲間との付き合いも始まった。ドラはヘンリーが隠し持っていたピストルを取り上げて、ヘンリーの翻意を促す。しかし、ヘンリーには、熟女・耀子の色香の方が魅力だったのだろう、豪華船内で催されるダンスに誘われて赴く。その帰り、酔いつぶれた耀子を介抱しようと、ヘンリーが街(女学校?)の教会に入ると、「神様の前で結婚しちゃうんだよ」などと耀子がうそぶく。ドラに言われて、波止場までヘンリーを迎えに行った砂子は二人を教会まで追跡してきたか、静かにドアを開け、無言で耀子と睨み合う。耀子が嘲けて笑いかけた時、砂子の手にしたピストル一発が炸裂、耀子はその場に倒れ込んだ。あわてて抱き起こすヘンリー。砂子のピストルはドラがヘンリーから取り上げた代物に他ならない。清純な女学生たちの間に、悲劇の幕が切って落とされたのである。砂子は「神様!」と救いを求め、叫んだが、神様は許してくれなかった。
気がつけば、砂子は「横浜から長崎へ、長崎から神戸へと渡り歩く哀しい女」になってしまっていたのである。神戸の波止場を朋輩・マスミ(逢初夢子)と、日傘をさしながら散歩している。マスミが「そろそろ横浜に住み替えだ」と言えば、砂子も「あたしも横浜に帰ろうかな」。マスミが後ろを振り返って「あの居候はどうするのさ」。二人の後ろから、砂子のヒモらしき貧乏画家・三浦が、とぼとぼ付いてきていたのだ。「犬ころみたいに付いてくるんだもの、どうしょうもないじゃないか」。「彼は一体、何者?」「あれでも画家よ。長崎からの道ずれさ、くっついて離れないんだもの」「あんたの亭主? 情夫?」「さあ、何だかねえ」と砂子は応えた。
かくて三人は横浜へ。横浜では真面目になったヘンリーとドラが新所帯を構えていた。まもなく子どもも生まれる。帰宅したヘンリーは、食事をしながら「砂ちゃんが戻って来たらしい。昔の面影はないそうだ」とドラに告げる。一瞬、顔を曇らせるドラ・・・。
ある雨の夜、客の来ない「ハマのキャバレー」では女たちが三々五々帰って行く。残されたのは砂子と紳士、そこにヘンリーが訪れた。びっくりする砂子、思わず厚化粧の姿を見られまいと壁に隠れたが、やがて見つめ合う二人。紳士は「邪魔者は消えるよ」と立ち去った。二人とも無言で俯いていたが「お酒、飲む?」「・・・」、ヘンリーは下を向いたまま首を振る。「ドラは今、どうしているかしら、消息知らない」「・・・・」「あたしの聞き方が悪かったわね。二人は今、幸せ?」「・・・・」「あなたたちのこと、心から祝福するわ」と言って砂子は涙ぐむ。ヘンリーは終始無言、「あたし、もう帰るわ。それとも、あたしのお客になる?」「・・・・」「冗談よ」。ヘンリーは無言のまま砂子のアパート(従業員寮)へ。「ドラによろしくね」と言って砂子がドアを開けると、のっそり三浦が顔を出し、パタンとドアを閉めた。やはり、無言のままヘンリーの姿は画面から消える。部屋の中では三浦が、隣に女の人が引っ越してきた。何か言い仕事はないか探している旨を砂子に告げる。「あんた、他人のことより自分のことを考えたら」とそっけない返事が返ってくるだけだった。
翌朝、砂子のアパートをドラが訪れる。砂子は一瞬たじろいだが「ここは、あなたの来るところではないわ」「私が来られないでいられると思って?」「ヘンリーは真面目に働いているし、家庭は円満だし、それを喜んでもらいたいとでもいうの」と、閉め出した後で、泣き崩れた。自分の姿は、あばずれですれっからし、相手は清楚な若奥様、あの仲良しが今はこんな関係になってしまうなんて、という悔恨が伝わってくる、名場面であった。
そして日曜日、今度は砂子がヘンリーの家を訪れる。ドラもヘンリーも歓迎、ヘンリーは昔を思い出したか、レコードをかけ砂子とダンスを踊る。馳走の準備をしていると、床に毛糸の玉がコロコロ転がっているのが見えた。その毛糸は生まれてくる子どものためにドラが靴下を編もうとしていた物、手を取り合って楽しそうに踊っている二人の足元に毛糸が絡みついていたのだ。そのことも気づかずに・・・、ドラは唖然として二人を見つめる。その視線を受けながら、砂子は腕時計に目をやり「もうそろそろお暇します」。砂子を見送りながら「送っていらしゃったら」とヘンリーを促す。ヘンリーと砂子は、あちこちと散歩しながら、昔、逢瀬を重ねた思い出の場所に辿り着いた。ヘンリーは言う。「砂子さん、お願いがあるんだ。真面目な生活に帰ってもらいたい。あなたの不幸な生活を見ていられない、苦しくて・・・」「帰りたい。でも出来ないことらしいわ。あなたの胸で泣かせて・・・」と砂子はヘンリーに縋りつく。そしてキャバレーに戻り、マスミが止めるのも聞かずに酒をあおりダンスに興じる。相手はいつもの紳士・・・。
砂子のアパートでは、三浦がせっせと洗濯の最中、そこに隣の女が通りかかる。今日も仕事にあぶれたようだ。「私にも手伝わせて」、三浦は砂子の下着も依頼しようと部屋に戻ると、ヘンリーが待っていた。三浦はかまわず洗濯物をまとめて出てていこうとすると、ヘンリーが「砂子さんは?」と問いかけた。「留、留守ですよ」と応じれば「君は一体、砂子さんの何なんだい」「何に見える?」「兄妹にも見えないし、まんざら他人でもなさそうだ。と言って亭主にはなおさら見えない」。三浦も再び出て行こうと振り返り「ところで、あなたは一体、あの人の何なんです?」「何に見える?」「兄妹にも見えないし、まんざら他人でもなさそうだが、亭主には絶対見えないよ」。この恋の鞘当ては、どちらに分があるのやら・・・。夜、三浦が洗濯物にアイロンをかけていると、砂子がフラフラと千鳥足で帰ってくる。「あんた、あたしの下着まで洗濯したの?」「隣のご婦人がやってくれたんだ」「じゃあ、この御礼を持っていきな」と金を渡す。入れ替わりにマスミがやって来た。「あたし、お店から足ヌケするよ。少し遠いところへ行くつもりさ。辛い浮世に短い命」。突然の話で砂子はびっくりしたが、その言葉を聞いて「私も連れてって」と言う。マスミは「落武者一騎、ひとりで逃げるのがせいぜいだよ」と言ってて出て行こうとする。しかし、ドアの外には刑事と警官の姿があった。一瞬たじろいだが、「悪いことはできないよ、あばよ」と言い残し、自ら曳かれて行った。
次の日か、三浦がヘンリーの家を訪れ、近頃ヘンリーがたびたび砂子のアパートを訪れているとドラに告げる。ショックを隠せないドラが「砂子さんはどんなお考えですの」と訊ねると、三浦は勝ち誇ったように「さあ、それが問題ですな」。ドラがたしかめようとして、アパートを訪れると案の定、ヘンリーが来ていた。三浦も砂子も不在、ドラはやむなく帰ろうとする。ヘンリーはドラを呼び止め「砂ちゃんに、何か用かい」「あなたは」「・・・・」、ドラは再び帰ろうとする。ヘンリーは「誤解しないでくれ」と言えば「誤解するようなことがあるんですの」と立ち去ろうとする。あわてて追いかけるヘンリー、家に戻ってからも気まずい沈黙が続いた。
一方、砂子のアパートでは大喧嘩が始まった。三浦をにらみつけ砂子の怒号がとぶ。「お前はとんだ悪戯をしたもんだね」、「あたしは、せっかく一つだけあった真面目な世間とのつながりをなくしてしまった」と嘆くと、珍しく三浦が抗弁した。「僕は、ヘンリーが憎かったんです!砂子さんには僕の気持ちがわからないんですか」。その言葉を聞いて、堪忍袋の緒が切れた。砂子は「出てお行き!」と叫ぶなり、三浦の持ち物、画材、キャンバスなどなど、一切をドアの外に投げ捨てる。三浦もまた放り出されてしまった。
「ハマのキャバレー」に、もうマスミの姿はない。砂子はいつもの紳士と酒を飲んでいる。そこにヘンリーがやって来た。砂子は笑って「ドラのお許しが出たの?」「ここに来るのに、許可がいるのか」「そうね、あなたはお客さんだったわね」「少し、話したいことがある」「あたし、お客様とは深刻な話はしないの」と言って、いつもの紳士とダンスに興じる。うなだれるヘンリー、つれなく袖にされる姿が一際あわれであった。
深夜、砂子がアパートに帰ると、ドラが待っていた。「ヘンリーは?」と訊ねる。砂子は「あたし、あなたのハズのことなんて知りませんわ」と他人行儀に応じれば「あなたが
一番知っていると思ったのに」「ドラ、私のことそんな女だと思っているの」、力なく帰って行くドラを放っておけず、砂子はヘンリーの家まで同行する。そこで「砂ちゃん、私もうすぐママになるのよ」という言葉を聞かされた。「それなのに、ヘンリーったら毎晩お酒を飲んで帰ってくるのよ」とドラは涙ぐむ。砂子はハッとして「あたしがいけなかったんだわ、甘えていたのよ」と自分の姿にはじめて気づいたか・・・。たちまち家を出て、ハマの歓楽街をしらみつぶしに探し回る。ヘンリーは4軒目の店に居た。「こんな所に居たのね、ドラは淋しく赤ちゃんの靴下(たあた)を編んでいるのよ」。ヘンリーは憔悴して「ぼくは、一体どうすればいいのか(わからない)」と言う。砂子はキッとして「早く家に帰ってパパになる勉強をなさればいいんだわ」とヘンリーを連れ戻した。「さあ、ここで生まれてくる赤ちゃんの名前でも考えていたらいいのよ」。ドラに「雨降って地固まる、ヘンリーを可愛がっておやりなさい」と言い残してその場を去って行く。「ヘンリー、ドラ、あたしはこれからどこに行けばいいの?」と呟きながら・・・。
アパートに戻ると、隣室から三浦が出てきた。「可哀想な女だ」。隣の女は医者に見放される病、もう永くはないと言う。砂子は、ベッドに横たわるその女を、一目みるなり驚愕した。自分が傷つけた、あのシェリダン耀子だったのである。見つめ合う二人、「砂子さん、あなただったの。シェリダン耀子もこうなってはおしまいね」と耀子が力なく笑う。窓の外は降りしきる雨。「こんな夜に世間から見捨てられて一人淋しく死んでいくなんて惨めね」。「でもこれが正しい裁きかも・・・、ヘンリーやドラはどうしているかしら」。砂子は「二人は結婚しましたわ、今、幸福に暮らしております」と告げる。「あなた、二人をそっとしておいてあげなければいけないわよ」「あたし、そのことに気がつかなかったんです。でも、二人は今、幸福です」「砂子さん、私がいい見本よ。早く真面目な生活に帰りなさい」「でも、世間は許してくれるでしょうか」「待つのよ、許してくれるまで待つのよ、じっと堪えて」「わかったわ、耀子さん。あたし待ちます。許してくれるまで待ちますわ」と、耀子の膝元で泣き崩れた。「逢えて本当によかったわ」、それが耀子の遺言であった。窓の外の雨はいっそう激しく降り注ぐ。哀しい女たちの涙を象徴しているかのように・・・。
かくて「横浜よ、さようなら」の日がやって来た。すっかり旅支度の整った砂子に、三浦が言う。「僕はどうなるんだね」、砂子はニッコリして「旅は道連れ、あたしに話し相手が一人ぐらいあってもいいんだわ」。パッと表情が輝いた三浦もまた慌てて旅支度を始める。やがて二人は船の甲板、海を見つめている。三浦が手にしている(砂子の)肖像画を見て砂子が言う。「そんなもの、捨てておしまい!」。三浦は一瞥したが、惜しげもなく二枚の絵を海に投げ捨てた。波間を漂う二枚の絵、それは過去との訣別、新しい生活、とりわけ真面目な生活への餞であったかもしれない。船は港を離れた。五色のテープが乱れる中、ヘンリーとドラが波止場に駆けつける。一足先に見送りに来ていた、酒場の紳士が「よろしく言っていましたよ」と二人に告げて立ち去った。二人は遠ざかる船を見つめる。カモメが飛び交い、波間に漂う砂子の肖像画が見え隠れするうちに、この映画は「終」となった。
映画はサイレントだが、オートバイの音、ピストルの音、波の音、雨の音、風の音、人物の話し声、叫び声、泣き声・・・などが鮮やかに聞こえてくる力作である。
映画の眼目は、男女の色模様で「よくある話」、とりわけ二枚目(イケメン)ヘンリーの優柔不断さに振り回される女たち、砂子、ドラ、耀子の姿が哀愁を誘う。三枚目の三浦が「ボクはヘンリーが憎い」と言う心情には十分、共感できる。三浦には女を選り好みする気などさらさらない。徹底したフェミニストなのだ。ヘンリーは変貌した砂子を見て「その姿を見るのが苦しい」と言い、新妻のドラを捨て置いて酒場をさまよう。そんな姿は見苦しく、男らしさのひとかけらも感じられない。その根性が憎いのさろう。三浦の風采は凡庸、未だにうだつが上がらないとはいえ、ただひたすら砂子に追従することを目指す心意気の方が、よほど男らしいではないか。しかし、その魅力は砂子には通じない。そこら辺りの「心模様」がこの映画の眼目かもしれない。さらにまた、ほんの端役ながら、いつも砂子に寄り添い、決してそれ以上踏み込もうとしない酒場の(無名)紳士の「男振り」も、実に清々しく爽やかで、際立っていたと思うのだが・・・、男女の色模様は、げに「不可思議」というべきか。
一方、女学生時代の砂子、ドラを演じた及川道子、井上雪子の清純な美しさは輝いていた。それが、ひょんなことから、たちまち「あばずれ・すれっからし」「所帯やつれ」に変貌する姿も見事である。その領分では、マスミの風情が一枚上か、「辛い浮世に短い命」「あばよ!」という「決めゼリフ」がたいそう堂に入っていたと、私は思う。
監督・清水宏の作品では、『有りがたうさん』『大学の若旦那』『按摩と女』『簪(かんざし)』等が有名で、この作品はそれほど知られていない(もしくは不評の)ようだが、夭逝した及川道子を主人公に据え、江川宇礼雄、井上雪子といったハーフの俳優にヘンリー、ドラという外人もどきの役柄を脇役に配した演出はユニークでであり、貴重な異色作品あると、私は思った。 (2017.6.9)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-31
付録・邦画傑作選・「噂の娘」(監督・成瀬巳喜男・1935年)
ユーチューブで映画「噂の娘」(監督・成瀬巳喜男・1935年)を観た。東京にある老舗「灘屋酒店」の家族の物語である。主人・健吉(御橋公)は婿養子に入ったが、妻はすでに他界、義父・啓作(汐見洋)、姉娘・邦江(千葉早智子)、妹娘・紀美子(梅園龍子)、他に使用人数名と暮らしている。向かいの床屋(三島雅夫)が客と話している様子では、「灘屋は最近、左前。隠居の派手好きがたたったか。主人の健吉は、傾きかけた店に婿養子として入って大変だ」。健吉にはお葉(伊藤智子)という妾がおり、料理屋を任せている。繁盛しているが、お葉はその店を売り、健吉に役立てようと考えている。姉・邦江の気性は旧来の和風気質、父の稼業をかいがいしく助け、祖父の遊興も許容している。親孝行の典型といえよう。他方、妹・紀美子は正反対、帳場の金をくすねて遊びに行こうとする。邦江に咎められると「いいわよ、今度のお姉さんのお見合い、付き添ってあげないから」。その縁談は、健吉の義弟(邦江の伯父)(藤原釜足)が持ち込んだ。先方は大店・相模屋の息子・佐藤新太郎(大川平八郎)。健吉はあまり乗り気ではなかったが、邦江は「幸せになれそうだ」と思った。なぜなら、自分がこの家を出れば、その後にお葉を迎え入れることができる。しかも、自分と妹は腹違い、紀美子はお葉の娘なのだから。健吉とお葉、紀美子の三人で暮らせるようにすることが、邦江の「幸せ」なのである。しかし、紀美子はそのことを知らない。紀美子はお葉を、父の「妾」に過ぎないと敬遠気味であった。
邦江は、自分の「幸せ」を実現するために、お葉自身、祖父、伯父、そして父に「話をつける」。お葉を迎え入れることは、皆が同意、それとなく紀美子にも話して見たのだが「私、お父さんのお妾サンなんて、お母さんと呼べないわ」という答であった。
邦江の縁談は、妙な方向に進んでしまった。相手の新太郎は、付き添った紀美子の方を気に入っった様子、伯父は「あんなお転婆のどこがいいのやら。今の若い者の気持ちがわからない」と嘆く。「でも、この縁談は紀美子の方に変えようか」と持ちかけるが、健吉は不同意、「邦江の気持ちも察してやらねば」と、このことは邦江にも紀美子にも隠しておこうということになった。
しかし、紀美子と新太郎は、銀座(?)で偶然再会、逢瀬を重ねるようになる。今度は、そのことを知らない邦江と健吉・・・。
一方、邦江は、お葉宅からの帰り道、浅草(?)で、家具屋を除いている祖父を見つけた。「着物屋ではなく家具屋を覗くなんて珍しいわね」と言うと「なあに、お前の縁談もあることだからね。でも金は無い。明日は明日の風が吹くだよ。それにしても最近のお父さんは焦っているのではないか、店の酒の味が昔と違う。お父さんが何かしているのではないか。お前が確かめてほしい」と聞かされた。ある雨の日に、健吉が一人酒蔵で何かをしている。問い詰めると「酒の味がもっとよくなる研究をしている」という答であった。
一抹の不安を抱えながら、邦江は、伯父宅に、見合いの件、お葉の件で訪れる。その帰り道で衝撃的な現場を目撃した。見合い相手の新太郎が、紀美子と連れ立っている姿である。帰宅して紀美子に質すと「お姉さんは何も知らないのよ。新太郎さんは私をお嫁に欲しいと言っているの。叔父さんもお父さんもそのことを知っているのに隠している。私は、偶然、新太郎さんに会って、その話を聞いたのよ」。
打ちひしがれた邦江は帳場で泣いている。健吉が見咎めて「どうかしたのか」と問いかけたが「何でもありません」と答えるだけであった。
健吉は、お葉の店を訪ねる。「幸い、良い買手がつきそうです」「すまない」「私は一人でも暮らしていけます」。お葉は、邦江にいい婿を迎え灘屋を再建してもらいたい、自分は娘の紀美子と暮らせればよい、という考えもよぎったか。「明日、紀美子の誕生日だ。その機会に、実母として紹介しよう」と健吉は帰って行った。
いよいよ大詰め、灘屋の一室では紀美子の誕生祝い、友だちが集まって新太郎からのプレゼント(西洋人形)を眺め、ジャズのレコードで踊っている。そんな折り、伯父から突然の電話が入った。「新太郎の親から、紀美子さんを欲しいと言ってきている。紀美子の気持ちを聞いて欲しい」驚いた健吉「ともかく、聞いてみる」と電話を切る。そこにお葉が訪れた。「二階で待っていてくれ」と言い、紀美子を呼び出す。「お前、お父さんやお姉さんに内緒で、佐藤の倅と親しくしていたというじゃないか。どんなつもりだったんだ!」「・・・・」「お前は、姉さんがどんなに優しい気持ちでお前や、お前のお母さんのことを考えていてくれたか、わかるまい」。一瞬、紀美子の表情が変わった。「今日は、お前に会わせたい人が居る。来なさい」と二階に連れて行く。待っているお葉。見つめ合うお葉と紀美子・・・。お葉の視線は熱い。紀美子の視線は冷たい。「お前を生んだお母さんだ、挨拶しなさい」。紀美子は無言、邦江がお茶を持って登ってきた。「姉さんにも、謝らなければならないだろう。お前や、お母さんや、家のことばかり考えていた姉さんの心を踏みにじったんだ。謝りなさい」邦江は「姉さんには謝らなくてもいいのよ。でも、お母さんには挨拶なさい」と取りなすが、なおも紀美子は無言、健吉はたまらず「今日こそお前のわがままを叩き直してやる」と手を上げると、「今になって、そんなこと言われるなんて、イヤです。お母さんなんていらない!、お父さんなんていらない!、この家なんていらない!」と叫ぶなり、紀美子は階段を降りていく。あわてて追いかける邦江、驚いている友だちの前で家を出る気配をみせる。二階に残されたお葉と健吉は言葉が失っているところに、使用人の小僧がやってきた。「警察の人が来ています。旦那に用があるそうです」。
向かいの床屋では隠居の啓介が髭を当たってもらっていたが、店の前がただならぬ様子、刑事、警官、野次馬で人だかりができている。床屋が「何か、あったんでしょうか」と心配そうに問いかけるが「なあに、何でもありませんよ」。店を出ると健吉が近づいて「すみません」と頭を下げた。「いいとも、いいとも、なるようになっただけだよ。ああ、行っといで」と優しくねぎらう。床屋が「これからどうなるんでしょう」「看板が変わるだけだ」と吐き捨てた。
店に残された邦江たち、紀美子はボストンバックを手にして家を出て行こうとするのだが・・・、お葉が紀美子をじっと見つめる。紀美子も見つめ直したとき、ボストンバックは足元に落ちた。その後の経過は誰にもわからない。
床屋では、亭主が次の客(滝沢修?)に向かって「とうとう灘屋も駄目になりましたね。次は何屋になるんでしょう」と言えば、客は笑いながら「いくらか賭けようか」「ようございますとも、また酒屋かな、それとも八百屋かな、八百屋はすぐ近くにあるし・・・」などと思案するうちに、この映画は「終」となった。
登場人物の隠居・啓作、主人・健介、長女・邦江、伯父、妾・お葉たちは、いずれも和服姿、次女・紀美子と新太郎は洋服姿というコントラストが「生き様」の違いを象徴している。和服姿は、江戸、明治、大正、昭和へと伝統を継承する立場、それに対して、洋服姿は伝統に抗う、洋式の生活意識を求めている。啓作が三味線をつま弾き、俗曲を披露すれば、紀美子はジャズのレコード、ソーシャル・ダンスで対抗する。和服派が重んじるのは「細やかな心づかい」、あくまでも他人との義理・人情を大切にするが、洋服派にとって大事なのは「自己」と「自我」、とりわけ「女が男の犠牲になること」を嫌うフェミニズムなのである。
この映画の眼目は、酒屋の名店が「没落」する姿を通して、「滅びの美学」を描出することにあったのか、洋風文化への転換期を描きたかったのか、判然としない。成瀬監督の真骨頂は、同年前作の映画『女優と詩人』に代表されるフェミニズム、「女の逞しさ・したたかさ」だと思われるが、この映画では、和風への「未練」、伝統への「執着」も、いささか感じられた。それというのも、主役を演じた千葉早智子の存在があったからか。彼女は数年後、成瀬監督の夫人に収まる身、その魅力を、和風にするか洋風にするか、という成瀬監督の「迷い」があったとすれば、「むべなるかな」と納得できる。
いずれにしても、お互いの気持ち、心情を重ねようとする人たちと、陋習を打破して自己主張を大切にする人たちが織りなす人間模様の描出は鮮やかであった。なかでも、悠々と江戸好みの風情を楽しむ隠居老人・啓作を演じた汐見洋の魅力が光っていた。成瀬監督にしては異色の「傑作」であった、と私は思う。(2017.5.26)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

邦江は、自分の「幸せ」を実現するために、お葉自身、祖父、伯父、そして父に「話をつける」。お葉を迎え入れることは、皆が同意、それとなく紀美子にも話して見たのだが「私、お父さんのお妾サンなんて、お母さんと呼べないわ」という答であった。
邦江の縁談は、妙な方向に進んでしまった。相手の新太郎は、付き添った紀美子の方を気に入っった様子、伯父は「あんなお転婆のどこがいいのやら。今の若い者の気持ちがわからない」と嘆く。「でも、この縁談は紀美子の方に変えようか」と持ちかけるが、健吉は不同意、「邦江の気持ちも察してやらねば」と、このことは邦江にも紀美子にも隠しておこうということになった。
しかし、紀美子と新太郎は、銀座(?)で偶然再会、逢瀬を重ねるようになる。今度は、そのことを知らない邦江と健吉・・・。
一方、邦江は、お葉宅からの帰り道、浅草(?)で、家具屋を除いている祖父を見つけた。「着物屋ではなく家具屋を覗くなんて珍しいわね」と言うと「なあに、お前の縁談もあることだからね。でも金は無い。明日は明日の風が吹くだよ。それにしても最近のお父さんは焦っているのではないか、店の酒の味が昔と違う。お父さんが何かしているのではないか。お前が確かめてほしい」と聞かされた。ある雨の日に、健吉が一人酒蔵で何かをしている。問い詰めると「酒の味がもっとよくなる研究をしている」という答であった。
一抹の不安を抱えながら、邦江は、伯父宅に、見合いの件、お葉の件で訪れる。その帰り道で衝撃的な現場を目撃した。見合い相手の新太郎が、紀美子と連れ立っている姿である。帰宅して紀美子に質すと「お姉さんは何も知らないのよ。新太郎さんは私をお嫁に欲しいと言っているの。叔父さんもお父さんもそのことを知っているのに隠している。私は、偶然、新太郎さんに会って、その話を聞いたのよ」。
打ちひしがれた邦江は帳場で泣いている。健吉が見咎めて「どうかしたのか」と問いかけたが「何でもありません」と答えるだけであった。
健吉は、お葉の店を訪ねる。「幸い、良い買手がつきそうです」「すまない」「私は一人でも暮らしていけます」。お葉は、邦江にいい婿を迎え灘屋を再建してもらいたい、自分は娘の紀美子と暮らせればよい、という考えもよぎったか。「明日、紀美子の誕生日だ。その機会に、実母として紹介しよう」と健吉は帰って行った。
いよいよ大詰め、灘屋の一室では紀美子の誕生祝い、友だちが集まって新太郎からのプレゼント(西洋人形)を眺め、ジャズのレコードで踊っている。そんな折り、伯父から突然の電話が入った。「新太郎の親から、紀美子さんを欲しいと言ってきている。紀美子の気持ちを聞いて欲しい」驚いた健吉「ともかく、聞いてみる」と電話を切る。そこにお葉が訪れた。「二階で待っていてくれ」と言い、紀美子を呼び出す。「お前、お父さんやお姉さんに内緒で、佐藤の倅と親しくしていたというじゃないか。どんなつもりだったんだ!」「・・・・」「お前は、姉さんがどんなに優しい気持ちでお前や、お前のお母さんのことを考えていてくれたか、わかるまい」。一瞬、紀美子の表情が変わった。「今日は、お前に会わせたい人が居る。来なさい」と二階に連れて行く。待っているお葉。見つめ合うお葉と紀美子・・・。お葉の視線は熱い。紀美子の視線は冷たい。「お前を生んだお母さんだ、挨拶しなさい」。紀美子は無言、邦江がお茶を持って登ってきた。「姉さんにも、謝らなければならないだろう。お前や、お母さんや、家のことばかり考えていた姉さんの心を踏みにじったんだ。謝りなさい」邦江は「姉さんには謝らなくてもいいのよ。でも、お母さんには挨拶なさい」と取りなすが、なおも紀美子は無言、健吉はたまらず「今日こそお前のわがままを叩き直してやる」と手を上げると、「今になって、そんなこと言われるなんて、イヤです。お母さんなんていらない!、お父さんなんていらない!、この家なんていらない!」と叫ぶなり、紀美子は階段を降りていく。あわてて追いかける邦江、驚いている友だちの前で家を出る気配をみせる。二階に残されたお葉と健吉は言葉が失っているところに、使用人の小僧がやってきた。「警察の人が来ています。旦那に用があるそうです」。
向かいの床屋では隠居の啓介が髭を当たってもらっていたが、店の前がただならぬ様子、刑事、警官、野次馬で人だかりができている。床屋が「何か、あったんでしょうか」と心配そうに問いかけるが「なあに、何でもありませんよ」。店を出ると健吉が近づいて「すみません」と頭を下げた。「いいとも、いいとも、なるようになっただけだよ。ああ、行っといで」と優しくねぎらう。床屋が「これからどうなるんでしょう」「看板が変わるだけだ」と吐き捨てた。
店に残された邦江たち、紀美子はボストンバックを手にして家を出て行こうとするのだが・・・、お葉が紀美子をじっと見つめる。紀美子も見つめ直したとき、ボストンバックは足元に落ちた。その後の経過は誰にもわからない。
床屋では、亭主が次の客(滝沢修?)に向かって「とうとう灘屋も駄目になりましたね。次は何屋になるんでしょう」と言えば、客は笑いながら「いくらか賭けようか」「ようございますとも、また酒屋かな、それとも八百屋かな、八百屋はすぐ近くにあるし・・・」などと思案するうちに、この映画は「終」となった。
登場人物の隠居・啓作、主人・健介、長女・邦江、伯父、妾・お葉たちは、いずれも和服姿、次女・紀美子と新太郎は洋服姿というコントラストが「生き様」の違いを象徴している。和服姿は、江戸、明治、大正、昭和へと伝統を継承する立場、それに対して、洋服姿は伝統に抗う、洋式の生活意識を求めている。啓作が三味線をつま弾き、俗曲を披露すれば、紀美子はジャズのレコード、ソーシャル・ダンスで対抗する。和服派が重んじるのは「細やかな心づかい」、あくまでも他人との義理・人情を大切にするが、洋服派にとって大事なのは「自己」と「自我」、とりわけ「女が男の犠牲になること」を嫌うフェミニズムなのである。
この映画の眼目は、酒屋の名店が「没落」する姿を通して、「滅びの美学」を描出することにあったのか、洋風文化への転換期を描きたかったのか、判然としない。成瀬監督の真骨頂は、同年前作の映画『女優と詩人』に代表されるフェミニズム、「女の逞しさ・したたかさ」だと思われるが、この映画では、和風への「未練」、伝統への「執着」も、いささか感じられた。それというのも、主役を演じた千葉早智子の存在があったからか。彼女は数年後、成瀬監督の夫人に収まる身、その魅力を、和風にするか洋風にするか、という成瀬監督の「迷い」があったとすれば、「むべなるかな」と納得できる。
いずれにしても、お互いの気持ち、心情を重ねようとする人たちと、陋習を打破して自己主張を大切にする人たちが織りなす人間模様の描出は鮮やかであった。なかでも、悠々と江戸好みの風情を楽しむ隠居老人・啓作を演じた汐見洋の魅力が光っていた。成瀬監督にしては異色の「傑作」であった、と私は思う。(2017.5.26)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-30
付録・邦画傑作選・「落第はしたけれど」(監督・小津安二郎・1930年)
ユーチューブで映画「落第はしたけれど」(監督・小津安二郎・1930年)を観た。前作「学生ロマン若き日」の続編である。W大学応援部の高橋(齋藤達雄)たちは、いよいよ卒業試験の時期を迎えた。試験場では監督(大国一郎?)の目を盗みあちこちでカンニング、その方法も様々である。学生同士は皆「仲間」、高橋が後ろを見て「三」と指で示せば、すかさず学友が「三」の答を紙に書き(机間巡視中の)監督の背中に貼り付ける。監督が高橋の脇を通り過ぎる瞬間にそれを取ろうとするのだが、監督が振り向いた。あわてて手を引っ込め時計を見る。そのやりとりを繰り返す光景が何とも可笑しかった。その日の試験は終了、高橋たちは下宿に戻る。そこは賄い付きの大部屋、五、六人の学生がひしめき合って
いる。配役の字幕には、落第生・横尾泥海男、関時男、及第生・月田一郎、笠智衆などと
記されているが、笠智衆の他は誰が誰やら、判然としなかった。高橋は明日の試験のためにカンニングの準備、白いワイシャツの背中一面に答案を綴る。一同は勉強に疲れ眠気が襲ってきた。「何か食べよう」と二階の窓を開けて、向かいの喫茶店に声をかける。顔を出したの看板娘(田中絹代)。どうやら高橋とは恋仲の様子。おか持ちにサンドイッチを積んで持ってきた。取り次ぎに出た下宿屋の息子(青木富夫)もおこぼれを頂戴する。和気藹々の空気が爽やかである。娘は帰り際、高橋を呼んで角砂糖をプレゼント、卒業祝いのネクタイも編んでいるらしい。やがて、一同は雑魚寝状態で眠りに就いた。
翌朝、「朝だよ!早く皆起きて!」と、下宿のおばさん(二葉かほる)が入ってくる。
あたりを見回せば部屋は散らかり放題、一同を叩き起こして汚れ物をまとめる。ふと目に付いたのは白いワイシャツ、それも一緒に持ち去ってしまった。最後に起き出した高橋、ワイシャツは?と探したが後の祭り、おばさんが出前のクリーニングに出してしまったとは・・・。
かくて卒業試験は終了、卒業生名簿が掲示された。経済学部77名の名が記されていたが、高橋の氏名はない。一人の学生が学務課に泣きついている。「よく調べて下さい」「成績が悪いんだからしょうがない」などと問答をしている。高橋は肩を落として庭に出ると、同様に落第した応援部の仲間4人が待っていた。でも、屈託がない。肩を組み、足を踏みならして「四月にまた会おう」、落第なんてどこ吹く風と別れて行った。
高橋は喫茶店に戻り、独りケーキを食べている。そこに学務課に泣きついた学生が入ってきた。「何とか及第したよ。君からいろいろ教えてもらっていたのに、申し訳ない」と謝れば「おめでとう」と応じる。しかし、淋しさ、悔しさは隠せない。そこにやって来たのは娘、あわてて席をはずしていった学生を見て「あの方、どうだったの」「何とかビリで卒業できたよ」「そう、でもこれからの就職が大変ね。あなたは運動部だから安心だけど」、娘はまだ高橋の落第を知らないらしい。そこにどやどやと及第組の学生たちが入ってきた。「それじゃあ」と高橋は出て行く。
下宿に戻った高橋、しげしげと握り鋏(和鋏)を見つめている。おもむろにその先端を
喉に突き立てようとして引っ込める。やがて足袋を脱ぎ足の爪を切り始める。そこに息子がやって来た。「御飯を用意したから、皆で一緒に食べようよ」。しかし、自分以外は皆及第なので気が進まない。躊躇しているとビリで卒業する学生が誘いに来た。「売り払った本を買い戻してくる」と外出の素振りを見せるが「自分の本を使えばいい、皆あげるよ」。とうとう祝いの席に連れて行かれた。
おばさんの手料理(チラシ?赤飯?ビールもある)が待っている。「それにしても高橋さんだけ落第だなんて気の毒ね」。息子が「ラクダイって何だい?」と尋ねるが、一同は俯いて応えられない。「ねえ、ラクダイって何さ」と再度尋ねれば、ビリの学生曰く「ラクダイとは偉いということだよ」・・・。
翌日、及第組は楽しそうに学生服を背広に着替えてハイキングへ。独り高橋は部屋に残り、箱入りの背広などに目をやり無聊を託ってる。机の引き出しを開けると、娘からプレゼントされた角砂糖がでてきた。それを積み上げたり、放り投げて口で受けとめる等しているところに息子がやって来た。「坊や、大きくなったら何になりたい?」「小父さんのように大学に行き、ラクダイになるんだ!」思わず、ずっこける高橋、そこに娘が訪ねてきた。あわてて息子に角砂糖をプレゼント、追い払う。娘は卒業祝いのネクタイを持ってきたのだ。箱入りの背広を取り出して「着てごらんなさいよ。よく似合うわよ。ネクタイ締めてあげるわ。今日は活動にでも行きましょうよ」。しかし、落第したことを隠している高橋の表情は冴えない。思い切って「あのね、ボクは背広を着る資格が無いんだ」と言いかけると、娘は「卒業しないからといって、背広を着てはいけなということはないわ。あたし、何もかもみんな知っているのよ。あんなに勉強したのにね」と涙ぐむ。でも二人は若い。気をとりなおして活動へ出かける・・・。
やがて4月、新学期がやって来た。しかし、なぜか卒業組の4人はまだ高橋と一緒に下宿住まい、就職出来ず、仕送りも途絶えて、背広を質屋に入れる有様で、手紙が届いたと思えば「不採用」の通知、すっかり落ち込んでいる。落第した高橋は元気いっぱい、「パンでも食べろよ」と小銭をカンパする。そして迎えに来た落第組と共に学校へ・・・。「こんなことなら、急いで卒業するんじゃなかった」とぼやく面々の姿があわれであった。学校はまもなくWK戦の季節、後輩たちを集めて応援の練習に取り組む落第組の姿が、生き生きと映されて、この映画の幕は下りる。
なるほど「落第はしたけれど」日本男児は健在なり!という「心意気」がひしひしと伝わってくる傑作であった。とりわけ、当時の「学生気質」が(エリートには違いないが、互いに相手を思いやる「温もり」)感じられて清々しく、競争にあけくれる現代の学生と一味違った人間模様が、鮮やかに描出されていた。子どもから「小父さん」と呼ばれ、タバコ、酒もたしなむ学生が、一方では「仲間と肩を組んで、ステップを踏む」「角砂糖を積木のように積み上げたかと思うと、放り投げて口で受けとめる」など愛嬌・滑稽な振る舞いを見せる「アンバランス」も魅力的であった。小津監督自身は旧制中学で寄宿舎生活を体験、その後、神戸高等商業学校、三重師範学校を受験するがいずれも「落第」(不合格)、小学校の代用教員を経て、松竹蒲田撮影所に入社した。大学生活は未経験にもかかわらず、前作の「学生ロマンス若き日」に続き、往時の「学生気質」をここまで詳細に描出できるとは驚嘆すべきことだと、私は思った。 (2017.2.17)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

いる。配役の字幕には、落第生・横尾泥海男、関時男、及第生・月田一郎、笠智衆などと
記されているが、笠智衆の他は誰が誰やら、判然としなかった。高橋は明日の試験のためにカンニングの準備、白いワイシャツの背中一面に答案を綴る。一同は勉強に疲れ眠気が襲ってきた。「何か食べよう」と二階の窓を開けて、向かいの喫茶店に声をかける。顔を出したの看板娘(田中絹代)。どうやら高橋とは恋仲の様子。おか持ちにサンドイッチを積んで持ってきた。取り次ぎに出た下宿屋の息子(青木富夫)もおこぼれを頂戴する。和気藹々の空気が爽やかである。娘は帰り際、高橋を呼んで角砂糖をプレゼント、卒業祝いのネクタイも編んでいるらしい。やがて、一同は雑魚寝状態で眠りに就いた。
翌朝、「朝だよ!早く皆起きて!」と、下宿のおばさん(二葉かほる)が入ってくる。
あたりを見回せば部屋は散らかり放題、一同を叩き起こして汚れ物をまとめる。ふと目に付いたのは白いワイシャツ、それも一緒に持ち去ってしまった。最後に起き出した高橋、ワイシャツは?と探したが後の祭り、おばさんが出前のクリーニングに出してしまったとは・・・。
かくて卒業試験は終了、卒業生名簿が掲示された。経済学部77名の名が記されていたが、高橋の氏名はない。一人の学生が学務課に泣きついている。「よく調べて下さい」「成績が悪いんだからしょうがない」などと問答をしている。高橋は肩を落として庭に出ると、同様に落第した応援部の仲間4人が待っていた。でも、屈託がない。肩を組み、足を踏みならして「四月にまた会おう」、落第なんてどこ吹く風と別れて行った。
高橋は喫茶店に戻り、独りケーキを食べている。そこに学務課に泣きついた学生が入ってきた。「何とか及第したよ。君からいろいろ教えてもらっていたのに、申し訳ない」と謝れば「おめでとう」と応じる。しかし、淋しさ、悔しさは隠せない。そこにやって来たのは娘、あわてて席をはずしていった学生を見て「あの方、どうだったの」「何とかビリで卒業できたよ」「そう、でもこれからの就職が大変ね。あなたは運動部だから安心だけど」、娘はまだ高橋の落第を知らないらしい。そこにどやどやと及第組の学生たちが入ってきた。「それじゃあ」と高橋は出て行く。
下宿に戻った高橋、しげしげと握り鋏(和鋏)を見つめている。おもむろにその先端を
喉に突き立てようとして引っ込める。やがて足袋を脱ぎ足の爪を切り始める。そこに息子がやって来た。「御飯を用意したから、皆で一緒に食べようよ」。しかし、自分以外は皆及第なので気が進まない。躊躇しているとビリで卒業する学生が誘いに来た。「売り払った本を買い戻してくる」と外出の素振りを見せるが「自分の本を使えばいい、皆あげるよ」。とうとう祝いの席に連れて行かれた。
おばさんの手料理(チラシ?赤飯?ビールもある)が待っている。「それにしても高橋さんだけ落第だなんて気の毒ね」。息子が「ラクダイって何だい?」と尋ねるが、一同は俯いて応えられない。「ねえ、ラクダイって何さ」と再度尋ねれば、ビリの学生曰く「ラクダイとは偉いということだよ」・・・。
翌日、及第組は楽しそうに学生服を背広に着替えてハイキングへ。独り高橋は部屋に残り、箱入りの背広などに目をやり無聊を託ってる。机の引き出しを開けると、娘からプレゼントされた角砂糖がでてきた。それを積み上げたり、放り投げて口で受けとめる等しているところに息子がやって来た。「坊や、大きくなったら何になりたい?」「小父さんのように大学に行き、ラクダイになるんだ!」思わず、ずっこける高橋、そこに娘が訪ねてきた。あわてて息子に角砂糖をプレゼント、追い払う。娘は卒業祝いのネクタイを持ってきたのだ。箱入りの背広を取り出して「着てごらんなさいよ。よく似合うわよ。ネクタイ締めてあげるわ。今日は活動にでも行きましょうよ」。しかし、落第したことを隠している高橋の表情は冴えない。思い切って「あのね、ボクは背広を着る資格が無いんだ」と言いかけると、娘は「卒業しないからといって、背広を着てはいけなということはないわ。あたし、何もかもみんな知っているのよ。あんなに勉強したのにね」と涙ぐむ。でも二人は若い。気をとりなおして活動へ出かける・・・。
やがて4月、新学期がやって来た。しかし、なぜか卒業組の4人はまだ高橋と一緒に下宿住まい、就職出来ず、仕送りも途絶えて、背広を質屋に入れる有様で、手紙が届いたと思えば「不採用」の通知、すっかり落ち込んでいる。落第した高橋は元気いっぱい、「パンでも食べろよ」と小銭をカンパする。そして迎えに来た落第組と共に学校へ・・・。「こんなことなら、急いで卒業するんじゃなかった」とぼやく面々の姿があわれであった。学校はまもなくWK戦の季節、後輩たちを集めて応援の練習に取り組む落第組の姿が、生き生きと映されて、この映画の幕は下りる。
なるほど「落第はしたけれど」日本男児は健在なり!という「心意気」がひしひしと伝わってくる傑作であった。とりわけ、当時の「学生気質」が(エリートには違いないが、互いに相手を思いやる「温もり」)感じられて清々しく、競争にあけくれる現代の学生と一味違った人間模様が、鮮やかに描出されていた。子どもから「小父さん」と呼ばれ、タバコ、酒もたしなむ学生が、一方では「仲間と肩を組んで、ステップを踏む」「角砂糖を積木のように積み上げたかと思うと、放り投げて口で受けとめる」など愛嬌・滑稽な振る舞いを見せる「アンバランス」も魅力的であった。小津監督自身は旧制中学で寄宿舎生活を体験、その後、神戸高等商業学校、三重師範学校を受験するがいずれも「落第」(不合格)、小学校の代用教員を経て、松竹蒲田撮影所に入社した。大学生活は未経験にもかかわらず、前作の「学生ロマンス若き日」に続き、往時の「学生気質」をここまで詳細に描出できるとは驚嘆すべきことだと、私は思った。 (2017.2.17)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-29
付録・邦画傑作選・「路上の霊魂」(監督・村田実・1921年)
ユーチューブで映画「路上の霊魂」(監督・村田実・1921年)を観た。ヴィルヘルム・シュミットボンの『街の子』(森鴎外訳)とマクシム・ゴーリキーの『夜の宿(どん底)』(小山内薫訳)が原作で、ナ、ナ、ナント、日本の演劇界の革新に半生を捧げた小山内薫自身が出演しているとは・・・。ウィキペディア百科事典では〈『路上の霊魂』は同時に進行する出来事をクロスカッティングしたり、回想場面を挿入したりする近代映画の技法をふんだんに取り入れた、日本映画初の芸術大作というべきものだった〉と紹介されている。
冒頭では「文部省推薦」という文字、タイトルに続いて「吾々は人類全体に対して憐れみの心を持たなくてはならない。例えばキリストは人類全体を憐れみ給うた。そして、吾々にもそうせよと仰せられた。人を憐れむには時がある。その時をはずさないようにせるが好い。マクシム・ゴーリキー」という文章が映し出される。
登場人物は、山奥で伐材所を営む親方・杉野泰(小山内薫)と息子の浩一郎(東郷是也、のちの鈴木伝明)、浩一郎の妻・耀子(澤村春子)、娘・文子(久松三岐子)、浩一郎の許嫁・光子(伊達竜子)、伐材所の少年・太郎(村田実、彼はこの映画の監督でもある)、
別荘の令嬢(英百合子)、別荘の執事(茂原熊彦、彼はこの映画の脚本を執筆している)、
出獄者・鶴吉(南光明)、亀三(蔦村繁)、別荘番(岡田宗太郎)、八木節の姉(東栄子)
八木節の弟(小松武雄)、クリスマスの客(春野恵美奈)といった面々である。
浩一郎には許嫁の光子がいたが、ヴァイオリニストになりたい一心で都会に出奔、杉野はやむなく光子をそばにおいて帰りを待っている。しかし浩一郎はすでにピアニストの耀子と結婚し、文子という娘までもうけていた。都会で演奏活動を始めたが、批評家との折り合いが悪く、出世の道は断たれたか・・・。今では、妻子と共に故郷に帰らざるをえない。三人は、ただただ歩き続け、空腹と疲労で行き倒れ寸前であった。そんな折り、たまたま分岐点で行き会ったのは、こちらも放浪の旅を続ける出獄者・鶴吉、亀三の二人、亀三は労咳で衰弱している。一つのパンを半分にし、それをまた等分にして朝食をすませたが、見れば娘の衰弱も甚だしい。二人は初め親子三人から何かを強奪しようとしたのだが、相手は何も持っていない。気の毒にと思い、残りのパンを娘に与えて、右の道を辿り始める。その行き着く先は軽井沢の豪華な別荘であることを知ってか、知らずか・・・。一方、浩一郎と妻子は左の道へ・・・、その先には懐かしいわが家があるのだが・・・。
山奥の別荘にはおきゃんな令嬢が居た。執事と馬車で散歩に出ても、つねに単独行動、物陰から、探し回る執事の帽子めがけて空気銃を一発発射、執事が帽子を飛ばされ慌てている間に、街中へ繰り出した。そこでは八木節の姉弟が大道芸を披露中、令嬢は拍手喝采して見物していたが、踊りを終えた弟が帽子を袋替わりに近づいても、入れるお金を持っていない。たまたま居合わせた伐材所の少年・太郎が、代わりに銅貨を入れてあげる。令嬢と太郎は顔見知り、お互いに好意を寄せていることが窺われる。やがて、執事が馬車で到着、令嬢を見つけて「お嬢様、こんなところに。さあ、家に帰りましょう」と言うが、アッカンベエをして逃げ回る。その様子は抱腹絶倒の名場面であった。
やがてもうすぐクリスマス・イヴ、別荘はその準備に余念がない。令嬢は表に八木節の姉弟が通りかかるのを見て、「今晩、来るように」と執事に言いつける。鶴吉、亀三の出獄者も別荘に辿り着いた。邸内に入り込み室内を物色中、食べ物を探しているのだ。そんなところを別荘番に見つかり、お互いを鞭打つように仕置きされたが、亀三が激しく咳き込む様子を見て、別荘番に一瞬「憐れみの情」が湧き上がったのだろう、持っていた銃を投げ出した。その様子を窺っていた令嬢は、二人を許し食べ物を準備するよう、別荘番に言いつける。
浩一郎妻子三人も、ようやく杉野の家に辿り着いたが、杉野はまだ山から帰っていない。出迎えたのは許嫁の光子、浩一郎妻子を見て複雑な気持ちを隠せなかったが、御馳走の準備を始める。まもなく杉野も帰宅、十数年ぶりの父子対面となる。「お父さん、私たち親子を温かく迎えて下さい」と、浩一郎は必死に頼んだが、許せる話ではない。杉野は思った。妻子に罪はない。しかし、浩一郎は絶対に許せない。光子が準備した御馳走も与えず「屋外に出て行け」と言い放つ。外は猛吹雪、浩一郎たち三人はやむなく納屋に避難、藁で暖をとるのだが・・・。杉野は不安になった。あの妻子はどうしているだろうか。納屋に居た三人を見つけて逡巡する。浩一郎には幻想が現れ、あげくは父に「決闘を申し込む」始末、光子もたまらずやって来て「お部屋を用意しました」と取りなした。杉野は「オカミさんと子どもは連れて行きなさい」と言ったが、今度は妻の耀子が応じない。「私はあなたと離れない」と言って浩一郎の足元に縋り付く。しかし、浩一郎はヴァイオリンの幻聴に誘われるように納屋を出て行ってしまった。そんな大人同士の葛藤の中で、娘の文子は息絶えていた。その一部始終を、なすすべもなく見届けていた太郎の悲しみ、驚愕とも悔恨ともつかぬ杉野の表情が印象的であった。
別荘では令嬢を中心にイヴのパーティーが開かれている。出獄者の鶴吉、亀三、八木節の姉弟、杉野家の使用人たちも招かれて、明るく楽しい雰囲気が満ちあふれている。やがてお開き、令嬢のベッドにはサンタクロースもプレゼントに現れた。翌日は、昨夜の猛吹雪が嘘のように晴れわたり、令嬢が屋外に飛び出した。傍には太郎も居る。二人連れだって鶴吉と亀三の「新しい門出」を見送りに出たのだ。しかし、そこで鶴吉と亀三が見たのは、林の中、雪に埋もれている浩一郎の亡骸であった。その場にやって来た令嬢がいう。「もし爺や(別荘番)が二人を憐れんでやらなかったら」(爺やは二人に殺されていたかもしれない。そして二人はまた獄舎につながれる身となったかもしれない)と言い、旅立っていく二人の方に目をやる、太郎もまた「もし旦那(杉野)がこの方を憐れんでおやりになったら」と言い亡骸に目を落とす。
そんな二人が顔を見合わせ立ち尽くすうちに、この映画は「終」を迎えた。
この映画の眼目は、ゴーリキーの言葉にあるとおり「人を憐れむには時がある。その時をはずさないようにするが好い」ということであろう。「時をはずされた」浩一郎妻子三人と、三人の窮状を憐れみ、パンを施した「時をはずさず、はずされなかった」出獄者二人の《運命》が、「同時に進行する出来事をクロスカッティングしたり、回想場面を挿入したりする近代映画の技法手法」で見事に描き出されている。まさに「日本映画初の芸術大作」というにふさわしい傑作であると、私も思った。中でも一番の魅力は、別荘の令嬢を演じた英百合子の初々しさであろうか。当時は21歳、はち切れんばかりの若さを、自由奔放、のびのびと演じている。彼女もまた少年・太郎から憐れみを施され(八木節姉弟へのカンパ代を立て替えて貰い)、出獄者二人に憐れみを施している(家に招き入れ御馳走をしている)。また、小山内薫の重厚な演技も見逃せない。「人を憐れむ時」をはずしてしまった、悔恨と苦渋の表情は真に迫っていたが、ではどうして「はずしてしまった」のだろうか。許嫁を捨て、自分本位に生きた息子をどうしても許すことができない、妻子に罪はないが、父として、男としては許せない。許嫁に何と詫びればいいのか。息子から決闘を挑まれて「まず他のことはおいても、名誉ある人間が貴様の相手になれると思うか」と吐き捨てた言葉が、すべてを物語っている。杉野は名誉を守り、息子を捨てたのである。その父親像は日本独自のものであろうか。それにしても、この作品の原作はゴーリキー・「どん底」とのこと、あらためてフランス映画「どん底」(監督・ジャン・ルノアール)を見なおしたが、共通点を見出すことはできなかった。また、少年・太郎役を演じた村田実が、その若さで監督であったとは驚きである。いずれにせよ、日本映画が小山内薫の助力により新しい一歩を踏み出した、貴重な歴史的作品を見られたことは望外の幸せであった。感謝。 (2017.7.29)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

冒頭では「文部省推薦」という文字、タイトルに続いて「吾々は人類全体に対して憐れみの心を持たなくてはならない。例えばキリストは人類全体を憐れみ給うた。そして、吾々にもそうせよと仰せられた。人を憐れむには時がある。その時をはずさないようにせるが好い。マクシム・ゴーリキー」という文章が映し出される。
登場人物は、山奥で伐材所を営む親方・杉野泰(小山内薫)と息子の浩一郎(東郷是也、のちの鈴木伝明)、浩一郎の妻・耀子(澤村春子)、娘・文子(久松三岐子)、浩一郎の許嫁・光子(伊達竜子)、伐材所の少年・太郎(村田実、彼はこの映画の監督でもある)、
別荘の令嬢(英百合子)、別荘の執事(茂原熊彦、彼はこの映画の脚本を執筆している)、
出獄者・鶴吉(南光明)、亀三(蔦村繁)、別荘番(岡田宗太郎)、八木節の姉(東栄子)
八木節の弟(小松武雄)、クリスマスの客(春野恵美奈)といった面々である。
浩一郎には許嫁の光子がいたが、ヴァイオリニストになりたい一心で都会に出奔、杉野はやむなく光子をそばにおいて帰りを待っている。しかし浩一郎はすでにピアニストの耀子と結婚し、文子という娘までもうけていた。都会で演奏活動を始めたが、批評家との折り合いが悪く、出世の道は断たれたか・・・。今では、妻子と共に故郷に帰らざるをえない。三人は、ただただ歩き続け、空腹と疲労で行き倒れ寸前であった。そんな折り、たまたま分岐点で行き会ったのは、こちらも放浪の旅を続ける出獄者・鶴吉、亀三の二人、亀三は労咳で衰弱している。一つのパンを半分にし、それをまた等分にして朝食をすませたが、見れば娘の衰弱も甚だしい。二人は初め親子三人から何かを強奪しようとしたのだが、相手は何も持っていない。気の毒にと思い、残りのパンを娘に与えて、右の道を辿り始める。その行き着く先は軽井沢の豪華な別荘であることを知ってか、知らずか・・・。一方、浩一郎と妻子は左の道へ・・・、その先には懐かしいわが家があるのだが・・・。
山奥の別荘にはおきゃんな令嬢が居た。執事と馬車で散歩に出ても、つねに単独行動、物陰から、探し回る執事の帽子めがけて空気銃を一発発射、執事が帽子を飛ばされ慌てている間に、街中へ繰り出した。そこでは八木節の姉弟が大道芸を披露中、令嬢は拍手喝采して見物していたが、踊りを終えた弟が帽子を袋替わりに近づいても、入れるお金を持っていない。たまたま居合わせた伐材所の少年・太郎が、代わりに銅貨を入れてあげる。令嬢と太郎は顔見知り、お互いに好意を寄せていることが窺われる。やがて、執事が馬車で到着、令嬢を見つけて「お嬢様、こんなところに。さあ、家に帰りましょう」と言うが、アッカンベエをして逃げ回る。その様子は抱腹絶倒の名場面であった。
やがてもうすぐクリスマス・イヴ、別荘はその準備に余念がない。令嬢は表に八木節の姉弟が通りかかるのを見て、「今晩、来るように」と執事に言いつける。鶴吉、亀三の出獄者も別荘に辿り着いた。邸内に入り込み室内を物色中、食べ物を探しているのだ。そんなところを別荘番に見つかり、お互いを鞭打つように仕置きされたが、亀三が激しく咳き込む様子を見て、別荘番に一瞬「憐れみの情」が湧き上がったのだろう、持っていた銃を投げ出した。その様子を窺っていた令嬢は、二人を許し食べ物を準備するよう、別荘番に言いつける。
浩一郎妻子三人も、ようやく杉野の家に辿り着いたが、杉野はまだ山から帰っていない。出迎えたのは許嫁の光子、浩一郎妻子を見て複雑な気持ちを隠せなかったが、御馳走の準備を始める。まもなく杉野も帰宅、十数年ぶりの父子対面となる。「お父さん、私たち親子を温かく迎えて下さい」と、浩一郎は必死に頼んだが、許せる話ではない。杉野は思った。妻子に罪はない。しかし、浩一郎は絶対に許せない。光子が準備した御馳走も与えず「屋外に出て行け」と言い放つ。外は猛吹雪、浩一郎たち三人はやむなく納屋に避難、藁で暖をとるのだが・・・。杉野は不安になった。あの妻子はどうしているだろうか。納屋に居た三人を見つけて逡巡する。浩一郎には幻想が現れ、あげくは父に「決闘を申し込む」始末、光子もたまらずやって来て「お部屋を用意しました」と取りなした。杉野は「オカミさんと子どもは連れて行きなさい」と言ったが、今度は妻の耀子が応じない。「私はあなたと離れない」と言って浩一郎の足元に縋り付く。しかし、浩一郎はヴァイオリンの幻聴に誘われるように納屋を出て行ってしまった。そんな大人同士の葛藤の中で、娘の文子は息絶えていた。その一部始終を、なすすべもなく見届けていた太郎の悲しみ、驚愕とも悔恨ともつかぬ杉野の表情が印象的であった。
別荘では令嬢を中心にイヴのパーティーが開かれている。出獄者の鶴吉、亀三、八木節の姉弟、杉野家の使用人たちも招かれて、明るく楽しい雰囲気が満ちあふれている。やがてお開き、令嬢のベッドにはサンタクロースもプレゼントに現れた。翌日は、昨夜の猛吹雪が嘘のように晴れわたり、令嬢が屋外に飛び出した。傍には太郎も居る。二人連れだって鶴吉と亀三の「新しい門出」を見送りに出たのだ。しかし、そこで鶴吉と亀三が見たのは、林の中、雪に埋もれている浩一郎の亡骸であった。その場にやって来た令嬢がいう。「もし爺や(別荘番)が二人を憐れんでやらなかったら」(爺やは二人に殺されていたかもしれない。そして二人はまた獄舎につながれる身となったかもしれない)と言い、旅立っていく二人の方に目をやる、太郎もまた「もし旦那(杉野)がこの方を憐れんでおやりになったら」と言い亡骸に目を落とす。
そんな二人が顔を見合わせ立ち尽くすうちに、この映画は「終」を迎えた。
この映画の眼目は、ゴーリキーの言葉にあるとおり「人を憐れむには時がある。その時をはずさないようにするが好い」ということであろう。「時をはずされた」浩一郎妻子三人と、三人の窮状を憐れみ、パンを施した「時をはずさず、はずされなかった」出獄者二人の《運命》が、「同時に進行する出来事をクロスカッティングしたり、回想場面を挿入したりする近代映画の技法手法」で見事に描き出されている。まさに「日本映画初の芸術大作」というにふさわしい傑作であると、私も思った。中でも一番の魅力は、別荘の令嬢を演じた英百合子の初々しさであろうか。当時は21歳、はち切れんばかりの若さを、自由奔放、のびのびと演じている。彼女もまた少年・太郎から憐れみを施され(八木節姉弟へのカンパ代を立て替えて貰い)、出獄者二人に憐れみを施している(家に招き入れ御馳走をしている)。また、小山内薫の重厚な演技も見逃せない。「人を憐れむ時」をはずしてしまった、悔恨と苦渋の表情は真に迫っていたが、ではどうして「はずしてしまった」のだろうか。許嫁を捨て、自分本位に生きた息子をどうしても許すことができない、妻子に罪はないが、父として、男としては許せない。許嫁に何と詫びればいいのか。息子から決闘を挑まれて「まず他のことはおいても、名誉ある人間が貴様の相手になれると思うか」と吐き捨てた言葉が、すべてを物語っている。杉野は名誉を守り、息子を捨てたのである。その父親像は日本独自のものであろうか。それにしても、この作品の原作はゴーリキー・「どん底」とのこと、あらためてフランス映画「どん底」(監督・ジャン・ルノアール)を見なおしたが、共通点を見出すことはできなかった。また、少年・太郎役を演じた村田実が、その若さで監督であったとは驚きである。いずれにせよ、日本映画が小山内薫の助力により新しい一歩を踏み出した、貴重な歴史的作品を見られたことは望外の幸せであった。感謝。 (2017.7.29)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-28
付録・邦画傑作選・「淑女と髭」(監督・小津安二郎・1931年)
サイレント喜劇映画の傑作である。冒頭は剣道の大会場面、皇族の審判長(突貫小僧)も臨席しているが、興味なさそうに何かを吹き飛ばして遊んでいる。学生の岡島(岡田時彦)が次々と勝ち進み敵(学習院?)の大将(齋藤達雄)と対決する。しかし、岡島の戦法は「いい加減」、試合を中断する素振りを見せ、敵が油断した隙を突いて「面」を取るという、極めてアンフェアな技を駆使する。それを知り尽くしている大将も同じ戦法で臨んだが、「いい加減さ」では岡島の方が上、あえなく一本「胴」を取られてしまった(剣道大会そのものが戯画化されていることは興味深い)。大喜びする学生の応援団、その中でも親友の行本(月田一郎)は「岡島の胴は天下無敵だなあ」と感嘆する。優勝した岡島が面を外すと、鍾馗(しょうき)然とした髭面が現れた。試合後、行本は「おめでとう!今日は妹の誕生日だし家に来いよ。祝杯をあげよう」と岡島を誘う。
行本家では妹・幾子(飯塚敏子)の誕生パーティーが始まろうとしている。行本は家令(坂本武)と新聞紙を丸めた刀で剣道の真似事、立場は行本が上だが腕は家令が上、「若様、ゴメン」と一本取られてしまった。憤然とする行本、平謝りの家令、その場の様子が聞こえてくるようで、たいそう面白かった。
一方、岡島は、学帽に羽織袴、朴歯に杖というバンカラ姿で行本家に向かう。その途中、若い女同士が道ばたで揉めていた。洋装の不良モガ(伊達里子)が和服のタイピスト広子(川崎弘子)から金を脅し取ろうとしているらしい。しつこくつきまとい金を巻き上げた瞬間、腕を掴まれた。岡島が助け船を出したのだ。蟇口を取り戻し「早く、お帰んなさい」と広子を退かせる。すかさずやって来たのが与太者二人、「余計なマネをしてくれたな」と殴りかかってくるのを、一人は「胴」、もう一人は「小手」と杖の早業、なるほど「岡島の胴は天下無敵」であったのだ。「おぼえていやがれ」というモガに「その不格好な洋装は忘れられんよ」と笑い飛ばし、「失敬」と去って行く姿が実に爽やかであった。
岡島が行本邸に着くと、誕生パーティーが始まっていた。あたりを見回して「女ばかりじゃないか」と不満そう、幾子も「またあの髭ッ面を連れてきたの。時代遅れであたしダイッキライ」と行本を責める。「いいじゃあないか、お前たちが感化してモダンにしてくれよ」ととりなすが、岡島は挨拶の後、イスに座り込んでケーキを食べまくる始末、幾子は行本を引っ張り、その場から出て行ってしまった。残った女友達6人(その中には井上雪子も居る)、岡島に恥をかかせようと相談「一緒に踊ってくれませんか」。岡島「二人では無理ですが一人なら踊れます」。・・・、家令の詩吟で剣舞(「城山」?)を踊り出す。その姿は抱腹絶倒、「天下無敵」の名舞台であった。しかし、女友達一同は、呆れかえって早々に帰ってしまった。それを知って泣き出す幾子・・・。私の笑いは止まらなかった。 やがて、大学は「就活」の季節。岡島も髭面で面接試験を受けに行く。その会社の受け付けにいたのは偶然にもタイピストの広子、さらにまた偶然に社長も(岡島より貧相な)髭面、結果は不合格であった。広子は岡島のアパートを訪ね、「あなたが不合格になったのは髭の所為、お剃りになれば・・・」と勧める。またまた偶然にもアパートの隣は床屋であった。
広子の助言に従った岡島はたちまちホテルに採用される。その報告をしに行本家へ、行本は残念がったが、幾子は大満足、すっかり岡島に惚れ込んでしまったか・・・、上流階級の見合い相手、モボ(南條康雄)に向かって「剣道をしない人とは結婚いたしません」「なぜです?」「私の身を守っていただけないから」「警察と治安維持法が守ってくれますよ」「それならあたし警察か、治安維持法と結婚します」といった「やりとり」が、当時の世相を反映して(皮肉って)、たいそう興味深かった。小津監督の反骨に拍手する。 岡島は広子の家にも報告・御礼に訪れたが、広子の母(飯田蝶子)はセールスと間違えて玄関払い、様子を見に来た広子に「私を助けてくれた岡島さんじゃないの」と言われ、ビックリ仰天、一転して愛嬌を振りまく景色には大笑い。広子もまた小父さんが持ちかけてきた縁談を断って、岡島に嫁ぎたいと言う。母はやむなく、岡島の真意を確かめに勤め先のホテルへ・・・。岡島の仕事はフロント係。母からの話は「願ってもないこと」と快諾して持ち場についたのだが、ホテルにたむろする不良のモガ一味、盗品の隠匿?、売買?に巻き込まれたか・・・?(モガが、ホテルで食事中の客から掏り取ったブローチを手紙に包んでフロントに投げ込んだように見えたが、手紙の文字が判読できないので詳細は不明)夜の7時、モガがハイヤーでホテルに乗りつけた。なぜか髭をつけた岡島、その車に乗り込み、モガを自分のアパートに連れて行く。部屋に入った二人・・・、岡島はモガに向かって「両親はいないのか、兄弟は?」などと尋ねるが「あたいは前科者」という答が返ってくるだけ。着替えようとして着物がほころびているのに気がついた。それを縫おうとすれば、モガが取り上げて縫おうとする。しかし、縫い物は二人とも苦手、そこは洗濯ばさみではさんでズボンを脱いだ。モガが「あたい、あんたが看てくれるならまともになろうと思うんだ」などと言った時、突然入り口のドアが開いて、行本、母(吉川満子)、幾子が訪れた。縁談話を持ってきた様子、しかし、女が居る。母は「まあ、汚らわしい。だから言わないこっちゃない。所詮釣り合わないことなんだ!」と呆れ、涙ぐむ幾子を急かせて出て行く。行本は「すまん!」と笑顔混じりに帰って行った。
いよいよ大詰め、翌朝、今度は広子がアパートにいそいそとやって来る。ドアをノックすれば出てきたのはモガ、「あなたは、どなた?」(もないもんだ!いつか喝上げをした相手をもう忘れているとは・・・)広子は毅然と「私は岡島さんの恋人です」と言い放ち入室する。部屋の隅では岡島が剣道着のまま寝込んでいる。ほころびたままの着物を被りながら・・・、広子はそれを手に取り洗濯ばさみをはずしながら、一針、一針縫い始めた。その様子をじっと見ているモガ。やがて、岡島が目をさました。広子を見て「この女が居るのに、よく帰ってしまわなかったね」「ええ、私、確信していますから」。岡島、思わず「偉い!」と叫んで広子の手を握りしめる。・・・二人の様子を見ていたモガ、意を決したように「岡島さん、あたい、もう帰るよ」「また、仲間の所へか」「ううん、あたい、あんたが忠告してくれたようにするよ。この方のように、確信をもって生きていくんだ」と言う。そして広子に頭を下げた。頬笑んで送り出す広子に微笑み返す。やがて、窓から見送る二人に何度も頭を下げ、最後は大きく手を振ってモガの姿は見えなくなった。
映画の前半はスラップ・スティックコメディ、後半はラブ・ロマンスに転じ、ハッピーエンドで大団円となる。思いが叶わなかったのは、上流階級の面々といった演出が小気味よく、さわやかな感動をおぼえた。また、行本が妹・幾子に「髭を生やした偉人」を次々に紹介、その中にカール・マルクス(の写真)まで含まれていようとは驚きである。さらにまた、岡島が広子から「どうして髭をお生やしになりますの」と問われ、リンカーンの肖像画を指さして「女よけです」と答えると、クスリと笑って「無理ですわ」と広子が応じる場面もお見事、「剃っても刈っても生えるのは髭である」(アブラハム・リンカーン)というエンディングの字幕がひときわ印象的な余韻を残していた。(2017.2.16)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

行本家では妹・幾子(飯塚敏子)の誕生パーティーが始まろうとしている。行本は家令(坂本武)と新聞紙を丸めた刀で剣道の真似事、立場は行本が上だが腕は家令が上、「若様、ゴメン」と一本取られてしまった。憤然とする行本、平謝りの家令、その場の様子が聞こえてくるようで、たいそう面白かった。
一方、岡島は、学帽に羽織袴、朴歯に杖というバンカラ姿で行本家に向かう。その途中、若い女同士が道ばたで揉めていた。洋装の不良モガ(伊達里子)が和服のタイピスト広子(川崎弘子)から金を脅し取ろうとしているらしい。しつこくつきまとい金を巻き上げた瞬間、腕を掴まれた。岡島が助け船を出したのだ。蟇口を取り戻し「早く、お帰んなさい」と広子を退かせる。すかさずやって来たのが与太者二人、「余計なマネをしてくれたな」と殴りかかってくるのを、一人は「胴」、もう一人は「小手」と杖の早業、なるほど「岡島の胴は天下無敵」であったのだ。「おぼえていやがれ」というモガに「その不格好な洋装は忘れられんよ」と笑い飛ばし、「失敬」と去って行く姿が実に爽やかであった。
岡島が行本邸に着くと、誕生パーティーが始まっていた。あたりを見回して「女ばかりじゃないか」と不満そう、幾子も「またあの髭ッ面を連れてきたの。時代遅れであたしダイッキライ」と行本を責める。「いいじゃあないか、お前たちが感化してモダンにしてくれよ」ととりなすが、岡島は挨拶の後、イスに座り込んでケーキを食べまくる始末、幾子は行本を引っ張り、その場から出て行ってしまった。残った女友達6人(その中には井上雪子も居る)、岡島に恥をかかせようと相談「一緒に踊ってくれませんか」。岡島「二人では無理ですが一人なら踊れます」。・・・、家令の詩吟で剣舞(「城山」?)を踊り出す。その姿は抱腹絶倒、「天下無敵」の名舞台であった。しかし、女友達一同は、呆れかえって早々に帰ってしまった。それを知って泣き出す幾子・・・。私の笑いは止まらなかった。 やがて、大学は「就活」の季節。岡島も髭面で面接試験を受けに行く。その会社の受け付けにいたのは偶然にもタイピストの広子、さらにまた偶然に社長も(岡島より貧相な)髭面、結果は不合格であった。広子は岡島のアパートを訪ね、「あなたが不合格になったのは髭の所為、お剃りになれば・・・」と勧める。またまた偶然にもアパートの隣は床屋であった。
広子の助言に従った岡島はたちまちホテルに採用される。その報告をしに行本家へ、行本は残念がったが、幾子は大満足、すっかり岡島に惚れ込んでしまったか・・・、上流階級の見合い相手、モボ(南條康雄)に向かって「剣道をしない人とは結婚いたしません」「なぜです?」「私の身を守っていただけないから」「警察と治安維持法が守ってくれますよ」「それならあたし警察か、治安維持法と結婚します」といった「やりとり」が、当時の世相を反映して(皮肉って)、たいそう興味深かった。小津監督の反骨に拍手する。 岡島は広子の家にも報告・御礼に訪れたが、広子の母(飯田蝶子)はセールスと間違えて玄関払い、様子を見に来た広子に「私を助けてくれた岡島さんじゃないの」と言われ、ビックリ仰天、一転して愛嬌を振りまく景色には大笑い。広子もまた小父さんが持ちかけてきた縁談を断って、岡島に嫁ぎたいと言う。母はやむなく、岡島の真意を確かめに勤め先のホテルへ・・・。岡島の仕事はフロント係。母からの話は「願ってもないこと」と快諾して持ち場についたのだが、ホテルにたむろする不良のモガ一味、盗品の隠匿?、売買?に巻き込まれたか・・・?(モガが、ホテルで食事中の客から掏り取ったブローチを手紙に包んでフロントに投げ込んだように見えたが、手紙の文字が判読できないので詳細は不明)夜の7時、モガがハイヤーでホテルに乗りつけた。なぜか髭をつけた岡島、その車に乗り込み、モガを自分のアパートに連れて行く。部屋に入った二人・・・、岡島はモガに向かって「両親はいないのか、兄弟は?」などと尋ねるが「あたいは前科者」という答が返ってくるだけ。着替えようとして着物がほころびているのに気がついた。それを縫おうとすれば、モガが取り上げて縫おうとする。しかし、縫い物は二人とも苦手、そこは洗濯ばさみではさんでズボンを脱いだ。モガが「あたい、あんたが看てくれるならまともになろうと思うんだ」などと言った時、突然入り口のドアが開いて、行本、母(吉川満子)、幾子が訪れた。縁談話を持ってきた様子、しかし、女が居る。母は「まあ、汚らわしい。だから言わないこっちゃない。所詮釣り合わないことなんだ!」と呆れ、涙ぐむ幾子を急かせて出て行く。行本は「すまん!」と笑顔混じりに帰って行った。
いよいよ大詰め、翌朝、今度は広子がアパートにいそいそとやって来る。ドアをノックすれば出てきたのはモガ、「あなたは、どなた?」(もないもんだ!いつか喝上げをした相手をもう忘れているとは・・・)広子は毅然と「私は岡島さんの恋人です」と言い放ち入室する。部屋の隅では岡島が剣道着のまま寝込んでいる。ほころびたままの着物を被りながら・・・、広子はそれを手に取り洗濯ばさみをはずしながら、一針、一針縫い始めた。その様子をじっと見ているモガ。やがて、岡島が目をさました。広子を見て「この女が居るのに、よく帰ってしまわなかったね」「ええ、私、確信していますから」。岡島、思わず「偉い!」と叫んで広子の手を握りしめる。・・・二人の様子を見ていたモガ、意を決したように「岡島さん、あたい、もう帰るよ」「また、仲間の所へか」「ううん、あたい、あんたが忠告してくれたようにするよ。この方のように、確信をもって生きていくんだ」と言う。そして広子に頭を下げた。頬笑んで送り出す広子に微笑み返す。やがて、窓から見送る二人に何度も頭を下げ、最後は大きく手を振ってモガの姿は見えなくなった。
映画の前半はスラップ・スティックコメディ、後半はラブ・ロマンスに転じ、ハッピーエンドで大団円となる。思いが叶わなかったのは、上流階級の面々といった演出が小気味よく、さわやかな感動をおぼえた。また、行本が妹・幾子に「髭を生やした偉人」を次々に紹介、その中にカール・マルクス(の写真)まで含まれていようとは驚きである。さらにまた、岡島が広子から「どうして髭をお生やしになりますの」と問われ、リンカーンの肖像画を指さして「女よけです」と答えると、クスリと笑って「無理ですわ」と広子が応じる場面もお見事、「剃っても刈っても生えるのは髭である」(アブラハム・リンカーン)というエンディングの字幕がひときわ印象的な余韻を残していた。(2017.2.16)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-27
付録・邦画傑作選・《「驟雨」(監督・成瀬巳喜男・昭和31年)》
結婚してから四年、まだ子どもは生まれない。これからも期待できないだろう。たまの日曜日だというのに、夫婦には予定がない。朝食後、妻は編み物をし、夫は庭を眺める。夫が欠伸をすれば、妻もつられて欠伸をする。夫婦の会話。夫「晩のおかずは何だい?」妻「晩は未定です」夫「何かご馳走していただけますか?」妻「・・・(無言)」。夫は横腹をさすりながら「胃薬を飲み忘れた」と言う。妻は黙ってコップの水と薬瓶を差し出す。再び夫婦の会話。夫「散歩に行こうか、それとも・・・。ちょっと遅いかなあ、もう・・」妻「でも、多摩川か井の頭ぐらいなら・・・」夫「子どもみたいだなあ。いい年をして・・・」妻「いいじゃないの」夫「君の所にいくらある?」妻「もうイヤ。日曜日のたんびに・・・」夫は投げやりに呟く。「行くんなら前の日に決めておかなくちゃ・・・」
これは、昭和三十一年に封切られた映画「驟雨」(監督・成瀬巳喜男 脚本・水木洋子)の冒頭場面である。夫は佐野周二、妻は原節子、早くも倦怠期に入った夫婦の雰囲気が、見事に描き出されていた。実を言えば、この二人、その七年前(昭和二十四年封切)に「お嬢さん乾杯」(監督・木下恵介 脚本・新藤兼人)でも共演しているのである。戦後没落した華族のお嬢さん(原節子)が、復興景気に乗った自動車会社の若社長(佐野周二)と見合いし、婚約するまでの物語である。「住んでる世界がまったく違う」深窓の令嬢と田舎出の成金社長が、様々な齟齬を重ねながら、「お嬢さん」が庶民の世界に飛び降りる決心をしたところで終幕となった。「あの人はどんなにお嬢さんに惚れていたかしれませんよ」とバーのマダムに告げられ、「(わたくしも)惚れております」というセリフを残して佐野周二を追いかける時、あの名曲「旅の夜風」が行進曲のように流れた幕切れは、新しい戦後社会の「はじまり」を予感するのに十分であった。二人は、幸せになるに違いない。明るい家庭を築き、いつまでも楽しく「惚れ合って」暮らしてほしい。誰もがそのように祈ったはずであった。
だが、しかし、である。「驟雨」の佐野周二からは、「若社長」時代のエネルギー、バイタリティーがすっかり消え失せていた。かつては、「お金なんかいくらでももうかる」と豪語し、没落した「お嬢さん一族」の借金百万円をプレゼント、自分はいさぎよく身を引こうとした「男気」はどこへ行ってしまったのか。十万円の報奨金につられ、化粧品会社を早期退職して、田舎暮らしをしたいというのである。
一方、「お嬢さん・原節子」のエネルギー、バイタリティーは「驟雨」でも健在であった。新聞のレシピを切り抜いてスクラップ、見た目のグリンピースよりは、栄養満点の鮭を選び、、商店街では細切れの肉を正直に量り売りする店を見つけている。出入りしている野良犬が傷つけた鶏を飼い主から買い取り、さっさと鍋料理に調理してしまう腕前は、見事と言う他ない。夫に怒鳴られ台所で泣いているのかと思えば、平然と「お茶漬け」を掻き込んでいる。その食欲こそがすべての出発点であろう。スカートに靴下、ゲタ履きという身なりで買い物に出ても、「お嬢さん・原節子」の姿は光り輝いて見えた。夫の同僚たちは、彼女の美貌を見逃さない。バーのマダムに仕立てて、一山当てようともくろむ。「どうです?奥さん」と誘われて、「まあ、どうしましょう」と、浮かべる満面の笑みは、伝説の女優「原節子」の面目躍如というところであった。
アダムとイブの神話以来、女は男の従属物のように見なされ、男系社会が人類の歴史を作ってきたように思われているが、事実は、全く逆である。女が男よりもたくましく、「賢い」ことは、「平均寿命」の差を見れば一目瞭然であろう。したがって、いつの時代でも、どこの家庭でも「女は男より賢い」のであり、すべての妻は、妻であるということだけで、「すでに賢妻である」ということを銘記すべきである。作り話の中で、「愚かな妻」「か弱い妻」「可哀想な妻」「虐げられた妻」「耐え忍ぶ妻」などなど、女が悲劇の主役として描かれることは少なくないが、多くの場合、その作者は男であり、愚かな男の「特権意識」や「願望」が窺われて見苦しい。さらに愚かな男は、作り話を「現実」と混同し、悲劇のヒロインを「実生活」の場でも、自分の妻に演じさせようとしている。そのような傾向が現代にもあることを、私は憂慮する。末尾ながら「驟雨」の原作者は男(岸田国士)だったが、その戯曲集を脚色したのは水木洋子という才媛であったことを特記したい。(2006.4.1)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

これは、昭和三十一年に封切られた映画「驟雨」(監督・成瀬巳喜男 脚本・水木洋子)の冒頭場面である。夫は佐野周二、妻は原節子、早くも倦怠期に入った夫婦の雰囲気が、見事に描き出されていた。実を言えば、この二人、その七年前(昭和二十四年封切)に「お嬢さん乾杯」(監督・木下恵介 脚本・新藤兼人)でも共演しているのである。戦後没落した華族のお嬢さん(原節子)が、復興景気に乗った自動車会社の若社長(佐野周二)と見合いし、婚約するまでの物語である。「住んでる世界がまったく違う」深窓の令嬢と田舎出の成金社長が、様々な齟齬を重ねながら、「お嬢さん」が庶民の世界に飛び降りる決心をしたところで終幕となった。「あの人はどんなにお嬢さんに惚れていたかしれませんよ」とバーのマダムに告げられ、「(わたくしも)惚れております」というセリフを残して佐野周二を追いかける時、あの名曲「旅の夜風」が行進曲のように流れた幕切れは、新しい戦後社会の「はじまり」を予感するのに十分であった。二人は、幸せになるに違いない。明るい家庭を築き、いつまでも楽しく「惚れ合って」暮らしてほしい。誰もがそのように祈ったはずであった。
だが、しかし、である。「驟雨」の佐野周二からは、「若社長」時代のエネルギー、バイタリティーがすっかり消え失せていた。かつては、「お金なんかいくらでももうかる」と豪語し、没落した「お嬢さん一族」の借金百万円をプレゼント、自分はいさぎよく身を引こうとした「男気」はどこへ行ってしまったのか。十万円の報奨金につられ、化粧品会社を早期退職して、田舎暮らしをしたいというのである。
一方、「お嬢さん・原節子」のエネルギー、バイタリティーは「驟雨」でも健在であった。新聞のレシピを切り抜いてスクラップ、見た目のグリンピースよりは、栄養満点の鮭を選び、、商店街では細切れの肉を正直に量り売りする店を見つけている。出入りしている野良犬が傷つけた鶏を飼い主から買い取り、さっさと鍋料理に調理してしまう腕前は、見事と言う他ない。夫に怒鳴られ台所で泣いているのかと思えば、平然と「お茶漬け」を掻き込んでいる。その食欲こそがすべての出発点であろう。スカートに靴下、ゲタ履きという身なりで買い物に出ても、「お嬢さん・原節子」の姿は光り輝いて見えた。夫の同僚たちは、彼女の美貌を見逃さない。バーのマダムに仕立てて、一山当てようともくろむ。「どうです?奥さん」と誘われて、「まあ、どうしましょう」と、浮かべる満面の笑みは、伝説の女優「原節子」の面目躍如というところであった。
アダムとイブの神話以来、女は男の従属物のように見なされ、男系社会が人類の歴史を作ってきたように思われているが、事実は、全く逆である。女が男よりもたくましく、「賢い」ことは、「平均寿命」の差を見れば一目瞭然であろう。したがって、いつの時代でも、どこの家庭でも「女は男より賢い」のであり、すべての妻は、妻であるということだけで、「すでに賢妻である」ということを銘記すべきである。作り話の中で、「愚かな妻」「か弱い妻」「可哀想な妻」「虐げられた妻」「耐え忍ぶ妻」などなど、女が悲劇の主役として描かれることは少なくないが、多くの場合、その作者は男であり、愚かな男の「特権意識」や「願望」が窺われて見苦しい。さらに愚かな男は、作り話を「現実」と混同し、悲劇のヒロインを「実生活」の場でも、自分の妻に演じさせようとしている。そのような傾向が現代にもあることを、私は憂慮する。末尾ながら「驟雨」の原作者は男(岸田国士)だったが、その戯曲集を脚色したのは水木洋子という才媛であったことを特記したい。(2006.4.1)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-26
付録・邦画傑作選・「学生ロマンス若き日」(監督・小津安二郎・1929年)
ユーチューブで映画「学生ロマンス若き日」(監督・小津安二郎・1929年)を観た。 昭和初期における大学生の人間模様が詳細に描かれていてたいそう面白かった。
舞台の始まりは「都の西北」、大学に近い下宿屋である。二階の障子窓には「二階かしま」という貼り紙、一人の学生がそこを訪れるとすでに先入者がいた。渡辺(結城一郎)という学生である。彼は何かと調子よい、なるほど「C調」という人物はこの時代から居たのだ。貼り紙の目的はガールハント(今で言うナンパ)、シャンな娘の到来を待っている。最初の学生は「男」だから駄目、二番目は娘だったが「不細工」だから駄目、ようやく三番目に頃合いの娘・千恵子(松井潤子)がやって来た。下宿屋の坊主(小藤田正一)が「今度はシャンだよ」と紹介するところを見ると、そこの内儀(高松栄子)も渡辺の企みを許容しているらしい。渡辺、千恵子に「この部屋は眺めもいいですよ。私は今日立ち退きます」などと言い、千恵子も気に入った。翌日、荷物を運び込む段になったが、渡辺はまだ居座っている。「昨日は日が悪かったので、今から立ち退きます。あなたが雇った荷車で私の荷物を運び出しましょう」などと調子がいい。出がけには額縁の絵を1枚プレゼントして立ち去った。自分の荷物を車屋に引かせて、渡辺は行き先を模索する。不動産屋を訪れたが適当な物件がない。持ち合わせの金銭もなかったか、とうとう学友・山本(齋藤達雄)の下宿に転がり込んだ。山本、驚いて拒絶しても「どこ吹く風」、まんまと同居人になってしまう。山本はどこまでも温和しく不器用、でも一人のガールフレンドが居た。彼女こそ渡辺の部屋に転入した千恵子だったとは・・・。かくて、渡辺と山本は千恵子をめぐって張り合うことになる。どうみてもC調・渡辺の方が分がいい。大学の冬休み、千恵子と山本は赤倉温泉にスキーを楽しみに行く約束になっていたが、渡辺もちゃっかりと割り込んでくる。「忘れ物をしました」などと言って千恵子の部屋を訪れ、山本のために編んでいたスキー用の靴下をゲット、山本に見せる。山本は「どこかで見たような靴下だ」と思うだけで真相には気づかない。そのコントラストが当時の「学生気質」を鮮やかに浮き彫りしている。いよいよ赤倉温泉の最寄り駅「田口」(今の妙高高原駅)に到着した。周囲は何もない。降り立った二人は宿までのおよそ5キロ(?)の道をスキーで辿る。ここでも、技術は渡辺が上、山本は「こけつまろびつ」の態でようやく宿に着いた。
やがて、ゲレンデで千恵子に遭遇、山本と渡辺の「恋のさや当て」も佳境に入る。どうやら渡辺の勝ちに終わるかと思いきや、結果は意外や意外、千恵子は先行していた大学スキー部主将・畑本(日守新一)との「見合い」に来ていたという次第・・・。意気消沈して帰京する渡辺と山本の姿が「絵」になっていた。東京にに向かう列車の中、千恵子から一同にプレゼントされた蜜柑を、山本は力なく頬張り、渡辺は手編みの靴下に入れて車窓から放り投げる。学生のロマンスはあえなく終わったのである。山本の下宿に戻った二人、ふさぎ込んでいる山本に、渡辺「もっといいシャンを見つけてやるよ」と言い終わると、一枚の紙を取りだし「二階かしま」と墨書する。渡辺の説明(ナンパのテクニック)を聞きながら、次第に山本の表情が緩み元気が蘇ってくる。男同士の「友情」が仄見える名場面であった。画面は再び「都の西北」、冒頭の場面へと移りつつ、学生ロマンが再開するだろうと期待するうちに閉幕・・・。
しかし、わからないのは「女心」と言うべきか、千恵子は初めから畑本と決めていたのか、それともゲレンデの三者を天秤にかけたのか。女の「したたかさ」は昔も今も変わりがない。男にとって女とは「全く不可解な存在」であることを、(生涯独身を貫いた)小津安二郎監督は描きたかったのかもしれない。 末尾ながら、スキー部員を演じた「若き日」の笠智衆、千恵子の伯母をかいがいしく演じる飯田蝶子の姿も懐かしく、その存在感を十分に味わえたことは望外の幸せであった。 さらに余談だが、この映画の舞台となった赤倉温泉は、戦後青春映画の傑作「泥だらけの純情」(監督・中平康・1963年)で、「若き日」の吉永小百合と浜田光夫が心中を遂げた場所でもある。その雪景色をバックに、やはり女の一途な「したたかさ」に翻弄される男の宿命が描かれていたことは、実に興味深いことである。 (2017.1.18)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

舞台の始まりは「都の西北」、大学に近い下宿屋である。二階の障子窓には「二階かしま」という貼り紙、一人の学生がそこを訪れるとすでに先入者がいた。渡辺(結城一郎)という学生である。彼は何かと調子よい、なるほど「C調」という人物はこの時代から居たのだ。貼り紙の目的はガールハント(今で言うナンパ)、シャンな娘の到来を待っている。最初の学生は「男」だから駄目、二番目は娘だったが「不細工」だから駄目、ようやく三番目に頃合いの娘・千恵子(松井潤子)がやって来た。下宿屋の坊主(小藤田正一)が「今度はシャンだよ」と紹介するところを見ると、そこの内儀(高松栄子)も渡辺の企みを許容しているらしい。渡辺、千恵子に「この部屋は眺めもいいですよ。私は今日立ち退きます」などと言い、千恵子も気に入った。翌日、荷物を運び込む段になったが、渡辺はまだ居座っている。「昨日は日が悪かったので、今から立ち退きます。あなたが雇った荷車で私の荷物を運び出しましょう」などと調子がいい。出がけには額縁の絵を1枚プレゼントして立ち去った。自分の荷物を車屋に引かせて、渡辺は行き先を模索する。不動産屋を訪れたが適当な物件がない。持ち合わせの金銭もなかったか、とうとう学友・山本(齋藤達雄)の下宿に転がり込んだ。山本、驚いて拒絶しても「どこ吹く風」、まんまと同居人になってしまう。山本はどこまでも温和しく不器用、でも一人のガールフレンドが居た。彼女こそ渡辺の部屋に転入した千恵子だったとは・・・。かくて、渡辺と山本は千恵子をめぐって張り合うことになる。どうみてもC調・渡辺の方が分がいい。大学の冬休み、千恵子と山本は赤倉温泉にスキーを楽しみに行く約束になっていたが、渡辺もちゃっかりと割り込んでくる。「忘れ物をしました」などと言って千恵子の部屋を訪れ、山本のために編んでいたスキー用の靴下をゲット、山本に見せる。山本は「どこかで見たような靴下だ」と思うだけで真相には気づかない。そのコントラストが当時の「学生気質」を鮮やかに浮き彫りしている。いよいよ赤倉温泉の最寄り駅「田口」(今の妙高高原駅)に到着した。周囲は何もない。降り立った二人は宿までのおよそ5キロ(?)の道をスキーで辿る。ここでも、技術は渡辺が上、山本は「こけつまろびつ」の態でようやく宿に着いた。
やがて、ゲレンデで千恵子に遭遇、山本と渡辺の「恋のさや当て」も佳境に入る。どうやら渡辺の勝ちに終わるかと思いきや、結果は意外や意外、千恵子は先行していた大学スキー部主将・畑本(日守新一)との「見合い」に来ていたという次第・・・。意気消沈して帰京する渡辺と山本の姿が「絵」になっていた。東京にに向かう列車の中、千恵子から一同にプレゼントされた蜜柑を、山本は力なく頬張り、渡辺は手編みの靴下に入れて車窓から放り投げる。学生のロマンスはあえなく終わったのである。山本の下宿に戻った二人、ふさぎ込んでいる山本に、渡辺「もっといいシャンを見つけてやるよ」と言い終わると、一枚の紙を取りだし「二階かしま」と墨書する。渡辺の説明(ナンパのテクニック)を聞きながら、次第に山本の表情が緩み元気が蘇ってくる。男同士の「友情」が仄見える名場面であった。画面は再び「都の西北」、冒頭の場面へと移りつつ、学生ロマンが再開するだろうと期待するうちに閉幕・・・。
しかし、わからないのは「女心」と言うべきか、千恵子は初めから畑本と決めていたのか、それともゲレンデの三者を天秤にかけたのか。女の「したたかさ」は昔も今も変わりがない。男にとって女とは「全く不可解な存在」であることを、(生涯独身を貫いた)小津安二郎監督は描きたかったのかもしれない。 末尾ながら、スキー部員を演じた「若き日」の笠智衆、千恵子の伯母をかいがいしく演じる飯田蝶子の姿も懐かしく、その存在感を十分に味わえたことは望外の幸せであった。 さらに余談だが、この映画の舞台となった赤倉温泉は、戦後青春映画の傑作「泥だらけの純情」(監督・中平康・1963年)で、「若き日」の吉永小百合と浜田光夫が心中を遂げた場所でもある。その雪景色をバックに、やはり女の一途な「したたかさ」に翻弄される男の宿命が描かれていたことは、実に興味深いことである。 (2017.1.18)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-25
付録・邦画傑作選・「上陸第一歩」(監督・島津保次郎・1932年)
ユーチューブで映画「上陸第一歩」(監督・島津保次郎・1932年)を観た。何とも「摩訶不思議」な映画である。タイトルを見て、戦意高揚の国策映画と思いきや(しかし、1930年代に国策映画はあり得ない)、アメリカ映画「紐育の波止場」の翻案で、島津監督の「第1回トーキー作品」、主演の水谷八重子(28歳)も映画初出演ということである。(ウィキペディア百科事典参照)
「摩訶不思議」の原因は、一に映画自体(画像)は「サイレント」の様相を呈し、役者(特に主役・岡譲二)のセリフは「字幕並」、にもかかわらず、二に主演・水谷八重子の演技は「新派」の舞台そのまま、三に背景は船舶、波止場、アパート、酒場、ホテルといった洋風の雰囲気に加えて、女性の多くは和服姿、飲食物はパン、ミルク、ウィスキー等々、その「アンバランス」が目立つからである。
しかし、今、そのアンバランスがたまらなく魅力的である。
冒頭は、ある港町の風景が延々と映し出される。灯台、大小の船々、飛び交うカモメ、折しも大型の貨物船が入港した。それをアパートのベランダから「港の女」・さと(水谷八重子)が眺めている。「エミちゃん、船が入って来たよ。」と呼びかければ「ナーンダ、貨物船か。フランスの船でも来ればいいのに」。どうやらそこは、酒場で働く女たちの寮らしい。
一方、船のボイラー室では火夫たちが、上半身裸で懸命に石炭を釜に放り込んでいる。「坂田、上がったら今晩も遊びか」「何を言ってやがるンでー」。坂田と呼ばれた男(岡譲二)、船室(食堂)に戻ると夕食も食べずに髭を剃る。周囲では司厨長・野沢(河村黎吉)たちが小博打(チンチロリン)に興じていた。坂田の弟分、倉庫番・戸村(滝口新太郎)が「兄貴!俺も遊びに連れてってくれ」と頼む。やがて、埠頭に降り立った二人、その前を一人の女が通り過ぎた。行く手を見るとそこは海。「兄貴!様子が変だぞ」と言っているうちに、案の定、女は着物姿のまま海に飛び込んだ。あわてて、坂田も飛び込んで助け出す。とりあえず「待合所」に運び入れ、達磨ストーブで暖をとった、女(実はさと)の様子を見ていた坂田は「オイ、ウィスキーを買ってこい。小さいのでいいんだぞ」と戸村に命じ、さとを抱き起こし外套を被せる。「おめえ、寒かねえか、馬鹿なマネをしやがって」。さとは外套を投げ捨てて「あんた、こんなところに私を連れてきてどうするつもり」と食ってかかる始末。「そんなこたあ知るもんか。死にかかっている人を黙って見過ごすわけにゃあいかねえ」「人が生きようと死のうとあんたにはかかわりのないこと、さっさと行ってしまえばよかったんだ」「おまえ、ずいぶんのぼせ上がっていやがる。その前にとっとと着物を脱いで乾かせばいいじゃあねえか」「あたしだって女だ、男の前で裸になんかなれるもんか!ずいぶん血の巡りが悪い男だねえ」。待合所の外で待つ坂田、ウィスキーを買ってきた戸村も同様に叩き出され、「おめえもずいぶん血の巡りが悪い男だな」などというやりとりが何とも面白かった。
外気の寒さに当たったか、坂田は「カゼをひきそうだ。酒場に行って一杯やるから、おめえはあの女の番をしていろ」と戸村に命じ去って行く。一息ついたさと、戸村に坂田の様子を尋ねれば酒場に行った由、置き忘れられた坂田のパイプを持って自分も酒場に駆けつける。(ずぶ濡れの和服がそんなに早く乾こうはずもないのに、ちゃっかり着ている姿が何とも可笑しい。)そこは船員たちの溜まり場で、司厨長・野沢も顔を出して、坂田とさとの間に割って入ろうとしたのだが(野沢がウイスキーの瓶をさとに差し出して「一杯酌してくれ」という光景も滑稽で、笑ってしまった)・・・、いよいよ大物が登場する。港を牛耳る「ブルジョアの政」(奈良真養)とその子分「プロペラのしげ」(江川宇礼雄)たちである。政は野沢とも懇意で、先刻は「密売品」の取引(それは不調に終わったが)をしてきたばかり。さとを見つけると「おい!さと、今までどこにずらかって居やがった」と捕縛しようとする。さとは政の手によって上海に売り飛ばされようとしていたのだ。「キャー」というさとの声を聞いて、坂田は敢然と政に立ち向かう。「オイ、待った!」「何だ貴様は」「俺は○○丸の釜焚きだ」「釜焚きなんかにこの女を横取りされるような俺じゃねえぞ」「横取りも縦取りもあるもんか。俺はこの女を拾ったんだ」、脇からプロペラのしげが「拾ったんなら持ち主に返せよ」。坂田はさとに「お前は政の女か」と確かめ「違います!」というので、連れて帰ろうとする。政は「待て! 勝手なマネはさせない。この女を置いて行け」とピストルを取り出した。それを見た坂田「フン、パチンコ出しやがったな」と言うなり政に掴みかかろうとして、子分たちと大乱闘が始まった。強い、強い。かかってくる相手を殴りつけ、投げ飛ばし、文字通り孤軍奮闘を絵で描いたような場面、途中からは、さとがビール瓶を天井のシャンディアに投げつけ、辺りは一瞬真っ暗闇、その中でも乱闘は続く・・・。どうやら、坂田が政を叩きのめして終わったようだ。政の情婦(沢蘭子)までもが坂田に向かって「あんた、いい腕前だねえ、今晩一晩預けておくよ」などと目を細める。収まらないのは酒場のマダム(吉川満子)、メチャクチャにされた酒場の店内、「あんた、このお店どうしてくれるのさ」と情婦に噛みつくが「まあ、しょうがないじゃないか」でその場はチョンとなった。(何ともあっさりした結着である)
坂田とさとは川岸の安宿(リバーサイド・ホテル)に落ち着いた。坂田は故郷の母親に手紙を書いている。その様子を見て、さとが繰り広げる身の上話。生まれは北海道網走、母は妹を産むなり死んでしまった。私はその赤ん坊の守りに明け暮れていた。私は母の連れ子、やがて義父が私を女郎に売ろうとしたので、家を飛び出した。それからはあちこちを転々・・・、「あたしなんか、いてもいなくても、どうでもいい女なんだ」と弱音を吐く。坂田「おめえ、初めはずいぶん強気だったじゃねえか」「だって、あんたは仇だと思っていたんだもの」「昔のことなんか思い出すのはよせ。俺はそんな話、聞きたくねえぞ。おめえ、もう寝た方がいいぜ」。どこかでサイレンの音が聞こえる。「火事かしら」「そんなこたあ、俺の知ったこっちゃねえよ」。さとにベッドを提供、坂田もソファで眠りに就いた。
翌朝、さとは早起きしてパンとミルク、林檎と歯みがきを買って来た。起き出した坂田が洗面所で歯を磨いていると、おかみ(飯田蝶子)がやって来て「あの娘、朝からはしゃいで買い物してきたわよ、お安くないねえ」と冷やかした。部屋に戻り、朝食を始めるとドアの音がして舎弟の戸村がやって来た。「兄貴、チーフが呼んでいる。埠頭まで来てくれ」「乗り込みは今夜8時だ。朝っぱらから何の用だ」と言いながらも、出かける様子。さとは「乗り込みが8時ならここに戻って来てよ。あたし御飯をたくから一緒に食べよう」と言う。坂田は巾着を取り出してテーブルに置く。「これ何?」「何かの足しに使ってくれ」「あたしなら大丈夫。もう死ぬなんて考えない」「それなら、ずらかる時にでも使えばいい」「あんた、帰っちゃいや」「俺は船乗りだ。帰らなければ暮らしていけねえんだよ」「あんた、8時までここで待ってるから戻って来てね」。
坂田と戸村は埠頭に向かった。そこは倉庫・ビルの工事現場、鉄骨にドリルを撃ち込む轟音が響きわたる。やがて、現れたのは司厨長・野沢と「ブルジョアの政」一味、向かい合うなりピストル3発、坂田はその場に倒れ込んだ。しかしそれは芝居、油断して取り囲む一味、政が「船に運び込め」と言うやいなや、坂田は政に掴みかかり、またもや大乱闘が始まった。政は坂田に突き飛ばされ本当に倒れ込む。一味もあえなく退治されてしまった。
坂田がホテルに戻ると、待っていたのは「プロペラのしげ」、さとの見張り役だった。坂田を見て驚くしげ、今頃、坂田は政に殺られているはずなのに・・・、しどろもどろで言い訳をするしげを張り倒し追い払う。「覚えていろ」と捨て台詞を吐くしげを、難なく階段下に突き落としてしまった。
その後二人は、「あんたって本当に強いのね。あたしあんたのおかみさんになりたい。あんたが帰ってきたら首にしがみついちゃう」「ハハハハ、俺は陸に上がったら何にもできねえでくの坊だ」「それでもいいの、一件家を借りて草花を育てるの」などと対話していたが、入口に人の気配、訪れたのは刑事(岡田宗太郞)たち、戸村もいる。「坂田とはお前か、殺人の嫌疑がかかっている。同行してもらおう」。さとは驚いて「この人が人殺しなんてするはずがありません」と刑事の前に立ちふさがる。戸村も「初めに政がピストルを3発撃ったんです」と弁護。しかし、坂田は「政が死んだんなら、私がやったこと。しょうがない。お供します」と従った。さとは、必死に「あんた、あたし待っている。いつまでも待っているわ。だから戻って来てね」と取り縋る。(しばらくの間)坂田は「お前が待っていると言うのならなら、戻ってくるよ」と応じた。さとは「本当!あたし、うれしい!」と泣き崩れた。「じゃ、あばよ」と言い残し、坂田は牽かれて行く。さとは身もだえして、いつまでも泣き続ける。やがて窓の外には、いつもの港の風景が・・・。矢追婦美子の歌う主題歌が流れるうちに、この映画の幕は下りた。
この映画の魅力は、(前述したように)「アンバランス」(の魅力)である。水谷八重子の、文字通り「芝居じみた」(新派風の)セリフに対して、岡譲二は(サイレント映画の)「字幕」をアッケラカンと棒読みするように応じる。その風貌とは裏腹に「べらんめえ」調の口跡が素晴らしい。「気は優しく(単純で)力持ち」といった往時のヒーローの風情が滲み出ている。筋書きは「悲劇」だが、景色はコミカルで、どこまでも明るい。しかも、水谷八重子の「うれし泣き」でハッピーエンドという大団円は見事であった。島津監督はトーキー初挑戦、水谷も映画初出演、アメリカ映画の翻案という「不慣れ」(不自然)も手伝ってか、あちこちには、ほのぼのとした「ぎこちなさ」が垣間見られる。それがまたさらに「アンバランス」の魅力を際立たせるという、「傑作」というよりは「珍品」に値する「稀有・貴重な作物」だと、私は思う。(2017.2.13)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

「摩訶不思議」の原因は、一に映画自体(画像)は「サイレント」の様相を呈し、役者(特に主役・岡譲二)のセリフは「字幕並」、にもかかわらず、二に主演・水谷八重子の演技は「新派」の舞台そのまま、三に背景は船舶、波止場、アパート、酒場、ホテルといった洋風の雰囲気に加えて、女性の多くは和服姿、飲食物はパン、ミルク、ウィスキー等々、その「アンバランス」が目立つからである。
しかし、今、そのアンバランスがたまらなく魅力的である。
冒頭は、ある港町の風景が延々と映し出される。灯台、大小の船々、飛び交うカモメ、折しも大型の貨物船が入港した。それをアパートのベランダから「港の女」・さと(水谷八重子)が眺めている。「エミちゃん、船が入って来たよ。」と呼びかければ「ナーンダ、貨物船か。フランスの船でも来ればいいのに」。どうやらそこは、酒場で働く女たちの寮らしい。
一方、船のボイラー室では火夫たちが、上半身裸で懸命に石炭を釜に放り込んでいる。「坂田、上がったら今晩も遊びか」「何を言ってやがるンでー」。坂田と呼ばれた男(岡譲二)、船室(食堂)に戻ると夕食も食べずに髭を剃る。周囲では司厨長・野沢(河村黎吉)たちが小博打(チンチロリン)に興じていた。坂田の弟分、倉庫番・戸村(滝口新太郎)が「兄貴!俺も遊びに連れてってくれ」と頼む。やがて、埠頭に降り立った二人、その前を一人の女が通り過ぎた。行く手を見るとそこは海。「兄貴!様子が変だぞ」と言っているうちに、案の定、女は着物姿のまま海に飛び込んだ。あわてて、坂田も飛び込んで助け出す。とりあえず「待合所」に運び入れ、達磨ストーブで暖をとった、女(実はさと)の様子を見ていた坂田は「オイ、ウィスキーを買ってこい。小さいのでいいんだぞ」と戸村に命じ、さとを抱き起こし外套を被せる。「おめえ、寒かねえか、馬鹿なマネをしやがって」。さとは外套を投げ捨てて「あんた、こんなところに私を連れてきてどうするつもり」と食ってかかる始末。「そんなこたあ知るもんか。死にかかっている人を黙って見過ごすわけにゃあいかねえ」「人が生きようと死のうとあんたにはかかわりのないこと、さっさと行ってしまえばよかったんだ」「おまえ、ずいぶんのぼせ上がっていやがる。その前にとっとと着物を脱いで乾かせばいいじゃあねえか」「あたしだって女だ、男の前で裸になんかなれるもんか!ずいぶん血の巡りが悪い男だねえ」。待合所の外で待つ坂田、ウィスキーを買ってきた戸村も同様に叩き出され、「おめえもずいぶん血の巡りが悪い男だな」などというやりとりが何とも面白かった。
外気の寒さに当たったか、坂田は「カゼをひきそうだ。酒場に行って一杯やるから、おめえはあの女の番をしていろ」と戸村に命じ去って行く。一息ついたさと、戸村に坂田の様子を尋ねれば酒場に行った由、置き忘れられた坂田のパイプを持って自分も酒場に駆けつける。(ずぶ濡れの和服がそんなに早く乾こうはずもないのに、ちゃっかり着ている姿が何とも可笑しい。)そこは船員たちの溜まり場で、司厨長・野沢も顔を出して、坂田とさとの間に割って入ろうとしたのだが(野沢がウイスキーの瓶をさとに差し出して「一杯酌してくれ」という光景も滑稽で、笑ってしまった)・・・、いよいよ大物が登場する。港を牛耳る「ブルジョアの政」(奈良真養)とその子分「プロペラのしげ」(江川宇礼雄)たちである。政は野沢とも懇意で、先刻は「密売品」の取引(それは不調に終わったが)をしてきたばかり。さとを見つけると「おい!さと、今までどこにずらかって居やがった」と捕縛しようとする。さとは政の手によって上海に売り飛ばされようとしていたのだ。「キャー」というさとの声を聞いて、坂田は敢然と政に立ち向かう。「オイ、待った!」「何だ貴様は」「俺は○○丸の釜焚きだ」「釜焚きなんかにこの女を横取りされるような俺じゃねえぞ」「横取りも縦取りもあるもんか。俺はこの女を拾ったんだ」、脇からプロペラのしげが「拾ったんなら持ち主に返せよ」。坂田はさとに「お前は政の女か」と確かめ「違います!」というので、連れて帰ろうとする。政は「待て! 勝手なマネはさせない。この女を置いて行け」とピストルを取り出した。それを見た坂田「フン、パチンコ出しやがったな」と言うなり政に掴みかかろうとして、子分たちと大乱闘が始まった。強い、強い。かかってくる相手を殴りつけ、投げ飛ばし、文字通り孤軍奮闘を絵で描いたような場面、途中からは、さとがビール瓶を天井のシャンディアに投げつけ、辺りは一瞬真っ暗闇、その中でも乱闘は続く・・・。どうやら、坂田が政を叩きのめして終わったようだ。政の情婦(沢蘭子)までもが坂田に向かって「あんた、いい腕前だねえ、今晩一晩預けておくよ」などと目を細める。収まらないのは酒場のマダム(吉川満子)、メチャクチャにされた酒場の店内、「あんた、このお店どうしてくれるのさ」と情婦に噛みつくが「まあ、しょうがないじゃないか」でその場はチョンとなった。(何ともあっさりした結着である)
坂田とさとは川岸の安宿(リバーサイド・ホテル)に落ち着いた。坂田は故郷の母親に手紙を書いている。その様子を見て、さとが繰り広げる身の上話。生まれは北海道網走、母は妹を産むなり死んでしまった。私はその赤ん坊の守りに明け暮れていた。私は母の連れ子、やがて義父が私を女郎に売ろうとしたので、家を飛び出した。それからはあちこちを転々・・・、「あたしなんか、いてもいなくても、どうでもいい女なんだ」と弱音を吐く。坂田「おめえ、初めはずいぶん強気だったじゃねえか」「だって、あんたは仇だと思っていたんだもの」「昔のことなんか思い出すのはよせ。俺はそんな話、聞きたくねえぞ。おめえ、もう寝た方がいいぜ」。どこかでサイレンの音が聞こえる。「火事かしら」「そんなこたあ、俺の知ったこっちゃねえよ」。さとにベッドを提供、坂田もソファで眠りに就いた。
翌朝、さとは早起きしてパンとミルク、林檎と歯みがきを買って来た。起き出した坂田が洗面所で歯を磨いていると、おかみ(飯田蝶子)がやって来て「あの娘、朝からはしゃいで買い物してきたわよ、お安くないねえ」と冷やかした。部屋に戻り、朝食を始めるとドアの音がして舎弟の戸村がやって来た。「兄貴、チーフが呼んでいる。埠頭まで来てくれ」「乗り込みは今夜8時だ。朝っぱらから何の用だ」と言いながらも、出かける様子。さとは「乗り込みが8時ならここに戻って来てよ。あたし御飯をたくから一緒に食べよう」と言う。坂田は巾着を取り出してテーブルに置く。「これ何?」「何かの足しに使ってくれ」「あたしなら大丈夫。もう死ぬなんて考えない」「それなら、ずらかる時にでも使えばいい」「あんた、帰っちゃいや」「俺は船乗りだ。帰らなければ暮らしていけねえんだよ」「あんた、8時までここで待ってるから戻って来てね」。
坂田と戸村は埠頭に向かった。そこは倉庫・ビルの工事現場、鉄骨にドリルを撃ち込む轟音が響きわたる。やがて、現れたのは司厨長・野沢と「ブルジョアの政」一味、向かい合うなりピストル3発、坂田はその場に倒れ込んだ。しかしそれは芝居、油断して取り囲む一味、政が「船に運び込め」と言うやいなや、坂田は政に掴みかかり、またもや大乱闘が始まった。政は坂田に突き飛ばされ本当に倒れ込む。一味もあえなく退治されてしまった。
坂田がホテルに戻ると、待っていたのは「プロペラのしげ」、さとの見張り役だった。坂田を見て驚くしげ、今頃、坂田は政に殺られているはずなのに・・・、しどろもどろで言い訳をするしげを張り倒し追い払う。「覚えていろ」と捨て台詞を吐くしげを、難なく階段下に突き落としてしまった。
その後二人は、「あんたって本当に強いのね。あたしあんたのおかみさんになりたい。あんたが帰ってきたら首にしがみついちゃう」「ハハハハ、俺は陸に上がったら何にもできねえでくの坊だ」「それでもいいの、一件家を借りて草花を育てるの」などと対話していたが、入口に人の気配、訪れたのは刑事(岡田宗太郞)たち、戸村もいる。「坂田とはお前か、殺人の嫌疑がかかっている。同行してもらおう」。さとは驚いて「この人が人殺しなんてするはずがありません」と刑事の前に立ちふさがる。戸村も「初めに政がピストルを3発撃ったんです」と弁護。しかし、坂田は「政が死んだんなら、私がやったこと。しょうがない。お供します」と従った。さとは、必死に「あんた、あたし待っている。いつまでも待っているわ。だから戻って来てね」と取り縋る。(しばらくの間)坂田は「お前が待っていると言うのならなら、戻ってくるよ」と応じた。さとは「本当!あたし、うれしい!」と泣き崩れた。「じゃ、あばよ」と言い残し、坂田は牽かれて行く。さとは身もだえして、いつまでも泣き続ける。やがて窓の外には、いつもの港の風景が・・・。矢追婦美子の歌う主題歌が流れるうちに、この映画の幕は下りた。
この映画の魅力は、(前述したように)「アンバランス」(の魅力)である。水谷八重子の、文字通り「芝居じみた」(新派風の)セリフに対して、岡譲二は(サイレント映画の)「字幕」をアッケラカンと棒読みするように応じる。その風貌とは裏腹に「べらんめえ」調の口跡が素晴らしい。「気は優しく(単純で)力持ち」といった往時のヒーローの風情が滲み出ている。筋書きは「悲劇」だが、景色はコミカルで、どこまでも明るい。しかも、水谷八重子の「うれし泣き」でハッピーエンドという大団円は見事であった。島津監督はトーキー初挑戦、水谷も映画初出演、アメリカ映画の翻案という「不慣れ」(不自然)も手伝ってか、あちこちには、ほのぼのとした「ぎこちなさ」が垣間見られる。それがまたさらに「アンバランス」の魅力を際立たせるという、「傑作」というよりは「珍品」に値する「稀有・貴重な作物」だと、私は思う。(2017.2.13)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-24
付録・邦画傑作選・「東京の英雄」(監督・清水宏・1935年)
冒頭のタイトルに続き、「配役」になると、女性の歌声が流れ出す。耳を澄ませると、「並ぶ小窓に はすかいに 交わす声々日が落ちる 旅暮れて行く空の鳥 母の情けをしみじみと」と聞こえるが、定かではない。主なる登場人物は、根本嘉一・岩田祐吉、春子・吉川満子、寛一・藤井貢、加代子・桑野通子、秀雄・三井秀夫(後の三井弘次)である。さらに、寛一の少年時代を突貫小僧、加代子を市村美津子、秀雄を横山準(爆弾小僧)が演じている。
冒頭場面は東京郊外、省線電車が見える空き地には大きな土管、その上に腰かけた数人の子どもたちが電車に手を振っている。そこに一人の少年・寛一(突貫小僧)が、バットとグローブを携えてやって来た。「野球しないか」と呼びかけるが「もうお父さんが帰る時分だからいやだよ」と断られた。寛一はすごすごと家に戻るが、待っていたのは婆や(高松栄子)だけ、「家のお父さんはどうして毎晩帰りが遅いの」と訊ねると「お偉くなられたからいろいろとお仕事がおありなさるのですよ」という答、やむなく一人で夕食を摂る。なるほど父・根本嘉一(岩田祐吉)は立派な家を構えている。しかし、寛一の母はどこにも見当たらない。父子家庭に違いない。嘉一の仕事は山師、「龍現山金鉱発掘資金募集事務所」という看板を掲げ、「天下の宝庫開かる!配当有利、絶対確実」というポスターで資金を集めているが、思うような成果が得られないようだ。
嘉一が帰宅すると婆やが言う。「旦那様のお帰りが毎日遅いので、坊ちゃまが淋しそうでございます」「後添えを考えているのだが・・・」。かくて、嘉一は「求妻」の新聞広告を出し、再婚する運びとなった。相手の春子(吉川満子)には二人の子どもが居る。加代子(市村美津子)と秀雄(横山準)である。寛一と父は「じゃあ、お母さんばかりじゃなく、妹も弟も貰うんだね」「仲良くしなければダメだぞ」「生意気だったらノシちゃうよ」などと対話する。
やがて、新しい家族は江の島を観光、嘉一、春子、加代子が連れだって「あなたが来て下さったのでこれからは事業に専念できます」と言いながら桟橋を歩いていると、後ろから秀雄が泣きながら追いついた。振り返ると、寛一が向こうで仁王立ちになっている。嘉一が駆け寄ると「今日から兄弟だっていうのに彼奴、僕のこと寛一さんだーか君だなんて言うんだもの(殴ってやった)あいつ、水臭いんだよ」。嘉一は寛一を黙ってみんなのもとに連れて行く。ともかくも、家族が揃い、明るい家庭がスタートする筈だったのに。
数日後、「龍現山金鉱発掘資金募集事務所の内面暴露す 早くも首領株失踪」という見出しの新聞記事が載った。事務所に殺到する出資者たちの群衆が、自宅にまでも押し寄せる。嘉一は集めた出資金を持ち逃げ、姿をくらましたのである。春子は対応に追われるが追及者たちの前で「再婚早々で何もわかりません」と頭を下げる他はなかった。「でも、私は主人を信じております。大切な子どもを私なんかに預けてくださるんですもの」。婆やが「もし、このままお帰りにならなかったら」と問うと「子どもだけは立派に育てて見せますわ。日は浅くても親と子どもですもの」と言いながら、加代子と秀雄よりも、寛一の方に優しい眼差しを向ける。その場面は、この映画の眼目の伏線であることが、後になってわかるのだが・・・。まもなく、春子は、家屋・家財すべてを売り払い安アパートの二階に転居する。新聞の求人広告に目をやりながら、「女給では年を取り過ぎているし、女中ではコブ付きだし、事務員は履歴書がないし・・」と思案にくれていたが、高級クラブの仕事にありつけた。朝食を食べながら寛一が「お母さんのクラブってどんな所?」と訊ねると「社長さんたちが大勢集まって相談したり、お休みしたりする所よ」。すかさず加代子が「お母さんはどんな役?」と問いかける。しかし春子は答えることができなかった。子どもたち三人は蒲団の中で母を待つ。帰宅した母に、寛一は「ずいぶん遅いんだね」と案じると「お仕事が忙しいから」「じゃあ、偉くなったんだよ」と秀雄に話しかける。婆やの話を思い出していたのだろう。時には、子どもたち三人だけで泣き明かす夜も少なくなかった。
そして十年が過ぎ、春子と子どもたち三人は、山の手の瀟洒な二階建ての家に住んで居た。まもなく、加代子(桑野通子)の嫁ぐ日がやって来る。家に訪れた呉服屋の前で、婚礼の晴れ着を選んでいる。大学生になった寛一(藤井貢)と秀雄(三井秀夫)が「いつのまに相手を見つけたんだい」「まだコロッケも作れないのに、早いんじゃないの」などと冷やかせば「秀ちゃんだって、いい人がいるんじゃないの」と言い返す。三人の景色は和気藹々、「子どもたちだけは立派に育てて見せますわ」という春子の決意は実現しつつあるのだ。そして婚礼の当日がやってきた。「こうやって見ると、加代子もなかなかいい花嫁さんですね」と寛一が春子に話しかける。顔を見合わせ頬笑む春子と秀雄。「お前たちが大学を卒業してくれれば、私は楽隠居だわ」と春子はほっとしたように見えたのだが。 そうは問屋が卸さなかった。一家は転がり落ちるように悲劇を演じ始める。その源は春子の生業にあった。女手ひとつで子どもたち三人を育てることは並大抵ではない。まして、二階建ての立派な家を構えることなど、堅気の商売では夢のような話である。しかし、その夢が実現しているとすれば、春子の稼業はまともではない。事実、彼女は子どもたちに内緒でチャブ屋を経営していたのだ。そのことが嫁ぎ先に知れ、加代子は追い返される。絶望した彼女は銀座の街娼に転落。秀雄もまた大学を捨て、与太者の仲間入り、今では顔役になっている。
しかし、寛一だけは、まともに大学を卒業、新聞記者の職を得た。スーツ姿の寛一を見て春子は涙ぐむ。これで責任を果たしたと思い、泣き崩れながら「許しておくれ、実は、私は・・・」と真実を打ち明けようとする。寛一は春子の口をふさぎ「お母さん、何も言ってはいけません。私はわかっています。お母さんはボクにとって日本一のお母さんです」と言い放った。血のつながらない息子だけが、母に寄り添い孝行する景色は、たまらなく美しく、私の涙は止まらなかった。寛一は加代子や秀雄を見つけ出し「家に帰るように」と説得、二人は家の前まで来たが、どうしても足が前に進まずに引き返していく。
まもなく、悲劇の大詰めがやって来た。秀雄がヤクザ仲間に刺されたのである。事情を聞けば、雇われた会社の社長は根本嘉一、妻子を捨てて雲隠れした義父であったという。そんな会社はゴメンだと脱けようとして、「裏切り者」の制裁を受けたのだ。秀雄は「こんな姿はお母さんに見せたくない。黙っていてほしい」と言い残し、息を引き取る。寛一は、憤然として、嘉一の会社に乗り込んだ。「満蒙金鉱開発」を看板に、性懲りも無く、阿漕な経営をしている。父に向かって「一新聞記者として取材に来ました。あなたの会社はまともですか」「勿論」「では、なぜ不良連中を雇ったんです。弟の秀雄はそれで殺されたんですよ」驚く嘉一、次第に力が脱けうなだれていく。「お父さん、ボクはお母さんのために、秀雄のために、加代子のために、そして世間のために、自決を要求します」。 直ちに寛一は、新聞記者として、父の会社の不正を暴露する。その記事は「特ダネ」として表彰された。その報酬を持って家に帰ると、春子と加代子が泣いている。「お母さん、喜んでください。ボクは表彰されました」。しかし、春子は「私はそんなことをしてもらうために、大学を出したんじゃない。お父様に何と言ってお詫びをすればいいか・・」と泣き崩れた。寛一も泣いている「お詫びをしなければならないのはお父さんの方です。ボクは親の罪を世間に公表したんです。それで親孝行ができたんです」最後に「お父さんはお母さんに、くれぐれもよろしくと言っていましたよ」と言うと部屋を出た。
寛一は自室に行き、机の上にあった父親の似顔絵を壁に貼る。それは十年前、彼が描き、秀雄に与えたもの、秀雄はそれを今まで大切に保管していたのであった。そして、窓を開け外を眺める。目にしたのは夕刊を配達する少年の姿、その姿に昔の秀雄、あるいは自分自身の姿を重ねていたかもしれない。寛一の心中には、あの冒頭の歌・・・「並ぶ小窓にはすかいに 交わす声々日が落ちる 旅暮れて行く空の鳥 母の情けをしみじみと」・・・が聞こえていたに違いない。その少年の姿が消え去ると、この映画は「終」となった。
この映画の眼目は「生みの親より育ての親」という諺に象徴される、《絆》であることは間違いない。同時に、寛一にとっての「生みの親」(父)は罪深き詐欺師であり、加代子や秀雄にとっての「生みの親」(母)は世間に顔向けできない人非人なのである。寛一は父を許せない。加代子や秀雄は母を許せない。その悲しい人間模様が、実にきめ細やかな景色として、鮮やかに描き出されている。また、子ども時代、腕白でさぞかし親を手こずらせていたであろう寛一が、成人するにつれて人一倍、母を大切に思う姿も際立っていた。(突貫小僧から藤井貢へのバトンタッチという配役が見事である)それというのも春子が、三人の子どもに分け隔てない愛情を注いできたからに他ならない。吉川満子の表情一つ一つが、そのことを雄弁に物語る。三人の異母兄弟は、彼女の愛情によって固く結ばれていたのである。不幸にも秀雄は落命したが、残された寛一と加代子で春子を支え、さらに、改心した嘉一が、家族に加わる日も遠くはないだろうことを予感させる。清水宏監督、渾身の傑作であった、と私は思う。
(2017.6.2)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

冒頭場面は東京郊外、省線電車が見える空き地には大きな土管、その上に腰かけた数人の子どもたちが電車に手を振っている。そこに一人の少年・寛一(突貫小僧)が、バットとグローブを携えてやって来た。「野球しないか」と呼びかけるが「もうお父さんが帰る時分だからいやだよ」と断られた。寛一はすごすごと家に戻るが、待っていたのは婆や(高松栄子)だけ、「家のお父さんはどうして毎晩帰りが遅いの」と訊ねると「お偉くなられたからいろいろとお仕事がおありなさるのですよ」という答、やむなく一人で夕食を摂る。なるほど父・根本嘉一(岩田祐吉)は立派な家を構えている。しかし、寛一の母はどこにも見当たらない。父子家庭に違いない。嘉一の仕事は山師、「龍現山金鉱発掘資金募集事務所」という看板を掲げ、「天下の宝庫開かる!配当有利、絶対確実」というポスターで資金を集めているが、思うような成果が得られないようだ。
嘉一が帰宅すると婆やが言う。「旦那様のお帰りが毎日遅いので、坊ちゃまが淋しそうでございます」「後添えを考えているのだが・・・」。かくて、嘉一は「求妻」の新聞広告を出し、再婚する運びとなった。相手の春子(吉川満子)には二人の子どもが居る。加代子(市村美津子)と秀雄(横山準)である。寛一と父は「じゃあ、お母さんばかりじゃなく、妹も弟も貰うんだね」「仲良くしなければダメだぞ」「生意気だったらノシちゃうよ」などと対話する。
やがて、新しい家族は江の島を観光、嘉一、春子、加代子が連れだって「あなたが来て下さったのでこれからは事業に専念できます」と言いながら桟橋を歩いていると、後ろから秀雄が泣きながら追いついた。振り返ると、寛一が向こうで仁王立ちになっている。嘉一が駆け寄ると「今日から兄弟だっていうのに彼奴、僕のこと寛一さんだーか君だなんて言うんだもの(殴ってやった)あいつ、水臭いんだよ」。嘉一は寛一を黙ってみんなのもとに連れて行く。ともかくも、家族が揃い、明るい家庭がスタートする筈だったのに。
数日後、「龍現山金鉱発掘資金募集事務所の内面暴露す 早くも首領株失踪」という見出しの新聞記事が載った。事務所に殺到する出資者たちの群衆が、自宅にまでも押し寄せる。嘉一は集めた出資金を持ち逃げ、姿をくらましたのである。春子は対応に追われるが追及者たちの前で「再婚早々で何もわかりません」と頭を下げる他はなかった。「でも、私は主人を信じております。大切な子どもを私なんかに預けてくださるんですもの」。婆やが「もし、このままお帰りにならなかったら」と問うと「子どもだけは立派に育てて見せますわ。日は浅くても親と子どもですもの」と言いながら、加代子と秀雄よりも、寛一の方に優しい眼差しを向ける。その場面は、この映画の眼目の伏線であることが、後になってわかるのだが・・・。まもなく、春子は、家屋・家財すべてを売り払い安アパートの二階に転居する。新聞の求人広告に目をやりながら、「女給では年を取り過ぎているし、女中ではコブ付きだし、事務員は履歴書がないし・・」と思案にくれていたが、高級クラブの仕事にありつけた。朝食を食べながら寛一が「お母さんのクラブってどんな所?」と訊ねると「社長さんたちが大勢集まって相談したり、お休みしたりする所よ」。すかさず加代子が「お母さんはどんな役?」と問いかける。しかし春子は答えることができなかった。子どもたち三人は蒲団の中で母を待つ。帰宅した母に、寛一は「ずいぶん遅いんだね」と案じると「お仕事が忙しいから」「じゃあ、偉くなったんだよ」と秀雄に話しかける。婆やの話を思い出していたのだろう。時には、子どもたち三人だけで泣き明かす夜も少なくなかった。
そして十年が過ぎ、春子と子どもたち三人は、山の手の瀟洒な二階建ての家に住んで居た。まもなく、加代子(桑野通子)の嫁ぐ日がやって来る。家に訪れた呉服屋の前で、婚礼の晴れ着を選んでいる。大学生になった寛一(藤井貢)と秀雄(三井秀夫)が「いつのまに相手を見つけたんだい」「まだコロッケも作れないのに、早いんじゃないの」などと冷やかせば「秀ちゃんだって、いい人がいるんじゃないの」と言い返す。三人の景色は和気藹々、「子どもたちだけは立派に育てて見せますわ」という春子の決意は実現しつつあるのだ。そして婚礼の当日がやってきた。「こうやって見ると、加代子もなかなかいい花嫁さんですね」と寛一が春子に話しかける。顔を見合わせ頬笑む春子と秀雄。「お前たちが大学を卒業してくれれば、私は楽隠居だわ」と春子はほっとしたように見えたのだが。 そうは問屋が卸さなかった。一家は転がり落ちるように悲劇を演じ始める。その源は春子の生業にあった。女手ひとつで子どもたち三人を育てることは並大抵ではない。まして、二階建ての立派な家を構えることなど、堅気の商売では夢のような話である。しかし、その夢が実現しているとすれば、春子の稼業はまともではない。事実、彼女は子どもたちに内緒でチャブ屋を経営していたのだ。そのことが嫁ぎ先に知れ、加代子は追い返される。絶望した彼女は銀座の街娼に転落。秀雄もまた大学を捨て、与太者の仲間入り、今では顔役になっている。
しかし、寛一だけは、まともに大学を卒業、新聞記者の職を得た。スーツ姿の寛一を見て春子は涙ぐむ。これで責任を果たしたと思い、泣き崩れながら「許しておくれ、実は、私は・・・」と真実を打ち明けようとする。寛一は春子の口をふさぎ「お母さん、何も言ってはいけません。私はわかっています。お母さんはボクにとって日本一のお母さんです」と言い放った。血のつながらない息子だけが、母に寄り添い孝行する景色は、たまらなく美しく、私の涙は止まらなかった。寛一は加代子や秀雄を見つけ出し「家に帰るように」と説得、二人は家の前まで来たが、どうしても足が前に進まずに引き返していく。
まもなく、悲劇の大詰めがやって来た。秀雄がヤクザ仲間に刺されたのである。事情を聞けば、雇われた会社の社長は根本嘉一、妻子を捨てて雲隠れした義父であったという。そんな会社はゴメンだと脱けようとして、「裏切り者」の制裁を受けたのだ。秀雄は「こんな姿はお母さんに見せたくない。黙っていてほしい」と言い残し、息を引き取る。寛一は、憤然として、嘉一の会社に乗り込んだ。「満蒙金鉱開発」を看板に、性懲りも無く、阿漕な経営をしている。父に向かって「一新聞記者として取材に来ました。あなたの会社はまともですか」「勿論」「では、なぜ不良連中を雇ったんです。弟の秀雄はそれで殺されたんですよ」驚く嘉一、次第に力が脱けうなだれていく。「お父さん、ボクはお母さんのために、秀雄のために、加代子のために、そして世間のために、自決を要求します」。 直ちに寛一は、新聞記者として、父の会社の不正を暴露する。その記事は「特ダネ」として表彰された。その報酬を持って家に帰ると、春子と加代子が泣いている。「お母さん、喜んでください。ボクは表彰されました」。しかし、春子は「私はそんなことをしてもらうために、大学を出したんじゃない。お父様に何と言ってお詫びをすればいいか・・」と泣き崩れた。寛一も泣いている「お詫びをしなければならないのはお父さんの方です。ボクは親の罪を世間に公表したんです。それで親孝行ができたんです」最後に「お父さんはお母さんに、くれぐれもよろしくと言っていましたよ」と言うと部屋を出た。
寛一は自室に行き、机の上にあった父親の似顔絵を壁に貼る。それは十年前、彼が描き、秀雄に与えたもの、秀雄はそれを今まで大切に保管していたのであった。そして、窓を開け外を眺める。目にしたのは夕刊を配達する少年の姿、その姿に昔の秀雄、あるいは自分自身の姿を重ねていたかもしれない。寛一の心中には、あの冒頭の歌・・・「並ぶ小窓にはすかいに 交わす声々日が落ちる 旅暮れて行く空の鳥 母の情けをしみじみと」・・・が聞こえていたに違いない。その少年の姿が消え去ると、この映画は「終」となった。
この映画の眼目は「生みの親より育ての親」という諺に象徴される、《絆》であることは間違いない。同時に、寛一にとっての「生みの親」(父)は罪深き詐欺師であり、加代子や秀雄にとっての「生みの親」(母)は世間に顔向けできない人非人なのである。寛一は父を許せない。加代子や秀雄は母を許せない。その悲しい人間模様が、実にきめ細やかな景色として、鮮やかに描き出されている。また、子ども時代、腕白でさぞかし親を手こずらせていたであろう寛一が、成人するにつれて人一倍、母を大切に思う姿も際立っていた。(突貫小僧から藤井貢へのバトンタッチという配役が見事である)それというのも春子が、三人の子どもに分け隔てない愛情を注いできたからに他ならない。吉川満子の表情一つ一つが、そのことを雄弁に物語る。三人の異母兄弟は、彼女の愛情によって固く結ばれていたのである。不幸にも秀雄は落命したが、残された寛一と加代子で春子を支え、さらに、改心した嘉一が、家族に加わる日も遠くはないだろうことを予感させる。清水宏監督、渾身の傑作であった、と私は思う。
(2017.6.2)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-23
付録・邦画傑作選・「島の娘」(監督・野村芳亭・1933年)
ユーチューブで映画「島の娘」(監督・野村芳亭・1933年)を観た。昭和中期以前の世代にとっては、あまりにも有名な流行歌「島の娘」(詞・長田幹彦、曲・佐々木俊一、歌・小唄勝太郎)を主題歌とするサイレント映画(オールサウンド版)である。タイトルと同時に、「島の娘」のメロディー(BGM)が流れ、原案・長田幹彦、脚色・柳井隆雄と示されているので、筋書きも「主(ぬし)は帰らぬ波の底」という歌詞を踏まえて作られたようだ。
冒頭の場面は、東京湾汽船の甲板、一人の学生が恋人とおぼしき女性の写真を取りだし、海に破り捨てた。その様子を見ていた水商売風の女が近づいて曰く「情死の相手が欲しいなら、私じゃいけません」「余計なお世話です」「短気なマネをしないでね」、しかし学生は応えずに離れて行った。学生の名は大河秀人(竹内良一)、一高出身の帝大生である。女は、酌婦のおしま(若水絹子)、流れ流れて、東京から大島に舞い戻ってきた風情だ。船室に戻って、女衒風の男(宮島健一)にタバコの火をもらう。「また、島の娘をさらいに来たんだね。だからあたしみたいなおばあちゃんが戻ってこなければならなくなるんだ」「人聞きが悪い。これも人助けなんだ」などと対話をするうちに、船は波浮の港に着いた。
そこの寺川屋旅館では、主人が他界後、屋台骨が傾き、伯父(河村黎吉)、女将(鈴木歌子)が、娘のお絹(坪内美子)を東京に売る算段を女衒風の男としている。それを知ったお絹は(亡父も許した)恋人の船員、月山一郎(江川宇礼雄)と束の間の逢瀬を浜辺で過ごす。「明日の船で東京に売られていきます。あたし、いっそのこと死にたい」「ボクだって死にたい。でも、あなたを死なせたら、可愛がってくれた、あなたのお父さんに申し訳ない」「生きましょう、生きて戦いましょう」「丈夫でいれば必ず合える」。しかし、お絹には「もう、これっきり会えない」予感があった。背景には、小唄勝太郎の「ハー 島で育てば娘十六恋心 一目忍んで主と一夜の仇情け」という歌声が流れ、お絹の「心もよう」が鮮やかに描出される。勝太郎は当時29歳、その美声はこの場面でしか堪能できない逸品だと、私は思った。
一方、帝大生の大河は、やはり死にどころを求めて大島にやって来たのだ。三原山に登ったが、自然の崇高さに打たれたか、椿の花を携えて麓に降りて来る。盛り場で客引き女に囲まれて料理屋の中へ、そこには船で一緒だったおしまが居た。「よく、もどってきたわね。世間は広いんだ。女に振られたくらいでで一生を無駄にしてはいけない」と優しく酒を注ぐ。辺りでは酌婦連中が、寺川屋の娘が売られていくという話をしている。「かわいそうに、あたしが代わってやりたいよ」「金が仇の世の中さ」。なるほど、寺川屋は土地でも評判の旅館であったことがわかる。時刻は11時を過ぎた。大河は「今夜はそこに泊まろう」と決めた。
大河が寺川屋へ向かう途中、一郎とバッタリ出会い道を訊ねる。一郎は船主(水島亮太郎)に借金を申し込んだが「二十、三十(円)なら何とかしようが、二千両となると無理だ。悪く思わんでくれ」と断られ、深夜の道をさまよっていたらしい。大河と出会ったのは郵便局の前、そういえば、お絹には兄さんがいた。もしかしたら、兄さんが帰ってきたのかもしれない。「あなたは寺川屋の親類の方ですか」「いえ、旅の者です」。大河と別れた時、郵便局の灯りが消えた。とっさに、一郎は郵便局に忍び込む。二階の金庫に手をかけたとき、灯りが点いた。一郎は二階から飛び降りて逃走したが、その姿を見られてしまった。
翌朝は一郎の船が北海道に向けて出航する。お絹もまた東京行きの船に乗ることになっていた。寺川屋では、その準備の最中、女将がお絹との別れを惜しんでいると、帳場に大河がやって来た。女衒に「そのお金があれば、解決できるのですね」と言い、財布から百円札を20枚、ポンと手渡す。「あやしい金ではありません。兄から分け与えられたもの、私には必要のない金です」。一同は、びっくり仰天、お絹は島に留まることができたのだ。お絹は、そのことを一郎に知らせようと女中(高松栄子)と一緒に港へ走ったが、船は出航していた。
寺川屋では大河に感謝、大河とお絹が四方山話をするうちに、五年前に亡くなった寺川屋の息子は、一高時代、大河の親友であったことが判明、伯父や女将は「倅の引き合わせかもしれません、ずっと長逗留してください」と勧める。
かくて、大河とお絹の交流が始まった。どうやら大河はお絹に惹かれている様子、三原山に登山行、椿の花を手折り弁当を食べながら、思いを告白しようとしたのだが・・・。お絹はそれを遮って「私には約束した人がいるんです」。大河は一瞬ガックリ、椿の花を投げ捨てたが、「そうだよな。それでいいんだ」と思ったか、亡兄の代わりを務めようと思ったか、お絹の相談にのる。一郎が郵便局に忍び込んだことがわかれば、伯父は結婚に反対するだろうというお絹の心配に「大した罪にはならないでしょう。二人が一緒になれるようボクが伯父さんに取り持ちますから安心して下さい」。伯父も快く承諾した。
月日が流れ、大河が東京に帰る日がやってきた。見送りにきたお絹に向かって「楽しい思い出をありがとう。一郎さんが戻ったら幸せな家庭を作ってください」。なぜかおしまも見送りに、「とうとう死なずに帰るのね」「あんたの言ったことは本当だったよ。おかげで美しい世界を見せて貰った。初めからやり直します。ありがとう」。
まもなく一郎の船も帰港する。その日、お絹は女中と一緒に、いそいそと桟橋に向かったが、降り立つ船員の中に一郎の姿はない。船長がお絹たちを船内に呼び、「僕は二度とお目にかかる資格のない人間になってしまいました。意気地のない僕を許してください。死んでもあなたを護っています。幸せに暮らしてください。お絹様 一郎」という文面の遺書と遺品を手渡す。本人の希望で水葬にしたとのこと、あの時 「もう、これっきり会えない」と思ったお絹の予感は当たったのである。
お絹は家に戻り、女中と遺品を整理する。一郎の帽子をしっかりと胸に抱きしめ泣いていると、東京から大河の小包が届いた。中には大河の「婚礼写真」の他に「祝い物」が添えられている。お絹と一郎の華燭を寿ぐ品に違いない。お絹は「大河様、おめでとうございます」と呟き、悲しみをこらえる他はなかった。
大詰めは、お絹と一郎が逢瀬を重ねた海岸の岩場、お絹が海を眺めて佇んでいる。やって来たのはおしま、「お嬢さん、お約束の人、お亡くなりになったんですってね。そうして海を見つめているお気持ち、私にはよく解ります。女はいつも悲しいものですわ。これまでに何度も死にたいと思いました。でも残った親、兄弟のことを思うと死ねませんでした」お絹も応えて「わたし死にません。辛くても我慢して、お母様のために生きて行きます」「私たちこんなに辛い目にあって生きているんだから、年をとってあの世に行ったら、きっと神様が可愛がってくれるでしょう」などと涙ながらに語り合う。やがて、お島は帯に挟んだからウィスキーの小瓶を取り出し、「一郎さんはお酒が好きだったのでしょう。飲ませてあげましょうね」と海に注いだ。その時、聞こえてきたのは小唄勝太郎の歌声、「ハー 沖は荒海吹いた東風(やませ)が別れ風 主は船乗り海の底・・・・」、まさに、この映画の眼目が艶やかに浮き彫りされる名場面であった。その声とお絹、おしまの二人の立ち姿が、大河の言う「美しい世界」を見事に描き出しており、私の涙は止まらなかった。
この映画の映像は「古色蒼然」、茫として見極められぬ場面も多い。動きもコマ落ちでぎこちない景色だが、さればこそ貴重な作品。戦前歌謡映画の傑作であることに変わりはない。中でも、小唄勝太郎の往時の美声に巡り会えたことは望外の幸せであった。
(2017.5.24)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

冒頭の場面は、東京湾汽船の甲板、一人の学生が恋人とおぼしき女性の写真を取りだし、海に破り捨てた。その様子を見ていた水商売風の女が近づいて曰く「情死の相手が欲しいなら、私じゃいけません」「余計なお世話です」「短気なマネをしないでね」、しかし学生は応えずに離れて行った。学生の名は大河秀人(竹内良一)、一高出身の帝大生である。女は、酌婦のおしま(若水絹子)、流れ流れて、東京から大島に舞い戻ってきた風情だ。船室に戻って、女衒風の男(宮島健一)にタバコの火をもらう。「また、島の娘をさらいに来たんだね。だからあたしみたいなおばあちゃんが戻ってこなければならなくなるんだ」「人聞きが悪い。これも人助けなんだ」などと対話をするうちに、船は波浮の港に着いた。
そこの寺川屋旅館では、主人が他界後、屋台骨が傾き、伯父(河村黎吉)、女将(鈴木歌子)が、娘のお絹(坪内美子)を東京に売る算段を女衒風の男としている。それを知ったお絹は(亡父も許した)恋人の船員、月山一郎(江川宇礼雄)と束の間の逢瀬を浜辺で過ごす。「明日の船で東京に売られていきます。あたし、いっそのこと死にたい」「ボクだって死にたい。でも、あなたを死なせたら、可愛がってくれた、あなたのお父さんに申し訳ない」「生きましょう、生きて戦いましょう」「丈夫でいれば必ず合える」。しかし、お絹には「もう、これっきり会えない」予感があった。背景には、小唄勝太郎の「ハー 島で育てば娘十六恋心 一目忍んで主と一夜の仇情け」という歌声が流れ、お絹の「心もよう」が鮮やかに描出される。勝太郎は当時29歳、その美声はこの場面でしか堪能できない逸品だと、私は思った。
一方、帝大生の大河は、やはり死にどころを求めて大島にやって来たのだ。三原山に登ったが、自然の崇高さに打たれたか、椿の花を携えて麓に降りて来る。盛り場で客引き女に囲まれて料理屋の中へ、そこには船で一緒だったおしまが居た。「よく、もどってきたわね。世間は広いんだ。女に振られたくらいでで一生を無駄にしてはいけない」と優しく酒を注ぐ。辺りでは酌婦連中が、寺川屋の娘が売られていくという話をしている。「かわいそうに、あたしが代わってやりたいよ」「金が仇の世の中さ」。なるほど、寺川屋は土地でも評判の旅館であったことがわかる。時刻は11時を過ぎた。大河は「今夜はそこに泊まろう」と決めた。
大河が寺川屋へ向かう途中、一郎とバッタリ出会い道を訊ねる。一郎は船主(水島亮太郎)に借金を申し込んだが「二十、三十(円)なら何とかしようが、二千両となると無理だ。悪く思わんでくれ」と断られ、深夜の道をさまよっていたらしい。大河と出会ったのは郵便局の前、そういえば、お絹には兄さんがいた。もしかしたら、兄さんが帰ってきたのかもしれない。「あなたは寺川屋の親類の方ですか」「いえ、旅の者です」。大河と別れた時、郵便局の灯りが消えた。とっさに、一郎は郵便局に忍び込む。二階の金庫に手をかけたとき、灯りが点いた。一郎は二階から飛び降りて逃走したが、その姿を見られてしまった。
翌朝は一郎の船が北海道に向けて出航する。お絹もまた東京行きの船に乗ることになっていた。寺川屋では、その準備の最中、女将がお絹との別れを惜しんでいると、帳場に大河がやって来た。女衒に「そのお金があれば、解決できるのですね」と言い、財布から百円札を20枚、ポンと手渡す。「あやしい金ではありません。兄から分け与えられたもの、私には必要のない金です」。一同は、びっくり仰天、お絹は島に留まることができたのだ。お絹は、そのことを一郎に知らせようと女中(高松栄子)と一緒に港へ走ったが、船は出航していた。
寺川屋では大河に感謝、大河とお絹が四方山話をするうちに、五年前に亡くなった寺川屋の息子は、一高時代、大河の親友であったことが判明、伯父や女将は「倅の引き合わせかもしれません、ずっと長逗留してください」と勧める。
かくて、大河とお絹の交流が始まった。どうやら大河はお絹に惹かれている様子、三原山に登山行、椿の花を手折り弁当を食べながら、思いを告白しようとしたのだが・・・。お絹はそれを遮って「私には約束した人がいるんです」。大河は一瞬ガックリ、椿の花を投げ捨てたが、「そうだよな。それでいいんだ」と思ったか、亡兄の代わりを務めようと思ったか、お絹の相談にのる。一郎が郵便局に忍び込んだことがわかれば、伯父は結婚に反対するだろうというお絹の心配に「大した罪にはならないでしょう。二人が一緒になれるようボクが伯父さんに取り持ちますから安心して下さい」。伯父も快く承諾した。
月日が流れ、大河が東京に帰る日がやってきた。見送りにきたお絹に向かって「楽しい思い出をありがとう。一郎さんが戻ったら幸せな家庭を作ってください」。なぜかおしまも見送りに、「とうとう死なずに帰るのね」「あんたの言ったことは本当だったよ。おかげで美しい世界を見せて貰った。初めからやり直します。ありがとう」。
まもなく一郎の船も帰港する。その日、お絹は女中と一緒に、いそいそと桟橋に向かったが、降り立つ船員の中に一郎の姿はない。船長がお絹たちを船内に呼び、「僕は二度とお目にかかる資格のない人間になってしまいました。意気地のない僕を許してください。死んでもあなたを護っています。幸せに暮らしてください。お絹様 一郎」という文面の遺書と遺品を手渡す。本人の希望で水葬にしたとのこと、あの時 「もう、これっきり会えない」と思ったお絹の予感は当たったのである。
お絹は家に戻り、女中と遺品を整理する。一郎の帽子をしっかりと胸に抱きしめ泣いていると、東京から大河の小包が届いた。中には大河の「婚礼写真」の他に「祝い物」が添えられている。お絹と一郎の華燭を寿ぐ品に違いない。お絹は「大河様、おめでとうございます」と呟き、悲しみをこらえる他はなかった。
大詰めは、お絹と一郎が逢瀬を重ねた海岸の岩場、お絹が海を眺めて佇んでいる。やって来たのはおしま、「お嬢さん、お約束の人、お亡くなりになったんですってね。そうして海を見つめているお気持ち、私にはよく解ります。女はいつも悲しいものですわ。これまでに何度も死にたいと思いました。でも残った親、兄弟のことを思うと死ねませんでした」お絹も応えて「わたし死にません。辛くても我慢して、お母様のために生きて行きます」「私たちこんなに辛い目にあって生きているんだから、年をとってあの世に行ったら、きっと神様が可愛がってくれるでしょう」などと涙ながらに語り合う。やがて、お島は帯に挟んだからウィスキーの小瓶を取り出し、「一郎さんはお酒が好きだったのでしょう。飲ませてあげましょうね」と海に注いだ。その時、聞こえてきたのは小唄勝太郎の歌声、「ハー 沖は荒海吹いた東風(やませ)が別れ風 主は船乗り海の底・・・・」、まさに、この映画の眼目が艶やかに浮き彫りされる名場面であった。その声とお絹、おしまの二人の立ち姿が、大河の言う「美しい世界」を見事に描き出しており、私の涙は止まらなかった。
この映画の映像は「古色蒼然」、茫として見極められぬ場面も多い。動きもコマ落ちでぎこちない景色だが、さればこそ貴重な作品。戦前歌謡映画の傑作であることに変わりはない。中でも、小唄勝太郎の往時の美声に巡り会えたことは望外の幸せであった。
(2017.5.24)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-21
付録・邦画傑作選・「青春の夢いまいずこ」(監督・小津安二郎・1932年)
ユーチューブで映画「青春の夢いまいづこ」(監督・小津安二郎・1932年)を観た。この作品は三年前の「学生ロマンス若き日」、二年前の「落第はしたけれど」に続く、第3弾とでもいえようか。戦前の青春ドラマ(学生ロマンス)の中でも屈指の名品である。
舞台は前作と同じW大学、登場する俳優も、齋藤達雄、大山健二、笠智衆、田中絹代、飯田蝶子といった常連に、江川宇礼雄が加わった。
冒頭場面は大学構内、例によって応援部の連中が学生を集めて練習をしている。そこには熊田(大山健二)、島崎(笠智衆)、堀野(江川宇礼雄)らの顔が見えるが、斎木(齋藤達雄)の姿はない。彼は貧しい母子家庭のため遊んでいる隙はないのだ。休憩時でも時間を惜しんで本を読んでいる。しかし、成績は振るわない。教授の話では「中学レベル」だそうだ。しかし、熊田、島崎、堀野たちは斎木を見捨てない。ともすれば孤立しがちの斎木を、だからこそ仲間として大切に思う。それが往時の「学生気質」(友情)なのである。というのも、彼らに共通するのは「勉強嫌い」で「遊び好き」、試験の際にはカンニングで協力し合う、固い絆で結ばれているからだ。
学生たちに人気のあるのがべーカリー軒の娘・お繁(田中絹代)、大学構内に、おか持ちを下げて出前もしている。堀野たちも授業の合間にベーカリー軒に通い、お繁との親交を重ねていた。とりわけ、堀野はお繁に御執心、彼は今をときめく堀野商事社長(武田春郞)の御曹司とくれば、お繁が玉の輿に乗れるのは間近であった筈なのだが・・・。
堀野が帰宅すると、山村男爵夫人(葛城文子)と令嬢(伊達里子)が応接室で待っていた。令嬢の風情はどう見ても気障なモガ、舶来のライターで紙巻きタバコをプカプカ吹かしている。父の話では、伯父(水島亮太郎)の紹介(縁談話)で「お前に会いに来た」由、「お父さん、そんな話、断って下さい」、父も同意して「息子は酒を飲むと乱暴になります」。令嬢は「まあ、素敵! 男はそれでなくっちゃ」などと動じない。「ドロボーもしますよ」とダメを押せば「私も哲夫さんの心を盗みたい」などとほざく。いよいよ、堀野本人が登場して、ライターを放り投げる、ハンドバックが灰皿替わり、などの狼藉を加えれば、令嬢の怒りは爆発、たちまち縁談破談となった。その様子を見て父と息子は大笑い、二人で祝杯を挙げる。「ワシもあんな娘は気に入らない」、父子の気持ちは通じていたのである。
翌日は、大学の試験日。例によって試験官の目を盗み、堀野たちがカンニングを試みているところに、小使い(坂本武)がやって来た。この小使い、学生の間でも人気がある。ある時など、ベーカリー軒で将棋を指していた熊田と堀野の勝負がつかず、将棋盤を持ったまま教室に向かう二人を見て、自分もその仲間入り、三人で教室に入り込む。講義が始まってもまだ指している。教授に見咎められ、あわてて抜き足差し足、へっぴり腰で教室を退出する姿がたいそう可笑しかった。
試験官は小使いの話を聞いて、顔を曇らせた。「おい、堀野!お父さんが病気だ。すぐ帰宅しなさい。試験は追試験を受ければよい」。堀野は、「朝まで元気だったのに、信じられない」という思いで、あわてて帰宅。自宅には伯父を初め多くの社員が詰めかけている。父は脳溢血のため危篤状態、号泣する堀野に手を握られながら、まもなく息を引き取った。
かくて、堀野はやむなく大学を中退、堀野商事の新社長に就任する。副社長の伯父がその旨を社員一同に説明するのだが話が長すぎる。もう1時間半も話し続けているのだ。早く終わりにしてくれという空気の中で、いよいよ新社長の挨拶となった。堀野は一同の前で、ぺこりと頭を下げると「親爺同様、よろしくお願いします」という一言だけで終わった。割れるような拍手、幸先よいスタートを切ったのである。
数日後の朝、出勤前の堀野が準備をしていると、婆やが「近頃は、お坊ちゃまも社長らしく成ってきましたね」などと言う。その時、熊田、島崎、斎木が訪れた。「俺たちを君の会社で雇わないか」と言う。堀野にも異存はないが「入社試験があるぞ。合格できるかな。その前に卒業できるのか」と冷やかした。
まもなく入社試験日、熊田、島崎、斎木たちは「①インフレーションとは何ぞや、②9月18日事件とは何ぞや ③次の語句を簡単に説明せよ イ・リットン報告 ロ・生命線ハ・ホラ信 ニ・天国に結ぶ恋 ホ・大塩平八郎」という問題を前に悪戦苦闘している。それでも熊田と島崎は得意のカンニングを駆使して合格しそう(答案を事前に入手済み)、斎木だけがボンヤリしている。どうやら答案をなくしたらしい。監視に来た堀野はその様子を見て、問題作成者から答案を取り寄せ、丸めて斎木の足元に落とす。斎木は堀野を見やって頬笑む。堀野もまたうなずいて微笑み返した。その様子を、すでに無事書き終えた熊田が寿ぐ。まさに、今でも学生時代の友情でしっかりと結ばれている景色が鮮やかであった。ちなみに、「9.18事件」とは、柳条湖事件のことである。「リットン報告」とは、「国際連盟日支紛争調査委員会報告書」のことであり、リットンとはその委員長の名前である。「生命線」とは、満州国のことである。「天国に結ぶ恋」とは、坂田山で心中した大学生と女学生の純愛を詠った流行歌のことである。「大塩平八郎」とは江戸幕府に反乱を起こした大阪奉行与力の名前である。さて「ホラ信」とは何ぞや、私にもわからなかった。
次の字幕には「一難去ってまた一難」。
伯父はまたまた堀野に縁談話を持ってきた。これで6回目である。ある令嬢を引き合わせて「映画にでも・・・」と促す。堀野は渋々承知して自動車で映画館に向かう。令嬢は「シネマなんかより、二人切りになれる所に行かない」「大磯の坂田山へでも行きますか」「まあ嬉しい」と令嬢がしなだれかかる。堀野は辟易として窓の外に目をやると、お繁が歩いている。その隣には大きな荷車が。自動車を止めて事情を聞くと、近頃は学生さんも不景気で、ベーカリー軒は閉業、これからアパートに引っ越すのだと言う。デパートの売り子にでもなるつもり、「それならボクの会社に来たらどうだい。学生の二、三人も入ったから、君を歓迎すると思うよ」。堀野は欣然として立ち戻り、令嬢に向かって「引っ越しの手伝いをするので、ボクはここで失礼します。どうぞボクにお構いなく」と言うなり、自動車に荷車の荷物をどんどん運び込む。令嬢はいたたまれず、自動車を降りてプイとどこかに行ってしまった。お繁のアパートで荷物の整理をしていると、ドアを叩く音がする。花束を携えた斎木がやって来た。中に堀野が居るのを見て、バツが悪そうだったが、堀野は「よおーっ、会社をサボってきたのか。たまにはいいだろう。安い月給なんだから」と鷹揚に迎えた。お繁も「あたし、明日から会社のお仲間よ」と報告するが、斎木はどうしてもバツが悪い。堀野から「ボンヤリしてないで、君も手伝えよ」と誘われても「これから会社に戻るよ」と花束をお繁に渡して、出て行ってしまった。堀野は「熊田も、島崎もボクを社長扱いするんだ、さびしいなあ」と溜息を吐く。
翌日、社長室では伯父がカンカンに怒っていた。「いったい何度ワシにに恥をかかせれば気が済むんだ。これで五度目だぞ」「六度目ですよ」「益々もってけしからん」堀野は初めて本心を打ち明けた。「実は、学生時代から好きな娘がいるんです」「それを何故もっと早く言わんか。それで、どんな娘だい?」「それはしばらくボクに預からせてください」。
その夜、堀野は熊田、島崎、斎木と銀座でビールを飲みながら会食する。「学生時代、お繁ちゃんは俺たちの共有財産だった。その人をオレが独占する以上、諸君の意見を聞きたい。」三人は神妙な面持ちで聞いていたが、斎木はうつむき加減、「斎木、どう思う?」、斎木はようやく顔をあげて「異論はないよ」、熊田も島崎も同意した。「じゃあ乾杯だ。さあ、飲もう」。堀野の心は躍る。斎木は堀野を見つめ頬笑み、天井に目をやる、勢いよく回っていた扇風機が次第に弱まり、力なく止まった。
堀野が帰宅すると、斎木の母(飯田蝶子)が訪れていた。満面の笑みを浮かべて、堀野に感謝する。「この就職難の折に、お宝を頂けるなんて、あなた様のお陰だと、私どもは毎日、お宅様の方をあ拝んでおりますよ」。堀野も笑いながら「拝むんならボクではなく、一日も早く斎木君に嫁でもらって早くラクになることですね」と応じれば「それが、大変都合よく嫁が見つかったんです」、それはおめでたい、いったいどなたですと訊ねる前に、斎木の母は「御存知と思いますが、学校の前の洋食屋にいたお繁さんという娘なんです」。堀野の顔が変わった。「そうですか、それはいつの話ですか」「卒業する一ト月頃前でしょうか、初めて私に打ち明けたんです」。堀野の心は千々に乱れた。その足で、すぐお繁のアパートへ。「早速だけど、お繁ちゃんは斎木と結婚の約束をしたのかい」、お繁は頷く。「なんだって、斎木なんかと・・・、君は学生時代、ボクがどう思っていたかわからなかったのか」「あたし、もう二度とあなたは戻ってこないと思って、あきらめていたんです。その時に斎木さんからお話があって。いつも皆さんの後からとぼとぼ付いていく斎木さんがお気の毒だったんです。あたしの力で斎木さんの灰色の生活を明るくしようと思ったんです。あたしのような者でなければ、斎木さんのお嫁になる人はいないでしょう。」堀野は、帰ろうとする。「お怒りになったの」「その気持ちでいつまでも斎木を愛してやってくれ給え」という言葉を精一杯残し、振り返ることはなかった。お繁が見送ろうとして窓を開けると、花火が一発、美しい模様を描き出して消えた。
斎木の下宿先では、熊田、島崎と三人で苦いビールを飲んでいる。消沈した母も居る。島崎は「口じゃあ何とでも言っても、彼奴も普通の社長さ。社長と女事務員、おあつらえどおりの型だ」と冷ややかな口調、熊田は「お繁ちゃんばかりが女じゃない。気を落とさないように。また、いい娘を見つければいい」と斎木をいたわる。母が「近頃じゃ、おまんまを頂くのも大変になりましたね」と取りなすが、ビールが先に進まない。それじゃあ、と熊田が腰を上げ、帰路に就く。そこまで一緒に行こうと、斎木も連れだって三人が夜道を歩き出した。(その直後から映画の画面は極端に暗転、「ケラレ」状態になる。人物の心象を浮き彫りにするためか、それとも撮影の不具合か。)向こうから自動車が近づいて来る。乗っていたのは堀野、今、斎木の家に向かう途中であった。「みんな一緒でちょうどいい、斎木に話があって来たんだ」。しばらく歩きながら、堀野は斎木に詰問する。「君はどういう気持ちで、お繁ちゃんとオレの結婚に賛成したんだ」「・・・」「君はオレが友だちの恋人を奪って喜ぶ男だと思っているのか」「・・・」「斎木、グズグズしないでハッキリ返事しろ!」島崎が「斎木だって君に厚意を示したいと思ってしたことだ。そう頭から責めちゃかわいそうじゃないか」と間に入ると「オレは君たちにも言い分があるんだ。オレの前に出ると犬みたいに尻尾を振って、それでも友だちなのか。いつ、そんなことをしてくれと頼んだ、いつ喜んだ」「・・・」「学校時代の友情はどこへ行ったんだ!」。ようやく、斎木が口を開いた。「僕達親子が幸せに暮らせるのは君のおかげだ。社長の君に逆らうことは僕達の生活に逆らうことなんだ」といった瞬間、堀野の鉄拳が飛んだ。よろめく斎木に向かって「そんなことで恋人まで譲る奴があるか、馬鹿!」。なおも殴りかかろうとのを熊田と島崎が必死で止める。「オレの言い分のどこが間違っているか。もしそう思うなら、オレを殴るなり蹴るなり、何とでもしろ」と叫ぶ。熊田と島崎は、掴んでいた斎木の腕を静かに放した。「オレは斎木の卑屈な気持ちを叩き直してやるんだ」というなり、無抵抗の斎木の頬を10回、20回・・・41回と平手打ちする。顔を押さえて斎木は崩れ落ちた。熊田が堀野に近づいて「すまなかった」、島崎も深々と頭を下げた。そうか、わかってくてたかと、堀野は斎木の前にひざまづき、「ゆるしてくれ」と嗚咽する。しっかりと斎木の手を握り、斎木も力強く握り返す。そして、青春の夢は今、蘇ったのである。堀野の胸裡には、優しかった父の臨終の時、手を握って泣き崩れた自分の姿が浮かんできたかもしれない
大詰めは、丸の内にあるビルの屋上、昼休みの社員がくつろいでいる所に、堀野がやって来た。熊田と島津がキャッツボールの手を止めて、「もう、そろそろだぞ」。三人で、新婚旅行に向かう斎木とお繁を見送るつもり。熱海に向かう東海道線が通過する。「あそこだ!手を振っている」。三人もまた列車に向かって大きく手を振る。列車の中でも斎木とお繁がハンカチを振っている。屋上の三人が顔を見合わせて頬笑むうちに、この映画は「終」となった。
この映画の眼目は、文字通り「青春の夢」、門地、身分、貧富を超えた「友情」であろう。その夢は往々にして崩される。お繁の本心は堀野の玉の輿の乗ることだが、それは夢、早々にあきらめて、風采の上がらない斎木をさせようとする。「友情」というよりは「同情」である。そのことを斎木は堀野に言い出せない。島崎は「厚意」(厚情)と思ったが、堀野は「卑屈」だと感じる。斎木の「僕達親子が幸せに暮らせるのは君のおかげだ。社長の君に逆らうことは僕達の生活に逆らうことなんだ」という言葉が許せない。もっと自信を持て、「逆らわない人生」で自分を守るなんて、卑屈としか言いようがない。その言い分に、熊田も島崎も逆らうことができなかったということは皮肉である。いずれにせよ、最も傷ついたのは堀野自身であったはずだが、彼には「社長」という重責がある。卑屈になぞなっていられない(メソメソしていられない、他人を恨んだりする暇がない)事情があるのだ。その精神は、敬愛する父親から学んだ賜物かもしれない。はたして、斎木の卑屈な気持ちは、堀野の鉄拳によってどこまで払拭されたか、そこが問題である。
小津安二郎監督は、この映画の前作「大人の絵本 生まれてはみたけれど」で、ほぼ同じ「卑屈」という問題を取り上げている。子ども時代は「実力主義」だが、大人になると「金権主義」に変貌していく世の中を、子どもの目から捉えた佳品である。その子どもたちの成長した結果が、「青春の夢いまいずこ」だとすれば、斎木の卑屈な気持ちは払拭されなければならない。そこらあたりが小津監督の願いを込めた結論ではないだろうか。(2017.6.3)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

舞台は前作と同じW大学、登場する俳優も、齋藤達雄、大山健二、笠智衆、田中絹代、飯田蝶子といった常連に、江川宇礼雄が加わった。
冒頭場面は大学構内、例によって応援部の連中が学生を集めて練習をしている。そこには熊田(大山健二)、島崎(笠智衆)、堀野(江川宇礼雄)らの顔が見えるが、斎木(齋藤達雄)の姿はない。彼は貧しい母子家庭のため遊んでいる隙はないのだ。休憩時でも時間を惜しんで本を読んでいる。しかし、成績は振るわない。教授の話では「中学レベル」だそうだ。しかし、熊田、島崎、堀野たちは斎木を見捨てない。ともすれば孤立しがちの斎木を、だからこそ仲間として大切に思う。それが往時の「学生気質」(友情)なのである。というのも、彼らに共通するのは「勉強嫌い」で「遊び好き」、試験の際にはカンニングで協力し合う、固い絆で結ばれているからだ。
学生たちに人気のあるのがべーカリー軒の娘・お繁(田中絹代)、大学構内に、おか持ちを下げて出前もしている。堀野たちも授業の合間にベーカリー軒に通い、お繁との親交を重ねていた。とりわけ、堀野はお繁に御執心、彼は今をときめく堀野商事社長(武田春郞)の御曹司とくれば、お繁が玉の輿に乗れるのは間近であった筈なのだが・・・。
堀野が帰宅すると、山村男爵夫人(葛城文子)と令嬢(伊達里子)が応接室で待っていた。令嬢の風情はどう見ても気障なモガ、舶来のライターで紙巻きタバコをプカプカ吹かしている。父の話では、伯父(水島亮太郎)の紹介(縁談話)で「お前に会いに来た」由、「お父さん、そんな話、断って下さい」、父も同意して「息子は酒を飲むと乱暴になります」。令嬢は「まあ、素敵! 男はそれでなくっちゃ」などと動じない。「ドロボーもしますよ」とダメを押せば「私も哲夫さんの心を盗みたい」などとほざく。いよいよ、堀野本人が登場して、ライターを放り投げる、ハンドバックが灰皿替わり、などの狼藉を加えれば、令嬢の怒りは爆発、たちまち縁談破談となった。その様子を見て父と息子は大笑い、二人で祝杯を挙げる。「ワシもあんな娘は気に入らない」、父子の気持ちは通じていたのである。
翌日は、大学の試験日。例によって試験官の目を盗み、堀野たちがカンニングを試みているところに、小使い(坂本武)がやって来た。この小使い、学生の間でも人気がある。ある時など、ベーカリー軒で将棋を指していた熊田と堀野の勝負がつかず、将棋盤を持ったまま教室に向かう二人を見て、自分もその仲間入り、三人で教室に入り込む。講義が始まってもまだ指している。教授に見咎められ、あわてて抜き足差し足、へっぴり腰で教室を退出する姿がたいそう可笑しかった。
試験官は小使いの話を聞いて、顔を曇らせた。「おい、堀野!お父さんが病気だ。すぐ帰宅しなさい。試験は追試験を受ければよい」。堀野は、「朝まで元気だったのに、信じられない」という思いで、あわてて帰宅。自宅には伯父を初め多くの社員が詰めかけている。父は脳溢血のため危篤状態、号泣する堀野に手を握られながら、まもなく息を引き取った。
かくて、堀野はやむなく大学を中退、堀野商事の新社長に就任する。副社長の伯父がその旨を社員一同に説明するのだが話が長すぎる。もう1時間半も話し続けているのだ。早く終わりにしてくれという空気の中で、いよいよ新社長の挨拶となった。堀野は一同の前で、ぺこりと頭を下げると「親爺同様、よろしくお願いします」という一言だけで終わった。割れるような拍手、幸先よいスタートを切ったのである。
数日後の朝、出勤前の堀野が準備をしていると、婆やが「近頃は、お坊ちゃまも社長らしく成ってきましたね」などと言う。その時、熊田、島崎、斎木が訪れた。「俺たちを君の会社で雇わないか」と言う。堀野にも異存はないが「入社試験があるぞ。合格できるかな。その前に卒業できるのか」と冷やかした。
まもなく入社試験日、熊田、島崎、斎木たちは「①インフレーションとは何ぞや、②9月18日事件とは何ぞや ③次の語句を簡単に説明せよ イ・リットン報告 ロ・生命線ハ・ホラ信 ニ・天国に結ぶ恋 ホ・大塩平八郎」という問題を前に悪戦苦闘している。それでも熊田と島崎は得意のカンニングを駆使して合格しそう(答案を事前に入手済み)、斎木だけがボンヤリしている。どうやら答案をなくしたらしい。監視に来た堀野はその様子を見て、問題作成者から答案を取り寄せ、丸めて斎木の足元に落とす。斎木は堀野を見やって頬笑む。堀野もまたうなずいて微笑み返した。その様子を、すでに無事書き終えた熊田が寿ぐ。まさに、今でも学生時代の友情でしっかりと結ばれている景色が鮮やかであった。ちなみに、「9.18事件」とは、柳条湖事件のことである。「リットン報告」とは、「国際連盟日支紛争調査委員会報告書」のことであり、リットンとはその委員長の名前である。「生命線」とは、満州国のことである。「天国に結ぶ恋」とは、坂田山で心中した大学生と女学生の純愛を詠った流行歌のことである。「大塩平八郎」とは江戸幕府に反乱を起こした大阪奉行与力の名前である。さて「ホラ信」とは何ぞや、私にもわからなかった。
次の字幕には「一難去ってまた一難」。
伯父はまたまた堀野に縁談話を持ってきた。これで6回目である。ある令嬢を引き合わせて「映画にでも・・・」と促す。堀野は渋々承知して自動車で映画館に向かう。令嬢は「シネマなんかより、二人切りになれる所に行かない」「大磯の坂田山へでも行きますか」「まあ嬉しい」と令嬢がしなだれかかる。堀野は辟易として窓の外に目をやると、お繁が歩いている。その隣には大きな荷車が。自動車を止めて事情を聞くと、近頃は学生さんも不景気で、ベーカリー軒は閉業、これからアパートに引っ越すのだと言う。デパートの売り子にでもなるつもり、「それならボクの会社に来たらどうだい。学生の二、三人も入ったから、君を歓迎すると思うよ」。堀野は欣然として立ち戻り、令嬢に向かって「引っ越しの手伝いをするので、ボクはここで失礼します。どうぞボクにお構いなく」と言うなり、自動車に荷車の荷物をどんどん運び込む。令嬢はいたたまれず、自動車を降りてプイとどこかに行ってしまった。お繁のアパートで荷物の整理をしていると、ドアを叩く音がする。花束を携えた斎木がやって来た。中に堀野が居るのを見て、バツが悪そうだったが、堀野は「よおーっ、会社をサボってきたのか。たまにはいいだろう。安い月給なんだから」と鷹揚に迎えた。お繁も「あたし、明日から会社のお仲間よ」と報告するが、斎木はどうしてもバツが悪い。堀野から「ボンヤリしてないで、君も手伝えよ」と誘われても「これから会社に戻るよ」と花束をお繁に渡して、出て行ってしまった。堀野は「熊田も、島崎もボクを社長扱いするんだ、さびしいなあ」と溜息を吐く。
翌日、社長室では伯父がカンカンに怒っていた。「いったい何度ワシにに恥をかかせれば気が済むんだ。これで五度目だぞ」「六度目ですよ」「益々もってけしからん」堀野は初めて本心を打ち明けた。「実は、学生時代から好きな娘がいるんです」「それを何故もっと早く言わんか。それで、どんな娘だい?」「それはしばらくボクに預からせてください」。
その夜、堀野は熊田、島崎、斎木と銀座でビールを飲みながら会食する。「学生時代、お繁ちゃんは俺たちの共有財産だった。その人をオレが独占する以上、諸君の意見を聞きたい。」三人は神妙な面持ちで聞いていたが、斎木はうつむき加減、「斎木、どう思う?」、斎木はようやく顔をあげて「異論はないよ」、熊田も島崎も同意した。「じゃあ乾杯だ。さあ、飲もう」。堀野の心は躍る。斎木は堀野を見つめ頬笑み、天井に目をやる、勢いよく回っていた扇風機が次第に弱まり、力なく止まった。
堀野が帰宅すると、斎木の母(飯田蝶子)が訪れていた。満面の笑みを浮かべて、堀野に感謝する。「この就職難の折に、お宝を頂けるなんて、あなた様のお陰だと、私どもは毎日、お宅様の方をあ拝んでおりますよ」。堀野も笑いながら「拝むんならボクではなく、一日も早く斎木君に嫁でもらって早くラクになることですね」と応じれば「それが、大変都合よく嫁が見つかったんです」、それはおめでたい、いったいどなたですと訊ねる前に、斎木の母は「御存知と思いますが、学校の前の洋食屋にいたお繁さんという娘なんです」。堀野の顔が変わった。「そうですか、それはいつの話ですか」「卒業する一ト月頃前でしょうか、初めて私に打ち明けたんです」。堀野の心は千々に乱れた。その足で、すぐお繁のアパートへ。「早速だけど、お繁ちゃんは斎木と結婚の約束をしたのかい」、お繁は頷く。「なんだって、斎木なんかと・・・、君は学生時代、ボクがどう思っていたかわからなかったのか」「あたし、もう二度とあなたは戻ってこないと思って、あきらめていたんです。その時に斎木さんからお話があって。いつも皆さんの後からとぼとぼ付いていく斎木さんがお気の毒だったんです。あたしの力で斎木さんの灰色の生活を明るくしようと思ったんです。あたしのような者でなければ、斎木さんのお嫁になる人はいないでしょう。」堀野は、帰ろうとする。「お怒りになったの」「その気持ちでいつまでも斎木を愛してやってくれ給え」という言葉を精一杯残し、振り返ることはなかった。お繁が見送ろうとして窓を開けると、花火が一発、美しい模様を描き出して消えた。
斎木の下宿先では、熊田、島崎と三人で苦いビールを飲んでいる。消沈した母も居る。島崎は「口じゃあ何とでも言っても、彼奴も普通の社長さ。社長と女事務員、おあつらえどおりの型だ」と冷ややかな口調、熊田は「お繁ちゃんばかりが女じゃない。気を落とさないように。また、いい娘を見つければいい」と斎木をいたわる。母が「近頃じゃ、おまんまを頂くのも大変になりましたね」と取りなすが、ビールが先に進まない。それじゃあ、と熊田が腰を上げ、帰路に就く。そこまで一緒に行こうと、斎木も連れだって三人が夜道を歩き出した。(その直後から映画の画面は極端に暗転、「ケラレ」状態になる。人物の心象を浮き彫りにするためか、それとも撮影の不具合か。)向こうから自動車が近づいて来る。乗っていたのは堀野、今、斎木の家に向かう途中であった。「みんな一緒でちょうどいい、斎木に話があって来たんだ」。しばらく歩きながら、堀野は斎木に詰問する。「君はどういう気持ちで、お繁ちゃんとオレの結婚に賛成したんだ」「・・・」「君はオレが友だちの恋人を奪って喜ぶ男だと思っているのか」「・・・」「斎木、グズグズしないでハッキリ返事しろ!」島崎が「斎木だって君に厚意を示したいと思ってしたことだ。そう頭から責めちゃかわいそうじゃないか」と間に入ると「オレは君たちにも言い分があるんだ。オレの前に出ると犬みたいに尻尾を振って、それでも友だちなのか。いつ、そんなことをしてくれと頼んだ、いつ喜んだ」「・・・」「学校時代の友情はどこへ行ったんだ!」。ようやく、斎木が口を開いた。「僕達親子が幸せに暮らせるのは君のおかげだ。社長の君に逆らうことは僕達の生活に逆らうことなんだ」といった瞬間、堀野の鉄拳が飛んだ。よろめく斎木に向かって「そんなことで恋人まで譲る奴があるか、馬鹿!」。なおも殴りかかろうとのを熊田と島崎が必死で止める。「オレの言い分のどこが間違っているか。もしそう思うなら、オレを殴るなり蹴るなり、何とでもしろ」と叫ぶ。熊田と島崎は、掴んでいた斎木の腕を静かに放した。「オレは斎木の卑屈な気持ちを叩き直してやるんだ」というなり、無抵抗の斎木の頬を10回、20回・・・41回と平手打ちする。顔を押さえて斎木は崩れ落ちた。熊田が堀野に近づいて「すまなかった」、島崎も深々と頭を下げた。そうか、わかってくてたかと、堀野は斎木の前にひざまづき、「ゆるしてくれ」と嗚咽する。しっかりと斎木の手を握り、斎木も力強く握り返す。そして、青春の夢は今、蘇ったのである。堀野の胸裡には、優しかった父の臨終の時、手を握って泣き崩れた自分の姿が浮かんできたかもしれない
大詰めは、丸の内にあるビルの屋上、昼休みの社員がくつろいでいる所に、堀野がやって来た。熊田と島津がキャッツボールの手を止めて、「もう、そろそろだぞ」。三人で、新婚旅行に向かう斎木とお繁を見送るつもり。熱海に向かう東海道線が通過する。「あそこだ!手を振っている」。三人もまた列車に向かって大きく手を振る。列車の中でも斎木とお繁がハンカチを振っている。屋上の三人が顔を見合わせて頬笑むうちに、この映画は「終」となった。
この映画の眼目は、文字通り「青春の夢」、門地、身分、貧富を超えた「友情」であろう。その夢は往々にして崩される。お繁の本心は堀野の玉の輿の乗ることだが、それは夢、早々にあきらめて、風采の上がらない斎木をさせようとする。「友情」というよりは「同情」である。そのことを斎木は堀野に言い出せない。島崎は「厚意」(厚情)と思ったが、堀野は「卑屈」だと感じる。斎木の「僕達親子が幸せに暮らせるのは君のおかげだ。社長の君に逆らうことは僕達の生活に逆らうことなんだ」という言葉が許せない。もっと自信を持て、「逆らわない人生」で自分を守るなんて、卑屈としか言いようがない。その言い分に、熊田も島崎も逆らうことができなかったということは皮肉である。いずれにせよ、最も傷ついたのは堀野自身であったはずだが、彼には「社長」という重責がある。卑屈になぞなっていられない(メソメソしていられない、他人を恨んだりする暇がない)事情があるのだ。その精神は、敬愛する父親から学んだ賜物かもしれない。はたして、斎木の卑屈な気持ちは、堀野の鉄拳によってどこまで払拭されたか、そこが問題である。
小津安二郎監督は、この映画の前作「大人の絵本 生まれてはみたけれど」で、ほぼ同じ「卑屈」という問題を取り上げている。子ども時代は「実力主義」だが、大人になると「金権主義」に変貌していく世の中を、子どもの目から捉えた佳品である。その子どもたちの成長した結果が、「青春の夢いまいずこ」だとすれば、斎木の卑屈な気持ちは払拭されなければならない。そこらあたりが小津監督の願いを込めた結論ではないだろうか。(2017.6.3)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-21
付録・邦画傑作選・「女の歴史」(監督・成瀬巳喜男・1963年)
ユーチューブで映画「女の歴史」(監督・成瀬巳喜男・1963年)を観た。この映画には三組の男女が登場する。一は清水幸一(宝田明)と信子(高峰秀子)の夫婦、二は幸一の父・清水正二郎(清水元)と母・君子(夏原夏子)の夫婦、三は幸一の息子・功平(少年期・堀米広幸、成人後・山崎努)と恋人・富永みどり(星由里子)のカップルである。 時代は戦前、戦中、敗戦直後から戦後にかけて、舞台は東京深川、栃木の疎開先、東京自由が丘へと移りゆく中で、男は次々と死に、女だけが「たくましく」生き抜いていく、文字通り「女の歴史」が鮮やかに描かれていた。その主人公・信子は深川の商人・増田兼吉(藤原釜足)、つね(菅井きん)夫妻の娘として成長し、木場の材木問屋の息子・幸一と見合いで結ばれた。まもなく一子・功平が誕生したが、幸一の父・正二郎は湯河原で馴染みの芸者と情死、幸一も応召し戦死する。信子の実家も東京大空襲で全滅、信子は女手一つで姑の君子を養い、息子の功平を育てることになった。戦中は防災訓練、疎開先の畑作業、戦後は闇屋などと「力仕事」も健気にこなす。闇屋の得意先、美容院を経営する三沢玉枝(淡路恵子)の縁があったか、信子も美容院を開業、功平も成人して自動車のセールスマンになった。マイカーで着々と顧客を増やし、会社では有望株、接待で行きつけのキャバレー・ホステス富永みどりと恋仲になり結婚の約束をする。信子に承諾を求めたが拒否され、功平はさっさと団地で新所帯を構える。しかし、突然の交通事故で功平も他界、つまりは信子と姑の君子だけが残される羽目に・・・。葬儀も終えたある雨の日のこと・・・、信子は生きがいをなくし放心状態、功平の遺影を前にして、君子は「これであんたもあたしも他人になった、あたしは老人ホームに入るよ」と言う。「お母さんさえよければ、あたしは今のままでいいのよ」などと語り合うところに、突然、みどりがやって来た。信子は「ここはあなたの来るところではない。功平をあたしから取りあげて、命まで落とさせてしまったんだ。早く出て行って」となじる。みどりは「私のお腹には赤ちゃんがいます」。信子は一瞬絶句、「・・・誰の子どもかわかりゃあしない」「戸籍も入っています。この謄本を見て下さい」。君子が「へえ、功平は戸籍まで入れたのか」と、うれしそうに取りなしたが、「おばあちゃんは黙っていて下さい」と突っぱねた。売り言葉に買い言葉、みどりは「では、殺します。お金をください」。信子は札束をみどりの前に放り出す。たまらず、みどりは立ち去った。君子が「アレ、お金、置いて行っちゃったよ。男なんて勝手なもんだ。あたしの亭主も、幸一も、功平も、女に子どもを産ませてさっさと逝ってしまった。今度、生まれてくるときは、あたしは絶対、男にするよ。・・・でも、功平の子どもがいたなんて、おしい気もするねえ」と言う。その嘆きを聞いて信子の気が変わった。あわてて、みどりの団地に向かいドアを叩いたが留守、隣人(塩沢とき)が「今まで、家に居たんだけど、病院に行きましたよ」。信子は病院にかけつけ受け付けで問い合わせる。「さきほどお帰りになりましたよ」「では、手術は終わって?」「いえ、今日は診察だけです。母子手帳を貰いに来たんです」「・・・・」。信子の表情に安堵の色が見えた。雨の中、団地に帰るみどりの姿、タクシーが追い着いて、信子が降りてきた。一瞬、見つめ合う二人、信子は「さっきは、ひどいことを言ってゴメンナサイね。初めからあなたに会っていれば、こんなことにはならなかった。あたし自分のことしか考えていなくて・・・」と謝ったが、キッと表情を固くするみどり、そのまま行き過ぎようとして振り返ると、信子が雨に濡れて立ち尽くしている。みどりも女である。そばに寄ると、「濡れますから、家にどうぞ」という一言で、二人の誤解はとけたのであった。
大詰めは一年後、自由が丘の美容院、みどりも美容院で働いていた。生まれたのは功という名の男児、今日も君子が公園に連れ出して遊んでいる。信子が迎えに行けば、功は一人で遊んでいた。「イサオ、危ないじゃないの」と抱き上げると、君子はブランコで老爺と談笑中、信子に気がついて終わりにする。「おばあちゃん、功を一人にして、危ないじゃないの」「大丈夫、ちゃんと見ているんだから。それにしても、あのおじいちゃん、へんなおじいちゃんだよ。こんど一緒にヘルスセンターに行かないかって、あたしを誘うんだもの」。信子は呆れて「へえ、でもおばあちゃんだって、相当へんなおばあちゃんだわよ」などと語り合ううちに、この映画は「終」となった。
前述したように、「女の歴史」とは、姑・清水君子、嫁・清水信子、義娘・富永みどりへと受け継がれる三代の歴史である。三人の連れ合い、清水正二郎、清水幸一、清水功平という男たちはいずれも、早々に歴史の舞台から姿を消した。正二郎は情死、幸一は戦死、功平は事故死、まことに呆気ない死に様であったが、もう一人、秋本隆(仲代達矢)という男がいる。彼は幸一の親友で、やはり応召したが戦地に赴くことなく生還した。戦後まもなく信子の窮状を救ったが、事業の失敗で姿をくらます。その頃、幸一には恋人・木下静代(草笛光子)が居たことが発覚、信子は秋本を頼りに思っていたのだが・・・。ほぼ十数年ぶりに、秋本と信子が偶然、渋谷で再会した時には、秋本はすでに結婚、成人に近い娘(宮本豊子)もいる始末で、男の身勝手さ、甲斐性のなさが際立つ場面であった。
そんな中、一際、光彩を放っていたのは姑・清水君子の生き様である。服毒死した夫・正二郎を引き取りに行った湯河原で、もう一人の遺体(情死の相手)に遭遇、その時は猛り狂ったが、以後は、好々爺ならぬ好々婆として信子に支えられながら支える、そのアッケラカンとした風情を、女優・夏原夏子は見事に描出していた。とりわけ、訪ねて来たみどりに、信子が悪口雑言を浴びせ追い返した後、「あんたもずいぶん強い女になったねえ、あたしならあんなことは言えないよ」という一言は印象的であった。どちらかといえば「陰」の嫁に対して「陽」の姑というコントラストが、二人の固く結ばれた「女の絆」をいっそう鮮やかに浮き彫りする。終始一貫、「女のたくましさ、したたかさ」を追求した、名手・成瀬巳喜男監督、渾身の一作であったと、私は思う。
(2017.7.28)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

大詰めは一年後、自由が丘の美容院、みどりも美容院で働いていた。生まれたのは功という名の男児、今日も君子が公園に連れ出して遊んでいる。信子が迎えに行けば、功は一人で遊んでいた。「イサオ、危ないじゃないの」と抱き上げると、君子はブランコで老爺と談笑中、信子に気がついて終わりにする。「おばあちゃん、功を一人にして、危ないじゃないの」「大丈夫、ちゃんと見ているんだから。それにしても、あのおじいちゃん、へんなおじいちゃんだよ。こんど一緒にヘルスセンターに行かないかって、あたしを誘うんだもの」。信子は呆れて「へえ、でもおばあちゃんだって、相当へんなおばあちゃんだわよ」などと語り合ううちに、この映画は「終」となった。
前述したように、「女の歴史」とは、姑・清水君子、嫁・清水信子、義娘・富永みどりへと受け継がれる三代の歴史である。三人の連れ合い、清水正二郎、清水幸一、清水功平という男たちはいずれも、早々に歴史の舞台から姿を消した。正二郎は情死、幸一は戦死、功平は事故死、まことに呆気ない死に様であったが、もう一人、秋本隆(仲代達矢)という男がいる。彼は幸一の親友で、やはり応召したが戦地に赴くことなく生還した。戦後まもなく信子の窮状を救ったが、事業の失敗で姿をくらます。その頃、幸一には恋人・木下静代(草笛光子)が居たことが発覚、信子は秋本を頼りに思っていたのだが・・・。ほぼ十数年ぶりに、秋本と信子が偶然、渋谷で再会した時には、秋本はすでに結婚、成人に近い娘(宮本豊子)もいる始末で、男の身勝手さ、甲斐性のなさが際立つ場面であった。
そんな中、一際、光彩を放っていたのは姑・清水君子の生き様である。服毒死した夫・正二郎を引き取りに行った湯河原で、もう一人の遺体(情死の相手)に遭遇、その時は猛り狂ったが、以後は、好々爺ならぬ好々婆として信子に支えられながら支える、そのアッケラカンとした風情を、女優・夏原夏子は見事に描出していた。とりわけ、訪ねて来たみどりに、信子が悪口雑言を浴びせ追い返した後、「あんたもずいぶん強い女になったねえ、あたしならあんなことは言えないよ」という一言は印象的であった。どちらかといえば「陰」の嫁に対して「陽」の姑というコントラストが、二人の固く結ばれた「女の絆」をいっそう鮮やかに浮き彫りする。終始一貫、「女のたくましさ、したたかさ」を追求した、名手・成瀬巳喜男監督、渾身の一作であったと、私は思う。
(2017.7.28)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-19
付録・邦画傑作選・「残菊物語」(監督・溝口健二・1939年)
原作は村松梢風、五代目尾上菊五郎(河原崎権十郞)の養子・二代目尾上菊之助(花柳章太郎)の物語である。冒頭は歌舞伎座の楽屋裏、これから「東海道四谷怪談」隠亡堀の場が始まろうとしている。有名な「戸板返し」後の「だんまり」で、菊之助は与茂七を演じたのだが、直助役の菊五郎は、いたって不満足、「ダイコ」(大根)役者だと決めつける。火の玉(人魂)の扱いまでもなっていないなどと当たり散らす始末、周囲の連中は「二百十日」(の嵐)が来た、などと閉口していた。直ちに菊之助を呼びつけ叱ろうとしたが、守田勘弥(葉山純之輔)が間に入ってなだめ、取り巻きも「たいそうよくできた」と褒めそやす。。菊之助は仲良しの中村福助(高田浩吉)にも「できはどうだった?」と訊ねるが口を閉ざされ、「柳橋に繰り込もう」と誘うのだが「先約がある」と断られた。独りで柳橋に向かったが、待合の客(結城一郎)たちも、菊之助の「大根振り」を肴に酒を酌み交わしている。馴染みの芸妓(伏見信子)にも振られたか、深夜、人力車で帰宅の途中、弟を子守している乳母・お徳(森赫子)に出会った。お徳は、入谷の伯母が菊之助の芸をけなすので、今日観てきたという。「それでどうだった?」「世間のおだてやお世辞にのってはいけないと思います。伯母の言う通りでした。あなたは、いずれは六代目を継ぐお方、御贔屓衆と遊ぶのはほどほどに、芸の修業に励んで下さい」。その一言に、菊之助は「ありがとう。そう言ってくれたのはお前が初めてだ」。以後はプッツリと遊びを止め、お徳を相談相手にする。しかし、その様子を見咎めた周囲が黙っていない。義母の里(梅村蓉子)はお徳に「お前は使用人の分際で余計なことをおしでない。菊之助の嫁になってこの家に入り込む魂胆だろう」と言い、すぐさま隙を出した。お徳が居なくなったことに驚いた菊之助は、お徳の実家を訪ねるがそこにも居ない。雑司ヶ谷に居ることを突き止め、鬼子母神の境内でようやく再会できたのだが、それ以後は全く音信不通になった。
菊之助は覚悟を決めた。母や兄に向かって「親の七光りで人気が出てもしょうがない。六代目の名跡もこの家も要らない。あっしは独りでやっていきたいんだ」と言う。その言葉を隣室で聞いていた菊五郎が激怒した。「そんな奴は、今すぐ、ここから出て行け!」
かくて、菊之助は大阪へ・・・、叔父・尾上多見蔵(尾上多見太郎)の下で1年修業する。しかし、評判は散々でうだつが上がらない。多見蔵に「叔父さん、不出来な舞台ばかりですみません。このまま御厄介になっていてよろしいのでしょうか」と問えば「何を言うてんのや。若い時に褒められるような奴はろくな役者になれへん。大船に乗ったつもりでしっかりやんなはれ。多見蔵がついているがな!」と励まされた。しかしまだ心は晴れない。鬱々として表に出ると、お徳が待っていた。菊之助の舞台を観ていたのである。夢ではないかとびっくりする菊之助、「なぜ、もっと早く来てくれなかったんだ」「家の者が厳しくて出られなかったんです。でも若旦那の不評判を聞いて、居ても立ってもいられなくなって来たんです」「あっしは自惚れていた。1年経ってもこのざまだ」。だがお徳の反応は、1年前のあの時とは変わっていた。「他の人が何と言っても、(今日の舞台で)あたしには1年間の苦労が見えました。東京での甘えが消えて、若旦那の力が出てきたんです。だから、これからも頑張ってください」。「そうだろうか、そうだといいんだけど」菊之助には一筋の光りが見えた。「そうですとも」とお徳の力強い相槌が支える。
二人はその足で、菊之助の貸間に赴いた。「荷物はどうした」「駅に預けてあります」「じゃあ、明日取ってこよう」「ここで御厄介になってもよろしいんですか」「今から、夫婦じゃないか」「あたしは若旦那を立派にしてお宅にお返しするために来ました」「その後はどうする?」「さあ、わかりません」「来たばかりで水くさいことを言うもんじゃないよ」。見る見る、菊之助には大きな力が湧き出してきた。数日後か、貸間に豪華な鏡台が届く。貸し主の按摩元俊(志賀廼家辨慶)が二階に運び上げようとするが上がらない。菊之助は、一階に降りてつくづくと眺め「いい鏡台だ」「いいお芝居のためにはいい鏡台が要りますわ」「お金はどうした」「あたしがいらない物を売ってこしらえました」「・・・すまないね」、元俊の娘・おつる(最上米子)が「おとっつあん、わてもこんなんほしいわあ」と羨ましがっているところに、菊之助の弟子(橘一嘉)が飛び込んで来た。「大変です!親方がさっき亡くなりました」。かくて、菊之助は、多見蔵という大阪での大きな後楯を失ってしまう。
菊之助は、お徳の反対を押し切って「旅回り一座」の太夫元(石原須磨男)に身を預けることに決めた。
そして4年が経った。一座では金をめぐってもめ事が絶えない。その様子を見て、お徳は「ああ、いやだいやだ、早く旅回りから脱け出したい」と愚痴をこぼす。菊之助は「お気の毒だね。こんな男にくっついて来たのが因果だ。いやなら出て行ったっていいんだぜ。わっしはこっちの方が面白いんだ。目をむくだけでお客は喜んでくれる」「あなたはずいぶんお変わりになりましたねえ」「また意見かい、意見ならもうたくさんだ」。二人の間にも亀裂が生じたか・・・。
ある雨の晩、突然どやどやと女相撲(白妙公子)の連中がやって来て、小屋を壊し始めた。菊之助は「何するんだ!」と止めようとしたが、太夫元はドロン、一座はバラバラになる。菊之助とお徳は、行くところもなく名古屋の木賃宿に辿り着いたのだが、お徳の咳が止まらない。初めは、雨に打たれたからと甘く見ていたが、病は刻一刻と進行する。そんな折、宿の客が芝居のチラシをもらって来た。見ると、「中村福助一座公演」と書いてある。菊之助は一瞥するだけで終わったが、お徳は一座の楽屋を訪れて懇願する。「どうか、若旦那を舞台に立たせてやってください」。その気持ちが通じたか、一同は同意する。しかも、もし人気が出たら、東京の舞台に出られるよう菊五郎に進言するという話まで取り付けた。その代わり、「お徳さん、あんたの役目は終わった。その時は身を引くように」。それでも、お徳は喜んで木賃宿に戻り、菊之助に知らせる。半信半疑だったが、菊之助も促されて舞台に立つ。演目は「関の扉」、役は福助の代わりの墨染であった。その菊之助の舞台姿に一同は、そして、観客は目を見張る。五年間の苦労が花を結んでいたのだ。
菊之助は、晴れて名古屋から東京に向かう。しかし、そこにお徳の姿は見られなかった。
必死であちことと探し回る菊之助に福助の父・中村芝翫(嵐徳三郎)が言う。「お徳は、自分から身を引いたのだ。そっとしておいておやり」。
独り、大阪のなつかしい貸間に戻ったお徳は、誰もいない二階の部屋にうずくまっている。按摩元俊の娘・おつるが戻ってきてその姿を見つける。驚いて「まあ、姐さん、どないしていやはった。でもお達者で何よりや。それで菊さんは?」・・・「とっくに別れたわ。あんな男と一緒に居るの面白くなくなったのよ」「しばらく会わんうちに、姐さん、すっかり変わりはりましたなあ」「そうかしら、そうね、少し変わったかもしれないわねえ」
菊之助は東京での公演も大成功、菊五郎と共に大阪公演(初下り)に赴く。公演の演目は「石橋」、菊五郎、菊之助、福助が連獅子の舞を厳かに、かつ艶やかに披露する。大入りの観衆が大喝采の拍手を贈るうちに幕は下り、「船乗り込み」が始まろうとする時、人混みを分けて按摩元俊がやって来た。入梅以後、お徳さんが身体をこわして、医者から「あぶない」と言われているとのこと、菊之助はすぐにでも飛んでいきたい素振りだが、「わっしには大事な仕事があるんで・・・」と戸惑うと、近くに居た菊五郎が言う。「菊、行ってやんねえ。女房に会ってきてやんな。役者の芸ってのはな、いくら教えたって上手になれるもんじゃあねえ。おめえがこれまでになったのは、お徳が骨身を惜しんで励まして、修業させてくれたおかげなんだ。おらあ、菊之助の親爺として礼を言ったと言ってくんねえ」
大詰めは、懐かしい貸間の二階、(臨終間際の)お徳の手をとり菊之助が言う。「お父っつあんが許してくれたんだよ。女房に会ってこいと言われた。礼を言ってくれと言われた」「本当ですか」とお徳は涙に暮れる。そして「早く、船乗り込みに言って下さい」と言う。
中之島から乗り込んだ菊之助が、周囲の観客に大きく手を広げ、頭を下げる。その心中にお徳の姿を思い浮かべ、再び頭を下げたとき、お徳は息を引き取ったのである。そして画面には「完」という文字が・・・。
この映画の眼目は、女の献身的な母性が、男の苦労を支え、その苦労が男の実力を磨き上げるといった「人間模様」の描出であり、単なる悲劇(メロドラマ)とは無縁の名作であることがよくわかった。
見どころの一は、菊之助を東京に送り出し、大阪の貸間に戻って「とっくに別れたわ。あんな男と一緒に居るの面白くなくなったのよ」という一言である。それは本心ではない。菊之助という役者(男)を育て上げた、お徳という女が打った最初で最後の一芝居(「愛想づかし」)なのである。菊之助はお徳との「つながり」が原因で、東京を追われた。また今の「つながり」で菊之助の評判に傷がつくようなことがあれば、元も子もない。そうした思いが、お徳を「空芝居」にかき立てたに違いない。
見どころの二は、お徳に感謝する菊五郎の心根である。それは終局の「菊、行ってやんねえ。女房に会ってきてやんな。役者の芸ってのはな、いくら教えたって上手になれるもんじゃあねえ。おめえがこれまでになったのは、お徳が骨身を惜しんで励まして、修業させてくれたおかげなんだ。おらあ、菊之助の親爺として礼を言ったと言ってくんねえ」というセリフに結実化している。その言葉を聞いて、私の涙は止まらなかった。
見どころの三は、菊之助を演じた花柳章太郎の「男振り」であろうか。並み居る役者連中の中で、やはり光っている。えもいわれぬ色香を漂わせている。さすがは、新派の大看板、後には「人間国宝」「文化功労者」に数えられる逸材の片鱗を見せているのである。
見どころの四は、スクリーンに再現される戦前大歌舞伎の舞台模様の数々である。長回しのショットで、往時の「東海道四谷怪談」「関の扉」「石橋」を存分に鑑賞できたことは望外の幸せであった。感謝。
(2017.6.23)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

菊之助は覚悟を決めた。母や兄に向かって「親の七光りで人気が出てもしょうがない。六代目の名跡もこの家も要らない。あっしは独りでやっていきたいんだ」と言う。その言葉を隣室で聞いていた菊五郎が激怒した。「そんな奴は、今すぐ、ここから出て行け!」
かくて、菊之助は大阪へ・・・、叔父・尾上多見蔵(尾上多見太郎)の下で1年修業する。しかし、評判は散々でうだつが上がらない。多見蔵に「叔父さん、不出来な舞台ばかりですみません。このまま御厄介になっていてよろしいのでしょうか」と問えば「何を言うてんのや。若い時に褒められるような奴はろくな役者になれへん。大船に乗ったつもりでしっかりやんなはれ。多見蔵がついているがな!」と励まされた。しかしまだ心は晴れない。鬱々として表に出ると、お徳が待っていた。菊之助の舞台を観ていたのである。夢ではないかとびっくりする菊之助、「なぜ、もっと早く来てくれなかったんだ」「家の者が厳しくて出られなかったんです。でも若旦那の不評判を聞いて、居ても立ってもいられなくなって来たんです」「あっしは自惚れていた。1年経ってもこのざまだ」。だがお徳の反応は、1年前のあの時とは変わっていた。「他の人が何と言っても、(今日の舞台で)あたしには1年間の苦労が見えました。東京での甘えが消えて、若旦那の力が出てきたんです。だから、これからも頑張ってください」。「そうだろうか、そうだといいんだけど」菊之助には一筋の光りが見えた。「そうですとも」とお徳の力強い相槌が支える。
二人はその足で、菊之助の貸間に赴いた。「荷物はどうした」「駅に預けてあります」「じゃあ、明日取ってこよう」「ここで御厄介になってもよろしいんですか」「今から、夫婦じゃないか」「あたしは若旦那を立派にしてお宅にお返しするために来ました」「その後はどうする?」「さあ、わかりません」「来たばかりで水くさいことを言うもんじゃないよ」。見る見る、菊之助には大きな力が湧き出してきた。数日後か、貸間に豪華な鏡台が届く。貸し主の按摩元俊(志賀廼家辨慶)が二階に運び上げようとするが上がらない。菊之助は、一階に降りてつくづくと眺め「いい鏡台だ」「いいお芝居のためにはいい鏡台が要りますわ」「お金はどうした」「あたしがいらない物を売ってこしらえました」「・・・すまないね」、元俊の娘・おつる(最上米子)が「おとっつあん、わてもこんなんほしいわあ」と羨ましがっているところに、菊之助の弟子(橘一嘉)が飛び込んで来た。「大変です!親方がさっき亡くなりました」。かくて、菊之助は、多見蔵という大阪での大きな後楯を失ってしまう。
菊之助は、お徳の反対を押し切って「旅回り一座」の太夫元(石原須磨男)に身を預けることに決めた。
そして4年が経った。一座では金をめぐってもめ事が絶えない。その様子を見て、お徳は「ああ、いやだいやだ、早く旅回りから脱け出したい」と愚痴をこぼす。菊之助は「お気の毒だね。こんな男にくっついて来たのが因果だ。いやなら出て行ったっていいんだぜ。わっしはこっちの方が面白いんだ。目をむくだけでお客は喜んでくれる」「あなたはずいぶんお変わりになりましたねえ」「また意見かい、意見ならもうたくさんだ」。二人の間にも亀裂が生じたか・・・。
ある雨の晩、突然どやどやと女相撲(白妙公子)の連中がやって来て、小屋を壊し始めた。菊之助は「何するんだ!」と止めようとしたが、太夫元はドロン、一座はバラバラになる。菊之助とお徳は、行くところもなく名古屋の木賃宿に辿り着いたのだが、お徳の咳が止まらない。初めは、雨に打たれたからと甘く見ていたが、病は刻一刻と進行する。そんな折、宿の客が芝居のチラシをもらって来た。見ると、「中村福助一座公演」と書いてある。菊之助は一瞥するだけで終わったが、お徳は一座の楽屋を訪れて懇願する。「どうか、若旦那を舞台に立たせてやってください」。その気持ちが通じたか、一同は同意する。しかも、もし人気が出たら、東京の舞台に出られるよう菊五郎に進言するという話まで取り付けた。その代わり、「お徳さん、あんたの役目は終わった。その時は身を引くように」。それでも、お徳は喜んで木賃宿に戻り、菊之助に知らせる。半信半疑だったが、菊之助も促されて舞台に立つ。演目は「関の扉」、役は福助の代わりの墨染であった。その菊之助の舞台姿に一同は、そして、観客は目を見張る。五年間の苦労が花を結んでいたのだ。
菊之助は、晴れて名古屋から東京に向かう。しかし、そこにお徳の姿は見られなかった。
必死であちことと探し回る菊之助に福助の父・中村芝翫(嵐徳三郎)が言う。「お徳は、自分から身を引いたのだ。そっとしておいておやり」。
独り、大阪のなつかしい貸間に戻ったお徳は、誰もいない二階の部屋にうずくまっている。按摩元俊の娘・おつるが戻ってきてその姿を見つける。驚いて「まあ、姐さん、どないしていやはった。でもお達者で何よりや。それで菊さんは?」・・・「とっくに別れたわ。あんな男と一緒に居るの面白くなくなったのよ」「しばらく会わんうちに、姐さん、すっかり変わりはりましたなあ」「そうかしら、そうね、少し変わったかもしれないわねえ」
菊之助は東京での公演も大成功、菊五郎と共に大阪公演(初下り)に赴く。公演の演目は「石橋」、菊五郎、菊之助、福助が連獅子の舞を厳かに、かつ艶やかに披露する。大入りの観衆が大喝采の拍手を贈るうちに幕は下り、「船乗り込み」が始まろうとする時、人混みを分けて按摩元俊がやって来た。入梅以後、お徳さんが身体をこわして、医者から「あぶない」と言われているとのこと、菊之助はすぐにでも飛んでいきたい素振りだが、「わっしには大事な仕事があるんで・・・」と戸惑うと、近くに居た菊五郎が言う。「菊、行ってやんねえ。女房に会ってきてやんな。役者の芸ってのはな、いくら教えたって上手になれるもんじゃあねえ。おめえがこれまでになったのは、お徳が骨身を惜しんで励まして、修業させてくれたおかげなんだ。おらあ、菊之助の親爺として礼を言ったと言ってくんねえ」
大詰めは、懐かしい貸間の二階、(臨終間際の)お徳の手をとり菊之助が言う。「お父っつあんが許してくれたんだよ。女房に会ってこいと言われた。礼を言ってくれと言われた」「本当ですか」とお徳は涙に暮れる。そして「早く、船乗り込みに言って下さい」と言う。
中之島から乗り込んだ菊之助が、周囲の観客に大きく手を広げ、頭を下げる。その心中にお徳の姿を思い浮かべ、再び頭を下げたとき、お徳は息を引き取ったのである。そして画面には「完」という文字が・・・。
この映画の眼目は、女の献身的な母性が、男の苦労を支え、その苦労が男の実力を磨き上げるといった「人間模様」の描出であり、単なる悲劇(メロドラマ)とは無縁の名作であることがよくわかった。
見どころの一は、菊之助を東京に送り出し、大阪の貸間に戻って「とっくに別れたわ。あんな男と一緒に居るの面白くなくなったのよ」という一言である。それは本心ではない。菊之助という役者(男)を育て上げた、お徳という女が打った最初で最後の一芝居(「愛想づかし」)なのである。菊之助はお徳との「つながり」が原因で、東京を追われた。また今の「つながり」で菊之助の評判に傷がつくようなことがあれば、元も子もない。そうした思いが、お徳を「空芝居」にかき立てたに違いない。
見どころの二は、お徳に感謝する菊五郎の心根である。それは終局の「菊、行ってやんねえ。女房に会ってきてやんな。役者の芸ってのはな、いくら教えたって上手になれるもんじゃあねえ。おめえがこれまでになったのは、お徳が骨身を惜しんで励まして、修業させてくれたおかげなんだ。おらあ、菊之助の親爺として礼を言ったと言ってくんねえ」というセリフに結実化している。その言葉を聞いて、私の涙は止まらなかった。
見どころの三は、菊之助を演じた花柳章太郎の「男振り」であろうか。並み居る役者連中の中で、やはり光っている。えもいわれぬ色香を漂わせている。さすがは、新派の大看板、後には「人間国宝」「文化功労者」に数えられる逸材の片鱗を見せているのである。
見どころの四は、スクリーンに再現される戦前大歌舞伎の舞台模様の数々である。長回しのショットで、往時の「東海道四谷怪談」「関の扉」「石橋」を存分に鑑賞できたことは望外の幸せであった。感謝。
(2017.6.23)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-18
付録・邦画傑作選・「芸者ワルツ」(渡辺邦男・1952年)
DVD(新東宝【歌謡シリーズ】傑作選)で映画「芸者ワルツ」(監督・渡辺邦男・1952年)を観た。その内容は「元伯爵の令嬢から一転、花柳界へ身を沈めた薄倖の女性。芸者ゆえに身にしみる恋の辛さに隠れて泣いた舞扇」と要約されているが、大詰めはハッピー・エンドで締めくくられる。元伯爵・朝吹誠通(高田稔)の令嬢・千恵子(相馬千恵子)が、花柳界へ身を沈め、芸者として出会った新興実業家・六郷信太郎(龍崎一郎)と結ばれるまでのメロドラマである。二人の周囲には、信太郎の父・恭造(柳家金語楼)、恭造の妻・とし(花岡菊子)、信太郎の友人・楠田(田崎潤)、千恵子の妹・美津子(久保菜穂子)、朋輩・栄龍(宮川玲子)、照代(旭輝子)、つばめ(野上千鶴子)、花丸(藤京子)、はん子(神楽坂はん子)、置屋の女将・吉田富枝(清川玉枝)といった面々が登場し、色を添えている。筋書きは単純。元華族の朝吹家は没落、誠通は病身で働けない。長女の千恵子は父妹に隠れて芸者稼業、一家を支えている。折しも、箱根で慰安の仕事が入り、向かった先はホテル・清嵐荘、そこは朝吹家のかつての別荘、今は六郷信太郎の手に渡っていた。そこで父・恭造の「社長就任披露」が催される。恭造は小学校卒で仕事のことは何もわからない。20年前は朝吹家の車引きであった。この別荘にも再三訪れ、千恵子の子守までしたことがあった。信太郎は謹厳実直で親孝行、そんな父を「社長にするなんて」と仕事仲間・楠田から呆れられるが、「お前とオレは全く考え方が違うんだ」と取り合わなかった。この恭造を騙して一儲けしようと企む山崎一味(芸名不詳の男優二人)、箱根から帰ると恭造を呼び出して、行きつけの待合へ。書類を前にして、署名するように強要する。その場面を目撃した千恵子が信太郎に連絡、事なきを得たが、その後、信太郎と千恵子の「恋愛」が芽生える。信太郎の思いを察した恭造は、千恵子の自宅を探し当て、誠通と再会する。「どうか息子の嫁に千恵子お嬢さんをください」と頼んだが、誠通は激高、「没落しているからといって、馬鹿にするな!」と追い返した。かくて、千恵子の芸者稼業が誠通に知れ渡り、父娘の愁嘆場。しかし恭造がそれとなく置いていった、(恩返しの)別荘の権利書を見て驚愕、誠通は「今日ほど、人の情けを感じたことはない」と、華族のプライドを捨て、陳謝するといった次第。後はお決まりの展開で、大団円を迎える。 筋書きは単純だが、見どころは満載。まず第一に、信太郎の父・恭造を演じた柳家金語楼の風情である。元は車引き、伯爵家の使用人として、どこまでも腰が低く、愛想をふりまく。楠田からは「オジサン」と呼ばれ、「三等重役」は有名だが「さだめし三等社長というこころだ」とこけにされてもおこらない。極め付きは、行きつけの待合で山崎一味が署名を強要、ペンを持たされながら、「字が書けない」「ワッハッハー」と笑い飛ばす場面、相手を見下すわけではなく、からかうわけでもなく、まさに「煙に巻く」笑いとでもいおうか、観ている私も涙が出るほど可笑しかった(共感できた)のである。
第二は、芸者仲間が寄り合う景色である。2万円貯めて金貸しをめざす、つばめ役の野上千鶴子、医師を目指しているが学費が払えない照代役の旭輝子、男に貢ぎ過ぎいつも文無しの栄龍役の宮川玲子、新玉のくせに男心をくすぐる花丸役の藤京子、美声で稼ぎまくるはん子役の神楽坂はん子、みんなを束ねて面倒見る人情派・女将役の清川玉枝、文字通り「適材適所」の配役で、それぞれの個性が随所で輝いている。極め付きは、待合の廊下で、照代がはん子に「だから今夜は酔わせてね」の唄い方を伝授される場面、途中から、つばめも、栄龍も加わり「合唱」に進展する有様は、《粋の極致》、とりわけ神楽坂はん子の「初々しさ」が魅力的であった。
その他にも、信太郎役・龍崎一郎の「男振り」、元伯爵役・高田稔の(やつれた)「風格」、美津子役・(デビューまもない)久保菜穂子の「可憐さ」、楠田役・田崎潤の「磊落振り」等など、見どころは枚挙にいとまがない。「新東宝【歌謡シリーズ】傑作選」という看板に偽りはなかった、と私は思う。(2017.5.17)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

第二は、芸者仲間が寄り合う景色である。2万円貯めて金貸しをめざす、つばめ役の野上千鶴子、医師を目指しているが学費が払えない照代役の旭輝子、男に貢ぎ過ぎいつも文無しの栄龍役の宮川玲子、新玉のくせに男心をくすぐる花丸役の藤京子、美声で稼ぎまくるはん子役の神楽坂はん子、みんなを束ねて面倒見る人情派・女将役の清川玉枝、文字通り「適材適所」の配役で、それぞれの個性が随所で輝いている。極め付きは、待合の廊下で、照代がはん子に「だから今夜は酔わせてね」の唄い方を伝授される場面、途中から、つばめも、栄龍も加わり「合唱」に進展する有様は、《粋の極致》、とりわけ神楽坂はん子の「初々しさ」が魅力的であった。
その他にも、信太郎役・龍崎一郎の「男振り」、元伯爵役・高田稔の(やつれた)「風格」、美津子役・(デビューまもない)久保菜穂子の「可憐さ」、楠田役・田崎潤の「磊落振り」等など、見どころは枚挙にいとまがない。「新東宝【歌謡シリーズ】傑作選」という看板に偽りはなかった、と私は思う。(2017.5.17)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-17
付録・邦画傑作選・「隣の八重ちゃん」(監督・島津保次郎・1934年)
ユーチューブで映画「隣の八重ちゃん」(監督・島津保次郎・1934年)を観た。(戦前の)ホーム・ドラマのはしりとでも言うべき佳品である。登場するのは、東京郊外(多摩川べり、あるいは江戸川べり)に隣同士で暮らしている二つの中流家庭、服部家と新井家の家族である。タイトルにある八重ちゃん(逢初夢子)は、服部家の次女、女学校に通い、父・昌作(岩田祐吉)、母・浜子(飯田蝶子)と暮らしている。隣の新井家には父・幾造(水島亮太郎)、母・松子(葛城文子)、長男・恵太郎(大日向伝)、次男・精二(磯野秋雄)が居る。恵太郎は帝大生、精二は(旧制)○○生、今日も家の前でキャッチボールをしている。精二は野球部のピッチャーとして、甲子園を目指しているので、兄の恵太郎が特訓をしている景色である。その時、ボールが逸れて服部家のガラスを割ってしまった。出てきたのは、八重子「また、割ったの」と言うところに、母の浜子が銭湯から帰ってきた。「どうも、すみません」と謝る恵太郎に「いいんですよ、男の子は元気が良くてうらやましい」などと責める様子もない。両家は家族ぐるみの交流をしているようだ。ガラス屋(阿部正二郎)が修理に来て終わると、浜子が「いくら?」と訊ねる。「お代は向こうのお宅が払うことになっています」「いいわよ、こっちで払うから。いくらなの?」「15銭です」「高い、10銭にしときなさいよ。またすぐに頼むんだから」といったやりとりが、たいそう面白かった。
次の日だろうか、恵太郎が大学から帰宅すると鍵がかかっている。垣根を乗り越えて、服部宅へ、「おばさん、腹減っちゃった」「お茶漬けでよかったら、お食べ」、浜子は市場へ買い物に。そこに、八重子が友だちの真鍋悦子(高杉早苗)を伴い帰宅する。「あの人帝大でしょ」「独法よ」。八重子が着替えをするのを見て、悦子が「あなたのオッパイ、いい形ね。あたしのはペッチャンコ・・・」などと言う声を聞いて、恵太郎はドギマギ・・・、「はしたない話してるねえ、男性の居る前で」「いいじゃないの、女同士だもの。それより、近頃、恵太郎さん、そんなことに興味があるの」とやり込められた。その日の夜だろうか、服部宅で、両家の主人が二人で酒を酌み交わしている。宴もたけなわ、昌作が盛んに気炎をあげていると、この家の長女・京子(岡田嘉子)がやって来た。玄関で泣いている。嫁ぎ先を出てきたらしい。酔いも覚めて幾造は自宅に戻る。「困った。嫁に行った京子さんが帰ってきたんだ」「まあ、奥さんもさぞ心配でしょう」「死んでも帰らないと言ってるんだ」。
その翌日だろうか、翌々日だろうか。いずれにしても日曜日、両家の主人は連れだって釣りに行った模様・・・。恵太郎と精二がキャッチボールの練習をしていると、隣家から言い争う声が聞こえる。京子が働きに出たいと言い、浜子がそれに反対しているのだ。京子が「カフェで働けば、私一人で生きて行けるわ」「まあ、何ていうことを!それでは世間に顔向けができない」。興奮した浜子は下駄をはき違えて隣家に赴く。途中で、精二と恵太郎に向かって「またガラスを毀しちゃ困るよ!」、いつもとは違う豹変振りに、あっけにとられる二人の姿がたまらなく可笑しかった。恵太郎は、練習を中断して、京子に会いに行く。「あたし、どうしていいか、わからないの」「くよくよしないことです」などと語り合うちに、八重子が友だちの病気見舞いから帰って来た。恵太郎と京子の姿を見ると、プイとして精二の所に行き「精二さん、遊ばない」「でも、こんな恰好で汚れているから」「洗えばいいじゃないの」・・・、結局、八重子と精二、恵太郎、京子の四人で映画を観に行くことになった。映画はベティー・ブープのアニメーション、観客は笑いこけているが八重子は面白くない。隣には精二、京太郎の隣には京子が座っているからだ。映画館を出ると、京子の奢りでシャモ鍋を食べに行く。新井宅では釣りの獲物を天ぷらにして、主人同士が酒を汲み交わしている。京子もシャモ屋で酒を注文、恵太郎に勧める。自分もしたたか飲んで酔いつぶれ、帰りのタクシーの中では、恵太郎にしなだれかかる。「お姉さん、迷惑よ」「いいじゃないの、奢ってあげたんだから少しくらい迷惑かけたって」そんな姉の姿に八重子は不潔感をおぼえたか、表情は曇るばかりであった。
また、次の日か、川縁の道を恵太郎と京子が散歩している。京子は「逢瀬」を楽しんでいる風情だが、恵太郎はどこか辟易としている様子。土手に腰を下ろして、京子が「あたし、もう一度、娘に戻りたい。でも、八重子のように純にはなれないわ。ねえ、恵ちゃん、あたしのこと愛してくれない」と言ったとたん、恵太郎は「もう、帰ろうよ」「イヤ、あたしは帰らない」「では、ボクは一人で帰るよ」と言い残してその場を去った。後ろから「逃げるの」という声が聞こえる。
翌日は、いよいよ精二たちの野球大会(甲子園行きの予選)。八重子と恵太郎も応援にかけつける。試合は一進一退、延長戦にもつれ込んだが、精二の投打にわたる活躍で優勝することができた。甲子園行きが決まったのである。三人が大喜びで帰宅すると、松子が沈痛な面持ちで言う。「大変なことが起きたんだよ。八重ちゃん、あんたのお姉さんが家出したんだよ」。家では浜子が、京子の置き手紙を手にして泣いていた。「こんなことになるんじゃないかと思っていたんだよ」恵太郎もやってきて「大丈夫、帰ってきますよ」と慰めるが「だって、死にたいって書いてあるんです」と置き手紙を手渡す。「おばさん、とにかく探してきます」と、八重子と連れだって探しに出た。思いあたるのは、昨日の土手あたり、二人はくまなく探したが京子の姿はどこにもなかった。そして「何もかもがいっぺんに来た」。服部に朝鮮への栄転の知らせが入ったのである。京子のことに関わってはいられない。服部は業務の引き継ぎ、引っ越しの手配、新井は新聞社へ「尋ね人」の広告依頼、残った者は荷造り、トラックへの積み込みと忙しい。やがて、服部が迎えの車に乗って帰ってきた。まもなく出発の時が近づいたのである。名残を惜しむ浜子、「今後のことはよろしくお願いします。京子のことが気がかりで・・・」「今さら何を言っているんだ、さあ行くぞ」、浜子は八重子に促されて泣く泣く車に乗り込む。精二が「おばさん、さようなら」と言えば「甲子園、頑張ってね」という言葉。こんな時でも、相手のことを気遣う浜子の姿は、当時の日本女性の典型であろうか。
服部家の出発を見送った恵太郎と精二がキャッチボールをしていると、ひょっこり八重子が帰ってきた。「見送ってきたわ」「八重ちゃんの本箱と机、運んでおいたよ」。八重子は女学校を卒業するまで、新井家に下宿することになっていたのである。「もう、隣の八重ちゃんじゃないわ。アハハハハ」と屈託ない八重ちゃんの笑いで、この映画は「終」となった。
気がかりなのは、京子の行方だが、そんなことには頓着しないことが、この映画の特長だと思われる。基調にあるのは、あくまで健全な生活意識であり、公序良俗と醇風美俗の空気が色濃く漂っている。その中で、京子の風情は異色、異端であるばかりか、不貞の匂いさえ感じさせる。嫁ぎ先との不和で実家に舞い戻るケースは少なくない。例えば、樋口一葉の「十三夜」、家に逃れてきた娘・せきに向かって、父は「子供と別れて実家で泣き暮らすなら、辛抱して夫のもとで泣き暮らすのも同じ」と諭す。娘もそれを聞き入れて嫁ぎ先に戻るが、それは明治時代の話、服部家の父・昌作、娘・京子には、そんな「絆」はほとんど感じられない。なるほど、たとえ戦前(の家庭)であっても、時代は確実に変わっていったのだということを痛感した次第である。
八重子もまた、空き家になった自宅を眺めて、お姉さんは帰っていないかと一瞬、思いを馳せるが、その曇った表情が、すぐに屈託ない笑顔に変わる。そこらあたりが、この映画の魅力であり、ホームドラマの原点といわれる所以であろう。それにしても、今、京子はいったいどこで何をしているのだろうか。下世話好きな私にとっては、実に興味深い問題である。嫁ぎ先に戻ったか、カフェで働き口を見つけたか。いずれにせよ、置き手紙に書いてあるような結果にはならないだろうことは、確かなのだが・・・。
(2017.5.30)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

次の日だろうか、恵太郎が大学から帰宅すると鍵がかかっている。垣根を乗り越えて、服部宅へ、「おばさん、腹減っちゃった」「お茶漬けでよかったら、お食べ」、浜子は市場へ買い物に。そこに、八重子が友だちの真鍋悦子(高杉早苗)を伴い帰宅する。「あの人帝大でしょ」「独法よ」。八重子が着替えをするのを見て、悦子が「あなたのオッパイ、いい形ね。あたしのはペッチャンコ・・・」などと言う声を聞いて、恵太郎はドギマギ・・・、「はしたない話してるねえ、男性の居る前で」「いいじゃないの、女同士だもの。それより、近頃、恵太郎さん、そんなことに興味があるの」とやり込められた。その日の夜だろうか、服部宅で、両家の主人が二人で酒を酌み交わしている。宴もたけなわ、昌作が盛んに気炎をあげていると、この家の長女・京子(岡田嘉子)がやって来た。玄関で泣いている。嫁ぎ先を出てきたらしい。酔いも覚めて幾造は自宅に戻る。「困った。嫁に行った京子さんが帰ってきたんだ」「まあ、奥さんもさぞ心配でしょう」「死んでも帰らないと言ってるんだ」。
その翌日だろうか、翌々日だろうか。いずれにしても日曜日、両家の主人は連れだって釣りに行った模様・・・。恵太郎と精二がキャッチボールの練習をしていると、隣家から言い争う声が聞こえる。京子が働きに出たいと言い、浜子がそれに反対しているのだ。京子が「カフェで働けば、私一人で生きて行けるわ」「まあ、何ていうことを!それでは世間に顔向けができない」。興奮した浜子は下駄をはき違えて隣家に赴く。途中で、精二と恵太郎に向かって「またガラスを毀しちゃ困るよ!」、いつもとは違う豹変振りに、あっけにとられる二人の姿がたまらなく可笑しかった。恵太郎は、練習を中断して、京子に会いに行く。「あたし、どうしていいか、わからないの」「くよくよしないことです」などと語り合うちに、八重子が友だちの病気見舞いから帰って来た。恵太郎と京子の姿を見ると、プイとして精二の所に行き「精二さん、遊ばない」「でも、こんな恰好で汚れているから」「洗えばいいじゃないの」・・・、結局、八重子と精二、恵太郎、京子の四人で映画を観に行くことになった。映画はベティー・ブープのアニメーション、観客は笑いこけているが八重子は面白くない。隣には精二、京太郎の隣には京子が座っているからだ。映画館を出ると、京子の奢りでシャモ鍋を食べに行く。新井宅では釣りの獲物を天ぷらにして、主人同士が酒を汲み交わしている。京子もシャモ屋で酒を注文、恵太郎に勧める。自分もしたたか飲んで酔いつぶれ、帰りのタクシーの中では、恵太郎にしなだれかかる。「お姉さん、迷惑よ」「いいじゃないの、奢ってあげたんだから少しくらい迷惑かけたって」そんな姉の姿に八重子は不潔感をおぼえたか、表情は曇るばかりであった。
また、次の日か、川縁の道を恵太郎と京子が散歩している。京子は「逢瀬」を楽しんでいる風情だが、恵太郎はどこか辟易としている様子。土手に腰を下ろして、京子が「あたし、もう一度、娘に戻りたい。でも、八重子のように純にはなれないわ。ねえ、恵ちゃん、あたしのこと愛してくれない」と言ったとたん、恵太郎は「もう、帰ろうよ」「イヤ、あたしは帰らない」「では、ボクは一人で帰るよ」と言い残してその場を去った。後ろから「逃げるの」という声が聞こえる。
翌日は、いよいよ精二たちの野球大会(甲子園行きの予選)。八重子と恵太郎も応援にかけつける。試合は一進一退、延長戦にもつれ込んだが、精二の投打にわたる活躍で優勝することができた。甲子園行きが決まったのである。三人が大喜びで帰宅すると、松子が沈痛な面持ちで言う。「大変なことが起きたんだよ。八重ちゃん、あんたのお姉さんが家出したんだよ」。家では浜子が、京子の置き手紙を手にして泣いていた。「こんなことになるんじゃないかと思っていたんだよ」恵太郎もやってきて「大丈夫、帰ってきますよ」と慰めるが「だって、死にたいって書いてあるんです」と置き手紙を手渡す。「おばさん、とにかく探してきます」と、八重子と連れだって探しに出た。思いあたるのは、昨日の土手あたり、二人はくまなく探したが京子の姿はどこにもなかった。そして「何もかもがいっぺんに来た」。服部に朝鮮への栄転の知らせが入ったのである。京子のことに関わってはいられない。服部は業務の引き継ぎ、引っ越しの手配、新井は新聞社へ「尋ね人」の広告依頼、残った者は荷造り、トラックへの積み込みと忙しい。やがて、服部が迎えの車に乗って帰ってきた。まもなく出発の時が近づいたのである。名残を惜しむ浜子、「今後のことはよろしくお願いします。京子のことが気がかりで・・・」「今さら何を言っているんだ、さあ行くぞ」、浜子は八重子に促されて泣く泣く車に乗り込む。精二が「おばさん、さようなら」と言えば「甲子園、頑張ってね」という言葉。こんな時でも、相手のことを気遣う浜子の姿は、当時の日本女性の典型であろうか。
服部家の出発を見送った恵太郎と精二がキャッチボールをしていると、ひょっこり八重子が帰ってきた。「見送ってきたわ」「八重ちゃんの本箱と机、運んでおいたよ」。八重子は女学校を卒業するまで、新井家に下宿することになっていたのである。「もう、隣の八重ちゃんじゃないわ。アハハハハ」と屈託ない八重ちゃんの笑いで、この映画は「終」となった。
気がかりなのは、京子の行方だが、そんなことには頓着しないことが、この映画の特長だと思われる。基調にあるのは、あくまで健全な生活意識であり、公序良俗と醇風美俗の空気が色濃く漂っている。その中で、京子の風情は異色、異端であるばかりか、不貞の匂いさえ感じさせる。嫁ぎ先との不和で実家に舞い戻るケースは少なくない。例えば、樋口一葉の「十三夜」、家に逃れてきた娘・せきに向かって、父は「子供と別れて実家で泣き暮らすなら、辛抱して夫のもとで泣き暮らすのも同じ」と諭す。娘もそれを聞き入れて嫁ぎ先に戻るが、それは明治時代の話、服部家の父・昌作、娘・京子には、そんな「絆」はほとんど感じられない。なるほど、たとえ戦前(の家庭)であっても、時代は確実に変わっていったのだということを痛感した次第である。
八重子もまた、空き家になった自宅を眺めて、お姉さんは帰っていないかと一瞬、思いを馳せるが、その曇った表情が、すぐに屈託ない笑顔に変わる。そこらあたりが、この映画の魅力であり、ホームドラマの原点といわれる所以であろう。それにしても、今、京子はいったいどこで何をしているのだろうか。下世話好きな私にとっては、実に興味深い問題である。嫁ぎ先に戻ったか、カフェで働き口を見つけたか。いずれにせよ、置き手紙に書いてあるような結果にはならないだろうことは、確かなのだが・・・。
(2017.5.30)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-16
付録・邦画傑作選・「東京の合唱」(監督・小津安二郎・1931年)
ユーチューブで映画「東京の合唱」(監督・小津安二郎・1931年)を観た。保険会社に勤める男・岡島伸二(岡田時彦)が主人公の物語である。冒頭場面は、旧制中学校の校庭、体育の授業が始まろうとしている。大村先生(齋藤達雄)が勢いよく飛び出して、集合をかける。一同が整列、「上着を脱いで集まれ」と号令したが、一人だけ脱がない生徒が居た。「おいお前、上着を脱いでこい」と言われ、渋々脱ぐと上半身は裸、下着を身につけていなかったのだ。その理由は不明だが、一風変わっている。先生に呼ばれると、ヨタヨタと近づく。「やり直し!」と言われて、今度は「行進」の歩様。腰に差した煙草入れ(?)を取り上げられ、一同は大笑い、振り返って舌を出す。「舌を出すとは何事か。この場に立っておれ」と罰せられた。彼こそが、若き日の岡島であったのだ。大村先生と生徒たちの「絡み」がたいそう可笑しく、往時の学園風景が見事に描き出され、私の笑いは止まらなかった。
その時から幾星霜、今の岡島は会社員、妻・すが子(八雲恵美子)、長男(菅原秀雄)、長女(高峰秀子)、乳飲み子の次男を抱える世帯主である。
今日はボーナスの支給日、出勤の準備をしていると、長男が「パパ、自転車がほしい。買ってよ」とせがむ。「ママに聞いてごらん」、妻も了承。長女も「あたしにも何か買ってよ」というと、長男が「お前は紙風船、買ってもらったじゃないか、欲ばり!」と小突く。「アーン」と泣き出す、子役・高峰秀子の姿がたまらなく魅力的であった。
岡島は出勤、いよいよボーナスが支給される昼休み、社員は社長室の前に並んで期待を膨らませる。一人ずつ順番に手渡されて、「いくら?」と思うが、周囲の目がある。確認する場所はトイレの中、中にはあわてて札束を便器に落としてしまう者も居た。岡島もめでたくボーナスを受領、扇風機で鉛筆を削り、何を買おうか予算を立てる。ふと、横を見ると、老社員の山口(坂本武)がふさぎ込んでいる。先刻、解雇を言い渡されたのだ。
山口の勧誘で生命保険に加入した者が、翌日、交通事故で死亡したことが原因らしい。それを聞いて、岡島の反骨心が燃え上がった。「おい、みんな!山口さんは解雇だそうだ。勧誘と事故死は関係ない、会社が金を払うのは当然じゃないか」と呼びかければ、一同「そうだ、そうだ」、同僚の一人(山口勇)が「社長に談判しよう」と提案した。岡島が「よく言った。じゃあ君が談判に行ってくれ」と言うと、とたんにトーン・ダウン、「・・・でも会社に損失を与えたことは間違いないんだからなあ」。岡島が「なあんだ、口ほどにもない奴だ」「何!じゃあ、お前が行けるものなら行って見ろ」といきり立つ。岡島は、平然と社長室に入っていった。深々と社長(谷麗光)に一礼し、談判を始めるが、社長は聞き入れない。秘書(宮島健一)がとりなすが、岡島も引き下がらない。口で争い、扇子で争い、小突き合い、とうとう社長を押し倒す。激昂した社長は、即刻「お前はクビだ」と宣言する。かくて、岡島もまた、失業の身となってしまった。
フラフラと岡島が自宅に帰っていく。手にしているのは自転車ではなく、オモチャのスクーターだった。待ち焦がれて迎えに出た長男が「自転車は?」と問えば、スクーターを手渡す。今度は、長男が怒り出した。「なんだ、こんなもの!」と言ってスクーターを放り出すなり、泣き出した。やむなくスクーターを拾って家に戻ると、長女が次男をあやしていた。「ママは?」「公営市場に買い物に行ったわ」。岡島は力なく座り込む。そこに長男も戻ってきた。下駄を放り投げ、部屋に上がると障子に穴をあける。ドスンドスンと音を立て岡島に抗議する。「パパの嘘つき!」岡島は再度、スクーターを取り出してなだめたが、長男は頑として聞かず、父を足蹴にした。もうこれまでと、岡島は長男を抱え上げ、数十回の尻叩き、長男は大声で泣き叫ぶ。その様子を長女と次男があっけにとられて眺めている。父子の修羅場はたいそう見応えがあった。やがてすが子が帰宅する。一目散に駆け寄る長男、いったい何事があったのか、「あんまり我が儘を言うから叱ったんだ」事情を聞いて、妻が言う。「パパが悪い。子どもに嘘をつくなんて、どんなにか楽しみにしていたものを」。長女までも「パパの嘘つき」と言って舌を出す。「何が悪い」と言い返してみたものの・・・、岡島は力なく封筒を取り出して、すが子に渡す。入っていたのは解雇通知の辞令。「社長と喧嘩したんだ。こちらの言い分が正当でも、相手が社長だからしかたがない」。うなだれるすが子、気を取り直してスクーターを長男に与え「これで我慢おし」。しかし長男は再び「イヤだ」といって泣き出す始末、その母子の様子を見て、「かわいそうだ、買ってあげよう」と岡島は決めた。一件落着、子どもたちは辞令を紙飛行機に折って遊び始める。岡島も一緒に・・・。
数日後、岡島は職探し、上野公園(日比谷公園かもしれない)辺りを通りかかると、共に解雇された山口が、サンドイッチマンの態でビラまきをしている。ぶら下げている看板には「健康安全週間・東京市」と記されてあった。しばし、ベンチで二人は語り合う。その向かいでは失業者の親子か、子どもが下駄をぶつけて大泣きしている。「思い切り泣ける子どもがうらやましい」と山口が言う。その時、人々が駆けだして、ただならぬ様子、「動物小屋のクマが檻を破って逃げ出した」とのこと、山口は、見に行こうと誘ったが、岡島は「クマが逃げ出したって僕らの人生には何のかかわりもないじゃないですか」とその場を動こうとしなかった。
今日もあぶれて岡島が家に戻る道、自転車を買ってもらった長男が、子どもたちに混じって魚掬いをしている。声をかけると「美代ちゃんが病気になった。クズマンジュウが当たったらしい」と言う。あわてて帰宅、すが子は次男を抱きながら氷を砕いている。長女は寝かされて、苦しそう。「なんでクズマンジュウなんか食べさせたんだ」「古新聞を売ったお金が入ったので、せめて子どもたちの好きなものを食べさせてあげようと思って。お医者様は入院させた方がいいと・・・」「金のことが心配なのか。金なんかどうにでもなる。早く車屋さんを呼んでこい」と長男に言いつける。自転車に飛び乗って、長男は車屋へ。かくて入院の運びとなった。和室の病室で一同が待機していると医者の診察が始まる。「この分なら御心配はいりません」という結果に岡島は安堵、長男と家に戻ろうとする。すが子が「ここの支払い、大丈夫?」と問いかけると、岡島はさびしく肯いて帰路についた。
やがて退院。家族一同は大喜びで家に戻る。岡島と長男、長女は車座になって「手遊び」を始めたが、すが子が箪笥を開けると、中の着物はすべて無くなっていた。驚いて「箪笥の中は空っぽよ」と言うと「そのおかげで、美代子はこんなに元気になれたんだ」と手遊びを続ける。長男がすが子も誘い、やがて四人の手遊びが始まった。子どもたちは大喜びだが、これからのことを思うと、すが子は浮かれられない。精一杯はしゃいでいる岡島を見つめ、そっと涙をぬぐうすが子の姿は天下一品、夫婦、親子の絆が見事に結実した名場面であった、と私は思う。
次の日も岡島は職探し、職業紹介所の前で珍しい人物に出会った。学校時代の恩師、大村先生である。今では教職を退き、女房(飯田蝶子)と一緒に「洋食屋」を始めたという。「手伝ってもらえないか。その代わりに君の就職口を世話するよ。これでも文部省に知り合いが居るんだ」という依頼に「恩返しのつもりで」と同意、しかし、その手伝いは宣伝の旗持ちだったとは・・・。二本の幟を担いで、先生はビラ配り、「カロリー軒のライスカレー」を広めようとしているのである。たまたま、その情景を市電の中からすが子たちが目にする。岡島の就職を知人に頼みに行く途中であった。
岡島が帰宅すると、すが子の様子が素っ気ない。「お前も出かけたのかい」「あなたの口を頼みに行ったんです」「それでどうだった」首を振りながら「それより、途中で大変なものを見てしまったんです」「何を?」「あなたを見てしまったんです。あんなことまでしてほしいと頼んでいません」。岡島は悄然として「あの爺さんは、昔の先生なんだ。手伝いをすれば就職口を世話してくれると言うもんだから」「当てになるんですか」「困ったときは、当てにならないことでも当てにするもんだ」。しみじみと窓の外の洗濯物を見つめながら「オレも昔のような覇気がなくなった」と呟く。その姿を見て、すが子の気持ちが変わった。「あたしも、先生の所にお手伝いに行きます!」
かくて四、五日後、カロリー軒では大村先生を囲んで同窓会が開かれる。岡島が幹事を務めたのだろう。懐かしい面々が一堂に会して昔話に花が咲く。自慢のライスカレーにビールで乾杯、かいがいしく手伝うすが子の姿もある。岡島の子どもたちも手伝いに来ていた。長女はスプーンを配り、御相伴に預かるといった按配で、実に賑々しく活気あふれる雰囲気であった。先生は紋付き羽織に着替えて、威儀を正し、一同に訓示する。その後で「誠に相済まないが、会費は頂戴する」といった一言が可笑しかった。宴もたけなわという時、郵便が届いた。先生が開けると、「岡島の就職口が見つかった」という文部省からの知らせであった。「栃木県の女学校で英語の先生を求めている。君は英語は達者かね」。岡島は一も二もなく承諾、「とにもかくにも行くことに決めようね」とすが子に言えば、寝ている次男を見つめながら「きっといつかは東京に帰って来れますわ」と、都落ちの思いを噛みしめる。
いよいよ大詰め、すが子も宴席に加わると、遅刻の常連だった同窓生もやって来た。先生の「君は相変わらずだね」に皆は大笑い、一同が起立して「寮歌の合唱だ!」。「三年の春は過ぎやすし 花くれないのかんばせも 今わかれてはいつか見む・・・」と歌いながら、大村先生と岡島は、ふと涙ぐむ。「よかったなあ、おめでとう」「ありがとうございました」という師弟の絆が浮き彫りされ、やがて二人には笑顔が・・・、岡島の覇気は今、蘇ったかと思われるうちに、この映画は「終」を迎えた。
この映画の見どころは満載だが、一に、子どもたちの生き生きとした姿であろう。長男・菅原秀雄の利かん気、腕白振り、長女・高峰秀子のやんちゃ振り、おしゃまな風情、さらに次男の可愛さも見逃せない。彼の演技は「泣く」「眠る」「手足を動かす」「じっと見つめる」程度だが、思わず抱きしめてみたくなる魅力を放っている。二に、大村先生の飄々とした風格である。ある時は厳しく、ある時はコミカルに、そして極め付きは温もりのある優しいまなざし、まさに「我が師の恩」を感じさせる教員の姿を、齋藤達雄は見事に演じきった。小津安二郎監督は、以後も「一人息子」(1936年)でトンカツ屋になった元教員(笠智衆)、「秋刀魚の味」(1963年)でラーメン屋になった元教員(東野英次郎)を描いている。その初代としての貫禄は十分であった。三に、岡島を演じる岡田時彦とすが子を演じる八雲恵美子の「夫婦愛」である。どこか型破り、反骨心旺盛だが頼りない夫に、気をもみながらも付いていく健気な妻、「夫唱婦随」の生き様に秘められた愛情が鮮やかに描き出される。二人は前年作の「その夜の妻」でも、夫婦役として共演しているが、その時に比べて「絆」がいっそう強まっているように、私は感じた。
終わりに、この映画のタイトルは「東京の合唱」と書いて「東京のコーラス」と読む。しかも寮歌をコーラスするなど、現代では唐突とも思われるが、そのコーラスが登場するのは大詰め、しかもエンディングを飾るという演出は心憎いばかりである。数多い小津映画の傑作の中でも、屈指の名品であることは間違いない。(2017.5.31)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

その時から幾星霜、今の岡島は会社員、妻・すが子(八雲恵美子)、長男(菅原秀雄)、長女(高峰秀子)、乳飲み子の次男を抱える世帯主である。
今日はボーナスの支給日、出勤の準備をしていると、長男が「パパ、自転車がほしい。買ってよ」とせがむ。「ママに聞いてごらん」、妻も了承。長女も「あたしにも何か買ってよ」というと、長男が「お前は紙風船、買ってもらったじゃないか、欲ばり!」と小突く。「アーン」と泣き出す、子役・高峰秀子の姿がたまらなく魅力的であった。
岡島は出勤、いよいよボーナスが支給される昼休み、社員は社長室の前に並んで期待を膨らませる。一人ずつ順番に手渡されて、「いくら?」と思うが、周囲の目がある。確認する場所はトイレの中、中にはあわてて札束を便器に落としてしまう者も居た。岡島もめでたくボーナスを受領、扇風機で鉛筆を削り、何を買おうか予算を立てる。ふと、横を見ると、老社員の山口(坂本武)がふさぎ込んでいる。先刻、解雇を言い渡されたのだ。
山口の勧誘で生命保険に加入した者が、翌日、交通事故で死亡したことが原因らしい。それを聞いて、岡島の反骨心が燃え上がった。「おい、みんな!山口さんは解雇だそうだ。勧誘と事故死は関係ない、会社が金を払うのは当然じゃないか」と呼びかければ、一同「そうだ、そうだ」、同僚の一人(山口勇)が「社長に談判しよう」と提案した。岡島が「よく言った。じゃあ君が談判に行ってくれ」と言うと、とたんにトーン・ダウン、「・・・でも会社に損失を与えたことは間違いないんだからなあ」。岡島が「なあんだ、口ほどにもない奴だ」「何!じゃあ、お前が行けるものなら行って見ろ」といきり立つ。岡島は、平然と社長室に入っていった。深々と社長(谷麗光)に一礼し、談判を始めるが、社長は聞き入れない。秘書(宮島健一)がとりなすが、岡島も引き下がらない。口で争い、扇子で争い、小突き合い、とうとう社長を押し倒す。激昂した社長は、即刻「お前はクビだ」と宣言する。かくて、岡島もまた、失業の身となってしまった。
フラフラと岡島が自宅に帰っていく。手にしているのは自転車ではなく、オモチャのスクーターだった。待ち焦がれて迎えに出た長男が「自転車は?」と問えば、スクーターを手渡す。今度は、長男が怒り出した。「なんだ、こんなもの!」と言ってスクーターを放り出すなり、泣き出した。やむなくスクーターを拾って家に戻ると、長女が次男をあやしていた。「ママは?」「公営市場に買い物に行ったわ」。岡島は力なく座り込む。そこに長男も戻ってきた。下駄を放り投げ、部屋に上がると障子に穴をあける。ドスンドスンと音を立て岡島に抗議する。「パパの嘘つき!」岡島は再度、スクーターを取り出してなだめたが、長男は頑として聞かず、父を足蹴にした。もうこれまでと、岡島は長男を抱え上げ、数十回の尻叩き、長男は大声で泣き叫ぶ。その様子を長女と次男があっけにとられて眺めている。父子の修羅場はたいそう見応えがあった。やがてすが子が帰宅する。一目散に駆け寄る長男、いったい何事があったのか、「あんまり我が儘を言うから叱ったんだ」事情を聞いて、妻が言う。「パパが悪い。子どもに嘘をつくなんて、どんなにか楽しみにしていたものを」。長女までも「パパの嘘つき」と言って舌を出す。「何が悪い」と言い返してみたものの・・・、岡島は力なく封筒を取り出して、すが子に渡す。入っていたのは解雇通知の辞令。「社長と喧嘩したんだ。こちらの言い分が正当でも、相手が社長だからしかたがない」。うなだれるすが子、気を取り直してスクーターを長男に与え「これで我慢おし」。しかし長男は再び「イヤだ」といって泣き出す始末、その母子の様子を見て、「かわいそうだ、買ってあげよう」と岡島は決めた。一件落着、子どもたちは辞令を紙飛行機に折って遊び始める。岡島も一緒に・・・。
数日後、岡島は職探し、上野公園(日比谷公園かもしれない)辺りを通りかかると、共に解雇された山口が、サンドイッチマンの態でビラまきをしている。ぶら下げている看板には「健康安全週間・東京市」と記されてあった。しばし、ベンチで二人は語り合う。その向かいでは失業者の親子か、子どもが下駄をぶつけて大泣きしている。「思い切り泣ける子どもがうらやましい」と山口が言う。その時、人々が駆けだして、ただならぬ様子、「動物小屋のクマが檻を破って逃げ出した」とのこと、山口は、見に行こうと誘ったが、岡島は「クマが逃げ出したって僕らの人生には何のかかわりもないじゃないですか」とその場を動こうとしなかった。
今日もあぶれて岡島が家に戻る道、自転車を買ってもらった長男が、子どもたちに混じって魚掬いをしている。声をかけると「美代ちゃんが病気になった。クズマンジュウが当たったらしい」と言う。あわてて帰宅、すが子は次男を抱きながら氷を砕いている。長女は寝かされて、苦しそう。「なんでクズマンジュウなんか食べさせたんだ」「古新聞を売ったお金が入ったので、せめて子どもたちの好きなものを食べさせてあげようと思って。お医者様は入院させた方がいいと・・・」「金のことが心配なのか。金なんかどうにでもなる。早く車屋さんを呼んでこい」と長男に言いつける。自転車に飛び乗って、長男は車屋へ。かくて入院の運びとなった。和室の病室で一同が待機していると医者の診察が始まる。「この分なら御心配はいりません」という結果に岡島は安堵、長男と家に戻ろうとする。すが子が「ここの支払い、大丈夫?」と問いかけると、岡島はさびしく肯いて帰路についた。
やがて退院。家族一同は大喜びで家に戻る。岡島と長男、長女は車座になって「手遊び」を始めたが、すが子が箪笥を開けると、中の着物はすべて無くなっていた。驚いて「箪笥の中は空っぽよ」と言うと「そのおかげで、美代子はこんなに元気になれたんだ」と手遊びを続ける。長男がすが子も誘い、やがて四人の手遊びが始まった。子どもたちは大喜びだが、これからのことを思うと、すが子は浮かれられない。精一杯はしゃいでいる岡島を見つめ、そっと涙をぬぐうすが子の姿は天下一品、夫婦、親子の絆が見事に結実した名場面であった、と私は思う。
次の日も岡島は職探し、職業紹介所の前で珍しい人物に出会った。学校時代の恩師、大村先生である。今では教職を退き、女房(飯田蝶子)と一緒に「洋食屋」を始めたという。「手伝ってもらえないか。その代わりに君の就職口を世話するよ。これでも文部省に知り合いが居るんだ」という依頼に「恩返しのつもりで」と同意、しかし、その手伝いは宣伝の旗持ちだったとは・・・。二本の幟を担いで、先生はビラ配り、「カロリー軒のライスカレー」を広めようとしているのである。たまたま、その情景を市電の中からすが子たちが目にする。岡島の就職を知人に頼みに行く途中であった。
岡島が帰宅すると、すが子の様子が素っ気ない。「お前も出かけたのかい」「あなたの口を頼みに行ったんです」「それでどうだった」首を振りながら「それより、途中で大変なものを見てしまったんです」「何を?」「あなたを見てしまったんです。あんなことまでしてほしいと頼んでいません」。岡島は悄然として「あの爺さんは、昔の先生なんだ。手伝いをすれば就職口を世話してくれると言うもんだから」「当てになるんですか」「困ったときは、当てにならないことでも当てにするもんだ」。しみじみと窓の外の洗濯物を見つめながら「オレも昔のような覇気がなくなった」と呟く。その姿を見て、すが子の気持ちが変わった。「あたしも、先生の所にお手伝いに行きます!」
かくて四、五日後、カロリー軒では大村先生を囲んで同窓会が開かれる。岡島が幹事を務めたのだろう。懐かしい面々が一堂に会して昔話に花が咲く。自慢のライスカレーにビールで乾杯、かいがいしく手伝うすが子の姿もある。岡島の子どもたちも手伝いに来ていた。長女はスプーンを配り、御相伴に預かるといった按配で、実に賑々しく活気あふれる雰囲気であった。先生は紋付き羽織に着替えて、威儀を正し、一同に訓示する。その後で「誠に相済まないが、会費は頂戴する」といった一言が可笑しかった。宴もたけなわという時、郵便が届いた。先生が開けると、「岡島の就職口が見つかった」という文部省からの知らせであった。「栃木県の女学校で英語の先生を求めている。君は英語は達者かね」。岡島は一も二もなく承諾、「とにもかくにも行くことに決めようね」とすが子に言えば、寝ている次男を見つめながら「きっといつかは東京に帰って来れますわ」と、都落ちの思いを噛みしめる。
いよいよ大詰め、すが子も宴席に加わると、遅刻の常連だった同窓生もやって来た。先生の「君は相変わらずだね」に皆は大笑い、一同が起立して「寮歌の合唱だ!」。「三年の春は過ぎやすし 花くれないのかんばせも 今わかれてはいつか見む・・・」と歌いながら、大村先生と岡島は、ふと涙ぐむ。「よかったなあ、おめでとう」「ありがとうございました」という師弟の絆が浮き彫りされ、やがて二人には笑顔が・・・、岡島の覇気は今、蘇ったかと思われるうちに、この映画は「終」を迎えた。
この映画の見どころは満載だが、一に、子どもたちの生き生きとした姿であろう。長男・菅原秀雄の利かん気、腕白振り、長女・高峰秀子のやんちゃ振り、おしゃまな風情、さらに次男の可愛さも見逃せない。彼の演技は「泣く」「眠る」「手足を動かす」「じっと見つめる」程度だが、思わず抱きしめてみたくなる魅力を放っている。二に、大村先生の飄々とした風格である。ある時は厳しく、ある時はコミカルに、そして極め付きは温もりのある優しいまなざし、まさに「我が師の恩」を感じさせる教員の姿を、齋藤達雄は見事に演じきった。小津安二郎監督は、以後も「一人息子」(1936年)でトンカツ屋になった元教員(笠智衆)、「秋刀魚の味」(1963年)でラーメン屋になった元教員(東野英次郎)を描いている。その初代としての貫禄は十分であった。三に、岡島を演じる岡田時彦とすが子を演じる八雲恵美子の「夫婦愛」である。どこか型破り、反骨心旺盛だが頼りない夫に、気をもみながらも付いていく健気な妻、「夫唱婦随」の生き様に秘められた愛情が鮮やかに描き出される。二人は前年作の「その夜の妻」でも、夫婦役として共演しているが、その時に比べて「絆」がいっそう強まっているように、私は感じた。
終わりに、この映画のタイトルは「東京の合唱」と書いて「東京のコーラス」と読む。しかも寮歌をコーラスするなど、現代では唐突とも思われるが、そのコーラスが登場するのは大詰め、しかもエンディングを飾るという演出は心憎いばかりである。数多い小津映画の傑作の中でも、屈指の名品であることは間違いない。(2017.5.31)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-15
付録・邦画傑作選・「按摩と女」(監督・清水宏・1938年)
ユーチューブで映画「按摩と女」(監督・清水宏・1938年)を観た。監督・清水宏、戦前傑作の逸品である。山の温泉場(おそらく塩原か?)に向かう按摩の徳一(徳大寺伸)と福市(日守新一)が四方山話をしながら歩いている。青葉の頃になったので、海の温泉場から山の湯治場に一年ぶりでやって来たのだ。「こうしていると、青葉の景色が見えるようだ」「今日は目明きを何人追い越した?」「17人だ」「おかげで、馬の尻や犬に何度もぶつかった」「近頃の目明きは頼りにならない」などと語り合いながら、「だから、俺たちは勘を働かせなくちゃいけない」と徳一が言う。「あっちから、子どもがやって来る。何人いると思う?」、福市が勘を働かせて「8人だな」と言えば、徳一は「いや、8人半だ。赤ん坊が負ぶさっている」「赤ん坊?ハハハ、赤ん坊には気がつかなかったな」。やがて、子どもたちが二人とすれ違う。たしかに、間違いなく7人と赤ん坊を負ぶった1人が通り過ぎた。確認して歩き出そうとすると、徳一が「ちょっと待った」と福一を制止する。前方に大きな馬糞があったのだ。二人は巧妙にその場を通り脱ける。「徳さん、もう少しゆっくり歩こうよ、疲れてしまった」「日のあるうちに宿につきたいからね」「俺たちには関係ない、いつも夜道ばかりじゃないか」「それはそうだけど、さっき俺たちを追い抜いていった学生たちを追い越してやりたいんだよ」「そりゃあ、無理だよ」「何故?」「何故ったって、無理なものは無理だよ」「無理が通れば道理が引っ込む。俺は無理を通すんだ!」と急ぎ足になった途端、徳はが大きな石に躓き転倒する。その時、後方からトテ馬車が近づいて来た。あわてて道の両脇に馬車を避け、見送る。「いい女が乗っていたねえ、東京の女だよ。東京の匂いがしたよ」。たしかに、その馬車には一人の女・三沢美千穂(高峰三枝子)、そして東京の男・大村真太郎(佐分利進)、甥の研一(爆弾小僧)さらにもう一人、謎の男(赤城正太郎)の4人が乗っていた。馭者の話、「あの按摩たちはここの湯治場の名物なんですよ。毎年、暖かくなると南の海の温泉場からやって来るんです。そのたびに何人追い抜いたといい気持ちになっているうですよ。寒くなるとまた南の温泉場に帰って行くんです」。
その日の夜、さっそく徳一と福市にお呼びがかかった。街の小橋を渡りながら「今日は福さん、どこだい」「俺は観音屋だ」「俺は鯨屋だ」と言って別れる。徳一は鯨屋を訪れ、主人(坂本武)に「今年もよろしくお願いいたします」と、手土産を渡して挨拶、「海の温泉場の景気はどうだい」「さっぱりです」「どこも同じだなあ」と語り合うところに、女中のお菊(春日京子)が二階から降りてきて、「四番のお客様と、学生さんのところよろしく」と告げる。四番のお客様とは、馬車に乗っていた東京の女・美千穂、学生とは、ここに来るまでに追い抜いて行った連中(近衛敏明、磯野秋雄、廣瀬徹、水原弘志)であった。徳一は美千穂の肩を揉みながら「奥様は東京の方ですか」「まあ奥様だなんて」失礼しました、お嬢様でしたか」。美千穂は笑いをこらえるが多くを語らない。「だいぶ、この筋が凝っていらっしゃいますねえ。何か考えごと、心配事がおありになるのでは」「どんなことか、おわかり?」「そこまでは・・・」。次は、学生たちの部屋。「按摩さん、今日はずいぶん速歩で追いかけて来るんで、俺たちは恐くなって逃げ出したんだよ」「そうでしたか。それは残念でした!」「どうして?」「いえ、とにかく残念でした」などと言いながら、学生4人の足を徹底的に揉みまくる。捻り鉢巻きで片肌脱ぎの懸命な姿が、たいそう「絵になっていた」。一方、福市の客は、ハイキングの女学生(槇芙佐子、三浦光子、中井戸雅子、関かほる、平野鮎子)と、大村真太郎であった。女学生は、蒲団の上ではしゃぎながら「按摩さん、今日追い抜かれたんで、足がこんなに痛くなってしまったわ。按摩賃、負けなさいよ」などと福市をやり込める。「近頃の女学生は大胆になったわ」と、美千穂が徳一に語ったことが裏書きされる場面であった。大村の部屋では、真太郎を揉んでいる福市の鼻を、研一が紙縒りをつくり、黙ってくすぐる。そのたびにアブを追い払うような仕種をみせる福市の姿も絶品、永久保存に値する名場面であった、と私は思う。(現代では、障害者の尊厳を傷つける行為としてカットされるべき一コマであるにしても・・・、ただし映画の中ではそのままでは終わらない)
翌朝、学生たちは峠越えのハイキングに出発したが、スタート早々、昨日の「揉み返し」が来て歩けない。やむなく宿屋に引き返す。その様子を見て、女学生たちが爽やかに追い抜いて行った。徳一たちが按摩宿でたむろしているとお菊が迎えに来た。「徳さん、東京のお客さんから名指しよ」。徳一はお菊に「内緒だよ」と言って、伊豆からの土産物・椿油をプレゼント、福市ら按摩仲間(油井宏信、飯島善太郎、大杉恒雄)が「ナイショダヨ、ナイショ、ナイショ」と冷やかすが、徳一は一向に動じない。徳一が鯨屋に向かう途中、たしかに美千穂に遭遇したはずだが、なぜか美千穂は立ち去った。念のため鯨屋に赴く。案の定、美千穂は不在、「戻るまで待ちましょう」と主人の肩を揉み始める。主人は「今日は朝から大変だよ。学生さんたちが帰ってきて風呂に入っている間に、金銭すべてを盗られてしまった。その時、宿に居たのは東京のお客様はずだったが、まさか・・・」と言う所に、美千穂が研一を連れて戻って来た。河原で魚釣りをしている研一に声をかけ、釣れた魚で昼食を摂ろうと約束をして来たらしい。徳一が美千穂の部屋に向かうと、前は学生の部屋。「おや、きのうの学生さん。峠越えは?」「それどころじゃないよ、足が痛くて歩けない。その上、空き巣に入られてすってんてんだ」「それは、御災難でした。いずれまた」とケロッとした様子で、美千穂の部屋へ・・・。しかし、美千穂は「さっき気づかれ逃げ出したんで汗かいちゃった、一風呂浴びてくるわ、按摩さんも入らない?」「えっ、一緒にですか」「まあ、イヤよ、一緒になんて」。フラレた徳一がしょんぼりしていると、傍に居た研一が団扇を近づけていたずらをしようとする。気配を感じた徳一が団扇を叩き落とすと、研一が泣き出した。今度は、徳一が福市の仇を取ったのである。その場面も、たいそう可笑しく、私の笑いは止まらなかった。
鯨屋の主人は学生たちの滞在費と帰りの汽車賃を弁償、一件落着になりそうだったのだが・・・。
その後、話は、①研一を通して、観音屋での美千穂と真太郎の出会い、③真太郎の延泊決意、④美千穂が観音屋に出向き真太郎、研一と夕食を共にする、⑤按摩部屋に観音屋から迎えが来る。徳一は観音屋だと聞いて仕事を福市に譲る、④しかし仲間から、美千穂は今晩は観音屋に居るという話を聞いて、あわてて福市を追いかける、⑤その途中、小橋で涼んでいる学生たちとぶつかり、大喧嘩。⑥翌朝、福市から、昨日観音屋にも空き巣が入って大騒ぎ、自分も調べられたと聞く。⑦河原では真太郎と美千穂の「身の上話」、⑧その夜、小橋で真太郎と美千穂の「交情話」、⑨徳一と研一の出会いと交流。⑤徳一と美千穂の交流、という展開を見せるが、詳細は割愛する。
やがて、真太郎と研一は東京へ帰って行った。一人残った美千穂は、雨の中、河原を散歩する。その日の夜、小橋の所で、徳一は「他の宿屋でも空き巣が続発している。警察が滞在客をしらみつぶしに調べるそうだ」とう話を福市から聞かされる。空き巣の犯人は美千穂に違いない、そう盲信した徳一は慌てて鯨屋の美千穂の部屋に駆け込む。「早く、早く逃げて下さい。しらみつぶしに探しています」「えっ!探している?」「手が回っています、こうしちゃあいられません」、美千穂にも衝撃が走った。二人は裸足のまま鯨屋の裏口から脱け出し、路地の暗がりに身を隠す。「ここでしばらく待って居てください。すぐに荷物を持って参ります」。美千穂が「按摩さん!」と行くのを止めようとすると「来ちゃあいけません。私は何もかも知っていたんです。目明きの目をごまかせても私の目をごまかすことはできません。私はとても辛かったんです。早く逃げてください。私の目の届かない遠いところへ」「・・・・」「鯨屋さんで学生さんたちのお金がなくなった時、他でも盗難事件があったときにも、私があなたを信じようとして苦しみました」。その言葉を聞いて、美千穂の肩の力が脱けていく。「按摩さん、あんた何かとんでもない間違いをしてるんじゃない」「いえ、私の目に狂いはありません。あなたは考え事をしたり、心配したり、物音に怯えていたじゃありませんか」「バカバカしくて話にもならないわ。でも、それほどまでに私の身を心配してくれていたんだから、何もかもお話ししましょう」。
美千穂は東京の「囲われ者」(妾)、旦那のお世話になるのがイヤで逃げてきたのである。奥様やお嬢様に申し訳なくて逃げてきたのである。しかし、旦那は必ず探しに来るだろう。だから、馬車のラッパの音や人の足音にも怯えていたのである。「按摩さん、私を逃がしてくれようとしたあなたに何の恨みもありません。あなたの目は見え過ぎていたんです。これからも、獣のような旦那の目の届かない所へ逃げて逃げて、逃げ回りますわ」徳一は、「お客様!」と言って跪き、頭を垂れる他はなかった。
大詰めは、雨の中、馬車に乗り込む美千穂の姿、続いて警官が一人の男を曳いて乗り込んで来る。美千穂が来た時にも乗っていた、あの謎の男であった。走り出す馬車を見送るお菊、番頭、そしてもちろん徳一、福市の姿もある。最後、美千穂はお菊に向かって「坊やから手紙が来たら、早く大人になって立派な人になるようにってねと返事、出しといてね」と言い残し、去って行った。思わず馬車を追いかけて駆け出すす徳一、その目には今、ハッキリと美千穂の面影が映っていたに違いない。
この映画の演出、展開、映像には寸分の隙もない傑作である。見どころは満載だが、まず一番は、按摩・徳一、福市コンビの景色であろう。道理よりも無理を通す覇気、それでいて女にはめっぽう惚れっぽい徳一の心意気と、いつも受け身で醒めている福市の安定感が、絶妙の呼吸で場面を引き立てる。何かを感じると、杖を振り上げて構える福市の姿勢がたまらなく魅力的である。徳一も学生4人と渡り合い、自分の負傷と同等に相手を傷つける実力はさすが、研一のいたずらにも一瞬で対応し「おじさんは、何だってできるんだよ」と、一本橋をするすると渡ってみせる姿は光っていた。この映画で見せた、徳大寺伸、日守新一の所作は、戦後、勝新太郎に引き継がれ、あの「座頭市」を生み出したことは間違いないだろう。二番目は、女・三沢美智穂の風情であろうか。日陰者でありながらどこか清純、徳一から「お嬢様ですか」と言われ苦笑する。高峰三枝子は当時20歳になる直前、でも研一からは「おばちゃん」と呼ばれ、慕われても不自然でない風格を備えている。大村役の佐分利信との「逢瀬」(交情場面)でも、互角に渡り合い、ふと「もう一晩泊まろうか」という気持ちにさせる魅力が輝いていた。按摩仲間、学生連中にも「不思議な女だ」と興味を抱かせる。最後まで徳一を「按摩さん」と呼ぶ姿も、凜として清々しかった。三番目は、大村の甥、研一を演じた爆弾小僧(横山準)の「やんちゃ振り」である。福市へのいたずらが成功したので徳一にも仕掛け、逆に驚かされた途端に泣き出す。風呂に潜って泳ぎ始める、大村と美千穂に放っておかれると「つまんねえ」と言って、その場を去る。両親と死別、独身の叔父に育てられる淋しさも十分に伝わって来た。四番目は、街中の小川に架けられた小さな橋である。その橋はドラマの起承転結に必ず登場する。人物がそこにさしかかると、必ず何かが起きるのだ。例えば按摩二人の仕事始め、例えば徳一と学生の喧嘩、例えば大村と美千穂の「逢瀬」、そこに現れる徳一の姿などなど、いわば、人生の舞台、分岐点として、人々の心象を代弁する役割を持っている。そうした監督・清水宏の演出(仕掛け)は心憎いばかり・・・、見どころは他にも多く、枚挙に暇がないほどだが、長くなるので割愛する。
戦前邦画、珠玉の名品であったと、私は思う。 (2017.6.8)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

その日の夜、さっそく徳一と福市にお呼びがかかった。街の小橋を渡りながら「今日は福さん、どこだい」「俺は観音屋だ」「俺は鯨屋だ」と言って別れる。徳一は鯨屋を訪れ、主人(坂本武)に「今年もよろしくお願いいたします」と、手土産を渡して挨拶、「海の温泉場の景気はどうだい」「さっぱりです」「どこも同じだなあ」と語り合うところに、女中のお菊(春日京子)が二階から降りてきて、「四番のお客様と、学生さんのところよろしく」と告げる。四番のお客様とは、馬車に乗っていた東京の女・美千穂、学生とは、ここに来るまでに追い抜いて行った連中(近衛敏明、磯野秋雄、廣瀬徹、水原弘志)であった。徳一は美千穂の肩を揉みながら「奥様は東京の方ですか」「まあ奥様だなんて」失礼しました、お嬢様でしたか」。美千穂は笑いをこらえるが多くを語らない。「だいぶ、この筋が凝っていらっしゃいますねえ。何か考えごと、心配事がおありになるのでは」「どんなことか、おわかり?」「そこまでは・・・」。次は、学生たちの部屋。「按摩さん、今日はずいぶん速歩で追いかけて来るんで、俺たちは恐くなって逃げ出したんだよ」「そうでしたか。それは残念でした!」「どうして?」「いえ、とにかく残念でした」などと言いながら、学生4人の足を徹底的に揉みまくる。捻り鉢巻きで片肌脱ぎの懸命な姿が、たいそう「絵になっていた」。一方、福市の客は、ハイキングの女学生(槇芙佐子、三浦光子、中井戸雅子、関かほる、平野鮎子)と、大村真太郎であった。女学生は、蒲団の上ではしゃぎながら「按摩さん、今日追い抜かれたんで、足がこんなに痛くなってしまったわ。按摩賃、負けなさいよ」などと福市をやり込める。「近頃の女学生は大胆になったわ」と、美千穂が徳一に語ったことが裏書きされる場面であった。大村の部屋では、真太郎を揉んでいる福市の鼻を、研一が紙縒りをつくり、黙ってくすぐる。そのたびにアブを追い払うような仕種をみせる福市の姿も絶品、永久保存に値する名場面であった、と私は思う。(現代では、障害者の尊厳を傷つける行為としてカットされるべき一コマであるにしても・・・、ただし映画の中ではそのままでは終わらない)
翌朝、学生たちは峠越えのハイキングに出発したが、スタート早々、昨日の「揉み返し」が来て歩けない。やむなく宿屋に引き返す。その様子を見て、女学生たちが爽やかに追い抜いて行った。徳一たちが按摩宿でたむろしているとお菊が迎えに来た。「徳さん、東京のお客さんから名指しよ」。徳一はお菊に「内緒だよ」と言って、伊豆からの土産物・椿油をプレゼント、福市ら按摩仲間(油井宏信、飯島善太郎、大杉恒雄)が「ナイショダヨ、ナイショ、ナイショ」と冷やかすが、徳一は一向に動じない。徳一が鯨屋に向かう途中、たしかに美千穂に遭遇したはずだが、なぜか美千穂は立ち去った。念のため鯨屋に赴く。案の定、美千穂は不在、「戻るまで待ちましょう」と主人の肩を揉み始める。主人は「今日は朝から大変だよ。学生さんたちが帰ってきて風呂に入っている間に、金銭すべてを盗られてしまった。その時、宿に居たのは東京のお客様はずだったが、まさか・・・」と言う所に、美千穂が研一を連れて戻って来た。河原で魚釣りをしている研一に声をかけ、釣れた魚で昼食を摂ろうと約束をして来たらしい。徳一が美千穂の部屋に向かうと、前は学生の部屋。「おや、きのうの学生さん。峠越えは?」「それどころじゃないよ、足が痛くて歩けない。その上、空き巣に入られてすってんてんだ」「それは、御災難でした。いずれまた」とケロッとした様子で、美千穂の部屋へ・・・。しかし、美千穂は「さっき気づかれ逃げ出したんで汗かいちゃった、一風呂浴びてくるわ、按摩さんも入らない?」「えっ、一緒にですか」「まあ、イヤよ、一緒になんて」。フラレた徳一がしょんぼりしていると、傍に居た研一が団扇を近づけていたずらをしようとする。気配を感じた徳一が団扇を叩き落とすと、研一が泣き出した。今度は、徳一が福市の仇を取ったのである。その場面も、たいそう可笑しく、私の笑いは止まらなかった。
鯨屋の主人は学生たちの滞在費と帰りの汽車賃を弁償、一件落着になりそうだったのだが・・・。
その後、話は、①研一を通して、観音屋での美千穂と真太郎の出会い、③真太郎の延泊決意、④美千穂が観音屋に出向き真太郎、研一と夕食を共にする、⑤按摩部屋に観音屋から迎えが来る。徳一は観音屋だと聞いて仕事を福市に譲る、④しかし仲間から、美千穂は今晩は観音屋に居るという話を聞いて、あわてて福市を追いかける、⑤その途中、小橋で涼んでいる学生たちとぶつかり、大喧嘩。⑥翌朝、福市から、昨日観音屋にも空き巣が入って大騒ぎ、自分も調べられたと聞く。⑦河原では真太郎と美千穂の「身の上話」、⑧その夜、小橋で真太郎と美千穂の「交情話」、⑨徳一と研一の出会いと交流。⑤徳一と美千穂の交流、という展開を見せるが、詳細は割愛する。
やがて、真太郎と研一は東京へ帰って行った。一人残った美千穂は、雨の中、河原を散歩する。その日の夜、小橋の所で、徳一は「他の宿屋でも空き巣が続発している。警察が滞在客をしらみつぶしに調べるそうだ」とう話を福市から聞かされる。空き巣の犯人は美千穂に違いない、そう盲信した徳一は慌てて鯨屋の美千穂の部屋に駆け込む。「早く、早く逃げて下さい。しらみつぶしに探しています」「えっ!探している?」「手が回っています、こうしちゃあいられません」、美千穂にも衝撃が走った。二人は裸足のまま鯨屋の裏口から脱け出し、路地の暗がりに身を隠す。「ここでしばらく待って居てください。すぐに荷物を持って参ります」。美千穂が「按摩さん!」と行くのを止めようとすると「来ちゃあいけません。私は何もかも知っていたんです。目明きの目をごまかせても私の目をごまかすことはできません。私はとても辛かったんです。早く逃げてください。私の目の届かない遠いところへ」「・・・・」「鯨屋さんで学生さんたちのお金がなくなった時、他でも盗難事件があったときにも、私があなたを信じようとして苦しみました」。その言葉を聞いて、美千穂の肩の力が脱けていく。「按摩さん、あんた何かとんでもない間違いをしてるんじゃない」「いえ、私の目に狂いはありません。あなたは考え事をしたり、心配したり、物音に怯えていたじゃありませんか」「バカバカしくて話にもならないわ。でも、それほどまでに私の身を心配してくれていたんだから、何もかもお話ししましょう」。
美千穂は東京の「囲われ者」(妾)、旦那のお世話になるのがイヤで逃げてきたのである。奥様やお嬢様に申し訳なくて逃げてきたのである。しかし、旦那は必ず探しに来るだろう。だから、馬車のラッパの音や人の足音にも怯えていたのである。「按摩さん、私を逃がしてくれようとしたあなたに何の恨みもありません。あなたの目は見え過ぎていたんです。これからも、獣のような旦那の目の届かない所へ逃げて逃げて、逃げ回りますわ」徳一は、「お客様!」と言って跪き、頭を垂れる他はなかった。
大詰めは、雨の中、馬車に乗り込む美千穂の姿、続いて警官が一人の男を曳いて乗り込んで来る。美千穂が来た時にも乗っていた、あの謎の男であった。走り出す馬車を見送るお菊、番頭、そしてもちろん徳一、福市の姿もある。最後、美千穂はお菊に向かって「坊やから手紙が来たら、早く大人になって立派な人になるようにってねと返事、出しといてね」と言い残し、去って行った。思わず馬車を追いかけて駆け出すす徳一、その目には今、ハッキリと美千穂の面影が映っていたに違いない。
この映画の演出、展開、映像には寸分の隙もない傑作である。見どころは満載だが、まず一番は、按摩・徳一、福市コンビの景色であろう。道理よりも無理を通す覇気、それでいて女にはめっぽう惚れっぽい徳一の心意気と、いつも受け身で醒めている福市の安定感が、絶妙の呼吸で場面を引き立てる。何かを感じると、杖を振り上げて構える福市の姿勢がたまらなく魅力的である。徳一も学生4人と渡り合い、自分の負傷と同等に相手を傷つける実力はさすが、研一のいたずらにも一瞬で対応し「おじさんは、何だってできるんだよ」と、一本橋をするすると渡ってみせる姿は光っていた。この映画で見せた、徳大寺伸、日守新一の所作は、戦後、勝新太郎に引き継がれ、あの「座頭市」を生み出したことは間違いないだろう。二番目は、女・三沢美智穂の風情であろうか。日陰者でありながらどこか清純、徳一から「お嬢様ですか」と言われ苦笑する。高峰三枝子は当時20歳になる直前、でも研一からは「おばちゃん」と呼ばれ、慕われても不自然でない風格を備えている。大村役の佐分利信との「逢瀬」(交情場面)でも、互角に渡り合い、ふと「もう一晩泊まろうか」という気持ちにさせる魅力が輝いていた。按摩仲間、学生連中にも「不思議な女だ」と興味を抱かせる。最後まで徳一を「按摩さん」と呼ぶ姿も、凜として清々しかった。三番目は、大村の甥、研一を演じた爆弾小僧(横山準)の「やんちゃ振り」である。福市へのいたずらが成功したので徳一にも仕掛け、逆に驚かされた途端に泣き出す。風呂に潜って泳ぎ始める、大村と美千穂に放っておかれると「つまんねえ」と言って、その場を去る。両親と死別、独身の叔父に育てられる淋しさも十分に伝わって来た。四番目は、街中の小川に架けられた小さな橋である。その橋はドラマの起承転結に必ず登場する。人物がそこにさしかかると、必ず何かが起きるのだ。例えば按摩二人の仕事始め、例えば徳一と学生の喧嘩、例えば大村と美千穂の「逢瀬」、そこに現れる徳一の姿などなど、いわば、人生の舞台、分岐点として、人々の心象を代弁する役割を持っている。そうした監督・清水宏の演出(仕掛け)は心憎いばかり・・・、見どころは他にも多く、枚挙に暇がないほどだが、長くなるので割愛する。
戦前邦画、珠玉の名品であったと、私は思う。 (2017.6.8)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-14
付録・邦画傑作選・「吾輩ハ猫デアル」(監督・山本嘉次郎・1936年)
ユーチューブで映画「吾輩ハ猫デアル」(監督・山本嘉次郎・1936年)を観た。原作は夏目漱石の小説、その主役は「吾輩」と名乗る猫だが、映画に登場する猫は、何とも貧相で、旧制中学の教員・珍野苦沙弥先生(丸山定夫)宅に迷い込み、女中の清(芸名不詳・好演)につまみ出されそうになったとき、先生が「置いてやればいい」という一言で、ようやく珍野家の一員に加えられた。清に雑巾で足を拭かれたとたん、床に放り出された。思わず「ギャー」と叫ぶなど、可愛らしい様子は微塵も見られない。どこにでも居る、ただの野良猫に過ぎず、登場人物の合間を時折、通り過ぎる程度の役回りであることが、たいそう面白かった。
映画の主要な登場人物は、先生の他、その妻女(英百合子)、美学者・迷亭(徳川夢声)、先生の教え子で理学士の水島寒月(北沢彪)、観月の友人で詩人の越智東風(藤原釜足)、近所の実業家・金田(森野鍛冶哉)、その妻女・鼻子(清川玉枝)、その娘・富子(千葉早智子)、先生の教え子・多々良三平(宇留木浩)、車夫(西村楽天?)の女房(清川虹子)といった面々である。
話は迷亭が先生宅を訪れ、「寒月君が恋をしているようだ」と言う所から始まる。ある梅見の宴で、寒月と金田富子が出会い、向島の安倍博士邸で行われた演奏会でも、富子のピアノに合わせて寒月はヴァイオリンを弾いた。どうやら恋をしているのは富子の方らしい。梅見の宴には東風も居り、富子に一目惚れ、演奏会でも新体詩を捧げたがケンモホロロ、全く相手にされない。終演後、富子が寒月に「自動車でお送りします」と声をかけるが、寒月は「いえ、ボクは土手を歩いて帰ります」と断った。吾妻橋にさしかかったとき「寒月さーん」と呼ぶ声が聞こえる。その声は川の中から・・・、寒月は意を決して欄干から飛び込んだが、気がつくと橋の真ん中に立っていたそうである。翌日、迷亭が再び、今度は寒月を伴って先生宅を訪れ、寒月から直接そのホラ話を聞いたのだが・・・、その場に、またまた先生の教え子・多々良三平が訪ねてくる。佐賀から上京したとのこと、土産の山芋を持参している。三平曰く「これからの時代は金が物を言う、株で一儲けしようと思うとります。実業家が天下を取るでしょう。先生も学問なんかやめて実業家になりませんか」。応えて先生曰く「わしは金は嫌いだ、儲けたければ勝手に儲ければいいだろう」持参した山芋を見て、「これは何だね」「山芋ですたい。先生もこれを食べて、ひとつ元気になりしゃんしゃい」。
しかし、その山芋を口にすることはできなかった。その日の夜、寝静まった先生宅に泥棒が闖入、着物と一緒に盗まれてしまったからである。泥棒の闖入と同時に、猫の「吾輩」はニャーニャーと鳴きながら、部屋を出て行く。何の役にも立たない猫の景色が、ことのほか絵になっていた。
次の日の朝、先生は盗まれた品々を書き出している。その場の細君とのやりとりは抱腹絶倒、「何だ、お前の恰好は、宿場女郎のようだ」「帯を盗られたんだからしょうがないでしょ」「いくらだ」「6円です」「高すぎる。1円50銭にしておけ」「そんな帯、ありませんよ」「あとは?」「山芋一箱」「いくらだ?」「知りませんよ」「じゃあ12円50銭にしておこう」「そんな高い山芋がありますか、バカバカしい」「だって、お前は今、知らないと、言ったじゃあないか」「知らなくたって、そんな法外な値段がありますか」
「知らんけれども十二円五十銭は法外だとは何だ。まるで論理に合わん。それだから貴様はオタンチン・パレオロガスだと云うんだ」「何ですって」「オタンチン・パレオロガスだよ」「何ですそのオタンチン・パレオロガスって云うのは」「何でもいい。それからあとは――俺の着物は一向いっこう出て来んじゃないか」「あとは何でも宜ようござんす。オタンチン・パレオロガスの意味を聞かしてちょうだい」「意味も何なにもあるもんか」「教えて下すってもいいじゃありませんか、あなたはよっぽど私を馬鹿にしていらっしゃるのね。きっと人が英語を知らないと思って悪口をおっしゃったんだよ。私だってそれくらい知っていますよ」「じゃあ、何だ。言って見ろ」「オタンチンとは頭のこと、パレオロガスとは禿げのことでしょ!」といった、丁々発止の「やりとり」は、月並の夫婦の間では、決して聞くことはできないであろう。
数日後、先生が勤めから帰ると、迷亭が訪れていた。そこにまた、金田富子の母・鼻子が自宅(洋館のある大きな屋敷)から先生宅まで、わずか数十メートルの道を自家用車で乗りつけた。この母親の名前は不詳だが、鼻が異様に高いので先生たちがつけた仇名である。初対面で、先生と迷亭はまずこの鼻に驚いたが、そんなことはおくびにも出さず応対すれば、いきなり「こちらに出入りしている、水島寒月という人は、どんな人物でしょうか」と切り出した。富子の婿として寒月がふさわしい人物か、身元調査に来たのである。理学士として将来有望か、博士号を取れるかなどなどを探りに来たらしい。先生も迷亭も、その高飛車な態度に「鼻持ちならない」と感じている様子がよくわかる。「寒月という人はどんなことを勉強しているのですか」「大学院で、地球の磁気の研究をしています。最近では『首縊りの力学』という論文を書きました」「そんなことでは博士号をとれそうもありませんね」「いや、本人が首をくくらなければ、できないこともないでしょう」「もっとわかりやすいものを勉強していると都合がいいんですがね」「寒月君が作った歌があります。《よべの泊りの十六小女郎、親がないとて、荒磯の千鳥、さよの寝覚の千鳥に泣いた、親は船乗り 波の底》というのはどうでしょう」「アラすてき!しゃみ(三味線)に乗りますわね」。鼻子は寒月の「人となり」を感じ取ったか、「それではこれで失礼いたします。私が来たことは寒月さんには御内密に・・・」と言って帰って言ったのだが・・・。見送った先生と迷亭の笑いが止まらない。「なんだ、あの鼻は!」「あの鼻は猫背だよ」「あれは19世紀に売れ残って20世紀に店ざらしといった顔だ」と言いたい放題、しかし、その様子を隣の車屋夫婦に見られてしまった。この夫婦、鼻子から言いつけられて先生宅(寒月の動静)を日頃から監視しているのである。
かくて、その情報はすぐさま金田家に伝えられる。金田家の事業は証券取引、従業員が忙しく立ち働く中に多々良三平の姿もあった。先生の友人の紹介で金田家に就職したらしい。
やがて、金田から先生宅への「いやがらせ」が始まる。先生宅の隣は金田が出資した学生寮、寄宿生たちが「まっくろけ節」を唄って大騒ぎ、野球のボールを投げ込んでは、先生の仕事の邪魔をする始末、とうとう先生は「神経衰弱」(ノイローゼ)で寝込んでしまった。見舞いに来た迷亭と話し込んでいる時、玄関に刑事が訪れた。先日の泥棒を捕まえたので同行・報告に来たという。あわてて先生、「ごくろうさまです」と泥棒の方に挨拶をしてしまった。迷亭に指摘され、「でも、あっちの方が偉そうだったぞ、袋手なんかしていたもの」「あれは手錠を隠していただけだ」「なんだ、そうか」「そんなに暢気なら、神経衰弱も大したことはないな」。
一方、金田富子は越智東風が舞台監督を務める芝居のヒロインに出演することに・・・、寒月に招待状を出したのだが、彼は用事があって故郷に帰ったという。富子は拍子抜け、さんざんに駄々をこねて、「舞台には出ない」という。6時開演だというのに、30分超過しても幕が上げられない。その最中、多々良三平が観客席の金田のもとに飛んで来た。(世界)情勢の変化で、株が暴落したという。見る見る顔面蒼白となった金田は、急いで帰宅。芝居の公演もメチャクチャになってしまった。そのことを報告に先生宅を訪れる東風、迷亭も同席している。3人でビールでも飲んでいたか、先生に抱かれていた猫の「吾輩」もその「おこぼれ」を舐めだした。そこにやって来たのが寒月、玄関先に直立している。よく見ると、隣には妙齢の女性が・・・、「実は、故郷に帰って嫁をもらって来ました。御紹介します、これが愚妻です」「そうか、そうだったのか」、一同は「これはめでたい」と寿ぐ空気に包まれたが、「大変!猫が井戸に落ちました」という声が鳴り響く。先生も迷亭もあわてて井戸の中を覗き込むが、時すでに遅し、猫はあえなく溺死してしまった。ビールを舐めたことが災いになったのだろう。
先生は猫を供養し墓を建てた。墓標には「この下に稲妻起る宵あらん」と墨書されている。そこに多々良三平がやって来た。「金田家は株の暴落で潰れました。私も一文無し、また一から出直します。金田からどうしても富子を嫁に貰って欲しいと頼まれたので貰ってやることにしました。ハハハハハ」「そうか、それもまた、いいだろう」「先生、あれは何ですか」「猫の墓だよ」「あの猫は死んだんですか、惜しいことをしましたなあ、うまそうな猫だったのに」、先生の細君は呆れて「まあ、いやだ、三平さん、猫食べるの?」などと言ううちに、この傑作は「終」となった。
それにしても、昔の役者には「風格」があった。その筆頭が苦沙弥先生を演じた丸山定夫、表向きは学問を極めようとする素振りを見せながら、その実は昼寝をしたり、「鼻毛にも白髪がある」と感心したり、絵を描いたり、要するに「遊んで」暮らしている。妻女役の英百合子に向かって「馬鹿野郎」と言うことが日課になっている。それに対して英百合子も負けてはいない。彼女は彼女で「バカバカしい」と言って応じる。この二人の対話には、えもいわれぬ「味わい」(ユーモア)が感じられるのだ。極め付きは、「オタンチン・パレオロガスだよ」という時の丸山の表情、妻女に向かって思い切り「しかめ面」をしてみせる場面は笑いが止まらなかった。原作者・夏目漱石の「余裕派」の風情を、いとも自然に醸し出す。美学者・迷亭を演じた徳川夢声もまた然り、先生の妻女に、蕎麦の食べ方を伝授したり、「月並み」とはどんな意味かを講釈したり、遊び人としての「貫禄」は十分、そこに居るだけで「ホッとする」、魅力的な風格を備えている。金田を演じた森野鍛冶哉の「成金」振り、鼻子・清川玉枝の「高慢」さ、富子・千葉早智子の「わがまま」放題、寒月・北沢彪の「二枚目」、東風・藤原釜足の「三枚目」もどき、車屋夫婦・西村楽天?、清川虹子の「庶民」気質、三平・宇留木浩の「拝金」主義等など、それぞれの役者の個性が、明治時代の世相・人間を曼荼羅模様のように鮮やかに描出している。
この映画の1年前、丸山、徳川、森野、藤原、宇留木は、やはり監督・山本嘉次郎のもとで、夏目漱石原作の「坊ちゃん」を演じていた。主人公・坊ちゃんは宇留木、校長は徳川、赤シャツは森野、山嵐は丸山、うらなりは藤原という配役であった。宇留木は新人としてデビューした第1作であり、1年後には堂々と三平役をこなしている。したがって、この「吾輩ハ猫デアル」は「坊ちゃん」のチームワークを土台として、さらに大きく花開いた名作だともいえるだろう。以後、宇留木は33歳で夭逝、丸山は広島で被爆、44歳で没したという。まことに残念、惜しい人材を失ったと思う。 (2017.5.5)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

映画の主要な登場人物は、先生の他、その妻女(英百合子)、美学者・迷亭(徳川夢声)、先生の教え子で理学士の水島寒月(北沢彪)、観月の友人で詩人の越智東風(藤原釜足)、近所の実業家・金田(森野鍛冶哉)、その妻女・鼻子(清川玉枝)、その娘・富子(千葉早智子)、先生の教え子・多々良三平(宇留木浩)、車夫(西村楽天?)の女房(清川虹子)といった面々である。
話は迷亭が先生宅を訪れ、「寒月君が恋をしているようだ」と言う所から始まる。ある梅見の宴で、寒月と金田富子が出会い、向島の安倍博士邸で行われた演奏会でも、富子のピアノに合わせて寒月はヴァイオリンを弾いた。どうやら恋をしているのは富子の方らしい。梅見の宴には東風も居り、富子に一目惚れ、演奏会でも新体詩を捧げたがケンモホロロ、全く相手にされない。終演後、富子が寒月に「自動車でお送りします」と声をかけるが、寒月は「いえ、ボクは土手を歩いて帰ります」と断った。吾妻橋にさしかかったとき「寒月さーん」と呼ぶ声が聞こえる。その声は川の中から・・・、寒月は意を決して欄干から飛び込んだが、気がつくと橋の真ん中に立っていたそうである。翌日、迷亭が再び、今度は寒月を伴って先生宅を訪れ、寒月から直接そのホラ話を聞いたのだが・・・、その場に、またまた先生の教え子・多々良三平が訪ねてくる。佐賀から上京したとのこと、土産の山芋を持参している。三平曰く「これからの時代は金が物を言う、株で一儲けしようと思うとります。実業家が天下を取るでしょう。先生も学問なんかやめて実業家になりませんか」。応えて先生曰く「わしは金は嫌いだ、儲けたければ勝手に儲ければいいだろう」持参した山芋を見て、「これは何だね」「山芋ですたい。先生もこれを食べて、ひとつ元気になりしゃんしゃい」。
しかし、その山芋を口にすることはできなかった。その日の夜、寝静まった先生宅に泥棒が闖入、着物と一緒に盗まれてしまったからである。泥棒の闖入と同時に、猫の「吾輩」はニャーニャーと鳴きながら、部屋を出て行く。何の役にも立たない猫の景色が、ことのほか絵になっていた。
次の日の朝、先生は盗まれた品々を書き出している。その場の細君とのやりとりは抱腹絶倒、「何だ、お前の恰好は、宿場女郎のようだ」「帯を盗られたんだからしょうがないでしょ」「いくらだ」「6円です」「高すぎる。1円50銭にしておけ」「そんな帯、ありませんよ」「あとは?」「山芋一箱」「いくらだ?」「知りませんよ」「じゃあ12円50銭にしておこう」「そんな高い山芋がありますか、バカバカしい」「だって、お前は今、知らないと、言ったじゃあないか」「知らなくたって、そんな法外な値段がありますか」
「知らんけれども十二円五十銭は法外だとは何だ。まるで論理に合わん。それだから貴様はオタンチン・パレオロガスだと云うんだ」「何ですって」「オタンチン・パレオロガスだよ」「何ですそのオタンチン・パレオロガスって云うのは」「何でもいい。それからあとは――俺の着物は一向いっこう出て来んじゃないか」「あとは何でも宜ようござんす。オタンチン・パレオロガスの意味を聞かしてちょうだい」「意味も何なにもあるもんか」「教えて下すってもいいじゃありませんか、あなたはよっぽど私を馬鹿にしていらっしゃるのね。きっと人が英語を知らないと思って悪口をおっしゃったんだよ。私だってそれくらい知っていますよ」「じゃあ、何だ。言って見ろ」「オタンチンとは頭のこと、パレオロガスとは禿げのことでしょ!」といった、丁々発止の「やりとり」は、月並の夫婦の間では、決して聞くことはできないであろう。
数日後、先生が勤めから帰ると、迷亭が訪れていた。そこにまた、金田富子の母・鼻子が自宅(洋館のある大きな屋敷)から先生宅まで、わずか数十メートルの道を自家用車で乗りつけた。この母親の名前は不詳だが、鼻が異様に高いので先生たちがつけた仇名である。初対面で、先生と迷亭はまずこの鼻に驚いたが、そんなことはおくびにも出さず応対すれば、いきなり「こちらに出入りしている、水島寒月という人は、どんな人物でしょうか」と切り出した。富子の婿として寒月がふさわしい人物か、身元調査に来たのである。理学士として将来有望か、博士号を取れるかなどなどを探りに来たらしい。先生も迷亭も、その高飛車な態度に「鼻持ちならない」と感じている様子がよくわかる。「寒月という人はどんなことを勉強しているのですか」「大学院で、地球の磁気の研究をしています。最近では『首縊りの力学』という論文を書きました」「そんなことでは博士号をとれそうもありませんね」「いや、本人が首をくくらなければ、できないこともないでしょう」「もっとわかりやすいものを勉強していると都合がいいんですがね」「寒月君が作った歌があります。《よべの泊りの十六小女郎、親がないとて、荒磯の千鳥、さよの寝覚の千鳥に泣いた、親は船乗り 波の底》というのはどうでしょう」「アラすてき!しゃみ(三味線)に乗りますわね」。鼻子は寒月の「人となり」を感じ取ったか、「それではこれで失礼いたします。私が来たことは寒月さんには御内密に・・・」と言って帰って言ったのだが・・・。見送った先生と迷亭の笑いが止まらない。「なんだ、あの鼻は!」「あの鼻は猫背だよ」「あれは19世紀に売れ残って20世紀に店ざらしといった顔だ」と言いたい放題、しかし、その様子を隣の車屋夫婦に見られてしまった。この夫婦、鼻子から言いつけられて先生宅(寒月の動静)を日頃から監視しているのである。
かくて、その情報はすぐさま金田家に伝えられる。金田家の事業は証券取引、従業員が忙しく立ち働く中に多々良三平の姿もあった。先生の友人の紹介で金田家に就職したらしい。
やがて、金田から先生宅への「いやがらせ」が始まる。先生宅の隣は金田が出資した学生寮、寄宿生たちが「まっくろけ節」を唄って大騒ぎ、野球のボールを投げ込んでは、先生の仕事の邪魔をする始末、とうとう先生は「神経衰弱」(ノイローゼ)で寝込んでしまった。見舞いに来た迷亭と話し込んでいる時、玄関に刑事が訪れた。先日の泥棒を捕まえたので同行・報告に来たという。あわてて先生、「ごくろうさまです」と泥棒の方に挨拶をしてしまった。迷亭に指摘され、「でも、あっちの方が偉そうだったぞ、袋手なんかしていたもの」「あれは手錠を隠していただけだ」「なんだ、そうか」「そんなに暢気なら、神経衰弱も大したことはないな」。
一方、金田富子は越智東風が舞台監督を務める芝居のヒロインに出演することに・・・、寒月に招待状を出したのだが、彼は用事があって故郷に帰ったという。富子は拍子抜け、さんざんに駄々をこねて、「舞台には出ない」という。6時開演だというのに、30分超過しても幕が上げられない。その最中、多々良三平が観客席の金田のもとに飛んで来た。(世界)情勢の変化で、株が暴落したという。見る見る顔面蒼白となった金田は、急いで帰宅。芝居の公演もメチャクチャになってしまった。そのことを報告に先生宅を訪れる東風、迷亭も同席している。3人でビールでも飲んでいたか、先生に抱かれていた猫の「吾輩」もその「おこぼれ」を舐めだした。そこにやって来たのが寒月、玄関先に直立している。よく見ると、隣には妙齢の女性が・・・、「実は、故郷に帰って嫁をもらって来ました。御紹介します、これが愚妻です」「そうか、そうだったのか」、一同は「これはめでたい」と寿ぐ空気に包まれたが、「大変!猫が井戸に落ちました」という声が鳴り響く。先生も迷亭もあわてて井戸の中を覗き込むが、時すでに遅し、猫はあえなく溺死してしまった。ビールを舐めたことが災いになったのだろう。
先生は猫を供養し墓を建てた。墓標には「この下に稲妻起る宵あらん」と墨書されている。そこに多々良三平がやって来た。「金田家は株の暴落で潰れました。私も一文無し、また一から出直します。金田からどうしても富子を嫁に貰って欲しいと頼まれたので貰ってやることにしました。ハハハハハ」「そうか、それもまた、いいだろう」「先生、あれは何ですか」「猫の墓だよ」「あの猫は死んだんですか、惜しいことをしましたなあ、うまそうな猫だったのに」、先生の細君は呆れて「まあ、いやだ、三平さん、猫食べるの?」などと言ううちに、この傑作は「終」となった。
それにしても、昔の役者には「風格」があった。その筆頭が苦沙弥先生を演じた丸山定夫、表向きは学問を極めようとする素振りを見せながら、その実は昼寝をしたり、「鼻毛にも白髪がある」と感心したり、絵を描いたり、要するに「遊んで」暮らしている。妻女役の英百合子に向かって「馬鹿野郎」と言うことが日課になっている。それに対して英百合子も負けてはいない。彼女は彼女で「バカバカしい」と言って応じる。この二人の対話には、えもいわれぬ「味わい」(ユーモア)が感じられるのだ。極め付きは、「オタンチン・パレオロガスだよ」という時の丸山の表情、妻女に向かって思い切り「しかめ面」をしてみせる場面は笑いが止まらなかった。原作者・夏目漱石の「余裕派」の風情を、いとも自然に醸し出す。美学者・迷亭を演じた徳川夢声もまた然り、先生の妻女に、蕎麦の食べ方を伝授したり、「月並み」とはどんな意味かを講釈したり、遊び人としての「貫禄」は十分、そこに居るだけで「ホッとする」、魅力的な風格を備えている。金田を演じた森野鍛冶哉の「成金」振り、鼻子・清川玉枝の「高慢」さ、富子・千葉早智子の「わがまま」放題、寒月・北沢彪の「二枚目」、東風・藤原釜足の「三枚目」もどき、車屋夫婦・西村楽天?、清川虹子の「庶民」気質、三平・宇留木浩の「拝金」主義等など、それぞれの役者の個性が、明治時代の世相・人間を曼荼羅模様のように鮮やかに描出している。
この映画の1年前、丸山、徳川、森野、藤原、宇留木は、やはり監督・山本嘉次郎のもとで、夏目漱石原作の「坊ちゃん」を演じていた。主人公・坊ちゃんは宇留木、校長は徳川、赤シャツは森野、山嵐は丸山、うらなりは藤原という配役であった。宇留木は新人としてデビューした第1作であり、1年後には堂々と三平役をこなしている。したがって、この「吾輩ハ猫デアル」は「坊ちゃん」のチームワークを土台として、さらに大きく花開いた名作だともいえるだろう。以後、宇留木は33歳で夭逝、丸山は広島で被爆、44歳で没したという。まことに残念、惜しい人材を失ったと思う。 (2017.5.5)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-13
付録・邦画傑作選・「浮草」(監督・小津安二郎・1959年)
ユーチューブで映画「浮草」(監督・小津安二郎・1959年)を観た。私はこの映画の原点である「浮草物語」(監督・小津安二郎・1934年)について、以下のように綴った。
〈小津監督は、戦後(1959年)「浮草」というタイトルでリメイクしている。喜八は嵐駒十郞(中村 鴈治郎)、おたかはすみ子(京マチ子)、かあやんはお芳(杉村春子)、信吉は清(川口浩)、おときは加代(若尾文子)と役名・俳優を変え、三井秀男も、三井弘次と改名し、今度は一座の座員役で登場している。もちろんトーキー、カラー映画の豪華版になったが、その出来映えや如何に、やはり戦前は戦前、戦後は戦後、その違いがくっきりと現れて、甲乙はつけがたい。二つの作品に出演している三井弘次ならば何と答えるだろうか・・・。〉
物語の舞台を信州の田舎から、三重県の海辺に変え、時代も戦前から戦後に移ったが、あらすじはほとんど変わらないので割愛する。
「浮草物語」同様に、この「浮草」も見どころ満載の名品であった。まず第一は、嵐駒十郞(中村鴈治郎)の風情である。旅回り一座の親方としての貫禄は十分、十年ぶりにやって来た海辺の町で、かつての情婦・お芳(杉村春子)と再会、一子・清(川口浩)の成長ぶりに目を細める。お芳は清を育て上げ一膳飯屋を細々と営んでいる。「御苦労やったな」と感謝する駒十郞の思いを受けとめつつ、駒十郞の舞台を惚れ惚れと見つめているお芳の姿も絶品であった。さればこそ、今の女房・すみ子(京マチ子)の気持ちは収まらないのである。「なんや、コソコソと・・・、あたしに隠れて」と迫るが、駒十郞も金箔付の遊び人「ゴチャゴチャ言うな!わいが、倅に会ってどこが悪い。もうお前との縁もこれっきりや」と渡り合う雨中のバトルは壮絶だったが、どこか哀愁も漂い、まさに「浮草」人生の極め付きであった。中村鴈治郎、杉村春子、京マチ子といった大スターが丁々発止と繰り広げる、三つ巴の愛憎劇が一番の見どころである。
二番目は、初々しい加代(若尾文子)と清の「色模様」であろうか。どこまでも清々しく溌剌とした清を、初めは金銭ずくで誘惑する加代、次第に自分の「汚れ」を思い知り、身を引こうとするのだが、清の純真さに抗えない。大詰めでは、駒十郞に打擲されながらも、「親方!、あたしも一緒に連れて行ってください」という一言で、彼女の汚れは清められたのである。駒十郞は「可愛いこと言うやんか、しばらく面倒みてやってんか」とお芳に頼んで去って行く。かくて清と加代は結ばれ、お芳と三人で幸せな暮らしを始めるのだろう。
三番目は、一人っきりになってしまった者同士の邂逅であろうか。駒十郞とすみ子は誰もいない駅舎で再会する。初めは目も会わさず、駒十郞はタバコを吸おうとマッチを探す。すみ子が近づいてマッチを擦るが、駒十郞は横を向いて応じない。しかし、すみ子はあきらめない。もう一本擦って、駒十郞の鼻先に差し出す。やむなく駒十郞はその火をもらって、大きく煙を吐く。ややあって「親方、これからどこへ?」「・・・・」「あたしは迷っていますねん」「・・・・」「ねえ、親方、教えてえな」「・・・、桑名でも行こうか。あそこの旦那に頼もうか・・・」「まあ、桑名!あたし、あそこの旦那とは懇意ですねん」すみ子の表情に光りがさした。「乗るかそるかや。もういっぺん、やり直すか」「やりまひょ、やりまひょ」。すみ子は窓口に飛んで行き「桑名、二枚!」と切符を求める。やがて二人は車中の人、仲良く酒を酌み交わす。この絶妙の呼吸は、たまらなく魅力的、「浮草」暮らしが、性懲りもなく再開するのである。
四番目は、座員・吉之助(三井弘次)の「役者ぶり」である。同輩の矢太蔵(田中春男)と仙太郎(潮万太郎)が、先行きの見通しが立たない一座の空気を読んで「ドロン」の相談を始めると「オレはイヤだね。それで、これまでお世話になった親方に義理が立つと思うのか」と正論を吐きながら、気がついた時には親方の蟇口、文芸部のカメラ、座員の金などを掠めて雲隠れ・・・。その一芝居(手際)はお見事、それにしても三井弘次は「浮草物語」の信吉役(清役に同じ)、変われば変わるもの、その豹変振りには舌を巻いてしまった。
最後は、町の床屋・小川軒の景色、看板娘のあい子(野添ひとみ)に弥太蔵は一目惚れ、「髭を当たってもらおうか」と迫ると、出てきたのは母(高橋とよ)、弥太蔵を一睨みして「座れ!」と手で合図する。弥太蔵は「まだ、そんなに伸びてないな」と尻込みしたが、お構いなく問答無用の態で、再度「座れ!」と強要する場面は抱腹絶倒、私の笑いはとまらなかった。かくて弥太蔵のホッペタには、大きな絆創膏が貼られる羽目になってしまったのである。
さらに加えれば、すみ子が演じる劇中劇「国定忠治」の名場面、「オレには生涯てめえという強い味方があったのだ」という雄姿は、女っぽく仇っぽく、油の乗りきった京マチ子ならではの迫力があった。その、めったに見られない舞台姿を拝見できたことも望外の幸せであった。
「浮草」は「浮草物語」から25年、時代、舞台を変えて見事に蘇った。一座の謳い文句(テーマ・ミュージック)は当時(1959年)はやりの「南国土佐を後にして」、そのメロディーが随所に流れて、面々の浮草稼業をひときわ鮮やかに彩っていた。それから、さらに58年、まさに「昭和は遠くなりにけり」といった今日、この頃ではある。
(2017.7.5)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

〈小津監督は、戦後(1959年)「浮草」というタイトルでリメイクしている。喜八は嵐駒十郞(中村 鴈治郎)、おたかはすみ子(京マチ子)、かあやんはお芳(杉村春子)、信吉は清(川口浩)、おときは加代(若尾文子)と役名・俳優を変え、三井秀男も、三井弘次と改名し、今度は一座の座員役で登場している。もちろんトーキー、カラー映画の豪華版になったが、その出来映えや如何に、やはり戦前は戦前、戦後は戦後、その違いがくっきりと現れて、甲乙はつけがたい。二つの作品に出演している三井弘次ならば何と答えるだろうか・・・。〉
物語の舞台を信州の田舎から、三重県の海辺に変え、時代も戦前から戦後に移ったが、あらすじはほとんど変わらないので割愛する。
「浮草物語」同様に、この「浮草」も見どころ満載の名品であった。まず第一は、嵐駒十郞(中村鴈治郎)の風情である。旅回り一座の親方としての貫禄は十分、十年ぶりにやって来た海辺の町で、かつての情婦・お芳(杉村春子)と再会、一子・清(川口浩)の成長ぶりに目を細める。お芳は清を育て上げ一膳飯屋を細々と営んでいる。「御苦労やったな」と感謝する駒十郞の思いを受けとめつつ、駒十郞の舞台を惚れ惚れと見つめているお芳の姿も絶品であった。さればこそ、今の女房・すみ子(京マチ子)の気持ちは収まらないのである。「なんや、コソコソと・・・、あたしに隠れて」と迫るが、駒十郞も金箔付の遊び人「ゴチャゴチャ言うな!わいが、倅に会ってどこが悪い。もうお前との縁もこれっきりや」と渡り合う雨中のバトルは壮絶だったが、どこか哀愁も漂い、まさに「浮草」人生の極め付きであった。中村鴈治郎、杉村春子、京マチ子といった大スターが丁々発止と繰り広げる、三つ巴の愛憎劇が一番の見どころである。
二番目は、初々しい加代(若尾文子)と清の「色模様」であろうか。どこまでも清々しく溌剌とした清を、初めは金銭ずくで誘惑する加代、次第に自分の「汚れ」を思い知り、身を引こうとするのだが、清の純真さに抗えない。大詰めでは、駒十郞に打擲されながらも、「親方!、あたしも一緒に連れて行ってください」という一言で、彼女の汚れは清められたのである。駒十郞は「可愛いこと言うやんか、しばらく面倒みてやってんか」とお芳に頼んで去って行く。かくて清と加代は結ばれ、お芳と三人で幸せな暮らしを始めるのだろう。
三番目は、一人っきりになってしまった者同士の邂逅であろうか。駒十郞とすみ子は誰もいない駅舎で再会する。初めは目も会わさず、駒十郞はタバコを吸おうとマッチを探す。すみ子が近づいてマッチを擦るが、駒十郞は横を向いて応じない。しかし、すみ子はあきらめない。もう一本擦って、駒十郞の鼻先に差し出す。やむなく駒十郞はその火をもらって、大きく煙を吐く。ややあって「親方、これからどこへ?」「・・・・」「あたしは迷っていますねん」「・・・・」「ねえ、親方、教えてえな」「・・・、桑名でも行こうか。あそこの旦那に頼もうか・・・」「まあ、桑名!あたし、あそこの旦那とは懇意ですねん」すみ子の表情に光りがさした。「乗るかそるかや。もういっぺん、やり直すか」「やりまひょ、やりまひょ」。すみ子は窓口に飛んで行き「桑名、二枚!」と切符を求める。やがて二人は車中の人、仲良く酒を酌み交わす。この絶妙の呼吸は、たまらなく魅力的、「浮草」暮らしが、性懲りもなく再開するのである。
四番目は、座員・吉之助(三井弘次)の「役者ぶり」である。同輩の矢太蔵(田中春男)と仙太郎(潮万太郎)が、先行きの見通しが立たない一座の空気を読んで「ドロン」の相談を始めると「オレはイヤだね。それで、これまでお世話になった親方に義理が立つと思うのか」と正論を吐きながら、気がついた時には親方の蟇口、文芸部のカメラ、座員の金などを掠めて雲隠れ・・・。その一芝居(手際)はお見事、それにしても三井弘次は「浮草物語」の信吉役(清役に同じ)、変われば変わるもの、その豹変振りには舌を巻いてしまった。
最後は、町の床屋・小川軒の景色、看板娘のあい子(野添ひとみ)に弥太蔵は一目惚れ、「髭を当たってもらおうか」と迫ると、出てきたのは母(高橋とよ)、弥太蔵を一睨みして「座れ!」と手で合図する。弥太蔵は「まだ、そんなに伸びてないな」と尻込みしたが、お構いなく問答無用の態で、再度「座れ!」と強要する場面は抱腹絶倒、私の笑いはとまらなかった。かくて弥太蔵のホッペタには、大きな絆創膏が貼られる羽目になってしまったのである。
さらに加えれば、すみ子が演じる劇中劇「国定忠治」の名場面、「オレには生涯てめえという強い味方があったのだ」という雄姿は、女っぽく仇っぽく、油の乗りきった京マチ子ならではの迫力があった。その、めったに見られない舞台姿を拝見できたことも望外の幸せであった。
「浮草」は「浮草物語」から25年、時代、舞台を変えて見事に蘇った。一座の謳い文句(テーマ・ミュージック)は当時(1959年)はやりの「南国土佐を後にして」、そのメロディーが随所に流れて、面々の浮草稼業をひときわ鮮やかに彩っていた。それから、さらに58年、まさに「昭和は遠くなりにけり」といった今日、この頃ではある。
(2017.7.5)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-12
付録・邦画傑作選・「雄呂血」(監督・二川文太郎・1925年)
ユーチューブで映画「雄呂血」(監督・二川文太郎・1925年)を観た。阪東妻三郎プロダクション第1回作品で、大正末期、日本に「剣戟ブーム」をもたらした記念碑的作品と言われている。あらすじは以下の通りである。(「ウィキペディア百科事典」より引用)
〈漢学者松澄永山の娘・奈美江と、その弟子で正義感の強い若侍・久利富平三郎はひそかに愛し合っていた。平三郎は師の誕生祝いの夜、同門の家老の息子の浪岡の無礼を怒り、腕力沙汰に及んだことから蟄居を命じられる。また奈美江を中傷誹謗していた家中の若侍を懲らしめたことが逆に永山の誤解を招き、師からも破門され、石もて追われるように故郷を捨て、旅に出る平三郎。平三郎は自分が正しいと信じてやったことが事毎に周りから曲解され、そのこころは次第に荒んでいき、無頼の浪人となり下がり、虚無の深淵に沈んでいく。たまたまある町の料亭で働く千代を知り、女の情を求めて牢を破って訪ねたもののすでに千代は人の妻となっていた。捕吏に追われた平三郎は侠客・次郎三のもとへ飛び込むが、この侠客が喰わせ者。病に難渋する旅の夫婦を助けたは良いがその妻に言い寄り手篭めにしようとする。しかもその妻女こそ、かつての恩師の娘、初恋の人の奈美江であった。平三郎の白刃一閃、見事次郎三を斬り捨てるがもはや脱出かなわず、十重二十重の重囲のなかに堕ち、乱闘又乱闘の大立ち回りの末、ついに力尽き捕えられ、群衆の悪罵を浴び引かれていく。その中に涙に濡れ、平三郎を伏し拝む奈美江夫婦の姿があったことを、群衆の誰一人知る者はいなかった。〉
この映画の眼目は「善と悪」、一見善人と見られていてもその根底に悪が潜んでいることもあり、無頼漢と思われている者の中に善行が秘められていることがある、つねに世の中はそうした矛盾を孕んでいることに気づかなければならない、といったあたりを、やや生硬な字幕が物語る。大正デモクラシーの影響も感じられて、たいそう興味深かった。 配役は無頼漢・久利富平三郎に阪東妻三郎、恩師・松澄永山に関操、その娘・奈美江に環歌子、家老の息子・浪岡真八郎に山村桃太郎、侠客・赤城二郎三に中村吉松、掏摸・二十日鼠の幸吉に中村琴之助、町の娘・お千代に森静子といった面々だが、阪東妻三郎を除いて私の知る俳優は皆無であった。見どころは、ほんの些細な出来事がきっかけで、純真・闊達・剛健の若侍が無頼漢へと落ち込んで行くプロセスである。「よかれ」と思う言動が、ことごとく裏目に出てしまう。「とかくこの世はままならず」「渡る世間は鬼ばかり」といった現代にも通じる人間模様を、そのやるせない風情によって阪東妻三郎は見事に描出していた、と私は思う。平三郎は何一つ悪事(殺人)をしていない、そのことを知っているのは観客だけである。しかし大詰めでは、堪忍袋の緒が切れた。最愛の人を陵辱しようとする「善人」・二郎三を成敗、百人近い捕り手を相手に斬って斬って斬りまくる。誰が見ても無頼漢、悪逆非道の振る舞いだが、最愛の人だけは手を合わせて見守る。力尽き牽かれて行く平三郎を泣き崩れるて見送る奈美江の姿がことのほか「絵」になっていた。
映画はサイレントだが(弁士の説明があるにしても)、私にはその「場」の音が聞こえる。邦画史上に残る一級品の名作であった。
(2017.1.16)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

〈漢学者松澄永山の娘・奈美江と、その弟子で正義感の強い若侍・久利富平三郎はひそかに愛し合っていた。平三郎は師の誕生祝いの夜、同門の家老の息子の浪岡の無礼を怒り、腕力沙汰に及んだことから蟄居を命じられる。また奈美江を中傷誹謗していた家中の若侍を懲らしめたことが逆に永山の誤解を招き、師からも破門され、石もて追われるように故郷を捨て、旅に出る平三郎。平三郎は自分が正しいと信じてやったことが事毎に周りから曲解され、そのこころは次第に荒んでいき、無頼の浪人となり下がり、虚無の深淵に沈んでいく。たまたまある町の料亭で働く千代を知り、女の情を求めて牢を破って訪ねたもののすでに千代は人の妻となっていた。捕吏に追われた平三郎は侠客・次郎三のもとへ飛び込むが、この侠客が喰わせ者。病に難渋する旅の夫婦を助けたは良いがその妻に言い寄り手篭めにしようとする。しかもその妻女こそ、かつての恩師の娘、初恋の人の奈美江であった。平三郎の白刃一閃、見事次郎三を斬り捨てるがもはや脱出かなわず、十重二十重の重囲のなかに堕ち、乱闘又乱闘の大立ち回りの末、ついに力尽き捕えられ、群衆の悪罵を浴び引かれていく。その中に涙に濡れ、平三郎を伏し拝む奈美江夫婦の姿があったことを、群衆の誰一人知る者はいなかった。〉
この映画の眼目は「善と悪」、一見善人と見られていてもその根底に悪が潜んでいることもあり、無頼漢と思われている者の中に善行が秘められていることがある、つねに世の中はそうした矛盾を孕んでいることに気づかなければならない、といったあたりを、やや生硬な字幕が物語る。大正デモクラシーの影響も感じられて、たいそう興味深かった。 配役は無頼漢・久利富平三郎に阪東妻三郎、恩師・松澄永山に関操、その娘・奈美江に環歌子、家老の息子・浪岡真八郎に山村桃太郎、侠客・赤城二郎三に中村吉松、掏摸・二十日鼠の幸吉に中村琴之助、町の娘・お千代に森静子といった面々だが、阪東妻三郎を除いて私の知る俳優は皆無であった。見どころは、ほんの些細な出来事がきっかけで、純真・闊達・剛健の若侍が無頼漢へと落ち込んで行くプロセスである。「よかれ」と思う言動が、ことごとく裏目に出てしまう。「とかくこの世はままならず」「渡る世間は鬼ばかり」といった現代にも通じる人間模様を、そのやるせない風情によって阪東妻三郎は見事に描出していた、と私は思う。平三郎は何一つ悪事(殺人)をしていない、そのことを知っているのは観客だけである。しかし大詰めでは、堪忍袋の緒が切れた。最愛の人を陵辱しようとする「善人」・二郎三を成敗、百人近い捕り手を相手に斬って斬って斬りまくる。誰が見ても無頼漢、悪逆非道の振る舞いだが、最愛の人だけは手を合わせて見守る。力尽き牽かれて行く平三郎を泣き崩れるて見送る奈美江の姿がことのほか「絵」になっていた。
映画はサイレントだが(弁士の説明があるにしても)、私にはその「場」の音が聞こえる。邦画史上に残る一級品の名作であった。
(2017.1.16)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-11
付録・邦画傑作選・「東京の女」(監督・小津安二郎・1933年)
二組の男女(同胞)が登場する。その一は姉・ちか子(岡田嘉子)と弟・良一(江川宇礼雄)、その二は兄(奈良真養)と妹・春江(田中絹代)である。姉はタイピスト、夜は大学教授の下で翻訳補助を行い、大学に通う弟の学資を稼いでいる。兄は警察官、妹は良一の恋人である。二組の男女はそれぞれ慎ましく暮らし、やがては良一の卒業、良一と春江の結婚も間近と思われていたのだが・・・。ある日、姉の会社に警察官が訪れ、人事課長に姉の勤務状況、退勤後の様子などを訊ねた。実を言えば、姉の翻訳補助は真っ赤な嘘で、夜は「いかがわしい」仕事をしているという情報が警察に入った。その噂を耳にした兄が、ちか子に確かめようとするが、春江は「私の方が、ちか子さんも話しやすいでしょう」とちか子宅に赴いた。ちか子はまだ帰宅していない。良一ひとりが待っている。春江はとまどい躊躇・・・、しかし良一に急かされて噂の真相を打ち明けてしまった。驚く良一、「そんな話は聞きたくもない。帰ってくれ!」と春江を追い出した。深夜、ちか子が帰宅する。沈み込んでいる良一の様子を見て、ちか子が訝れば「姉さん、今までどこで何をしていたんだ!」と問い質す。一瞬、ちか子は言葉に詰まったが「私が何をしていようと、あなたは勉強だけしていればいいのよ。お姉さんを信じてちょうだい。あなたが卒業することだけを楽しみにしているのだから・・・」。良一は「信じていたから恨めしいんだ。何だってそんな所に出入りしていたんだ。馬鹿だよ。何だってそんな道を選んだんだ」と言うや否や、ちか子を執拗に平手打ち、そのままぷいと家を飛び出してしまった。
翌日、春江宅を訊ねるちか子、昨日の様子を春江が話し始めると「電話だよ」という使いがやって来た。電話は兄からであった。「・・・良ちゃんが自殺した・・・」驚愕する春江、ちか子の元で泣き崩れる。
やがて、ちか子の家。入り口で新聞記者たち(笠智衆、大山健二、?)が取材している。「自殺の原因で思いあたることは?」「何もありません」とちか子は首を振る。奥では良一の亡骸を呆然と見つめる春江、記者の一人が近づいて「あなたとこの方との関係は?」「・・・・」、仲間が「オイ、これでは特ダネになりそうもないぜ」、記者たちは退去して行った。ちか子と春江は二人きり、見つめ合う顔には大粒の涙が流れ落ちる。「良ちゃんは最後まで姉さんのことをわかってくれなかったわね。これしきりのことで死ぬなんて・・・・弱虫!」というちか子の言葉が聞こえた。泣き崩れる春江、ちか子は一点を見つめ、何事か決意する。
大詰めは、道を笑いながら歩く記者二人、電柱に貼られた号外「東京日日新聞」の記事に見入る。タイトルは「某○○事件の一味逮捕」と記されていた。それを指差して一人の記者(大山健二?)いわく「この記事じゃあ君の社に十四五分出し抜かれたなあ」、微笑みながら無言でうなずくもう一人(笠智衆)、その二人が遠ざかりビルの中に消えると、この映画は「終」となった。
なるほど、ちか子宅に取材に来ていた記者連中の目的はスクープ、良一の自殺が「某○○事件」のようなニュース・バリューがあるかどうか探りに来ていたのだ。しかしその目的はちか子の決意によってはねのけられた。さもありなん、ちか子は良一のように「弱くはなかった」からである。ちか子が選んだ道は、良一の学資援助のみならず「非合法活動」の支援だったことを窺わせるエンディングであった。受け止め方、解釈は様々だが、(その曖昧さの中に)小津監督の(当時の秘められた)反骨精神が滲み出ている、画期的な名作だと、私は確信するのである。
(2017.2.28)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

翌日、春江宅を訊ねるちか子、昨日の様子を春江が話し始めると「電話だよ」という使いがやって来た。電話は兄からであった。「・・・良ちゃんが自殺した・・・」驚愕する春江、ちか子の元で泣き崩れる。
やがて、ちか子の家。入り口で新聞記者たち(笠智衆、大山健二、?)が取材している。「自殺の原因で思いあたることは?」「何もありません」とちか子は首を振る。奥では良一の亡骸を呆然と見つめる春江、記者の一人が近づいて「あなたとこの方との関係は?」「・・・・」、仲間が「オイ、これでは特ダネになりそうもないぜ」、記者たちは退去して行った。ちか子と春江は二人きり、見つめ合う顔には大粒の涙が流れ落ちる。「良ちゃんは最後まで姉さんのことをわかってくれなかったわね。これしきりのことで死ぬなんて・・・・弱虫!」というちか子の言葉が聞こえた。泣き崩れる春江、ちか子は一点を見つめ、何事か決意する。
大詰めは、道を笑いながら歩く記者二人、電柱に貼られた号外「東京日日新聞」の記事に見入る。タイトルは「某○○事件の一味逮捕」と記されていた。それを指差して一人の記者(大山健二?)いわく「この記事じゃあ君の社に十四五分出し抜かれたなあ」、微笑みながら無言でうなずくもう一人(笠智衆)、その二人が遠ざかりビルの中に消えると、この映画は「終」となった。
なるほど、ちか子宅に取材に来ていた記者連中の目的はスクープ、良一の自殺が「某○○事件」のようなニュース・バリューがあるかどうか探りに来ていたのだ。しかしその目的はちか子の決意によってはねのけられた。さもありなん、ちか子は良一のように「弱くはなかった」からである。ちか子が選んだ道は、良一の学資援助のみならず「非合法活動」の支援だったことを窺わせるエンディングであった。受け止め方、解釈は様々だが、(その曖昧さの中に)小津監督の(当時の秘められた)反骨精神が滲み出ている、画期的な名作だと、私は確信するのである。
(2017.2.28)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-10
付録・邦画傑作選・《「泥だらけの純情」(日活・監督中平康・昭和38年)》
出会ってから、わずか七回の「逢瀬」で、見事な「情死」を果たした男女がいる。
日活映画「泥だらけの純情」(原作・藤原審爾 脚本・馬場当 監督・中平康 昭和38年)に登場した、次郎(浜田光夫)と真美(吉永小百合)である。
物語の梗概は以下のとおりである。
◆組長・塚田に頼まれてヤクを森原組の事務所に届けていたチンピラヤクザの次郎は、不良学生にからまれている外交官の令嬢・樺島真美を助ける。しかし、その乱闘の最中、相手があやまって自分の持っていたナイフで死んでしまったことにより、殺人の疑いをかけられる羽目に陥ってしまう。現場に落ちていたヤクからガサ入れを食らうことを恐れた兄貴分の花井は、彼に自首をすすめる。新聞を見て驚いた真美は、刑事にことの真相を話し、次郎は釈放される。そのことをきっかけに、二人はデートを重ねる仲となっていくが、その資金を捻出するために次郎は、悪事を繰り返していく。逮捕されても簡単な尋問だけで釈放される次郎に、疑いを抱く塚田。実は警察は例のヤクに目をつけ、大規模なガサ入れを狙い、彼を泳がせていたのだ。塚田から自首をすすめられる次郎。一方真美は父の仕事で外国へ行くことに。追い詰められた二人は、自分たちだけの世界を求め、雪山へと逃れるのだった。◆(ビデオ「にっかつ名画館・泥だらけの純情」解説パンフレットから引用)
次郎と真美の「逢瀬」はわずか七回、しかも「デートの楽しさ」を味わえたのは、そのうちのたった一回ではなかったか。
殺人の容疑が晴れたあと、真美の母から次郎に現金の「謝礼」が届く。しかし、次郎の気は済まない。真美を助けたのは、「銭のためではない」からである。次郎は、真美の「澄んだ瞳」が不良学生に汚されないために、助けたのだ。だから、もし謝礼の気持ちがあるのなら、直接、真美が次郎に会って「ありがとう」とお礼を言えば、それで気が済むのである。親分、兄貴から無理矢理「謝礼」を受け取らされた次郎の気持ちはおさまらず、真美の学校や自宅にまで、弟分と押しかけた。しかし、玄関のベルを押す勇気はなかった。
【逢瀬・一】
ところがである。翌日、突然、真美が次郎の安アパートを訪れた。次郎は、仰天して真美を出迎える。
「友だちに言われてきたのか?」
「自分でよく考えてきました」
「こんなところは、お嬢さんの来るところじゃないんだ。送っていくから帰れよ」
「はい」
玄関口で立ち話をしている二人に、アパートの住人たちは、興味津々で声をかけた。
「ジロちゃん、かわいい子だねえ。あんたのスケかい?」
「うるせえ!」
「照れることないじゃないか」
と、冷やかされながら、二人は駅に向かった。
次郎は、思ったに違いない。
(お嬢さん、わかった。もういい。オレは、昨日、お嬢さんの学校や自宅まで「引っかけるつもりで」会いに行ったけど、何もできなかった。しかも弟分まで連れて・・・。それに比べて、お嬢さんは、自分でよく考え、一人で来てくれた。もういい。お嬢さんの気持ちはよくわかった。ありがとう)
次郎は、真美の切符を買い、渋谷駅の構内で「別れの言葉」を言った。
「いいかい。今度あんな目にあったら、大声をあげなよ。黙っていてはどうにもならないんだ、じゃあ!」
それで終われば、よかったのかもしれない。しかし、次郎の気持ちに「変化」が生じた。(まだ、時間がある。せっかく会いに来てくれたお嬢さんを楽しませたい。いや、できれば、自分が楽しみたい。もしかしたら「引っかかる」かもしれない・・・)
次郎は、戻りかけた道を引き返し、真美の乗った電車を探す。
「お嬢さん!」と呼んでみると、真美が電車のドアから顔を出した。次郎は、間一髪でその電車に、飛び乗ることができた。
二人は、ボクシングを観戦し、帰途につく。途中で、話し合いながら、自分たちの生活が「全く違う」ことに惹かれ合う。ジュースを飲みながら「動物の生態」という教養番組を視聴、バイブルを読んで就寝するという真美。ウイスキーをラッパ飲みしてスポーツ雑誌を読みふけるという次郎・・・。しかし、次郎は、(これで本当に終わりにしよう)と思っていた。ホームの売店でピーナッツを買い、真美にプレゼントする。
「半分ずつしようか」といい、真美の手袋にピーナッツを注ぎこんだ。ベルが鳴り、電車のドアが閉まりかけたそのとき、真美が「殺し文句」を吐いたのだ。
「さっきのママへの電話(注・母に門限を延ばしてもらった電話)、『いちばん好きなお友だちと遊んでいます』って!」
この一言で、次郎は、真美を「忘れること」ができなくなってしまったのだと思う。
(もしかしたら、お嬢さんはオレを必要としているのかもしれない!)
思えば、この時の「逢瀬」こそが、「未来を展望し」、「自分たちだけの世界」を共有できた、至福の「ひととき」ではなっかたか。
次郎は、居酒屋に飛び込むと、客が楽しんでいたテレビの娯楽番組のチャンネルを、「動物の生態」に切り替える。「何するんだ!」という客の抗議を「ひとにらみ」ではね除け、平然とジュースを飲みながら皇帝ペンギンの映像を見つめる。アパートのベットに入り、「聖書」を拾い読みしながら眠りにつく。
真美は、真美で、オールドパーをラッパ飲みしながら、ボクシング雑誌に目を通し、挙げ句の果てには、姿見の前でシャドーボクシングまで始める始末であった。
【逢瀬・二、三】
以後、真美の誘いで「現代音楽祭」のコンサート、上野公園と二回デートを重ねるが、真美の表情は曇りがちである。
真美は思っていた。
(次郎さんは、チンピラヤクザになって「柄が悪い」ふりをしているけれど、本当は「悪い人」ではない。心の優しい、温かい人なんだ。それは、私自身が一番よく知っている。私と会うたびに、次郎さんはケガをする。初めての時、あの不良学生から私を助けようとして、おなかを刺された。その次の時も、電車のドアに指を挟まれた。この前も、コンサートの帰り、私に嫌がらせをした不良を二人殴り倒してくれたけど、指の爪をはがしてしまった。本当は、そんなに強くない。でも、そんな次郎さんを私は忘れられない。いつも一緒にいたい。どうすればいいのだろう?)
上野公園でのデートは、真美の都合で、すぐに帰らなければならなかった。でも、真美は言った。
「来週の土曜日は、(略)ママをだまして出て参ります。一日中どこへでも行けますわ」
「本当かい?」
「ママに嘘ばっかりついてるの」
「どうしてよ?」
「あなたに嘘つきたくないから・・・」
次郎は、確信した。(お嬢さんは、本気だ! オレはこれからどうすればいいのだろう?)
そして、本当の疑問をぶつけてみた。
「でもよ。あんた、オレと歩いていて恥ずかしくないかい?」
「恥ずかしいって?」
次郎の兄貴分は、恋人から海水浴に誘われたけど、「約束をほっぽっちゃった」という。背中一面に、雷様の刺青をしているからだ。
「海水浴だろ? 引け目感じちゃうよな」
「あなたも、してます? 刺青?」
「オレは、チンピラだからしてねえけどよ」
真美は、必死で次郎に訴えた。(今だ! 次郎さんに、本当の気持ちを言おう!)
「やめられません、ヤクザ! ヤクザっていけないと思うんです! 野蛮だし、法律にだって背いているし! でも、私、次郎さんは、まじめで正しい人だと思っています。どんなこと、なさっていようと・・・」
次郎は、返す言葉がない。「その通り」だからだ。
「土曜日な! 横浜駅で待ってるよ。十二時!」
それだけ言うと、逃げるようにその場を立ち去った。(わかっているよ、そんなこと!好きでヤクザやってるわけじゃない。オレの親父は「バタ屋」だ。オレのお袋は「淫売あがり」だぞ! そんなオレが一人前に生きて行くには、どうすればいいんだ。ヤクザにでもなるほかに道はないではないか! お嬢さん、わかってくれ。今のオレには、こんな自分をどうすることもできないんだ。今度の土曜日、お嬢さんは本当に来てくれるだろうか?)
しかし、土曜日、「約束を守った」のは、真美の方だった。次郎は「ポン引き」の疑いで警察に挙げられていたからである。
上野駅で、真美は半日待った。しかし、次郎は来ない。
真美は、待って、待って、待ち続けた。次郎のことが、いっときも忘れられなかった。何度もアパートに手紙を送ったが、返事は来ない。家族で赤倉にスキーに行っても、思うのは次郎からの返事のことばかり、もし返事が来なければ「死んでしまうかもしれません」とまで、手紙に綴ったが・・・。決心してヤクザの事務所にも行った。親分・兄貴分にも会い、次郎が警察に拘束されていることを知った。それでも、真美はあきらめなかった。次郎のアパートに行って待ち続ける。
どれくらいの日にちが経っただろうか。やがて、次郎は保釈された。組の事務所で挨拶をすませると、親分は「スケ(真美)と別れろ」という。兄貴分は、真美が事務所に訪ねてきたことを告げ、届いた手紙を焼きながら、「たくあんとセロリを食べている人間は、(住んでる世界)が違う」と次郎を諭した。しかし、次郎は迷っていた。(兄貴は、手紙を焼いてしまったけど、なんと書いてあったのだろうか? お嬢さんがオレのカミさんになるはずがない、でも、もしかしたら、オレを必要としてくれるかもしれないではないか)
【逢瀬・四】
憔悴してアパートに戻ると、真っ暗な部屋の中で、真美が待っていた。
驚愕する次郎。「お嬢さん!」と叫んで絶句した。真美は「お会いしたくて、飛んできました。毎日、毎日、このお部屋でお待ちしていたんです」と言う。
次郎がスーツのポケットに手を入れると、あのときのピーナッツが出てきた。それを二人で食べながら、真美が言った。
「次郎さん、あたし、もういやなんです。あなたが警察なんかに入れられてしまうの」 次郎も、答えた。
「やばいことは、もうやめたよ」
真美は、母の知人に頼んで、次郎の「仕事」を探すと言う。次郎は「乗り気」ではなかったが、(もしかしたら、堅い仕事につけるかもしれない)と淡い希望がわいてきた。
「かなわないよ、お嬢さんには」と言って、応じる羽目になってしまった。
【逢瀬・五、六】
次の日曜日、次郎は正装して、真美の自宅を訪れた。弟の「天文台開き」のパーティーに招待されたのである。真美は、その場で、次郎を母の知人に紹介し、次郎の「仕事」を見つけてもらおうと考えた。とりあえず、母に次郎を引き合わせたが、母は「どなたなの?」と訝しがる。真美が、「ほら、この前お願いした、あの新宿の時の・・・」と言いかけたとき、母の表情が変わった。真美を、物陰に呼んで叱責する。
「なんてことなさるの! あんな人、私が板東様に御紹介できると思っているの?私たちのおつきあいできる方じゃありません。家へくるのなんか遠慮していただかなくっちゃ!」
その様子を窺っていた次郎は、全てを察知し、上着を翻して、乱暴に立ち去る。「次郎さん!」と呼び止めようとする真美は、振り返りざま母をののしった。
「ママ! ママは真美の敵よ!」
真美は、心の底からそう思ったに違いない。あっけにとられているパーティーの参加者をしりめに、真美は次郎の後を追う。
どこをどう探したか、真美が次郎を見つけた時は、もう夜になっていた。盛り場のダンスホールで女と酔いしれる次郎、真美は弟分に取り次ぎ頼む。しかし、次郎は、もう、真美とかかわるつもりはない。真美を、にらみつけて、冷たく言った。
「何しに来たんだ!」
「おわびに参りました」
「帰れよ!」
「今度こそきっと、いいお仕事探してきますから・・・」
「よしてくれ! あんたは、これ以上オレに恥じかかせる気かい!」
「次郎さん・・・」
「ほっといてくれってんだよう!」
その場を立ち去ろうとする次郎の腕をつかんで、真美は叫んだ。
「好きなんです! あなたが好きなんです!」
次郎は、真美の必死な告白を、確かに耳にして、混乱し、逡巡した。
「好きだって? このオレを? そんなこと言わないでくれ! 好きだなんて、そんな・・・」
(どうしていいかわからない! しかし、そんなことはあり得ない。あっては、いけないことなんだ!)
「お嬢さんは、オレを知らないんだよ、オレは、町のダニだい! チンピラヤクザのご正体知らないから・・・。な、けえんな!」
しかし、真美は次郎の目を見つめたまま、動かない。
次郎は仕方なく、その場に居合わせた女を「凌辱」して見せた。泣きながら逃げ出した真美の背中にに向かって、「オレの親父は『バタ屋』だぞ! お袋は『淫売上がり』だぞ!二度と来やがるな!」と叫び、次郎もまた泣き崩れた。
(すべては終わった。これでいいんだ)そう言い聞かせ、自分を納得させた次郎のところに、親分から呼び出しがかかった。兄貴分が言う。
「・・・・。サツじゃあ、二、三日中に徹底的な『ガサ入れやる』ってはりきっているそうだ。これからのヤクザには計算だっているぞ。おめえもここいらへんががソロバンのはじきごろよ。・・・・。どうだ、二、三年、行ってこねえか」 突然の話に困惑する次郎、兄貴分はたたみかける。
「『ガサ入れ』の出鼻をくじいて、おめえが自首するんだ。組もしのげるし、サツのメンツだって、たたあな・・・。横浜のスケのことだけど、はい切れます、切れましただけじゃ、他人はうなずいてるようなつらしてても、腹の底では感心してやいねえんだぞ・・」
(そうか。真美と切れた証拠を見せろ、というのか!)次郎は、決意した。
「わかったよ兄貴、行くよ、オレ」
その他に、何ができるというのか。
【逢瀬・七】
兄貴分に付き添われて自首する日が来た。次郎は、自分のアパートで身だしなみを整え、弟分に言う。 「兄貴に言ってきな。いつでも出かけられます。お待ちしてますってな」
ところが、である。弟分と入れ代わりに、やってきたのは真美であった。
真美は、大きな旅行鞄を持っている。
「何しに来たんだ」と訝る次郎に、真美は答える。
「お別れを言いに参りました」
今晩の飛行機で、父のいるアルジェリアに「旅立つ」と言う。一瞬、愕然とする次郎。しかし、思い直して語りかけた。
「事情があって、オレ、ムショに行くことになっちまったんだ。・・・お嬢さんとオレは、ここではっきり別の世界の人間になりに行くってわけだ。会えやしねえ、絶対にもう!」
「次郎さん!」
「いいんだよ、その方がいいんだよ」
でも、真美は応じなかった。次郎に、すがりつき、懇願する。
「いやです、あたし、いやです! あたし行きたくないんです! 行きません! 次郎さんも、行かないで!・・・本当は、最初からあたし、もう家へなんか・・・。その覚悟できました!」
「お嬢さん!」
次郎がそう叫んだ時、窓のしたでブレーキの音がした。兄貴分と弟分が、迎えに来たのだ。二人は、反射的に、その場から脱走する。次郎の部屋には、真美の旅行鞄が一つ残されているだけだった。
二人は、「身一つ」で必死に逃げた。駅前からバスに飛び乗り、地下鉄へ、そこにはすでにヤクザの追っ手が手配されていた。やむなく、次郎は馴染みの女のアパートに逃げ込む。真美の母から捜索願を受けた警察やマスコミも動き始め、二人は完全に孤立した。しかし、神様が味方したのだろう。捜査網をどうにかくぐり抜け、大森の安アパートに落ち着くことができた。三十六時間が経過しても二人は見つからない。次郎と真美は、やっと「二人だけの世界」に浸ることができた。何もない六畳の一間で、タンメンをすする。 「こんなにおいしい物、生まれて初めて食べました」という真美。それでも、次郎は真美に帰宅を勧める。真美は応じなかった。ブロバリンの入った薬瓶を手にして「あたしの気持ちは決まっています。あたし、死にます。一人で死ぬんだって、ちっともさびしいことなんか・・」
次郎は「ばか!」と叫んで真美を平手打ち、真美はうれしそうに答えた。
「死にません! 死にません。次郎さんと一緒にいられる限り・・・」
そのとき、ドアをノックする音。おびえる二人。おそるおそる次郎がドアを開けると、それは新聞の勧誘員だった。二人の会話は、そのままで終わったが、次郎の気持ちは決まった。ようやく、決心がついた。(もうオレは、お嬢さんを守るしかない!)
勧誘員が置いていった「村田英雄ショー」のパンフレットで「折り鶴」を作る。それは、二人が初めて取り組んだ「仕事」に他ならない。次郎が切々と唄う「王将」に、真美は思わず涙する。それは、次郎の心に初めて触れることができた、「喜び」の涙だったに違いない。
アパートの「生活」は、「一瞬」のうちに過ぎた。これから、本当の「生活」に向かって、二人は出発するのである。真美の思い出深い赤倉のスキー場で、「雪だるま」を作るために・・・。
(お嬢さんには、かなわないなあ!)、しかし次郎の心は「充実」していた。
かくて、二人は、わずか七回の「逢瀬」で、見事な「情死」を遂げたのである。
雪深い雑木林の中で、二人の亡骸を見聞する警官がつぶやいた。
「こんな仲のよい心中は、初めてだな」
この「情死」をどのように評価するか。映画では、真美の同級生がマスコミのインタビューに答えて言う。
「わたくし、樺島さんとあの方の、ああした愛情のあり方に疑問を持っております。恋愛というものは、誰にも祝福されるような形でなければいけないんじゃあないでしょうか?」
はたして、「誰にも祝福されるような形」の恋愛とはどのようなものだろうか。当事者が、「お互いに相手を必要と感じるならば」、それが「愛情のあり方」に他ならない。次郎と真美は「住んでる世界」の違いを超えて、「二人だけの世界」を創り出すことができた。それが「たった七回の逢瀬」であったにしても、二人にとっては、文字通り「命をかけた」闘いであり、至福の時間ではなかったか。「誰にも祝福されるような形」とは、次郎にとってはヤクザの幹部、真美にとっては上流社会の令夫人に納まることだろうが、二人はその道を選ばなかった。その代償として「死」という現実が待っていたとはいえ、「どうせ人間は一回死ぬのだ」と割り切ってしまえば、いいことなのである。周囲から祝福されても、必要としない相手と無為な時間をだらだらと費やしている男女は、枚挙にいとまがないではないか。
したがって、この「情死」は、最高のできばえとして評価されてよい、と私は思う。
では、その最高傑作は何によって生み出されたのだろうか。
「七回の逢瀬」を辿ればわかるように、それは、ひとえに真美(女)の「決断力」「行動力」の賜であった。「純情可憐」な容貌の内に秘められた、その覇気は、しばしば「殺し文句」となってほとばしり出る。
①「さっきのママへの電話、『一番好きなお友だちと遊んでいます』って!」
②「ママに嘘ばっかりついているの」「あなたに嘘つきたくないから」
③「やめられません?ヤクザ! いけないと思うんです、ヤクザ! 野蛮だし・・・」
④「好きなんです! あなたが好きなんです!」
⑤「いやです、あたし、いやです。あたし、行きたくないんです。行きません! 次郎 さんも行かないで!・・・本当は、最初からあたし、もう家へなんか・・・。その覚悟できました」
⑥「あたしの気持ちは決まっています。あたし、死にます。一人で死ぬんだって、ちっともさびしいことなんか・・・」
⑦「死にません、死にません。次郎さんと生きていられる限り・・・」
このような言葉を「逢瀬」ごとに、浴びせられたら、次郎でなくても、たいていの男なら「まいってしまう」に違いない。
次郎と真美の関係は、終始、真美の主導のもとに展開し、終結したことは明らかである。それは、「男中心」と思われている人間社会の中で、実は、「弱者」として存在しているかに見える「女」が実権を握っていることの証左に他ならない。
(2006.5.1)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

日活映画「泥だらけの純情」(原作・藤原審爾 脚本・馬場当 監督・中平康 昭和38年)に登場した、次郎(浜田光夫)と真美(吉永小百合)である。
物語の梗概は以下のとおりである。
◆組長・塚田に頼まれてヤクを森原組の事務所に届けていたチンピラヤクザの次郎は、不良学生にからまれている外交官の令嬢・樺島真美を助ける。しかし、その乱闘の最中、相手があやまって自分の持っていたナイフで死んでしまったことにより、殺人の疑いをかけられる羽目に陥ってしまう。現場に落ちていたヤクからガサ入れを食らうことを恐れた兄貴分の花井は、彼に自首をすすめる。新聞を見て驚いた真美は、刑事にことの真相を話し、次郎は釈放される。そのことをきっかけに、二人はデートを重ねる仲となっていくが、その資金を捻出するために次郎は、悪事を繰り返していく。逮捕されても簡単な尋問だけで釈放される次郎に、疑いを抱く塚田。実は警察は例のヤクに目をつけ、大規模なガサ入れを狙い、彼を泳がせていたのだ。塚田から自首をすすめられる次郎。一方真美は父の仕事で外国へ行くことに。追い詰められた二人は、自分たちだけの世界を求め、雪山へと逃れるのだった。◆(ビデオ「にっかつ名画館・泥だらけの純情」解説パンフレットから引用)
次郎と真美の「逢瀬」はわずか七回、しかも「デートの楽しさ」を味わえたのは、そのうちのたった一回ではなかったか。
殺人の容疑が晴れたあと、真美の母から次郎に現金の「謝礼」が届く。しかし、次郎の気は済まない。真美を助けたのは、「銭のためではない」からである。次郎は、真美の「澄んだ瞳」が不良学生に汚されないために、助けたのだ。だから、もし謝礼の気持ちがあるのなら、直接、真美が次郎に会って「ありがとう」とお礼を言えば、それで気が済むのである。親分、兄貴から無理矢理「謝礼」を受け取らされた次郎の気持ちはおさまらず、真美の学校や自宅にまで、弟分と押しかけた。しかし、玄関のベルを押す勇気はなかった。
【逢瀬・一】
ところがである。翌日、突然、真美が次郎の安アパートを訪れた。次郎は、仰天して真美を出迎える。
「友だちに言われてきたのか?」
「自分でよく考えてきました」
「こんなところは、お嬢さんの来るところじゃないんだ。送っていくから帰れよ」
「はい」
玄関口で立ち話をしている二人に、アパートの住人たちは、興味津々で声をかけた。
「ジロちゃん、かわいい子だねえ。あんたのスケかい?」
「うるせえ!」
「照れることないじゃないか」
と、冷やかされながら、二人は駅に向かった。
次郎は、思ったに違いない。
(お嬢さん、わかった。もういい。オレは、昨日、お嬢さんの学校や自宅まで「引っかけるつもりで」会いに行ったけど、何もできなかった。しかも弟分まで連れて・・・。それに比べて、お嬢さんは、自分でよく考え、一人で来てくれた。もういい。お嬢さんの気持ちはよくわかった。ありがとう)
次郎は、真美の切符を買い、渋谷駅の構内で「別れの言葉」を言った。
「いいかい。今度あんな目にあったら、大声をあげなよ。黙っていてはどうにもならないんだ、じゃあ!」
それで終われば、よかったのかもしれない。しかし、次郎の気持ちに「変化」が生じた。(まだ、時間がある。せっかく会いに来てくれたお嬢さんを楽しませたい。いや、できれば、自分が楽しみたい。もしかしたら「引っかかる」かもしれない・・・)
次郎は、戻りかけた道を引き返し、真美の乗った電車を探す。
「お嬢さん!」と呼んでみると、真美が電車のドアから顔を出した。次郎は、間一髪でその電車に、飛び乗ることができた。
二人は、ボクシングを観戦し、帰途につく。途中で、話し合いながら、自分たちの生活が「全く違う」ことに惹かれ合う。ジュースを飲みながら「動物の生態」という教養番組を視聴、バイブルを読んで就寝するという真美。ウイスキーをラッパ飲みしてスポーツ雑誌を読みふけるという次郎・・・。しかし、次郎は、(これで本当に終わりにしよう)と思っていた。ホームの売店でピーナッツを買い、真美にプレゼントする。
「半分ずつしようか」といい、真美の手袋にピーナッツを注ぎこんだ。ベルが鳴り、電車のドアが閉まりかけたそのとき、真美が「殺し文句」を吐いたのだ。
「さっきのママへの電話(注・母に門限を延ばしてもらった電話)、『いちばん好きなお友だちと遊んでいます』って!」
この一言で、次郎は、真美を「忘れること」ができなくなってしまったのだと思う。
(もしかしたら、お嬢さんはオレを必要としているのかもしれない!)
思えば、この時の「逢瀬」こそが、「未来を展望し」、「自分たちだけの世界」を共有できた、至福の「ひととき」ではなっかたか。
次郎は、居酒屋に飛び込むと、客が楽しんでいたテレビの娯楽番組のチャンネルを、「動物の生態」に切り替える。「何するんだ!」という客の抗議を「ひとにらみ」ではね除け、平然とジュースを飲みながら皇帝ペンギンの映像を見つめる。アパートのベットに入り、「聖書」を拾い読みしながら眠りにつく。
真美は、真美で、オールドパーをラッパ飲みしながら、ボクシング雑誌に目を通し、挙げ句の果てには、姿見の前でシャドーボクシングまで始める始末であった。
【逢瀬・二、三】
以後、真美の誘いで「現代音楽祭」のコンサート、上野公園と二回デートを重ねるが、真美の表情は曇りがちである。
真美は思っていた。
(次郎さんは、チンピラヤクザになって「柄が悪い」ふりをしているけれど、本当は「悪い人」ではない。心の優しい、温かい人なんだ。それは、私自身が一番よく知っている。私と会うたびに、次郎さんはケガをする。初めての時、あの不良学生から私を助けようとして、おなかを刺された。その次の時も、電車のドアに指を挟まれた。この前も、コンサートの帰り、私に嫌がらせをした不良を二人殴り倒してくれたけど、指の爪をはがしてしまった。本当は、そんなに強くない。でも、そんな次郎さんを私は忘れられない。いつも一緒にいたい。どうすればいいのだろう?)
上野公園でのデートは、真美の都合で、すぐに帰らなければならなかった。でも、真美は言った。
「来週の土曜日は、(略)ママをだまして出て参ります。一日中どこへでも行けますわ」
「本当かい?」
「ママに嘘ばっかりついてるの」
「どうしてよ?」
「あなたに嘘つきたくないから・・・」
次郎は、確信した。(お嬢さんは、本気だ! オレはこれからどうすればいいのだろう?)
そして、本当の疑問をぶつけてみた。
「でもよ。あんた、オレと歩いていて恥ずかしくないかい?」
「恥ずかしいって?」
次郎の兄貴分は、恋人から海水浴に誘われたけど、「約束をほっぽっちゃった」という。背中一面に、雷様の刺青をしているからだ。
「海水浴だろ? 引け目感じちゃうよな」
「あなたも、してます? 刺青?」
「オレは、チンピラだからしてねえけどよ」
真美は、必死で次郎に訴えた。(今だ! 次郎さんに、本当の気持ちを言おう!)
「やめられません、ヤクザ! ヤクザっていけないと思うんです! 野蛮だし、法律にだって背いているし! でも、私、次郎さんは、まじめで正しい人だと思っています。どんなこと、なさっていようと・・・」
次郎は、返す言葉がない。「その通り」だからだ。
「土曜日な! 横浜駅で待ってるよ。十二時!」
それだけ言うと、逃げるようにその場を立ち去った。(わかっているよ、そんなこと!好きでヤクザやってるわけじゃない。オレの親父は「バタ屋」だ。オレのお袋は「淫売あがり」だぞ! そんなオレが一人前に生きて行くには、どうすればいいんだ。ヤクザにでもなるほかに道はないではないか! お嬢さん、わかってくれ。今のオレには、こんな自分をどうすることもできないんだ。今度の土曜日、お嬢さんは本当に来てくれるだろうか?)
しかし、土曜日、「約束を守った」のは、真美の方だった。次郎は「ポン引き」の疑いで警察に挙げられていたからである。
上野駅で、真美は半日待った。しかし、次郎は来ない。
真美は、待って、待って、待ち続けた。次郎のことが、いっときも忘れられなかった。何度もアパートに手紙を送ったが、返事は来ない。家族で赤倉にスキーに行っても、思うのは次郎からの返事のことばかり、もし返事が来なければ「死んでしまうかもしれません」とまで、手紙に綴ったが・・・。決心してヤクザの事務所にも行った。親分・兄貴分にも会い、次郎が警察に拘束されていることを知った。それでも、真美はあきらめなかった。次郎のアパートに行って待ち続ける。
どれくらいの日にちが経っただろうか。やがて、次郎は保釈された。組の事務所で挨拶をすませると、親分は「スケ(真美)と別れろ」という。兄貴分は、真美が事務所に訪ねてきたことを告げ、届いた手紙を焼きながら、「たくあんとセロリを食べている人間は、(住んでる世界)が違う」と次郎を諭した。しかし、次郎は迷っていた。(兄貴は、手紙を焼いてしまったけど、なんと書いてあったのだろうか? お嬢さんがオレのカミさんになるはずがない、でも、もしかしたら、オレを必要としてくれるかもしれないではないか)
【逢瀬・四】
憔悴してアパートに戻ると、真っ暗な部屋の中で、真美が待っていた。
驚愕する次郎。「お嬢さん!」と叫んで絶句した。真美は「お会いしたくて、飛んできました。毎日、毎日、このお部屋でお待ちしていたんです」と言う。
次郎がスーツのポケットに手を入れると、あのときのピーナッツが出てきた。それを二人で食べながら、真美が言った。
「次郎さん、あたし、もういやなんです。あなたが警察なんかに入れられてしまうの」 次郎も、答えた。
「やばいことは、もうやめたよ」
真美は、母の知人に頼んで、次郎の「仕事」を探すと言う。次郎は「乗り気」ではなかったが、(もしかしたら、堅い仕事につけるかもしれない)と淡い希望がわいてきた。
「かなわないよ、お嬢さんには」と言って、応じる羽目になってしまった。
【逢瀬・五、六】
次の日曜日、次郎は正装して、真美の自宅を訪れた。弟の「天文台開き」のパーティーに招待されたのである。真美は、その場で、次郎を母の知人に紹介し、次郎の「仕事」を見つけてもらおうと考えた。とりあえず、母に次郎を引き合わせたが、母は「どなたなの?」と訝しがる。真美が、「ほら、この前お願いした、あの新宿の時の・・・」と言いかけたとき、母の表情が変わった。真美を、物陰に呼んで叱責する。
「なんてことなさるの! あんな人、私が板東様に御紹介できると思っているの?私たちのおつきあいできる方じゃありません。家へくるのなんか遠慮していただかなくっちゃ!」
その様子を窺っていた次郎は、全てを察知し、上着を翻して、乱暴に立ち去る。「次郎さん!」と呼び止めようとする真美は、振り返りざま母をののしった。
「ママ! ママは真美の敵よ!」
真美は、心の底からそう思ったに違いない。あっけにとられているパーティーの参加者をしりめに、真美は次郎の後を追う。
どこをどう探したか、真美が次郎を見つけた時は、もう夜になっていた。盛り場のダンスホールで女と酔いしれる次郎、真美は弟分に取り次ぎ頼む。しかし、次郎は、もう、真美とかかわるつもりはない。真美を、にらみつけて、冷たく言った。
「何しに来たんだ!」
「おわびに参りました」
「帰れよ!」
「今度こそきっと、いいお仕事探してきますから・・・」
「よしてくれ! あんたは、これ以上オレに恥じかかせる気かい!」
「次郎さん・・・」
「ほっといてくれってんだよう!」
その場を立ち去ろうとする次郎の腕をつかんで、真美は叫んだ。
「好きなんです! あなたが好きなんです!」
次郎は、真美の必死な告白を、確かに耳にして、混乱し、逡巡した。
「好きだって? このオレを? そんなこと言わないでくれ! 好きだなんて、そんな・・・」
(どうしていいかわからない! しかし、そんなことはあり得ない。あっては、いけないことなんだ!)
「お嬢さんは、オレを知らないんだよ、オレは、町のダニだい! チンピラヤクザのご正体知らないから・・・。な、けえんな!」
しかし、真美は次郎の目を見つめたまま、動かない。
次郎は仕方なく、その場に居合わせた女を「凌辱」して見せた。泣きながら逃げ出した真美の背中にに向かって、「オレの親父は『バタ屋』だぞ! お袋は『淫売上がり』だぞ!二度と来やがるな!」と叫び、次郎もまた泣き崩れた。
(すべては終わった。これでいいんだ)そう言い聞かせ、自分を納得させた次郎のところに、親分から呼び出しがかかった。兄貴分が言う。
「・・・・。サツじゃあ、二、三日中に徹底的な『ガサ入れやる』ってはりきっているそうだ。これからのヤクザには計算だっているぞ。おめえもここいらへんががソロバンのはじきごろよ。・・・・。どうだ、二、三年、行ってこねえか」 突然の話に困惑する次郎、兄貴分はたたみかける。
「『ガサ入れ』の出鼻をくじいて、おめえが自首するんだ。組もしのげるし、サツのメンツだって、たたあな・・・。横浜のスケのことだけど、はい切れます、切れましただけじゃ、他人はうなずいてるようなつらしてても、腹の底では感心してやいねえんだぞ・・」
(そうか。真美と切れた証拠を見せろ、というのか!)次郎は、決意した。
「わかったよ兄貴、行くよ、オレ」
その他に、何ができるというのか。
【逢瀬・七】
兄貴分に付き添われて自首する日が来た。次郎は、自分のアパートで身だしなみを整え、弟分に言う。 「兄貴に言ってきな。いつでも出かけられます。お待ちしてますってな」
ところが、である。弟分と入れ代わりに、やってきたのは真美であった。
真美は、大きな旅行鞄を持っている。
「何しに来たんだ」と訝る次郎に、真美は答える。
「お別れを言いに参りました」
今晩の飛行機で、父のいるアルジェリアに「旅立つ」と言う。一瞬、愕然とする次郎。しかし、思い直して語りかけた。
「事情があって、オレ、ムショに行くことになっちまったんだ。・・・お嬢さんとオレは、ここではっきり別の世界の人間になりに行くってわけだ。会えやしねえ、絶対にもう!」
「次郎さん!」
「いいんだよ、その方がいいんだよ」
でも、真美は応じなかった。次郎に、すがりつき、懇願する。
「いやです、あたし、いやです! あたし行きたくないんです! 行きません! 次郎さんも、行かないで!・・・本当は、最初からあたし、もう家へなんか・・・。その覚悟できました!」
「お嬢さん!」
次郎がそう叫んだ時、窓のしたでブレーキの音がした。兄貴分と弟分が、迎えに来たのだ。二人は、反射的に、その場から脱走する。次郎の部屋には、真美の旅行鞄が一つ残されているだけだった。
二人は、「身一つ」で必死に逃げた。駅前からバスに飛び乗り、地下鉄へ、そこにはすでにヤクザの追っ手が手配されていた。やむなく、次郎は馴染みの女のアパートに逃げ込む。真美の母から捜索願を受けた警察やマスコミも動き始め、二人は完全に孤立した。しかし、神様が味方したのだろう。捜査網をどうにかくぐり抜け、大森の安アパートに落ち着くことができた。三十六時間が経過しても二人は見つからない。次郎と真美は、やっと「二人だけの世界」に浸ることができた。何もない六畳の一間で、タンメンをすする。 「こんなにおいしい物、生まれて初めて食べました」という真美。それでも、次郎は真美に帰宅を勧める。真美は応じなかった。ブロバリンの入った薬瓶を手にして「あたしの気持ちは決まっています。あたし、死にます。一人で死ぬんだって、ちっともさびしいことなんか・・」
次郎は「ばか!」と叫んで真美を平手打ち、真美はうれしそうに答えた。
「死にません! 死にません。次郎さんと一緒にいられる限り・・・」
そのとき、ドアをノックする音。おびえる二人。おそるおそる次郎がドアを開けると、それは新聞の勧誘員だった。二人の会話は、そのままで終わったが、次郎の気持ちは決まった。ようやく、決心がついた。(もうオレは、お嬢さんを守るしかない!)
勧誘員が置いていった「村田英雄ショー」のパンフレットで「折り鶴」を作る。それは、二人が初めて取り組んだ「仕事」に他ならない。次郎が切々と唄う「王将」に、真美は思わず涙する。それは、次郎の心に初めて触れることができた、「喜び」の涙だったに違いない。
アパートの「生活」は、「一瞬」のうちに過ぎた。これから、本当の「生活」に向かって、二人は出発するのである。真美の思い出深い赤倉のスキー場で、「雪だるま」を作るために・・・。
(お嬢さんには、かなわないなあ!)、しかし次郎の心は「充実」していた。
かくて、二人は、わずか七回の「逢瀬」で、見事な「情死」を遂げたのである。
雪深い雑木林の中で、二人の亡骸を見聞する警官がつぶやいた。
「こんな仲のよい心中は、初めてだな」
この「情死」をどのように評価するか。映画では、真美の同級生がマスコミのインタビューに答えて言う。
「わたくし、樺島さんとあの方の、ああした愛情のあり方に疑問を持っております。恋愛というものは、誰にも祝福されるような形でなければいけないんじゃあないでしょうか?」
はたして、「誰にも祝福されるような形」の恋愛とはどのようなものだろうか。当事者が、「お互いに相手を必要と感じるならば」、それが「愛情のあり方」に他ならない。次郎と真美は「住んでる世界」の違いを超えて、「二人だけの世界」を創り出すことができた。それが「たった七回の逢瀬」であったにしても、二人にとっては、文字通り「命をかけた」闘いであり、至福の時間ではなかったか。「誰にも祝福されるような形」とは、次郎にとってはヤクザの幹部、真美にとっては上流社会の令夫人に納まることだろうが、二人はその道を選ばなかった。その代償として「死」という現実が待っていたとはいえ、「どうせ人間は一回死ぬのだ」と割り切ってしまえば、いいことなのである。周囲から祝福されても、必要としない相手と無為な時間をだらだらと費やしている男女は、枚挙にいとまがないではないか。
したがって、この「情死」は、最高のできばえとして評価されてよい、と私は思う。
では、その最高傑作は何によって生み出されたのだろうか。
「七回の逢瀬」を辿ればわかるように、それは、ひとえに真美(女)の「決断力」「行動力」の賜であった。「純情可憐」な容貌の内に秘められた、その覇気は、しばしば「殺し文句」となってほとばしり出る。
①「さっきのママへの電話、『一番好きなお友だちと遊んでいます』って!」
②「ママに嘘ばっかりついているの」「あなたに嘘つきたくないから」
③「やめられません?ヤクザ! いけないと思うんです、ヤクザ! 野蛮だし・・・」
④「好きなんです! あなたが好きなんです!」
⑤「いやです、あたし、いやです。あたし、行きたくないんです。行きません! 次郎 さんも行かないで!・・・本当は、最初からあたし、もう家へなんか・・・。その覚悟できました」
⑥「あたしの気持ちは決まっています。あたし、死にます。一人で死ぬんだって、ちっともさびしいことなんか・・・」
⑦「死にません、死にません。次郎さんと生きていられる限り・・・」
このような言葉を「逢瀬」ごとに、浴びせられたら、次郎でなくても、たいていの男なら「まいってしまう」に違いない。
次郎と真美の関係は、終始、真美の主導のもとに展開し、終結したことは明らかである。それは、「男中心」と思われている人間社会の中で、実は、「弱者」として存在しているかに見える「女」が実権を握っていることの証左に他ならない。
(2006.5.1)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-09
付録‥邦画傑作選・「婦系図」(監督・野村芳亭・1934年)
ユーチューブで映画「婦系図」(監督・野村芳亭・1934年)を観た。原作は泉鏡花の新聞小説で1907年(明治40年)に発表され、翌年には新派の舞台で演じられている。有名な「湯島境内の場」は原作にはなく、いわば演劇のために脚色されたものである。それから27年後、野村芳亭(野村芳太郎の父)によって、初めて映画化された。
その物語は、参謀本部でドイツ語の翻訳官を務める早瀬主税(岡譲二)の自宅に、静岡の有力者・河野秀臣(武田春郞)の妻とみ子(青木しのぶ)と息子英吉(小林十九二)が訪れているところから始まる。主税と英吉は静岡時代の友人、主税はその後上京、神田で「隼の力」という異名で悪事を働いた与太者だったが、「真砂町の先生」こと大学教授・酒井俊蔵(志賀靖郎)に諭され、今の地位を得ることができたのだ。しかし、馴染みの柳橋芸者・蔦吉(田中絹代)と同棲中、いずれは先生の許しを頂いて正妻の座に据えるつもりだったが、今はまだ外来者に会わせることができない。事情を知っているのは、女中のお源(飯田蝶子)、出入りの魚屋「めの惣」こと、め組の惣吉(河村黎吉)、蔦吉の朋輩・小芳(吉川満子)くらいであった。
主税の家に客が訪れるたびに、蔦吉は身を隠して時間を過ごす。その様子を見て惣吉は気の毒がったが、蔦吉は、いずれ晴れて女房になれると思うと苦にならなかった。
河野家の訪問は縁談話、酒井の娘・妙子(大塚君代)を英吉の嫁として迎えたい、その仲介と身元調査を頼みに来たのである。しかし、主税は取り合わなかった。妙子は酒井が小芳に生ませた娘、河野家にも妻の不貞で生まれた娘が居る。複雑な人間模様(婦系図)が伏線となって、悲劇は進む。
業を煮やした河野家は改めて坂田令之進(芸名不詳)という家令(?)を主税の元に送り、縁談の仲介を頼んだが、主税は断固拒絶、坂田は退散する。その時、出口で蔦吉と鉢合わせ、主税と蔦吉の同棲を知ることになったか。
主税はその後、真砂町の酒井を訪れる。奥ではすでに坂田と酒井が面談中(坂田の憤慨・糾弾、酒井の謝罪と縁談承認などなど)で書生(三井秀男)から「先生は今、ゴキゲンが悪い」と追い返された。ブラブラと、本郷の夜店に立ち寄り「三世相」(陰陽道の占い本)を手にする。「一円です」という親父(坂本武)に「高すぎる、半額なら・・」と戸惑っているところに、五十銭硬貨二つが投げ出された。見ればそこに立っていたのは酒井。「先生!」と驚く主税、そのまま主税宅に赴くと言う。しかし行った先は柳橋の料亭、途中で「掏摸騒ぎ」に遭遇し、主税は男にぶつかられたがそのまま、歩き続ける。料亭の部屋には小芳も呼ばれた。清元?、新内?の音曲が流れる中、弟子と恩師、恩師の日陰者の三者の「絡み」は、寸分の隙もなく往時の人間模様を鮮やかに描出する。酒井、かつての愛妾・小芳に向かっては「朋輩の蔦吉はどこにいる、知らないとは薄情だ。俺が教えてやろう、主税の家だ」と言い、主税に向かっては「弟子の分際で、妙子の縁談を邪魔するとは何事だ」「先生、英吉は妙子さんの相手としてふさわしくありません」「何をほざくか。芸者風情を家に引きずり込んでいる奴に何が言えるか」。主税は、恩師のため小芳のために妙子の吉凶を占おうとしたのだが、何を言っても通じない。じっと耐えている小芳、しばらく瞑目して、主税は「先生、私が考え違いをしておりました」と終に謝る。酒井は主税に酒を注ぎ「では、女と別れるか、それとも俺と別れるか」、「女を捨てるか、俺を捨てるか。グズグズせずに返答せい!」と迫った。主税、きっぱりと「女を捨てます。どうか幾久しくお杯を」と平伏、その場は平穏に戻る。小芳の泣き崩れる声だけが余韻を残しながら・・・。
主税が料亭を出ると、闇にまみれて男が待っていた。「旦那、さっきの物をいただきましょう」「何だ」「とぼけちゃいけませんぜ」。懐に手を入れると大きな皮財布。「ああ、これか、じゃあお前は掏摸か」。早く返せと匕首を振り回すその男を組伏して、主税いわく「この財布は返してやる」「では半分ずつということで」「そうではない、被害者に返すのだ。俺も昔は同じことをしていたんだ。ある先生のおかげで真っ当な道を歩けるようになった。こんなことをていて長続きするはずがない。改心して明るい世界を歩くように」と説諭すれば、男「改心・・・」と言って固まった。昔は同じ道を歩いていた兄貴が・・・、という思いだったか、戻った財布をしっかりと抱きしめ「旦那、私はこれから自首します。明るい世界を歩きます」。返された匕首もすぐさま池に投げ捨てる。主税、「昔、俺もあんな風だったな、先生に恩返しをしなければ」と思ったかどうか、そのまま闇の中に消えて行く男を見送った。
大詰めは、御存知「湯島境内の場」、「俺はもう、死んだ気になってお前に話す」「そんな冗談言ってないで、さあ」「冗談じゃない。どうか俺と別れてくれ」「別れる?……からかってないで、早くうちへ帰りましょうよ」「そんな暢気な場合じゃない……本当なんだ。どうか俺と縁を切ってくれ」「縁を切る?貴方気でも違ったんじゃないんですか」「気が違えば結構だ。……俺は正気でいっているんだ」「そう、正気でいうのなら、私も正気で返事をするわ。そんなことはね、いやなこってす」
「俺は決して薄情じゃない。誓ってお前を飽きゃァしない」「また飽きられてたまるもんですか。切れるの、別れるのってそんなことはね、芸者の時にいうことよ。今の私には、死ねといって下さい」、という名セリフそのままに、田中絹代と岡譲二が描き出す愁嘆場は筆舌に尽くしがたい風情であった。後世(1942年)「知るや白梅玉垣にのこる二人の影法師」(詞・佐伯孝夫)と詠われたように、その二人の姿が、ひときわ艶やかに浮かび出て、この映画の幕は下りた。
余談だが、現代の浪曲師・二葉百合子も「湯島境内の場」を中心に、お蔦・主税の《心意気》を鮮やかに描き出している。「先生から俺を捨てるか、女を捨てるか、と言われた時、女を捨てますと言ったんだ」という言葉を聞いて、お蔦は「よくぞ言ってくれました。それでこそあなたの男が立ちますわ」と答える。そこには、男に翻弄される女の「意地」も仄見えて、芸者の「誠」とはそのようなものだったのかと、感じ入る。
続いて、天津ひずるも、湯島から1年後の後日談、「めの惣」宅に身を寄せ、病に斃れていくお蔦の最後を見事に詠い上げている。そこでは、酒井俊蔵がおのれの不実を恥じ、お蔦に心から詫びる場面も添えられていた。
「婦系図」は以後、長谷川一夫・山田五十鈴、鶴田浩二・山本富士子、天知茂・高倉みゆき、市川雷蔵・万里昌代らのコンビによって映画化されているが、その先駆けとしての役割を十分に果たし、「お手本」としての価値を十二分に備えている名作だったと、私は思う。(2017.2.7)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

その物語は、参謀本部でドイツ語の翻訳官を務める早瀬主税(岡譲二)の自宅に、静岡の有力者・河野秀臣(武田春郞)の妻とみ子(青木しのぶ)と息子英吉(小林十九二)が訪れているところから始まる。主税と英吉は静岡時代の友人、主税はその後上京、神田で「隼の力」という異名で悪事を働いた与太者だったが、「真砂町の先生」こと大学教授・酒井俊蔵(志賀靖郎)に諭され、今の地位を得ることができたのだ。しかし、馴染みの柳橋芸者・蔦吉(田中絹代)と同棲中、いずれは先生の許しを頂いて正妻の座に据えるつもりだったが、今はまだ外来者に会わせることができない。事情を知っているのは、女中のお源(飯田蝶子)、出入りの魚屋「めの惣」こと、め組の惣吉(河村黎吉)、蔦吉の朋輩・小芳(吉川満子)くらいであった。
主税の家に客が訪れるたびに、蔦吉は身を隠して時間を過ごす。その様子を見て惣吉は気の毒がったが、蔦吉は、いずれ晴れて女房になれると思うと苦にならなかった。
河野家の訪問は縁談話、酒井の娘・妙子(大塚君代)を英吉の嫁として迎えたい、その仲介と身元調査を頼みに来たのである。しかし、主税は取り合わなかった。妙子は酒井が小芳に生ませた娘、河野家にも妻の不貞で生まれた娘が居る。複雑な人間模様(婦系図)が伏線となって、悲劇は進む。
業を煮やした河野家は改めて坂田令之進(芸名不詳)という家令(?)を主税の元に送り、縁談の仲介を頼んだが、主税は断固拒絶、坂田は退散する。その時、出口で蔦吉と鉢合わせ、主税と蔦吉の同棲を知ることになったか。
主税はその後、真砂町の酒井を訪れる。奥ではすでに坂田と酒井が面談中(坂田の憤慨・糾弾、酒井の謝罪と縁談承認などなど)で書生(三井秀男)から「先生は今、ゴキゲンが悪い」と追い返された。ブラブラと、本郷の夜店に立ち寄り「三世相」(陰陽道の占い本)を手にする。「一円です」という親父(坂本武)に「高すぎる、半額なら・・」と戸惑っているところに、五十銭硬貨二つが投げ出された。見ればそこに立っていたのは酒井。「先生!」と驚く主税、そのまま主税宅に赴くと言う。しかし行った先は柳橋の料亭、途中で「掏摸騒ぎ」に遭遇し、主税は男にぶつかられたがそのまま、歩き続ける。料亭の部屋には小芳も呼ばれた。清元?、新内?の音曲が流れる中、弟子と恩師、恩師の日陰者の三者の「絡み」は、寸分の隙もなく往時の人間模様を鮮やかに描出する。酒井、かつての愛妾・小芳に向かっては「朋輩の蔦吉はどこにいる、知らないとは薄情だ。俺が教えてやろう、主税の家だ」と言い、主税に向かっては「弟子の分際で、妙子の縁談を邪魔するとは何事だ」「先生、英吉は妙子さんの相手としてふさわしくありません」「何をほざくか。芸者風情を家に引きずり込んでいる奴に何が言えるか」。主税は、恩師のため小芳のために妙子の吉凶を占おうとしたのだが、何を言っても通じない。じっと耐えている小芳、しばらく瞑目して、主税は「先生、私が考え違いをしておりました」と終に謝る。酒井は主税に酒を注ぎ「では、女と別れるか、それとも俺と別れるか」、「女を捨てるか、俺を捨てるか。グズグズせずに返答せい!」と迫った。主税、きっぱりと「女を捨てます。どうか幾久しくお杯を」と平伏、その場は平穏に戻る。小芳の泣き崩れる声だけが余韻を残しながら・・・。
主税が料亭を出ると、闇にまみれて男が待っていた。「旦那、さっきの物をいただきましょう」「何だ」「とぼけちゃいけませんぜ」。懐に手を入れると大きな皮財布。「ああ、これか、じゃあお前は掏摸か」。早く返せと匕首を振り回すその男を組伏して、主税いわく「この財布は返してやる」「では半分ずつということで」「そうではない、被害者に返すのだ。俺も昔は同じことをしていたんだ。ある先生のおかげで真っ当な道を歩けるようになった。こんなことをていて長続きするはずがない。改心して明るい世界を歩くように」と説諭すれば、男「改心・・・」と言って固まった。昔は同じ道を歩いていた兄貴が・・・、という思いだったか、戻った財布をしっかりと抱きしめ「旦那、私はこれから自首します。明るい世界を歩きます」。返された匕首もすぐさま池に投げ捨てる。主税、「昔、俺もあんな風だったな、先生に恩返しをしなければ」と思ったかどうか、そのまま闇の中に消えて行く男を見送った。
大詰めは、御存知「湯島境内の場」、「俺はもう、死んだ気になってお前に話す」「そんな冗談言ってないで、さあ」「冗談じゃない。どうか俺と別れてくれ」「別れる?……からかってないで、早くうちへ帰りましょうよ」「そんな暢気な場合じゃない……本当なんだ。どうか俺と縁を切ってくれ」「縁を切る?貴方気でも違ったんじゃないんですか」「気が違えば結構だ。……俺は正気でいっているんだ」「そう、正気でいうのなら、私も正気で返事をするわ。そんなことはね、いやなこってす」
「俺は決して薄情じゃない。誓ってお前を飽きゃァしない」「また飽きられてたまるもんですか。切れるの、別れるのってそんなことはね、芸者の時にいうことよ。今の私には、死ねといって下さい」、という名セリフそのままに、田中絹代と岡譲二が描き出す愁嘆場は筆舌に尽くしがたい風情であった。後世(1942年)「知るや白梅玉垣にのこる二人の影法師」(詞・佐伯孝夫)と詠われたように、その二人の姿が、ひときわ艶やかに浮かび出て、この映画の幕は下りた。
余談だが、現代の浪曲師・二葉百合子も「湯島境内の場」を中心に、お蔦・主税の《心意気》を鮮やかに描き出している。「先生から俺を捨てるか、女を捨てるか、と言われた時、女を捨てますと言ったんだ」という言葉を聞いて、お蔦は「よくぞ言ってくれました。それでこそあなたの男が立ちますわ」と答える。そこには、男に翻弄される女の「意地」も仄見えて、芸者の「誠」とはそのようなものだったのかと、感じ入る。
続いて、天津ひずるも、湯島から1年後の後日談、「めの惣」宅に身を寄せ、病に斃れていくお蔦の最後を見事に詠い上げている。そこでは、酒井俊蔵がおのれの不実を恥じ、お蔦に心から詫びる場面も添えられていた。
「婦系図」は以後、長谷川一夫・山田五十鈴、鶴田浩二・山本富士子、天知茂・高倉みゆき、市川雷蔵・万里昌代らのコンビによって映画化されているが、その先駆けとしての役割を十分に果たし、「お手本」としての価値を十二分に備えている名作だったと、私は思う。(2017.2.7)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-08
付録・邦画傑作選・「忠烈実録忠臣蔵」(監督・マキノ省三・1928年)
ユーチューブで、映画「忠烈 実録忠臣蔵」(監督・マキノ省三・1928年)を観た。監督のマキノ省三は「日本映画の父」と言われ、邦画草創期の基礎を築いた人物である。この映画のフィルムは火災、戦災などにより匹散していたが、戦後、息子のマキノ雅弘によって採集・修復・再編集されたそうである。したがって、往時の作品そのものではないにしても、その面影は十分に堪能できる。場面は「刃傷松の廊下」から始まり、「赤穂城内大評定(血判状)」「城明け渡し」「一力茶屋」「山科閑居」「大石東下り」「吉良邸討ち入り」へと展開する。登場人物は大石内蔵之助を筆頭に100人を超える。その陣容(配役)は以下の通りである。(「ウィキペディア百科事典」より引用)
伊井蓉峰(大石内蔵之助良雄)、諸口十九(浅野内匠頭)、市川小文治(吉良上野介義央)、勝見庸太郎(立花左近)、月形龍之介(清水一角)、中根龍太郎(松野河内守)、嵐長三郎(脇坂淡路守)、片岡千恵蔵(お目附 服部一郎右衛門)、片岡市太郎(勅使 柳原権大納言)、杉狂児(忠婢 拳固のお源)、中根龍太郎(伜 与太九呂)マキノ正博(大石主税良金)、小島陽三(将軍 綱吉公)、松本時之助(浅野大学)、中村東之助(田村右京太夫)、小岩井昇三郎(伊達左京之亮)、山本礼三郎(梶川与惣兵衛)、
金子新(院使 高野中納言)市川小莚次(院使 清閑中納言)、松村光男(僧良雪)、荒木忍(吉良間者 前野平内)、川田弘道(吉良間者 猿橋右門)、菊波正之助(大石の下僕 実は吉良の間者万吉)、秋吉薫(吉良の間者 石束甚八)、中田国義(切腹上使 荘田下総守)、若松文男(お目附 岡田伝八郎)、静間静之助(介錯)、梅田五郎(お茶坊主 平井長庵)、守本専一(石堂・田村の臣)、大味正徳(榊原・田村の臣)、斉藤俊平(高味勘解由・田村の臣)、児島武彦(大老 柳沢美濃守)、大谷万六(太鼓持 千住)、都賀清司(大石の僕・八動)、松尾文人(二男 大石千代松)、都賀一司(三男 大石大三郎)、津村博(清水一角 弟)、尾上松緑(吉良の間者牧山大五郎)、藤井六輔(そばやの爺〆助)、大国一郎( 吉良の家来 和久牛太郎)、マキノ正美(吉良左兵衛之介)、児島武彦(菅野の父 七郎左衛門)、嵐冠(間の一子 十太郎)、染井達郎(堀部弥兵衛金丸)、松村光男(堀部喜兵衛光延)、若松文男(吉田忠左衛門)、嵐冠吉郎(間瀬久太夫正明)、原田耕造(村瀬喜兵衛秀道)、大味正徳(小野寺十内秀和)、柳妻麗三郎(奥田孫太夫重盛)、中村東之助(原惣右衛門元辰)、松本熊夫(貝賀弥左衛門友信)、西郷昇(千葉三郎兵衛光忠)、南部国男( 木村岡右衛門貞行)、木村猛(中村勘助正辰)、森清(菅谷半之亟政則)、大谷鬼若(早水藤左衛門満堯)、橘正明(前原伊助宗房)、嵐長三郎(寺坂吉右衛門信行)、星月英之助( 岡島八十右衛門常樹)、市川小莚次(神崎与五郎則安)、矢野武夫(萱野和助常成)、市川小文治(片岡源五右衛門高房)、豊島龍平(横川勘平宗利)、小岩井昇三郎(三村次郎左衛門包常)、金子新(潮田又之丞高教・東下り)、東郷久義(赤埴源蔵重賢)、山本礼三郎(堀部安兵衛武庸)、佐久間八郎(不破数右衛門正種)、英まさる(近松勘六行重)、坂本二郎(富森助右衛門正因)、沢村錦之助(倉橋伝助武幸)、武井龍三(武林唯七隆重)、天野刃一(大高源吾忠雄)、八雲燕之助(吉田沢右衛門兼貞)、鈴木京平(矢田五郎右衛門助武)、片岡千恵蔵(萱野三平)、市川谷五郎(小野寺幸右衛門秀富)、川島清(杉野十平次次房)、藤岡正義(大石瀬左衛門信清)、牧光郎(村松三太夫高直)、有村四郎(奥田貞右衛門行高)、小金井勝(間十次郎光興)、松坂進(磯貝十郎左衛門正久)、市原義雄(岡野金右衛門包秀)、マキノ登六(間新六)、久賀龍三郎(勝田新左衛門武堯)、潮龍二(間瀬孫九郎正辰)、マキノ梅太郎(矢頭右衛門七教兼)、尾上松緑(大野九郎兵衛)、大谷万六(勅使 玉虫七郎右衛門)、徳川良之助(勅使 近藤源八)、守本専一(勅使 藤井彦四郎)、荒尾静一(勅使 早川宗助)、高山久(勅使 田中清兵衛)、嵐冠三郎(豊田八太夫)、尾上延三郎(豊田庄助)、玉木悦子(浅野後室瑤泉院)、花岡百合子(戸田の局)、石川新水( 大石の室お陸)、マキノ智子(早水藤左衛門の娘千賀)、松浦築枝(浮橋太夫)、渡辺綾子(軽藻太夫)、住ノ江田鶴子(吉野太夫)、三保松子(女中お梶)、河上君江(吉良の侍女妙香)、水谷蘭子(そばやの姉お富)、岡島艶子(三平の新妻露野)、鈴木澄子(清水一角の姉)、大林梅子(吉良の間者お梅)、五十川鈴子(浮橋の引舟芳子)、都賀静子(浮橋の引舟田毎)、広田昴(百足屋与助)、玉木潤一郎(具足屋為五郎)、大岡怪童(研屋伝九郎)大国一郎(狂人荒物屋千五郎)・・・(嗚呼、記すのにくたびれてしまった!)
まさに忠烈と言うよりは壮絶、文字通り錚々たるメンバーだが、特別の人物を除いて、彼ら一人一人を映像の中で識別することは困難であった。また当初のフィルムは消失しているので再編集後は登場しない人物もあるだろう。筋書き以上に、私の知る俳優が、どの役で、どの場面に登場するか、興味津々で鑑賞することができた。嵐長三郎(後の嵐寬壽郞)、片岡知恵蔵、月形龍之介、尾上松緑、山本礼三郎といった面々に注目する。松の廊下で、手負いの吉良上野介を罵倒する脇坂淡路守を演じた嵐寬壽郞、赤穂城内大評定での大野九郎兵衛・尾上松緑の姿はハッキリと確認できたが、片岡知恵蔵、月形龍之介、山本礼三郎は「どこでどうしているのやら」、ぼうとして見極められなかった。でも、それでよい。パズルのように何度でも観て「発見する」喜びが増えたのだから。
一方、面白いことに、全く知らなかった俳優が忽然と現れた。大石主税を演じたマキノ正博(後のマキノ雅弘)である。主役の大石内蔵助と絡むので出番は多く、否が応でもその姿が印象に残るという仕掛け、なるほど、この映画をリメイクしたのは彼自身なのだから、(自分の出番を多くしたいという気持ちも察しられ)「さもありなん」と妙に納得してしまった次第である。
いずれにせよ「実録」と銘打っているのだから、この物語は史実に近いかもしれない。(ただし、立花左近は架空の人物である)
松の廊下で内匠頭が一人仲間はずれ、身の置き所もなく「これからどうすればいいか」、上野介に教えを乞う場面は真に迫っていた。以後、数多く作られた「忠臣蔵」映画の原点として貴重な役割を果たしていることは間違いない。
さらに言えば、マキノ省三の映画は「あくまで芝居を映す」(1スジ 2ヌケ 3ドウサ)ことが基本、その伝統は1960年代の任侠映画「日本侠客伝」シリーズまで受け継がれていると、私は思う。
(2017.1.15)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

伊井蓉峰(大石内蔵之助良雄)、諸口十九(浅野内匠頭)、市川小文治(吉良上野介義央)、勝見庸太郎(立花左近)、月形龍之介(清水一角)、中根龍太郎(松野河内守)、嵐長三郎(脇坂淡路守)、片岡千恵蔵(お目附 服部一郎右衛門)、片岡市太郎(勅使 柳原権大納言)、杉狂児(忠婢 拳固のお源)、中根龍太郎(伜 与太九呂)マキノ正博(大石主税良金)、小島陽三(将軍 綱吉公)、松本時之助(浅野大学)、中村東之助(田村右京太夫)、小岩井昇三郎(伊達左京之亮)、山本礼三郎(梶川与惣兵衛)、
金子新(院使 高野中納言)市川小莚次(院使 清閑中納言)、松村光男(僧良雪)、荒木忍(吉良間者 前野平内)、川田弘道(吉良間者 猿橋右門)、菊波正之助(大石の下僕 実は吉良の間者万吉)、秋吉薫(吉良の間者 石束甚八)、中田国義(切腹上使 荘田下総守)、若松文男(お目附 岡田伝八郎)、静間静之助(介錯)、梅田五郎(お茶坊主 平井長庵)、守本専一(石堂・田村の臣)、大味正徳(榊原・田村の臣)、斉藤俊平(高味勘解由・田村の臣)、児島武彦(大老 柳沢美濃守)、大谷万六(太鼓持 千住)、都賀清司(大石の僕・八動)、松尾文人(二男 大石千代松)、都賀一司(三男 大石大三郎)、津村博(清水一角 弟)、尾上松緑(吉良の間者牧山大五郎)、藤井六輔(そばやの爺〆助)、大国一郎( 吉良の家来 和久牛太郎)、マキノ正美(吉良左兵衛之介)、児島武彦(菅野の父 七郎左衛門)、嵐冠(間の一子 十太郎)、染井達郎(堀部弥兵衛金丸)、松村光男(堀部喜兵衛光延)、若松文男(吉田忠左衛門)、嵐冠吉郎(間瀬久太夫正明)、原田耕造(村瀬喜兵衛秀道)、大味正徳(小野寺十内秀和)、柳妻麗三郎(奥田孫太夫重盛)、中村東之助(原惣右衛門元辰)、松本熊夫(貝賀弥左衛門友信)、西郷昇(千葉三郎兵衛光忠)、南部国男( 木村岡右衛門貞行)、木村猛(中村勘助正辰)、森清(菅谷半之亟政則)、大谷鬼若(早水藤左衛門満堯)、橘正明(前原伊助宗房)、嵐長三郎(寺坂吉右衛門信行)、星月英之助( 岡島八十右衛門常樹)、市川小莚次(神崎与五郎則安)、矢野武夫(萱野和助常成)、市川小文治(片岡源五右衛門高房)、豊島龍平(横川勘平宗利)、小岩井昇三郎(三村次郎左衛門包常)、金子新(潮田又之丞高教・東下り)、東郷久義(赤埴源蔵重賢)、山本礼三郎(堀部安兵衛武庸)、佐久間八郎(不破数右衛門正種)、英まさる(近松勘六行重)、坂本二郎(富森助右衛門正因)、沢村錦之助(倉橋伝助武幸)、武井龍三(武林唯七隆重)、天野刃一(大高源吾忠雄)、八雲燕之助(吉田沢右衛門兼貞)、鈴木京平(矢田五郎右衛門助武)、片岡千恵蔵(萱野三平)、市川谷五郎(小野寺幸右衛門秀富)、川島清(杉野十平次次房)、藤岡正義(大石瀬左衛門信清)、牧光郎(村松三太夫高直)、有村四郎(奥田貞右衛門行高)、小金井勝(間十次郎光興)、松坂進(磯貝十郎左衛門正久)、市原義雄(岡野金右衛門包秀)、マキノ登六(間新六)、久賀龍三郎(勝田新左衛門武堯)、潮龍二(間瀬孫九郎正辰)、マキノ梅太郎(矢頭右衛門七教兼)、尾上松緑(大野九郎兵衛)、大谷万六(勅使 玉虫七郎右衛門)、徳川良之助(勅使 近藤源八)、守本専一(勅使 藤井彦四郎)、荒尾静一(勅使 早川宗助)、高山久(勅使 田中清兵衛)、嵐冠三郎(豊田八太夫)、尾上延三郎(豊田庄助)、玉木悦子(浅野後室瑤泉院)、花岡百合子(戸田の局)、石川新水( 大石の室お陸)、マキノ智子(早水藤左衛門の娘千賀)、松浦築枝(浮橋太夫)、渡辺綾子(軽藻太夫)、住ノ江田鶴子(吉野太夫)、三保松子(女中お梶)、河上君江(吉良の侍女妙香)、水谷蘭子(そばやの姉お富)、岡島艶子(三平の新妻露野)、鈴木澄子(清水一角の姉)、大林梅子(吉良の間者お梅)、五十川鈴子(浮橋の引舟芳子)、都賀静子(浮橋の引舟田毎)、広田昴(百足屋与助)、玉木潤一郎(具足屋為五郎)、大岡怪童(研屋伝九郎)大国一郎(狂人荒物屋千五郎)・・・(嗚呼、記すのにくたびれてしまった!)
まさに忠烈と言うよりは壮絶、文字通り錚々たるメンバーだが、特別の人物を除いて、彼ら一人一人を映像の中で識別することは困難であった。また当初のフィルムは消失しているので再編集後は登場しない人物もあるだろう。筋書き以上に、私の知る俳優が、どの役で、どの場面に登場するか、興味津々で鑑賞することができた。嵐長三郎(後の嵐寬壽郞)、片岡知恵蔵、月形龍之介、尾上松緑、山本礼三郎といった面々に注目する。松の廊下で、手負いの吉良上野介を罵倒する脇坂淡路守を演じた嵐寬壽郞、赤穂城内大評定での大野九郎兵衛・尾上松緑の姿はハッキリと確認できたが、片岡知恵蔵、月形龍之介、山本礼三郎は「どこでどうしているのやら」、ぼうとして見極められなかった。でも、それでよい。パズルのように何度でも観て「発見する」喜びが増えたのだから。
一方、面白いことに、全く知らなかった俳優が忽然と現れた。大石主税を演じたマキノ正博(後のマキノ雅弘)である。主役の大石内蔵助と絡むので出番は多く、否が応でもその姿が印象に残るという仕掛け、なるほど、この映画をリメイクしたのは彼自身なのだから、(自分の出番を多くしたいという気持ちも察しられ)「さもありなん」と妙に納得してしまった次第である。
いずれにせよ「実録」と銘打っているのだから、この物語は史実に近いかもしれない。(ただし、立花左近は架空の人物である)
松の廊下で内匠頭が一人仲間はずれ、身の置き所もなく「これからどうすればいいか」、上野介に教えを乞う場面は真に迫っていた。以後、数多く作られた「忠臣蔵」映画の原点として貴重な役割を果たしていることは間違いない。
さらに言えば、マキノ省三の映画は「あくまで芝居を映す」(1スジ 2ヌケ 3ドウサ)ことが基本、その伝統は1960年代の任侠映画「日本侠客伝」シリーズまで受け継がれていると、私は思う。
(2017.1.15)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-07
付録・邦画傑作選・「愛の世界 山猫とみの話」(監督・青柳信雄・1943年)
ユーチューブで映画「愛の世界 山猫とみの話」(監督・青柳信雄・1943年)を観た。戦時下における教育映画の名作である。
主人公は、小田切とみ(高峰秀子)16歳、彼女の父は行方不明、母とは7歳の時に死別、母が遊芸人だったことから9歳の時、曲馬団に入れられた。現在の保護者は伯父になっているが折り合いが悪く、放浪を繰り返し、警察に度々補導されている。性格は強情、粗暴で、一切口をきかない・・・、ということで少年審判所に送られた。その結果、東北にある救護院、四辻学院で教育を受けることになる。彼女の身柄を引き受けに来たのは(新任の)山田先生(里見藍子)。市電、汽車、バスを乗り継いで学院に向かうが、とみは口を閉ざしたまま山田先生の話しかけに応じようとしないばかりか、「隙あらば逃げだそう」という気配も窺われる。事実、高崎駅で先生が水を汲みに行き戻ると、とみの姿は消えていた。あわてて探せばホームに立っている。「小田切さーん」と呼びかけられ、走り出した列車に飛び乗るという離れ業を演じる始末、ようやく学院の門前まで辿り着き、先生が「疑って悪かったわ、何でも悪い方にばかり考えてしまって・・」と言った途端、今度は本当に逃げ出した。道を駆け下り、畦道伝いに、田圃、叢を抜け、沼地へと逃げていく。必死に追いかける先生もまた走る、走る。とみは沼地に踏み込み、ずぶ濡れ、先生もずぶ濡れになって後を追う。「捕まえる」というよりは「助ける」ために・・・。やがて、とみの行く手には高い石垣が待っていた。万事休す、キッとして先生を睨むとみ。しかし、先生は意外にも、その場(水中)にしゃがみ込み泣き伏してしまった。とみは逃走を断念する。 かくて、とみは学院の一員となったが、「無言の行」は相変わらず、誰とも言葉を交わさない。院長の四辻(菅井一郎)は「初めはみんなそうだ、そのうちに必ずよくなる」と確信、山田先生を励ますが、とみの強情、粗暴は変わらず、院生とのトラブルは増え続ける。「親切にされると、下心があるんじゃないかと疑い深くなるものだ。彼女の乱暴は、身を守る手段なのだ」という院長の言葉は、現代にも通じる至言だろう。
院生たちの不満は、一に、新参のとみが心を開かないこと(緘黙を貫いていること)、二に、そうしたとみを院長が許容していること、三に、山田先生がとみだけを可愛がっていることに向けられる。とみには「山猫」という異名がつけられた。とりわけ、とみにつらく当たるのは足を引きずる年長の院生(配役不明・好演)、院生の間では一目置かれているボス的存在である。裁縫の時間に、彼女が山田先生をからかう言動を目にして、とみは彼女に掴みかかり「組んず解れつ」の大暴れ。その夜とみは、四辻院長が「あの子が他人のために乱暴したのは初めてだ。大変な変化だよ、もうあんたとあの子は他人ではないということだ。ますます他の子どもたちはあなたに当たってくるだろう」と話しているのを盗み聞き、山田先生が自分のために苦しんでいることを知る。翌日、音楽の授業ではとみが歌わないので、院生たちは全員歌うのを止めて抵抗する。件のボスが「歌わなくていいのなら私も歌うのはいやです!」と言えば山田先生はなすすべもなく職員室に引き下がる。すっかり自信を失った山田先生に、四辻は「あなたは彼女を愛してさえいればいいんだよ、責任は私がとる!」、四辻の妻も「誰もが経験することなのよ」と慰めたのだが・・・。院生たちが「大変です!小田切さんが逃げました」と駆け込んで来た。とみはボスと一対一で決着をつけ(相手を叩きのめし)脱走したのである。
院長は直ちに駐在所、駅その他の機関に連絡、捜索を始めたが、とみの行方は杳として知れなかった。それもそのはず、彼女は人里を避け山奥に向かっていたのだから。その晩は嵐、恐怖を乗り越えて翌日、一軒の小屋に辿り着いた。粗末な部屋に人の気配はない。しかし、囲炉裏には鍋が吊され雑炊が煮えている。思わず、それを口にするとみ。やがて人の気配がした。物陰に隠れて見ていると、「そろそろ出来ている頃だぞ、ああ腹減った」
と言いながら子どもが二人入って来た。茶わんが一つ足りない。「あれ?誰かが食った」「ヤダイ、ヤダイ、ヤダイ・・・」という様子を見て、とみが姿を現し、初めて言葉を発した。「あたいが食べたんだよ、昨日一晩中、山の中にいてたまらなくおなかが空いていたもんだから。ごめんよ」と謝る。
子ども二人は、勘一(小高つとむ)、勘二(加藤博司)という兄弟で、母親を亡くし、猟師の父親松次郎(進藤英太郎)が権次郎という熊をしとめに出かけている間は、二人きりで留守番をしているのだという。
その日の夜も嵐、強風から小屋を守る兄弟に「ボンヤリしていないでつっかえ棒を持って来いよ」と言われたり、翌朝には「味噌汁に入れるマイタケを採りに行こう」と誘われたり、牧場の裸馬に乗って見せたり、父が居ないと寂しがる勘二に逆立ちをして笑わせたり、勘一から「姉ちゃん、父ちゃんが戻るまで一緒にいてくれよな」とせがまれたり・・・、ようやく、とみは「身の置き所」を見つけたようだ。しかしその安穏はいつまでも続かなかった。米櫃の米が底をついたのだ。やむなく、とみは、村から食料を盗み出すようになっていく。村人からの訴えが相次ぎ、「山猫」という異名は村人たちにも及ぶ始末、事態を憂慮した駐在(永井柳筰)や山田先生は、応援を率いて、山狩りをすることになったのである。
追っ手が迫って来た。とみは兄弟に盗んできたイモを渡し「すぐに戻ってくるから、これを食べていなさい」と言うが、「ヤダイ!姉ちゃんと一緒に行くんだい」と抱きつかれた。もうこれまでと、とみは兄弟を連れて脱出する。折しも父・松次郞が戻って来て、山田先生、捜索隊と鉢合わせ。「山猫が子どもたちを掠って逃げた」という声に、松次郎は仰天、銃を持って追おうとする。「待って下さい、落ち着いて。あの子がそんなことをするはずがありません」「山猫とは誰なんだ!」「私の娘です」、という山田先生の言葉を振り切って松次郎は駆けだした。必死でその後に続く山田先生・・・、森の中で一発の銃声が聞こえた。思わず倒れ込む山田先生。やがて、兄弟が松次郎を見つけた。「父ちゃん!」と駆け寄ってすがりつく。両手でしっかりと兄弟を抱きしめる父、その光景を呆然と見つめるとみ、力なく歩き出し、倒れている山田先生を見つける。「先生!」と叫んだが反応がない。もう一度、揺り起こして「先生!」と呼ぶ。気がついた先生、一瞬、逃げ出そうとするとみを捕まえて、ビンタ(愛の鞭)一発。とみは先生の胸に飛び込んで泣き崩れた。
勘一と勘二が父・松次郎の懐に飛び込んで、その温もりを感じたように、とみもまた山田先生の「一発」に母の愛を確かめることができたのだろう。二人は抱きしめ合いながら、心ゆくまで泣き続ける・・・。
大詰めは、四辻学院の農作業場、晴れわたった大空の下、「錦の衣はまとわねど 父と母との故郷の・・・」という歌声の中で、院生、院長、山田先生らが、溌剌と鍬を振るい、斜面の畑を耕している。麓の方から「お姉ちゃん、お姉ちゃん」という声がした。勘一と勘二である。傍らには松次郎、駐在さんの姿も見える。思わず駆け降りる、とみ。山田先生にぶつかり「ゴメンナサイ」、走りながら「ゴメンナサイ」、最後に立ち止まり、振り返って院生たち全員に「ゴメンナサーイ!」。まさに「錦の衣はまとわねど 父と母との故郷」に向けた、とみの澄み切ったメッセージで、この映画の幕は下りた。
戦時下の「国策映画」とはいえ、いつの時代でも、教育とは「愛の世界」に支えられなければ成り立たないこと、社会はつねに変動していくが人間の「愛」は永久に不変だということを心底から納得した次第である。(2017.2.3)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

主人公は、小田切とみ(高峰秀子)16歳、彼女の父は行方不明、母とは7歳の時に死別、母が遊芸人だったことから9歳の時、曲馬団に入れられた。現在の保護者は伯父になっているが折り合いが悪く、放浪を繰り返し、警察に度々補導されている。性格は強情、粗暴で、一切口をきかない・・・、ということで少年審判所に送られた。その結果、東北にある救護院、四辻学院で教育を受けることになる。彼女の身柄を引き受けに来たのは(新任の)山田先生(里見藍子)。市電、汽車、バスを乗り継いで学院に向かうが、とみは口を閉ざしたまま山田先生の話しかけに応じようとしないばかりか、「隙あらば逃げだそう」という気配も窺われる。事実、高崎駅で先生が水を汲みに行き戻ると、とみの姿は消えていた。あわてて探せばホームに立っている。「小田切さーん」と呼びかけられ、走り出した列車に飛び乗るという離れ業を演じる始末、ようやく学院の門前まで辿り着き、先生が「疑って悪かったわ、何でも悪い方にばかり考えてしまって・・」と言った途端、今度は本当に逃げ出した。道を駆け下り、畦道伝いに、田圃、叢を抜け、沼地へと逃げていく。必死に追いかける先生もまた走る、走る。とみは沼地に踏み込み、ずぶ濡れ、先生もずぶ濡れになって後を追う。「捕まえる」というよりは「助ける」ために・・・。やがて、とみの行く手には高い石垣が待っていた。万事休す、キッとして先生を睨むとみ。しかし、先生は意外にも、その場(水中)にしゃがみ込み泣き伏してしまった。とみは逃走を断念する。 かくて、とみは学院の一員となったが、「無言の行」は相変わらず、誰とも言葉を交わさない。院長の四辻(菅井一郎)は「初めはみんなそうだ、そのうちに必ずよくなる」と確信、山田先生を励ますが、とみの強情、粗暴は変わらず、院生とのトラブルは増え続ける。「親切にされると、下心があるんじゃないかと疑い深くなるものだ。彼女の乱暴は、身を守る手段なのだ」という院長の言葉は、現代にも通じる至言だろう。
院生たちの不満は、一に、新参のとみが心を開かないこと(緘黙を貫いていること)、二に、そうしたとみを院長が許容していること、三に、山田先生がとみだけを可愛がっていることに向けられる。とみには「山猫」という異名がつけられた。とりわけ、とみにつらく当たるのは足を引きずる年長の院生(配役不明・好演)、院生の間では一目置かれているボス的存在である。裁縫の時間に、彼女が山田先生をからかう言動を目にして、とみは彼女に掴みかかり「組んず解れつ」の大暴れ。その夜とみは、四辻院長が「あの子が他人のために乱暴したのは初めてだ。大変な変化だよ、もうあんたとあの子は他人ではないということだ。ますます他の子どもたちはあなたに当たってくるだろう」と話しているのを盗み聞き、山田先生が自分のために苦しんでいることを知る。翌日、音楽の授業ではとみが歌わないので、院生たちは全員歌うのを止めて抵抗する。件のボスが「歌わなくていいのなら私も歌うのはいやです!」と言えば山田先生はなすすべもなく職員室に引き下がる。すっかり自信を失った山田先生に、四辻は「あなたは彼女を愛してさえいればいいんだよ、責任は私がとる!」、四辻の妻も「誰もが経験することなのよ」と慰めたのだが・・・。院生たちが「大変です!小田切さんが逃げました」と駆け込んで来た。とみはボスと一対一で決着をつけ(相手を叩きのめし)脱走したのである。
院長は直ちに駐在所、駅その他の機関に連絡、捜索を始めたが、とみの行方は杳として知れなかった。それもそのはず、彼女は人里を避け山奥に向かっていたのだから。その晩は嵐、恐怖を乗り越えて翌日、一軒の小屋に辿り着いた。粗末な部屋に人の気配はない。しかし、囲炉裏には鍋が吊され雑炊が煮えている。思わず、それを口にするとみ。やがて人の気配がした。物陰に隠れて見ていると、「そろそろ出来ている頃だぞ、ああ腹減った」
と言いながら子どもが二人入って来た。茶わんが一つ足りない。「あれ?誰かが食った」「ヤダイ、ヤダイ、ヤダイ・・・」という様子を見て、とみが姿を現し、初めて言葉を発した。「あたいが食べたんだよ、昨日一晩中、山の中にいてたまらなくおなかが空いていたもんだから。ごめんよ」と謝る。
子ども二人は、勘一(小高つとむ)、勘二(加藤博司)という兄弟で、母親を亡くし、猟師の父親松次郎(進藤英太郎)が権次郎という熊をしとめに出かけている間は、二人きりで留守番をしているのだという。
その日の夜も嵐、強風から小屋を守る兄弟に「ボンヤリしていないでつっかえ棒を持って来いよ」と言われたり、翌朝には「味噌汁に入れるマイタケを採りに行こう」と誘われたり、牧場の裸馬に乗って見せたり、父が居ないと寂しがる勘二に逆立ちをして笑わせたり、勘一から「姉ちゃん、父ちゃんが戻るまで一緒にいてくれよな」とせがまれたり・・・、ようやく、とみは「身の置き所」を見つけたようだ。しかしその安穏はいつまでも続かなかった。米櫃の米が底をついたのだ。やむなく、とみは、村から食料を盗み出すようになっていく。村人からの訴えが相次ぎ、「山猫」という異名は村人たちにも及ぶ始末、事態を憂慮した駐在(永井柳筰)や山田先生は、応援を率いて、山狩りをすることになったのである。
追っ手が迫って来た。とみは兄弟に盗んできたイモを渡し「すぐに戻ってくるから、これを食べていなさい」と言うが、「ヤダイ!姉ちゃんと一緒に行くんだい」と抱きつかれた。もうこれまでと、とみは兄弟を連れて脱出する。折しも父・松次郞が戻って来て、山田先生、捜索隊と鉢合わせ。「山猫が子どもたちを掠って逃げた」という声に、松次郎は仰天、銃を持って追おうとする。「待って下さい、落ち着いて。あの子がそんなことをするはずがありません」「山猫とは誰なんだ!」「私の娘です」、という山田先生の言葉を振り切って松次郎は駆けだした。必死でその後に続く山田先生・・・、森の中で一発の銃声が聞こえた。思わず倒れ込む山田先生。やがて、兄弟が松次郎を見つけた。「父ちゃん!」と駆け寄ってすがりつく。両手でしっかりと兄弟を抱きしめる父、その光景を呆然と見つめるとみ、力なく歩き出し、倒れている山田先生を見つける。「先生!」と叫んだが反応がない。もう一度、揺り起こして「先生!」と呼ぶ。気がついた先生、一瞬、逃げ出そうとするとみを捕まえて、ビンタ(愛の鞭)一発。とみは先生の胸に飛び込んで泣き崩れた。
勘一と勘二が父・松次郎の懐に飛び込んで、その温もりを感じたように、とみもまた山田先生の「一発」に母の愛を確かめることができたのだろう。二人は抱きしめ合いながら、心ゆくまで泣き続ける・・・。
大詰めは、四辻学院の農作業場、晴れわたった大空の下、「錦の衣はまとわねど 父と母との故郷の・・・」という歌声の中で、院生、院長、山田先生らが、溌剌と鍬を振るい、斜面の畑を耕している。麓の方から「お姉ちゃん、お姉ちゃん」という声がした。勘一と勘二である。傍らには松次郎、駐在さんの姿も見える。思わず駆け降りる、とみ。山田先生にぶつかり「ゴメンナサイ」、走りながら「ゴメンナサイ」、最後に立ち止まり、振り返って院生たち全員に「ゴメンナサーイ!」。まさに「錦の衣はまとわねど 父と母との故郷」に向けた、とみの澄み切ったメッセージで、この映画の幕は下りた。
戦時下の「国策映画」とはいえ、いつの時代でも、教育とは「愛の世界」に支えられなければ成り立たないこと、社会はつねに変動していくが人間の「愛」は永久に不変だということを心底から納得した次第である。(2017.2.3)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-06
付録・邦画傑作選・「何が彼女をそうさせたか」(監督・鈴木重吉・1930年)
ユーチューブで映画「何が彼女をそうさせたか」(監督・鈴木重吉・1930年)を観た。この映画はフィルムが消失し永らく「幻の名作」と伝えられていたが、1990年代になってモスクワで発見され復元されたものである。私は高校時代、日本史の授業でその存在を知った。原作者・藤森成吉の名前もその時に受験知識として覚えたものである。タイトルが翻訳文体であることも特徴的であった。その「幻の名作」を今、観ることができるなんて夢のような出来事である。
映画の主人公「彼女」とは中村すみ子(高津慶子)という薄幸な女性のことである。父の手紙を持って鉄道の線路をとぼとぼと歩く。疲れ果て行き倒れになる寸前、貧乏な車引き土井老人(片岡好右衛門)に助けられた。事情を聞くと、新田の町に住む伯父、山田寬太(浅野節)を訪ね、学校に通いたいと言う。老人は雑炊を馳走し、翌朝、すみ子を馬車に乗せて町に向かう。入口まで来ると「あれが新田の町だ、伯父さんの家は警官に訊くとよい」と送り出す。「ありがとう!、学校に行ったら遊びに行くね」と手を振って別れたが、伯父の家は「貧乏人の子だくさん」を絵に描いたような有様で、七人の子どもが犇めいている。すみ子から手渡された手紙を読むと、それは遺書。「この金ですみ子を学校に通わせて・・・」と書いてある。封筒からこぼれ落ちる数枚の札。伯父は驚いてその札を懐に入れようとするが、女房(園千枝子)も黙っていない。たちまち伯父夫婦のバトルが始まった。札を奪い合って火鉢の土瓶がひっくり返る、舞い上がる灰神楽、泣き出す赤児、その様子を見て 「また喧嘩が始まった、バンザイ、バンザイ」と面白がる子どもたちの風景は、まさにトラジ・コミックの典型であった。しかし伯父夫婦は、父娘の願いを無視して、すみ子を曲芸団に売り渡す。「早くおし!」と女房に急き立てられながら、すみ子は、父の手紙と土井老人からプレゼントされた銀貨だけは手放さなかった。曲馬団でのテント生活が始まる。彼女の役は、団長(浜田格)が投げるナイフの「的」、恐怖で失神するすみ子、でも優しい仲間が居た。彼女同様に売られてきた孤児たちである。なかでも、年長の市川新太郎(海野龍人)は頼りになった。団長は冷酷無比、団員たちを酷使し絞り上げる。団員たちが抗議しても受け入れない。「もう我慢できねえ」と彼らは決起して脱走した。すみ子も新太郎と一緒に逃げ出し、新太郎の姉が居る由井の町へと向かう。「ここまでくれば大丈夫」と一息ついたが、すみ子の体力は限界、一歩も先に進めなくなってしまった。新太郎は「道を確かめてくる、ここを動いちゃいけないよ」と言って立ち去った。待っていたのは「運命のいたずら」か、新太郎は自動車にはねられて病院へ・・・。1年後、すみ子の姿はある警察署の中にあった。詐欺師・作平(小島洋々)の手先をつとめ捕縛されたのだ。巡査部長は「可哀想な娘だなあ、お前は猿回しの『猿』のように使われたんだよ」と説諭、やがて作平も逮捕され、すみ子は私立の養育院に送られる。そこは老人と浮浪者の養護施設。ここでも人々は待遇の悪さに呻吟していた。母乳を十分に与えられず泣き叫ぶ赤ん坊を、見かねたすみ子が子守する。唄を歌いながら、優しかった土井老人、新太郎の面影を追ううちに、その心が通じたか赤ん坊はスヤスヤと眠りについた。感謝する母親。そんな時、事務員が来てすみ子の名を呼んだ。「お前は秋山県会議員の所へ女中に行くんだ」。羨ましがる周囲の人々、すみ子は「さようなら、赤ちゃん」と眠っている赤ちゃんの手を頬に当て涙ぐむ。一同に別れを告げ、風呂敷包み一つを抱えて養育院を出ていく彼女の姿はひときわ美しかった。
だがしかし、秋山議員宅での女中奉公も長続きしない。わがまま娘の朝食の世話を任されたが、娘は出された魚の骨が刺さったと大騒ぎ、議員の細君(二条玉子)が「娘を殺す気か」などと怒鳴り立てる。その様子を笑って見ている床の間の布袋像は印象的、上流階級の幼稚さ・未熟さを暗示している。すみ子は娘の食べ残した魚を女中部屋に持ち帰り、毛抜きで骨を除く。女中頭に「お嬢様は御自分で骨を取らないんですか」と尋ねると「取るくらいなら食べないんですって」という答、「まあ、ずいぶん不自由な方ですね」という言葉に女中連中は大笑い、自分たちの遅い朝食を摂り始めた。そこに居住まいを正してやって来た細君、「奥の物を洗ってから食事をしなさい」「水が出しっぱなし」、すみ子が新香に醤油をかけるのを見て「香の物にはむらさきをかけてはいけません」等々、小言・雑言を浴びせまくる。最後にはすみ子に向かって「お前はこれまで随分不幸な目に会ったそうだが、養育院に比べ高価な魚を食べられて幸せだろ」と毒づいた。これまで堪え忍んできたすみ子、堪忍袋の緒が切れたか、キッとして「お魚ならいつも食べています!残り物なんか犬しか食べません」と言うや否や、持っていた皿を投げつけた。戸棚の硝子が割れて大きな穴があく。女中仲間は驚いたが、陰では応援している様子がよくわかる。かくて、すみ子は再び養育院に戻された。
すみ子の次(三年後)の奉公先は琵琶の師匠(藤閒林太郎)宅。ある雨の日、何気なく窓の外を見ると、向こうの軒下で雨宿りをしている青年がこちらを見ている。「・・・すみちゃん?」その声は、あの時「運命のいたずら」で離れ離れになった新太郎だったとは・・・。新太郎は今、役者になって劇団「ことぶき」に居るという。居場所を教えて去って行った。すみ子に一筋の光が見えた。その夜、師匠の酒の相手をしていると、いきなり腕を掴まれ引き寄せられる。「何をするんです!」と振り払い、すみ子は一目散に新太郎の元へ走り去った。
新太郎の貸間での新所帯が始まる。いそいそと炊事に取り組むすみ子、ようやく幸せの日々が始まったかに見えたが、帰宅した新太郎曰く「劇団との契約を取り消された」。知り合いにも金の工面を頼んだが「ツゴウツカズ」との返事。万策尽きた二人は心中を決意する。荒涼とした浜辺を彷徨う二人、近くには十字架のような棒杭が立ち並んでいる。二人の様子を訝る漁師たち。案の定、月の浜辺を後にして二人は入水する。「女が溺れているぞ!」、予期していた漁師たちが船を出して、すみ子を救出、彼女は修道院・天使園に収容される。「悔い改めよ、然らば、汝等は救はれん」「富める者の天国に入るは難し」という言葉を胸に、すみ子は神の子となったか。信仰生活に入ることを決意したすみ子がポプラ並木の下で聖書を読んでいると、まもなく退園する信者・島村かく(間英子)がやって来る。「あんたの亭主、生きていたってよ、私が出所して手紙を出してやるよ。早く手紙を書きなよ」「いえ、私は新しい生活に入ります」と断ったが、「心中までした相手を簡単に忘れてたまるもんか、いいから早く書いておしまいよ、走り書きでいいんだから・・・」。その誘惑に勝てず、すみ子は新太郎への手紙を認め、かくに託した。やがて礼拝が始まる。信者一同の前で園主(尾崎静子)いわく「島村かく姉妹は立派に悔い改め巣立ちます。お手本にしましょう」。式は無事終わったように見えたが、またまた「運命のいたずら」か、かくの懐から手紙がポトリと落ちた。見咎めた園主、「かくさん、お待ちなさい」と呼び止めて手紙を読む。「何てことを!あなたは神を欺いたのです。出所どころか懲戒房行きです」「どうか、お許しを!あれは頼まれたのです」、すべては後の祭り、一人残されたかくが絶叫する。「ああ、この子羊をお許し下さい!」。
その数時間後か、園主がすみ子に問い質す。「あなたはこの手紙をかくさんに頼んだのですね」「はい、でもぜひ書けって言われたものですから」「嘘はいけません!自分の罪を他人になすりつけてはいけません。あなたは死んだのです。生きる屍です。汚らわしい男のことはは忘れなさい。今度の礼拝日に皆の前で悔い改めるのです。懺悔をしなさい」「それだけはできません」「耐えるのです、耐えて強くなるのです」「どうか勘弁して下さい」と謝ったが聞き入れらることはなかった。そして日曜の礼拝日が来た。園主はすみ子に懺悔を強いる。すみ子は動かない。園主は「よござんす、それでは私が告白します」と言って、すみ子の罪を暴露した。「あんなに謝ったのに神は許してくれないのか」、すみ子の信仰心は「怒り」に変わり、聖書を十字架に向かって投げつける。「神なんて嘘だ!」というすみ子の叫びが響き渡る。やがて夜が来た。激しい半鐘の音が鳴り響き、教会は炎に包まれる。混乱し逃げ惑う信者たち、現金を手に逃げ出す園主、狂喜して踊るすみ子、「ああ、赤い天使が舞っている、みんな天国へ、みんな天国へ・・・」
しかし、まもなく警官の手がすみ子をしっかりと捕まえる。「お前だな、火をつけたのは」「はい、私がつけました」という字幕の最後に「何が彼女をそうさせたか」という文字が浮かび上がりこの映画は終わった。
すみ子という薄幸な女性の半生がリアルに描かれており、現代でも十分に説得力のある名作である、と私は思った。特に彼女を取り巻く人々の群像は人間的であり、土井老人、新太郎の「清貧」、養育院の面々の庶民的な「温もり」、曲芸団員の「連帯感」に、伯父夫婦、団長、議員細君、琵琶師匠、島村かく等に見られる「我欲」「冷酷」「俗情」、園主の「狂信」が対置される構図(演出)はお見事。また、伯父夫婦の子どもたちが見せる「喧騒」と「愛嬌」、布袋様にも笑われる議員の娘の「醜態」、議員細君に小言を食らう女中仲間の「表情」は喜劇的であり、トラジ・コミックなドタバタ風景も楽しめる。
さらに言えば、主人公・中村すみ子の財産は「風呂敷包み」一つだけ、それが彼女の「無産」の象徴として、「清貧」「薄幸」の生き様を鮮やかに描出していた。
なるほど、「昭和5年キネマ旬報優秀作品第1位」にふさわしい名作であることを、あらためて確認した次第である。
(2017.2.1)
.jpg)




にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

映画の主人公「彼女」とは中村すみ子(高津慶子)という薄幸な女性のことである。父の手紙を持って鉄道の線路をとぼとぼと歩く。疲れ果て行き倒れになる寸前、貧乏な車引き土井老人(片岡好右衛門)に助けられた。事情を聞くと、新田の町に住む伯父、山田寬太(浅野節)を訪ね、学校に通いたいと言う。老人は雑炊を馳走し、翌朝、すみ子を馬車に乗せて町に向かう。入口まで来ると「あれが新田の町だ、伯父さんの家は警官に訊くとよい」と送り出す。「ありがとう!、学校に行ったら遊びに行くね」と手を振って別れたが、伯父の家は「貧乏人の子だくさん」を絵に描いたような有様で、七人の子どもが犇めいている。すみ子から手渡された手紙を読むと、それは遺書。「この金ですみ子を学校に通わせて・・・」と書いてある。封筒からこぼれ落ちる数枚の札。伯父は驚いてその札を懐に入れようとするが、女房(園千枝子)も黙っていない。たちまち伯父夫婦のバトルが始まった。札を奪い合って火鉢の土瓶がひっくり返る、舞い上がる灰神楽、泣き出す赤児、その様子を見て 「また喧嘩が始まった、バンザイ、バンザイ」と面白がる子どもたちの風景は、まさにトラジ・コミックの典型であった。しかし伯父夫婦は、父娘の願いを無視して、すみ子を曲芸団に売り渡す。「早くおし!」と女房に急き立てられながら、すみ子は、父の手紙と土井老人からプレゼントされた銀貨だけは手放さなかった。曲馬団でのテント生活が始まる。彼女の役は、団長(浜田格)が投げるナイフの「的」、恐怖で失神するすみ子、でも優しい仲間が居た。彼女同様に売られてきた孤児たちである。なかでも、年長の市川新太郎(海野龍人)は頼りになった。団長は冷酷無比、団員たちを酷使し絞り上げる。団員たちが抗議しても受け入れない。「もう我慢できねえ」と彼らは決起して脱走した。すみ子も新太郎と一緒に逃げ出し、新太郎の姉が居る由井の町へと向かう。「ここまでくれば大丈夫」と一息ついたが、すみ子の体力は限界、一歩も先に進めなくなってしまった。新太郎は「道を確かめてくる、ここを動いちゃいけないよ」と言って立ち去った。待っていたのは「運命のいたずら」か、新太郎は自動車にはねられて病院へ・・・。1年後、すみ子の姿はある警察署の中にあった。詐欺師・作平(小島洋々)の手先をつとめ捕縛されたのだ。巡査部長は「可哀想な娘だなあ、お前は猿回しの『猿』のように使われたんだよ」と説諭、やがて作平も逮捕され、すみ子は私立の養育院に送られる。そこは老人と浮浪者の養護施設。ここでも人々は待遇の悪さに呻吟していた。母乳を十分に与えられず泣き叫ぶ赤ん坊を、見かねたすみ子が子守する。唄を歌いながら、優しかった土井老人、新太郎の面影を追ううちに、その心が通じたか赤ん坊はスヤスヤと眠りについた。感謝する母親。そんな時、事務員が来てすみ子の名を呼んだ。「お前は秋山県会議員の所へ女中に行くんだ」。羨ましがる周囲の人々、すみ子は「さようなら、赤ちゃん」と眠っている赤ちゃんの手を頬に当て涙ぐむ。一同に別れを告げ、風呂敷包み一つを抱えて養育院を出ていく彼女の姿はひときわ美しかった。
だがしかし、秋山議員宅での女中奉公も長続きしない。わがまま娘の朝食の世話を任されたが、娘は出された魚の骨が刺さったと大騒ぎ、議員の細君(二条玉子)が「娘を殺す気か」などと怒鳴り立てる。その様子を笑って見ている床の間の布袋像は印象的、上流階級の幼稚さ・未熟さを暗示している。すみ子は娘の食べ残した魚を女中部屋に持ち帰り、毛抜きで骨を除く。女中頭に「お嬢様は御自分で骨を取らないんですか」と尋ねると「取るくらいなら食べないんですって」という答、「まあ、ずいぶん不自由な方ですね」という言葉に女中連中は大笑い、自分たちの遅い朝食を摂り始めた。そこに居住まいを正してやって来た細君、「奥の物を洗ってから食事をしなさい」「水が出しっぱなし」、すみ子が新香に醤油をかけるのを見て「香の物にはむらさきをかけてはいけません」等々、小言・雑言を浴びせまくる。最後にはすみ子に向かって「お前はこれまで随分不幸な目に会ったそうだが、養育院に比べ高価な魚を食べられて幸せだろ」と毒づいた。これまで堪え忍んできたすみ子、堪忍袋の緒が切れたか、キッとして「お魚ならいつも食べています!残り物なんか犬しか食べません」と言うや否や、持っていた皿を投げつけた。戸棚の硝子が割れて大きな穴があく。女中仲間は驚いたが、陰では応援している様子がよくわかる。かくて、すみ子は再び養育院に戻された。
すみ子の次(三年後)の奉公先は琵琶の師匠(藤閒林太郎)宅。ある雨の日、何気なく窓の外を見ると、向こうの軒下で雨宿りをしている青年がこちらを見ている。「・・・すみちゃん?」その声は、あの時「運命のいたずら」で離れ離れになった新太郎だったとは・・・。新太郎は今、役者になって劇団「ことぶき」に居るという。居場所を教えて去って行った。すみ子に一筋の光が見えた。その夜、師匠の酒の相手をしていると、いきなり腕を掴まれ引き寄せられる。「何をするんです!」と振り払い、すみ子は一目散に新太郎の元へ走り去った。
新太郎の貸間での新所帯が始まる。いそいそと炊事に取り組むすみ子、ようやく幸せの日々が始まったかに見えたが、帰宅した新太郎曰く「劇団との契約を取り消された」。知り合いにも金の工面を頼んだが「ツゴウツカズ」との返事。万策尽きた二人は心中を決意する。荒涼とした浜辺を彷徨う二人、近くには十字架のような棒杭が立ち並んでいる。二人の様子を訝る漁師たち。案の定、月の浜辺を後にして二人は入水する。「女が溺れているぞ!」、予期していた漁師たちが船を出して、すみ子を救出、彼女は修道院・天使園に収容される。「悔い改めよ、然らば、汝等は救はれん」「富める者の天国に入るは難し」という言葉を胸に、すみ子は神の子となったか。信仰生活に入ることを決意したすみ子がポプラ並木の下で聖書を読んでいると、まもなく退園する信者・島村かく(間英子)がやって来る。「あんたの亭主、生きていたってよ、私が出所して手紙を出してやるよ。早く手紙を書きなよ」「いえ、私は新しい生活に入ります」と断ったが、「心中までした相手を簡単に忘れてたまるもんか、いいから早く書いておしまいよ、走り書きでいいんだから・・・」。その誘惑に勝てず、すみ子は新太郎への手紙を認め、かくに託した。やがて礼拝が始まる。信者一同の前で園主(尾崎静子)いわく「島村かく姉妹は立派に悔い改め巣立ちます。お手本にしましょう」。式は無事終わったように見えたが、またまた「運命のいたずら」か、かくの懐から手紙がポトリと落ちた。見咎めた園主、「かくさん、お待ちなさい」と呼び止めて手紙を読む。「何てことを!あなたは神を欺いたのです。出所どころか懲戒房行きです」「どうか、お許しを!あれは頼まれたのです」、すべては後の祭り、一人残されたかくが絶叫する。「ああ、この子羊をお許し下さい!」。
その数時間後か、園主がすみ子に問い質す。「あなたはこの手紙をかくさんに頼んだのですね」「はい、でもぜひ書けって言われたものですから」「嘘はいけません!自分の罪を他人になすりつけてはいけません。あなたは死んだのです。生きる屍です。汚らわしい男のことはは忘れなさい。今度の礼拝日に皆の前で悔い改めるのです。懺悔をしなさい」「それだけはできません」「耐えるのです、耐えて強くなるのです」「どうか勘弁して下さい」と謝ったが聞き入れらることはなかった。そして日曜の礼拝日が来た。園主はすみ子に懺悔を強いる。すみ子は動かない。園主は「よござんす、それでは私が告白します」と言って、すみ子の罪を暴露した。「あんなに謝ったのに神は許してくれないのか」、すみ子の信仰心は「怒り」に変わり、聖書を十字架に向かって投げつける。「神なんて嘘だ!」というすみ子の叫びが響き渡る。やがて夜が来た。激しい半鐘の音が鳴り響き、教会は炎に包まれる。混乱し逃げ惑う信者たち、現金を手に逃げ出す園主、狂喜して踊るすみ子、「ああ、赤い天使が舞っている、みんな天国へ、みんな天国へ・・・」
しかし、まもなく警官の手がすみ子をしっかりと捕まえる。「お前だな、火をつけたのは」「はい、私がつけました」という字幕の最後に「何が彼女をそうさせたか」という文字が浮かび上がりこの映画は終わった。
すみ子という薄幸な女性の半生がリアルに描かれており、現代でも十分に説得力のある名作である、と私は思った。特に彼女を取り巻く人々の群像は人間的であり、土井老人、新太郎の「清貧」、養育院の面々の庶民的な「温もり」、曲芸団員の「連帯感」に、伯父夫婦、団長、議員細君、琵琶師匠、島村かく等に見られる「我欲」「冷酷」「俗情」、園主の「狂信」が対置される構図(演出)はお見事。また、伯父夫婦の子どもたちが見せる「喧騒」と「愛嬌」、布袋様にも笑われる議員の娘の「醜態」、議員細君に小言を食らう女中仲間の「表情」は喜劇的であり、トラジ・コミックなドタバタ風景も楽しめる。
さらに言えば、主人公・中村すみ子の財産は「風呂敷包み」一つだけ、それが彼女の「無産」の象徴として、「清貧」「薄幸」の生き様を鮮やかに描出していた。
なるほど、「昭和5年キネマ旬報優秀作品第1位」にふさわしい名作であることを、あらためて確認した次第である。
(2017.2.1)
.jpg)

にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-05
付録・邦画傑作選。《「浮草物語」(監督小津安二郎・1934年)》
戦前の「大衆演劇」を描いた邦画に「浮草物語」(監督小津安二郎・1934年)がある。ユーチューブで観賞できるが、サイレント版であり、全く沈黙の世界である。しかし、場面の随所にはセリフの字幕が挿入されており、不自由はしない。
登場するのは市川喜八(坂本武)一座、信州(?)の田舎町に九年ぶりにやってきた。この町には喜八の隠し子の信吉(三井秀男)が、居酒屋を営む母・かあやん(飯田蝶子)と共に住んでいる。到着早々、喜八は現在の女房・おたか(八雲理恵子)に「土地の御贔屓筋の挨拶回りだ」と偽って居酒屋へ・・・、久しぶりに再会する喜八とかあやん、ニッコリと微笑み合って、「もうそろそろ来る頃だろうと思っていたよ」「信吉は大きくなったか」「ああ、農学校を卒業して今は専修科に通っているよ」「女手ひとつで随分苦労をしたろうな」「なーに、生きがいだから、ちっとも苦にはならないよ・・・、一本つけようか」・・・。昔、浮き名を流した中年男女の、互いをいたわり合う会話が清々しい。信吉には、親が旅役者ではまずかろうと、「お父さんは役場に勤めていたが、死んでしまった」と告げてある。「そのままにしておこう」と二人が確認し合ううちに、信吉が帰ってきた。かあやんが「信吉おかえり。芝居のおじさんが来てるよ!」。信吉もニッコリ笑って喜八を迎えた。「ずいぶん大きくなったなあ」。かあやんが「来年は検査だよ」というと喜八は信吉の身体をまぶしそうに眺めて「ウン、甲種だな」。「おじさん!、鮎釣りにいかないか」「ヨシ、行こう」、二人は近くの河原に赴いた。釣り糸を流しながら会話する。「おじさん、今度は長く居られるんだろう」「ああ、お客が入れば一年でも居られるさ」「楽屋に遊びに行ってもいいかな」「あんなところは、お前の来る所じゃねえ、人種が違うんだ」。
その夜の興行は大入り満員、演目は「慶安太平記」であった。喜八の丸橋忠弥がほろ酔い気分で登場、ふらつきながら見栄を切ったが、犬がなかなか出てこない。袖に向かって「オイ、犬、犬はどうした!」と小声で叫んだ、出番の子役・富坊(突貫小僧)、あわててぬいぐるみを被り、客席から登場して忠弥に突進・・・、その様子が何とも可愛らしく、観客の大喝采が聞こえるようであった。しかし、突然降り出した驟雨のため、小屋の雨漏りが甚だしく、楽屋も客席も右往左往して、大騒動となってしまった。
次の日も、次の日も、次の日も雨は止まない。芝居は休演で、座員は無聊を託っているが、喜八は連日の居酒屋通い、一同は「それにしても親方はのんきだなあ」という言葉に古参の座員・とっつあん(谷麗光)が口を滑らした。「そりゃあ、この土地に来たら仕方ねえよ」。それを聞きとがめたおたかが問い詰める。「お前さん、妙なことをお言いだねえ」。金まで掴まされて、とっつあんは、やむなく真相を白状、おたかの知るところとなった。おたかの気持ちは収まらず、妹分のおとき(坪内美子)を連れて居酒屋に押しかける。「おかみさん、一本つけておくんない」。二階では喜八と信吉がトウモロコシを囓りながら将棋に興じていたが、かあやんが昇ってきた。「お迎えだよ」。驚いた喜八が下に降りると、おたかとおときが酒を酌み交わしている。思わず「何しに来やがった!」とおたかを店からつまみ出し、痴話喧嘩が始まった。雨の中、「てめえなんかが出しゃばる幕か、オレがオレの倅に会いに行くのが何が悪い」「そんな口がきける義理かい。高崎の御難のことを忘れたか。あんまり舐めたマネ、おしでないよ!」」といったやりとりが、何とも真に迫っていて、男女の色模様が千変万化する景色に圧倒された。とどのつまり「おめえとの縁も今日っきりだ、二度とあの家の敷居をまたぐと承知しねえぞ。オレの倅とお前なんぞとは人種が違うんだ」という捨てセリフでその場は終わったが、喜八とおたかの亀裂は決定的となった。おたかは、おときに金を渡して信吉を誘惑させるが、おときは信吉に夢中の有様、若い二人は本気で逢瀬を楽しむ始末に・・・。
ようやく雨が上がって、座員一同、河原で衣装の洗濯にとりかかったが、一人おときの姿が見えない。喜八はその日の夜、信吉に会おうと居酒屋を訪れたが、「この頃、毎晩出て行くんだよ」というかあやんの話。やむなく小屋に戻ったが、おときを送ってきた信吉の姿を目撃、おときを問い詰めると「お姉さんに頼まれて誘惑した、でも今では私の方が夢中なの」、驚いて「おたかを呼べ!」・・・、おたかは少しも悪びれずに「お前さん、何か私に用かい」「てめえ、オレの倅をどうしようてんだ」「どうもしないさ、息子さんも旅役者を情婦にするなんて、あんたそっくりということさ。これであんたとアタシは五分と五分・・・、せいぜい悔しがるがいい!」」と言い放った。そしておときも行方をくらました。喜八、居酒屋に駆けつけたが、案の定、信吉とおときは駆け落ち状態に・・・。喜八、全身の力が脱けて、「かあやん、こいつはエライことになったぜ」と言うなり座り込む。「学があっても蛙の子は蛙、女には手を出すのも早えや」と嘆息するばかり。すっかり気落ちして一座の解散を決意してしまった、翌日には衣装を売り払い、一同の旅賃を捻出・・・、古着屋が富坊の犬のぬいぐるみを、つまんで棄てる情景はおかしくもあり、侘びしくもあり、印象に残る場面であった。
独り身になった喜八、風呂敷包み一つで居酒屋にやって来た。「一座は解散したよ、また旅に出るよ」というのを、かあやんが必死で押しとどめ「当分、ここで暮らせばいいじゃないか、信吉だってわかってくれるさ。親子三人で楽しく暮らそうよ」「何から何まですまねえな」と喜八もその気になったのだが・・・、行方不明の信吉が帰ってきた。おときも一緒だ。喜八、「すみません」と謝るおときに近づき、「どこへいっていやがった」と打擲し始めた。信吉「おじさん、謝っているのに撲たなくたっていいじゃないか」と止めに入ったが、「手前も手前だ、おっかさんが心配しているのがわからねえのか」と平手打ち、信吉、激昂して喜八を突き飛ばした。今度は、かあやんが黙っていない。「お前、この人を誰だと思ってるんだ。お前の本当のお父さんなんだよ」。信吉「お父さんは、村役場に勤めていて、とうに死んだはずじゃないか。本当のお父さんなら、20年も僕たちを放っておくわけがない」「お父さんはお前が堅気になってもらいたくて、本当のことを言わなかったんだよ。お前の学資はみんなお父さんが欠かさず送ってくれていたのに・・・」。信吉たまらず二階に駆け上り泣き崩れた。親子名のりが、とんだ修羅場となる名場面の連続で、私の涙は止まらなかった。喜八、すぐに風呂敷包みを手にすると、「かあやん、やっぱりオレは旅に出るよ」、それを聞いたおとき「親方!私も連れてって。お世話になった親方にこのまま不義理ではお別れできません。生まれ変わって親方のために働きます」、喜八、その言葉を聞いて「かあやん、今の言葉を聞いたか、可愛いこというじゃねえか。気立てのやさしいいい娘なんだ。ここで面倒見てやってくんねえか」・・・肯くおかやん。喜八、安堵して「さっきは殴ったりして悪かったな。信吉を立派にしてやってくれ」とおときに謝る。まだ必死に止めるかあやんに「今度は信吉の親父といっても不足の無い大高島(注・喜八の屋号は高島屋)になって戻ってくらあ、その時は引き幕でも一つ贈ってくんな」と言い残し、居酒屋を立ち去った。おときがあわてて信吉を呼びに行く。2階から降りてきた信吉、「おじさんは?}と尋ねるが、かあやんは答えない。再度「おじさんは」問い直すとようやく「おとうさんかい?」と確かめてから、「また旅に出て行ったよ」、後を追おうとする信吉にかあやんが言う。「止めなくたっていいんだよ、お前さえ偉くなってくれればいいんだよ、おとうさんは、いつだって、こうやって出て行くんだから・・・」その場に立ち尽くして嗚咽する信吉。画面は沈黙だが、私には役者ひとりひとりの肉声がはっきりと聞こえるのである。やがて停車場にやってきた喜八、窓口で上諏訪までの切符を求める。ふと見ると、待合室にはおたきが座っていた。見過ごしてタバコを吸おうとしたがマッチが見当たらない。探していると、いつのまにやらおたきが近づきマッチを差し出す。喜八、黙って受け取りながら一服すると、「お前さん、どこまで行くの?」「上諏訪までだ、」お前はどこだ?」「まだどこって、当てもないのさ」「・・・どうだい、もう一旗一緒に揚げて見る気はねえか」それを聞いておたかの心も決まった。キッとして立ち上がると窓口へ行き「上諏訪1枚!」
車中で、酒を酌み交わし駅弁に舌鼓をうつ、何とも小粋な場面で閉幕となった。
この作品には三組の男女、喜八とかあやん、信吉とおとき、そして喜八とおたき、が登場する。三つ巴の愛と憎しみが綯い交ぜになった人間模様(愛の不条理)を、文字通りサイレントという沈黙の手法で描出する、小津安二郎の手腕はお見事、さすが「オズの魔法使い」である。筋外には、のどかな山村の風景、芝居の舞台風景、富坊と猫の貯金箱、それを狙うとっつあんらの大人たち、雨上がりの河原で座員一同が洗濯する様子など、戦前の貴重な映像が添えられて、見どころ満載の作品に仕上がっていた。「うたかた」にも似た役者の人生が、浮草のように儚くわびしいものであることを、心底から納得した次第である。
小津監督は、戦後(1959年)「浮草」というタイトルでリメイクしている。喜八は嵐駒十郞(中村 鴈治郎)、おたかはすみ子(京マチ子)、かあやんはお芳(杉村春子)、信吉は清(川口浩)、おときは加代(若尾文子)と役名・俳優を変え、三井秀男も、三井弘次と改名し、今度は一座の座員役で登場している。もちろんトーキー、カラー映画の豪華版になったが、その出来映えや如何に、やはり戦前は戦前、戦後は戦後、その違いがくっきりと現れて、甲乙はつけがたい。二つの作品に出演している三井弘次ならば何と答えるだろうか・・・。(2016.8.13)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

登場するのは市川喜八(坂本武)一座、信州(?)の田舎町に九年ぶりにやってきた。この町には喜八の隠し子の信吉(三井秀男)が、居酒屋を営む母・かあやん(飯田蝶子)と共に住んでいる。到着早々、喜八は現在の女房・おたか(八雲理恵子)に「土地の御贔屓筋の挨拶回りだ」と偽って居酒屋へ・・・、久しぶりに再会する喜八とかあやん、ニッコリと微笑み合って、「もうそろそろ来る頃だろうと思っていたよ」「信吉は大きくなったか」「ああ、農学校を卒業して今は専修科に通っているよ」「女手ひとつで随分苦労をしたろうな」「なーに、生きがいだから、ちっとも苦にはならないよ・・・、一本つけようか」・・・。昔、浮き名を流した中年男女の、互いをいたわり合う会話が清々しい。信吉には、親が旅役者ではまずかろうと、「お父さんは役場に勤めていたが、死んでしまった」と告げてある。「そのままにしておこう」と二人が確認し合ううちに、信吉が帰ってきた。かあやんが「信吉おかえり。芝居のおじさんが来てるよ!」。信吉もニッコリ笑って喜八を迎えた。「ずいぶん大きくなったなあ」。かあやんが「来年は検査だよ」というと喜八は信吉の身体をまぶしそうに眺めて「ウン、甲種だな」。「おじさん!、鮎釣りにいかないか」「ヨシ、行こう」、二人は近くの河原に赴いた。釣り糸を流しながら会話する。「おじさん、今度は長く居られるんだろう」「ああ、お客が入れば一年でも居られるさ」「楽屋に遊びに行ってもいいかな」「あんなところは、お前の来る所じゃねえ、人種が違うんだ」。
その夜の興行は大入り満員、演目は「慶安太平記」であった。喜八の丸橋忠弥がほろ酔い気分で登場、ふらつきながら見栄を切ったが、犬がなかなか出てこない。袖に向かって「オイ、犬、犬はどうした!」と小声で叫んだ、出番の子役・富坊(突貫小僧)、あわててぬいぐるみを被り、客席から登場して忠弥に突進・・・、その様子が何とも可愛らしく、観客の大喝采が聞こえるようであった。しかし、突然降り出した驟雨のため、小屋の雨漏りが甚だしく、楽屋も客席も右往左往して、大騒動となってしまった。
次の日も、次の日も、次の日も雨は止まない。芝居は休演で、座員は無聊を託っているが、喜八は連日の居酒屋通い、一同は「それにしても親方はのんきだなあ」という言葉に古参の座員・とっつあん(谷麗光)が口を滑らした。「そりゃあ、この土地に来たら仕方ねえよ」。それを聞きとがめたおたかが問い詰める。「お前さん、妙なことをお言いだねえ」。金まで掴まされて、とっつあんは、やむなく真相を白状、おたかの知るところとなった。おたかの気持ちは収まらず、妹分のおとき(坪内美子)を連れて居酒屋に押しかける。「おかみさん、一本つけておくんない」。二階では喜八と信吉がトウモロコシを囓りながら将棋に興じていたが、かあやんが昇ってきた。「お迎えだよ」。驚いた喜八が下に降りると、おたかとおときが酒を酌み交わしている。思わず「何しに来やがった!」とおたかを店からつまみ出し、痴話喧嘩が始まった。雨の中、「てめえなんかが出しゃばる幕か、オレがオレの倅に会いに行くのが何が悪い」「そんな口がきける義理かい。高崎の御難のことを忘れたか。あんまり舐めたマネ、おしでないよ!」」といったやりとりが、何とも真に迫っていて、男女の色模様が千変万化する景色に圧倒された。とどのつまり「おめえとの縁も今日っきりだ、二度とあの家の敷居をまたぐと承知しねえぞ。オレの倅とお前なんぞとは人種が違うんだ」という捨てセリフでその場は終わったが、喜八とおたかの亀裂は決定的となった。おたかは、おときに金を渡して信吉を誘惑させるが、おときは信吉に夢中の有様、若い二人は本気で逢瀬を楽しむ始末に・・・。
ようやく雨が上がって、座員一同、河原で衣装の洗濯にとりかかったが、一人おときの姿が見えない。喜八はその日の夜、信吉に会おうと居酒屋を訪れたが、「この頃、毎晩出て行くんだよ」というかあやんの話。やむなく小屋に戻ったが、おときを送ってきた信吉の姿を目撃、おときを問い詰めると「お姉さんに頼まれて誘惑した、でも今では私の方が夢中なの」、驚いて「おたかを呼べ!」・・・、おたかは少しも悪びれずに「お前さん、何か私に用かい」「てめえ、オレの倅をどうしようてんだ」「どうもしないさ、息子さんも旅役者を情婦にするなんて、あんたそっくりということさ。これであんたとアタシは五分と五分・・・、せいぜい悔しがるがいい!」」と言い放った。そしておときも行方をくらました。喜八、居酒屋に駆けつけたが、案の定、信吉とおときは駆け落ち状態に・・・。喜八、全身の力が脱けて、「かあやん、こいつはエライことになったぜ」と言うなり座り込む。「学があっても蛙の子は蛙、女には手を出すのも早えや」と嘆息するばかり。すっかり気落ちして一座の解散を決意してしまった、翌日には衣装を売り払い、一同の旅賃を捻出・・・、古着屋が富坊の犬のぬいぐるみを、つまんで棄てる情景はおかしくもあり、侘びしくもあり、印象に残る場面であった。
独り身になった喜八、風呂敷包み一つで居酒屋にやって来た。「一座は解散したよ、また旅に出るよ」というのを、かあやんが必死で押しとどめ「当分、ここで暮らせばいいじゃないか、信吉だってわかってくれるさ。親子三人で楽しく暮らそうよ」「何から何まですまねえな」と喜八もその気になったのだが・・・、行方不明の信吉が帰ってきた。おときも一緒だ。喜八、「すみません」と謝るおときに近づき、「どこへいっていやがった」と打擲し始めた。信吉「おじさん、謝っているのに撲たなくたっていいじゃないか」と止めに入ったが、「手前も手前だ、おっかさんが心配しているのがわからねえのか」と平手打ち、信吉、激昂して喜八を突き飛ばした。今度は、かあやんが黙っていない。「お前、この人を誰だと思ってるんだ。お前の本当のお父さんなんだよ」。信吉「お父さんは、村役場に勤めていて、とうに死んだはずじゃないか。本当のお父さんなら、20年も僕たちを放っておくわけがない」「お父さんはお前が堅気になってもらいたくて、本当のことを言わなかったんだよ。お前の学資はみんなお父さんが欠かさず送ってくれていたのに・・・」。信吉たまらず二階に駆け上り泣き崩れた。親子名のりが、とんだ修羅場となる名場面の連続で、私の涙は止まらなかった。喜八、すぐに風呂敷包みを手にすると、「かあやん、やっぱりオレは旅に出るよ」、それを聞いたおとき「親方!私も連れてって。お世話になった親方にこのまま不義理ではお別れできません。生まれ変わって親方のために働きます」、喜八、その言葉を聞いて「かあやん、今の言葉を聞いたか、可愛いこというじゃねえか。気立てのやさしいいい娘なんだ。ここで面倒見てやってくんねえか」・・・肯くおかやん。喜八、安堵して「さっきは殴ったりして悪かったな。信吉を立派にしてやってくれ」とおときに謝る。まだ必死に止めるかあやんに「今度は信吉の親父といっても不足の無い大高島(注・喜八の屋号は高島屋)になって戻ってくらあ、その時は引き幕でも一つ贈ってくんな」と言い残し、居酒屋を立ち去った。おときがあわてて信吉を呼びに行く。2階から降りてきた信吉、「おじさんは?}と尋ねるが、かあやんは答えない。再度「おじさんは」問い直すとようやく「おとうさんかい?」と確かめてから、「また旅に出て行ったよ」、後を追おうとする信吉にかあやんが言う。「止めなくたっていいんだよ、お前さえ偉くなってくれればいいんだよ、おとうさんは、いつだって、こうやって出て行くんだから・・・」その場に立ち尽くして嗚咽する信吉。画面は沈黙だが、私には役者ひとりひとりの肉声がはっきりと聞こえるのである。やがて停車場にやってきた喜八、窓口で上諏訪までの切符を求める。ふと見ると、待合室にはおたきが座っていた。見過ごしてタバコを吸おうとしたがマッチが見当たらない。探していると、いつのまにやらおたきが近づきマッチを差し出す。喜八、黙って受け取りながら一服すると、「お前さん、どこまで行くの?」「上諏訪までだ、」お前はどこだ?」「まだどこって、当てもないのさ」「・・・どうだい、もう一旗一緒に揚げて見る気はねえか」それを聞いておたかの心も決まった。キッとして立ち上がると窓口へ行き「上諏訪1枚!」
車中で、酒を酌み交わし駅弁に舌鼓をうつ、何とも小粋な場面で閉幕となった。
この作品には三組の男女、喜八とかあやん、信吉とおとき、そして喜八とおたき、が登場する。三つ巴の愛と憎しみが綯い交ぜになった人間模様(愛の不条理)を、文字通りサイレントという沈黙の手法で描出する、小津安二郎の手腕はお見事、さすが「オズの魔法使い」である。筋外には、のどかな山村の風景、芝居の舞台風景、富坊と猫の貯金箱、それを狙うとっつあんらの大人たち、雨上がりの河原で座員一同が洗濯する様子など、戦前の貴重な映像が添えられて、見どころ満載の作品に仕上がっていた。「うたかた」にも似た役者の人生が、浮草のように儚くわびしいものであることを、心底から納得した次第である。
小津監督は、戦後(1959年)「浮草」というタイトルでリメイクしている。喜八は嵐駒十郞(中村 鴈治郎)、おたかはすみ子(京マチ子)、かあやんはお芳(杉村春子)、信吉は清(川口浩)、おときは加代(若尾文子)と役名・俳優を変え、三井秀男も、三井弘次と改名し、今度は一座の座員役で登場している。もちろんトーキー、カラー映画の豪華版になったが、その出来映えや如何に、やはり戦前は戦前、戦後は戦後、その違いがくっきりと現れて、甲乙はつけがたい。二つの作品に出演している三井弘次ならば何と答えるだろうか・・・。(2016.8.13)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-04
付録・邦画傑作選・「限りなき舗道」(監督・成瀬巳喜男・1934年)
ユーチューブで映画「限りなき舗道」(監督・成瀬巳喜男・1934年)を観た。成瀬監督最後のサイレント映画である。舞台は東京銀座、カフェの女給二人が登場する。一人は島杉子(忍節子)、もう一人は中根袈裟子(香取千代子)。杉子はしとやかで控えめ、袈裟子は活発でドライと性格は正反対だが、仲良くアパートに同居している。隣の部屋には貧乏画家の山村真吉(日守新一)も居り、袈裟子に好意を感じているようだ。杉子には相愛のボーイフレンド・原田町夫(結城一朗)が居たが、故郷に縁談話があるようで、結着を迫られている様子・・・。ある日、カフェに映画会社・自由が丘撮影所のスカウトがやって来た。人気女優・東山すま子が急に引退を表明したので、その穴埋めを探しに来たのだ。四、五人の女給の中で白羽の矢が立ったのは杉子、翌日、出勤する杉子と袈裟子を待ち伏せしていたスカウト(笠智衆)が「女優になりませんか。今の10倍以上は俸給を払いますよ」と誘う。そういえば近々、杉子の弟(磯野秋雄)が上京、杉子と同居することになっている。袈裟子は早々に引っ越さなければならない、という事情もあって、杉子は女優業に食指が動いたか。出勤後、自由が丘撮影所に向かおうとして交通事故、走ってきた自動車にはねられてしまった。運転していたのは上流階級、山内家の御曹司・山内弘(山内光)。ケガは打撲傷、数日間の入院で済んだが、終始、見舞いを続けた山内が謝罪する。「こちらこそ、急いでいたので不注意でした。御迷惑をおかけしました」という杉子に心惹かれたか、杉子も山内の優しさ・誠意に絆されたか、加えて、入院中の杉子に連絡がとれなかった原田から離別の便りが届いたこともあってか、山内と杉子は「恋人同士」として結婚する。しかし、山内の母(葛城文子)や姉(若葉信子)は気に入らない。洋風、派手好き、上流階級の久山淑子(井上雪子?)を許嫁として迎えたかったらしい。何かにつけて杉子の振る舞いに「格が違う」と難癖をつける。
そんな折、袈裟子の方はちゃっかりと自由が丘撮影所と交渉、女優業に収まった。馴染みの画家・真吉にも撮影所の仕事を斡旋する。しかし羽振りのよかったのは初めだけ、近頃は「役がつかない」、真吉に向かって「あんたが近づくからだ」などと八つ当たりを始める有様だった。杉子と袈裟子、いずれも思い通りにならないのが人生・・・。
いよいよ大詰めへ、姑、小姑の嫌がらせにじっと耐える杉子、彼女を守れずに苦しむ山内に「しばらくお暇をいただきます」と言って杉子は弟が居る元のアパートに戻っていく。事情を知った弟は「初めからこうなると思っていたよ。でもまた二人で働いて出直そう」と慰め励ます。自暴自棄になった山内は、杉子と幸せの時間を過ごした、思い出の箱根路を別の女とドライブ、「どこまで行くの?」と問われれば「俺はどこまでも突っ走りゃいいんだ!」、しかしその直後、転落事故を起こして重態に・・・。山内から家令(谷麗光)が迎えに来た。「世間体もありますのでお戻りください」。杉子は凜として「世間体のためならお断りします」。弟も断ったが「でも、お気の毒なあの人のためにお会いしましょう。私にはどうしてもお母さんやお姉さんに言いたいことがあるんです」。病室に行くと母と姉に囲まれて、山内は包帯姿でベッドの中、「杉子さん、弘はこんな姿になりました」という母の言葉をやり過ごして、杉子は山内の枕元に跪く。気がついた山内「杉さん、逢いたかった。僕は君を苦しめ通しだったね。でも心から君を愛している」と手を差し出せば、杉子も手を握り返し「でも私たちの愛だけではどうにもならないものがあるようです。あなたはいい方だけど弱かった」。その一言を最後に杉子は夫と決別した。母と姉に向かって「今日はお別れにまいりました。はっきり申し上げます。こんなことになってしまったのはみんなお母様とお姉様のせいです。お母様は初めから私を愛そうとはなさらなかった。」「それはひがみです」と姉が言い返せば「ひがみかもしれません。でもお母様が愛していたのは山内家という家名だったのです。それで母親と言えるでしょうか。それでいいのでしょうか」。うなだれる母、弘の呼ぶ声が聞こえる。立ち去ろうとする杉子に母が懇願する。「お願いですから弘のそばに居てやって下さい!」だがしかし、「私、失礼いたします」と言い残すと、杉子はドアの外に消え去った。まもなく山内の様態は急変し息を引き取る。しばし、杉子は廊下に佇んでいたが、哀しみに耐える強さが際立つ艶姿であった。サイレントとは言いながら、周囲の物音、人物の声が聞こえてくる名場面であったと私は思う。
ラストシーンは再び銀座、貧乏画家・山村が似顔絵の出店を出している。「ハイ、お弁当よ」とやって来たのは袈裟子、二人は結婚して貧乏生活を始めたようだ。「杉子さんが聞いたらビックリするだろうね」などと語り合う。杉子も元のカフェの女給に舞い戻った。自動車の運転免許を取り、仕事を見つけた弟も、愛車を見せにやって来る。「お茶でも飲んでいかない」と誘うが「少しでも、働かなくちゃ」、欣然と走り去った。見送りながら、ふと乗合バスに目をやると、座席には原田町夫の姿が・・・。うつむく杉子、通り過ぎる路面電車、歩く人々、車などなど賑やかな銀座の風景を映しながら、この佳品は「終」となった。
監督・成瀬巳喜男は「女性映画」の名手と言われている。なるほど、杉子、袈裟子、山内家の母、弘の姉、許嫁の久山淑子といった面々が見事な人間模様を描出している。上流家庭を守ろうとする女性たち、貧しくても幸せを求めてしたたかに生きる女性たち、その逞しさ・強さに比べて男たちは弱い。山内弘も原田町夫も「旧家」の家風(格)には抗えず、自らの人生を台無しにしてしまった。わずかに貧乏な山村だけが、ささやかな幸せを掴んだようだ。それにしても、最後、偶然に出会った原田と杉子、二人の今後の運命やいかに?「舗道」とは現代人が歩む道(人生)だとすれば、《限りなき》出会い、別離が繰り返されるであろうことも間違いない。(2017.1.30)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

そんな折、袈裟子の方はちゃっかりと自由が丘撮影所と交渉、女優業に収まった。馴染みの画家・真吉にも撮影所の仕事を斡旋する。しかし羽振りのよかったのは初めだけ、近頃は「役がつかない」、真吉に向かって「あんたが近づくからだ」などと八つ当たりを始める有様だった。杉子と袈裟子、いずれも思い通りにならないのが人生・・・。
いよいよ大詰めへ、姑、小姑の嫌がらせにじっと耐える杉子、彼女を守れずに苦しむ山内に「しばらくお暇をいただきます」と言って杉子は弟が居る元のアパートに戻っていく。事情を知った弟は「初めからこうなると思っていたよ。でもまた二人で働いて出直そう」と慰め励ます。自暴自棄になった山内は、杉子と幸せの時間を過ごした、思い出の箱根路を別の女とドライブ、「どこまで行くの?」と問われれば「俺はどこまでも突っ走りゃいいんだ!」、しかしその直後、転落事故を起こして重態に・・・。山内から家令(谷麗光)が迎えに来た。「世間体もありますのでお戻りください」。杉子は凜として「世間体のためならお断りします」。弟も断ったが「でも、お気の毒なあの人のためにお会いしましょう。私にはどうしてもお母さんやお姉さんに言いたいことがあるんです」。病室に行くと母と姉に囲まれて、山内は包帯姿でベッドの中、「杉子さん、弘はこんな姿になりました」という母の言葉をやり過ごして、杉子は山内の枕元に跪く。気がついた山内「杉さん、逢いたかった。僕は君を苦しめ通しだったね。でも心から君を愛している」と手を差し出せば、杉子も手を握り返し「でも私たちの愛だけではどうにもならないものがあるようです。あなたはいい方だけど弱かった」。その一言を最後に杉子は夫と決別した。母と姉に向かって「今日はお別れにまいりました。はっきり申し上げます。こんなことになってしまったのはみんなお母様とお姉様のせいです。お母様は初めから私を愛そうとはなさらなかった。」「それはひがみです」と姉が言い返せば「ひがみかもしれません。でもお母様が愛していたのは山内家という家名だったのです。それで母親と言えるでしょうか。それでいいのでしょうか」。うなだれる母、弘の呼ぶ声が聞こえる。立ち去ろうとする杉子に母が懇願する。「お願いですから弘のそばに居てやって下さい!」だがしかし、「私、失礼いたします」と言い残すと、杉子はドアの外に消え去った。まもなく山内の様態は急変し息を引き取る。しばし、杉子は廊下に佇んでいたが、哀しみに耐える強さが際立つ艶姿であった。サイレントとは言いながら、周囲の物音、人物の声が聞こえてくる名場面であったと私は思う。
ラストシーンは再び銀座、貧乏画家・山村が似顔絵の出店を出している。「ハイ、お弁当よ」とやって来たのは袈裟子、二人は結婚して貧乏生活を始めたようだ。「杉子さんが聞いたらビックリするだろうね」などと語り合う。杉子も元のカフェの女給に舞い戻った。自動車の運転免許を取り、仕事を見つけた弟も、愛車を見せにやって来る。「お茶でも飲んでいかない」と誘うが「少しでも、働かなくちゃ」、欣然と走り去った。見送りながら、ふと乗合バスに目をやると、座席には原田町夫の姿が・・・。うつむく杉子、通り過ぎる路面電車、歩く人々、車などなど賑やかな銀座の風景を映しながら、この佳品は「終」となった。
監督・成瀬巳喜男は「女性映画」の名手と言われている。なるほど、杉子、袈裟子、山内家の母、弘の姉、許嫁の久山淑子といった面々が見事な人間模様を描出している。上流家庭を守ろうとする女性たち、貧しくても幸せを求めてしたたかに生きる女性たち、その逞しさ・強さに比べて男たちは弱い。山内弘も原田町夫も「旧家」の家風(格)には抗えず、自らの人生を台無しにしてしまった。わずかに貧乏な山村だけが、ささやかな幸せを掴んだようだ。それにしても、最後、偶然に出会った原田と杉子、二人の今後の運命やいかに?「舗道」とは現代人が歩む道(人生)だとすれば、《限りなき》出会い、別離が繰り返されるであろうことも間違いない。(2017.1.30)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-03
付録・邦画傑作選・「にごりえ」(監督・今井正・1953年)
ユーチューブで映画「にごりえ」(監督・今井正・1953年)を観た。樋口一葉の「十三夜」「大つごもり」「にごりえ」が原作、三話の長編(130分)オムニバス映画である。文学座、前進座、東京俳優協会の錚々たるメンバーが顔を揃えており、第一話「十三夜」では、丹阿弥谷津子、芥川比呂志、三津田健、田村秋子、第二話「大つごもり」では、久我美子、中村伸郞、荒木道子、長岡輝子、竜岡晋、仲谷昇、岸田今日子、北村和夫、子役として河原崎健二、第三話「にごりえ」では、淡島千景、宮口精二、杉村春子、山村聰、南美江、賀原夏子、十朱久雄、加藤武、小池朝雄、神山繁、子役として松山省二、といった面々が登場する。以下、そのストーリーをウィキペディア百科事典から引用する。(カッコ内芸名を追加する)
【十三夜】
夫の仕打ちに耐えかね、せき(丹阿弥谷津子)が実家に戻ってくる。話を聞いた母(田村秋子)は憤慨し出戻りを許すが、父親(三津田健)は、子供と別れて実家で泣き暮らすなら辛抱して夫のもとで泣き暮らすのも同じ、と諭し、車屋(芥川比呂志)を呼んで、夜道を帰す。しばらく行くと車屋が突然「これ以上引くのが嫌になったから降りてくれ」と言いだす。月夜の明かりで顔がのぞくと、それは幼なじみの録之助であった。せきは車を降り、肩を並べて歩き始める。録之助の身の上話を聞き、励ますせき。別の車が拾える広小路に着き、短い再会を終えて再び別々の道を行く二人。
【大つごもり】
女中のみね(久我美子)は、育ててくれた養父母(中村伸郞・荒木道子)に頼まれ、奉公先の女主人・あや(長岡輝子)に借金2円を申し込む。約束の大みそかの日、あやはそんな話は聞いていないと突っぱね、急用で出かけてしまう。ちょうどそのとき、当家に20円の入金があり、みねはこの金を茶の間の小箱に入れておくように頼まれる。茶の間では放蕩息子の若旦那・石之助(仲谷昇)が昼寝をしていたが、思いあぐねたみねは、小箱から黙って2円を持ちだし、訪ねてきた養母に渡してしまう。主人の嘉兵衛(竜岡晋)が戻ると、石之助は金を無心し始める。石之助とはなさぬ仲であるあやは、50円を歳暮代わりに石之助に渡して家から追い払う。その夜、主人夫婦は金勘定を始め、茶の間の小箱をみねに持ってこさせる。勝手に2円を持ちだしたことを言いだせないみね。あやが引き出しを開けると20円すべてがなくなっている。引き出しには、その金ももらっていくと書かれた石之助の書き置きが残されていた。
【にごりえ】
銘酒屋「菊乃井」の人気酌婦・お力(淡島千景)に付きまとう男・源七(宮口精二)。源七はお力に入れ上げたあげく、仕事が疎かになって落ちぶれ、妻(杉村春子)と子(松山省二)と長屋住まいをかこっている。お力と別れてもなお忘れられず、いまだに仕事には身が入らない。妻には毎日愚痴をこぼされ、責められる日々。一度は惚れた男の惨状を知るがゆえに、お力も鬱鬱とした日を送っている。ある日、源七の子が菓子を持って家に帰る。お力にもらった菓子と知り、妻は怒り、子を連れ、家を出る。妻が戻ってみると、源七の姿がない。菊乃井でもお力が行方不明で騒ぎになっていた。捜索中の警官が心中らしい男女の遺体を見つける。女には抵抗のあとが認められた。
「十三夜」は、昔、一緒に遊んだ男女が偶然再会する物語。男はタバコ屋の倅で人気者だったが、なぜか身を持ち崩して車引き、浅草の安宿にくすぶっている。女は良家に嫁いだが、夫とは不仲、しかし子どものために辛抱する覚悟を決めた。二人が二人とも幸せではない。その運命をどうしようもなく引きずって生きて行かなければならない。そうした「やるせなさ」を感じながら、きっぱりと別れを告げる二人の姿が清々しく、詩情豊かな逸品に仕上がっていた。
「大つごもり」の若旦那・石之助もはぐれ者、親の財産を食いつぶす放蕩三昧を重ねているが、心根は温かく優しい。まだ小娘の奉公人・みねのために「泥をかぶった」潔さが光っている。
「にごりえ」もまた、酌婦・お力のために身を持ち崩した源七という男の悲劇。新しく現れた羽振りのいい客(山村聰)の前で、お力の気持ちは揺れ動く。「この人に身を任せたい、でもあの人のことが忘れられない」、その気持ちの根底にあるのは自分の生い立ち、(足の不自由な)飾り職人の娘として生まれ、極貧の暮らしを重ねてきた。その暮らしを今、(自分のために)源七一家が強いられていると思うと、「どうしようもない」「どうにでもなれ」と、やけ酒をあおる他はないのである。その気持ちは源七も同じであったか、妻子を追い出し、割腹した。「無理心中」か、「合意の情死」か、それは誰にもわからない。
以上、三つの話に共通するのは、「貧しさの景色」と「幕切れの余韻」であろうか。「愛別離苦」、その裏返しの「怨憎会苦」という迷いであろうか。いずれにせよ、樋口一葉の原作が忠実に映像化されていたことに変わりはない。
登場した俳優連中の「実力」も半端ではない。丹阿弥谷津子、久我美子、淡島千景の役柄はまさに適材適所、相手役・芥川比呂志、仲谷昇、宮口精二の三者三様の「男っぷり」、田村秋子、長岡輝子、杉村春子の「女っぷり」、河原崎健二、松山省二の「子どもっぷり」、三津田健、中村伸郎、竜岡晋の「父親気質」、端役でも存在感を示す十朱久雄、北村和夫、荒木道子、景色に色を添える岸田今日子、加藤治子らの姿が綺羅星のごとく居並んでいる。
1950年代、屈指の傑作であると、私は思った。(2017.5.18)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

【十三夜】
夫の仕打ちに耐えかね、せき(丹阿弥谷津子)が実家に戻ってくる。話を聞いた母(田村秋子)は憤慨し出戻りを許すが、父親(三津田健)は、子供と別れて実家で泣き暮らすなら辛抱して夫のもとで泣き暮らすのも同じ、と諭し、車屋(芥川比呂志)を呼んで、夜道を帰す。しばらく行くと車屋が突然「これ以上引くのが嫌になったから降りてくれ」と言いだす。月夜の明かりで顔がのぞくと、それは幼なじみの録之助であった。せきは車を降り、肩を並べて歩き始める。録之助の身の上話を聞き、励ますせき。別の車が拾える広小路に着き、短い再会を終えて再び別々の道を行く二人。
【大つごもり】
女中のみね(久我美子)は、育ててくれた養父母(中村伸郞・荒木道子)に頼まれ、奉公先の女主人・あや(長岡輝子)に借金2円を申し込む。約束の大みそかの日、あやはそんな話は聞いていないと突っぱね、急用で出かけてしまう。ちょうどそのとき、当家に20円の入金があり、みねはこの金を茶の間の小箱に入れておくように頼まれる。茶の間では放蕩息子の若旦那・石之助(仲谷昇)が昼寝をしていたが、思いあぐねたみねは、小箱から黙って2円を持ちだし、訪ねてきた養母に渡してしまう。主人の嘉兵衛(竜岡晋)が戻ると、石之助は金を無心し始める。石之助とはなさぬ仲であるあやは、50円を歳暮代わりに石之助に渡して家から追い払う。その夜、主人夫婦は金勘定を始め、茶の間の小箱をみねに持ってこさせる。勝手に2円を持ちだしたことを言いだせないみね。あやが引き出しを開けると20円すべてがなくなっている。引き出しには、その金ももらっていくと書かれた石之助の書き置きが残されていた。
【にごりえ】
銘酒屋「菊乃井」の人気酌婦・お力(淡島千景)に付きまとう男・源七(宮口精二)。源七はお力に入れ上げたあげく、仕事が疎かになって落ちぶれ、妻(杉村春子)と子(松山省二)と長屋住まいをかこっている。お力と別れてもなお忘れられず、いまだに仕事には身が入らない。妻には毎日愚痴をこぼされ、責められる日々。一度は惚れた男の惨状を知るがゆえに、お力も鬱鬱とした日を送っている。ある日、源七の子が菓子を持って家に帰る。お力にもらった菓子と知り、妻は怒り、子を連れ、家を出る。妻が戻ってみると、源七の姿がない。菊乃井でもお力が行方不明で騒ぎになっていた。捜索中の警官が心中らしい男女の遺体を見つける。女には抵抗のあとが認められた。
「十三夜」は、昔、一緒に遊んだ男女が偶然再会する物語。男はタバコ屋の倅で人気者だったが、なぜか身を持ち崩して車引き、浅草の安宿にくすぶっている。女は良家に嫁いだが、夫とは不仲、しかし子どものために辛抱する覚悟を決めた。二人が二人とも幸せではない。その運命をどうしようもなく引きずって生きて行かなければならない。そうした「やるせなさ」を感じながら、きっぱりと別れを告げる二人の姿が清々しく、詩情豊かな逸品に仕上がっていた。
「大つごもり」の若旦那・石之助もはぐれ者、親の財産を食いつぶす放蕩三昧を重ねているが、心根は温かく優しい。まだ小娘の奉公人・みねのために「泥をかぶった」潔さが光っている。
「にごりえ」もまた、酌婦・お力のために身を持ち崩した源七という男の悲劇。新しく現れた羽振りのいい客(山村聰)の前で、お力の気持ちは揺れ動く。「この人に身を任せたい、でもあの人のことが忘れられない」、その気持ちの根底にあるのは自分の生い立ち、(足の不自由な)飾り職人の娘として生まれ、極貧の暮らしを重ねてきた。その暮らしを今、(自分のために)源七一家が強いられていると思うと、「どうしようもない」「どうにでもなれ」と、やけ酒をあおる他はないのである。その気持ちは源七も同じであったか、妻子を追い出し、割腹した。「無理心中」か、「合意の情死」か、それは誰にもわからない。
以上、三つの話に共通するのは、「貧しさの景色」と「幕切れの余韻」であろうか。「愛別離苦」、その裏返しの「怨憎会苦」という迷いであろうか。いずれにせよ、樋口一葉の原作が忠実に映像化されていたことに変わりはない。
登場した俳優連中の「実力」も半端ではない。丹阿弥谷津子、久我美子、淡島千景の役柄はまさに適材適所、相手役・芥川比呂志、仲谷昇、宮口精二の三者三様の「男っぷり」、田村秋子、長岡輝子、杉村春子の「女っぷり」、河原崎健二、松山省二の「子どもっぷり」、三津田健、中村伸郎、竜岡晋の「父親気質」、端役でも存在感を示す十朱久雄、北村和夫、荒木道子、景色に色を添える岸田今日子、加藤治子らの姿が綺羅星のごとく居並んでいる。
1950年代、屈指の傑作であると、私は思った。(2017.5.18)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-02
付録・邦画傑作選・「恋も忘れて」(監督・清水宏・1937年)
ユーチューブで映画「恋も忘れて」(監督・清水宏・1937年)を観た。横浜のホテル(実際はチャブ屋)で働く一人の女・お雪(桑野通子)とその息子・春雄(爆弾小僧)が、様々な「仕打ち」を受ける物語(悲劇)である。
筋書きは単純、お雪はシングルマザー、一人息子の春雄(小学校1年生)を立派に育て上げようと、水商売に甘んじている。しかし、その生業が災いして春雄は孤立、かけがえのない命を落としてしまう。それだけの話だが、見どころは満載、寸分の隙もない演出が見事である。
その一は、女優・桑野通子の「魅力」(存在感)である。冒頭、港町の路地を、お雪が日傘を回しながら歩いていると、向こうから春雄の上級生・小太郎(突貫小僧)が駆けてきた。呼び止めて「坊や、坊や、ウチの春坊は?」と問いかけると「春坊?オレは春坊の守っ子じゃあねえやい」と過ぎ去った。その後姿を見送りながら「・・憎っくいガキだね」と呟く。その一言で、お雪の素性が露わになる。すれっからしの商売女、金に不自由はしないが、世間からは受け入れられていない。お雪は世間と闘っているのである。その足で職場に赴くと、女給連中を集めて、上司のマダム(岡村文子)に談判(団体交渉)をする気配である。「借金に縛られた上、衣装は自前、食事も自前、これじゃやっていけないわ。衣装代の半分くらいは払ってもらおうよ。もしダメなら、お客さんの飲んだビール代から何割か回してもらおうよ」。一同は大賛成、早速マダムと掛けあうが、マダムの回答はゼロ、「そんな言い分があるんなら、観光船のいい客ばかりでなく、油に汚れた石炭臭い連中にもっとサービスして、客を増やさないか。イヤなら辞めてもらっていいんだよ」。一同はがっかり、お雪は「あたし、今日は休むよ」と、プイと帰宅してしまったが、春雄の姿を見ると「やっぱり稼がなくては」と思い直し、ホテルに戻る姿がいじらしい。また、春雄をいじめから守ろうと転校させる。連れだって登校する途中で、春雄が「もういいよ、自分一人で行けるから」「どうして?」「もう、大丈夫だよ」、自分の派手な洋服姿がまずかったのかと帰宅して、しみじみと鏡を見つめる姿も「絵になっていた」。外に向かっては突っ張り、子どもに対しては優しい母性愛、そのコントラストを桑野通子は鮮やかに描き出すのである。加えて、用心棒・恭助(佐野周二)との「色模様」も格別、あくまでも、あっさりと淡泊に、まさに「恋も忘れて」男を惹きつけるのである。
その二は、春雄を演じた爆弾小僧と、彼を目の敵にして虐める小太郎役・突貫小僧の「対決」である。船着き場の倉庫が彼らの遊び場だ。春雄がロープを吊したブランコに乗っていると、小太郎がやって来て「誰に断って乗ってるんだ、お前この頃生意気だぞ」「誰にも断らないよ」「オレに断ってもらいたいね」「お前に断ればダメだっていうだろ、だから断らないよ」「ああ、そうか」という《やりとり》で二人の対立が始まった。体力的には明らかに小太郎の方が優っている。しかし、春雄は負けていない。小太郎はブランコを独占、下級生に押させていたが、春雄が「オーイ、みんなウチに来ないか、お菓子ごちそうしてやらあ」と呼びかけると、「何、菓子がある?行ってやらあ」と真っ先に反応したのは小太郎、二階のアパートに続く階段で、下級生が昇ろうとすると「オレが先頭だ」と押しのける、先頭の春雄が「オレは?」言うと「お前はいいよ」と先頭を譲る。どこか抜けていてユーモラスな小太郎の風情は格別であった。部屋に入ると洋風のきらびやかな景色に「お前のウチ、金持ちだなあ」と小太郎は驚く。春雄は得意になって「この、母ちゃんの香水かけてやらあ、高いんだぞ」と、みんなの洋服に香水を振りまいたのだが・・・。翌日、みんなは「家に帰って怒られちゃった。あんなお母さんの子どもとは遊んではいけない」と口々に言う。かくて、春雄は孤立、転校の身となった。そこでも新しい友だちができかかるが、小太郎が邪魔をする。春雄は学校をサボって海に行く。そこで中国人の子どもたちと仲良くなり、倉庫の遊び場に誘ったが、またまた小太郎が登場、追い払われてしまった。この小太郎と春雄の「対決」が悲劇を招くことになるのだが・・・。
その三は、ホテルの用心棒・恭助(佐野周二)のダンディ気質である。彼は、マダムに指示されて、お雪の動向を監視する。最近、女給のB子が神戸にドロンしようとして発覚したばかり。つきまとう恭助に向かって、お雪は「毎日、御苦労ね。部屋に入って休んでいかない?向こうの《灘の生一本》があるわよ」。恭助はお雪の部屋に入る。ベッドで寝ている春雄に目をやると、「可愛いでしょ、あたしの子どもよ。この子を立派な大人に育てることが生きがいなの」「可愛いなあ、可愛いってことが何よりの親孝行だよ」。お雪から舶来のウィスキーを注がれて一気に飲み干すと「それじゃあ、失敬する」「もう一杯どう?」黙って、二坏目を飲み干すと「サヨナラ」と言って出て行った。思わず、「カッコいい」と唸ってしまう名場面であった。
観光船が入ってきた。ホテルは外人客で大賑わい、お雪も外人客と踊っていたが、この客がしつこくて離さない。「離して!」と悲鳴を上げると、恭助が飛んで来てその外人客を殴り倒す。その場はおさまったが、マダムは怒り心頭「大事なお客に何てことするんだい、もうお前は用無しだよ」。夜の道をお雪と歩きながら「悪かったな」「あたしは嬉しかったわ。あたし一人のために助けてくれたの」「あんたの坊やのためだよ」「ますます、嬉しいわ」・・・「じゃあここで失敬するよ」「ウチに寄ってかない」「向こうの《灘の生一本》はあるかい」「まだ残っているわよ」。そして部屋の中、眠っている春雄を見つめながら「あんたも、この子のために早く足を洗うんだな」「まだ、借金があるの。それともドロンしろって言うの?私を連れて逃げてくれるの?」。まじまじと見つめ合う二人・・・、「まあ、よく考えておくよ」と行って恭助は立ち去った。波止場に「人夫募集」という貼り紙があった。恭助はカムチャッカ行きの船に乗り込むことを決意したのである。
そのことを知らせに、恭助がアパートに行くが誰もいない。「書き置き」をして帰ろうとすると、ずぶ濡れの春雄がドアを開けるなり、倒れ込んで来た。驚いてベッドに運び込む。春雄は今日一日、雨の中をさまよい、例の倉庫に居たところを、小太郎に見つかり叩き出されて来たのだ。「坊や、しっかりしなきゃダメだよ」と励ますうちにお雪も戻って来た。医者を呼んで診察してもらう。「雨に濡れたんでしょう。これ以上発熱すると肺炎になるおそれがあります。安静にしてください」。恭助はホッとして、「春坊、ケンカに負けたんだろう」「お母ちゃんの悪口を言うんだもの」「お母ちゃんの悪口を言う奴なんてやっつけてやるんだ。男は強くならなくちゃ」「負けるもんか」という言葉を聞き、恭助は最後に「強くならなくちゃダメだぞ」と念を押して帰って言った。
お雪が、ふと茶だんすに目をやると「書き置き」が貼られていた。「逃がしてることも、連れて逃げることもできない。俺は大手を振ってお前を迎えに来る」と書かれてあった。
その四は大詰め、お雪は春雄を入院させるために、マダムに借金を依頼、家に戻ると春雄が居ない。あちことと探し歩き、やっと倉庫を探り当てた。春雄は恭助に「負けるもんか」と言い、「強くならなくちゃダメだぞ」と言われた「約束」を果たすために、小太郎に一騎打ちの闘いを挑んだのである。二人は「組んずほぐれつ」争ったが、最後は、春雄の「噛みつき」が功を奏して、小太郎は泣き出し逃げ去った。しかし、春雄の体力の消耗は激しく、容体は急変して息を引き取る。お雪は激しく泣き崩れた。亡お骸に向かって「坊や、お母ちゃんのために闘ってくれて、本当にありがとうよ。だけど、どうしてもう少し我慢してくれなかったの。もう少し我慢してくれれば、きっと恥ずかしくない立派なお母ちゃんになって見せたのに・・・これからお母ちゃんは独りぼっち、どうすればいいいの」と語りかける。やがて恭助がやって来た。変わり果てた春雄の姿を見て呆然、「春坊、カムチャッカの漁場で3年働くことにしてきたんだ。これじゃどうにもなんねえじゃねえか。遅かった」と跪いて涙ぐむ。・・・「でも、春坊。俺、行ってくるよ」と立ち上がり、お雪に「しばらくのお別れだ。これで足を洗いなよ」と封筒を差し出す。「こんなことまでしてくれなくても」とお雪が拒めば、「お前にやるんじゃない。坊やにやるんだ」と、封筒を亡骸の傍に置く。
それ以上、何も語らずに恭助は去って行った。お雪はなおも激しく泣き続けるうちに、「終」を迎えた。何ともやるせない結末である。
この映画の眼目は、水商売を稼業とする男や女に対する「偏見」の描出(告発)であろうか。その偏見は子どもの姿を通して現れる。小太郎は春雄に対しては「あんなお母さんの子と遊んではいけないと親に言われた」「お前と遊ぶと親に叱られる」と言い、転校先の子どもには「こいつと遊ぶと親に叱られるぞ」と助言する。子どもたちの背後には、(健全な)堅気の親が厳然と存在しているのだが、彼らは姿を現さない。小太郎たちも芯から春雄を憎んでいるわけではないだろう。親の「偏見」が子どもをコントロールしているのである。それは親の見えない圧力である。「あんな」という一言で済ます圧力である。春雄もまた「母親のために」闘った。その契機が恭助の「おだて」(圧力)だったとすれば、恭助の責任も重い。いずれにせよ、大人同士の「偏見」が子どもに波及し、子ども同士もまた「対立」を余儀なくされるという構図が「悲劇的」なのである。(この映画では)大人同士の対立は「利害」に絡むだけで済むが、子どもの世界では切実・深刻である。友だちができない、ということは自分の存在理由を失うことに等しいからである。春雄は必死に友だちを求め、ようやく中国人の友だちを見つけたが、彼らもまた社会から疎外される存在、追い払われる他はなかったのである。
監督・清水宏は、「子供をうまく使う監督」として有名だが、この作品もまた、大人以上のドラマを展開している。中でも、春雄役・爆弾小僧(横山準)、小太郎役・突貫小僧(青木冨夫)の「雌雄対決」は見応えがあった。お雪は春雄の亡骸に「どうして、もう少し我慢ができなかったの」と語りかけたが、それが子どもというものである。大人は我慢できるが子どもはできない。そのことを誰よりも理解しているのが、監督・清水宏に他ならないと私は思った。
(2017.6.17)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

筋書きは単純、お雪はシングルマザー、一人息子の春雄(小学校1年生)を立派に育て上げようと、水商売に甘んじている。しかし、その生業が災いして春雄は孤立、かけがえのない命を落としてしまう。それだけの話だが、見どころは満載、寸分の隙もない演出が見事である。
その一は、女優・桑野通子の「魅力」(存在感)である。冒頭、港町の路地を、お雪が日傘を回しながら歩いていると、向こうから春雄の上級生・小太郎(突貫小僧)が駆けてきた。呼び止めて「坊や、坊や、ウチの春坊は?」と問いかけると「春坊?オレは春坊の守っ子じゃあねえやい」と過ぎ去った。その後姿を見送りながら「・・憎っくいガキだね」と呟く。その一言で、お雪の素性が露わになる。すれっからしの商売女、金に不自由はしないが、世間からは受け入れられていない。お雪は世間と闘っているのである。その足で職場に赴くと、女給連中を集めて、上司のマダム(岡村文子)に談判(団体交渉)をする気配である。「借金に縛られた上、衣装は自前、食事も自前、これじゃやっていけないわ。衣装代の半分くらいは払ってもらおうよ。もしダメなら、お客さんの飲んだビール代から何割か回してもらおうよ」。一同は大賛成、早速マダムと掛けあうが、マダムの回答はゼロ、「そんな言い分があるんなら、観光船のいい客ばかりでなく、油に汚れた石炭臭い連中にもっとサービスして、客を増やさないか。イヤなら辞めてもらっていいんだよ」。一同はがっかり、お雪は「あたし、今日は休むよ」と、プイと帰宅してしまったが、春雄の姿を見ると「やっぱり稼がなくては」と思い直し、ホテルに戻る姿がいじらしい。また、春雄をいじめから守ろうと転校させる。連れだって登校する途中で、春雄が「もういいよ、自分一人で行けるから」「どうして?」「もう、大丈夫だよ」、自分の派手な洋服姿がまずかったのかと帰宅して、しみじみと鏡を見つめる姿も「絵になっていた」。外に向かっては突っ張り、子どもに対しては優しい母性愛、そのコントラストを桑野通子は鮮やかに描き出すのである。加えて、用心棒・恭助(佐野周二)との「色模様」も格別、あくまでも、あっさりと淡泊に、まさに「恋も忘れて」男を惹きつけるのである。
その二は、春雄を演じた爆弾小僧と、彼を目の敵にして虐める小太郎役・突貫小僧の「対決」である。船着き場の倉庫が彼らの遊び場だ。春雄がロープを吊したブランコに乗っていると、小太郎がやって来て「誰に断って乗ってるんだ、お前この頃生意気だぞ」「誰にも断らないよ」「オレに断ってもらいたいね」「お前に断ればダメだっていうだろ、だから断らないよ」「ああ、そうか」という《やりとり》で二人の対立が始まった。体力的には明らかに小太郎の方が優っている。しかし、春雄は負けていない。小太郎はブランコを独占、下級生に押させていたが、春雄が「オーイ、みんなウチに来ないか、お菓子ごちそうしてやらあ」と呼びかけると、「何、菓子がある?行ってやらあ」と真っ先に反応したのは小太郎、二階のアパートに続く階段で、下級生が昇ろうとすると「オレが先頭だ」と押しのける、先頭の春雄が「オレは?」言うと「お前はいいよ」と先頭を譲る。どこか抜けていてユーモラスな小太郎の風情は格別であった。部屋に入ると洋風のきらびやかな景色に「お前のウチ、金持ちだなあ」と小太郎は驚く。春雄は得意になって「この、母ちゃんの香水かけてやらあ、高いんだぞ」と、みんなの洋服に香水を振りまいたのだが・・・。翌日、みんなは「家に帰って怒られちゃった。あんなお母さんの子どもとは遊んではいけない」と口々に言う。かくて、春雄は孤立、転校の身となった。そこでも新しい友だちができかかるが、小太郎が邪魔をする。春雄は学校をサボって海に行く。そこで中国人の子どもたちと仲良くなり、倉庫の遊び場に誘ったが、またまた小太郎が登場、追い払われてしまった。この小太郎と春雄の「対決」が悲劇を招くことになるのだが・・・。
その三は、ホテルの用心棒・恭助(佐野周二)のダンディ気質である。彼は、マダムに指示されて、お雪の動向を監視する。最近、女給のB子が神戸にドロンしようとして発覚したばかり。つきまとう恭助に向かって、お雪は「毎日、御苦労ね。部屋に入って休んでいかない?向こうの《灘の生一本》があるわよ」。恭助はお雪の部屋に入る。ベッドで寝ている春雄に目をやると、「可愛いでしょ、あたしの子どもよ。この子を立派な大人に育てることが生きがいなの」「可愛いなあ、可愛いってことが何よりの親孝行だよ」。お雪から舶来のウィスキーを注がれて一気に飲み干すと「それじゃあ、失敬する」「もう一杯どう?」黙って、二坏目を飲み干すと「サヨナラ」と言って出て行った。思わず、「カッコいい」と唸ってしまう名場面であった。
観光船が入ってきた。ホテルは外人客で大賑わい、お雪も外人客と踊っていたが、この客がしつこくて離さない。「離して!」と悲鳴を上げると、恭助が飛んで来てその外人客を殴り倒す。その場はおさまったが、マダムは怒り心頭「大事なお客に何てことするんだい、もうお前は用無しだよ」。夜の道をお雪と歩きながら「悪かったな」「あたしは嬉しかったわ。あたし一人のために助けてくれたの」「あんたの坊やのためだよ」「ますます、嬉しいわ」・・・「じゃあここで失敬するよ」「ウチに寄ってかない」「向こうの《灘の生一本》はあるかい」「まだ残っているわよ」。そして部屋の中、眠っている春雄を見つめながら「あんたも、この子のために早く足を洗うんだな」「まだ、借金があるの。それともドロンしろって言うの?私を連れて逃げてくれるの?」。まじまじと見つめ合う二人・・・、「まあ、よく考えておくよ」と行って恭助は立ち去った。波止場に「人夫募集」という貼り紙があった。恭助はカムチャッカ行きの船に乗り込むことを決意したのである。
そのことを知らせに、恭助がアパートに行くが誰もいない。「書き置き」をして帰ろうとすると、ずぶ濡れの春雄がドアを開けるなり、倒れ込んで来た。驚いてベッドに運び込む。春雄は今日一日、雨の中をさまよい、例の倉庫に居たところを、小太郎に見つかり叩き出されて来たのだ。「坊や、しっかりしなきゃダメだよ」と励ますうちにお雪も戻って来た。医者を呼んで診察してもらう。「雨に濡れたんでしょう。これ以上発熱すると肺炎になるおそれがあります。安静にしてください」。恭助はホッとして、「春坊、ケンカに負けたんだろう」「お母ちゃんの悪口を言うんだもの」「お母ちゃんの悪口を言う奴なんてやっつけてやるんだ。男は強くならなくちゃ」「負けるもんか」という言葉を聞き、恭助は最後に「強くならなくちゃダメだぞ」と念を押して帰って言った。
お雪が、ふと茶だんすに目をやると「書き置き」が貼られていた。「逃がしてることも、連れて逃げることもできない。俺は大手を振ってお前を迎えに来る」と書かれてあった。
その四は大詰め、お雪は春雄を入院させるために、マダムに借金を依頼、家に戻ると春雄が居ない。あちことと探し歩き、やっと倉庫を探り当てた。春雄は恭助に「負けるもんか」と言い、「強くならなくちゃダメだぞ」と言われた「約束」を果たすために、小太郎に一騎打ちの闘いを挑んだのである。二人は「組んずほぐれつ」争ったが、最後は、春雄の「噛みつき」が功を奏して、小太郎は泣き出し逃げ去った。しかし、春雄の体力の消耗は激しく、容体は急変して息を引き取る。お雪は激しく泣き崩れた。亡お骸に向かって「坊や、お母ちゃんのために闘ってくれて、本当にありがとうよ。だけど、どうしてもう少し我慢してくれなかったの。もう少し我慢してくれれば、きっと恥ずかしくない立派なお母ちゃんになって見せたのに・・・これからお母ちゃんは独りぼっち、どうすればいいいの」と語りかける。やがて恭助がやって来た。変わり果てた春雄の姿を見て呆然、「春坊、カムチャッカの漁場で3年働くことにしてきたんだ。これじゃどうにもなんねえじゃねえか。遅かった」と跪いて涙ぐむ。・・・「でも、春坊。俺、行ってくるよ」と立ち上がり、お雪に「しばらくのお別れだ。これで足を洗いなよ」と封筒を差し出す。「こんなことまでしてくれなくても」とお雪が拒めば、「お前にやるんじゃない。坊やにやるんだ」と、封筒を亡骸の傍に置く。
それ以上、何も語らずに恭助は去って行った。お雪はなおも激しく泣き続けるうちに、「終」を迎えた。何ともやるせない結末である。
この映画の眼目は、水商売を稼業とする男や女に対する「偏見」の描出(告発)であろうか。その偏見は子どもの姿を通して現れる。小太郎は春雄に対しては「あんなお母さんの子と遊んではいけないと親に言われた」「お前と遊ぶと親に叱られる」と言い、転校先の子どもには「こいつと遊ぶと親に叱られるぞ」と助言する。子どもたちの背後には、(健全な)堅気の親が厳然と存在しているのだが、彼らは姿を現さない。小太郎たちも芯から春雄を憎んでいるわけではないだろう。親の「偏見」が子どもをコントロールしているのである。それは親の見えない圧力である。「あんな」という一言で済ます圧力である。春雄もまた「母親のために」闘った。その契機が恭助の「おだて」(圧力)だったとすれば、恭助の責任も重い。いずれにせよ、大人同士の「偏見」が子どもに波及し、子ども同士もまた「対立」を余儀なくされるという構図が「悲劇的」なのである。(この映画では)大人同士の対立は「利害」に絡むだけで済むが、子どもの世界では切実・深刻である。友だちができない、ということは自分の存在理由を失うことに等しいからである。春雄は必死に友だちを求め、ようやく中国人の友だちを見つけたが、彼らもまた社会から疎外される存在、追い払われる他はなかったのである。
監督・清水宏は、「子供をうまく使う監督」として有名だが、この作品もまた、大人以上のドラマを展開している。中でも、春雄役・爆弾小僧(横山準)、小太郎役・突貫小僧(青木冨夫)の「雌雄対決」は見応えがあった。お雪は春雄の亡骸に「どうして、もう少し我慢ができなかったの」と語りかけたが、それが子どもというものである。大人は我慢できるが子どもはできない。そのことを誰よりも理解しているのが、監督・清水宏に他ならないと私は思った。
(2017.6.17)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-03-01
付録・邦画傑作選・「恋の花咲く 伊豆の踊子」(監督・五所平之助・1933年)
ユーチューブで「恋の花咲く 伊豆の踊子」(監督・五所平之助・1933年)を観た。タイトルに「恋の花咲く」という文言が添えられているように、この作品は川端康成の原作を大きく改竄している。それはそれでよい、むしろその方が映画としては面白かった、と私は思う。主人公の学生・水原(大日向伝)は原作の「私」とは似ても似つかない快男児・好青年として描かれていた。水原が伊豆を旅して巡り合った旅芸人たちとの「絡み」と「行程」はほぼ原作を踏襲しているが、随所、随所に伏見晃の脚色が加えられている。その一、冒頭に登場するのは、自転車を全速力で走らせる一人の警官、伊豆の温泉町にある旅館・湯川楼の内芸者が借金を踏み倒して逃亡したと言う。村人に目撃者がいないかを尋ねているところに、かつて湯川楼に出入りしていた鉱山技師・久保田(河村黎吉)も加わり、金鉱の山を買って大儲けした湯川楼の噂をする。その二、ある村の入口で、一人の虚無僧が立札を見ている。「物乞い旅芸人立ち入るべからず」と書かれている。彼は立札を引き抜き倒して立ち去った。その様子を見ていた村の子どもたち。後から来た旅芸人の娘(薫・田中絹代)が倒されている立札に気づき手にしたところを村人から咎められる。「役場に来い」などと言われ娘の兄(永吉・小林十九二)が無実を主張し小競り合いが始まった。そこに通りかかったのが水原で、村人に「引き抜いた所を見たのか」と確かめる。「あたい見たよ」と証言したのは村の子ども、「さっき尺八吹きの男が引き抜いたんだ」。かくて旅芸人一同の窮地は救われた。以後、水原と旅芸人の旅程が始まったのである。その三、湯川楼という旅館は、水原の先輩・隆一(竹内良一)の実家、主人の善兵衛(新井淳)は永吉の父とも懇意にしており、旅芸人になった永吉、薫たちの後見人という立場であった。永吉の父から買った山から金鉱が出たが、儲けた金の一部は薫名義で貯金している。ゆくゆくは堅気の生活に戻して、薫を隆一の嫁にしたいと思っている。その四、技師の久保田は湯川楼の繁盛振りを見てなにがしかの現金を強請り取り、永吉にもけしかける。「君はダマされたんだ。分け前を貰って一緒に金鉱を掘りてよう」。そそのかされて永吉は湯川楼に向かったが「金が欲しければ妹を連れてこい」と追い返された。その様子に義憤を感じた水原も湯川楼に談判に行くが、そこで善兵衛の真意が解るという次第。その五、大詰めの下田港、水原は《先輩・隆一のために》薫との恋を諦める、真意を打ち明け「このことは誰にも言ってはいけないよ」と念を押した。薫の櫛と水原の万年筆を「愛の形見」として交換する。
以上は、川端康成の原作にはない「脚色・演出」である。まさに「文学」と「映画」(演劇)の違いが際立つ、傑作に仕上がっていたと、私は思う。加えて、見どころも満載。二十代の田中絹代が演じる薫の姿は天衣無縫、おきゃんで惚れっぽい娘の魅力が存分に溢れていた。大日向伝の「侠気」もお見事、さらに温泉宿には遊客・坂本武、芸妓・飯田蝶子までが登場、旅芸人・小林十九二と「剣舞・近藤勇」を競演する場面は抱腹絶倒、悲・喜劇を同時に味わえる逸品であった。
この作品は、「伊豆の踊子」映画化の第一作である。以後、薫役の美空ひばり版(1954年)、鰐淵晴子版(1960年)、吉永小百合版(1963年)、内藤洋子版(1967年)、山口百恵版(1974年)、早瀬美里版(1993年)が作られているが、それらの全てを見比べてみたい衝動にかられた次第である。(2017.1.28)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

以上は、川端康成の原作にはない「脚色・演出」である。まさに「文学」と「映画」(演劇)の違いが際立つ、傑作に仕上がっていたと、私は思う。加えて、見どころも満載。二十代の田中絹代が演じる薫の姿は天衣無縫、おきゃんで惚れっぽい娘の魅力が存分に溢れていた。大日向伝の「侠気」もお見事、さらに温泉宿には遊客・坂本武、芸妓・飯田蝶子までが登場、旅芸人・小林十九二と「剣舞・近藤勇」を競演する場面は抱腹絶倒、悲・喜劇を同時に味わえる逸品であった。
この作品は、「伊豆の踊子」映画化の第一作である。以後、薫役の美空ひばり版(1954年)、鰐淵晴子版(1960年)、吉永小百合版(1963年)、内藤洋子版(1967年)、山口百恵版(1974年)、早瀬美里版(1993年)が作られているが、それらの全てを見比べてみたい衝動にかられた次第である。(2017.1.28)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
2024-02-29
付録・邦画傑作選・「滝の白糸」(監督・溝口健二・1933年)
ユーチューブで映画「滝の白糸」(監督・溝口健二・1933年)を観た。原作は泉鏡花の小説、昭和世代以前には広く知れわたっている作品である。
時は明治23年(1890年)の初夏、高岡から石動に向かう乗合馬車が人力車に追い抜かれていく。乗客たちは「馬が人に追い抜かれるなんて情けない、もっと速く走れ」と、馬丁・村越欣弥(岡田時彦)を急かすが、彼は動じずに、悠然と馬車を操っている。乗客の女、実は水芸の花形・滝の白糸(入江たか子)が「酒手をはずむから」と挑発した。初めは取り合わなかった村越だったが、あまりにしつこく絡むので、それならと鞭一発。馬車は狂ったように走り出す。たちまち人力車を追い抜いたが今度は止まらない。馬車は揺れまくり、やっと止まった時には車軸が折れ、全く動かなくなってしまった。白糸は「文明の利器だというから乗ったのに、夕方までに石動に着くんでしょうね!」とからかう。村越はキッとして「姐さん、降りて下さい」と彼女を引きずり降ろし抱きかかえると、馬に乗り一目散、石動に向かって走り出した。他の乗客たちはその場に置き去りに・・・。
石動に着くと白糸は失神状態、霧を吹きかけて介抱すると村越は、再び高岡方面に戻って行った。気がついた白糸、その毅然とした振る舞いが忘れられない。傍の人に馬丁の名を尋ねると、「みんな欣さんと呼んでいますよ」。「そう、欣さん!」と面影を追う白糸の姿はひときわ艶やかであった。
この一件で、村越は馬車会社をクビになり放浪の身に・・・、金沢にやって来た。月の晩、疲れ果て卯辰橋の上で寝ていると、すぐ側で興行中の白糸が夕涼みに訪れる。「こんな所で寝ているとカゼを引きますよ」と語りかければ、相手はあの時の馬丁・村越欣弥であったとは、何たる偶然・・・。白糸は村越の事情を知り、責任を痛感して詫びる。「私の名前は水島友、二十四よ。あなたの勉学のために貢がせてください」。かくて、その夜、二人は小屋の楽屋で結ばれた。翌朝、まじまじと白糸の絵看板に見入る村越を制して「見てはいやよ、こうして二人で居る時は、私は堅気の水島友さ!」という言葉には、旅芸人・滝の白糸の、人間としての「誠」「矜持」が込められている。
東京に出た村越への仕送りは2年間続けられたが、「ままにならないのが浮世の常」、まして旅芸人の収入はたかが知れている。3年目になると思うに任せなくなってきた。加えて、白糸の「誠」は仲間内にも利用される。南京出刃打ち(村田宏寿)の女房に駆け落ちの金を騙し取られたり、一座の若者新蔵(見明凡太郎)と後輩・撫子(滝鈴子)の駆け落ちを助けたり・・・、で有り金は底をついてしまった。「欣さんはまもなく卒業、意地でも仕送りを続けなければ・・・」、白糸はやむなく高利貸し・岩淵剛蔵(菅井一郎)に身を売って300円を手にしたが、その帰り道、兼六園で待っていたのは岩淵と連んでいた出刃打ち一味、その金を強奪される。白糸は落ちていた出刃を手に岩淵宅にとって返せば「戻って来たな。こうなるとは初めから解っていたんだ」と襲いかかられた。もみ合う打ちに、岩淵は「強盗!」と叫んで床の間に倒れ込む。気がつけば白糸の出刃が岩淵の脇腹を突き刺していたのだ。彼女はその場にあった札束をわしづかみにして逃走する。行き先は東京、村越の下宿先。しかし、その姿はなく、再会を果たしたのは監房の中であった。 白糸は下宿を出るとすぐに捕縛され金沢に送られる。途中、汽車から飛び降り新蔵夫婦に匿われるが無駄な抵抗に終わった。出刃打にも岩淵殺しの嫌疑がかかり収監される。検事の取り調べに「あっしは白糸から金を奪ったが殺していない」。白糸は「出刃打から金を取られたことはありません」と否定する。監房の筵の上で、白糸は夢を見た。兼六園を村越と散策、わが子を抱いて池を見つめる。楽しい一時も束の間、まもなく看視に揺り起こされた。「新しい検事さんがお前と話をしたいそうだ」
村越が検事に任官され金沢に赴任していたのだ。取調室で見つめ合う二人、「よく眠れましたか。食べ物は口に合いますか」と気遣う村越に、白糸は水島友にかえって「よく出世なさいました」と満面の笑みを浮かべた。もう思い残すことはない。これまで逃げたのも一目会いたいと思ったから・・・。「どうぞ取り調べを始めて下さい」「そんなことができるわけがない」とうつむく村越、二人の交情はそのまま断ち切れたか・・・。
公判の法廷には村越検事が居る。滝の白糸こと水島友は、すべてありのままを証言し、自害した。お上の手を煩わせることなく、自らの身を処したのである。翌日、村越もまた、思い出深い卯辰橋でピストル自殺、この映画は終幕となった。
女優・高峰秀子は、戦前の女優で一番美しかったのは入江たか子であったと、回想したという。なるほど、滝の白糸は美しい。容貌ばかりでなく、鉄火肌、捨て身の「誠」が滲み出る美しさ、姐御の貫禄、遊芸の色気、温もりを伴った美しさなのである。それは、村越が下宿の老婆に「姉さんから仕送りをしてもらっている」と話していたことからも瞭然であろう。もとはと言えば、自分の悪ふざけが村越の運命を狂わせた、その償いのためだけに彼女は生き、死んで行ったのである。その「誠」を知ってか、知らずか村越も後を追う。「女性映画」の名手・成瀬巳喜男は「女のたくましさ」を描出することに長けている。一方、「女性映画」の巨匠・溝口健二が追求したのは「女の性」、(成瀬に向けて)「強いばかりが女じゃないよ」という空気が漂う、渾身の名作であった、と私は思う。お見事! (2017.2.5)

にほんブログ村


観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1

時は明治23年(1890年)の初夏、高岡から石動に向かう乗合馬車が人力車に追い抜かれていく。乗客たちは「馬が人に追い抜かれるなんて情けない、もっと速く走れ」と、馬丁・村越欣弥(岡田時彦)を急かすが、彼は動じずに、悠然と馬車を操っている。乗客の女、実は水芸の花形・滝の白糸(入江たか子)が「酒手をはずむから」と挑発した。初めは取り合わなかった村越だったが、あまりにしつこく絡むので、それならと鞭一発。馬車は狂ったように走り出す。たちまち人力車を追い抜いたが今度は止まらない。馬車は揺れまくり、やっと止まった時には車軸が折れ、全く動かなくなってしまった。白糸は「文明の利器だというから乗ったのに、夕方までに石動に着くんでしょうね!」とからかう。村越はキッとして「姐さん、降りて下さい」と彼女を引きずり降ろし抱きかかえると、馬に乗り一目散、石動に向かって走り出した。他の乗客たちはその場に置き去りに・・・。
石動に着くと白糸は失神状態、霧を吹きかけて介抱すると村越は、再び高岡方面に戻って行った。気がついた白糸、その毅然とした振る舞いが忘れられない。傍の人に馬丁の名を尋ねると、「みんな欣さんと呼んでいますよ」。「そう、欣さん!」と面影を追う白糸の姿はひときわ艶やかであった。
この一件で、村越は馬車会社をクビになり放浪の身に・・・、金沢にやって来た。月の晩、疲れ果て卯辰橋の上で寝ていると、すぐ側で興行中の白糸が夕涼みに訪れる。「こんな所で寝ているとカゼを引きますよ」と語りかければ、相手はあの時の馬丁・村越欣弥であったとは、何たる偶然・・・。白糸は村越の事情を知り、責任を痛感して詫びる。「私の名前は水島友、二十四よ。あなたの勉学のために貢がせてください」。かくて、その夜、二人は小屋の楽屋で結ばれた。翌朝、まじまじと白糸の絵看板に見入る村越を制して「見てはいやよ、こうして二人で居る時は、私は堅気の水島友さ!」という言葉には、旅芸人・滝の白糸の、人間としての「誠」「矜持」が込められている。
東京に出た村越への仕送りは2年間続けられたが、「ままにならないのが浮世の常」、まして旅芸人の収入はたかが知れている。3年目になると思うに任せなくなってきた。加えて、白糸の「誠」は仲間内にも利用される。南京出刃打ち(村田宏寿)の女房に駆け落ちの金を騙し取られたり、一座の若者新蔵(見明凡太郎)と後輩・撫子(滝鈴子)の駆け落ちを助けたり・・・、で有り金は底をついてしまった。「欣さんはまもなく卒業、意地でも仕送りを続けなければ・・・」、白糸はやむなく高利貸し・岩淵剛蔵(菅井一郎)に身を売って300円を手にしたが、その帰り道、兼六園で待っていたのは岩淵と連んでいた出刃打ち一味、その金を強奪される。白糸は落ちていた出刃を手に岩淵宅にとって返せば「戻って来たな。こうなるとは初めから解っていたんだ」と襲いかかられた。もみ合う打ちに、岩淵は「強盗!」と叫んで床の間に倒れ込む。気がつけば白糸の出刃が岩淵の脇腹を突き刺していたのだ。彼女はその場にあった札束をわしづかみにして逃走する。行き先は東京、村越の下宿先。しかし、その姿はなく、再会を果たしたのは監房の中であった。 白糸は下宿を出るとすぐに捕縛され金沢に送られる。途中、汽車から飛び降り新蔵夫婦に匿われるが無駄な抵抗に終わった。出刃打にも岩淵殺しの嫌疑がかかり収監される。検事の取り調べに「あっしは白糸から金を奪ったが殺していない」。白糸は「出刃打から金を取られたことはありません」と否定する。監房の筵の上で、白糸は夢を見た。兼六園を村越と散策、わが子を抱いて池を見つめる。楽しい一時も束の間、まもなく看視に揺り起こされた。「新しい検事さんがお前と話をしたいそうだ」
村越が検事に任官され金沢に赴任していたのだ。取調室で見つめ合う二人、「よく眠れましたか。食べ物は口に合いますか」と気遣う村越に、白糸は水島友にかえって「よく出世なさいました」と満面の笑みを浮かべた。もう思い残すことはない。これまで逃げたのも一目会いたいと思ったから・・・。「どうぞ取り調べを始めて下さい」「そんなことができるわけがない」とうつむく村越、二人の交情はそのまま断ち切れたか・・・。
公判の法廷には村越検事が居る。滝の白糸こと水島友は、すべてありのままを証言し、自害した。お上の手を煩わせることなく、自らの身を処したのである。翌日、村越もまた、思い出深い卯辰橋でピストル自殺、この映画は終幕となった。
女優・高峰秀子は、戦前の女優で一番美しかったのは入江たか子であったと、回想したという。なるほど、滝の白糸は美しい。容貌ばかりでなく、鉄火肌、捨て身の「誠」が滲み出る美しさ、姐御の貫禄、遊芸の色気、温もりを伴った美しさなのである。それは、村越が下宿の老婆に「姉さんから仕送りをしてもらっている」と話していたことからも瞭然であろう。もとはと言えば、自分の悪ふざけが村越の運命を狂わせた、その償いのためだけに彼女は生き、死んで行ったのである。その「誠」を知ってか、知らずか村越も後を追う。「女性映画」の名手・成瀬巳喜男は「女のたくましさ」を描出することに長けている。一方、「女性映画」の巨匠・溝口健二が追求したのは「女の性」、(成瀬に向けて)「強いばかりが女じゃないよ」という空気が漂う、渾身の名作であった、と私は思う。お見事! (2017.2.5)
にほんブログ村
観劇 ブログランキングへ

ブログランキングNo.1
Powered by FC2 Blog
Copyright © 脱「テレビ」宣言・大衆演劇への誘い All Rights Reserved.